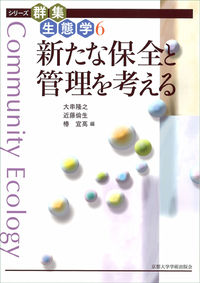| 口絵 i |
| はじめに v |
| 第1章 個体群から群集へ -新たな漁業管理の視点(松田裕之・森 光代) 1 |
| 1 漁業管理の古典理論とその限界 2 |
| (1)最大持続収穫量(MSY)理論 2 |
| (2)MSY理論への批判 3 |
| (3)被食者捕食者系の環境収容力と再生産力 6 |
| (4)多魚種系の最大持続生産量 8 |
| 2 生態系を考慮した漁業管理-生態系アプローチ 9 |
| (1)生態系を考慮した漁業管理とは何か 9 |
| (2)鯨類をめぐる生態系アプローチ-全生態系モデルと多種動態モデル 13 |
| (3)鯨類などにおける生態系管理の試み 16 |
| (4)生態系管理の今後の展望 18 |
| 3 多魚種管理の新たな理論 21 |
| (1)変動する海洋生態系に適した生態系管理とは? 21 |
| (2)海洋保護区 22 |
| (3)スイッチング漁獲 24 |
| 第2章 森林の管理と再生 -生物群集の考え方から(日野輝明) 27 |
| 1 はじめに 28 |
| 2 樹種多様性を考慮した森林のゾーニング 29 |
| (1)土地生産力と土地安定性に基づく森林のゾーニング 29 |
| (2)Hustonの種多様性の動態平衡モデル 30 |
| (3)動態平衡モデルに基づく森林の分類 34 |
| (4)動態平衡モデルに基づくゾーニング 36 |
| 3 生物多様性を考慮した森林管理 38 |
| (1)階層構造の多様化 38 |
| (2)種組成の多様化 40 |
| (3)林分配置の多様化 41 |
| (4)自然攪乱を模倣した森林管理 43 |
| 4 生物間相互作用を利用した森林管理 44 |
| (1)草食獣の採食による下刈り 44 |
| (2)共生微生物による定着・生育促進 48 |
| 5 シカとササの相互作用の動態に基づく森林生態系管理 51 |
| (1)シカとササの相互作用の動態 51 |
| (2)シカとササの相互作用に基づく森林再生 55 |
| (3)シカとササの相互作用と動物群集 58 |
| 6 おわりに 61 |
| 第3章 害虫管理の新展開 -群集生態学の視点から(安田弘法) 63 |
| 1 はじめに 64 |
| 2 第2次世界大戦以降の害虫防除 65 |
| (1)農薬万能時代と農薬により生じた問題 66 |
| (2)総合的害虫管理 66 |
| 3 害虫と天敵の相互作用 69 |
| (1)天敵の食性とギルド内捕食 69 |
| (2)天敵の種数と害虫の抑制効果 70 |
| (3)天敵を介した害虫間の見かけの競争 75 |
| 4 作物と害虫と天敵の相互作用 77 |
| (1)天敵から作物への間接効果 78 |
| (2)作物と害虫と天敵の間接相互作用網 80 |
| (3)作物の揮発物質を介した害虫と天敵の相互作用 81 |
| (4)作物・害虫・天敵の相互作用における土壌微生物の役割 84 |
| 5 害虫管理への新たな提言 87 |
| 6 今後の課題と展望 89 |
| (1)生物多様性の役割 90 |
| (2)群集生態学と応用生態学の連携 93 |
| 第4章 外来種問題と生物群集の保全(大河内勇・牧野俊一) 95 |
| 1 はじめに 96 |
| 2 外来種はいかに群集に定着するか-おもに種間競争と天敵から 98 |
| (1)種間競争 99 |
| (2)天敵 102 |
| 3 見えない外来種にどう対応するか-マツ材線虫病を例として 104 |
| (1)病原微生物の侵入 104 |
| (2)外来種としてのマツノザイセンチュウ 105 |
| (3)マツ材線虫病の感染メカニズム 105 |
| (4)宿主転換によるマツノザイセンチュウの繁栄 107 |
| (5)マツ材線虫病の根絶 109 |
| 4 送粉共生系への外来種の影響 110 |
| (1)外来ハナバチがもたらす影響 110 |
| (2)小笠原の送粉系に起きている変化 115 |
| 5 小笠原に侵入した外来種の制御を目的とした群集理論の適用 117 |
| (1)小笠原の外来種 117 |
| (2)外来種が更なる外来種の侵入を促進する 117 |
| (3)小笠原における外来種の制御が群集に及ぼす影響 120 |
| (4)外来種対策をどう進めるべきか 123 |
| 6 おわりに 126 |
| 第5章 農業生態系の修復-コウノトリの野生復帰を旗印に(内藤和明・池田 啓) 129 |
| 1 はじめに 130 |
| 2 生物多様性と群集の安定性 130 |
| (1)ミレニアム生態系評価と生態系サービス 130 |
| (2)生物多様性が群集の安定を促進する 131 |
| (3)里地・里山の生物多様性の危機 132 |
| 3 コウノトリを核にした食物網の復元 133 |
| (1)自然再生事業と生物群集の再生 133 |
| (2)コウノトリを核にした自然再生 135 |
| (3)水田生態系の現状と改善の方策 138 |
| (4)「コウノトリ育む農法」の広がり 140 |
| (5)冬期湛水と水田の生物群集 141 |
| (6)減農薬・無農薬と生物多様性 142 |
| (7)中干し延期によるカエル類の増加 143 |
| (8)一時的水域の役割-水田と河川 144 |
| (9)小規模水田魚道の設置 145 |
| (10)河川改修による浅場創出 147 |
| 4 生物群集の視点に立った環境修復 149 |
| (1)法律の改正や組織の再編が後押しした自然再生 149 |
| (2)社会的合意の重要性 150 |
| (3)実践的な研究の蓄積と順応的管理 151 |
| (4)修復目標を明らかにする 152 |
| (5)食物網の全体像は複雑 154 |
| (6)生息地の構造変化が群集の変化をうながす 155 |
| (7)昔の生物群集に戻せばよいとは限らない 156 |
| (8)環境修復における群集生態学の重要性 157 |
| (9)地域の環境保全学としての自然再生 158 |
| コラム 絶滅の連鎖が起こるとき-群集ネットワークを保全する(近藤倫生) 159 |
| 1 連鎖絶滅と生物群集の保全 160 |
| 2 生物群集の脆弱性を評価する 162 |
| 3 生物群集のアキレス腱を見つける 166 |
| 4 さらなる理解に向けて 168 |
| 終章 応用群集生態学への展望(椿 宜高・大串隆之・近藤倫生) 173 |
| 1 生物群集が提供する生態系サービス 176 |
| 2 生物群集といかにつきあうか 178 |
| 3 新たな応用群集生態学の課題 181 |
| 引用文献 185 |
| 索引 209 |
| 口絵 i |
| はじめに v |
| 第1章 個体群から群集へ -新たな漁業管理の視点(松田裕之・森 光代) 1 |
| 1 漁業管理の古典理論とその限界 2 |
| (1)最大持続収穫量(MSY)理論 2 |
| (2)MSY理論への批判 3 |