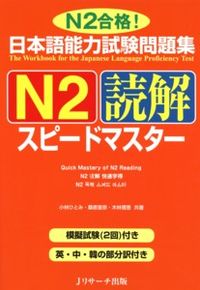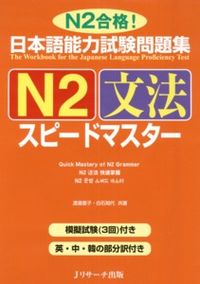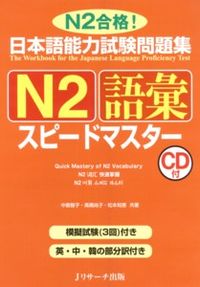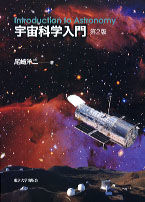1.
図書
東工大
赤間世紀著
出版情報:
東京 : カットシステム, 2011.11 xiv, 408p ; 21cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第1章 統計ソフトR 1
1.1 Rの歴史 2
1.2 Rの機能 3
1.3 本書の使用法 4
1.4 構文の構成 4
第2章 基本項目
2.1 データ属性 8
2.1.1 attr 8
2.1.2 attributes 9
2.1.3 comment 10
2.1.4 length 11
2.1.5 names 12
2.1.6 NULL 13
2.1.7 numeric 14
2.1.8 structure 15
2.1.9 typeof 15
2.2 日付と時間 16
2.2.1 Sys.time 16
2.2.2 Sys.Date 17
2.2.3 date 17
2.2.4 as.POSIX 18
2.2.5 difftime 19
2.2.6 strptime 20
2.2.7 weekdays 21
2.2.8 months 22
2.2.9 Date 22
2.2.10 DateTimeClasses 23
2.3 データタイプ 25
2.3.1 integer 25
2.3.2 numeric 26
2.3.3 double 27
2.3.4 complex 29
2.3.5 character 30
2.3.6 logical 31
2.3.7 vector 33
2.3.8 matrix 34
2.3.9 data.frame 35
2.3.10 array 37
2.3.11 list 39
2.3.12 seq 41
2.3.13 NA 42
2.3.14 is.finit 43
2.4 基本システム変数 44
2.4.1 commandArgs 44
2.4.2 LETTERS 45
2.4.3 NULL 46
2.4.4 Random 47
2.4.5 R.Version 48
2.5 データセット
2.5.1 ability.cov 50
2.5.2 airmiles 51
2.5.3 AirPassengers 52
2.5.4 airquality 53
2.5.5 anscombe 54
2.5.6 attenu 55
2.5.7 attitude 56
2.5.8 austres 57
2.5.9 beaver 58
2.5.10 BJsales 59
2.5.11 BOD 61
2.5.12 cars 62
2.5.13 ChickWeight 63
2.5.14 chickwts 64
2.5.15 C02 65
2.5.16 co2 66
2.5.17 crimtab67
2.5.18 discoveries 68
2.5.19 DNase 69
2.5.20 esoph 70
2.5.21 euro 71
2.5.22 eurodist 73
2.5.23 EuStockMarkets 75
2.5.24 faithful 76
2.5.25 Formaldehyde 77
2.5.26 freeny 78
2.5.27 HairEyeColor 80
2.5.28 Harman23.cor 81
2.5.29 Harman74.cor 82
2.5.30 Indometh 83
2.5.31 infert 84
2.5.32 InsectSprays 86
2.5.33 iris 87
2.5.34 islands 88
2.5.35 JohnsonJohnson 90
2.5.36 LakeHuron 91
2.5.37 lh 92
2.5.38 LifeCycleSavings 92
2.5.39 Loblolly 94
2.5.40 longley 95
2.5.41 lynx 96
2.5.42 morley 97
2.5.43 mtcars 98
2.5.44 nhtemp 99
2.5.45 Nile 100
2.5.46 nottem 101
2.5.47 occupationalStatus 102
2.5.48 Orange 103
2.5.49 OrchardSprays 104
2.5.50 PlantGrowth 106
2.5.51 precip 107
2.5.52 presidents 108
2.5.53 pressure 110
2.5.54 Puromycin 111
2.5.55 quakes 11 2
2.5.56 randu 113
2.5.57 rivers 114
2.5.58 rock 11 5
2.5.59 sleep 116
2.5.60 stackloss 118
2.5.61 state 120
2.5.62 sunspot.month 122
2.5.63 sunspot.year 122
2.5.64 sunspots 1 23
2.5.65 swiss 124
2.5.66 Theoph 126
2.5.67 Titanic 127
2.5.68 ToothGrowth 128
2.5.69 treering 130
2.5.70 trees 131
2.5.71 UCBAdmissions 132
2.5.72 UKDriverDeaths 133
2.5.73 UKgas 135
2.5.74 UKLungDeaths 136
2.5.75 USAccDeaths 137
2.5.76 USArrests 138
2.5.77 USJudgeRatings 139
2.5.78 USPersonalExpenditure 140
2.5.79 uspop 141
2.5.80 VADeaths 142
2.5.81 volcano 143
2.5.82 warpbreaks 144
2.5.83 women 145
2.5.84 WorldPhones 146
2.5.85 WWWusage 147
2.6 主なパッケージ 148
2.6.1 base-package 148
2.6.2 utilis-package 148
2.6.3 stats-package 148
2.6.4 graphics-package 148
2.6.5 grDevices-package 149
第3章 数学 151
3.1 算術 152
3.1.1 Arithmetic 152
3.1.2 Extremes 153
3.1.3 colSums 155
3.1.4 cumsum 156
3.1.5 prod 157
3.1.6 Round 158
3.1.7 range 159
3.1.8 sets 161
3.1.9 sort 162
3.1.10 sum 164
3.2 数学関数 165
3.2.1 abs 165
3.2.2 sign 166
3.2.3 log 167
3.2.4 Trig 168
3.2.5 Hyperbolic 170
3.2.6 Special 172
3.2.7 Bessel 174
3.2.8 norm 176
3 2 9 polyroot 177
3.3 論理演算 178
3.3.1 Comparison 178
3.3.2 Logic 180
3.3.3 logical 182
3.3.4 all 183
3.3.5 any 184
3.3.6 complete.cases 185
3.3.7 which 186
3.4 配列と行列 187
3.4.1 backsolve 187
3.4.2 col 190
3.4.3 row 191
3.4.4 crossprod 192
3.4.5 %*% 193
3.4.6 %o% 195
3.4.7 nrow 198
3.4.8 ncol 199
3.4.9 t 200
3.4.10 det 201
3.4.11 diag 202
3.4.12 dim 203
3.4.13 dimnames 204
3.4.14 row.names 206
3.4.15 row/colnames 207
3.4.16 eigen 208
3.4.17 kronecker 210
3.4.18 lower.tri 211
3.4.19 qr 213
3.4.20 svd 214
3.4.21 chol 215
3.4.22 solve 216
第4章 グラフィックス 219
4.1 プロット 220
4.1.1 plot 220
4.1.2 curve 222
4.1.3 barplot 223
4.1.4 pie 225
4.1.5 hist 227
4.1.6 boxplot 229
4.1.7 qqnorm 231
4.1.8 contour 233
4.2 グラフィックスデバイス 235
4.2.1 Devices 235
4.2.2 dev 236
4.2.3 embedFonts 238
4.2.4 Japanese 239
4.2.5 pdf 240
4.2.6 pictex 242
4.2.7 png 243
4.2.8 postscript 244
4.2.9 windows 246
4.2.10 xfig 248
4.3 カラー 249
4.3.1 RGB 249
4.3.2 XYZ 250
4.3.3 colors 251
4.3.4 rgb 252
第5章 プログラミング 253
5.1 制御 254
5.1.1 Control 254
5.1.2 ifelse 257
5.1.3 switch 258
5.1.4 function 259
5.1.5 debug 260
5.1.6 call 262
5.1.7 eval 263
5.1.8 expression 264
5.1.9 message 265
5.1.10 mode 266
5.1.11 name 267
5.1.12 stop 268
5.1.13 try 269
5.1.14 warning 270
5.2 メソッド 271
5.2.1 setClass 271
5.2.2 new 272
5.2.3 as 274
5.2.4 setMethod 275
5.2.5 is 277
5.3 入出力 279
5.3.1 scan 279
5.3.2 print 281
5.3.3 readline 282
5.3.4 readBin 283
5.3.5 readChar 284
5.3.6 read.table 286
5.3.7 write 288
5.3.8 write.table 289
5.3.9 sprintf 290
5.4 ユーティリティ 292
5.4.1 demo 292
5.4.2 edit 293
5.4.3 example 295
第6章 統計 297
6.1 確率分布と乱数 298
6.1.1 Beta 298
6.1.2 Binomial 300
6.1.3 Cauchy 302
6.1.4 Chisquare 303
6.1.5 Exponential 305
6.1.6 FDist 306
6.1.7 GammaDist 308
6.1.8 Geometric 309
6.1.9 Hypergeometric 310
6.1.10 Lognormal 312
6.1.11 NegBinomial 313
6.1.12 Normal 315
6.1.13 Poisson 317
6.1.14 TDist 318
6.1.15 Uniform 321
6.1.16 Weibull 322
6.2 記述統計 324
6.2.1 mean 325
6.2.2 median 326
6.2.3 quantile 327
6.2.4 IQR 328
6.2.5 Correlation 328
6.2.6 sd 331
6.2.7 fivenurn 332
6.2.8 skewness 333
6.2.9 kurtosis 335
6.3 推測統計 337
6.3.1 binom.test 339
6.3.2 prop.test 340
6.3.3 t.test 342
6.3.4 chisq.test 344
6.3.5 var.test 346
6.3.6 cor.test 347
6.4 統計モデル 349
6.4.1 formula 349
6.4.2 lm 350
6.4.3 summary.lm 353
6.4.4 predict.lm 354
6.4.5 nls 356
6.4.6 summary.nls 357
6.4.7 predict.nls 358
6.4.8 glm 360
6.5 時系列 362
6.5.1 ts 362
6.5.2 plot.ts 363
6.5.3 lag 365
6.5.4 diff 366
6.5.5 acf 367
6.5.6 plot.acf 369
6.5.7 spec.pgram 371
6.5.8 spectrum 374
6.5.9 ar 376
6.5.10 arima 378
6.5.11 garch 380
参考文献 384
逆引き索引 385
(1)基本項目 385
(2)データセット 387
(3)数学 390
(4)グラフィックス 392
(5)プログラミング 393
(6)統計 395
索引 398
第1章 統計ソフトR 1
1.1 Rの歴史 2
1.2 Rの機能 3
2.
図書
OpenCV2プログラミングブック制作チーム著
3.
図書
ブライアン・コックス, ジェフ・フォーショー [著] ; 柴田裕之訳
出版情報:
東京 : 紀伊國屋書店, 2011.9 329p ; 20cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
4.
図書
東工大
酒井俊典 [ほか] 共著
出版情報:
東京 : コロナ社, 2010 2冊 ; 21cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
1 土とは
1.1 土の生成 3
1.2 風化・堆積 7
1.3 岩石の種類 9
2 土の基本的物理量
2.1 土の三相 15
2.1.1 固相・液相・気相 15
2.1.2 体積に関する物理量 17
2.1.3 質量に関する物理量 19
2.1.4 体積と質量に関する物理量 19
2.1.5 三相の間隙比,飽和度,含水比による表現 23
2.1.6 土の単位体積重量 27
2.2 土の粒度 31
2.2.1 土粒子の分類 31
2.2.2 粒度試験 31
2.2.3 粒径加積曲線 35
2.3 土のコンシステンシー 41
2.3.1 液性限界・塑性限界 41
2.3.2 液性限界・塑性限界の試験方法 45
2.3.3 塑性図 47
2.4 土の工学的分類 51
2.4.1 工学的分類法(日本統一分類法) 51
2.4.2 工学的分類の方法 53
2.5 土の締固め 65
2.5.1 締固め曲線 65
2.5.2 締固め試験 67
2.5.3 締固め試験方法 71
2.5.4 種々の締固め特性 71
3 土中の水
3.1 土の透水係数 79
3.1.1 ダルシーの法則 79
3.1.2 透水試験 83
3.1.3 土の種類と透水係数 87
3.2 土中水の浸透 91
3.2.1 土中の水の流れ 91
3.2.2 流線網 95
3.2.3 流線網の描き方 99
4 圧密
4.1 有効応力・全応力 103
4.2 圧密理論 109
4.2.1 圧密とは 109
4.2.2 テルツァーギの圧密理論 109
4.3 圧密試験 115
4.3.1 圧密試験方法 115
4.3.2 圧密試験結果の整理 117
4.3.3 正規圧密状態・過圧密状態 125
5 地盤内応力
5.1 自重による地盤内応力 129
5.1.1 地盤内に作用する全応力 129
5.1.2 地盤内に作用する有効応力 131
5.1.3 圧密時の有効応力と間隙水圧 135
5.2 載荷による地盤内応力 141
付録 146
参考文献 152
英和索引 154
1 土とは
1.1 土の生成 3
1.2 風化・堆積 7
5.
図書
東工大
松井勇 [ほか] 著
出版情報:
東京 : 井上書院, 2010.4 271p ; 26cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
Ⅰ編 構造材料 11
序 12
1 木質構造(材料)の特徴 14
1-1 木質構造の特徴とディティール 14
1-1-1 全般的な特徴 14
1-2 構造・材料の長所・短所 18
1-2-1 長所 18
1-2-2 短所とその対策 18
1-3 材料の種類および性質・選択 18
1-3-1 樹種と用途 18
1-3-2 木質材料の種類と特徴 20
2 鉄骨構造(材料)の特徴 22
2-1 鉄骨構造の特徴とディテール 22
2-1-1 全般的な特徴 22
2-2 構造・材料の長所・短所 23
2-2-1 長所 23
2-2-2 短所とその対策 23
2-3 材料の種類および性質・選択 23
2-3-1 鋼材の種類と表記 23
2-3-2 鉄鋼製品 24
2-3-3 鋼材の形状・寸法表示 24
2-3-4 鋼材の接合 27
2-3-5 架構 28
3 鉄筋コンクリート構造(材料)の特徴 31
3-1 鉄筋コンクリート構造の特徴とディテール 31
3-1-1 全般的な特徴 31
3-2 構造・材料の長所・短所 32
3-2-1 長所 32
3-2-2 短所とその対策 33
3-3 材料の種類および性質・選択 34
3-3-1 コンクリートと鉄筋 34
3-3-2 コンクリートの設計基準強度およびそのワーカビリティー 34
3-3-3 鉄筋の種類と接合 36
3-3-4 構造体の総合的耐久性 37
4 組積造(材料)の特徴 39
Ⅱ編 部位と材料 43
序 44
1 屋根 45
1-1 要求条件 45
1-1-1 屋根に要求される条件 45
1-1-2 屋根材料に要求される性能 45
1-2 勾配屋根 46
1-2-1 勾配屋根の材料構成 47
1-2-2 屋根葺き材料の種類および特徴 47
1-3 陸屋根 48
1-3-1 陸屋根の材料構成 48
1-3-2 防水材の種類および特徴 49
2 外壁 50
2-1 要求条件 50
2-1-1 外壁に要求される条件 50
2-1-2 外壁仕上材料に要求される性能 50
2-2 外壁の材料構成 51
2-3 材料の種類および特徴 53
3 内壁 55
3-1 要求条件 55
3-1-1 内壁に要求される条件 55
3-1-2 内壁仕上材料に要求される性能 55
3-2 内壁の材料構成 56
3-3 材料の種類および特徴 57
4 天井
4-1 要求条件 59
4-1-1 天井に要求される条件 59
4-1-2 天井仕上材料に要求される性能 59
4-2 天井の材料構成 60
4-3 材料の種類および特徴 61
5 床 62
5-1 要求条件 62
5-1-1 床に要求される条件 62
5-1-2 床仕上材料に要求される性能 62
5-2 床の材料構成 63
5-3 材料の種類および特徴 64
6 建具 66
6-1 要求条件 66
6-1-1 建具に要求される条件 66
6-1-2 建具材料に要求される性能 67
6-2 建具の材料構成 67
6-2-1 建具の材料構成 67
6-2-2 建具のおもな部材名称 68
6-2-3 建具の種類 68
6-3 材料の種類および特徴 69
6-3-1 建具に用いられる材料分類 69
7 衛生器具 70
7-1 要求条件 70
7-1-1 衛生器具に要求される条件 70
7-1-2 材料に要求される性能 70
7-2 衛生器具の種類 71
7-3 材料の種類および特徴 71
Ⅲ編 材料の機能 73
序 74
1 防水性 76
1-1 水分の挙動 76
1-2 水分と材料の性質 77
1-3 防水工法と材料 77
1-3-1 隔壁(材料)表面を不透水性の材料で覆って水分を遮断する工法 77
1-3-2 隔壁(材料)自体の吸水・吸湿性を低下させて,透水・透湿が生じにくい性質に変える工法 77
1-3-3 材料や部材のすきまに不透水性の材料を詰める工法 78
2 防火性 79
2-1 構造,建築物および材料の分類 79
2-1-1 構造の分類 79
2-1-2 建築物の分類 81
2-1-3 材料の分類 81
2-2 材料の燃焼と種類 82
2-2-1 材料の燃焼 82
2-2-2 不燃・難燃材料の種類 82
3 断熱・保温性 85
3-1 機能と原理 85
3-1-1 熱の移動と性質 85
3-1-2 断熱材の性質 86
3-2 断熱材の種類と断熱工法 88
3-2-1 断熱材の種類 88
3-2-2 断熱工法 89
4 音響特性 90
4-1 機能と原理 90
4-2 吸音方法と材料 90
4-2-1 多孔質材料による方法 90
4-2-2 板状材料の振動による方法 91
4-2-3 膜状材料による方法 91
4-2-4 あなあき板による方法 91
4-2-5 成形吸音板による方法 91
4-3 遮音方法と材料 92
5 接着性・接合性 93
5-1 機能と性能 93
5-2 物理化学的接合 93
5-2-1 接着 93
5-2-2 溶接 97
5-2-3 自着 99
5-3 機械的接合 101
5-3-1 仕口・継手による接合 101
5-3-2 接合金物による接合 101
5-3-3 補強金物による接合 102
5-3-4 ラスによる接合 103
6 保護・仕上げ性 104
6-1 機能と性能 104
6-2 塗科 104
6-2-1 概説 104
6-2-2 種類 104
6-2-3 塗料の機能と素地 107
6-2-4 用途と製品 108
6-3 建築用仕上塗材 110
6-3-1 概説 110
6-3-2 薄付け仕上塗材 111
6-3-3 厚付け仕上塗材 111
6-3-4 複層仕上塗材 111
6-3-5 可とう形改修用仕上塗材 112
6-3-6 軽量骨材仕上塗材 112
6-3-7 建築用下地調整塗材 112
6-4 表面含浸材 113
6-4-1 概説 113
6-4-2 シラン系表面含浸材 113
6-4-3 ケイ酸塩系表面含浸材 114
6-5 塗り床材 115
6-5-1 概説 115
6-5-2 塗布型塗り床材 115
6-5-3 一体型塗り床材 116
7 水密・気密性 118
7-1 機能と原理 118
7-2 シーリング材・コーキング材 118
7-2-1 建築用シーリング材 118
7-2-2 建築用油性コーキング材 120
7-2-3 金属製建具用ガラスパテ 120
7-2-4 補修用注入エポキシ樹脂 120
7-3 ガスケット 121
7-3-1 建築用発泡体ガスケット 121
7-3-2 建築用ガスケット 121
8 材料の感覚的性能 123
8-1 概説 123
8-2 温冷感触 123
8-3 凹凸感触 124
8-4 べたつき感触 125
8-5 よごれの程度 126
8-6 打音感触 126
9 環境負荷と建築材料 128
9-1 概説 128
9-2 環境負荷低減のための建築材料のあり方 129
9-2-1 環境基本法とその関係法令に示される建築材料 129
9-2-2 長寿命と建築材料 130
9-2-3 自然共生と建築材料 130
9-2-4 省エネルギーと建築材料 130
9-2-5 省資源・循環と建築材料 131
9-2-6 室内空気汚染と建築材料 131
Ⅳ編 基本材料 133
序 134
1 金属材料 135
1-1 鉄鋼 135
1-1-1 製法 135
1-1-2 炭素鋼 137
1-1-3 特殊鋼 139
1-1-4 鋳鋼 140
1-1-5 用途と製品 140
1-2 アルミニウムおよびその合金 141
1-2-1 製法 141
1-2-2 種類・特徴 142
1-2-3 性質 142
1-2-4 用途と製品 144
1-3 銅およびその合金 145
1-3-1 製法 145
1-3-2 種類・特徴 145
1-3-3 性質 146
1-3-4 用途と製品 146
1-4 チタンおよびその合金 146
1-4-1 製法 146
1-4-2 種類・特徴 147
1-4-3 性質 147
1-4-4 用途と製品 148
1-5 亜鉛・スズ・鉛 148
1-5-1 製法 148
1-5-2 種類・特徴 149
1-5-3 性質 149
1-5-4 用途と製品 150
1-6 銀・金・白金 151
1-6-1 製法 151
1-6-2 種類・特徴 151
1-6-3 性質 152
1-6-4 用途と製品 152
1-7 耐久性 153
2 無機材料 156
2-1 石材 156
2-1-1 概説 156
2-1-2 種類および組成 156
2-1-3 一般的性質 156
2-1-4 製品 158
2-2 セメント 161
2-2-1 概説 161
2-2-2 ポルトランドセメントの製造 161
2-2-3 ポルトランドセメントの成分 161
2-2-4 ポルトランドセメントの水和 164
2-2-5 混和材 165
2-2-6 性質 167
2-3 コンクリート 170
2-3-1 コンクリート用材料 170
2-3-2 調合 181
2-3-3 フレッシュコンクリートの性質 188
2-3-4 初期性状 190
2-3-5 硬化コンクリートの性質 193
2-3-6 各種コンクリート 204
2-3-7 コンクリート製品 205
2-3-8 鉄筋コンクリート構造物の耐久性 208
2-4 石灰,せっこう,プラスター 215
2-4-1 概説 215
2-4-2 種類および組織,基本的性質 215
2-4-3 用途と製品 216
2-5 陶磁器 218
2-5-1 概説 218
2-5-2 素地の種類と性質 218
2-5-3 製品と用途 219
2-5-4 陶磁器の耐久性 222
2-6 ガラス 223
2-6-1 概説 223
2-6-2 種類・製法および加工法 223
2-6-3 一般的性質 224
2-6-4 製品と用途 225
3 有機材料 227
3-1 木材 227
3-1-1 構造と組織・木理・欠点 228
3-1-2 製材による種類 229
3-1-3 水分 230
3-1-4 一般的な性質 231
3-1-5 木材の耐久性 235
3-1-6 木質材料 238
3-2 プラスチック・ゴム 243
3-2-1 概要 243
3-2-2 種類 243
3-2-3 成形法・現場施工 244
3-2-4 性質 245
3-2-5 用途と製品 248
3-3 アスファルト 254
3-3-1 概説 254
3-3-2 種類と性質・用途 254
Ⅴ編 材料の基本的物性と単位 257
1 質量・重量・密度・比重 258
2 強度・応力度・ひずみ度 258
3 温度・熱に関する物性値と単位 260
4 水に関する物性値と単位 261
5 音に関する物性値と単位 262
6 光・照明に関する物性値と単位 263
7 表色・光沢 264
索引 267
Ⅰ編 構造材料 11
序 12
1 木質構造(材料)の特徴 14
6.
図書
電気学会第2次M2M技術調査専門委員会編
出版情報:
東京 : 森北出版, 2016.3 vi, 183p ; 22cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第1章 : M2Mシステムとは
第2章 : M2Mのアプリケーション事例
第3章 : M2Mシステム構築技術
第4章 : M2Mプラットフォーム
第5章 : M2Mネットワーク
第6章 : M2Mセキュリティ
第1章 : M2Mシステムとは
第2章 : M2Mのアプリケーション事例
第3章 : M2Mシステム構築技術
概要:
M2M/IoTにかかわるハードウェア、ソフトウェア、通信の全体像を解説。これからシステム構築に取り組む技術者におすすめです。
7.
図書
東工大
市川雅教著
目次情報:
続きを見る
1 はじめに 1
1.1 因子分析とは 1
1.2 因子分析の発展 4
2 因子分析モデル 7
2.1 モデルの定義 7
2.2 モデルの性質(1) 10
2.2.1 尺度不変性 10
2.2.2 (Λ,f,Φ)の不定性 12
2.2.3 (Λ,f)の不定性 15
2.2.4 因子得点の不定性 17
2.2.5 直交モデルにおける因子の寄与 18
2.3 共通因子分解Σ=ΛΛ'十Ψ 20
2.3.1 共通因子分解の存在 20
2.3.2 共通因子分解の一意性 23
2.4 モデルの性質(2) 26
2.4.1 Σ^(-1)の分解 26
2.4.2 1因子モデル 27
2.5 不等式 29
2.5.1 共通性と重相関係数の2乗(SMC)の関係 29
2.5.2 因子数の下限 29
2.5.3 共分散行列や相関係数行列の固有値に関する不等式 30
2.5.4 1因子モデル 32
2.6 関連するモデル 32
2.6.1 主成分分析 32
2.6.2 イメージ理論 35
3 母数の推定 41
3.1 不一致度関数の最小化による方法 41
3.1.1 最尤法 42
3.1.2 最小2乗法 45
3.1.3 標本相関係数行列の利用 45
3.2 その他の方法 47
3.2.1 主因子法 47
3.2.2 正準因子分析 50
3.2.3 アルファ因子分析 53
3.3 最尤推定値を求めるアルゴリズム 56
3.3.1 ニュートン・ラフソン法 57
3.3.2 不適解 65
3.3.3 数値例 67
4 推定量の標本分布と因子数の選択 69
4.1 最尤推定量の標本分布 69
4.1.1 漸近分布 69
4.1.2 漸近展開 77
4.2 因子数の選択 83
4.2.1 標本相関係数行列の固有値に基づく基準 83
4.2.2 尤度比検定 84
4.2.3 情報量規準 90
4.2.4 適合度指標 92
4.3 ブートストラップ法の利用 94
5 因子の回転(1) 100
5.1 因子の回転の基礎 100
5.1.1 直交回転と斜交回転 100
5.1.2 準拠因子と準拠構造 104
5.1.3 斜交モデルにおける因子の寄与 106
5.2 解析的回転とその基準 107
5.2.1 単純構造 107
5.2.2 直交回転の基準 109
5.2.3 斜交回転の基準 113
5.2.4 直交回転と斜交回転の統一的な基準 115
5.3 プロクラステス回転とその他の方法 121
5.4 因子の回転の例 128
6 因子の回転(2) 130
6.1 解析的回転のアルゴリズム 130
6.1.1 直交回転 130
6.1.2 直交回転(同時法) 136
6.1.3 斜交回転 138
6.1.4 その他のアルゴリズム 143
6.2 回転後の因子負荷量の標準誤差 144
6.2.1 制約付き最尤推定量の漸近分布 145
6.2.2 共分散行列の因子分析 145
6.2.3 相関係数行列の因子分析 148
7 因子得点 152
7.1 因子得点に関する推測 152
7.1.1 線形予測子 153
7.1.2 線形条件付不偏予測子 155
7.1.3 線形相関係数保存予測子 157
7.1.4 直交モデルの場合 160
A 付録 161
A.1 統計ソフトウェアについて 161
文献 163
索引 171
1 はじめに 1
1.1 因子分析とは 1
1.2 因子分析の発展 4
8.
図書
東工大
堀桂太郎著
出版情報:
東京 : 森北出版, 2011.11 viii, 163p ; 26cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第1章 コンピュータの発展
1.1 コンピュータアーキテクチャとは 1
1.2 コンピュータの歴史 3
1.2.1 機械式計算機以前 3
1.2.2 機械式計算機 4
1.2.3 電子式計算機 5
1.2.4 日本における計算機の歴史 7
1.3 コンピュータの分類 9
演習問題 10
第2章 ノイマン型コンピュータ
2.1 ノイマン型コンピュータの基本構成 11
2.1.1 ノイマン型コンピュータの特徴 11
2.1.2 基本構成 11
2.1.3 CPUの発展 12
2.1.4 CPUの構成 14
2.2 ノイマン型コンピュータの基本動作 16
2.2.1 命令実行の流れ 16
2.2.2 基本動作 16
2.2.3 サブルーチンの実行 19
2.2.4 フォン・ノイマンのボトルネック 20
2.2.5 パソコン用CPUの構成と動作 20
演習問題 22
第3章 命令セットアーキテクチャ
3.1 命令 24
3.1.1 機械語命令 24
3.1.2 命令の形式 24
3.1.3 命令セット 27
3.1.4 命令機能の評価 28
3.2 アドレッシング 29
3.2.1 アドレッシングとは 29
3.2.2 各種のアドレッシング 30
演習問題 32
第4章 ハーバードアーキテクチャ
4.1 ハーバードアーキテクチャの構成 33
4.1.1 ハーバードアーキテクチャの特徴 33
4.1.2 ハーバードアーキテクチャの例 36
4.2 RISCとCISC 36
4.2.1 RISCとは 36
4.2.2 CISC,RISCの実例 37
演習問題 40
第5章 演算アーキテクチャ
5.1 データの表現方法 41
5.1.1 10進数の表現 41
5.1.2 負の数の表現 43
5.1.3 実数の表現 44
5.1.4 文字データの表現 46
5.2 演算アルゴリズム 47
5.2.1 加減算アルゴリズム 47
5.2.2 乗算アルゴリズム 47
5.2.3 除算アルゴリズム 51
演習問題 55
第6章 制御アーキテクチャ
6.1 コンピュータの制御 56
6.2 ワイヤードロジック制御方式 56
6.2.1 コンピュータのモデル 57
6.2.2 命令実行時の動作 58
6.3 マイクロプログラム制御方式 61
6.3.1 マクロ命令とマイクロ命令 61
6.3.2 マイクロ命令の形式 62
演習問題 63
第7章 メモリアーキテクチャ
7.1 メモリ装置の基礎 64
7.1.1 メモリ装置の機能 64
7.1.2 メモリ装置の階層 65
7.2 ICメモリ 66
7.2.1 ICメモリの分類 66
7.2.2 RAM 67
7.2.3 ROM 70
7.3 補助記憶装置 72
7.3.1 ハードディスク装置 72
7.3.2 光ディスク装置 75
演習問題 77
第8章 キャッシュメモリと仮想メモリ
8.1 キャッシュメモリアーキテクチャ 78
8.1.1 キャッシュメモリとは 78
8.1.2 マッピング方式 79
8.1.3 主記憶装置への転送方式 81
8.2 仮想メモリアーキテクチャ 82
8.2.1 仮想メモリとは 82
8.2.2 分割方式 83
8.2.3 マッピング方式 85
演習問題 88
第9章 割込みアーキテクチャ
9.1 割込みの概要 89
9.1.1 割込みとは 89
9.1.2 割込みの分類 89
9.1.3 割込みベクタ 90
9.2 割込みの動作 91
9.2.1 割込み処理の流れ 91
9.2.2 割込み受付のタイミング 93
9.2.3 割込み信号の検出 93
9.2.4 ウオッチドッグタイマ 94
演習問題 95
第10章 パイプラインアーキテクチャ
10.1 パイプライン処理の基本 96
10.1.1 パイプラインとは 96
10.1.2 パイプラインの構成 96
10.2 ハザード 97
10.2.1 ハザードとは 97
10.2.2 遅延分岐と分岐予測 99
10.3 高速化技術 101
10.3.1 スーパーパイプライン 101
10.3.2 スーパースカラ 102
10.3.3 VLIW 103
10.3.4 ベクトルコンピュータ 103
10.3.5 マルチプロセッサ 104
演習問題 106
第11章 入出力アーキテクチャ
11.1 入出力装置の制御 107
11.1.1 直接制御方式 107
11.1.2 間接制御方式 108
11.1.3 入出力インタフェース 110
11.2 入力装置 111
11.2.1 キーボード 111
11.2.2 マウス 111
11.3 出力装置 112
11.3.1 ディスプレイ 112
11.3.2 プリンタ 113
11.4 ヒューマン・マシンインタフェース 114
11.4.1 データグローブ 114
11.4.2 3次元感触インタフェース 115
11.4.3 ヘッドマウントディスプレイ 115
演習問題 116
第12章 システムアーキテクチャ
12.1 OSの役割 117
12.1.1 モニタプログラムとOS 117
12.1.2 OSの目的 118
12.1.3 OSの構成 120
12.2 OSの機能 121
12.2.1 プロセス管理 121
12.2.2 入出力管理 122
12.2.3 ファイル管理 123
演習問題 124
第13章 ネットワークアーキテクチャ
13.1 ネットワークの形態 126
13.1.1 集中処理と分散処理 126
13.1.2 LAN 126
13.1.3 伝送制御方式 127
13.2 ネットワークの構成 128
13.2.1 クライアント・サーバ型 128
13.2.2 プロトコル 128
13.2.3 ネットワーク用機器 130
演習問題 132
第14章 コンピュータ設計演習
14.1 簡易コンピュータの構成 133
14.1.1 仕 様 133
14.1.2 構 成 134
14.2 CPUの設計 135
14.2.1 演算回路 135
14.2.2 レジスタ 135
14.2.3 制御回路 136
14.2.4 クロック回路 140
14.3 メモリ回路の設計 142
14.3.1 DMA回路 142
14.3.2 メモリIC 144
14.3.3 書込みパルス発生回路 144
14.3.4 電源回路 146
14.3.5 プログラミング 146
演習問題 147
付録A 148
付録B 148
演習問題の解答 150
参考文献 159
さくいん 160
第1章 コンピュータの発展
1.1 コンピュータアーキテクチャとは 1
1.2 コンピュータの歴史 3
9.
図書
出版情報:
Oxford, UK : Elsevier, c2010 339 p. ; 27 cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
10.
図書
東工大
映像情報メディア学会編
出版情報:
東京 : オーム社, 2010.5 x, 236p ; 21cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
Chapter1 映像符号化の基礎
1.1 映像信号の基礎 1
1.1.1 映像信号のディジタル化 1
1.1.2 映像信号フォーマット 3
1.2 可逆符号化 4
1.2.1 平均情報量(エントロピー) 4
1.2.2 固定長符号と可変長符号 5
1.2.3 ハフマン符号化と算術符号化 7
1.3 映像信号の性質 9
1.3.1 映像信号のフレーム内相関 9
1.3.2 映像信号のフレーム間相関 11
1.3.3 動き補償予測符号化 13
1.3.4 DCT(離散コサイン変換) 15
1.4 視覚特性と量子化 19
1.4.1 視覚特性 20
1.4.2 量子化処理とランレングス符号化 22
1.5 符号化方式の現状とこれから 25
Chapter2 変復調方式の基礎
2.1 変復調とは 27
2.2 ディジタル変調方式 29
2.2.1 振幅変調 29
2.2.2 位相変調 29
2.2.3 振幅位相変調 32
2.2.4 周波数変調 34
2.3 復調方式と誤り率特性 35
2.3.1 QAMの復調 35
2.3.2 誤り率特性 36
2.4 マルチキャリヤ方式 38
2.4.1 OFDM方式 39
2.4.2 OFDM方式の変復調回路 40
2.4.3 OFDM方式のマルチパス妨害対策 41
2.4.4 OFDM方式の伝送フレーム構成 42
2.5 MIMO伝送技術 43
2.5.1 MIMOとは 43
2.5.2 MIMO伝送方式 44
2.5.3 MIMO伝送方式の信号分離方法 44
Chapter3 伝送路符号化の基礎
3-1 誤り訂正符号 48
3.1.1 デジタル放送で用いられる誤り訂正符号 48
3.1.2 線形ブロック符号-ハミング符号,BCH符号,リードソロモン符号 51
3.1.3 畳込み符号およびビタビ復号 58
3.1 4 反復復号を用いた誤り訂正符号-ターボ符号,LDPC符号 60
3-2 セキュリティ技術の基礎 67
3.2.1 セキュリティ技術はなぜ必要か 67
3.2.2 暗号とは 68
3.2.3 共通鍵暗号 69
3.2.4 公開鍵暗号 70
3.2.5 ハイブリッド暗号 72
3.2.6 ハッシュ関数 73
3.2.7 メッセージ認証コード 73
3.2.8 ディジタル署名 75
3.3 デジタル放送のCAS技術 76
3.3.1 CAS技術の概要 76
3.3.2 国内におけるCAS技術 79
3.3.3 海外におけるCAS技術 82
3.4 信号多重,マルチメディア符号化 83
3.4.1 信号多重 83
3.4.2 マルチメディア符号化 90
Chapter4 BSデジタル放送
4.1 ISDB-Sの概要 101
4.2 伝送路符号化方式の構成 103
4.2.1 フレーム構成 104
4.2.2 TMCC情報 105
4.2.3 TMCC基本情報 109
4.2.4 外符号符号化 111
4.2.5 電力拡散 112
4.2.6 インタリーブ 113
4.2.7 時分割多重 116
4.2.8 内符号符号化 117
4.2.9 変調波生成 121
4.3 受信機の構成 125
4.3.1 受信アンテナから選局までの処理 126
4.3.2 伝送路復号 128
4.4 TC8PSK 131
4.5 ビットレートの計算 133
4.6 回線計算 134
4.7 階層変調 136
4.8 BS・広帯域CS放送で用いられる周波数 137
Chapter5 地上デジタル放送
5.1 はじめに-研究・開発の歴史 139
5.2 地上デジタル放送の要求条件 140
5.3 地上デジタル放送方式(ISDB-T) 141
5.3.1 地上デジタル放送方式(ISDB-T)の概要 142
5.3.2 伝送路符号化部の概要 144
5.4 地上デジタル放送の伝送セグメントの構成 160
5.4.1 12セグメントと1セグメントを使用したサービス(ワンセグ)の共存 160
5.4.2 1セグメントの伝送容量 162
Chapter6 ケーブルテレビ
6.1 デジタル放送のケーブルテレビ伝送技術 165
6.1.1 日本におけるディジタル伝送 165
6.1.2 伝送方式の分類 166
6.2 トランスモジュレーション方式 167
6.2.1 トランスモジュレーション方式の概要 167
6.2.2 MPEG 2 TSの再構成 167
6.2.3 QAMによる伝送路符号化 173
6.3 リマックス方式 178
6.3.1 自主放送によるリマックス方式 l78
6.3.2 HITSによるリマックス方式 178
6.3.3 地上デジタル放送における自主放送 180
6.4 パススルー方式 181
6.4.1 BSデジタル放送のパススルー方式 181
6.4.2 地上デジタル放送のパススルー方式 183
6.5 ケーブルテレビの標準化 184
Chapter7 IP伝送技術
7.1 IPTVの伝送方式 185
7.1.1 IPネットワークの基礎 185
7.1 2 IPパケットの伝送 189
7.1.3 IPTV 191
7.2 無線LAN 193
7.2.1 IEEE 802.11系無線LAN 193
7.2.2 無線LAN技術(物理層)概略 194
7.2.3 無線LAN技術(MAC層)概略 195
7.2.4 アドホックネットワーク 199
7.2.5 映像配信における課題 200
Chapter8 映像素材伝送
8.1 SNG 203
8.1.1 概要 203
8.1.2 衛星伝送の基礎 204
8.1.3 SNGの運用 207
8.1.4 SNGの課題 211
8.2 映像FPU 212
8.2.1 映像FPUの概要 212
8.2.2 映像FPU送信装置 1214
8.2.3 映像FPU受信装置 215
8.2.4 映像FPUの周波数割当て 215
8.2.5 映像FPUに必要なビットレート 216
8.2.6 映像FPUの伝送方式 217
8.2.7 映像FPUの回線設計 218
8.2.8 所要フェージングマージン,降雨減衰マージンの算出方法 219
8.3 有線素材伝送 222
8.3.1 非圧縮伝送 222
8.3.2 圧縮伝送 223
参考文献 226
索引 231
Chapter1 映像符号化の基礎
1.1 映像信号の基礎 1
1.1.1 映像信号のディジタル化 1
11.
図書
国際市民交流のためのイタリア語検定協会編
出版情報:
東京 : 国際市民交流のためのイタリア語検定協会 , 東京 : 丸善 (発売), 2013.8- 冊 ; 21cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
1級 : 2012年秋季(第35回)検定/問題
二次試験出題テーマ
2012年秋季(第35回)検定/解答と解説
2級
準2級
1級
1級 : 2012年秋季(第35回)検定/問題
二次試験出題テーマ
2012年秋季(第35回)検定/解答と解説
概要:
2013年秋季検定試験(1・2・準2級)、2014年春季検定試験(準2級)<br />2016年秋季検定試験(1・2・準2級)、2017年春季検定試験(準2級)<br />2017年秋季検定試験(1・2・準2級)、2018年春季検定試験(準
…
2級)を収録。<br />2018年秋季検定試験(1・2・準2級)、2019年春季検定試験(準2級)の問題、解答と解説・音源ダウンロードURLを収載。
続きを見る
12.
図書
東工大
自動車工学編集委員会編著
出版情報:
東京 : 東京電機大学出版局, 2011.10 x, 205p ; 22cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
1.自動車一般 1
1.1 自動車とはなにか 3
1.2 自動車のスタイルと基本構造
1.2.1 スタイリング・デザイン 3
1.2.2 インテリアデザインとパワー・プラント・レイアウト 6
2.エンジンの性能
2.1 往復動ピストンエンジンの作動 11
2.2 オットーサイクルのP-V線図とシリンダ内圧力 12
2.3 エンジン出力 13
2.4 平均有効圧力 14
2.5 エンジン出力特性 14
2.6 ピストン運動 15
2.6.1 クランク機構 15
2.6.2 ピストン速度 16
2.6.3 ピストン加速度 17
2.7 シリンダ内ガス圧力 19
2.8 シリンダ内ガス交換 20
2.8.1 4ストロークエンジン 20
2.8.2 2ストロークエンジン 25
2.9 シリンダ内ガスの圧縮 26
2.9.1 圧縮比,有効圧縮比,実圧縮比 26
2.9.2 圧縮時のガス流動 27
2.10 エンジンの燃焼 28
2.10.1 空燃費 28
2.10.2 ガソリンエンジンの排気組成 28
2.10.3 燃費供給 29
2.10.4 燃費過程 34
2.10.5 燃焼室形状 35
2.10.6 点火装置 38
2.10.7 ノッキング 40
2.11 燃料出力と熱効率 42
2.12 エンジンの出力 43
2.12.1 ピストン 43
2.12.2 ピストンリング 45
2.12.3 コネクティングロッド 47
2.12.4 クランクシャフト 48
2.13 排気系統 49
2.13.1 既燃焼ガス 49
2.13.2 排気ガス浄化装置 49
2.14 潤滑 52
2.14.1 潤滑装置 52
2.14.2 潤滑方法 53
2.15 冷却 53
2.15.1 水冷方式 53
2.15.2 空冷方式 56
2.16 始動装置 56
2.17 発電装置 57
2.18 蓄電池 58
2.18.1 バッテリの構造 58
2.18.2 バッテリ性能 58
2.19 ハイブリッドエンジン,他 58
2.19.1 ハイブリッドエンジンの利点 58
2.19.2 ハイブリッドエンジンの構成 59
2.20 電動機 59
2.21 ガスエンジン 60
3.動力伝達機構と懸架装置および操縦装置
3.1 クラッチ 61
3.1.1 クラッチの必要性 61
3.1.2 クラッチの種類 61
3.1.3 クラッチの容量 63
3.2 トランスミッション 63
3.2.1 トランスミッションの必要性 63
3.2.1 トランスミッションの構造 64
3.3 運転操作の簡略化(オートマチックトランスミッション,CVT) 66
3.3.1 自動変速機 66
3.4 懸架装置 71
3.4.1 懸架装置の動き 71
3.4.2 サスペンションの種類 71
3.4.3 ばねの種類 77
3.4.4 ショックアブソーバ 78
3.5 操縦装置 79
3.5.1 ステアリングシステムのデザイン 79
3.5.2 ステアリングコラムの安全設計 80
3.5.3 ステアリングコラムの諸形式 80
3.5.4 パワーステアリングの安全設計 81
3.5.5 電動パワーステアリング(EPS)の発達 82
4.車体およびタイヤの力学
4.1 空気力学 83
4.1.1 車体に動く空力6分力 83
4.1.2 ボディ形状と空気抵抗 84
4.1.3 走行安定性と空力特性 89
4.1.4 自動車の空力試験 92
4.2 車体の安全構造 96
4.3 タイヤの力学 97
4.3.1 タイヤの動的特性 97
4.3.2 ころがり抵抗 97
4.3.3 制動力と駆動力 99
4.3.3 ハイドロプレーニング 100
4.3.5 スタンディングウェーブ 101
5.運動性能
5.1 走行抵抗 103
5.2 動力性能 106
5.2.1 動力性能の概要 106
5.2.2 エンジン性能曲線 106
5.2.3 走行速度と駆動力 107
5.2.4 変速比と終減速比の選定 110
5.2.5 走行性能線図 113
5.2.6 余裕駆動力・余裕動力(馬力) 115
5.2.7 登坂性能 117
5.2.8 加速性能 118
5.2.9 加速性能の推定 119
5.2.10 燃料消費率 119
5.2.11 動力性能試験法 120
5.3 惰行性能 121
5.3.1 惰行とは 121
5.3.2 惰行運動と基礎方程式 121
5.3.3 惰行試験 122
5.4 制動性能 125
5.4.1 制動運動の概要 125
5.4.2 制動運動の基礎方程式 127
5.4.3 制動性能試験 129
5.5 オートバイの運動 130
5.5.1 オートバイのアライメントなど 131
5.5.2 2輪車はなぜ倒れないのか 132
5.5.3 オートバイの安定 133
5.5.4 オートバイの走行抵抗 136
6.操縦性と安定性
6.1 自動車運動の座標軸の定義 137
6.2 タイヤの特性 139
6.2.1 タイヤと路面間の摩擦力 139
6.2.2 コーナリングフォース 140
6.2.3 コーナリングパワー 144
6.2.4 キャンバスラスト 144
6.2.5 タイヤに生じるモーメント 145
6.2.6 駆動力,制動力とコーナリングフォース 146
6.3 定常円旋回運動 147
6.3.1 低速時の旋回運動 147
6.3.2 高速時の旋回運動 151
6.3.3 スタビリティファクタとスタティックマージン 153
6.3.4 ステア特性 154
6.3.5 ステア特性に及ぼす諸因子 156
6.4 過渡運動 158
6.4.1 動的方向安定性 158
6.4.2 外乱を受けた車両の運動 159
6.4.3 操舵,加速,制動時の車両の運動 160
6.5 限界性能 161
6.5.1 ドリフトアウトとスピンアウト 161
6.5.2 ジャッキアップとホイールリフト 161
6.5.3 横転 161
6.6 駆動方式別の旋回性能特性 162
6.6.1 前輪駆動車(FF車)と後輪駆動車(FR車) 162
6.6.2 タックイン現象 163
6.6.3 キックバック現象 164
6.6.4 トルクステア 164
6.6.5 コンプライアンスステア 165
6.7 4輪駆動車(4WD)の旋回特性 165
6.7.1 4WD車と2WD車(FF,FR)車 165
6.7.2 4WD車の定常円旋回 165
6.7.3 Jターン特性 165
6.7.4 旋回中のパワーオンとパワーオフ 166
6.7.5 4WD車の駆動方式と運動性能 167
6.8 4輪操舵車(4WS) 169
6.8.1 2WSと4WS車 169
6.8.2 4WS機構 169
6.9 オートバイの旋回運動 170
7.自動車人間工学
7.1 ドライバーの運転状況 174
7.1.1 運転するということ 174
7.1.2 運転しやすい,しにくいということ 174
7.1.3 運転できない,できなくなるということ 174
7.2 運転性能と操縦性,安定性のフィーリング 176
7.2.1 道路環境-自動車-ドライバー系 176
7.2.2 運転性能 177
7.2.3 操縦性,安定性のフィーリング 177
7.3 ドライバー・乗員の快適性 178
7.3.1 快適さとは 178
7.3.2 居住性・居住空間 178
7.3.3 空気調和 183
7.3.4 乗り心地 184
7.4 運転時の視覚情報と視認性 186
7.4.1 視界情報の重要性 186
7.5 ドライバーの運転挙動の把握とその評価 190
7.5.1 生体反応として人体から誘導される情報 190
7.5.2 生体情報の測定と解析 192
7.5.3 刺激や外乱に対する人間の生体反応 194
7.5.4 ドライバーの運転感覚による運転状態の主観的評価 195
7.5.5 ドライバーの生体反応による運転状態の客観的評価 195
索引 197
1.自動車一般 1
1.1 自動車とはなにか 3
1.2 自動車のスタイルと基本構造
13.
図書
東工大
Robert B. Grossman [著] ; 奥山格訳
出版情報:
東京 : 丸善, 2010.1 xx, 373p ; 21cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
1 基本的事項 1
1.1 有機化合物の構造と安定性 1
1.1.1 構造式を書くときのルール 1
1.1.2 Lewis構造式と共鳴 4
1.1.3 分子のかたち : 混成 11
1.1.4 芳香族性 14
1.2 Bronsted酸性度と塩基性度 17
1.2.1 pKa値 18
1.2.2 互変異性 21
1.3 反応速度論と熱力学 17
1.4 反応機構を書く前に注意すること 24
1.5 変換反応の種類 27
1.6 反応機構の種類 29
1.6.1 極性機構 29
1.6.2 ラジカル機構 42
1.6.3 ペリ環状反応機構 44
1.6.4 遷移金属触媒および遷移金属介在反応機構 45
1.7 まとめ 45
問題 46
2 塩基性条件における極性反応 53
2.1 C(sp3)-Xσ結合における置換と脱離 : その1 53
2.1.1 SN2機構による置換 54
2.1.2 E2とE1cB機構によるβ脱離 57
2.1.3 置換と脱離の選択性 60
2.2 求電子性π結合への求核種の付加 62
2.2.1 カルボニル化合物への付加 62
2.2.2 共役付加 : Michael反応 71
2.3 C(sp2)-Xσ結合における置換 74
2.3.1 カルボニル炭素における置換 74
2.3.2 アルケニルとアリール炭素における置換 79
2.3.3 金属挿入 : ハロゲン-金属交換 83
2.4 C(sp3)-Xσ結合における置換と脱離 : その2 85
2.4.1 SRN1機構による置換 85
2.4.2 脱離-付加機構による置換 86
2.4.3 一電子移動機構による置換 87
2.4.4 金属挿入 : ハロゲン-金属交換 88
2.4.5 α脱離 : カルベンの発生と反応 89
2.5 塩基で促進される転位反応 93
2.5.1 CからCへの移動 93
2.5.2 CからOまたはNへの移動 95
2.5.3 BからCまたはOへの移動 97
2.6 二つの多段階反応 98
2.6.1 Swern酸化 98
2.6.2 光延反応 99
2.7 まとめ 101
問題 103
3 酸性条件における極性反応 111
3.1 カルボカチオン 111
3.1.1 カルボカチオンの安定性 112
3.1.2 カルボカチオン発生法 : プロトン化の役割 116
3.1.3 カルボカチオンの典型的な反応 : 転位 119
3.2 C(sp3)-Xσにおける置換とβ脱離反応 124
3.2.1 SN1とSN2機構による置換 124
3.2.2 E1機構によるβ脱離 128
3.2.3 置換と脱離の選択性 129
3.3 求核性C=Cπ結合への求電子付加 130
3.4 求核性C=Cπ結合における置換 132
3.4.1 芳香族求電子置換反応 132
3.4.2 ジアゾニウム塩を経るアニリンの芳香族置換反応 136
3.4.3 脂肪族求電子置換反応 139
3.5 求電子性π結合における求核付加と置換 140
3.5.1 へテロ原子求核種 140
3.5.2 炭素求核種 144
3.6 まとめ 149
問題 149
4 環状反応 157
4.1 はじめに 157
4.1.1 ペリ環状反応の種類 157
4.1.2 ポリエンの分子軌道 163
4.2 電子環状反応 165
4.2.1 典型的な反応 165
4.2.2 立体特異性 172
4.2.3 立体選択性 177
4.3 付加環化 179
4.3.1 典型的な反応 179
4.3.2 位置選択性 193
4.3.3 立体特異性 194
4.3.4 立体選択性 201
4.4 シグマトロピー転位 206
4.4.1 典型的な反応 206
4.4.2 立体特異性 211
4.4.3 立体選択性 217
4.5 エン反応 221
4.6 まとめ 224
問題 226
5 ラジカル反応 235
5.1 ラジカル 235
5.1.1 安定性 235
5.1.2 閉殻分子からの発生 238
5.1.3 典型的な反応 243
5.1.4 連鎖機構と非連鎖機構 250
5.2 ラジカル連鎖反応 250
5.2.1 置換反応 250
5.2.2 付加と分裂反応 255
5.3 非連鎖ラジカル反応 264
5.3.1 光化学反応 264
5.3.2 金属による還元と酸化 266
5.3.3 環化芳香族化 274
5.4 その他のラジカル反応 274
5.4.1 アニオン性1,2-転位 : 非共有電子対の反転 174
5.4.2 三重項カルベンとニトレン 275
5.5 まとめ 277
問題 277
6 遷移金属反応 283
6.1 遷移金属の化学 283
6.1.1 構造の書き方 283
6.1.2 電子数の数え方 284
6.1.3 典型的な反応 289
6.1.4 化学量論反応と触媒機構 296
6.2 付加反応 297
6.2.1 後期金属触媒水素化とヒドロメタル化(Pd,Pt,Rh) 297
6.2.2 ヒドロホルミル化(Co,Rh) 299
6.2.3 ヒドロジルコニウム化(Zr) 300
6.2.4 アルケンの重合(Ti,Zr,Scなど) 302
6.2.5 アルケンのシクロプロパン化,エポキシ化,およびアジリジン化(Cu,Rh,Mn,Ti) 304
6.2.6 アルケンのジヒドロキシル化とアミノヒドロキシル化(Os) 306
6.2.7 アルケンとアルキンヘの求核付加(Hg,Pd) 308
6.2.8 共役付加反応(Cu) 311
6.2.9 還元的カップリング反応(Ti,Zr) 312
6.2.10 Pauson-Khand反応 316
6.2.11 Doetz反応(Cr) 318
6.2.12 金属触媒付加環化と環化三量化(Co,Ni,Rh) 321
6.3 置換反応 324
6.3.1 水素化分解(Pd) 324
6.3.2 ハロゲン化アルキルのカルボニル化(Ph,Rh) 326
6.3.3 Heck反応(Pd) 328
6.3.4 求核種とC(sp3)-Xのカップリング反応 : 熊田,Stille,鈴木,根岸,Buchwald-Hartwig,薗頭,およびUllmann反応(Ni,Pd,Ti) 329
6.3.5 アリル置換(Pd) 334
6.3.6 アルケンのパラジウム触媒求核置換 : Wacker酸化 335
6.3.7 Tebbe反応(Ti) 337
6.3.8 コバルト-アルキン錯体におけるプロパルギル置換 338
6.4 転位反応 339
6.4.1 アルケンの異性化(Rh) 339
6.4.2 オレフインとアルキンのメタセシス(Ru,W,Mo,Ti) 339
6.5 脱離反応 342
6.5.1 アルコールの酸化(Cr,Ru) 342
6.5.2 アルデヒドの脱カルボニル化(Rh) 343
6.6 まとめ 343
問題 344
7 総合間題 351
あとがき 357
索引 359
1 基本的事項 1
1.1 有機化合物の構造と安定性 1
1.1.1 構造式を書くときのルール 1
14.
図書
畠山史郎, 三浦和彦編著
出版情報:
東京 : 成山堂書店, 2014.5 viii, 160p, 図版 [8] p ; 19cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
1 PM2.5とは? : PM2.5とはそもそも何なのでしょうか?
PM2.5とはどんな物質ですか? ほか
2 PM2.5の発生と輸送 : PM2.5はどこから発生しているのでしょうか?
森林もPM2.5の発生源となると聞きましたが本当ですか? ほか
3 PM2.5の影響と対策 : PM2.5を吸入することによりどのような病気になるおそれがあるのですか?
PM2.5などの粒子状物質は植物に対して影響があるのでしょうか? ほか
4 光化学スモッグ・黄砂・エアロゾル : 光化学スモッグとPM2.5は関係あるのでしょうか?
PM2.5と同じく中国から飛んでくる黄砂とはどう違うのですか? ほか
1 PM2.5とは? : PM2.5とはそもそも何なのでしょうか?
PM2.5とはどんな物質ですか? ほか
2 PM2.5の発生と輸送 : PM2.5はどこから発生しているのでしょうか?
15.
図書
小林ひとみ, 桑原里奈, 木林理恵共著
出版情報:
東京 : Jリサーチ出版, 2011.4 127p ; 26cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
16.
図書
総務省統計局編集
出版情報:
東京 : 総務省統計局, 2015.2- 冊 ; 26cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
17.
図書
関雅弘著
出版情報:
新潟 : ミューズ・コーポレーション (印刷), 2012.5 149p ; 21cm
シリーズ名:
ガロアへの懸想 / 関雅弘著 ; 4
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
18.
図書
Society for biomaterials
出版情報:
N.J. : Society for Biomaterials, c2013 2 v. (977 p.) ; 27 cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
19.
図書
フランス語教育振興協会編
出版情報:
東京 : フランス語教育振興協会 , 東京 : 駿河台出版社 (発売), 2013.4- 冊 ; 21cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第1部 : 1級の傾向と対策
第2部 : 2013年度問題と解説・解答
第1部 : 準1級の傾向と対策
第1部 : 2級の傾向と対策
第1部 : 準2級の傾向と対策
第1部 : 3級の傾向と対策
第1部 : 4級の傾向と対策
第1部 : 5級の傾向と対策
第2部 2014年度問題と解説・解答 / 2014年度出題内容のあらまし
第2部 / 2014年度問題と解説・解答
2014年度春季出題内容のあらまし
2014年度秋季出題内容のあらまし
第2部 : 2015年度問題と解説・解答
第2部 2016年度問題と解説・解答 / 筆記試験・聞き取り試験
第2部 2016年度問題と解説・解答 / 1次試験・筆記試験—書き取り・聞き取り試験
2次試験・面接
2次試験
第2部 : 2017年度問題と解説・解答
第2部 2017年度問題と解説・解答 / 2017年度春季出題内容のあらまし
2017年度秋季出題内容のあらまし
第2部 : 2018年度問題と解説・解答
1級
準1級
2級
準2級
3級
4級
5級
第1部 : 1級の傾向と対策
第2部 : 2013年度問題と解説・解答
第1部 : 準1級の傾向と対策
20.
図書
東工大
日本バーチャルリアリティ学会編
出版情報:
東京 : 工業調査会, 2010.1 xiv, 384p, 図版 [7] p ; 22cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
口絵
はじめに
監修者・編集委員・執筆者一覧
第1章 バーチャルリアリティとは
1.1 バーチャルリアリティとは何か 5
1.1.1 バーチャルの意味 2
1.1.2 バーチャルリアリティとその三要素 5
1.1.3 バーチャルリアリティと人間の認知機構 7
1.1.4 バーチャルリアリティの概念と日本語訳 8
1.1.5 道具としてのバーチャルリアリティ 10
1.2 VRの要素と構成 10
1.2.1 VRの基本構成要素 11
1.2.1 VR世界のいろいろ 12
1.2.3 VRをどうとらえるか 14
1.3 VRの歴史 16
第2章 ヒトと感覚
2.1 脳神経系と感覚・運動 24
2.1.1 脳神経系の解剖的構造と神経生理学の基礎 24
2.1.2 知覚・認知心理学の基礎 25
2.1.3 感覚と運動 26
2.2 視覚 27
2.2.1 視覚の受容器と神経系 27
2.2.2 視覚の基本特性 28
2.2.3 空間の知覚 30
2.2.4 自己運動の知覚 31
2.2.5 高次視覚 32
2.3 聴覚 33
2.3.1 聴覚系の構造 33
2.3.2 聴覚の問題と音脈分離(音源分離) 35
2.3.3 聴覚による高さ,大きさ,音色,時間の知覚 36
2.3.4 聴覚による空間知覚 38
2.4 体性感覚・内臓感覚 40
2.4.1 体性感覚・内臓感覚の分類と神経機構 40
2.4.2 皮膚感覚 40
2.4.3 深部感覚 44
2.4.4 内臓感覚 45
2.5 前庭感覚 46
2.5.1 前庭感覚の受容器と神経系 46
2.5.2 平衡機能の基本特性 47
2.5.3 身体運動と傾斜の知覚特性 48
2.5.4 動揺病 49
2.5.5 前庭感覚と視覚の相互作用 51
2.6 味覚・嗅覚 52
2.6.1 味覚の受容器と神経系 52
2.6.2 味覚の特性 54
2.6.3 嗅覚の受容器と神経系 56
2.6.4 嗅覚の特性 58
2.7 モダリティ間相互作用と認知特性 59
2.7.1 視覚と聴覚の相互作用 59
2.7.2 体性感覚とその他のモダリティの相互作用 60
2.7.3 思考、記憶と学習 61
2.7.4 アフォーダンス 64
第3章 バーチャルリアリティ・インタフェース
3.1 バーチャルリアリティ・インタフェースの体系 66
3.2 入力インタフェース 69
3.2.1 物理的特性の計測 69
3.2.2 生理的特性の計測 75
3.2.3 心理的特性の計測 78
3.3 出力インタフェース 80
3.3.1 視覚ディスプレイ 81
3.3.2 聴覚ディスプレイ 86
3.3.3 前庭感覚ディスプレイ 88
3.3.4 味覚ディスプレイ 89
3.3.5 嗅覚ディスプレイ 90
3.3.6 体性感覚ディスプレイ 90
3.3.7 他の感覚との複合 94
3.3.8 神経系への直接刺激 95
3.4 入力と出力のループ 96
第4章 バーチャル世界の構成手法
4.1 総論 100
4.1.1 バーチャルリアリティのためのモデリング 100
4.1.2 レンダリング,シミュレーションとモデル 102
4.2.3 処理量とデータ量のトレードオフ 103
4.2 レンダリング 106
4.2.1 レンダリングのためのモデル 106
4.2.2 視覚レンダリングとモデル 107
4.2.3 聴覚レンダリングとモデル 110
4.2.4 力触覚レンダリングとモデル 114
4.3 シミュレーション 118
4.3.1 シミュレーションのためのモデル 118
4.3.2 空間のシミュレーション 119
4.3.3 物体のシミュレーション 124
剛体のシミュレーション 124
変形のシミュレーション 128
流体のシミュレーション 129
4.3.4 人物のシミュレーション 131
第5章 リアルとバーチャルの融合-複合現実感-
5.1 複合現実感 138
5.1.1 概念 138
5.1.2 レジストレーション技術 139
5.1.3 実世界情報提示技術 145
5.1.4 実世界モデリング技術 152
5.2 ウェアラブルコンピュータ 156
5.2.1 概念 156
5.2.2 情報提示技術 157
5.2.3 入力インターフェース技術 161
5.2.4 コンテキスト認識技術 166
5.3 ユビキタスコンピューティング 171
5.3.1 概念 171
5.3.2 ユビキタス環境構築技術 172
第6章 テレイグジスタンスと臨場感コミュニケーション 178
6.1 テレイグジスタンス 178
6.1.1 テレイグジスタンスとは 178
6.1.2 標準型テレイグジスタンス 188
6.1.3 拡張型テレイグジスタンス 190
6.1.4 相互テレイグジスタンス 196
6.1.5 テレイグジスタンスシステムの構成 201
6.2 臨場感コミュニケーション 215
6.2.1 臨場感コミュニケーションと超臨場感コミュニケーション 215
6.2.2 臨場感の構成要素 221
6.2.3 臨場感コミュニケーションのインタフェース 226
6.2.4 臨場感コミュニケーションシステムの実際 232
6.2.5 時間を越えるコミュニケーション 238
第7章 VRコンテンツ
7.1 VRコンテンツの要素 246
7.1.1 VRコンテンツを構成する要素 246
7.1.2 VRコンテンツの応用分野 249
7.1.3 VRコンテンツの日常生活 249
7.2 VRのアプリケーション 250
7.2.1 サイバースペースとコミュニケーション 250
7.2.2 医療 257
7.2.3 教育・訓練(シミュレータとその要素技術) 264
7.2.4 エンタテイメント 269
7.2.5 製造業 274
7.2.6 ロボティクス 278
7.2.7 可視化 286
7.2.8 デジタルアーカイブ,ミュージアム 292
7.2.9 地理情報システム 297
第8章 VRと社会
8.1 ヒト・社会の測定と評価 314
8.1.1 実験の計画 314
8.1.2 心理物理学的測定 315
8.1.3 統計的検定 318
8.1.4 調査的方法とその分析 319
8.1.5 VR心理学 321
8.2 システムの評価と設計 323
8.2.1 VRの人体への影響 323
8.2.2 福祉のためのVR 327
8.2.3 感覚の補綴と拡張 330
8.2.4 運動の補綴と拡張 332
8.3 文化と芸術を生み出すVR 337
8.3.1 メディアの進化 337
8.3.2 高臨場感メディアと超臨場感メディア 338
8.3.3 体感メディアと心感メディア 339
8.3.4 かけがえのあるメディアと、ないメディア 340
8.4 VR社会論 342
8.4.1 VRの社会的受容 342
8.4.2 VRの社会化 344
8.4.3 VRの乱用,悪用 346
8.4.4 VRにかかわる知的財産権 346
8.5 VR産業論 348
8.5.1 ゲームとVR 348
8.5.2 アートへの展開 350
8.5.3 省資源・省エネルギー・安心安全に貢献するVR 353
8.5.4 「いきがい」を生み出す産業むむけて 358
索引 363
日本バーチャルリアリティ学会とは 384
21.
図書
東工大
英語論文作成研究会編
出版情報:
東京 : 共立出版, 2011.10 viii, 220p ; 21cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第1章 基礎編 Basic Course
1.1 英語論文の作成要領 outline for writing scientific papers in English 2
1.1.1 論文の構成 construction of a paper 2
1.1.2和文英訳の例 examples of English translation 3
1.1.3 各章ごとの英作文の具体例 examples of English composition in each chapter 9
1.2式亜図亜ならびに表の書き方 how to write equations, figures, and tables 47
1.2.1 式を含む文章の例 examples of sentences including equations 47
1.2.2 図亜または表を含む文章の例 examples of sentences including figures and tables 59
1.2.3 式亜図亜ならびに表を含む文章の例 examples of sentences including equations, figures, and tables 69
第2章 応用編 Advance Course
2.1 光利用の測定システム light measuring system 78
2.2 生体観測電子顕微鏡 bio-electron microscope 88
2.3 機械的刺激を印加する細胞培養装置 cell culture system for application of mechanical strain 98
2.4 血球の検出技術 sensing techniques for blood cells 115
2.4.1 電気的な検出法 electrical sensing method 116
2.4.2 光による検出方式 light sensing method 121
2.5 無線システムの例 examples of wireless systems 124
2.5.1 通信システム communication systems 124
2.5.2 GPS システム GPS system 128
2.6 テレビカラーマネージメントシステムの例 examples of color management systems on TVs 134
2.7 音声信号処理の例 examples of audio signal processing 146
2.7.1 音声/話者認識システム speech/speaker recognition systems 147
2.7.2 音声信号処理 audio signal processing 150
2.8 Eメールの書き方 how to write E-mails 154
第3章 実践編 Practical Course
3.1 A Hybrid Sensor for the Optical Measurement of Surface Displacement 164
3.1.1 Introduction 165
3.1.2 Both methods and hybrid sensor 168
3.1.3 Experimental results by means of hybrid sensor 178
3.1.4 Conclusion 182
3.2 Noise Analysis and Noise Suppression with the Wavelet Transform for Low Contrast Urinary Sediment Images 184
3.2.1 Introduction 185
3.2.2 Noise Analysis 185
3.2.3 Algorithm for Noise Suppression 188
3.2.4 Discussion of Experimental Results 193
3.3 Charge-to-Mass Ratio Sensor for Toner Particles 197
3.3.1 Introduction 197
3.3.2Principle and Method 198
3.3.3 Experimental System 204
3.3.4 Improvement of the Toner Transportation System 206
3.4 A Pseudo-Super-Resolution Approach for TV Images 208
3.4.1 Introduction 208
3.4.2 Method and System 212
3.4.3 Experimental Results 217
3.4.4 Conclusion 219
第1章 基礎編 Basic Course
1.1 英語論文の作成要領 outline for writing scientific papers in English 2
1.1.1 論文の構成 construction of a paper 2
22.
図書
東工大
木村富美子, 水上象吾著
出版情報:
京都 : 昭和堂, 2010.3 xv, 200p ; 21cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第Ⅰ部 基礎編 1
第1章 算数・数学の復習 3
1.1 数の種類と四則債算 3
1.1.1 数の種類 3
1.1.2 四則演算 10
1.1.3 約数・倍数 10
1.1.4 素数と素因数分解 11
1.1.5 分数の掛け算・割り算 12
1.1.6 累乗と指数 13
1.2 式の計算 14
1.2.1 文字式 14
1.2.2 式の四則演算 15
1.2.3 式の展開 15
1.2.4 有理化 17
1.2.5 因数分解 18
1.2.6 方程式 19
1.2.7 連立方程式 21
1.2.8 不等式 23
1.3 数の関係 24
1.3.1 正比例、反比例 24
1.3.2 比と割合 25
第2章 数の計算 27
2.1 数列 27
2.1.1 等差数列 28
2.1.2 等比数列 28
2.1.3 数列の和・級数 28
2.2 n進数 29
2.3 約数と倍数 31
2.4 数と量の表現 32
2.4.1 比と割合 32
2.4.2 三角比 33
2.4.3 分数の計算 33
2.4.4 無理数の計算34
2.4.5 指数法則 35
2.4.6 対数の計算 36
2.4.7 複素数の計算 38
2.5 章の練習問題 39
2.5.1 練習問題 39
2.5.2 練習問題の解答 40
第3章 式の計算 45
3.1 文字式 45
3.1.1 式の種類 45
3.1.2 式の四則演算 45
3.1.3 式の展開 46
3.1.4 因数分解 47
3.1.5 有理式の計算法則 49
3.2 方程式と不等式 50
3.2.1 方程式 50
3.2.2 連立方程式 51
3.2.3 不等式 53
3.3 章の練習問題 54
3.3.1 練習問題 54
3.3.2 練習問題の解答 55
第4章 関数とクラフ 59
4.1 関数 59
4.2 一次関数 60
4.3 二次関数 63
4.3.1 放物線 63
4.3.2 円・楕円のグラフ 65
4.4 その他の関数 66
4.4.1 分数関数 66
4.4.2 無理関数 68
4.4.3 三角関数 68
4.4.4 指数関数 72
4.4.5 対数関数 74
4.4.6 逆関数 74
4.5 章の練習問題 75
4.5.1 練習問題 75
4.5.2 練習問題の解答 76
第5章 命題・論理 81
5.1 命題 81
5.1.1 命題の意味 81
5.1.2 逆・裏・対偶・否定 83
5.1.3 ド・モルガンの法則 84
5.2 論理85
5.2.1 必要条件・十分条件 85
5.2.2 三段論法 86
5.2.3 背理法 86
5.3 章の練習問題 87
5.3.1 練習問題 87
5.3.2 練習問題の解答 87
第6章 集合と確率 89
6.1 集合 89
6.1.1 集合の法則,定理 89
6.1.2 和集合・積集合 90
6.2 確率 93
6.2.1 順列・組み合わせ 93
6.2.2 確率の意味 95
6.3 章の練習問題 97
6.3.1 練習問題 97
6.3.2 練習問題の解答 98
第7章 平面図形・空間図形 101
7.1 平面図形 101
7.1.1 図形の性質 101
7.1.2 面積 106
7.2 空間図形 109
7.2.1 体積・表面積 109
7.2.2 展開図 111
7.3 図形の応用 114
7.3.1 相似 114
7.3.2 軌跡 115
7.3.3 回転 116
7.4 章の練習問題 117
7.4.1 練習問題 117
7.4.2 練習問題の解答 120
第8章 統計 123
8.1 記述統計 123
8.1.1 度数分布 123
8.1.2 代表値 127
8.1.3 相関係数 129
8.2 推測統計 131
8.2.1 母集団と標本 131
8.2.2 検定 132
8.3 章の練習問題 133
8.3.1 練習問題 133
8.3.2 練習問題の解答 134
第Ⅱ部 応用編 137
第9章 計算問題 139
9.1 速算法と近似法 139
9.2 計算問題 140
9.2.1 整数問題 140
9.2.2 その他の計算問題 141
9.3 章の練習問題 145
9.3.1 練習問題 145
9.3.2 練習問題の解答 147
第10章 文章問題 153
10.1 数の理解 153
10.2 文章問題の把握 154
10.3 割合・比率の問題 155
10.4 章の練習問題 157
10.4.1 練習問題 157
10.4.2 練習問題の解答 160
第11章 複合問題 167
11.1 問題の解き方 167
11.2 章の練習問題 168
11.2.1 練習問題 168
11.2.2 練習問題の解答 171
第12章 演習問題 179
12.1 集合問題の解き方 179
12.2 演習問題 180
12.3 演習問題の解答 185
第Ⅰ部 基礎編 1
第1章 算数・数学の復習 3
1.1 数の種類と四則債算 3
23.
図書
東工大
広島大学総合科学部化学系編
出版情報:
岡山 : 大学教育出版, 2011.9 135p ; 26cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
1.実験を始める前に 6
1.1 実験についての心得 6
1.1.1 予習
1.1.2 実験ノート
1.1.3 出席
1.1.4 実験に要する時間
1.2 実験室における一般的注意 7
1.2.1 基本的エチケット
1.2.2 実験する際の身じたく
1.2.3 実験室の配置
1.2.4 室内と実験台の整理整頓
1.2.5 実験廃棄物の処理
1.3 危険防止のための諸注意 9
1.3.1 薬品による火災の注意
1.3.2 薬品による外傷及び中毒に対する注意
1.3.3 ガラスなどによる外傷の処置とガラス器具の扱い方
1.4 レポートの書き方 11
1.4.1 形式
1.4.2 グラフの描き方
1.4.3 その他の注意
2.実験の基本操作 14
2.1 ガラス器具の洗浄法 14
2.1.1 ガラス器具の洗浄法
2.1.2 実験に関する説明
2.1.3 実験操作
2.2 測容器と電子天秤の使用法 17
2.2.1 測容器の使用法
2.2.2 電子天秤の使用法
2.2.3 実験に関する説明
2.2.4 実験操作
2.3 乾燥法 22
2.3.1 乾燥剤
2.3.2 固体の乾燥
2.4 ろ過法 26
2.4.1 普通ろ過
2.4.2 ろ紙の種類
2.4.3 ガラスろ過器
2.5 化合物の分画法 29
2.5.1 再結晶
2.5.2 分別結晶
2.5.3 脱色
2.5.4 クロマトグラフィー
2.6 有効数字 33
2.6.1 目盛りを読む
2.6.2 結果を比べる
2.6.3 有効数字
2.6.4 測定値の計算~加減法~
2.6.5 測定値の計算~乗除法~
2.6.6 効率的で精度を損なわない計算
2.6.7 例題
3.無機定性分析 37
3.1 はじめに 37
3.1.1 無機定性分析の基礎
3.1.2 沈殿の生成・溶解
3.1.3 イオン分族とその基本的な考え方
3.1.4 陽イオン分族操作の概要
3.2 実験に関する説明 47
3.2.1 実験器具
3.2.2 実験試薬
3.3 実験操作 49
3.3.1 基本操作と炎色反応
3.3.2 第1族陽イオンの特性反応と系統分析
3.3.3 第2族陽イオンの特性反応と系統分析
3.3.4 第3族陽イオンの特性反応と系統分析
3.3.5 未知試料により第1族から第3族までの陽イオンの系統分析
4.ガラス細工 67
4.1 はじめに 67
4.1.1 ガラス細工について
4.1.2 ガラスの種類と組成
4.1.3 ガラスの加工
4.2 実験に関する説明 67
4.2.1 実験器具
4.3 実験操作 68
4.3.1 バーナーの構造と使用法
4.3.2 管の持ち方
4.3.3 管の切断法
4.3.4 管の伸ばし方
4.3.5 管の曲げ方
4.3.6 管の溶接の仕方
4.3.7 圧縮輪とゴム止めの作り方
4.3.8 焼きなまし
4.3.9 歪みの検査
4.3.10 ガラス細工の実施
4.3.11 実験のあとしまつ
5.有機合成 77
5.1 はじめに 77
5.1.1 有機合成の基礎と一般的注意
5.1.2 パラレッドの合成と染色
5.1.3 パラレッド合成に用いられる反応の説明
5.2 実験に関する説明 83
5.2.1 実験器具
5.2.2 実験試薬
5.3 実験操作 85
5.3.1 アセトアニリドの合成
5.3.2 p-ニトロアニリンの合成
5.3.3 パラレッドの合成
6.酸塩基滴定 95
6.1 はじめに 95
6.1.1 滴定法(容量分析)の原理
6.1.2 酸塩基滴定(中和滴定)
6.1.3 標準溶液と1次標準、2次標準
6.1.4 pHの定義について
6.1.5 ガラス電極pHメーター
6.1.6 弱酸の解離と酸解離定数
6.2 実験に関する説明 101
6.2.1 実験器具
6.2.2 実験試薬
6.3 実験操作 103
6.3.1 シュウ酸標準溶液の調製
6.3.2 pHメーターの調整とpH測定
6.3.3 滴定曲線とpH指示薬の変色域の測定
6.3.4 シュウ酸標準溶液によるNaOH溶液の標定
6.3.5 NaOHによる酢酸溶液の滴定と酢酸の酸解離定数の決定
7.吸光光度法による定量 110
7.1 はじめに 110
7.1.1 物質による光の吸収
7.1.2 吸光光度法の法則
7.1.3 透過スペクトルと吸収スペクトル
7.1.4 検量線の作成と吸光光度法による定量
7.1.5 分光光度計の原理
7.2 実験に関する説明 113
7.2.1 実験器具
7.2.2 実験試薬
7.3 実験操作 115
7.3.1 試薬調製
7.3.2 分光光度計の準備
7.3.3 吸収スペクトル測定溶液の調製
7.3.4 吸収スペクトルの測定
7.3.5 検量線の作成
7.3.6 未知試料の鉄(Ⅱ)濃度の決定
8.実験のおわりに 120
8.1 第一実験室 120
8.2 第二実験室 120
8.3 第三実験室 121
付録1 定性分析用試薬の調製方法 124
付録2 常用対数表(1~99) 126
付録3 水の密度 129
付録4 原子量表 130
付録5 廃液の分別収集一例 131
付録6 広島大学総合科学部化学系教員室等の配置図 132
1.実験を始める前に 6
1.1 実験についての心得 6
1.1.1 予習
24.
図書
総務省統計局編集
出版情報:
東京 : 総務省統計局, 2010.1- 冊 ; 26cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
25.
図書
東工大
小笠原義仁著
出版情報:
東京 : 培風館, 2011.9 vi, 143p ; 22cm
シリーズ名:
情報数理シリーズ ; A-9
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
1. 準備 : 集合についての議論 1
1.1 直感的にわかる集合の議論 1
1.1.1 集合の表記 1
1.1.2 部分集合 2
1.1.3 和集合,共通部分,補集合 3
1.1.4 直積集合 7
1.2 直感的にわかる写像の議論 7
1.2.1 写像の定義 7
1.2.2 全射 8
1.2.3 単射 9
1.2.4 全単射,逆写像,合成写像 11
1.3 多くの集合を利用した議論 14
1.4 順序関係と同値関係 25
1.4.1 順序関係 25
1.4.2 同値関係 26
1.5 まとめ 31
1.5.1 定義 31
1.5.2 諸性質 33
2. 位相空間論の直感的な理解に向けて 35
2.1 位相空間,開集合 35
2.2 開基 39
2.3 距離空間 43
2.4 連続写像 50
2.5 部分空間 55
2.6 連結 62
2.7 完備距離空間 67
2.8 閉包,閉集合 73
2.9 内部,境界,外部 83
2.10 コンパクト 86
3. 開かれた可能性に向けて 95
3.1 密着位相,離散位相 95
3.2 分解空間 99
A. 実数Rについて 105
A.1 準備 105
A.2 連結,完備,コンパクトについて 108
問題の解答 113
参考文献 141
索引 142
1. 準備 : 集合についての議論 1
1.1 直感的にわかる集合の議論 1
1.1.1 集合の表記 1
26.
図書
東工大
平手小太郎著
出版情報:
東京 : 数理工学社 , 東京 : サイエンス社 (発売), 2011.10 xii, 234p ; 22cm
シリーズ名:
新・建築学 ; TKA-9
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第1章 太陽放射と日照 1
1.1 太陽放射の効果 2
1.1.1 太陽放射の分光分布 2
1.1.2 紫外放射 2
1.1.3 可視放射 4
1.1.4 赤外放射 6
1.1.5 日照、日射 7
1.2 日照の効果 8
1.2.1 日照の効用・影響 8
1.2.2 日照の意義 8
1.3 日照の指標 10
1章の問題 12
第2章 日照・日影 13
2.1 太陽の動き 14
2.1.1 太陽位置 14
2.1.2 時法 16
2.2 日照・日影の表示 18
2.2.1 太陽位置図 18
2.2.2 日影曲線 20
2.2.3 日ざし曲線 21
2.3 日照・日影の検討 22
2.3.1 日影曲線による日照・日影の検討 22
2.3.2 日照図表等による日照・日影の検討 23
2章の問題 26
第1章 太陽放射と日照 1
1.1 太陽放射の効果 2
1.1.1 太陽放射の分光分布 2
27.
図書
東工大
遠藤靖典著
出版情報:
東京 : コロナ社, 2010.4 viii, 228p ; 21cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
1. 情報通信ネットワークの概要
1.1 基本概念 1
1.1.1 通信とは 1
1.1.2 伝達の仕方 2
1.1.3 情報通信ネットワークとは 2
1.2 ネットワークの歴史 3
1.2.1 電話網 3
1.2.2 コンピュータネットワーク 5
1.3 ネットワークの分類 7
1.3.1 情報の種類による分類 7
1.3.2 サービス対象による分類 8
1.3.3 規模による分類 8
1.3.4 伝送方式による分類 9
1.3.5 交換方式による分類 9
1.4 ネットワークの構成条件と解決すべき問題 10
1.4.1 構成条件 10
1.4.2 解決すべき問題 11
2. ネットワーク構成の基本要素
2.1 通信端末装置 13
2.2 伝送路 14
2.2.1 有線伝送路 14
2.2.2 無線伝送路 21
2.3 交換機 25
2.3.1 役割 25
2.3.2 現在までの流れ 25
2.3.3 構造 27
3. ネットワークトポロジー
3.1 グラフ理論の基礎 28
3.1.1 グラフの規定 28
3.1.2 経路と連結性 29
3.1.3 グラフの例 30
3.1.4 オイラーグラフ 31
3.1.5 木とカットセット 32
3.2 ネットワーク 32
3.2.1 枝容量と経路表現 33
3.2.2 ネットワークのフロー 33
3.3 さまざまな構造のネットワーク 36
3.3.1 ネットワークの構造を決定する要因 36
3.3.2 さまざまなネットワークトポロジー 37
4. 伝送技術
4.1 フーリエ変換の基礎 40
4.1.1 フーリエ変換の概要 40
4.1.2 周期波のフーリエ級数展開 41
4.1.3 複素フーリエ級数展開 42
4.1.4 孤立波のフーリエ変換 43
4.1.5 周期波のフーリエ変換 44
4.1.6 畳込み 46
4.2 変調方式 47
4.2.1 概要 47
4.2.2 変調の種類 49
4.2.3 正弦変調方式 51
4.2.4 パルス変調方式 58
4.2.5 ディジタル変調方式 64
4.2.6 パルス符号変調方式 68
4.3 通信方式 71
4.3.1 伝送方向による種別 71
4.3.2 監視方式 72
4.4 多元接続・多重伝送 72
4.4.1 周波数分割多元接続 74
4.4.2 時分割多元接続 75
4.4.3 符号分割多元接続 77
4.4.4 光波長多重伝送 80
4.5 同期方式 80
4.5.1 非同期式 81
4.5.2 同期式 81
4.6 誤り制御 82
4.6.1 概要 82
4.6.2 誤り訂正・検出 84
4.6.3 代表的な誤り制御方式 86
5. 交換技術
5.1 交換機の概要 90
5.2 交換方式の分類 91
5.3 回線交換方式 93
5.3.1 空間分割交換方式 93
5.3.2 時分割交換方式 93
5.4 蓄積交換方式 96
5.4.1 概要 96
5.4.2 メッセージ交換方式 97
5.4.3 パケット交換方式 98
5.4.4 フレームリレー交換方式 101
5.4.5 ATM交換方式 103
5.5 信号方式 105
5.5.1 信号の種類 105
5.5.2 個別線信号方式 106
5.5.3 共通線信号方式 106
5.6 ネットワーク制御 108
5.6.1 ネットワーク制御の概要 108
5.6.2 ルーティングの分類 110
5.6.3 固定ルーティング 111
5.6.4 適応ルーティング 112
6. トラヒック理論
6.1 トラヒック理論の概要 116
6.2 基本単位 117
6.3 呼の生起分布 118
6.3.1 ランダム生起 118
6.3.2 準ランダム生起 121
6.4 呼の保留時間分布 122
6.4.1 一般的性質 123
6.4.2 保留時間分布の合成 123
6.4.3 種々の分布関数 124
6.5 トラヒック解析 128
6.5.1 交換線群 128
6.5.2 ケンドールの記号 129
6.5.3 輻輳 130
6.5.4 状態遷移確率 131
6.5.5 トラヒック解析の手順 134
6.5.6 即時式入線数無限完全線群の解析と大群化効果 134
6.5.7 即時式入線数有限完全線群の解析 139
6.5.8 待時式入線数無限完全線群の解析 140
7. ネットワークプロトコル
7.1 プロトコルの概要 143
7.1.1 現在までの流れ 143
7.1.2 プロトコルの三つの分類 145
7.2 データ通信プロトコル 145
7.2.1 DTE-DCE インタフェース 146
7.2.2 伝送制御手順 147
7.3 OSI参照モデル 150
7.3.1 概要 150
7.3.2 OSI 参照モデルの階層化構造 151
7.4 TCP/IP 154
7.4.1 概要 154
7.4.2 TCP/IP の階層化構造 155
7.4.3 IP 156
7.4.4 TCP 157
7.4.5 TCP/IP に含まれる通信サービス 158
8. ネットワークの信頼性
8.1 信頼性の概念 161
8.2 装置の信頼性 162
8.2.1 動作時間 162
8.2.2 信頼度関数 163
8.2.3 故障率 165
8.2.4 バスタブ曲線 168
8.2.5 稼働率 169
8.3 構造の信頼性 171
8.3.1 連結度と結合度 171
8.3.2 さまざまなトポロジーの連結度・結合度・冗長度 173
9. ネットワークセキュリティ
9.1 ネットワークセキュリティの概念 175
9.2 暗号 176
9.2.1 概要 176
9.2.2 秘密鍵暗号 178
9.2.3 公開鍵暗号 180
9.3 認証 184
9.3.1 ハッシュ関数 184
9.3.2 メッセージ認証 184
9.3.3 ユーザ認証 185
10. さまざまなネットワーク
10.1 固定電話網 187
10.1.1 品質 187
10.1.2 番号計画 189
10.1.3 信号の流れ 190
10.1.4 構成 192
10.2 携帯電話とPHS 194
10.2.1 移動体通信網 194
10.2.2 携帯電話 196
10.2.3 PHS 200
10.3 無線LAN 203
10.4 ADSL 205
10.4.1 概要 205
10.4.2 変調方式 205
10.4.3 構成 206
10.5 ISDN 208
10.5.1 概要 208
10.5.2 特徴 209
10.5.3 Iインタフェース 2100
10.5.4 次世代高速ISDN 213
10.6 インターネット 215
10.6.1 発展の流れ 215
10.6.2 利用目的 216
10.6.3 プロバイダとAUP 217
10.6.4 インターネットへの接続形態 218
引用・参考文献 221
索引 223
1. 情報通信ネットワークの概要
1.1 基本概念 1
1.1.1 通信とは 1
28.
図書
千葉滋著
29.
図書
ゲーテ [著] ; 高橋義孝訳
30.
図書
北村薫 [著]
目次情報:
続きを見る
マスカット・グリーン
腹中の恐怖
微塵隠れのあっこちゃん
三つ、惚れられ
よいしょ、よいしょ
元気でいてよ、R2‐D2。
さりさりさり
ざくろ
スイッチ
マスカット・グリーン
腹中の恐怖
微塵隠れのあっこちゃん
概要:
気心のしれた女同士で飲むお酒は、自分を少し素直にしてくれる...そんな中、思い出すのは、取り返しのつかない色んなこと(「元気でいてよ、R2‐D2。」)。産休中の女性編集者の下に突然舞い込んだ、ある大物作家の原稿。彼女は育児に追われながらも、
…
自ら本作りに乗り出すが...(「スイッチ」)。本人ですら気付かない本心がふと顔を出すとき、世界は崩れ出す。人の本質を巧みに描く、書き下ろしを含む9つの物語。
続きを見る
31.
図書
東工大
吉田彰編著 ; 藤井正浩 [ほか著]
出版情報:
東京 : 日本理工出版会, 2011.11 viii, 242p ; 22cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
まえがき
第1章 機械要素設計の基礎
1.1 機械と機械要素設計 1
1.1.1 機械と機械要素 1
1.1.2 設計の概念とプロセス 2
1.1.3 設計と標準化 4
1.2 材料強度・剛性と設計 6
1.2.1 静的強度 6
1.2.2 動的強度 14
1.2.3 高温および低温強度 21
1.2.4 許容応力と安全率 23
1.3 寸法精度と表面粗さ 25
1.3.1 寸法公差 25
1.3.2 はめあい 27
1.3.3 表面粗さ 29
演習問題 33
第2章 ね じ
2.1 ねじの基本と規格 35
2.1.1 ねじの基本 35
2.1.2 ねじの種類 36
2.2 ねじに作用する力と効率 39
2.2.1 ねじに作用する力 39
2.2.2 ねじの効率 41
2.2.3 締結ボルトに作用する力 44
2.3 ねじの強度 45
2.3.1 軸方向引張荷重を受ける場合 45
2.3.2 軸方向の荷重とねじりトルクを同時に受ける場合 46
2.3.3 せん断荷重を受ける場合 47
2.3.4 ねじのはめあい部の長さ 48
2.4 ねじ部品 50
2.4.1 ボルトとナット 50
2.4.2 ねじの緩み止めと座金 51
演習問題 54
第3章 軸・軸継手
3.1 軸の種類 57
3.1.1 断面形状による分類 57
3.1.2 作用による分類 57
3.1.3 軸線による分類 58
3.2 軸の強度と剛性 58
3.2.1 軸のトルクと動力 59
3.2.2 ねじりを受ける軸 60
3.2.3 曲げを受ける軸 61
3.2.4 ねじりと曲げを同時に受ける軸 63
3.2.5 軸の剛性 65
3.3 危険速度 67
3.4 キー,スプラインとセレーション 69
3.4.1 キー 69
3.4.2 スプラインとセレーション 72
3.4.3 ピン 72
3.4.4 フリクションジョイント 73
3.5 軸継手 74
3.5.1 軸継手の種類 75
3.5.2 軸継手の設計 77
演習問題 80
第4章 軸 受
4.1 軸受の種類 83
4.2 すべり軸受 84
4.2.1 流体潤滑の理論 85
4.2.2 ジャーナル軸受 90
4.2.3 軸受設計 92
4.3 転がり軸受 94
4.3.1 転がり軸受の形式と構造 94
4.3.2 転がり軸受の寿命 99
4.3.3 動等価荷重 102
4.3.4 疲れ寿命の補正 104
4.3.5 許容回転速度 104
4.3.6 転がり軸受の使用方法 104
演習問題 107
第5章 歯 車
5.1 歯車の種類 109
5.2 平歯車の創成歯切 112
5.3 歯車用語と平歯車のかみあい 113
5.3.1 歯車用語と非転位平歯車の寸法 113
5.3.2 かみあい率 115
5.3.3 歯面のすべりとすべり率 116
5.4 歯車の切下げ 118
5.5 転位歯車 119
5.5.1 転位歯車の切下げ限界 119
5.5.2 転位歯車の幾何 120
5.5.3 転位歯車のかみあい 121
5.5.4 歯先とがり 123
5.6 はすば歯車 125
5.6.1 はすば歯車のかみあい率 126
5.6.2 相当平歯車 127
5.7 歯車の強度設計 128
5.7.1 歯に作用する力 128
5.7.2 歯の曲げ強さ 129
5.7.3 歯面強さ 132
5.8 歯車の寸法管理 134
演習問題 137
第6章 ベルト・チェーン
6.1 巻掛け伝動装置 139
6.2 平ベルト伝動 139
6.2.1 摩擦伝動ベルトの基礎 139
6.2.2 平ベルト 143
6.2.3 平プーリ 144
6.2.4 平ベルト伝動装置の設計 144
6.3 Vベルト伝動 146
6.3.1 Vベルトの基礎 146
6.3.2 Vベルト 147
6.3.3 Vプーリ 149
6.3.4 細幅Vベルト伝動装置の設計 150
6.4 歯付ベルト 155
6.5 チェーン伝動 155
6.5.1 ローラチェーン 156
6.5.2 スプロケット 157
6.5.3 ローラチェーン伝動装置の設計 158
演習問題 160
第7章 クラッチ・ブレーキ
7.1 動力制御要素 161
7.2 クラッチ 161
7.2.1 かみあいクラッチ 161
7.2.2 摩擦クラッチ 162
7.2.3 自動クラッチ 166
7.3 ブレーキ 167
7.3.1 ブロックブレーキ 168
7.3.2 ドラムブレーキ 170
7.3.3 バンドブレーキ 171
7.3.4 ディスクブレーキ 172
7.4 つめ車 173
演習問題 175
第8章 ば ね
8.1 ばねの用途と種類 177
8.2 コイルばね 179
8.2.1 圧縮コイルばね 179
8.2.2 引張コイルばね 182
8.2.3 有効巻数 183
8.2.4 サ-ジング 183
8.3 重ね板ばね 185
8.4 トーションバー 187
8.5 その他のばね 189
演習問題 191
第9章 管・継手・バルブ・シール
9.1 管 193
9.1.1 管の種類 193
9.1.2 管の選定方法 194
9.2 管継手 197
9.2.1 管継手の種類と分類 197
9.2.2 接続方式 198
9.3 バルブ 199
9.4 シール 201
9.4.1 回転用シール 201
9.4.2 往復動用シール 203
9.4.3 ガスケット 204
9.4.4 シールの選定方法 206
演習問題 207
演習問題解答 209
参考図書 229
付表 233
索引 237
まえがき
第1章 機械要素設計の基礎
1.1 機械と機械要素設計 1
32.
図書
棚橋明美, 杉山ますよ, 野原ゆかり共著
出版情報:
東京 : Jリサーチ出版, 2011.4 61p ; 26cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
33.
図書
東工大
川口春馬監修
目次情報:
続きを見る
【第1編 微粒子製造と新規微粒子】
第1章 注目の微粒子作製技術
1. 金属・金属酸化物ナノ粒子のサイズ形態制御(杉本忠夫) 3
1.1 はじめに 3
1.2 金属および金属酸化物ナノ粒子の合成系とサイズ形態制御 3
1.2.1 均一還元反応系 3
1.2.2 化合物分解系 4
1.2.3 アルコキサイド加水分解系 4
1.2.4 金属イオン加水分解系 5
1.2.5 マイクロエマルション反応系 5
1.2.6 相転移系 5
1.3 最近の異方性貴金属ナノ粒子の生成機構とサイズ形態制御機構に関する考察 6
2. 磁性複合ナノ粒子の放射線や超音波による合成と評価(山本孝夫) 14
2.1 はじめに 14
2.2 複合ナノ粒子合成の問題点 14
2.3 新たな磁性複合ナノ粒子の概要 15
2.4 合成法の解説(放射線の場合を主として) 16
2.5 得られた磁性ナノ粒子の材料評価 19
2.6 得られた磁性ナノ粒子の吸着性能評価 22
3. 有機-無機ハイブリッド微粒子(岩村武、中條善樹) 25
3.1 はじめに 25
3.2 有機と無機のハイブリッド 25
3.3 有機‐無機ハイブリッド微粒子合成へのアプローチ 25
3.4 無機微粒子の表面修飾によるハイブリッド微粒子の合成 26
3.5 有機修飾アルコキシシランを用いた有機‐無機ハイブリッド微粒子の合成 27
3.6 シルセスキオキサンを用いた有機‐無機ハイブリッド微粒子の合成 28
3.7 金属ナノ粒子の表面修飾による有機‐無機ハイブリッド微粒子の合成 29
3.8 おわりに 32
4. 微粒子合成へのリビングラジカル重合の適用(川口春馬) 34
4.1 はじめに 34
4.2 微粒子生成重合 35
4.2.1 懸濁重合 35
4.2.2 乳化重合 35
4.2.3 ミニエマルション重合 35
4.2.4 分散重合 36
4.3 リビングラジカル重合概説 36
4.4 安定ラジカル重合(SFRP)および微粒子系への応用 38
4.5 原子移動ラジカル重合(ATRP)および微粒子系への応用 39
4.6 イニファータ法 41
4.7 Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer 42
4.8 退化的連鎖移動を利用した重合 44
4.9 おわりに 44
5. 微細エマルションの調製技術(福井寛) 46
5.1 はじめに 46
5.2 エマルションの調製方法 47
5.3 界面化学的手法による調製 48
5.3.1 転相乳化法によるエマルションの調製 48
5.3.2 HLB温度乳化法によるエマルションの調製 48
5.3.3 D相乳化法によるエマルションの調製 48
5.3.4 アミノ酸ゲル乳化によるエマルションの調製 49
5.3.5 凝集法によるエマルションの調製 49
5.3.6 マイクロエマルション 51
5.3.7 超臨界マイクロエマルション 51
5.4 機械力によるエマルションの調製 52
5.4.1 高圧ホモジナイザーによるエマルションの調製 53
5.4.2 膜乳化法によるエマルションの調製 53
5.5 おわりに 55
第2章 注目を集める微粒子
1. チタニア粒子の合成と色素増感太陽電池への応用(菊地隆司、星川豊久、江口浩一) 56
1.1 はじめに 56
1.2 グリコサーマル法によるチタニア粒子の調製 57
1.3 色素増感太陽電池の作製および発電性能評価 58
1.4 結果と考察 59
1.4.1 GT法により調製したTiO2と市販TiO2を用いた太陽電池の性能比較 59
1.4.2 GT法で調製したTiO2の結晶子径と発電特性 60
1.4.3 グリコサーマル法により調製したSi-TiO2を用いた電極の発電特性 62
1.4.4 TiO2/Si-TiO2混合電極の発電特性 64
1.5 おわりに 65
2. 中空粒子(藤正督) 67
2.1 はじめに 67
2.2 中空粒子の合成法 67
2.2.1 有機ビーズテンプレート法 67
2.2.2 エマルジョンテンプレート法 69
2.2.3 噴霧熱分解法 72
2.2.4 静電噴霧法 73
2.3 素材別にみた中空粒子 74
2.3.1 酸化ケイ素 74
2.3.2 酸化チタン 75
2.3.3 酸化亜鉛 77
3. バーコード化磁気微粒子(澤上一美、田島秀二) 82
3.1 はじめに 82
3.2 マルチプレックス(多重化)・アッセイ 82
3.3 バーコード化磁気微粒子 83
3.3.1 磁気微粒子 83
3.3.2 磁気微粒子のバーコード化 84
3.3.3 バーコード化磁気微粒子の応用範囲 86
3.3.4 バーコード化磁気微粒子の検出システム 86
3.4 バーコード化磁気微粒子を用いる自動化システム 87
3.5 おわりに 87
4. 球状超分子(今岡享稔、山元公寿) 90
4.1 はじめに 90
4.2 単一構造のナノスケール有機-金属複合体 90
4.2.1 樹状高分子 90
4.2.2 無機金属塩との錯形成 91
4.2.3 金属集積挙動の自在制御 94
4.3 金属集積構造体を利用した触媒への応用 94
4.3.1 錯体担持型触媒 94
4.3.2 金属微粒子系触媒 94
4.3.3 多電子触媒系への応用 95
4.4 おわりに 97
第3章 微粒子集積技術
1. 金属ナノ粒子の1次元配列法(鳥越幹二郎、江角邦男) 100
1.1 はじめに 100
1.2 ナノ粒子の1次元配列法 101
1.2.1 テンプレート法 101
1.2.2 テンプレートフリー法 104
1.3 おわりに 106
2. 二次元コロイド結晶(長井勝利) 108
2.1 はじめに 108
2.2 最密充填型構造の二次元コロイド結晶 108
2.2.1 移流集積法 109
2.2.2 電気泳動デポジション法 110
2.2.3 ラングミュア・ブロジェット(LB)法 110
2.3 非最密充填型構造の二次元コロイド結晶 111
2.3.1 荷電固体表面での単粒子膜形成 112
2.3.2 疎水性固体表面での単粒子膜形成 112
2.3.3 化学反応を伴う単粒子膜形成 114
2.4 パターン化固体表面上での二次元コロイド結晶 114
2.5 応用と展望 115
2.6 おわりに 116
3. 高分子イオンの交互積層多層粒子(須田光広、大久保恒夫) 119
3.1 はじめに 119
3.2 高分子イオンの交互積層多層粒子の調製 122
3.3 交互多層錯体の安定性 124
3.4 交互多層錯体の機能性 127
3.5 おわりに 128
【第2編 微粒子・粉体の応用展開】
第1章 レオロジー・トライボロジーと微粒子
1. 微粒子分散系へのレオロジー(中道敏彦) 133
1.1 はじめに 133
1.2 均一粒径の球形剛体粒子分散系の濃度依存性 133
1.3 非球形粒子および凝集体の濃度依存性 135
1.4 ラテックス濃厚分散体のレオロジー 137
1.5 粒径の影響 139
1.6 ラテックスの配合組成とレオロジー 140
1.6.1 アミン中和の影響 141
1.6.2 共溶剤の影響 141
1.6.3 シックナー、界面活性剤の影響 142
2. ナノ粒子分散系のエレクトロレオロジー(田中克史) 144
2.1 はじめに 144
2.2 マイクロ粒子分散系のER効果と諸問題 144
2.3 ナノ粒子分散系とER効果 145
2.4 ナノ粒子分散系におけるER効果の検討例 146
2.4.1 酸化チタンナノ粒子とその分散系の無電場下におけるレオロジー挙動 146
2.4.2 酸化チタンナノ粒子分散系におけるER効果 147
2.5 おわりに 151
第2章 情報・メディアと微粒子
1. 電子ペーパー(高橋泰樹) 153
1.1 はじめに 153
1.2 電子ペーパー 154
1.3 電子ペーパーの用途・応用例 154
1.4 電子ペーパーに要求される性能 156
1.5 微粒子を用いた電子ペーパーの開発例 157
1.5.1 マイクロカプセル化電気泳動方式 158
1.5.2 マイクロカップ電気泳動方式 159
1.5.3 トナーを用いた電気泳動方式(インプレーン) 159
1.5.4 トナーディスプレイ方式 161
1.5.5 異方性流体を用いた方式 161
1.5.6 電子粉流体方式 161
1.5.7 ツイストボール方式 163
1.6 おわりに 164
2. オンディマンド印刷/乾式電子写真対応グロスコート紙の開発-ナノとミクロのクロステクノロジー(木坂隆一、時吉智文) 166
2.1 はじめに 166
2.2 オンディマンド印刷について 166
2.2.1 大量印刷の時代から1部単位の個人情報を提供できるオンディマンド印刷の時代へ 166
2.2.2 オンディマンド印刷としての電子写真方式の特徴 166
2.3 電子写真方式で要望される用紙と要求品質について 168
2.3.1 オンディマンド印刷で要望される用紙 168
2.3.2 電子写真方式で印刷用グロスコート紙を用いた場合の問題点 168
2.4 PODグロスコートの開発におけるナノとミクロのクロステクノロジー 169
2.4.1 ブリスタ(トナー・ペーパー)改善技術 169
2.4.2 軽量化と定着ロールへの貼り付きの改善 172
2.5 電子写真画質をオフセット印刷に近づけるPODグロスコート 175
2.6 おわりに 176
3. 重合トナー(佐々木一郎) 178
3.1 はじめに 178
3.2 トナーへの要求特性 178
3.2.1 インクジェット法と電子写真法の比較 178
3.2.2 定着性 178
3.2.3 電子写真プロセスからの要求 178
3.2.4 製造コスト 179
3.3 バインダー樹脂 180
3.3.1 重合トナーの現状 180
3.3.2 各種バインダー樹脂の特徴 180
3.3.3 バインダー樹脂とトナーの定着性/耐オフセット性 180
3.3.4 重合トナーにおけるバインダー樹脂の動向 180
3.4 重合トナーの製法 181
3.4.1 粉砕法と重合法 181
3.4.2 重合法の分類 182
3.4.3 懸濁法 182
3.4.4 エマルション凝集法 183
3.5 重合トナーの特徴 184
3.5.1 重合トナーのメリット 184
3.5.2 重合トナーのデメリット 184
3.6 今後の重合トナー 185
3.6.1 トナー製法の本命 185
3.6.2 球形化処理 185
3.6.3 押出転相法 185
3.6.4 結晶性樹脂の活用 186
3.6.5 環境問題 186
3.7 おわりに 186
第3章 生体・医療と微粒子
1. 高分子ミセルやデンドリマーを用いたDDS(横山昌幸) 188
1.1 高分子ミセルによるDDS 188
1.1.1 DDS用薬物キャリヤーとしての特徴 188
1.1.2 研究の歴史 190
1.1.3 目的別分類 193
1.2 デンドリマー 194
1.2.1 DDS用薬物キャリヤーとしての特徴 194
1.2.2 運搬する対象による分類 195
2. 磁性ナノ粒子を用いた新しいガン治療法の開発(小林猛、井藤彰、本多裕之) 197
2.1 はじめに 197
2.2 マグネタイトナノ粒子を用いた磁場誘導加温型温熱療法 197
2.3 温熱療法とガン免疫における熱ショックタンパク質の役割 200
2.4 温熱療法によるガン細胞の免疫原性の亢進 202
2.5 温熱療法によるガン細胞の壊死に伴うHSPワクチン放出 203
2.6 今後の展望 207
3. 金コロイドとその修飾体(佐倉武司、長崎幸夫) 210
3.1 はじめに 210
3.2 金ナノ粒子の調製 210
3.3 バイオディテクションのための金ナノ粒子 211
3.4 安定金ナノ粒子の分子設計 213
3.5 安定金ナノ粒子による分子認識 215
3.6 将来性 216
3.7 おわりに 217
4. 創薬に向けた磁気アフェニティビーズの創製(壺内信吾、西尾広介、池田森人、成松宏樹、郷右近展之、半田宏) 219
4.1 はじめに 219
4.2 SGビーズの開発 220
4.3 ラテックス磁気ビーズの開発 225
4.4 アフェニティクロマトグラフィを利用した薬剤設計と今後の展開 228
第4章 光と微粒子
1. 高輝度液晶ディスプレイ(小池康博、多賀谷明広) 231
1.1 はじめに 231
1.2 光散乱ポリマー導光体と液晶ディスプレイバックライト 232
1.2.1 高輝度光散乱ポリマー導光体の実現 233
1.2.2 色むら解消 237
1.2.3 シートレス光散乱ポリマー導光体バックライトの提案 237
1.3 おわりに 240
2. ゲル粒子の調光材料としての応用(明石量磁郎、筒井浩明) 241
2.1 刺激応答性高分子ゲルとは 241
2.2 刺激応答性高分子ゲル粒子とその応用 241
2.3 着色ゲル粒子からなる新規調光材料 242
2.4 高分子ゲル調光材料の設計と特性 243
2.4.1 ゲル粒子の合成 244
2.4.2 特性評価 245
2.5 調光特性の評価と応用 246
2.5.1 調光特性の評価 246
2.5.2 調光ガラスへの応用検討 247
2.6 今後の展開 249
3. 酸化チタンによる環境浄化(竹内浩士) 251
3.1 はじめに 251
3.2 酸化チタン上での化学反応 251
3.3 ナノ粒子の重要性 252
3.3.1 表面積 252
3.3.2 その他の要因 254
3.4 具体的な材料 254
3.5 環境浄化への応用 256
3.5.1 空気の浄化 256
3.5.2 水質汚濁物質の分解 257
3.5.3 防汚(セルフクリーニング)機能 257
3.5.4 抗菌作用 257
3.6 今後の展開 257
第5章 ナノテクノロジーと微粒子
1. 半導体ナノ粒子(神谷格) 259
1.1 はじめに 259
1.2 半導体ナノ構造 260
1.3 半導体ナノ粒子の液相合成 261
1.4 半導体ナノ粒子の電子物性と応用 264
1.5 配位子と物性 267
1.6 おわりに 268
2. 3次元フォトニック結晶(三澤弘明、松尾繁樹) 270
2.1 はじめに 270
2.2 フォトニック結晶の構造と作製技術 270
2.3 マクロ形状制御による面心立方格子コロイド結晶の作製 272
2.4 おわりに 275
第6章 産業用微粒子
1. 燃料電池電極材料としての複合微粒子(福井武久) 277
1.1 はじめに 277
1.2 SOFC電極の性能と微細構造 279
1.3 SOFC電極開発と構造制御 280
1.4 複合微粒子を原料とする電極微細構造制御 281
1.4.1 LSM‐YSZ複合微粒子を用いた空気極の微細構造制御 282
1.4.2 NiO‐YSZ複合微粒子を適用した燃料極の微細構造制御 283
1.4.3 機械的手法を適用した電極微細構造制御 284
1.5 おわりに 284
2. 磁性流体(藤田豊久) 287
2.1 はじめに 287
2.2 磁性流体の製造方法 287
2.2.1 フェライト粒子分散型磁性流体 287
2.2.2 金属強磁性粒子分散型磁性流体 288
2.3 粒子の分散安定化 288
2.4 磁性流体の磁気特性 290
2.5 磁性流体の力学的特性 290
2.6 磁性流体の応用 292
2.6.1 磁性流体シール 292
2.6.2 磁性流体中の非磁性体あるいは磁性体に作用する力を利用した応用 294
2.6.3 プリンタへの応用 296
2.6.4 磁性流体の磁化の温度依存性を利用した応用 296
2.6.5 光学への応用 297
2.6.6 バイオ関連への応用 298
2.7 他の機能性流体との比較 299
3. 自動車排ガス中の微粒子計測・除去技術(後藤雄一) 302
3.1 自動車排ガス中の微粒子の現状 302
3.2 微粒子計測技術 304
3.3 粒子除去技術 309
3.3.1 酸化触媒 309
3.3.2 DPF 309
3.3.3 NOx吸蔵触媒(LNT;Lean NOx Trap) 311
3.3.4 尿素SCR(Urea SCR) 311
3.3.5 連続再生式DPFと尿素SCRを組み合わせたシステム(SCRTTM) 311
3.4 今後の動向 312
【第1編 微粒子製造と新規微粒子】
第1章 注目の微粒子作製技術
1. 金属・金属酸化物ナノ粒子のサイズ形態制御(杉本忠夫) 3
34.
図書
清水知子, 大場理恵子共著
出版情報:
東京 : Jリサーチ出版, 2018.12 191p ; 26cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
1 : 衣食住
2 : 趣味・活動
3 : 人・心・体
4 : 仕事・組織
5 : 自然・環境
6 : 地域生活
7 : 社会
8 : 科学
9 : 学問・研究
10 : N3‐N5レベルの漢字
1 : 衣食住
2 : 趣味・活動
3 : 人・心・体
概要:
1000の問題を解きながら、N2漢字を自然にマスター。英語・ベトナム語の部分訳、漢越音付き。
35.
図書
東工大
中條善樹, 中建介著 ; 大嶌幸一郎 [ほか] 編
出版情報:
東京 : 丸善, 2010.6 xiii, 252p ; 21cm
シリーズ名:
化学マスター講座
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
1 高分子とは 1
1.1 高分子とは何か 1
1.2 高分子の特性 2
1.3 高分子化学の歴史 4
1.4 高分子の分類 5
1.5 重合反応の分類 7
1.6 高分子の将来 10
演習問題 11
2 重縮合 13
2.1 重縮合の特徴 13
2.1.1 重縮合とは 13
2.1.2 重縮合に用いられる縮合反応とは 14
2.2 高分子の生成条件 18
2.2.1 反応度と分子量の関係 18
2.2.2 化学平衡 20
2.2.3 重縮合と環形成反応 21
2.3 重縮合の速度論 24
2.4 分子量を調節するには 26
2.5 分子量分布 28
2.6 交換反応 30
2.7 重縮合の方法 31
2.7.1 溶融重合法 31
2.7.2 溶液重合法 32
2.7.3 界面重合法 33
2.7.4 固相重合法 34
2.8 縮合系高分子の例 35
2.8.1 ポリアミド 35
2.8.2 ポリエステル 35
2.8.3 ポリカーボネート 36
2.8.4 ポリイミド 37
2.8.5 ヘテロ環構造を有する高分子 37
2.9 エンジニアリングプラスチック 38
2.9.1 エンプラとは 38
2.9.2 耐熱性高分子 39
演習問題 40
3 重付加,付加縮合 41
3.1 重付加の特徴 41
3.1.1 重付加と重縮合 41
3.1.2 重付加に使われる付加反応 43
3.2 重付加の例 45
3.2.1 ポリウレタン 45
3.2.2 イソシアナートを利用したその他の例 48
3.2.3 ラジカル反応が関与する重付加 48
3.2.4 累積二重結合への重付加 49
3.2.5 その他の活性水素化合物の重付加 50
3.2.6 電子移動重付加 52
3.3 付加縮合 54
3.3.1 熱硬化性樹脂 54
3.3.2 フェノール樹脂 54
3.3.3 尿素樹脂 56
3.3.4 メラミン樹脂 56
3.3.5 芳香族炭化水素樹脂 57
3.3.6 エポキシ樹脂 57
3.4 航空・宇宙材料への応用 58
演習問題 60
4 ラジカル重合 61
4.1 ラジカル重合とは 61
4.2 ラジカル重合の素反応 63
4.2.1 開始反応 63
4.2.2 生長反応 64
4.2.3 停止反応 65
4.2.4 連鎖移動反応 66
4.2.5 一次ラジカルによる停止反応 67
4.3 ラジカル重合の速度論 69
4.4 ラジカル重合における重合度と移動定数 73
4.5 ラジカル重合の方法 76
4.5.1 溶液重合 76
4.5.2 塊状重合 76
4.5.3 懸濁重合 76
4.5.4 分散重合 77
4.5.5 乳化重合 77
4.5.6 マイクロエマルション重合 79
4.5.7 固相重合 79
演習問題 80
5 ラジカル共重合 81
5.1 共重合とは 81
5.2 共重合体組成式 83
5.2.1 ラジカル共重合体の速度論的取扱い 82
5.2.2 末端モデル 84
5.3 Q-eスキーム 88
5.4 前末端モデル 90
演習問題 90
6 イオン重合 81
6.1 イオン重合の特徴 91
6.2 アニオン重合 92
6.2.1 アニオン重合可能なモノマー 92
6.2.2 開始剤と開始反応 95
6.2.3 生長反応 96
6.2.4 停止反応 99
6.3 カチオン重合 101
6.3.1 カチオン重合可能なモノマー 101
6.3.2 開始剤と開始反応 102
6.3.3 生長反応 105
6.3.4 停止反応 106
6.4 イオン重合の速度論 107
6.5 イオン共重合 108
6.6 環化重合 112
6.7 ヘテロ原子を含む多重結合の重合 113
6.7.1 孤立ヘテロ多重結合モノマー 113
6.7.2 累積ヘテロ多重結合モノマー 114
6.7.3 α,α-付加型モノマー 115
演習問題 115
7 遷移金属触媒重合 117
7.1 チーグラー-ナッタ重合 117
7.2 メタロセン触媒 122
7.3 メタセシス重合 12ヲ
7.3.1 メタセシス反応とは 123
7.3.2 開環メタセシス重合 123
7.3.3 非環状ジエンメタセシス重合 126
7.4 アセチレン化合物の重合 126
7.5 遷移金属触媒重縮合 127
演習問題 129
8 開環重合 131
8.1 開環重合の特徴 131
8.2 開環重合性 132
8.2.1 開環重合性とは 132
8.2.2 シクロアルカンの熱力学的考察 133
8.2.3 開環反応の活性化エネルギー 136
8.3 カチオン開環重合 137
8.3.1 カチオン開環重合性モノマー 137
8.3.2 カチオン開環重合の開始剤 138
8.4 アニオン開環重合 140
8.5 開環重合の例 141
8.5.1 環状エーテル類の開環重合 141
8.5.2 環状スルフィドの開環重合 144
8.5.3 環状ジスルフィドの開環重合 144
8.5.4 環状イミンの開環重合 145
8.5.5 ラクトン,ラクタムの開環重合 146
8.5.6 その他の例 149
8.6 開環異性化重合 150
8.7 ラジカル開環重合 152
演習 問題 153
9 リビング重合,立体規則性重合 155
9.1 高分子の構造を制御する 155
9.2 リビング重合 155
9.2.1 リビング重合とは 155
9.2.2 リビングアニオン重合 157
9.2.3 リビングカチオン重合 157
9.2.4 リビングラジカル重合 158
9.2.5 リビング配位重合 159
9.2.6 リビング重合の応用と展開 161
9.3 立体規則性重合 162
演習問題 164
10 特殊構造高分子 165
10.1 ブロック共重合体 165
10.2 枝分かれ構造をもつ高分子 167
10.2.1 分岐高分子とは 167
10.2.2 グラフト共重合体 168
10.2.3 スターポリマー 169
10.2.4 特殊なグラフト共重体 170
10.2.5 デンドリマー 171
10.2.6 ハイパーブランチポリマー 174
10.3 架橋反応 183
10.3.1 理想鎖のゲル化 183
10.3.2 架橋反応の方法 185
演習問題 192
11 高分子反応 193
11.1 高分子反応とは 193
11.2 高分子への官能基の導入 193
11.3 官能基変換による高分子の機能化 200
11.4 高分子の分解 202
11.5 高分子反応を利用した機能性高分子の例 205
演習問題 208
12 無機高分子,有機-無機ハイブリッド 209
12.1 無機高分子 209
12.1.1 無機高分子とは 209
12.1.2 ポリシロキサン 211
12.1.3 ポリホスファゼン 215
12.1.4 ポリシラン 218
12.1.5 ポリゲルマンとポリスタナン 219
12.1.6 前駆体高分子 220
12.2 有機-無機ハイブリッド高分子 223
12.3 有機-無機ハイブリッド 225
演習問題 227
13 生体高分子,高分子と環境 229
13.1 環境と高分子 229
13.2 天然高分子 231
13.2.1 概要 231
13.2.2 セルロース 232
13.2.3 デンプン 234
13.2.4 キチン・キトサン 234
13.2.5 タンパク質 235
13.3 生分解性高分子 235
13.3.1 生分解性高分子とは 235
13.3.2 ポリ乳酸 236
13.3.3 微生物を使った高分子合成 240
13.4 酵素触媒重合 241
演習問題 242
参考文献 243
索引 215
1 高分子とは 1
1.1 高分子とは何か 1
1.2 高分子の特性 2
36.
図書
東工大
日本雪氷学会編集
出版情報:
東京 : 朝倉書店, 2010.3 vi, 136p, 図版4p ; 19cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第1章 地上気象観測 1
1.1 はじめに 1
1.2 観測露場 1
1.3 気温,湿度 2
1.3.1 観測方法 2
1.3.2 測器 3
1.4 風向,風速 4
1.4.1 観測方法 4
1.4.2 測器 5
1.4.3 目測観測 7
1.5 日射,反射 7
1.5.1 観測方法 7
1.5.2 測器 7
1.6 降水量 8
1.6.1 観測方法 8
1.6.2 測器 9
1.6.3 捕捉率 9
1.7 大気現象と雲量 12
1.7.1 観測目的 12
1.7.2 雲量 12
1.7.3 大気現象と天気 12
第2章 降積雪の観測 15
2.1 はじめに 15
2.2 積雪深 15
2.2.1 雪尺 15
2.2.2 積雪深計 15
2.2.3 積雪水量 16
2.3 降雪深 18
2.3.1 積雪板 18
2.3.2 降雪の密度と降水量 20
2.3.3 積雪深計を用いた測定方法 20
第3章 融雪量の観測 23
3.1 はじめに 23
3.2 雪面低下法 24
3.2.1 観測方法 24
3.2.2 表層の密度 24
3.2.3 注意点 25
3.3 融雪パン法 25
3.3.1 融雪パン 25
3.3.2 蒸発パン 28
第4章 積雪断面観測 31
4.1 はじめに 31
4.2 準備 31
4.2.1 積雪断面の作成 31
4.2.2 観測機器および測定の準備 33
4.2.3 観測データの整理 34
4.3 雪温 34
4.4 層構造,雪質,粒度(粒径) 36
4.5 密度 39
4.6 含水率 41
4.6.1 秋田谷式含水率計の測定手順 43
4.6.2 遠藤式含水率計の測定手順 44
4.6.3 デノース式含水率計の測定手順 45
4.6.4 含水状態の定性測定(目視観測) 47
4.7 硬度 47
4.7.1 ラム高度の測定手順 49
4.7.2 木下式硬度計の測定手順 51
4.7.3 プッシュゲージによる測定方法 52
4.7.4 硬さの定性測定 53
第5章 化学分析のための積雪試料採取 55
5.1 はじめに 55
5.2 試料採取器具の洗浄 56
5.3 試料採取容器,保存容器の準備と洗浄 56
5.4 観測断面の作り方 57
5.5 採取方法 58
5.6 試料の融解と保存 59
第6章 雪粒子の観察と撮影 61
6.1 はじめに 61
6.2 必要な器具 61
6.3 雪粒子の観察 61
6.3.1 形状の観察 62
6.3.2 大きさの観察 63
6.4 雪粒子の撮影 63
6.4.1 基本的な撮影方法 63
6.4.2 より厳しい条件下における撮影 64
6.4.3 撮影例 64
第7章 広域積雪調査(スノーサーベイ) 71
7.1 はじめに 71
7.2 積雪深 72
7.3 積雪水量 72
7.4 スノーサーベイの方法 73
7.4.1 準備 73
7.4.2 測定点での行動 74
第8章 雪崩斜面における積雪安定性評価と弱層テスト 79
8.1 はじめに 79
8.2 積雪安定性評価 79
8.2.1 積雪安定性評価における着目点 79
8.2.2 雪崩の発生パターンとデータ収集 80
8.2.3 積雪安定性評価の手順 81
8.3 弱層テスト 82
8.3.1 弱層テストを実施する場所 82
8.3.2 弱層テストの方法とそれぞれの特徴 83
8.3.3 ハンドテスト 83
8.3.4 ショベルコンプレッションテスト 84
8.3.5 ルッチブロックテスト 88
8.3.6 シアーフレームテスト 92
付録 97
Ⅰ.雪の結晶分類 97
Ⅱ.雪質分類 100
Ⅲ.雪崩分類 106
付表 117
積雪観測用具取扱店リスト 127
文献 128
索引 133
第1章 地上気象観測 1
1.1 はじめに 1
1.2 観測露場 1
37.
図書
東工大
石丸清登著
出版情報:
東京 : 海文堂出版, 2010.5 viii, 231p ; 21cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第1章 記述統計 1
1.1 統計の役割 1
1.2 データの分布状態の把握 1
1.2.1 棒グラフとヒストグラム 2
1.2.2 累積構成比による要因分析 7
1.3 分布状態の定量的把握 13
1.4 Excelの分析ツールによる基本記述統計量 15
第2章 標本調査 19
2.1 集団の代表的統計量 19
2.1.1 母平均と母分散 19
2.1.2 標本平均の性質 21
2.2 正規母集団の統計的推定 23
2.2.1 母平均の区間推定 23
2.2.2 母分散の区間推定 27
2.3 正規母集団に関する検定 30
2.3.1 平均値の検定 31
2.3.2 分散の検定 34
2.4 正規母集団の比較 37
2.4.1 平均値の差の検定 37
2.4.2 等分散の検定 43
2.5 正規性の検定 46
第3章 相関係数と回帰分析 51
3.1 散布図 51
3.2 相関係数 57
3.3 単回帰分析 62
3.3.1 回帰係数の誤差 65
3.3.2 回帰係数の確率分布 67
3.3.3 回帰係数の検定 68
3.4 重回帰分析 77
3.5 カテゴリ変量を説明変数とする回帰分析 87
第4章 判別分析 93
4.1 重回帰分析による2群データ判別 93
4.2 線形判別器 101
4.2.1 境界線 107
4.3 ロジスティック回帰による2群判別 114
4.3.1 最尤推定法 114
4.3.2 分析の適合度 120
4.3.3 回帰係数の検定 124
第5章 分散分析 127
5.1 分散分析とは? 127
5.2 1元配置分散分析 129
5.3 2元配置分散分析 139
5.3.1 交互作用の検定 140
5.3.2 行・列要因効果の検定 147
5.4 回帰分析による分散分析 150
5.4.1 1元配置分散分析 150
5.4.2 2元は位置分散分析 155
第6章 比率の検定 161
6.1 母比率の検定 161
6.1.1 標準正規分布による検定 161
6.1.2 2項分布による検定 164
6.1.3 F分布・β分布による検定 166
6.2 母比率分布の検定(適合度の検定) 169
6.3 母比率の差の検定 174
第7章 関連性の検定 185
7.1 独立性の検定 185
7.1.1 カイ2乗検定 185
7.1.2 フィッシャーの直接確立法 190
7.2 適合度の検定と独立性の検定 194
7.3 2変量の関連性指標 195
7.4 ロジスティック回帰による2群の比較 201
第8章 データ包絡分析 207
8.1 データ包絡分析とは? 207
8.1.1 達成可能な改善目標 207
8.1.2 評価対称となる事業体 208
8.1.3 最適化問題としてのデータ包絡分析 209
8.2 データ包絡分析例 215
参考文献 225
索引 227
第1章 記述統計 1
1.1 統計の役割 1
1.2 データの分布状態の把握 1
38.
図書
千駄ケ谷日本語教育研究所著
出版情報:
東京 : スリーエーネットワーク, 2011.4- 冊 ; 26cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
39.
図書
カント [著] ; 中山元訳
40.
図書
畠山史郎, 野口恒著
出版情報:
東京 : 日刊工業新聞社, 2016.1 156p ; 21cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
序章 : PM2.5はなぜそれほど問題か
第1章 : PM2.5とは何か—その定義と環境基準の取り組み
第2章 : 危惧されるPM2.5の健康影響について
第3章 : PM2.5はどこから発生し、どんな微粒子か
第4章 : PM2.5はなぜ遠くまで飛来するのか—越境飛来メカニズムと観測ネットワーク
第5章 : PM2.5濃度はどのように測りますか—測定方法について
第6章 : PM2.5の拡散をどう防止するか—規制措置と国際協力
第7章 : PM2.5を防ぐにはどんな対策グッズがありますか
序章 : PM2.5はなぜそれほど問題か
第1章 : PM2.5とは何か—その定義と環境基準の取り組み
第2章 : 危惧されるPM2.5の健康影響について
41.
図書
東工大
松澤昭著 ; 浅田邦博, 松澤昭共編
出版情報:
東京 : 培風館, 2010.1-2011.2 2冊 ; 26cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
1 アナログCMOS回路とその学び方 1
1.1 現代におけるアナログCMOS回路技術の位置づけ 1
1.2 電子回路とは 3
1.3 アナログ回路とデジタル回路 3
1.4 アナログ回路とデジタル回路の使い分け 5
1.5 連続時間信号と離散時間信号 5
1.6 現代の電子回路設計に必要な基礎知識 6
2 電気回路理論と信号処理の基礎 9
2.1 電子回路の構成 9
2.2 信号源 10
2.2.1 電圧源 10
2.2.2 電流源 11
2.2.3 電圧源と電流源の等価性 11
2.2.4 制御電源 12
2.2.5 重ねの理 13
2.3 受動素子 14
2.3.1 抵抗 14
2.3.2 容量 15
2.3.3 インダクタ 17
2.4 微分方程式とラプラス変換 20
2.4.1 微分方程式 20
2.4.2 ラプラス変換 21
2.4.3 ラプラス逆変換 25
2.4.4 微分方程式への応用 26
2.4.5 各素子のラプラス表記 27
2.5 回路網方程式の解き方 29
2.5.1 キルヒホッフの法則 29
2.6 回路の時間応答と安定性 31
2.6.1 システム関数とインパルス応答 31
2.6.2 システムの安定性 32
2.6.3 インディシャル応答 33
2.7 システムの周波数特性 36
2.7.1 ポールとゼロおよびシステムの周波数特性 36
2.7.2 ボーデ図と骨格ボーデ図 40
2.8 離散時間システムと■変換 41
2.8.1 ■変換 41
2.8.2 ■変換の性質 43
2.8.3 ■逆変換の方法 45
2.8.4 入出力差分方程式の変換 48
2.8.5 入出力畳み込み演算関係式の変換 49
2.8.6 システムの伝達関数表現(ブロック線図) 49
2.8.7 離散時間システムの特性 50
2.8.8 簡単な離散時間フィルタとその周波数特性 53
2.8.9 伝達関数の極零点配置と周波数特性 55
3 半導体の基礎と半導体デバイス 57
3.1 半導体 57
3.1.1 エネルギー帯 58
3.1.2 電子密度と正孔密度 59
3.1.3 不純物の導入 60
3.2 PN接合ダイオード 61
3.2.1 PN接合 61
3.2.2 空乏層 63
3.2.3 電圧-電流特性 64
3.2.4 接合容量 66
3.3 バイポーラトランジスタ 66
3.3.1 基本電圧-電流特性 67
3.3.2 アーリー効果 70
3.4 MOSトランジスタ 71
3.4.1 MOSトランジスタの基本構造 71
3.4.2 キャリアの発生 71
3.4.3 しきい値電圧 74
3.4.4 電圧-電流特性 74
3.4.5 ドレイン電圧の影響 77
3.4.6 バックゲート効果 79
3.4.7 MOSトランジスタの容量 80
3.4.8 特殊な動作モードと微細化効果 83
3.5 受動素子と寄生素子 88
3.5.1 抵抗 89
3.5.2 容量 90
3.5.3 寄生バイポーラトランジスタ 92
4 MOSトランジスタのアナログ特性 95
4.1 小信号等価回路 95
4.2 小信号パラメータ 96
4.2.1 トランスコンダクタンスgm 96
4.2.2 ボディートランスコンダクタンスgmb 101
4.2.3 ドレインコンダクタンスgds 101
4.2.4 スイッチ回路のオンコンダクタンス 103
4.3 デバイス特性の変動やバラツキ 105
4.3.1 デバイスの温度特性 105
4.3.2 絶対値精度と相対値精度 106
4.4 雑音 109
4.4.1 熱雑音 110
4.4.2 フリッカー雑音(1/f雑音) 112
4.5 歪み 113
4.6 高周波等価回路 115
4.6.1 遮断周波数fT 115
4.7 MOSトランジスタの動作点と基本パラメータの決め方 116
4.7.1 飽和領域での動作 116
5 基本回路 121
5.1 MOSトランジスタを用いた基本増幅回路 121
5.2 各種接地方式 122
5.2.1 ソース接地回路 123
5.2.2 ゲート接地回路 125
5.2.3 ドレイン接地回路 127
5.2.4 カスコード回路 128
5.3 カレントミラー回路 130
5.3.1 基本カレントミラー回路 130
5.3.2 カスコードカレントミラー回路 131
5.4 電圧不感型バイアス電流回路 134
5.4.1 電圧不感型バイアス電流回路 135
5.4.2 バンドギャップ型バイアス回路 136
5.5 差動増幅回路 139
5.5.1 トランジスタ対と差動増幅回路 139
5.5.2 差動信号と同相信号 143
5.5.3 能動負荷を用いた高利得差動増幅器 145
5.6 周波数特性 147
5.6.1 ミラー効果 147
5.6.2 Yパラメータ 148
5.6.3 各種接地回路の周波数特性 149
5.7 負帰還回路技術 153
5.7.1 負帰還の原理 153
5.7.2 負帰還の効果 154
5.7.3 負帰還の種類 156
5.7.4 負帰還回路の安定性 159
6 演算増幅器 161
6.1 演算増幅器の基本特性 161
6.2 演算増幅器の基本回路 162
6.2.1 反転増幅回路 163
6.2.2 正転増幅回路 164
6.3 演算増幅器の線形演算回路への応用 164
6.3.1 加算回路 164
6.3.2 減算回路 165
6.3.3 積分回路 165
6.4 スイッチトキャパシタ回路 166
6.5 周波数特性と時間応答特性 167
6.5.1 小信号周波数特性 167
6.5.2 スルーレート 169
6.5.3 時間応答 170
6.6 基本演算増幅回路 170
6.6.1 基本演算増幅回路の電圧利得 171
6.6.2 基本演算増幅回路の各部の動作と入出力電圧範囲 172
6.7 高利得化 174
6.7.1 カスコード回路 174
6.7.2 折り返しカスコード回路 176
6.7.3 スーパーカスコード回路 178
6.8 コモンモードフィードバック回路 179
6.9 2段構成の演算増幅器と出力バッファ 182
6.9.1 2段構成の演算増幅器 182
6.9.2 出力バッファ 183
6.10 位相補償と周波数特性 186
6.10.1 発振条件 186
6.10.2 1段構成の増幅器の場合 187
6.10.3 2段構成の増幅器の場合 189
6.10.4 スルーレイト 191
6.11 雑音 191
6.12 オフセット電圧 192
7 フィルタ回路 193
7.1 フィルタ特性の仕様 193
7.2 各種フィルタ 194
7.3 伝達関数 195
7.4 群遅延特性 196
7.5 バターワースフィルタとチェビシェフフィルタ 198
7.5.1 バターワースフィルタ 199
7.5.2 チェビシェフフィルタ 201
7.6 LCラダーフィルタ 203
7.7 周波数変換とインピーダンススケーリング 205
7.7.1 周波数変換 206
7.7.2 インピーダンス変換 206
7.8 バイカットフィルタ 208
7.9 積分器 209
7.9.1 0Pアンプを用いた積分器 209
7.9.2 gm-C積分器 209
7.10 能動フィルタの合成 212
7.10.1 バイカットフィルタの合成 212
7.10.2 ラダーフィルタの合成 213
7.10.3 gm-C積分器を用いたラダーフィルタの合成 215
7.11 スイッチトキャパシタフィルタ 218
8 A/D D/A変換器 223
8.1 A/D D/A変換と基本仕様 223
8.1.1 標本化 224
8.1.2 量子化 230
8.1.3 変換特性仕様 231
8.2 D/A変換器 234
8.2.1 バイナリー型D/A変換器 234
8.2.2 デコード型D/A変換器 237
8.2.3 バイナリー型D/A変換器とデコード型D/A変換器 238
8.2.4 グリッチ 238
8.3 A/D変換器 239
8.3.1 並列型A/D変換器 239
8.3.2 直並列型A/D変換器 241
8.3.3 積分型A/D変換器 242
8.3.4 逐次比較型A/D変換器 243
8.3.5 パイプライン型A/D変換器 246
8.4 A/D D/A変換器用ビルディングブロック 250
8.4.1 比較器 250
8.4.2 サンプル・ホールド回路 257
8.5 パイプライン型A/D変換器の基本設計 263
8.5.1 演算増幅器の利得 264
8.5.2 容量ミスマッチ 265
8.5.3 ノイズ 267
8.5.4 演算増幅器の帯域と動作電流 272
9 ΔΣ型A/D D/A変換器 275
9.1 オーバーサンプリング技術 275
9.2 △Σ変調技術 276
9.3 高次の△Σ変調器 278
9.4 △Σ変調器の安定化 282
9.5 カスケード型△Σ変調器 284
9.6 バンドパス△Σ変調器 285
9.7 アナログ積分器 286
9.8 アナログ回路設計における留意事項 287
9.9 DACの出力誤差の低減 289
9.10 △Σ型DAC 291
10 発振回路とPLLシステム 293
10.1 発振回路 293
10.1.1 発振回路の発振条件 293
10.1.2 リング発振器 294
10.1.3 電流制限型リング発振器 296
10.1.4 インバータのジッタと位相雑音 297
10.1.5 LC発振器 300
10.1.6 LC発振器の位相雑音 301
10.2 位相同期ループ(PLL) 304
10.2.1 基本構成と各部の働き 305
10.2.2 フィルタとシステムのふるまい 310
10.2.3 PLLシステムの各部のノイズ特性 317
10.2.4 周波数シンセサイザ 319
10.2.5 データ抽出用PLL 321
10.2.6 PLLシステムのダイナミック動作 323
10.2.7 DLL 324
11 回路シミュレーション技術 327
11.1 SPICEのシミュレーション原理 328
11.2 バイアス条件 332
11.3 各種解析 334
11.3.1 DC解析 334
11.3.2 AC解析 335
11.3.3 過渡解析 337
11.4 いくつかの注意事項 338
11.4.1 初期条件 338
11.4.2 その他の注意事項 339
11.5 コーナー解析とバラツキ解析 341
11.6 SPICEに組み込まれているMOSFETモデル式 342
11.6.1 SPICE用MOSFETモデルの変遷 342
11.6.2 SPICEモデル式の変遷の歴史 343
11.6.3 閾値電圧の変遷の歴史 345
11.7 シミュレータを用いたトランジスタのキャラクタライズ 348
11.7.1 基本特性のキャラクタライズ 349
11.7.2 スイッチのキャラクライズ 353
12 レイアウトと実装技術 357
12.1 素子の配置 357
12.1.1 トランジスタの配置 357
12.2 配線 360
12.2.1 配線抵抗 361
12.2.2 配線容量 362
12.2.3 配線インダクタ 362
12.2.4 IRドロップ 363
12.2.5 配線遅延 364
12.2.6 クロストーク 366
12.3 電源インピーダンスとデカップリング 368
12.4 デジタル回路からのノイズの回り込み 371
参考文献 375
索引 377
1 アナログCMOS回路とその学び方 1
1.1 現代におけるアナログCMOS回路技術の位置づけ 1
1.2 電子回路とは 3
42.
図書
東工大
気象予報技術研究会編集
出版情報:
東京 : 朝倉書店, 2010.4 x, 291p, 図版 [3] p ; 26cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第0編 序論(新田尚)
1. はじめに 2
2. 気象予報士試験について 2
3. 学科試験の勉強の仕方 6
4. 実技試験の勉強の仕方 8
第Ⅰ編 学科試験
第1部 予報業務に関する一般知識
1. 大気の構造(古川武彦) 14
1.1 大気の組成 14
1.2 大気の鉛直構造 14
1.2.1 対流圏,対流圏界面 15
1.2.2 成層圏,成層圏界面 15
1.2.3 中間圏 16
1.2.4 熱圏,電離圏 16
1.2.5 標準大気 16
1.2.6 大気境界層 17
1.3 風・気温の鉛直構造 17
2. 大気の熱力学(山岸米二郎) 20
2.1 理想気体と状態方程式 20
2.1.1 理想気体の状態方程式 20
2.1.2 乾燥空気の状態方程式 20
2.1.3 ダルトンの分圧の法則 20
2.1.4 水蒸気量の表し方 20
2.1.5 湿潤空気の状態方程式 20
2.2 熱力学第一法則 21
2.2.1 内部エネルギーと比熱 21
2.2.2 乾燥空気の断熱変化と温位 21
2.2.3 未飽和湿潤空気の断熱変化 21
2.2.4 静力学平衡(静水圧平衡) 21
2.2.5 断熱減率 21
2.3 大気(空気塊)の熱力学的特性とエマグラム 22
2.3.1 エマグラム 22
2.3.2 湿潤空気塊の断熱変化 22
2.3.3 大気の安定度 23
3. 降水過程(伊藤朋之) 27
3.1 エーロゾル 27
3.2 凝結による雲の発生 27
3.2.1 水蒸気の凝結 27
3.2.2 水滴のサイズと平衡蒸気圧 28
3.2.3 凝結核と雲核 29
3.2.4 凝結による雲粒の成長 29
3.3 雲粒から雨滴への併合成長 29
3.3.1 水滴の落下速度 30
3.3.2 併合過程による水滴の成長 31
3.3.3 「暖かい雨」と「冷たい雨」 31
3.4 氷晶過程 32
3.4.1 氷晶核 32
3.4.2 雪結晶 32
3.4.3 併合成長 33
3.4.4 融解 34
3.5 雲と霧 34
3.5.1 雲 34
3.5.2 霧 35
3.6 気象光学 36
3.6.1 レイリー散乱による大気光象 36
3.6.2 ミー散乱による大気光象 37
3.6.3 幾何散乱による大気光象 37
4. 放射(二宮洸三) 42
4.1 放射の基礎 42
4.2 放射に関する物理法則 42
4.2.1 ウィーンの法則 42
4.2.2 ステファン-ボルツマンの法則 42
4.2.3 放射の距離逆2乗法則 42
4.2.4 太陽の高度角との関係 43
4.3 放射伝達にかかわる過程 43
4.4 放射平衡と大気の温室効果 43
4.4.1 放射平衡と放射平衡温度 43
4.4.2 地球の放射平衡 : 大気が赤外放射を吸収しない場合 44
4.4.3 地球の放射平衡 : 大気が赤外放射を完全に吸収する場合 44
4.5 地球と大気の熱収支 44
4.5.1 熱収支にかかわる諸過程 44
4.5.2 放射対流平衡 45
4.5.3 放射と熱源の緯度分布 45
4.6 放射と大気大循環 45
4.6.1 大気大循環 45
4.6.2 ハドレー循環 45
4.6.3 極循環 45
4.6.4 高緯度気団と熱帯・亜熱帯気団 45
4.6.5 極前線帯と温帯低気圧 46
4.7 放射と気象のリモートセンシング 46
4.7.1 気象レーダー 46
4.7.2 ウインドプロファイラ 46
4.7.3 透過計,散乱計 46
4.7.4 気象衛星観測 46
5. 大気の力学(二宮洸三) 49
5.1 大気の運動と大気に作用する力 49
5.1.1 気象力学の特徴 49
5.1.2 大気中で作用する力 49
5.2 基礎方程式系 50
5.2.1 運動方程式 50
5.2.2 全微分的時間変化と偏微分的時間変化 50
5.2.3 質量保存の法則と連続の式 50
5.2.4 状態方程式と熱力学第一法則 50
5.2.5 基本方程式の活用 50
5.2.6 水蒸気の連続の式 51
5.3 大規模現象を理解するための方程式系 51
5.3.1 静力学平衡 51
5.3.2 等圧面高度傾度と気圧傾度 52
5.3.3 連続の式 52
5.3.4 熱力学第一法則 52
5.4 地衡風と温度風 52
5.4.1 地衡風 52
5.4.2 温度風 53
5.4.3 層厚温度の移流 53
5.4.4 摩擦がある場合の定常状態 54
5.5 傾度風と旋衡風 54
5.5.1 傾度風 54
5.5.2 摩擦力の作用する場合 55
5.5.3 旋衡風 55
5.6 境界層と摩擦 55
5.6.1 境界層と自由大気 55
5.6.2 運動量輸送と摩擦力 55
5.7 水平発散と鉛直流 56
5.7.1 水平発散 56
5.7.2 鉛直流 56
5.8 渦度と渦度方程式 56
5.8.1 鉛直渦度 56
5.8.2 渦度方程式 58
5.8.3 絶対渦度と相対渦度 58
5.8.4 固定点における渦度の変化 59
5.9 擾乱のスケールと発達のメカニズム 59
5.9.1 擾乱のスケール 59
5.9.2 力学的不安定 59
5.10 温帯低気圧の発達 59
5.10.1 地上気圧の変化 59
5.10.2 上昇流 60
5.10.3 渦度方程式 60
5.10.4 準地衡風近似 60
5.10.5 オメガ(ω)方程式と傾向方程式 60
5.10.6 低気圧の発達と傾圧不安定 61
6. 気象現象(山岸米二郎) 64
6.1 成層圏の気象 64
6.2 大気大循環 65
6.2.1 大規模現象 65
6.2.2 エネルギーと水蒸気の循環と収支 66
6.3 総観規模現象(温帯低気圧と台風) 66
6.3.1 温帯低気圧 66
6.3.2 台 風 67
6.4 メソスケール現象 67
6.4.1 メソスケール現象の種類 67
6.4.2 積乱雲 67
6.4.3 積乱雲の組織化 67
6.4.4 竜巻とダウンバースト 68
6.5 海陸風,斜面風,山谷風 68
6.5.1 海陸風 68
6.5.2 斜面風と山谷風 68
7. 気候と環境(伊藤朋之) 72
7.1 気候システム 72
7.1.1 気候システム 72
7.1.2 気候モデル 73
7.1.3 エルニーニョ 73
7.2 気候の変動 76
7.2.1 ミランコビッチの仮説 77
7.2.2 ヤンガードリアス 78
7.2.3 縄文海進 78
7.2.4 マウンダー極小期と小氷期 78
7.2.5 火山噴火 78
7.3 地球温暖化 79
7.3.1 温室効果 79
7.3.2 温室効果気体 80
7.3.3 二酸化炭素 81
7.3.4 地球温暖化 82
7.3.5 温暖化の現状認識 83
7.4 オゾン層とオゾンホール 84
7.4.1 オゾン層問題 84
7.4.2 オゾン層の仕組み 84
7.4.3 オゾンホール 85
7.5 酸性雨 86
7.5.1 酸性沈着 86
7.5.2 酸性雨への取り組みの歴史 86
7.5.3 モニタリング 87
7.5.4 酸性雨関係諸量 87
7.5.5 日本の酸性雨 87
8. 気象業務法その他の気象業務に関する法規(稲葉弘樹) 91
8.1 予報業務の許可 91
8.1.1 予報とは 91
8.1.2 予報業務の許可 91
8.1.3 予報業務の許可の手続き 91
8.1.4 予報業務の変更,休・廃止 91
8.1.5 許可を受けた者の義務 92
8.2 観測に関する遵守事項 92
8.2.1 技術基準に従った観測の実施 92
8.2.2 観測施設の設置・廃止の届出 92
8.2.3 観測成果の報告 93
8.2.4 検定合格測器の使用 93
8.2.5 気象庁長官の求めによる検査の受忍 93
8.3 気象予報士 93
8.3.1 気象予報士とは 93
8.3.2 気象予報士資格の取得 93
8.3.3 気象予報士の登録等 94
8.4 警報・注意報 94
8.4.1 警報・注意報の定義 94
8.4.2 警報・注意報の種類 95
8.4.3 一般の利用に適合する警報・注意報の実施 96
8.4.4 警報・注意報の周知 96
8.4.5 警報の実施制限と例外 96
8.4.6 気象情報 97
8.4.7 消防法の火災警報 97
8.5 気象業務法における罰則 97
8.5.1 罰則の分類 97
8.5.2 遵守義務と行政処分 97
8.6 災害対策基本法 97
8.6.1 国,都道府県および市町村の責務 97
8.6.2 予報・警報の伝達等 98
8.6.3 事前措置および避難 99
8.6.4 応急措置 99
第2部 予報業務に関する専門知識
1. 観測の成果の利用 104
1.1 地上気象観測(足立崇) 104
1.1.1 気圧・風・気温の観測 104
1.1.2 降水,雲,大気現象,その他の観測 105
1.1.3 観測システムとデータの予報への利用 106
1.2 レーダー観測(足立崇) 107
1.2.1 レーダーとそのデータの特徴 107
1.2.2 レーダーのプロダクトとその予報への利用 108
1.2.3 ドップラーレーダーとそのデータの特徴 108
1.2.4 ドップラーレーダーのプロダクトとその予報への利用 109
1.3 高層観測(足立崇) 109
1.3.1 ゾンデによる観測とプロダクト 109
1.3.2 ウィンドプロファイラとそのデータの特徴 110
1.3.3 ウィンドプロファイラのプロダクトとその予報への利用 110
1.4 気象衛星(長谷川隆司) 113
1.4.1 各種気象衛星画像の特徴 113
1.4.2 雲形の判別 114
1.4.3 気象擾乱に伴う雲パターンの特徴 115
1.4.4 主な雲パターンの特徴 117
2 数値予報(新田尚) 122
2.1 数値予報の原理と手頂 122
2.2 数値予報モデル 122
2.3 予報(支配)方程式 123
2.4 物理過程 124
2.5 数値計算 124
2.6 初期値の作成と客観解析 126
2.7 アンサンブル予報 128
2.8 アプリケーション 130
2.9 「数値予報」試験問題の出題傾向 131
3. 短期予報,中期予報(週間予報)(足立崇) 138
3.1 擾乱とそれに伴う天気 138
3.1.1 温帯低気圧と前線 138
3.1.2 台風 139
3.1.3 梅雨前線 140
3.1.4 寒冷低気圧(寒冷渦),寒気内小低気圧(ポーラーロー) 140
3.1.5 高気圧 141
3.2 現象の予報 141
3.2.1 風 141
3.2.2 降雨,降雪,霧 142
3.2.3 雷雨と雷雨に伴う突風 143
3.3 天気予報ガイダンスの利用 144
3.4 解析資料の利用 145
3.4.1 地上および高層天気図 145
3.4.2 高層断面図とジェット気流 146
3.4.3 エマグラム(EMAGRAM) 146
3.5 短期予報 147
3.5.1 短期予報の種類と内容 147
3.5.2 短期予報支援資料の概要 148
3.5.3 予報の手順 148
3.5.4 予報用語 150
3.6 中期予報 151
3.6.1 週間天気予報の種類と内容 151
3.6.2 週間天気予報支援資料の概要 151
4. 長期予報(季節予報)(新田尚) 155
4.1 長期予報(季節予報)とは 155
4.2 日本の天候に影響を与える高気圧 156
4.2.1 太平洋高気圧 156
4.2.2 チベット高気圧 157
4.2.3 オホーツク海高気圧 157
4.2.4 シベリア高気圧 158
4.3 ブロッキング現象 159
4.4 偏西風(ジェット気流)の変動(東西指数)と日本の天候 161
4.4.1 ジェット気流の特性 161
4.4.2 東西指数(ゾーナルインデックス) 162
4.4.3 梅雨前線帯と梅雨ジェット 164
4.4.4 西谷型,東谷型 165
4.5 日本の天候に影響する熱帯の循環 165
4.5.1 熱帯域の熱源と太平洋高気圧などの大気の応答 166
4.5.2 マッデン-ジュリアン振動(MJO) 166
4.6 テレコネクション 166
4.6.1 テレコネクションとは 166
4.6.2 エルニーニョ/ラニーニャ現象 166
4.6.3 北極振動(AO) 169
4.6.4 定常ロスビー波とその影響 169
4.7 長期予報の方法 170
4.7.1 アンサンブル(数値)予報 170
4.7.2 統計的手法による予報 171
4.7.3 長期予報の確率的表現 172
4.8 異常天候早期警戒情報 172
4.9 「長期予報」試験問題の出題傾向 173
5. 局地予報(長谷川隆司) 178
5.1 海陸風 178
5.2 山谷風 178
5.3 おろし 179
5.3.1 フェーン 179
5.3.2 ボラ 180
5.4 積雲,積乱雲 180
5.4.1 集中豪雨 180
5.4.2 竜巻(トルネード) 180
5.4.3 ダウンバースト 181
5.5 都市気候 181
5.5.1 ヒートアイランド 181
5.5.2 その他の都市気象 182
6. 降水短時間予報,降水ナウキャスト(足立崇) 186
6.1 降水短時間予報 186
6.1.1 初期値の作成,解析雨量 186
6.1.2 実況補外予測 187
6.1.3 メソ数値予報による数値予測 188
6.1.4 実況補外予測とMSM予測の結合手法 188
6.1.5 防災情報への利用 188
6.2 降水ナウキャスト 188
7. 気象災害(伊藤朋之) 191
7.1 気象災害と気象情報 191
7.1.1 気象庁の発表する警報と注意報 191
7.1.2 「気象情報」 194
7.2 風害 194
7.2.1 風について 194
7.2.2 風の強さと吹き方 194
7.2.3 藤田スケール 195
7.2.4 強風による被害の様態 195
7.2.5 波浪害 196
7.2.6 高潮害 197
7.2.7 その他の風害 197
7.2.8 風害を発生させる気象条件 198
7.2.9 竜 巻 199
7.2.10 ダウンバースト 199
7.2.11 突風に関する情報 200
7.2.12 突風被害の調査 200
7.3 水害,大雨害 200
7.3.1 洪水・浸水による災害 200
7.3.2 土砂災害 203
7.3.3 水害をもたらす雨量 204
7.3.4 水害をもたらす気象 204
7.4 雪害 205
7.4.1 風雪害 205
7.4.2 積雪害 205
7.4.3 雪圧害 205
7.4.4 着雪害 205
7.4.5 なだれ 206
7.4.6 融雪害 206
7.5 寒冷害,東霜害,濃霧 206
7.5.1 寒冷害 206
7.5.2 凍害 206
7.5.3 霜害 206
7.5.4 濃霧の害 207
7.6 雷災,雷害 207
7.6.1 雷災 207
7.6.2 雹害 208
7.7 冷害,干害,高温害 208
7.7.1 冷害 208
7.7.2 干害 208
7.7.3 長期予報 208
7.7.4 異常天候早期警戒情報 209
7.7.5 猛暑とヒートアイランド現象 209
8. 予想の精度の評価(足立崇) 213
8.1 評価に用いるスコア 213
8.1.1 カテゴリー予報 213
8.1.2 量的予報 213
8.1.3 注意報・警報 213
8.2 降水有無の評価 213
8.3 気温の精度評価 214
8.4 確率予報の評価 214
8.5 予報の検証 214
9. 気象の予想の応用(古川武彦) 217
9.1 気象情報 217
9.2 気象予報と予報区 217
9.3 注意報・警報,伝達,発表基準 220
9.3.1 気象警報の伝達 220
9.3.2 気象警報の種類と内容 220
9.3.3 警報・注意報の発表,切替,継続 220
9.3.4 警報・注意報の発表基準 220
9.3.5 指定河川洪水予報 220
9.4 その他 221
9.4.1 土砂災害警戒情報,土壌雨量指数 221
9.4.2 降水短時間予報,降水ナウキャスト 221
9.4.3 記録的短時間大雨情報 221
9.4.4 竜巻注意情報卒唾 221
9.4.5 台風情報 222
9.4.6 火災警報,火災気象通報 222
9.4.7 異常天候早期警戒情報 222
第Ⅱ編 実技試験
第1部 気象概況およびその変動の把握(長谷川隆司)
1.1 気象概況の把握 226
1.1.1 地上天気図・高層天気図等の解読 227
1.1.2 状態曲線(エマグラム)解析 229
1.1.3 鉛直断面図解析 230
1.1.4 ウィンドプロファイラ解析 231
1.1.5 気象レーダー解析 232
1.1.6 気象衛星画像解析 232
1.1.7 前線の解析 232
1.1.8 温帯低気圧の発達・衰弱 237
1.1.9 重要な天気パターン 240
1.2 気象概況の変動の把握 246
1.2.1 予報作業の流れ 246
1.2.2 天気予報 247
1.3 週間天気予報 247
第2部 局地的な気象の予想(長谷川隆司)
2.1 降水短時間予報 251
2.2 時系列解析 252
2.3 シアライン,収束線解析 254
2.4 集中豪雨 257
2.5 地形効果 258
2.5.1 大規模な現象に伴う地形効果の例 258
2.5.2 局地的な地形効果 258
第3部 台風等緊急時における対応(山岸米二郎)
3.1 第3部で扱う範囲と最近の出題傾向 260
3.1.1 緊急時とは 260
3.1.2 注意報・警報関連の出題範囲 260
3.1.3 新しい防災気象情報 260
3.2 短時間大雨関連の防災気象情報 260
3.3 注意報と警報の発表と解除 262
3.4 沿岸波浪 265
3.5 全般海上警報 266
3.6 台風情報 267
3.7 台風と高潮 269
付録1 まとめのポケット知識(稲葉弘樹) 271
付録2 参考表 278
付録3 天気図分類(澤井哲滋) 281
索引 285
第0編 序論(新田尚)
1. はじめに 2
2. 気象予報士試験について 2
43.
図書
東工大
竹内伝史 [ほか] 共著
出版情報:
東京 : 鹿島出版会, 2011.10 viii, 158p ; 26cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
まえがき
序章 交通と交通計画学
(1) 交通 1
(2) 交通の発達と社会 1
(3) 交通と経済 2
(4) 交通とくらし 4
(5) 交通工学と交通計画学 5
(6) 「地域交通」の計画 5
第1章 交通問題と交通施設
1.1 交通問題の変遷と対策 7
1.1.1 都市交通の混雑とモータリゼーション 7
1.1.2 交通事故と交通公害 13
1.1.3 モータリゼーションが生んだ社会問題 16
1.2 交通施設と交通サービス 18
1.2.1 交通の三要素とサービスによる統合 18
1.2.2 地域交通の政策的把握 19
1.3 交通と社会資本の整備 22
1.3.1 近代国家における交通社会資本整備 22
1.3.2 交通社会資本整備の制度と議論 24
1.3.3 変革期の交通社会資本制度 27
第2章 地域の交通計画
2.1 計画対象としての地域 33
2.1.1 交通圏とその形成要件 33
2.1.2 人々の活動・交流レベルと交通体系 33
2.1.3 地域における日常交通圏とその状況 34
2.1.4 地域が直面している諸問題とその構造 35
2.2 市民の生活活動機会保障のためのモビリティ確保 36
2.2.1 市民のモビリティの本源的意味 36
2.2.2 生活交通という考え方~計画の対象としての生活交通 36
2.2.3 生活を支援する地域交通体系の要件 37
2.3 持続可能な地域社会の形成 38
2.3.1 地球環境問題と交通 38
2.3.2 環境にやさしい地域交通体系 39
2.3.3 安全で安心な地域交通体系 40
2.4 地域交通計画の策定・推進主体 40
2.4.1 地域の行政の「市民の足を守る」責務 40
2.4.2 公的関与の背景と論拠 41
2.4.3 究極の市民参画としての市民の適切な交通行動選択 42
2.5 地域交通計画における主要な施策 43
2.5.1 交通計画の考え方・施策の変遷 43
2.5.2 公共交通の特質と役割 44
2.5.3 交通需要マネジメント(TDM)とモビリティ・マネジメント(MM) 44
2.6 地域公共交通計画 45
2.6.1 地域交通計画(LTP)の経緯 45
2.6.2 地域公共交通マスタープランの役割 46
2.6.3 地域公共交通計画の策定プロセス 47
第3章 総合交通計画の技法
3.1 総合交通計画の意義 51
3.2 総合交通計画策定システム 51
3.2.1 上位計画と関連計画 51
3.2.2 計画策定プロセス 52
3.2.3 計画の進め方 52
3.2.4 計画の各種制約条件 52
3.3 都市交通の実態調査技法 53
3.3.1 総合都市交通体系調査 53
3.3.2 都市交通実態調査 54
3.3.3 都市交通マスタープラン策定調査 54
3.3.4 パーソントリップ調査の実施方法 54
3.3.5 交通量の集計 55
3.3.6 パーソントリップの実態調査の設計 59
3.3.7 地域の交通実態の事例 61
3.4 交通需要推計 70
3.4.1 交通需要の段階推計 70
3.4.2 発生・集中交通量の推計 70
3.4.3 分布交通量の推計 74
3.4.4 交通手段別分担交通量の推計 79
3.4.5 配分交通量の推計 85
3.4.6 非集計分析 91
3.4.7 ネットワーク均衡分析 92
3.5 計画代替案策定技法と計画評価技法 93
3.5.1 計画立案の作業過程 93
3.5.2 計画代替案 95
3.5.3 計画の評価主体 95
3.5.4 計画の評価技法 95
第4章 道路の交通工学と計画・設計
4.1 自動車交通流の概要 97
4.1.1 交通流の特性 97
4.1.2 交通流調査 100
4.1.3 交通量・速度・交通密度の関係 102
4.1.4 その他の自動車交通流の特性 102
4.1.5 歩行者の交通流特性 104
4.2 交通容量 104
4.2.1 交通容量の求め方 104
4.2.2 交通容量とサービス水準 104
4.2.3 単路部の交通容量 107
4.2.4 分・合流部の交通容量 108
4.2.5 平面・信号交差点の交通容量 108
4.2.6 平面交差点の計画と設計 112
4.2.7 信号制御方式 114
4.3 道路の計画 116
4.3.1 道路の機能上の分類 116
4.3.2 道路網計画 116
4.3.3 道路網の構成と地区交通 118
4.4 道路の設計 122
4.4.1 道路の種類 122
4.4.2 道路の設計 124
4.5 道路交通システム 132
4.5.1 ITS(高度道路交通システム) 133
4.5.2 駐車のマネジメント 134
第5章 地域公共交通の計画
5.1 公共交通の体系 137
5.1.1 公共交通 137
5.1.2 公共交通機関の種類 137
5.1.3 公共交通システムと都市規模 140
5.1.4 公共交通の政策 140
5.2 路線網の計画 142
5.2.1 都市の基幹路線網 142
5.2.2 一般路線網とフィーダーシステム 142
5.2.3 都市の少量即応輸送と短距離大量輸送 143
5.3 駅の配置と駅勢圏 144
5.3.1 駅の種類と計画 144
5.3.2 駅配置の計画 144
5.3.3 駅勢圏 146
5.3.4 駅の計画 146
5.4 駅前広場とバスターミナル 147
5.4.1 駅前広場の機能 147
5.4.2 駅前広場の計画 148
5.4.3 駅前広場面積の算定 148
5.4.4 駅前広場の施設配置と設計 150
5.4.5 バスターミナルの計画 152
5.5 公共交通のサービス計画 153
5.5.1 公共交通サービス計画 153
5.5.2 公共交通の経営 153
索引 155
まえがき
序章 交通と交通計画学
(1) 交通 1
44.
図書
東工大
樋口芳樹, 中川敦史著
出版情報:
東京 : 共立出版, 2010.4 xii, 253p, 図版[1]p ; 21cm
シリーズ名:
これからの生命科学 / 津田基之企画
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第1部 構造生物学の基礎
第1章 生物学から構造生物学へ-生物学と構造化学の融合 3
1.1 構造生物学の重要性とその応用 3
1.2 生命-細胞,核酸,タンパク質 5
1.3 遺伝子からタンパク質へ-セントラルドグマ 5
1.4 タンパク質の分類 7
1.5 細胞内のタンパク質-適所,適量,適時の調節 9
第2章 機能性生体高分子(核酸やタンパク質)ができるまで-小分子から生体高分子へ 11
2.1 核酸・タンパク質の基本構造 11
2.1.1 核酸の構成単位-糖,塩基,リン酸 11
2.1.2 核酸(DNA)の高次構造 12
2.1.3 タンパク質の構成単位-アミノ酸 17
2.1.4 アミノ酸から一次構造へ-ペプチド結合 22
2.1.5 一次構造から二次構造へ 25
2.1.6 二次構造から三次構造へ 36
2.1.7 三次構造から四次構造へ 36
2.2 立体構造構築原理 42
2.2.1 構造安定化因子-さまざまな相互作用 42
2.2.2 一次構造から立体(三次)構造へ-タンパク質のフォールディング 49
2.2.3 構造の柔軟性 52
2.3 タンパク質の立体構造がもつ特徴のまとめ 53
第2部 細胞における機能分子の構造生物学
第3章 遺伝情報の発現-転写や翻訳にかかわるタンパク質や核酸 57
3.1 転写システム 58
3.1.1 HTHモチーフによる転写制御 59
3.1.2 Znフィンガーモチーフによる転写制御 65
3.1.3 他のモチーフによる転写制御 68
3.1.4 転写開始 70
3.2 翻訳システム-リボソーム 71
第4章 エネルギーの獲得-生命活動に必要なエネルギー生成にかかわるタンパク質 78
4.1 光合成にかかわるタンパク質 78
4.2 細胞呼吸にかかわるタンパク質 84
4.2.1 シトクロムc酸化酵素 85
4.2.2 ATP合成酵素 87
4.3 電子伝達タンパク質 89
4.3.1 c型シトクロム 89
4.3.2 鉄-硫黄クラスタータンパク質 92
第5章 物質輸送 96
5.1 トランスポーターとポンプタンパク質 97
5.1.1 カルシウムATPase(Ca2+-ATPase) 97
5.1.2 核内外への輸送-インポーチン,エクスポーチン 102
5.1.3 バクテリオロドプシン 104
5.2 小分子輸送タンパク質-ヘモグロビン,ミオグロビン 107
5.2.1 生理的性質 108
5.2.2 ミオグロビンとヘモグロビンの構造 109
5.2.3 オキシ型とデオキシ型の四次構造変化 110
5.2.4 グロビンフォールドタンパク質の進化 114
第6章 情報(シグナル)伝達 117
6.1 細胞表面の受容体(レセプター) 118
6.1.1 イオンチャネル連結型レセプター 118
6.1.2 酵素連結型レセプター 119+
6.1.3 Gタンパク質共役型レセプター 119
6.2 細胞内シグナル伝達分子 121
6.2.1 GTP結合タンパク質(Gタンパク質) 122
6.2.2 プロティンキナーゼ 126
6.2.3 標的タンパク質 130
6.2.4 ヌクレオチド結合性調節タンパク質の進化 141
6.2.5 カリウムチャネルと水チャネル分子 143
第7章 代謝 147
7.1 酵素反応 148
7.2 加水分解酵素-セリンプロテアーゼ 152
7.2.1 活性部位の構造の特徴 153
7.2.2 反応機構 155
7.2.3 他の加水分解酵素 157
7.3 酸化還元酵素-乳酸脱水素酵素 160
7.4 ラジカル酵素 162
7.5 酵素に見られる立体特異性 163
7.6 酵素の分子進化 165
7.7 分子シャペロン-シャペロニン : GroEL・GroES複合体 170
第8章 免疫 174
8.1 抗体-IgG 176
8.1.1 全体構造 176
8.1.2 抗原結合部位 178
8.2 MHCとT細胞受容体 180
8.2.1 MHCの構造 180
8.2.2 MHC分子とペプチドの結合 181
8.2.3 T細胞受容体・ペプチド・MHC複合体の構造 183
第9章 骨格(構造)形成 185
9.1 コラーゲン 186
9.2 ウイルスの外殻(キャプシド) 190
コラム : 発光タンパク質と蛍光タンパク質 192
第10章 基本構造のまとめ 195
10.1 αドメインタンパク質 195
10.1.1 4本αヘリックスバンドル構造 195
10.1.2 グロビンフォールド 197
10.2 βドメインタンパク質 201
10.2.1 βバレル 201
10.2.2 βサンドイッチ 203
10.2.3 βヘリックス 205
10.3 α/βドメインタンパク質 207
10.3.1 バレル型α/βドメイン 207
10.3.2 オープンシート型α/βドメイン 210
10.4 α+βドメインタンパク質 212
第3部 構造生物学研究の方法論
第11章 回折・散乱法 217
11.1 X線結晶解析法 217
11.1.1 精製・結晶化 217
11.1.2 X線源 219
11.1.3 クライオ実験技術 222
11.1.4 回折強度データ収集 223
11.1.5 結晶構造解析 225
11.2 中性子結晶解析法 227
11.3 電子顕微鏡法 229
11.4 FEL(自由電子レーザー)法 229
第12章 分光法 231
12.1 振動分光法 231
12.1.1 赤外分光法 232
12.1.2 ラマン分光法 233
12.2 磁気共鳴分光法 233
12.2.1 NMR法 234
12.2.2 EPR法 235
第13章 理論的手法-分子動力学法,分子軌道法 237
第14章 バイオインフォマティクス 239
14.1 構造・機能予測 239
14.2 Protein Data Bank(PDB) 241
14.3 分子の表示 245
索引 247
第1部 構造生物学の基礎
第1章 生物学から構造生物学へ-生物学と構造化学の融合 3
1.1 構造生物学の重要性とその応用 3
45.
図書
東工大
上野健爾著
目次情報:
続きを見る
math stories刊行にあたって iv
はじめに vi
CHAPTER1 数学の考え方-方程式を例にして 1
1.1 つるかめ算から連立方程式へ 3
1.1.1 つるかめ算 3
1.1.2 自分で問題を作ってみよう 5
1.1.3 式を立てる 6
1.2 連立方程式から行列へ 10
1.2.1 3元連立方程式-古代中国の解法 10
1.2.2 行列の発見 13
1.2.3 行列の和と差,スカラー倍 15
1.2.4 行列の積 15
1.2.5 行列のわり算-単位行列と逆行列 17
1.2.6 3行3列の行列の逆行列 20
1.2.7 3行3列の行列式と逆行列 21
1.2.8 連立方程式の解法と行列の変形 23
1.3 幾何学的視点からみた連立方程式 28
1.3.1 連立方程式と函数のグラフ 28
1.3.2 連立方程式と線形空間・線形写像 30
より抽象的な線形空間と線形写像 33
CHAPTER2 数とは何か-古代ギリシアから19世紀実数論の完成まで 35
2.1 整数のもつ性質 37
2.1.1 結合法則と分配法則 37
2.1.2 ユークリッドの互除法 39
2.1.3 素因数分解の一意性 41
2.1.4 「素数は無限にある」ことの証明 43
2.1.5 最大公約数 44
2.1.6 イデアルの導入 45
2.2 整数の合同 48
2.2.1 合同 48
2.2.2 倍数の判定法への応用 51
2.3 分数と循環小数 53
2.3.1 分数の導入 53
2.3.2 循環小数 54
2.3.3 循環節の長さとオイラーの函数 57
2.4 新しい数の体系-可換環と有限体 61
2.4.1 可換環Z/nZ 61
2.4.2 Z/nZでわり算はできるか? 64
2.4.3 有限体とフェルマーの小定理 66
2.4.4 オイラーの定理の証明 68
2.5 実数とは何か,どう定義できるのか? 71
2.5.1 無理数の発見-プラトン『テアイテトス』より 71
2.5.2 カントールの実数論 74
2.5.3 デデキントの実数論 75
2.5.4 数列の収束とエプシロン・デルタ論法 77
ヨーロッパ言語と日本語の違い 78
結合法則が成り立たない代数系 81
CHAPTER3 座標-幾何から代数へ 83
3.1 三平方の定理と三角比 85
3.1.1 数を線分で表す-公式の図形的証明 85
3.1.2 三平方の定理 86
3.1.3 角度と三角比 88
3.1.4 一般の角の三角比 90
3.2 平面座標と三角函数 92
3.2.1 座標による三角函数の定義 92
3.2.2 余弦定理と三角函数の加法公式 94
弧度法-新しい角度の単位 98
3.3 幾何から代数へ-角の三等分と作図問題 99
3.3.1 標識定規を使えば,角は三等分することができる 99
三平方の定理,再訪 101
3.3.2 作図可能な数 102
3.3.3 体とその拡大 105
3.3.4 定規とコンパスだけでは角の三等分はできない 108
3.3.5 20°は定規とコンパスのみでは作図できない 114
3.3.6 作図の三大難問 117
座標幾何学 121
CHAPTER4 ベクトルとベクトル空間 123
4.1 幾何ベクトルから数ベクトルへ 125
4.1.1 幾何ベクトル 125
4.1.2 ベクトルの分解と1次独立 127
4.1.3 ベクトル間の角度と内積 129
4.1.4 数ベクトルと平面座標 130
4.1.5 座標変換と行列の積 132
4.2 ベクトル空間 135
4.2.1 ベクトル空間の定義 135
4.2.2 1次独立 137
4.2.3 ベクトル空間の次元と基底 139
4.3 線形写像 143
4.3.1 線形写像の定義 143
4.3.2 連立方程式と線形写像 149
4.4 内積と内積空間-幾何ベクトルの復活 156
4.4.1 内積の定義 156
4.4.2 内積空間としての同型 158
CHAPTER5 方程式を解く 161
5.1 多項式と方程式 163
5.1.1 多項式 163
5.1.2 方程式を解くことと,体の拡大 164
5.1.3 多項式はなぜ整数に似ているのか 166
5.1.4 多項式環のイデアル 167
2次方程式と根の公式 168
5.2 複素数 170
5.2.1 複素数の誕生 170
5.2.2 複素数の四則演算 171
5.2.3 複素数の極座標表示 172
5.2.4 ド・モアブルの公式 174
ライプニッツの間違い 175
5.3 代数学の基本定理と3次・4次方程式の根 178
5.3.1 代数学の基本定理の証明の概要 178
5.3.2 1のn乗根と正多角形 180
5.3.3 3次方程式とカルダノの公式 181
カルダノの公式と複素数 183
5.3.4 フェラリの4次方程式の解法 184
5.4 アーベルが考えたこと-方程式を代数的に解くことの意味 187
5.4.1 方程式を解くためには何が必要か 187
5.4.2 根の基本対称式 191
5.4.3 アーベルの定理-5次方程式はべき根を使って解くことはできない 193
5.5 ラグランジュからガロアへ-方程式と群 195
5.5.1 置換と対称群 195
5.5.2 群の定義といくつかの例 199
5.5.3 2次対称群S2と2次方程式の解法 203
5.5.4 3次対称群S3と3次方程式の解法 206
5.5.5 ラグランジュによる3次方程式の解法の意味するもの 210
5.5.6 4次対称群S4と4次方程式の解法 219
5.5.7 剰余類と剰余群 229
5.5.8 共役類と単純群 233
5.5.9 ガロア群 234
5.5.10 体上の自己同型写像とガロア群 237
5.5.11 体の正規拡大とガロア理論の基本定理 242
参考文献 246
INDEX 247
math stories刊行にあたって iv
はじめに vi
CHAPTER1 数学の考え方-方程式を例にして 1
46.
学位
谷内一史
出版情報:
東京 : 東京工業大学, 2012
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
47.
図書
西口光一著
出版情報:
東京 : スリーエーネットワーク, 2012.10 25, 215p ; 26cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
48.
図書
細田條著
49.
図書
岡村浩著
50.
図書
総務省統計局編集
51.
図書
東工大
岩崎学著
出版情報:
東京 : 朝倉書店, 2010.7 vi, 210p ; 21cm
シリーズ名:
統計ライブラリー
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第1章 確率統計の基礎 1
1.1 確率と確率分布 1
1.1.1 確率の定義と性質 1
1.1.2 1変量の確率分布 3
1.1.3 2変量の確率分布 5
1.2 確率分布の特性値 7
1.2.1 期待値,分散,標準偏差 7
1.2.2 モーメントと母関数 8
1.2.3 確率変数の関数の期待値と分散(デルタ法) 12
1.3 統計的推測 13
1.3.1 尤度関数と最尤法 14
1.3.2 統計的検定 16
1.3.3 統計的推定 19
1.3.4 ベイズ流の推側 22
第2章 二項分布 24
2.1 二項分布の基本的性質 24
2.1.1 ベルヌーイ試行 24
2.1.2 二項分布の定義と特性 25
2.1.3 ベータ分布,F分布との関係 29
2.1.4 二項確率の近似 32
2.1.5 超幾何分布 34
2.1.6 多項分布 35
2.2 二項確率の検定 38
2.2.1 正確な検定 38
2.2.2 近似検定 40
2.2.3 実際の有意確率 41
2.3 二項確率の推定 43
2.3.1 点推定量(成功率)の統計的性質 43
2.3.2 その他の点推定量 45
2.3.3 区間推定(正確法) 46
2.3.4 区間推定(正規近似法) 48
2.3.5 最短信頼区間 50
2.3.6 区間推定法の比較 52
2.3.7 ベイズ推定 54
2.3.8 オッズと対数オッズ 56
2.4 ゼロトランケートとゼロ過剰 58
2.4.1 ゼロトランケートされた二項分布 58
2.4.2 ゼロ過剰な二項分布 61
第3章 二項分布の比較 66
3.1 比較のための基礎事項 66
3.1.1 比較の論点 66
3.1.2 確率分布とその性質 69
3.2 二項確率の差の検定 72
3.2.1 フィッシャー検定 73
3.2.2 正規近似による検定 75
3.2.3 検定法の比較 79
3.3 二項確率の差の推定 81
3.3.1 点推定 81
3.3.2 区間推定 83
3.3.3 推定法の比較 86
3.4 オッズ比と対数オッズ比 88
3.4.1 オッズ比の性質 88
3.4.2 オッズ比の推定と検定 91
3.5 複数の二項分布 95
3.5.1 確率の一様性の検定 95
3.5.2 傾向のある対立仮説 99
3.6 対応のある二項分布 102
3.6.1 基本的性質 102
3.6.2 推定と検定 106
3.7 サンプルサイズの設計 110
3.7.1 独立な二項分布 110
3.7.2 対応のある二項分布 114
第4章 ベータ二項分布 117
4.1 ベータ二項分布の性質とパラメータ推定 117
4.1.1 定義と性質 117
4.1.2 パラメータの推定 121
4.2 ゼロトランケートとゼロ過剰 123
4.2.1 ゼロトランケートされたベータ二項分布 123
4.2.2 ゼロ過剰なベータ二項分布 126
第5章 ポアソン分布 129
5.1 ポアソン分布の基本的性質 129
5.1.1 定義と性質 129
5.1.2 ガンマ分布,カイ2乗分布との関係 135
5.1.3 近似と変数変換 138
5.2 ポアソン分布における検定 140
5.2.1 ポアソンλに関する検定 140
5.2.2 実際の有意水準 143
5.2.3 ポアソン分布の比較 145
5.2.4 分布形の検定 148
5.3 ポアソン分布における推定 149
5.3.1 点推定量とその統計的性質 149
5.3.2 区間推定 150
5.3.3 区間推定法の比較 152
5.4 ゼロトランケートとゼロ過剰 155
5.4.1 ゼロトランケートされたポアソン分布 155
5.4.2 パラメータの推定 158
5.4.3 ゼロ過剰なポアソン分布 161
5.4.4 ゼロ過剰モデルでの推測 164
第6章 負の二項分布 168
6.1 負の二項分布の性質とパラメータ推定 168
6.1.1 定義と性質 168
6.1.2 期待値,分散,モーメント 172
6.1.3 ガンマポアソン分布 176
6.1.4 パラメータの推定 178
6.2 ゼロトランケートおよびゼロ過剰 181
6.2.1 ゼロトランケートされた負の二項分布の性質 181
6.2.2 パラメータの推定 184
6.2.3 ゼロ過剰な負の二項分布 187
第A章 付録 191
A1 ガンマ分布とカイ2乗分布 191
A2 ベータ分布とF分布 196
参考文献 203
索引 207
第1章 確率統計の基礎 1
1.1 確率と確率分布 1
1.1.1 確率の定義と性質 1
52.
図書
editors, Berno Misgeld, Thomas Schauer, Olaf Simanski
出版情報:
New York : Elsevier , Red Hook, NY : Printed from e-media with permission by Curran Associates, 2016, c2015 586 p. ; 28 cm
シリーズ名:
IFAC PapersOnline ; v. 48, Issue 20
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
53.
図書
東工大
中尾真一, 渡辺義公監修
目次情報:
続きを見る
【第1編 総論】
第1章 膜ろ過による水処理技術の現状と今後の展開(渡辺義公)
1. 浄水プロセスへの適用 3
2. 下水処理への適応 10
第2章 膜ろ過技術の現状と問題点(中尾真一)
1. 水処理における膜技術利用の歴史 18
1.1 膜ろ過技術の発明と実用化 18
1.2 廃水処理への応用 18
1.3 各種の精密ろ過膜の開発 19
2. 膜ろ過法概論 19
2.1 各種の膜分離技術 19
2.2 膜ろ過法概論 20
2.3 精密ろ過法 21
2.4 限外ろ過法 22
2.5 ナノろ過法 23
2.6 逆浸透法 25
3. 膜ろ過技術の問題点 26
3.1 ファウリング 26
3.2 膜ろ過法から発生する環境負荷 27
【第2編 技術編】
第1章 浄水システム
1. 浄水処理における膜ろ過技術の現状と今後の展開(伊藤雅喜) 31
1.1 水道と膜ろ過技術 31
1.2 日本における膜ろ過技術の開発 32
1.2.1 膜利用型新浄水システム開発研究(MAC21) 32
1.2.2 膜利用型新高度浄水技術開発研究(高度処理MAC21) 34
1.2.3 高効率浄水技術開発研究(ACT21) 36
1.2.4 環境影響低減化浄水技術研究(e-Water) 36
1.3 浄水処理における膜ろ過の現状 36
1.3.1 世界の膜ろ過の現状 36
1.3.2 日本の水道における膜ろ過の現状 37
1.4 浄水用膜ろ過の研究開発の課題 41
2. ハイブリッド型膜浄水システム 43
2.1 生物処理との組み合わせ(木村克輝) 43
2.1.1 はじめに 43
2.1.2 無機態窒素による水源汚染・独立栄養細菌と膜処理の組み合わせ 43
2.1.3 NH4+-N硝化型ハイブリッド膜浄水プロセス 44
2.1.4 NO3- -N除去型ハイブリッド膜浄水プロセス 48
2.1.5 おわりに 51
2.2 オゾン処理との組合せ(住田一郎) 53
2.2.1 はじめに 53
2.2.2 オゾン・活性炭+膜 53
2.2.3 オゾン+膜(+活性炭) 55
2.3 活性炭処理との組み合わせ(鈴木辰彦) 63
2.3.1 低圧ろ過膜と活性炭処理の組合わせ処理の概要 63
2.3.2 溶解性有機物の除去機構 64
2.3.3 活性炭処理との組み合わせでの膜の運転性に関して 66
2.3.4 プラント実験例 67
2.3.5 まとめ 70
第2章 下水・廃水処理システム
1. 下水・廃水処理における膜ろ過技術の現状と今後の展開(大熊那夫紀) 71
1.1 はじめに 71
1.2 下水・廃水処理の現状 71
1.2.1 従来型下水・廃水処理 71
1.2.2 膜利用型下水・廃水処理 73
1.2.3 下水道における膜分離活性汚泥法の現状 75
1.3 技術的課題 77
1.4 今後の展開 78
2. ハイブリッド型膜処理システム 80
2.1 膜分離活性汚泥処理システム(Membrane Bio Reactor : MBR)(小林真澄) 80
2.1.1 はじめに 80
2.1.2 MBRの特徴 80
2.1.3 MBR用膜エレメント/ユニット 82
2.1.4 MBR処理水の水質 82
2.1.5 RO膜との組み合わせ検討例 83
2.1.6 おわりに 86
2.2 膜分離型嫌気性処理システム(山本哲也) 88
2.2.1 嫌気性処理法の概要 88
2.2.2 膜分離型嫌気性処理の諸条件 90
(1) 膜分離型嫌気性処理の目的 90
(2) 原料 90
(3) フロー 90
(4) 膜素材,形状 90
(5) 膜フラックスと膜間差圧 92
(6) メタン発酵運転条件 92
(7) 分解率・バイオガス生成 92
2.2.3 膜分離型嫌気処理システムの実例 93
(1) 北空知衛生センター生ごみバイオガス化施設のフロー 93
(2) メタン発酵の状況 94
(3) 膜の運転状況 94
2.2.4 今後の展開 96
2.3 オゾン処理との組み合わせ処理システム(鬼塚卓也) 98
2.3.1 はじめに 98
2.3.2 オゾン耐性膜の仕様と特徴 98
2.3.3 溶存オゾンが膜間差圧に及ぼす影響 98
2.3.4 高流束連続膜ろ過運転 100
2.3.5 処理水質 100
2.3.6 おわりに 101
第3章 下水・廃水の再利用における膜処理システムの現状と今後の展開(澤田繁樹)
1. はじめに 103
2. 下水二次処理水のRO膜回収再利用 104
2.1 日本における実績 105
2.2 東京都における親水用水のための下水再利用 107
2.3 シンガポールにおける下水再利用-NEWaterの取り組み 109
3. NF膜およびRO膜を用いた産業廃水の再利用 112
3.1 金属加工工場における排水回収 113
3.2 飲料製造工場における排水回収 115
4. おわりに 116
第4章 膜を用いる海水淡水化システムの現状と今後の展開(永井正彦)
1. はじめに 119
2. RO海洋淡水化の普及 119
3. RO海水淡水化システム 121
3.1 海洋淡水化システム 121
3.2 海洋淡水化用膜モジュール 125
4. 大型プラント 126
4.1 SWCCジェッダプラント 126
4.2 SWCCメジナヤンブプラント 130
4.3 沖縄プラント 130
4.4 トリニダードトバゴプラント 131
4.5 バーレーンAddurプラント 131
4.6 造水コスト 132
5. 今後の展開 133
5.1 水質 133
5.2 エネルギー原単位 133
5.3 前処理 133
5.4 放流水 134
5.5 造水コストの低減 134
5.6 環境に対する影響 134
5.7 自然エネルギー利用 134
5.8 小型プラントのメンテナンスフリー化 135
5.9 海水総合利用 135
6. おわりに 136
【第3編 応用編】
第1章 膜型浄水システム
1. 小規模浄水システム(鬼塚卓也) 139
1.1 膜ろ過設備の導入状況 139
1.2 膜ろ過浄水設備導入計画における考慮すべき主な基本的事項 141
1.2.1 水源の種類と計画浄水量 141
(1) 水源の種類 141
(2) 計画浄水量 141
1.2.2 全体システムの構成 141
(1) 前処理設備 141
(2) 膜ろ過設備 141
(3) 後処理設備 142
(4) 排水処理 142
1.3 膜ろ過による小規模浄水システムの実施例 142
1.3.1 実施例I 142
1.3.2 実施例II 143
1.3.3 実施例III 143
1.3.4 実施例IV 144
1.3.5 実施例V 144
1.3.6 実施例VI 145
1.4 これからの小規模膜ろ過浄水システム 145
2. 中・大規模浄水システム(村田周和) 147
2.1 中・大規模浄水システム導入状況 147
2.2 中・大規模浄水システムの特徴 147
(1) 浄水処理単位 147
(2) 前処理 147
(3) 薬品洗浄設備 148
(4) 排水処理設備 148
2.3 実装置例 148
2.3.1 西空知広域水道企業団西空知浄水場 148
(1) 沿革 148
(2) 浄水場諸元 148
(3) 浄水設備 149
(4) 浄水水質 152
2.3.2 今市市水道部瀬尾浄水場 152
(1) 沿革 152
(2) 浄水場諸元 153
(3) 浄水設備 153
(4) 浄水水質 156
2.4 中・大規模浄水システムのまとめ 157
3. 海外の膜型浄水システム(米川均) 158
3.1 浄水処理への膜ろ過の普及 158
3.2 浄水処理の主なMF/UF膜技術 159
3.3 MF/UF膜を用いた複合浄水システム 162
3.4 今後の膜型浄水システムとその課題 164
第2章 用水・下水・排水処理システム
1. 純水・超純水製造(田村真紀夫) 166
1.1 純水・超純水とは 166
1.2 単位操作としての膜技術 166
1.2.1 イオン交換膜(Ion Exchange Membrane) 166
1.2.2 逆浸透膜(RO膜 : Reverse Osmosis Membrane) 168
1.2.3 限外ろ過膜(UF膜 : Ultra Filtration Membrane) 168
1.2.4 精密ろ過膜(MF膜 : Micro Filtration Membrane) 168
1.2.5 脱気膜(MD膜 : Membrane Degasifier) 169
1.3 超純水製造システム構成例 169
1.4 最新動向と将来 170
1.4.1 除濁膜の高流速化 170
1.4.2 RO膜の低圧化 171
1.4.3 RO膜ファウリング耐性向上 171
1.4.4 前段RO水回収率向上 172
1.4.5 純水製造の無薬品化 173
1.5 残された課題 175
2. ビル排水再利用システム(安中祐子) 176
2.1 ビル排水再利用システムとは 176
2.2 ビル排水再利用システムへの膜処理技術の導入 176
2.3 ビル排水再利用システムで利用される膜処理技術 178
2.3.1 処理フロー 178
2.3.2 膜分離装置 178
2.3.3 膜処理技術適用例 179
2.4 おわりに 185
3. 産業廃水処理システム 186
3.1 半導体・液晶工場システム(浦井紀久) 186
3.1.1 半導体・液晶工場水処理システムの概要 186
3.1.2 排水回収システムへの適用 186
(1) 無機系排水回収 187
(2) 有機系排水回収 188
3.1.3 排水処理装置への適用 189
(1) 研磨系,CMP系の排水処理,排水回収 189
(2) フッ酸排水処理への適用 191
3.1.4 薬液回収への適用 193
3.2 自動車工場排水(小野徳昭) 196
3.2.1 近年の膜処理技術の適用について 196
3.2.2 膜処理の事例(1)一般機械工場の膜式活性汚泥の適用事例 197
(1) 処理フロー 197
(2) 運転実績 197
3.2.3 膜処理の事例(2)前処理-ROを利用した排水回収 198
(1) 水質及び処理フロー 198
(2) 膜前処理 199
(3) RO処理 201
(4) コストと回収率 202
3.2.4 膜処理における油分の影響 202
3.2.5 まとめ 203
3.3 めっき総合廃水の再利用(納嵜克也) 205
3.3.1 はじめに 205
3.3.2 回転膜分離法による凝集ろ過 205
(1) めっき廃水の凝集ろ過 205
(2) 膜汚染物質 207
3.3.3 低圧逆浸透膜によるめっき廃水の再生 208
(1) 廃水中の溶存物質 208
(2) 低圧逆浸透膜によるめっき廃水回収試験 209
(3) 膜洗浄試験 209
3.3.4 プラント導入例 211
3.4 食品工場廃水(小林真澄) 215
3.4.1 食品工場排水の特徴 215
3.4.2 既存設備からの改造例 216
3.4.3 排水のリサイクル例 216
4. 廃棄物最終処分場浸出水処理システム(牛越健一) 219
4.1 はじめに 219
4.2 廃棄物最終処分場と浸出水処理 219
4.2.1 廃棄物と最終処分場 219
(1) 最終処分場の種類 219
(2) 埋立廃棄物と浸出水 219
4.2.2 最終処分場における浸出水処理 220
(1) オープン型最終処分場における浸出水処理 220
(2) クローズド型最終処分場における浸出水処理 220
4.3 浸出水処理における膜分離技術 221
4.3.1 精密ろ過膜,限外ろ過膜の応用 221
4.3.2 逆浸透膜の応用 222
4.3.3 電気透析膜の応用 226
4.4 脱塩処理における濃縮水処理技術 227
4.5 おわりに 228
5. 膜分離活性汚泥法を用いた畜産廃水処理システム(小林真澄) 230
5.1 はじめに 230
5.2 畜産排水処理の原水及び処理水水質について 230
5.3 膜分離活性汚泥法(MBRシステム)の特徴について 232
5.4 畜産排水処理にMBRシステムを用いる利点 233
5.5 設計のポイント 234
5.6 おわりに 235
6. 下水・廃水処理の再利用システム(岩堀博) 236
6.1 はじめに 236
6.2 シンガポールのニューウォータープロジェクト-都市2次処理下水の高度処理による非直接的水道水源への再利用- 236
6.3 クロラミン殺菌 238
6.4 NEWaterプラントの仕様 238
(1) MF膜前処理 238
(2) 低汚染RO層 239
(3) NEWater ROの設計仕様 240
(4) 下水再生処理ROシステム 240
(5) 水質データ 242
(6) 紫外線(UV)殺菌処理 243
(7) 維持管理 244
(8) 造水コスト 244
6.5 おわりに 244
7. 膜型浄化槽(和泉清司) 246
7.1 膜分離型浄化槽の歴史 246
7.2 槽浸漬型膜分離装置 246
7.3 開発の目標 247
7.4 事例紹介 248
7.4.1 大型浄化槽(51人槽以上) 248
7.4.2 家庭用浄化槽 249
7.4.3 単独処理浄化槽の合併処理化装置 250
7.4.4 農業集落排水処理 251
7.5 槽浸漬型膜分離法の運転及び維持管理方法 252
7.5.1 膜間閉塞防止対策 253
7.5.2 膜のファウリング対策 254
7.6 今後の展開 254
第3章 海水淡水化施設
1. 世界の海水淡水化施設(山村弘之) 256
1.1 海水淡水化施設の能力 256
1.2 大型海水淡水化施設の比較 256
1.3 海水淡水化技術の流れと特徴 257
1.4 海水淡水化技術の今後の動向予測 258
2. 膜前処理2段システム(岩堀博,船山健一郎) 260
2.1 はじめに 260
2.2 UF膜前処理 260
2.2.1 “RSシリーズ”の概要 261
(1) RSの特長 261
(2) 海水でのRS50性能 262
2.2.2 膜ろ過法およびRSシリーズの利点 263
2.2.3 閉鎖系海水でのUF膜前処理のSDI挙動 263
2.3 福岡海水淡水化施設におけるUF膜前処理 265
2.4 高圧海淡ROと低圧ROを用いる2段階脱塩処理システム 270
2.4.1 中空糸型海水淡水化RO・部分的2段階脱塩処理システム 270
2.4.2 新規スパイラル型の部分的2段階脱塩処理システム 272
3. 高回収率システム(山村弘之) 277
3.1 はじめに 277
3.2 濃縮水昇圧2段法システムの概要 277
3.3 高圧高濃度用2段目膜エレメントの開発 279
3.4 高効率2段法海水淡水化システムの開発と実証 280
3.5 微生物汚染対策技術 281
3.6 濃縮水昇圧2段法海水淡水化システムの実用化 281
3.7 膜前処理を併用した高回収率システム 282
3.8 おわりに 284
【第1編 総論】
第1章 膜ろ過による水処理技術の現状と今後の展開(渡辺義公)
1. 浄水プロセスへの適用 3
54.
図書
東工大
登坂宣好著
出版情報:
東京 : 東京大学出版会, 2010.6 xi, 281p ; 21cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
まえがき ⅲ
第0章 本書を読む前に 1
0.1 本書の特徴と構成 1
0.1.1 本書の特徴 1
0.1.2 本書の構成 3
0.2 学習の手引き 7
0.3 本書の基本的な考え方 10
第1章 微分方程式 13
1.1 方程式 13
1.2 微分方程式の定義 14
1.3 微分方程式と現象の数理モデル化 19
1.4 微分方程式の解 28
第2章 1階微分方程式 37
2.1 1階微分方程式の系譜 37
2.2 定数係数非同次形微分方程式(その1) 39
2.3 定数係数同次形微分方程式 41
2.3.1 指数関数解 41
2.3.2 積分因子法 43
2.3.3 指数関数解の挙動 44
2.4 定数係数非同次形微分方程式(その2) 45
2.4.1 積分因子法 45
2.4.2 定数変化法 46
2.5 変数係数非同次形微分方程式 48
2.6 変数分離型微分方程式 50
2.6.1 変数分離型解法 50
2.6.2 同次型微分方程式 53
2.7 ロジスティック方程式 55
2.7.1 変数分離型解法 55
2.7.2 数値解法(差分解法) 56
2.7.3 リターンマップ法 59
第3章 連立1階微分方程式 67
3.1 連立1階微分方程式の系譜 67
3.2 線形自律系 67
3.2.1 線形自律系の幾何学的意味 67
3.2.2 2次元線形自律系の解 71
3.2.3 行列の指数関数による解の表現 76
3.2.4 単一微分方程式の解との関係 89
3.3 線形非自律系 94
第4章 初期値問題の解法 99
4.1 線形定数係数非同次形微分方程式の解 99
4.2 たたみ込み積分 101
4.3 たたみ込み積分法による解法 105
4.3.1 線形1階定数係数非同次形微分方程式 105
4.3.2 線形2階定数係数非同次形微分方程式 107
4.4 初期値問題のグリーン関数 110
4.5 1自由度系の振動現象の解析 112
4.5.1 強制振動解 112
4.5.2 自由振動解 115
4.5.3 強制振動解と応答 116
4.5.4 一般の応答 120
4.5.5 調和応答 121
第5章 境界値問題の解法 126
5.1 弦の釣合い曲線に関する境界値問題 126
5.1.1 たたみ込み積分法による解法 126
5.1.2 弦の境界値問題のグリーン関数 132
5.2 弾性梁の釣合い曲線に関する境界値問題 136
5.2.1 たたみ込み積分法による解法 136
5.2.2 弾性梁の境界値問題のグリーン関数 145
5.3 グリーン関数法 147
5.4 グリーン関数と基本解 149
第6章 固有値問題の解法 154
6.1 固有角振動数 154
6.2 弦の固有値問題 155
6.2.1 弦の固有振動問題 155
6.2.2 たたみ込み積分法による解法 159
6.3 弾性梁の固有値問題 160
6.3.1 弾性梁の固有振動問題 160
6.3.2 たたみ込み積分法による解法 164
6.4 弾性棒の固有値問題 173
6.4.1 弾性棒の座屈問題 173
6.4.2 たたみ込み積分法による解法 182
第7章 微分方程式の諸解法 189
7.1 微分方程式の解法 189
7.2 微分演算子法 190
7.2.1 微分演算子法 190
7.2.2 たたみ込み積分法との関係 197
7.3 ラプラス変換法 199
7.3.1 ラプラス変換法 199
7.3.2 たたみ込み積分法との関係 209
7.4 ミクシンスキー演算子法 212
7.4.1 ミクシンスキー演算子法 212
7.4.2 ミクシンスキー演算子法の基本事項 213
7.4.3 初期値問題への適用 219
7.5 初期値問題の解法の比較 224
AppendixA 線形空間 229
A.1 線形空間 229
A.1.1 複素数上の線形空間 229
A.1.2 実線形空間の複素化 230
A.2 線形写像 233
A.2.1 線形写像の定義 233
A.2.2 線形写像の複素化 233
A.2.3 線形写像の表現行列 234
A.3 線形写像の標準化 235
A.3.1 線形写像の固有値、固有ベクトル、固有空間 235
A.3.2 線形写像の標準形 238
A.4 線形写像のスペクトル分解 241
A.4.1 射影 240
A.4.2 線形写像のスペクトル分解 241
A.4.3 射影の求め方 242
A.5 一般固有空間と一般スペクトル分解 244
A.5.1 一般固有空間 244
A.5.2 一般スペクトル分解 246
AppendixB 行列のスペクトル分解と指数関数 248
B.1 2次正方行列 248
B.1.1 相異なる2実根を有する場合 249
B.1.2 重根を有する場合 250
B.1.3 共役な複素根を有する場合 252
B.2 3次正方行列 253
B.2.1 相異なる3実根を有する場合 254
B.2.2 1つの実根と重根を有する場合 256
B.2.3 1つの実根と共役複素根を有する場合 259
B.2.4 3重根を有する場合 261
演習問題解答 265
参考文献 277
索引 279
まえがき ⅲ
第0章 本書を読む前に 1
0.1 本書の特徴と構成 1
55.
図書
渡邉亜子, 白石知代共著
出版情報:
東京 : Jリサーチ出版, 2011.5 123p ; 26cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
56.
図書
中島智子, 高橋尚子, 松本知恵共著
出版情報:
東京 : Jリサーチ出版, 2011.5 150p ; 26cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
57.
図書
安藤隆雄著
58.
図書
東工大
河辺哲次著
出版情報:
東京 : 裳華房, 2011.10 vii, 222p ; 21cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第1章 電荷による電場
1.1 クーロンの法則 1
1.1.1 クーロン力 2
1.1.2 重ね合わせの原理 4
1.2 電場と電気力線 7
1.2.1 電場 7
1.2.2 電気力線 11
1.3 電束と面積分 12
1.3.1 電束 12
1.3.2 電場の面積分 15
1.4 電場のガウスの法則 18
1.4.1 電束の計算法 19
1.4.2 電場の計算法 21
1.5 電位 25
1.5.1 仕事と線積分 25
1.5.2 電位と電位差 28
1.6 等電位面と電位の勾配 33
1.7 導体 37
1.7.1 静電誘導と導体の性質 37
1.7.2 コンデンサー 40
1.8 電場のエネルギー 44
第1章のまとめ 47
演習問題 48
第2章 電流による磁場
2.1 電流 51
2.1.1 定常電流とドリフト速度 52
2.1.2 オームの法則とジュール熱 56
2.2 定常電流とキルヒホッフの法則 60
2.3 定常電流による磁気作用 65
2.3.1 ビオ‐サバールの法則 66
2.3.2 磁場の計算法 68
2.4 アンペールの法則 72
2.5 過渡電流とRC回路 78
2.6 アンペール‐マクスウェルの法則 82
2.6.1 アンペールの法則のパラドックス 82
2.6.2 変位電流 84
2.7 磁場のガウスの法則 86
第2章のまとめ 90
演習問題 92
第3章 外部の磁場による力
3.1 ローレンツ力 94
3.1.1 電流にはたらく力 97
3.1.2 電流の間にはたらく力 98
3.2 コイルにはたらく力 100
3.3 コイルと磁石の磁場 105
第3章のまとめ 109
演習問題 110
第4章 電磁誘導
4.1 ファラデーの電磁誘導の法則 112
4.1.1 電磁誘導を示す実験 113
4.1.2 レンツの法則 116
4.2 誘導起電力と磁束の変化 118
4.2.1 誘導起電力 118
4.2.2 磁束の変化 119
4.3 誘導電流 121
4.3.1 変動する磁場の場合 121
4.3.2 運動するコイルの場合 125
4.4 インダクタンス 132
4.4.1 自己誘導とLR回路 132
4.4.2 相互誘導と変圧器 136
4.5 磁場のエネルギー 140
第4章のまとめ 142
演習問題 143
第5章 マクスウェル方程式と電磁波
5.1 変動する電磁場 145
5.1.1 マクスウェル方程式 146
5.1.2 電磁波と変位電流 148
5.2 電磁場の波動方程式 149
5.3 電磁波と光 153
5.3.1 平面電磁波 154
5.3.2 電磁波のエネルギー 157
5.4 マクスウェル方程式の微分形 159
第5章のまとめ 162
演習問題 163
第6章 交流回路
6.1 交流 164
6.1.1 交流の実効値 165
6.1.2 位相ベクトルと位相図 166
6.2 RLC直列回路 167
6.2.1 インピーダンス 169
6.2.2 回路素子のリアクタンス 172
6.3 共振回路 175
6.4 電気系と力学の振動系とのアナロジー 178
第6章のまとめ 183
演習問題 184
付録
A. 数学公式 186
B. 電場のガウスの法則の証明 193
C. アンペールの法則の証明 196
D. 磁束の変化量 198
E. 電磁場の相対性と誘導電場 200
F. マクスウェル方程式の平面波近似 203
G. マクスウェル方程式とベクトル場の積分公式 205
H. 電磁気学の単位 207
演習問題解答 210
さらに勉強するために 217
索引 219
第1章 電荷による電場
1.1 クーロンの法則 1
1.1.1 クーロン力 2
59.
図書
東工大
宮崎茂次著
出版情報:
東京 : 森北出版, 2010.5 vi, 148p ; 22cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
序章 本書の概要 1
第1章 生産管理と生産システム 3
1.1 生産と情報 3
1.1.1 生産活動と情報 3
1.1.2 生産の定義と内容 4
1.1.3 付加価値活動の観点からの生産 5
1.2 生産管理の概要 6
1.2.1 生産業務 6
1.2.2 生産管理サイクル 8
1.2.3 生産管理の目的 9
1.2.4 生産管理の手法 9
1.2.5 生産管理の役割 10
1.3 生産管理の機能 10
1.3.1 生産計画 11
1.3.2 生産実施および生産統制・照合 12
1.3.3 生産改善 12
1.3.4 生産管理の組織 13
1.4 生産システムの現状 14
1.4.1 生産システムの基本的概念 14
1.4.2 システム論からみた生産活動 15
1.4.3 生産形態の分類 16
1.4.4 効率的な生産システムへのアプローチ 16
1.5 新しい生産管理手法 18
1.5.1 サプライチェーンマネジメントシステム 19
1.5.2 モジュール化 21
1.5.3 ディジタル化 22
1.5.4 OEM 22
1.5.5 アウトソーシング 22
1.5.6 生産拠点の日本国内への回帰 23
第1章 演習問題 23
第2章 オペレーションズスケジューリング 25
2.1 オペレーションズスケジューリングのモデル 25
2.1.1 スケジューリングの分類 25
2.1.2 オペレーションズスケジューリングモデルの構成と分類 27
2.1.3 オペレーションズスケジューリングの目的 29
2.2 スケジューリングのモデルの定式化と困難性 30
2.2.1 スケジューリングの評価尺度 31
2.2.2 スケジューリング問題の表示 33
2.2.3 スケジューリング問題の困難性 33
2.3 単一工程スケジューリング問題の解法 35
2.3.1 平均実滞留時間の最小化 35
2.3.2 平均滞留時間(平均処理時間)の最小化 36
2.3.3 最大納期ずれ時間の最小化 37
2.3.4 最大納期遅れ時間0のもとでの平均滞留時間の最小化 37
2.3.5 スミスの解法の制約条件 38
2.4 フローショップスケジューリング問題の解法 39
2.4.1 ジョンソンの定理 39
2.4.2 ジョンソンの定理に基づくアルゴリズム 40
2.5 ジョブショップスケジューリング問題の解法 45
2.5.1 エイカーの図的最適化解法 45
2.5.2 エイカーの図的最適化解法のアルゴリズム 46
第2章 演習問題 49
第3章 最適化解法 51
3.1 分岐限界法 51
3.1.1 分岐限界法の特徴 51
3.1.2 分岐手続き 52
3.1.3 最新ノード探索手順 52
3.1.4 境界ノード探索手順 54
3.1.5 探索手順の選択 55
3.1.6 下界(上界)値と適用可能問題 55
3.2 分岐限界法のスケジューリング問題への適用 56
3.2.1 適用するスケジューリングのモデル 56
3.2.2 分岐限界法の利用 57
3.3 動的計画法 62
3.3.1 動的計画法の導入 62
3.3.2 動的計画法の解法 62
第3章 演習問題 67
第4章 在庫管理 69
4.1 在庫の役割と目的 69
4.1.1 景気の判断資料としての在庫 69
4.1.2 在庫の費用要因と動機 71
4.2 定量発注方式 72
4.2.1 経済的発注量モデル 72
4.2.2 経済的発注量モデルの解析 73
4.3 購入価格を考慮する定量発注方式 76
4.3.1 購入価格の割引を考慮するモデルの解析 76
4.3.2 購入価格を考慮する定量発注方式の解法 78
4.4 その他の在庫管理法 80
4.4.1 定期発注方式 80
4.4.2 (S, s)方式 81
第4章 演習問題 82
第5章 オペレーションズリサーチの手法 83
5.1 設備更新問題 83
5.1.1 設備更新問題の意味 83
5.1.2 設備更新問題の解析 84
5.2 物品交換理論 87
5.3 ラインバランシング問題 90
5.3.1 目標関数 91
5.3.2 ラインバラシング問題の定式化と解法 92
5.4 待ち行列理論 101
5.4.1 待ち行列モデル 101
5.4.2 待ち行列モデルの表記法 103
5.4.3 待ち行列モデルで求められる値 104
第5章 演習問題 105
第6章 品質管理法 107
6.1 品質管理法の七つの手法 107
6.2 管理図法 109
6.2.1 管理図とは 109
6.2.2 管理図の種類とその用途 110
6.2.3 管理図の見方 110
第6章 演習問題 113
第7章 生産システムの発展と課題 114
7.1 テイラーシステム 114
7.1.1 テイラーシステムの導入 114
7.1.2 「出来高払制私案」での主張 114
7.1.3 「工場管理法」での主張 116
7.1.4 「科学的管理法の諸原理」での主張 117
7.2 フォードシステム 118
7.2.1 フォード主義 118
7.2.2 フォード生産方式 119
7.3 ジャストインタイムシステム 120
7.3.1 ジャストインタイムシステムの理念と目的 120
7.3.2 ジャストインタイムシステムの手段 121
7.4 生産システムの今後の動向 126
7.4.1 金融操作で露呈した生産システムの問題点 126
7.4.2 製品設計思想のかい離 128
7.4.3 生産システムへの新しい考え方 129
第7章 演習問題 131
演習問題解答 132
参考文献 142
索引 145
序章 本書の概要 1
第1章 生産管理と生産システム 3
1.1 生産と情報 3
60.
図書
東工大
青木健一郎著
出版情報:
東京 : サイエンス社, 2011.11 ix, 197p ; 21cm
シリーズ名:
ライブラリ物理学コア・テキスト ; 2
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第1章 運動法則 1
1.1 力学とは 1
1.2 位置,速度,加速度 2
1.3 運動法則 4
1.4 概算とオーダー 7
1.5 力と圧力 8
1.5.1 力 8
1.5.2 地表付近での重力 9
1.5.3 圧力 10
第1章 演習問題 12
第2章 典型的な運動の例 13
2.1 一定の力の下での運動 13
2.1.1 等速度運動 13
2.1.2 等加速度運動 13
2.1.3 地表付近での重力下の運動 15
2.1.4 等速円運動 17
2.2 質点と物体 17
2.2.1 質点と物体 17
2.2.2 外力と内力 18
2.3 調和振動 20
2.4 連成振動 23
2.5 摩擦や抵抗のある運動 26
2.5.1 表面同士の摩擦 26
2.5.2 抵抗を受ける物体の低速運動 28
2.5.3 一定の力と抵抗力を受ける低速の物体の運動 29
2.5.4 調和振動に抵抗力が加わった場合 32
2.5.5 低速ではない物体の受ける抵抗 34
2.6 決定論とカオス 36
第2章 演習問題 40
第3章 エネルギー,運動量と保存則 41
3.1 エネルギー 41
3.2 エネルギー保存 43
3.3 位置エネルギーと仕事 46
3.3.1 仕事とエネルギー 46
3.3.2 保存力 47
3.3.3 エネルギーと仕事 : 具体例 51
3.3.4 保存力とエネルギー保存 55
3.4 運動量 57
3.4.1 運動量と力積 57
3.4.2 運動量の保存 58
3.4.3 保存則の適用例 : 2粒子の弾性衝突(重心系) 60
3.4.4 保存則の適用例 : 2粒子の弾性衝突(実験室系) 61
3.5 角運動量 62
3.5.1 角運動量とは 62
3.5.2 角運動量の満たす運動方程式 63
3.5.3 角運動量の保存 64
3.6 保存力の下での1次元運動 67
3.6.1 位置エネルギーと運動領域 67
3.6.2 1次元系の運動方程式の解 68
3.7 ビリアル定理 70
3.8 保存力以外について 71
3.8.1 散逸 71
3.8.2 強制振動 73
第3章 演習問題 77
第4章 2体問題と中心力 79
4.1 2体問題と重心系 79
4.1.1 2つの物体の運動 79
4.1.2 2体問題 80
4.2 中心力の下での運動 81
4.2.1 2次元極座標系 81
4.2.2 中心力と角運動量保存 82
4.2.3 ケプラーの法則 84
4.2.4 中心力問題の解 85
4.3 3次元調和振動子 86
4.3.1 運動の定性的性質 86
4.3.2 rの時間依存性r(t) 87
4.3.3 軌道r(ψ) 87
4.3.4 運動の性質88
4.3.5 直交座標系の結果との関係 89
4.4 位置エネルギー1/rの場合 89
4.4.1 引力の場合の一般の軌道(k>0) 89
4.4.2 斥力の場合の一般の軌道(k<0) 92
4.4.3 L=0の場合の軌道 93
4.4.4 時間依存性 94
4.4.5 楕円運動の周期 96
4.4.6 円軌道 98
4.4.7 散乱 99
第4章 演習問題 102
第5章 剛体の運動 104
5.1 剛体と重心 104
5.2 剛体の回転運動 105
5.2.1 剛体の並進と回転運動 109
5.2.2 力のモーメントと仕事 110
5.3 剛体のつり合い 111
5.3.1 剛体のつり合いの例 112
5.4 固定軸のまわりの回転運動 114
5.4.1 運動方程式 114
5.4.2 慣性テンソルと慣性モーメントの例 116
5.4.3 固定軸のまわりの回転の例 120
5.5 回転座標系 123
5.6 慣性力 127
5.7 剛体の運動と歳差運動 129
5.7.1 剛体の運動方程式 129
5.7.2 剛体の自由な運動 129
第5章 演習問題 131
第6章 解析力学 133
6.1 ラグランジアン 133
6.1.1 ラグランジアンと運動方程式 133
6.1.2 ラグランジアンと拘束条件 134
6.1.3 ラグランジアンの例 138
6.1.4 作用と変分 140
6.1.5 ラグランジァンを使う理由 141
6.1.6 連続対称性とネーターの定理 142
6.2 ハミルトニアン 145
6.2.1 ハミルトニアンと運動方程式 145
6.2.2 ハミルトニアンとエネルギー 146
6.2.3 時間変化とポアソン括弧 147
6.2.4 力学系と位相空間 148
第6章 演習問題 151
付録A 単位と物理量 152
A.1 単位と次元について 152
A.2 物理定数,物理量,定数など 154
付録B 関連する数学のまとめ 156
B.1 ベクトル 156
B.2 行列 158
B.3 複素数と関数の性質 160
B.4 極座標 162
B.5 2次曲線と極座標 163
B.5.1 楕円(0
B.5.2 放物線(e=1) 164
B.5.3 双曲線(e>1) 165
B.6 微分165
B.6.1 微分と偏微分 165
B.6.2 微分に関わる性質 167
B.7 積分 169
B.8 常微分方程式 172
B.8.1 微分方程式とは 172
B.8.2 常微分方程式の解 173
B.8.3 解析的に解が求まる常微分方程式の例 175
解答例 181
索引 194
第1章 運動法則 1
1.1 力学とは 1
1.2 位置,速度,加速度 2
61.
図書
東工大
利光和彦 [ほか] 共著
出版情報:
東京 : パワー社, 2010.2 viii, 210p ; 22cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第1章 流体の基礎
1.1 流体の定義と学問 1
1.2 単位と単位系 2
1.3 流体の物理的性質 4
1.3.1 基本物理量 4
1.3.2 状態方程式 6
1.3.3 粘性 7
1.3.4 圧縮性 9
1.3.5 表面張力と毛管現象 11
1.4 流体のモデル化 14
1.4.1 完全流体 14
1.4.2 粘性流体 15
1.4.3 圧縮性流体 15
1.4.4 粘性圧縮性流体とその他 16
練習問題(第1章) 17
第2章 流体静力学
2.1 静止流体の力学 19
2.1.1 圧力の定義 19
2.1.2 圧力の単位 19
2.1.3 圧力の等方性 21
2.1.4 圧力の平衡方程式 22
2.2 静止流体における圧力変化 24
2.2.1 静止液体中の圧力変化 24
2.2.2 ヘッド 25
2.2.3 大気中の圧力 25
2.2.4 圧力測定 26
2.2.5 容器平面壁に作用する力 28
2.2.6 容器曲面壁に作用する力 31
2.2.7 浮カ 33
2.2.8 浮体の安定 34
2.3 相対的圧力平衡 35
2.3.1 相対的静止 35
2.3.2 等加速度直線運動する容器 35
2.3.3 等角速度回転運動する容器 36
練習問題(第2章) 39
第3章 流体運動の基礎方程式
3.1 流れの状態 41
3.1.1 層流と乱流 41
3.1.2 定常流と非定常流 42
3.1.3 一様流と非一様流 43
3.1.4 一次元・二次元・三次元流れ・軸対称流れ 43
3.1.5 流線・流跡線・流脈線 44
3.2 質量保存の法則 45
3.2.1 一次元流れの連続の式 45
3.2.2 オイラーの連続の方程式 47
3.3 流体粒子の加速度 49
3.3.1 一次元流れの加速度 49
3.3.2 三次元流れの加速度 49
3.4 運動方程式 50
3.4.1 一次元流れのオイラーの運動方程式 50
3.4.2 三次元流れのオイラーの運動方程式 52
3.5 エネルギー保存の法則 54
3.5.1 ベルヌーイの定理 54
3.5.2 ベルヌーイの定理の応用 55
3.6 運動量保存の法則 62
3.6.1 運動量の法則 62
3.6.2 運動量の法則の応用 64
3.6.3 角運動量の法則 70
3.6.4 角運動量の法則の応用 70
練習問題(第3章) 74
第4章 完全流体の流れ
4.1 流線と流れ関数 77
4.2 流体粒子の変形と回転 78
4.3 渦度と循環 81
4.4 渦なし流れと速度ポテンシャル 83
4.5 流れ関数と速度ポテンシャル 85
4.6 複素速度ポテンシャル 86
4.7 簡単な二次元渦なし流れの例 88
4.7.1 一様流 88
4.7.2 直線状渦糸 88
4.7.3 吹出しと吸込み 90
4.7.4 二重吹出し 91
4.8 円柱まわりの流れ 94
4.8.1 一様流中に置かれた円柱まわりの流れ 94
4.8.2 円柱まわりに循環のある流れ 96
練習問題(第4章) 100
第5章 粘性流体理論
5.1 粘性流体の運動方程式 103
5.2 レイノルズの相似則 108
5.3 粘性流体方程式の厳密解 110
5.3.1 平行平板間の流れ(クエット・ポアズイユ流れ) 110
5.3.2 瞬間的に運動を始めた平板上の流れ(レイリーの問題) 112
練習問題(第5章) 117
第6章 管内における流れ
6.1 流体摩擦 119
6.2 管摩擦損失 121
6.2.1 層流の場合の管摩擦損失 122
6.2.2 乱流の場合の管摩擦損失 125
6.2.3 円管でない場合の管摩擦損失 128
6.2.4 助走区間での摩擦損失 129
6.3 管路における損失 130
6.3.1 損失ヘッドと損失を考慮したベルヌーイの式 131
6.3.2 代表的な損失 133
6.3.3 水力こう配線とエネルギーこう配線 134
6.4 境界層 136
6.4.1 主流と境界層 136
6.4.2 境界層の厚さの定義 137
6.4.3 境界層内の速度分布 138
6.4.4 境界層のはく離 140
練習問題(第6章) 142
第7章 物体まわりの流れ
7.1 流れの中にある物体に働く抵抗 145
7.2 抗力 146
7.2.1 圧力抵抗 147
7.2.2 摩擦抵抗 149
7.3 円柱まわりの流れとカルマン渦列 151
7.4 揚力と翼 153
練習問題(第7章)157
第8章 圧縮性流れ
8.1 音波と音速 159
8.2 マッハ数 161
8.3 圧縮性流れの特徴と分類 161
8.4 マッハ円錐 162
8.5 流れの閉塞現象 164
8.6 等エントロピー流れの関係式 167
8.7 ラバルノズル内の等エントロピー流れ 168
8.8 衝撃波の発生と形態 173
8.9 垂直衝撃波の関係式 175
8.10 衝撃波を伴うラバルノズル内の流れ 176
8.11 静止気体中を伝ぱする垂直衝撃波 180
練習問題(第8章) 183
第9章 次元解析および相似則
9.1 次元解析 185
9.1.1 ロード・レイリー法 187
9.1.2 バッキンガムのπ定理 188
9.2 相似則 190
9.2.1 相似の条件 191
9.2.2 無次元パラメータ 192
9.2.3 相似則の緩和 194
練習問題(第9章) 195
練習問題・解答 197
参考書籍 203
索引 205
第1章 流体の基礎
1.1 流体の定義と学問 1
1.2 単位と単位系 2
62.
図書
小林吹代著
出版情報:
東京 : 技術評論社, 2017.8 255p ; 19cm
シリーズ名:
数学への招待
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
1章 マルコフ方程式 : マルコフ解と2次方程式—x2+y2+z2=3xyzの「無数」にある解は?
マルコフ解の家系図—マルコフ解は「家系図」にある解で全部? ほか
2章 4マルコフ解と5マルコフ解 : 4マルコフ方程式—x2+y2+z2=xyz+4では「未解決問題」が即解決?
4マルコフ解の家系図—4マルコフ解は「家系図」にある解で全部? ほか
3章 kマルコフ方程式 : 2‐1マルコフ方程式—x2+y2+z2=2xyz+1と「同じ方程式」は?
kマルコフ方程式—「kの正負」で何かちがいはあるの? ほか
4章 kマルコフ解の拡張 : 「kが正」のkマルコフ解の家系図—「解をもたないkマルコフ方程式」は1≦k≦100の中でどれ?
「kが負」のkマルコフ解の家系図—「単独スタート解をもつkマルコフ方程式」は−100≦k≦−1の中でどれ? ほか
5章 2‐1マルコフ解と「不思議な多項式」 : 「見かけ」を変えた2‐nマルコフ方程式—Z2=(X2−1)(Y2−1)と「同じ方程式」は?
(x2−1)(y2−1)=(z2−h2)2—「シェルピンスキー流の条件」下で見つかる無数にある解は? ほか
1章 マルコフ方程式 : マルコフ解と2次方程式—x2+y2+z2=3xyzの「無数」にある解は?
マルコフ解の家系図—マルコフ解は「家系図」にある解で全部? ほか
2章 4マルコフ解と5マルコフ解 : 4マルコフ方程式—x2+y2+z2=xyz+4では「未解決問題」が即解決?
63.
図書
東工大
清水良明著
出版情報:
東京 : コロナ社, 2010.2 vi, 247p ; 21cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
1. はじめに
2. 意思決定問題の認識と定義のための方法
2.1 合理性と意思決定規則 8
2.2 問題発見と問題定義のためのシステムズアプローチ 10
2.2.1 ISM法 11
2.2.2 機能構造モデル化手法-IDEF0 14
2.2.3 その他の方法 22
2.3 まとめ 26
演習問題 27
3. モデル化とシステム解析法
3.1 動的システムのモデル化と解析 28
3.1.1 構造モデルによる解析 29
3.1.2 非構造モデルによるシステム解析 38
3.2 ペトリネットによる離散事象システムのモデル化 43
3.2.1 離散事象システムのモデル化の要件 43
3.2.2 ペトリネットの基礎 45
3.2.3 Sインバリアントと制御問題 49
3.3 ニューラルネットワークによるモデル化 53
3.3.1 BPネットワーク 54
3.3.2 RBFネットワーク 58
3.4 まとめ 60
演習問題 62
4. 最適化理論と最適化手法
4.1 最適化問題の定義と分類 64
4.2 線形計画法 68
4.2.1 図解法 69
4.2.2 線形代数学的察 70
4.2.3 シンプレックス法序論 74
4.2.4 幾何学的解釈 77
4.2.5 シンプレックス法 78
4.2.6 退化問題 81
4.2.7 双対問題 83
4.2.8 感度解析とパラメータ問題 86
4.2.9 漸進的線形計画法と内点法 90
4.3 非線形計画法 92
4.3.1 NLPの最適化理論 92
4.3.2 NLPの最適化手法 98
4.4 離散的最適化問題 111
4.4.1 図解法 111
4.4.2 分岐限定法による解法 113
4.4.3 応用例 116
4.5 メタヒューリスティック最適化手法 118
4.5.1 遺伝的アルゴリズム(GA) 119
4.5.2 擬似アニーリング法(SA) 128
4.5.3 タブーサーチ(TS) 131
4.5.4 差分進化法(DE) 133
4.5.5 粒子群最適化法(PSO) 135
4.5.6 その他の方法 137
4.6 発展的適用 138
4.6.1 ハイブリッド解法 138
4.6.2 最適制御問題の解法 141
4.7 数理計画法のソルバ 146
4.7.1 各種ソルバの所在 146
4.7.2 Excelソルバの使用法 147
4.8 まとめ 149
演習問題 151
5. 多目的計画法による実行支援
5.1 多目的最適化の基礎概念 155
5.2 多目的解析手法 158
5.2.1 従来法 159
5.2.2 多目的進化法 161
5.3 多目的最適化手法 168
5.3.1 選好最適性の必要条件 168
5.3.2 多目的最適化手法の分類 171
5.3.3 非対話的解法 172
5.3.4 対話的解法 174
5.3.5 多目的混合整数計画法問題のハイブリッド解法 187
5.4 有限の選択肢からの多目的最適決定法 191
5.4.1 価値評価法 191
5.4.2 階層分析法(AHP) 191
5.4.3 その他の方法 198
5.5 まとめ 199
演習問題 201
6. 最適化工学の確立に向けて
6.1 現状の最適化技術の認識と分析 203
6.2 学術的最適化からの分析と提案 205
6.3 応用最適化技術からの分析と提案 205
6.4 最適化工学の確立に向けた展望 209
6.4.1 教育のあり方へのテーゼ 209
6.4.2 実効化へのテーゼ 210
6.4.3 理念形成へのテーゼ 211
6.5 具体例を用いた最適化問題定式化手順 211
6.6 まとめ 217
7. おわりに
付録 222
引用・参考文献 229
演習問題解答 240
索引 244
1. はじめに
2. 意思決定問題の認識と定義のための方法
2.1 合理性と意思決定規則 8
64.
図書
東工大
尾崎洋二著
出版情報:
東京 : 東京大学出版会, 2010.3 xi, 267p ; 21cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第2版 まえがき
初版 まえがき
第1章 大きく進展する宇宙科学 1
1.1 なぜ宇宙科学(天文学)を学ぶのか 1
1.2 大きく変わる天文学 2
1.3 天体観測手段の変遷 4
1.4 電磁波の波長と見える天体 7
第2章 太陽と太陽系 9
2.1 太陽 10
2.1.1 太陽の概観 10
2.1.2 太陽の表面およびその外層 11
2.1.3 太陽の活動現象 16
2.1.4 太陽のエネルギー源 20
2.1.5 太陽ニュートリノの謎 21
2.1.6 日震学 33
2.2 太陽系の姿 38
2.2.1 新しい太陽系像 38
2.2.2 太陽系天体の大きさと軌道 40
2.2.3 惑星運動についてのケプラーの3法則 44
2.2.4 地球型惑星と月 45
2.2.5 木星型惑星 51
2.2.6 太陽系内小天体 54
2.2.7 太陽系形成のシナリオ 59
2.3 太陽系外惑星 62
2.3.1 他の星のまわりの回転ガス円盤の観測 62
2.3.2 系外惑星の発見 63
2.3.3 系外惑星の観測方法 65
2.3.4 系外惑星の特徴 68
第3章 恒星の世界 71
3.1 星についての基本的諸量 72
3.1.1 星までの距離 72
3.1.2 星の明るさ 73
3.1.3 星の運動 75
3.1.4 星からの放射スペクトルと星の光度 76
3.1.5 星のスペクトル型 79
3.1.6 星の化学組成 81
3.1.7 ヘルツシュプルング・ラッセル図(HR図) 81
3.2 いろいろな恒星 83
3.2.1 活動性に満ちた星の世界 83
3.2.2 連星 86
3.2.3 脈動変光星 88
3.2.4 星からの質量放出 91
3.2.5 褐色矮星 93
3.3 星の内部構造と進化 95
3.3.1 星はなぜ光り輝くのか 95
3.3.2 星のエネルギー源 96
3.3.3 星の内部構造と進化の理論 98
3.3.4 星の誕生と主系列への進化 99
3.3.5 主系列星 01
3.3.6 進化の進んだ星 105
3.3.7 大質量星の死と超新星爆発 104
3.3.8 大マゼラン雲に出現した超新星 107
3.3.9 小・中質量星の進化 111
3.3.10 白色矮星 113
3.4 パルサーと中性子星 117
3.4.1 星の死としての中性子星 117
3.4.2 パルサーの発見 118
3.4.3 かにパルサー 121
3.4.4 連星パルサー 123
3.5 近接連星とX線星 126
3.5.1 近接連星系 126
3.5.2 激変星 129
3.5.3 降着円盤と矮新星の爆発 131
3.5.4 X線星とX線天文学 133
3.5.5 X線近接連星 136
3.5.6 ブラックホールとX線星 139
3.6 ガンマ線バースト 143
第4章 わが銀河系 149
4.1 星間物質と星の誕生 150
4.1.1 星は現在も生まれている 150
4.1.2 星間ガスと星間塵 151
4.1.3 星間ガスの形態 153
4.1.4 星の誕生 158
4.1.5 星の誕生過程の観測 160
4.2 銀河系の姿 162
4.2.1 星団 162
4.2.2 銀河系の概観 164
4.2.3 銀河系の構造 166
4.2.4 銀河回転 168
4.2.5 暗黒物質(ダークマター) 170
4.2.6 MACHOの探査 172
4.2.7 銀河系の渦巻き構造 175
4.2.8 銀河の誕生と進化 176
第5章 銀河宇宙 179
5.1 系外銀河 179
5.1.1 系外銀河の発見 179
5.1.2 銀河の分類 181
5.1.3 銀河までの距離 184
5.1.4 銀河の赤方偏移とハッブルの法則 186
5.1.5 銀河団 189
5.1.6 宇宙の大規模構造 190
5.1.7 銀河間ガス 191
5.2 クエーサーと活動銀河核 192
5.2.1 電波源の発見 192
5.2.2 クエーサーの発見 195
5.2.3 クエーサーという天体 197
5.2.4 活動銀河中心核 199
5.2.5 エディントン限界 201
5.2.6 クエーサーおよび活動銀河核のモデル 202
5.2.7 巨大ブラックホールのまわりの回転円盤の観測 204
第6章 現代の宇宙論 211
6.1 膨張宇宙 211
6.2 一般相対論の膨張宇宙の解 212
6.3 ビッグバン宇宙論と定常宇宙論 218
6.4 宇宙背景放射の発見 221
6.5 ビッグバン宇宙での元素合成 221
6.6 宇宙のインフレーション 223
6.7 宇宙背景放射探査衛星「COBE」による観測 228
6.8 宇宙背景放射観測衛星「WMAP」による観測結果 230
6.9 宇宙の進化 : 宇宙の誕生から現在まで 234
第7章 宇宙の中の人間 239
7.1 宇宙観の変遷 239
7.2 現代の宇宙観 241
7.3 宇宙の歴史と人間 243
7.4 宇宙カレンダー 246
7.5 地球外文明について 246
7.6 宇宙の中の人間 247
付表 : 天文学上の主な発明発見と業績 00
参考文献 00
図表の出典 00
索引 00
第2版 まえがき
初版 まえがき
第1章 大きく進展する宇宙科学 1
65.
図書
東工大
丹治保典 [ほか] 著
出版情報:
東京 : 講談社, 2011.9 x, 244p ; 21cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
序章 1
生物化学工学の位置付け 1 1
生物化学工学の変遷 1 2
プロセスフローシート 2 4
スケールアップ 5
バイオプロセスの構成 6
バイオプロセスの実際 8
医療・医薬分野 8
食品分野 11
工業分野 16
環境分野 19
1章 生物化学工学の基礎 23
1.1 単位 23
1.2 移動論 25
1.2.1 収支 25
1.2.2 拡散と対流 26
1.2.3 物質と熱のフラックス 27
1.3 運動論 29
1.3.1 粘度 29
1.3.2 流体の流れ 31
1.3.3 固体粒子の沈降 34
演習問題 37
2章 代謝と生体触媒 39
2.1 細胞と生体分子 39
2.1.1 生物の分類と細胞 39
2.1.2 細胞を構成する要素 40
2.1.3 細胞を構成する分子 42
2.2 セントラルドグマと代謝 50
2.2.1 ゲノム,セントラルドグマ,タンパク質生合成 50
2.2.2 代謝 57
2.3 酵素 61
2.3.1 酵素の分類と名称 62
2.3.2 酵素活性 62
2.3.3 補因子 62
2.4 微生物 64
2.4.1 微生物の分類と特徴 64
2.4.2 微生物の環境と生理的特性 66
2.4.3 微生物の培養 68
2.5 動物細胞と植物細胞 69
2.5.1 動物細胞 69
2.5.2 植物細胞 71
2.6 育種と遺伝子組換え技術 73
2.6.1 有用微生物,酵素の探索 73
2.6.2 変異 74
2.6.3 遺伝子組換え 74
2.6.4 代謝工学 87
演習問題 90
3章 生物化学量論と速度論 93
3.1 生物化学量論 93
3.1.1 細胞組成と物質基準の収率因子 93
3.1.2 増殖の生物化学量論 97
3.1.3 基質の燃焼熱とエネルギー基準の収率因子 98
3.1.4 ATP生成基準の収率因子 101
3.2 酵素反応の速度論 102
3.2.1 Michaelis-Mentenの式 103
3.2.2 動力学定数の算出法 106
3.2.3 阻害剤の反応機構 108
3.2.4 基質阻害 111
3.2.5 アロステリック酵素に対する速度式 112
3.2.6 酵素活性の温度・pH依存性 112
3.3 細胞増殖の速度論 116
3.3.1 増殖速度 117
3.3.2 増殖曲線 119
3.3.3 基質消費速度 120
3.3.4 代謝産物の生成速度 121
演習問題 124
4章 バイオリアクター 127
4.1 バイオリアクターの種類と特徴 127
4.1.1 槽型のバイオリアクターを用いた回分操作 127
4.1.2 槽型のバイオリアクターを用いた連続操作 128
4.1.3 管型のバイオリアクターを用いた連続操作 129
4.1.4 槽型のバイオリアクターを用いた流加操作 130
4.2 バイオリアクターの基本設計-設計方程式 131
4.2.1 回分バイオリアクター 132
4.2.2 連続槽型バイオリアクター 132
4.2.3 管型バイオリアクター 133
4.2.4 流加バイオリアクター 134
4.3 基本的なバイオリアクター 134
4.3.1 回分バイオリアクターを用いた酵素反応 134
4.3.2 流通バイオリアクターを用いた酵素反応 136
4.3.3 流加バイオリアクターを用いた酵素反応 137
4.3.4 回分バイオリアクターを用いた微生物反応 137
4.3.5 連続槽型バイオリアクターを用いた微生物反応 139
4.4 種々のバイオリアクター 142
4.4.1 固定化生体触媒を用いたバイオリアクター 142
4.4.2 リサイクルを伴う微生物バイオリアクター 153
4.4.3 通気を伴う微生物バイオリアクター 156
4.4.4 バイオリアクターのスケールアップ 158
4.4.5 バイオリアクターの制御 160
4.5 滅菌操作 161
4.5.1 加熱滅菌 162
4.5.2 フィルター滅菌 167
4.5.3 高圧滅菌 168
演習問題 169
5章 バイオセパレーション 171
5.1 バイオセパレーションの特徴と目的 171
5.1.1 生物化学工学におけるバイオセパレーションの位置付け 171
5.1.2 バイオセパレーションの特徴 172
5.1.3 バイオセパレーションの基本原理 175
5.2 細胞の破砕 176
5.3 固体成分の分離 178
5.3.1 沈降分離と遠心力の利用 178
5.3.2 ろ過 181
5.4 吸着 184
5.4.1 吸着操作の種類と特徴 184
5.4.2 吸着平衡 185
5.5 膜分離 187
5.5.1 膜分離の特徴 187
5.5.2 膜の透過流束 189
5.5.3 濃度分極と阻止率 190
5.5.4 膜分離のモジュール 192
5.5.5 膜透過の輸送現象 194
5.6 抽出 196
5.6.1 抽出操作の種類と特徴 196
5.6.2 抽出装置 196
5.6.3 三角図表の利用 199
5.6.3 超臨界抽出 201
5.7 電気泳動 202
演習問題 206
6章 バイオプロセスの実際 209
6.1 バイオプロセスの実用化 209
6.2 動物細胞利用プロセス 209
6.3 ファインケミカル製品の生産プロセス-ジルチアゼムの製造プロセス 216
6.4 バイオリアクターの改良-気泡を使ったバイオプロセス 221
6.5 超臨界流体を用いたプロセス 224
6.5.1 超臨界流体を用いた抽出 224
6.5.2 超臨界流体を用いた滅菌 226
6.6 新しい乾燥・脱水プロセス-食品および廃棄物に対して 227
6.7 まとめ 229
演習問題の略解とヒント 230
参考書 235
索引 239
序章 1
生物化学工学の位置付け 1 1
生物化学工学の変遷 1 2
66.
図書
インターカルト日本語学校著 = Intercultural Institute of Japan = 草苑日本语学校 = 인터컬트일본어학교
出版情報:
東京 : ナツメ社, 2011.3 255p ; 26cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
67.
図書
東工大
工藤一浩監修
目次情報:
続きを見る
【第一編 総論】
第1章 総論(工藤一浩) 3
【第二編 評価】
第1章 材料
1. 有機トランジスタ材料の基礎評価(鎌田俊英) 11
1.1 半導体の基本性質 11
1.2 有機半導体の材料設計 12
1.3 トランジスタ動作評価 13
1.4 半導体性能の構造要因 16
1.5 電極材料 19
2. 高分子系有機トランジスタ材料(堀田収) 21
2.1 はじめに 21
2.2 高分子系有機トランジスタ材料のいろいろ 21
2.3 高分子系有機トランジスタ材料のバリエーション 23
2.4 まとめと将来展望 25
3. 低分子系有機トランジスタ材料(南方尚) 27
3.1 はじめに 27
3.2 含窒素原子系材料 27
3.3 含硫黄原子系材料 28
3.4 炭化水素系材料 28
3.5 まとめ 31
4. 有機単結晶トランジスタと界面ドーピング(岩佐義宏) 34
4.1 はじめに 34
4.2 有機単結晶FETの構造と作製法 35
4.2.1 有機ゲート絶縁膜法 35
4.2.2 貼り合わせ法 36
4.3 有機単結晶トランジスタの特性 37
4.4 界面ドーピング 40
4.5 おわりに 42
第2章 電気物性
1. 有機トランジスタの一般的電気物性(金藤敬一) 44
1.1 はじめに 44
1.2 トランジスタの種類 44
1.3 MOS型FET 47
1.4 電位分布 50
1.5 おわりに 52
2. 有機トランジスタ薄膜のその場測定(斉木幸一朗) 55
2.1 はじめに 55
2.2 FETその場測定装置 55
2.3 空乏層、蓄積層の厚み評価 56
2.3.1 閾値膜厚の評価 56
2.3.2 空乏層の観察 57
2.3.3 蓄積層厚の評価 59
2.4 チャネル容量の周波数依存性 61
3. 局所電気・電子物性(中村雅一) 64
3.1 はじめに 64
3.2 界面電子構造の評価 64
3.3 金属/半導体接触抵抗の評価 67
3.4 絶縁体/有機半導体界面の評価 72
3.5 局所的なキャリア輸送現象およびバンド状態の評価 73
第3章 FET
1. アモルファスシリコンとの違い 77
1.1 アモルファスシリコンとの一般的な差異(三島康由) 77
1.1.1 はじめに 77
1.1.2 物性的、素子構造的比較 78
1.1.3 トランジスタ特性、回路特性 80
1.1.4 まとめ 84
1.2 ディスプレイ用トランジスタから見た差異(服部励治) 85
1.2.1 はじめに 85
1.2.2 有機TFTディスプレイの種類 85
1.2.3 まとめ 93
2. 有機薄膜FETの物性(島田敏宏) 94
2.1 はじめに 94
2.2 電界効果ドーピングの熱力学と速度論 94
2.3 移動度の測定法 95
2.3.1 静的特性による方法 95
2.3.2 過渡光電流測定(time of flight、TOF法) 96
2.4 有機薄膜FETにおける散乱機構 96
2.4.1 粒界の影響 97
2.4.2 有機物に内在的な散乱機構:分子間フォノン散乱 97
2.4.3 構造の乱れ 97
2.4.4 不純物散乱 98
2.5 FETのTOF測定 98
2.6 今後の展望 101
第4章 薄膜形成
1. 薄膜形成技術と評価技術(八瀬清志) 103
1.1 はじめに:有機薄膜トランジスタ(TFT)の構造 103
1.2 エピタキシャル成長による分子配向制御有機FET 104
1.3 摩擦転写法による一軸配向分子の有機FET 107
1.4 おわりに 111
2. 印刷法・インクジェット法(佐野健志、脇坂健一郎) 113
2.1 はじめに 113
2.2 代表的な印刷法及びパターニング方法 113
2.3 各方式の説明 115
2.3.1 凸版 115
2.3.2 凹版 115
2.3.3 平版 116
2.3.4 孔版 116
2.3.5 インクジェット 116
2.3.6 レーザー熱転写 117
2.3.7 スピンコート 118
2.3.8 スプレーコート 118
2.3.9 バーコート 118
2.3.10 リフトオフ 118
2.3.11 フォトケミカルパターニング 119
2.3.12 自己組織化 119
2.4 おわりに 119
3. 有機トランジスタの自己組織化技術(安藤正彦) 121
3.1 はじめに 121
3.2 有機TFTの狙い 122
3.3 フラットディスプレイ応用の利点 122
3.4 有機TFTの自己整合集積製法 124
3.5 最近の動向 127
3.6 おわりに 129
【第三編 応用】
第1章 大面積センサー(染谷隆夫)
1. はじめに 133
2. 電子人工皮膚シート 133
2.1 低温硬化タイプのポリイミドのゲート絶縁膜 135
2.2 レーザー加工によるビア 136
2.3 「切り貼り」による有機集積回路 136
3. シート型スキャナー 137
3.1 デバイス構造と動作 138
3.2 3次元有機集積回路 140
4. 大面積エレクトロニクスの将来展望 141
5. 今後の課題 142
6. おわりに 142
第2章 ディスプレイ応用(中馬隆)
1. はじめに 145
2. 各種TFTの特徴 145
3. 有機半導体材料 146
4. 有機TFT構造 148
4.1 トップコンタクト構造 148
4.2 ボトムコンタクト構造 149
4.3 トップゲート型構造 149
5. 有機TFTによるアクティブマトリクス駆動ディスプレイ 149
5.1 液晶ディスプレイ 149
5.2 電気泳動型ディスプレイ 151
5.3 有機ELパネル 151
6. 今後の開発に向けて 153
第3章 印刷技術による情報タグとその周辺機器(小幡勝也)
1. はじめに 155
2. 印刷技術とは 155
3. 印刷方式 157
4. 印刷によるパターン形成 159
5. グラビア印刷法による有機EL素子の特性評価 160
5.1 発光層の膜厚制御 160
5.2 発光の均一化 161
5.3 有機EL素子の特性 162
6. フレキシブル有機ELパネルの試作 163
7. 情報タグ 164
【第四編 未来への技術】
第1章 遺伝子トランジスタによる分子認識の電気的検出(宮原裕二)
1. はじめに 169
2. 遺伝子FETによる一塩基多型検出の基本原理 170
3. 実験方法 172
3.1 FETチップ 172
3.2 DNAプローブの固定化 172
3.3 ハイブリダイゼーション 172
3.4 インターカレーション 172
3.5 DNA伸長反応 172
4. 分子認識反応の検出 173
4.1 遺伝子FETの電気特性変化 173
5. 遺伝子FETによる一塩基多型の検出 174
5.1 アレル特異的ハイブリダイゼーション 174
5.2 インターカレーションによる高精度化 174
5.3 プライマー伸長反応によるSNP解析 175
6. ナノチューブ、ナノワイヤーを用いたバイオチップ 176
7. おわりに 178
第2章 単一分子エレクトロニクス(和田恭雄)
1. はじめに:エレクトロニクスの将来像 180
1.1 情報デバイスの発展の歴史と新しいパラダイムの必要性 180
1.2 将来像としての単一分子デバイス 182
1.3 情報蓄積デバイスの展望 183
1.4 その他の応用 184
1.5 20年後のエレクトロニクスに向けて:単一分子エレクトロニクスが可能にすること 185
2. 単一分子デバイス実現に向けた計測技術 186
2.1 実現へのマイルストーン 186
2.2 第一のマイルストーン:単一分子の導電性評価 186
2.3 第二のマイルストーン:単一分子発光デバイス特性計測技術 188
2.4 第三のマイルストーン:超高速トランジスタ特性評価 188
3. 情報技術の更なる発展を見据えて 188
【第一編 総論】
第1章 総論(工藤一浩) 3
【第二編 評価】
68.
図書
東工大
瀬﨑仁, 木村聰城郎, 橋田充編集
出版情報:
東京 : 廣川書店, 2011.10 xviii, 537p ; 26cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第1章 緒論 (木村聰城郎) 1
1.1 薬剤学 2
1.2 医薬品 3
1.2.1 定義 3
1.2.2 分類 4
1.3 医薬品の適用 8
1.4 医薬品の用量 9
1.4.1 薬用量 9
1.4.2 小児薬用量 10
1.4.3 高齢者薬用量 10
1.5 医薬品の有効性と安全性 11
1.5.1 バイオアベイラビリティ 11
1.5.2 有効性と安全性 13
第2章 溶液 (藤田卓也) 15
2.1 溶液と溶解 16
2.1.1 溶液 16
2.1.2 溶解 18
2.2 溶解性の修飾 28
2.2.1 医薬品の可溶化 28
2.2.2 医薬品の難溶化 34
2.3 溶液の性質 34
2.3.1 溶液の束一性 34
2.3.2 弱電解質の解離平衡 37
2.3.3 緩衝液 40
2.3.4 ミリグラム当量(mEq) 42
2.3.5 等張化 42
2.3.6 浸透圧測定法 45
2.4 演習問題 46
第3章 安定性 (藤田卓也) 49
3.1 医薬品の分解反応 50
3.2 反応速度論 52
3.2.1 化学反応速度論 53
3.2.2 反応速度に影響を与える因子 61
3.3 製剤の安定化 66
3.4 演習問題 71
第4章 分散系 (際田弘志) 75
4.1 界面現象 77
4.1.1 表面張力 77
4.1.2 粒子の蒸気圧と溶解度 79
4.1.3 吸着と表面張力 79
4.1.4 固体表面のぬれ 80
4.1.5 表面張力の測定法 82
4.2 界面活性剤 84
4.2.1 界面活性剤の種類 84
4.2.2 臨界ミセル濃度 86
4.2.3 クラフト点と曇点 88
4.2.4 HLB 89
4.3 コロイド分散系 91
4.3.1 コロイド分散系の特徴 91
4.3.2 コロイドの種類 92
4.4 分散系製剤 94
4.4.1 エマルション 95
4.4.2 サスペンション 97
4.4.3 リポソーム 99
4.5 演習問題 101
第5章 レオロジー (横山祥子) 105
5.1 弾性変形と粘性流動 106
5.2 構造粘性 109
5.3 チキソトロピー 111
5.4 粘弾性の力学的模型 112
5.5 レオロジー的性質の測定方法 116
5.6 極限(固有)粘度と分子量 120
5.7 演習問題 121
第6章 固体の性質 (横山祥子) 123
6.1 固体の基礎的な性質 124
6.1.1 固体結晶 124
6.1.2 非晶質固体 126
6.1.3 結晶多形 126
6.1.4 水和物・溶媒和物 128
6.2 粉体 129
6.2.1 粒子径,粒度分布,粒子表面積 129
6.2.2 粒子形 137
6.2.3 付着性,凝集性 138
6.2.4 充填性,空隙率 139
6.2.5 流動性 141
6.2.6 その他の粉体物性 144
6.2.7 吸湿 145
6.3 演習問題 147
第7章 製剤(製剤化・製剤試験法) (山口俊和・長田俊治) 149
7.1 製剤の種類 150
7.1.1 製剤の形態と用法 150
7.1.2 製剤の開発 152
7.1.3 Good Manufacturing Practice 153
7.2 液状製剤 154
7.2.1 溶液状製剤 155
7.2.2 生薬由来製剤 155
7.2.3 エリキシル剤 157
7.2.4 シロップ剤 157
7.2.5 リモナーデ剤 158
7.2.6 外用液剤 158
7.3 分散系製剤 159
7.3.1 懸濁剤 159
7.3.2 乳剤 160
7.4 半固形製剤 161
7.4.1 軟膏剤 161
7.4.2 クリーム剤 165
7.4.3 ゲル剤 166
7.4.4 貼付剤 167
7.4.5 坐剤 171
7.5 固形製剤 174
7.5.1 散剤 174
7.5.2 顆粒剤 179
7.5.3 丸剤 183
7.5.4 錠剤 183
7.5.5 トローチ剤 194
7.5.6 カプセル剤 194
7.5.7 持続性製剤 198
7.6 無菌製剤 200
7.6.1 注射剤 200
7.6.2 点眼剤 210
7.6.3 眼軟膏剤 214
7.6.4 透析用剤 215
7.7 吸入剤 216
7.7.1 吸入エアゾール剤 216
7.7.2 吸入液剤 219
7.7.3 吸入粉末剤 220
7.8 製剤試験法 221
7.8.1 製剤均一性試験法 221
7.8.2 崩壊試験法 226
7.8.3 溶出試験法 227
7.8.4 摩損度および硬度試験法 231
7.8.5 無菌試験法 232
7.8.6 発熱性物質試験法/エンドトキシン試験法 232
7.8.7 不溶性異物検査法 233
7.8.8 不溶性微粒子試験法 233
7.8.9 安定性試験法 234
7.9 容器と包装 235
7.9.1 製剤の容器・包装 235
7.9.2 情報の記載 236
7.9.3 容器・包装材料試験法 237
7.10 演習問題 241
第8章 DDS(ドラッグデリバリーシステム) (高倉喜信) 243
8.1 DDSの目的と方法 244
8.2 DDSの開発 247
8.3 放出制御を目的としたDDS 248
8.4 吸収促進を目的としたDDS 251
8.5 プロドラッグ 252
8.6 高分子キャリアーを利用したDDS 255
8.7 微粒子性キャリアーを利用したDDS 258
8.8 演習問題 261
第9章 薬物の体内動態 (木村聰城郎) 265
9.1 生体膜透過機構 266
9.2 薬物の吸収 268
9.3 薬物の分布 306
9.4 薬物の代謝 317
9.5 薬物の排泄 331
9.6 演習問題 341
第10章 薬動学(ファーマコキネティクス) (檜垣和孝) 343
10.1 コンパートメントモデル解析 344
10.1.1 1-コンパートメントモデル 345
10.1.2 2-コンパートメントモデル 376
10.1.3 非線形コンパートメントモデル 386
10.2 生理学的薬物速度論 388
10.2.1 臓器クリアランス 389
10.2.2 固有クリアランス 391
10.2.3 クリアランスとバイオアベイラビリティ 396
10.2.4 生理学的モデル 397
10.2.5 ハイブリッドモデル 400
10.3 モーメント解析法 401
10.3.1 モーメントとは 402
10.3.2 平均滞留時間 404
10.3.3 非規格化モーメントとモーメントパラメータ 405
10.3.4 モーメントの算出 405
10.3.5 ラプラス変換とモーメント 411
10.3.6 コンパートメントモデルとの対応 412
10.3.7 Disposition kineticsの解析 418
10.3.8 Absorption kineticsの解析 419
10.4 ポピュレーションファーマコキネティクス 423
10.4.1 母集団薬物動態パラメータの推定法 425
10.4.2 非線形混合効果モデル解析 426
10.4.3 ベイジアン解析 427
10.4.4 ジゴキシンの母集団体内動態 430
10.5 演習問題 432
第11章 薬理効果の速度論的解析 (檜垣和孝) 435
11.1 薬力学モデル 437
11.1.1 固定効果モデル 437
11.1.2 シグモイドEmaxモデル 437
11.1.3 Emaxモデル 439
11.1.4 対数濃度-反応式 439
11.1.5 線形モデル 440
11.1.6 薬物が2種類の場合の薬力学モデル 440
11.2 薬理効果の速度論的解析 442
11.2.1 1-コンパートメントモデルとの結合 442
11.2.2 マルチコンパートメントモデルとの結合 445
11.2.3 薬効コンパートメントモデル 446
11.3 生体調節系を介した薬理効果 448
11.4 演習問題 451
第12章 臨床薬物速度論 (黒﨑勇二) 453
12.1 薬物相互作用 454
12.1.1 有害事象の要因としての医薬品 454
12.1.2 薬物相互作用 456
12.2 医薬品の安全性と医薬品情報 493
12.3 疾患時の薬物動態 494
12.4 加齢による薬物の体内動態の変化 500
12.5 TDM(治療薬物モニタリング) 505
12.6 演習問題 517
付録 519
索引 521
第1章 緒論 (木村聰城郎) 1
1.1 薬剤学 2
1.2 医薬品 3
69.
図書
東工大
山内清語, 野崎浩一編著
出版情報:
東京 : 三共出版, 2010.6 viii, 303p ; 22cm
シリーズ名:
複合系の光機能研究会選書 ; 1
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
巻頭言
はじめに
1章 原子軌道から励起状態へ(石井和之) 1
はじめに
1-1 量子力学の位置づけ 1
1-1-1 古典力学から量子力学へ 1
1-1-2 金属錯体のハミルトニアン 3
1-1-3 金属錯体の励起状態の記述 5
1-2 配位子場中のd電子の軌道 6
1-2-1 水素様原子モデル 7
1-2-2 結晶場理論 10
1-2-3 配位子場理論 14
1-3 電子励起状態の記述 17
1-3-1 単一電子配置のスピン軌道関数 17
1-3-2 単一励起電子配置のエネルギー 20
1-3-3 配置間相互作用(CI) 24
2章 遷移金属イオンの対称性と電子遷移(長谷川靖哉) 29
2-1 自由原子の電子状態とエネルギー準位 29
2-1-1 原子軌道 29
2-1-2 自由原子の電子状態と表記法 30
2-1-3 電子状態のエネルギー準位 33
2-2 対称性とエネルギー分裂 35
2-2-1 対称要素に基づく点群の決定 35
2-2-2 点群 37
2-2-3 群の表現と既約表現 40
2-2-4 指標表 45
2-2-5 群論による積分値の評価 47
2-2-6 対称積表現と反対称積表現 50
2-2-7 結晶場による電子状態のエネルギー準位の分裂 51
2-3 金属イオンの光学的電子遷移確率 59
2-3-1 選択律 59
2-3-2 遷移金属イオンのd-d遷移 60
2-3-3 希土類イオンのf-f遷移 63
2-3-4 希土類イオンのf-d遷移 70
2-3-5 全角運動量を考慮した配位子場分裂 70
3章 光物理過程(野崎浩一) 75
3-1 光と物質の相互作用 75
3-1-1 吸収スペクトルとエネルギー準位 75
3-1-2 光物理過程の概要 76
3-1-3 発光量子収量 78
3-2 吸収と放射の理論 79
3-2-1 EinsteinのA係数とB係数 79
3-2-2 光学的遷移確率の量子力学的導出 81
3-2-3 Lambert-Beer則と吸光係数 86
3-2-4 振動子強度 88
3-2-5 凝縮系の補正 89
3-2-6 Strickler-Bergの関係式 89
3-3 核の運動と電子との結合 92
3-3-1 断熱近似と荒い断熱近似 92
3-3-2 Jahn-Teller効果 94
3-3-3 FrancK-Condon原理 95
3-3-4 振電結合 97
3-4 電子状態間の遷移 99
3-4-1 可逆過程と不可逆過程 99
3-4-2 不可逆過程の遷移確率 102
3-4-3 内部転換 105
3-5 異なるスピン状態間の混合と遷移 106
3-5-1 スピン軌道結合 106
3-5-2 自由原子におけるスピン軌道結合 107
3-5-3 軌道角運動量の死滅とスピン軌道結合 110
3-5-4 項間交差 112
3-5-5 りん光 116
3-6 スペクトルの振動構造 118
3-6-1 吸収と発光のスペクトル 118
3-6-2 Huang-Rhysパラメータ 120
3-6-3 多基準振動モード系の振動構造 122
4章 電荷移動励起状態(野崎浩一) 129
4-1 電荷移動状態の波動関数とエネルギー(Mullikenの電荷移動理論) 130
4-2 電荷移動の遷移エネルギーと遷移確率 132
4-3 溶液中の電荷移動スペクトルの形状 134
4-4 電荷移動吸収・発行極大エネルギーの溶媒シフト 138
4-4-1 球形状分子内で電荷移動が起きる場合 140
4-4-2 分子間電荷移動の場合 144
4-5 電荷移動吸収帯による電子ドナー-アクセプター間の電子的相互作用の評価 145
4-6 電子的相互作用の量子化学的取り扱い-Generalized Mulliken-Hush理論 149
4-7 電子的相互作用の分子軌道論的解釈 150
5章 スピンと磁性 157
5-1 金属イオンの電子スピン 158
5-1-1 電子の軌道と量子数 158
5-1-2 スピン量子数 160
5-2 磁気モーメント 161
5-2-1 軌道角運動量に伴う磁気モーメント 161
5-2-2 スピン角運動量に伴う磁気モーメント 162
5-2-3 全角運動量に伴う磁気モーメント 162
5-2-4 Larmor歳差運動 163
5-2-5 Zeeman分裂 164
5-3 金属イオンの基底項 165
5-4 磁化率と磁性 167
5-4-1 Van Vleckの式 167
5-4-2 金属イオンの磁化率 170
5-4-3 多核金属錯体の磁性 171
5-4-4 2核金属錯体の磁化率の式 172
5-5 分子磁性体 174
5-5-1 反強磁性(Antiferromagnetism) 174
5-5-2 強磁性(Ferromagnetism) 174
5-5-3 フェリ磁性(Ferrimagnetism) 175
5-5-4 らせん磁性(Helical magnetism) 175
5-5-5 弱強磁性(Week ferromagnetism) 175
5-6 光スイッチィング分子 175
5-6-1 光誘起スピン転移現象 176
5-6-2 光誘起磁性体 178
おわりに
6章 励起三重項状態のスピン特性(山内清語・野崎浩一) 181
6-1 スピン副準位の記述と性質 183
6-1-1 ゼロ磁場の三重項状態 : 量子化学演習 183
6-1-2 電子構造・分光的性質とその関係 188
6-1-3 磁場下のスピン副準位と電子スピン共鳴 190
6-2 励起状態の性質とスピン軌道相互作用 193
6-2-1 励起状態のパラメータとスピン軌道相互作用 193
6-2-2 スピン軌道相互作用の演算子 193
6-2-3 スピン軌道相互作用の行列要素 195
6-2-4 State間の積分からMO間,AO間の積分へ 199
6-2-5 分光学的パラメータと行列要素 200
6-2-6 ESRパラメータと行列要素 202
6-2-7 白金錯体ESRスペクトルの解析例 204
6-3 MLCT励起状態からのりん光とゼロ磁場分裂 206
6-4 付録 212
6-4-1 スピン角運動量の行列要素 212
6-4-2 M-LLサブユニットのスピン軌道相互作用 214
7章 エネルギー移動(浅野素子) 219
7-1 エネルギー移動と分子間相互作用 220
7-1-1 “フェルスター機構と“Dexter機構”の違いと特徴 220
7-1-2 分子間相互作用と励起エネルギー移動の分類 221
7-2 エネルギー移動を理解するための物理法則と量子化学の基礎 224
7-2-1 光化学におけるスピン保存則 225
7-2-2 電子間相互作用 : クローン積分と交換積分 226
7-2-3 Fermiの黄金律 227
7-3 Foerster機構 228
7-3-1 Foersterの式 229
7-3-2 エネルギー移動速度の導出その1 : Fermiの黄金律 231
7-3-3 エネルギー移動速度の導出その2 : 双極子-双極子相互作用 234
7-4 Dexter機構 237
7-4-1 Dexterの式 238
7-4-2 スピン保存則とDexter機構の必要性 239
7-4-3 スピン関数を含めた分子間相互作用とエネルギー移動のメカニズム 241
7-4-4 Dexter機構によるエネルギー移動速度の導出 243
7-4-5 “フェルスター機構”と“Dexter機構”の比較と本質 243
Appendix 248
8章 光誘起電子移動(小堀康博) 257
8-1 電子移動反応の基礎理論 259
8-1-1 Marcus理論 259
8-1-2 電子移動速度の量子力学的取り扱い 266
8-2 長距離電子移動の電子的相互作用 271
8-2-1 空間を介した相互作用 271
8-2-2 軌道を介した相互作用 273
8-3 長距離電荷分離状態の交換相互作用 279
8-3-1 ラジカル対のスピン間相互作用 279
8-3-2 スピン交換相互作用のメカニズム 280
8-4 時間分解ESR法による交換相互作用の観測 286
8-4-1 スピン相関ラジカル対の原理 286
8-4-2 交換相互作用の定量解析と電子的相互作用 289
索引 299
巻頭言
はじめに
1章 原子軌道から励起状態へ(石井和之) 1
70.
図書
東工大
鈴木伸一, 宮崎忠國編著 ; 内田均 [ほか] 共著
出版情報:
東京 : コロナ社, 2010.4 vii, 196p, 図版[2]p ; 21cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
1 環境緑地学へのいざない
1.1 私たちの生活はどのように変化してきたか 1
1.2 身近な自然環境の保全にどのように貢献するか 2
2 地球環境と緑地
2.1 世界の森林 5
2.2 リモートセンシング 6
2.2.1 リモートセンシングの方式 8
2.2.2 リモートセンサー 9
2.2.3 リモートセンサーの仕様 10
2.2.4 リモートセンシングデータのデータ処理 11
3 植生と環境
3.1 植生と植物群落 14
3.2 植生のとらえ方 15
3.3 植生と環境要因 16
3.4 自然植生と代償植生 17
3.5 生物と環境の相互作用と生態系の発達 18
3.6 環境緑地学における植生の位置づけ,とらえ方 19
3.6.1 植生と景観 20
3.6.2 景観の把握 21
3.6.3 緑地の評価 21
4 ヒートアイランドと緑地
4.1 都市の発生と環境問題,そして公園緑地 22
4.2 公園緑地系統による都市の計画 24
4.3 大都市膨張と緑地計画 26
4.4 日本の緑地計画,その都市環境への対応 27
4.5 ヒートアイランド研究の現在 29
5 緑地の保全
5.1 田園風景の保全と再生 37
5.1.1 美しい田園は自然と共に生きる人々の生活によって守られてきた 37
5.1.2 中山間地域における農業の現在 39
5.1.3 中山間地域における小さな連携から始まる地域再生 40
5.2 住宅地における緑の継承と街づくりの展開 46
5.2.1 東久留米市学園町と自由学園 46
5.2.2 学園町憲章の制定 49
5.2.3 環境に対する住民の意識 50
5.2.4 環境共生都市を目指して 52
6 緑地を構成する動物の生態・保全
6.1 植物と昆虫の相互関係 55
6.1.1 生物間の相互作用 55
6.1.2 植物と昆虫の食われる─食う関係 56
6.1.3 植物と昆虫の共生関係 63
6.1.4 農生態系における作物と害虫 66
6.2 両生類の保全 68
6.2.1 日本に生息する両生類 68
6.2.2 水田とその周囲に生息する両生類の生活 72
6.2.3 両生類の減少要因 77
6.2.4 生息環境の保全と管理 86
7 フィールド調査
7.1 フィールド調査における注意事項 91
7.2 動物調査 92
7.2.1 哺乳類 93
7.2.2 両生類・爬虫類 96
7.2.3 鳥類 97
7.2.4 昆虫類 98
7.2.5 調査データのまとめ方 101
7.3 植物調査 105
7.3.1 フィールド調査における植物の位置づけ 105
7.3.2 フィールド調査における植物のとらえ方 106
7.3.3 植物相調査 106
7.3.4 植生調査 108
7.4 景観調査 113
8 緑地の創造
8.1 緑地とデザイン 116
8.1.1 緑地の計画と設計 117
8.1.2 デザインの方法と技法 119
8.1.3 デザインプロセス 122
8.2 地域の創造 123
8.2.1 デザインの課題 123
8.2.2 デザインの手順と方法 124
8.2.3 地域景観の分析からデザインコンセプト「盆地の盆」の提示 125
8.2.4 概念操作から形態操作への展開 126
9 緑地施設の設計・施工
9.1 設計図面 130
9.2 丁張り工 134
9.2.1 水盛遣形 134
9.2.2 U字溝の丁張り 136
9.3 階段工 136
9.3.1 階段の蹴上げと踏み面 137
9.3.2 階段工の留意事項 137
9.4 石積み工 139
9.4.1 空積みと練積み 140
9.4.2 石積み施工順序 140
9.5 石組工 141
9.6 飛石・蹲踞工 143
9.7 竹垣工 145
9.7.1 竹垣の種類と基本構造 145
9.7.2 四ツ目垣のつくり方 146
10 緑地の施工・管理
10.1 花壇 149
10.1.1 花壇に用いる植物 149
10.1.2 花壇のデザイン 152
10.1.3 花壇の施工 152
10.1.4 花壇の管理 153
10.2 樹木の移植 154
10.2.1 根回し 154
10.2.2 根巻 160
10.2.3 移植方法と根巻の仕方 160
10.3 樹木支柱 160
10.3.1 樹木支柱の目的 160
10.3.2 樹木支柱の種類 161
10.3.3 樹木支柱の管理と除去 161
10.4 ロープワーク 161
10.5 緑地関連管理道具 165
10.5.1 剪定道具 166
10.5.2 草刈り道具 167
10.5.3 掘削道具 168
10.5.4 整地・掃除道具 168
10.6 緑地関連維持管理用機械・建設機械 169
10.6.1 維持管理用機械 169
10.6.2 建設機械 173
10.7 剪定 176
10.7.1 剪定の目的 176
10.7.2 樹木の生理と剪定 177
10.8 樹木の病害虫防除 180
10.8.1 樹木に現れる病気の症状 180
10.8.2 おもな樹木の病害虫とその防除 181
10.9 施肥 183
10.9.1 肥料の三要素 183
10.9.2 有機質肥料と無機質肥料 184
10.9.3 施肥の時期 185
10.10 剪定残渣などの有効利用 185
10.10.1 堆肥の効果 186
10.10.2 堆肥のつくり方 186
10.10.3 堆肥の良し悪しの見極め 187
参考・引用文献 188
索引 193
1 環境緑地学へのいざない
1.1 私たちの生活はどのように変化してきたか 1
1.2 身近な自然環境の保全にどのように貢献するか 2
71.
図書
東工大
西川尚男著
出版情報:
東京 : 東京電機大学出版局, 2010.6 vi, 223p ; 22cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第1章 資源の枯渇と地球温暖化問題 1
1.1 エネルギーの流れ 1
1.2 発電構成 2
1.3 資源枯渇と地球環境問題 4
1.3.1 人類共通の課題 4
1.3.2 資源の枯渇 5
1.3.3 地球環境問題 6
1.4 CO2削減への取り組み 9
1.5 燃料電池の貢献 14
1.5.1 定置用燃料電池 14
1.5.2 燃料電池自動車 15
1.5.3 固体酸化物形燃料電池を利用した高効率発電システム 16
1.5.4 MCFCを用いたCO2回収システム 16
1.5.5 電力システムを補完する燃料電池と再生可能エネルギーからの水素製造 17
第2章 燃料電池の基本 19
2.1 燃料電池の原理と種類 19
2.1.1 固体高分子形燃料電池(PEFC) 20
2.1.2 りん酸形燃料電池(PAFC) 21
2.1.3 溶融炭酸塩形燃料電池(MCFC) 21
2.1.4 固体酸化物形燃料電池(SOFC) 23
2.2 燃料電池の理論効率と理論起電力 26
2.2.1 理論効率 26
2.2.2 理論起電力 27
2.2.3 高位発熱量と低位発熱量で表示した理論効率と理論起電力 27
2.2.4 燃料の違いからみる反応・理論起電力・理論効率 29
第3章 固体高分子形燃料電池(PEFC)のセル・スタック構成と水管理 31
3.1 PEFCのセル・スタック構成 31
3.1.1 触媒 32
3.1.2 高分子膜 41
3.1.3 セパレータ 45
3.2 水管理 48
3.2.1 セル内水分移動 48
3.2.2 並行流と対向流 51
3.2.3 加湿方式 52
第4章 セル性能 58
4.1 セル性能の向上 58
4.2 セル電圧特性 61
4.2.1 運転圧力特性 62
4.2.2 セル運転温度特性 63
4.2.3 利用率特性 64
4.2.4 加湿特性 71
4.2.5 一酸化炭素の影響 77
4.2.6 そのほかの不純物ガスの影響 80
第5章 セル劣化 84
5.1 触媒劣化 84
5.1.1 カソード触媒の劣化 84
5.1.2 アノード触媒の劣化 89
5.1.3 触媒坦持体の劣化 92
5.2 電解質膜劣化メカニズム 94
5.2.1 低加湿試験 94
5.2.2 開放電圧放置試験(OCV試験) 102
5.2.3 低加湿・負荷変動条件 111
5.2.4 膜劣化対策 112
5.3 カーボン劣化 113
5.3.1 高いセル電圧印加時のカーボン腐食 113
5.3.2 急激な電圧印加時のカーボン腐食 114
5.3.3 起動時のアノードに水素が流入した場合の腐食 118
5.3.4 水素欠乏時の腐食 121
第6章 セル診断技術 127
6.1 サイクリックボルタンメトリー測定法(CV法) 127
6.1.1 測定原理 127
6.1.2 測定方法と結果の評価 128
6.1.3 CV測定による触媒劣化の診断 130
6.2 分極分離手法 132
6.2.1 活性化分極,拡散分極,抵抗分極 132
6.2.2 O2ゲイン特性評価 137
6.2.3 分極分離手法の適用 138
6.2.4 分極分離手法の適応例 140
6.3 交流インピーダンス測定法 141
6.3.1 コールコールプロツトの代表例とセル電圧特性 144
6.3.2 分極分離と交流インピーダンス測定結果との関係 150
6.3.3 触媒層内のイオン伝導度の測定 150
6.4 ガスリーク測定法 157
6.5 湿度測定法 160
6.6 セル内水分分布測定法 163
6.7 参照電力によるカソード・アノード電位測定法 165
6.8 可視光・赤外線によるセル内酸素濃度測定法 166
6.9 MRIによる膜内水分測定法 168
6.10 サーモグラフィーによるセル内温度分布の測定法 169
6.11 膜内抵抗分布測定による水分分布の推定 170
6.12 ガス流路可視化と電流分布測定法 171
6.13 セル内の水蒸気,酸素および水素分圧測定法 175
第7章 加速試験方法 180
7.1 要素レベルの加速試験 180
7.1.1 触媒劣化の加速試験 180
7.1.2 膜劣化の加速試験 182
7.1.3 炭素基盤(GDL)劣化の加速試験 186
7.2 ショートスタックを用いた加速試験 187
7.2.1 カーボン腐食を模擬した加速試験方法 187
7.2.2 アノード触媒劣化加速試験 188
7.3 実セルレベルの加速寿命試験 189
第8章 PEFCの適用(自動車用と家庭用燃料電池) 196
8.1 自動車への適用 196
8.1.1 燃料電池自動車の開発経過 196
8.1.2 燃料電池自動車のシステム 199
8.1.3 燃料電池車の実証試験 200
8.1.4 燃料電池の技術的課題 203
8.1.5 今後の展開 205
8.2 家庭用燃料電池 206
8.2.1 家庭用燃料電池システムの構成 206
8.2.2 エネルギー需要と運転方法 208
8.2.3 大規模実証試験 209
8.2.4 技術課題 212
8.2.5 CO2削減効果と普及シナリオ 214
付録 216
索引 219
第1章 資源の枯渇と地球温暖化問題 1
1.1 エネルギーの流れ 1
1.2 発電構成 2
72.
図書
小田喜代重著
出版情報:
[東京] : 東京図書出版 , 東京 : リフレ出版 (発売), 2018.10 108p ; 22cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
自己紹介
天動説と地動説
教授との対話
エネルギー保存の法則から
時間と質量の法則 / 1
家族との会話 / 1
チョッと休憩time / 1
時間と質量の法則 / 2
チョッと休憩time / 2
家族との会話 / 2
速度とエネルギー
まとめの講義
チョッと休憩time : 3)歴物然自
チョッと休憩time(4
家族との会話 / 3
最後の授業
未来に向けて
73.
図書
東工大
内田治著
出版情報:
東京 : 東京図書, 2010.4 x, 213p ; 21cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
はじめに
第1章 データの要約と視覚化 1
Section1 統計量によるデータの要約 2
1-1 基本統計量による要約 2
1-2 パーセント点による要約 11
Section2 グラフによるデータの視覚化 14
2-1 ヒストグラム 14
2-2 幹葉図 19
2-3 箱ひげ図 21
2-4 ドットプロット 23
第2章 平均値に関する解析 27
Section1 母平均に関する検定と推定 28
1-1 母標準偏差が既知のときの検定と推定 28
1-2 母標準偏差が未知のときの検定と推定 37
Section2 母平均の差に関する検定と推定 43
2-1 2つの母平均の差の検定と推定 43
2-2 対応のあるデータの母平均の差の検定と推定 54
第3章 分散に関する解析 59
Section1 母分散に関する検定と推定 60
1-1 母分散に関する検定 60
1-2 母分散に関する推定 66
Section2 母分散の比に関する検定と推定 68
2-1 母分散の比に関する検定 68
2-2 母分散の比に関する推定 74
第4章 相関分析 77
Section1 相関関係の把握 78
1-1 散布図による視覚的把握 78
1-2 相関係数による数値的把握 85
Section2 母相関係数に関する検定と推定 89
2-1 母相関係数の検定 89
2-2 母相関係数の推定 94
第5章 回帰分析 97
Section1 直接回帰 98
1-1 回帰式の算出 98
1-2 回帰式の吟味 103
Section2 多項式回帰 116
2-1 多項式の算出 116
2-2 多項式の吟味 119
第6章 比率に関する解析 127
Section1 母比率に関する検定と推定 128
1-1 直接確率計算による母比率に関する検定 128
1-2 母比率に関する推定 134
Section2 母比率の差に関する検定と推定 137
2-1 母比率の差に関する検定 137
2-2 母比率の差に関する推定 142
第7章 分割表に関する解析 145
Section1 分割表とグラフ表現 146
1-1 分割表とは 146
1-2 グラフによる分割表の視覚化 155
Section2 分割表の検定 165
2-1 2×2分割表の検定 165
2-2 m×n分割表の検定 170
付録 統計処理に使えるEXCELの関数 177
付録1 Rのダウンロードとインストール 178
付録2 R関連の便利ツール 185
付録3 データの入力形式とグラフの作成 193
付録4 ExcelとRの統計関数 202
付録5 フリーの表計算ソフト 204
参考文献 209
索引 210
はじめに
第1章 データの要約と視覚化 1
Section1 統計量によるデータの要約 2
74.
図書
名和小太郎著
75.
図書
quakebook.org編
出版情報:
東京 : 語研, 2011.6 165p ; 21cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
76.
図書
国書日本語学校編
出版情報:
東京 : 国書刊行会, 2010.2 151p ; 26cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
77.
図書
奥村晴彦著
出版情報:
東京 : 技術評論社, 2010.8 xiii, 433p ; 23cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
78.
図書
加納千恵子 [ほか] 著
出版情報:
東京 : 凡人社, 2014.6 xiii, 387p ; 26cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
79.
図書
Educational Testing Service著
出版情報:
東京 : 国際ビジネスコミュニケーション協会, 2016.10- 冊 ; 27cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
TOEIC Listening &
Reading Testについて
本書の構成と使い方
サンプル問題 : 写真描写問題
応答問題
会話問題
説明文問題
短文穴埋め問題
長文穴埋め問題
読解問題
採点・結果について
Reading公開テストのお申し込み・お問い合わせ
TEST
TEST 1
TEST : 2
TOEIC Listening &
TOEIC Listening &
Reading Testについて
本書の構成と使い方
概要:
テスト2回分(計400問)を収録。解答、解説、和訳、音声スクリプト掲載。公式ナレーターによる音声CD付き。参考スコア範囲換算表付き。<br />テスト2回分(計400問)を収録。解答、解説、和訳、音声スクリプト掲載。公式スピーカーによる音声
…
CD付き。参考スコア範囲換算表付き。<br />テスト2回分(計400問)を収録。解答、解説、和訳、音声スクリプト掲載。公式スピーカーによる音声CD付き(音声ダウンロード可)。参考スコア範囲換算表付き。<br />テスト2回分(計400問)を収録。解答、解説、和訳、音声スクリプト掲載。公式スピーカーによる音声CD付き。音声ダウンロード可(特典付き)。参考スコア範囲換算表付き。
続きを見る
80.
図書
東工大
角田光雄監修
目次情報:
続きを見る
第1章 防汚技術の基礎(角田光雄)
1. 汚れるということ 1
1.1 汚染のモデル 1
1.2 種々な例について 2
1.2.1 気相からの汚染の例 2
1.2.2 液相からの汚染の例 11
1.2.3 固相中からの汚染の例 15
1.3 気体の吸着に関する基礎(気相からの汚染に関して) 20
1.4 吸着等温線 21
第2章 光触媒技術を応用した防汚技術
1. 光触媒の機能と材料(佐伯義光) 27
1.1 はじめに 27
1.2 光触媒の原理と機能 28
1.3 実用化のための機能設計とハイブリット化 29
1.3.1 シリカ・シリコーン系蓄水性物質の添加 30
1.3.2 Cu,Agなどの遷移金属の添加 30
1.3.3 光触媒の複合化(TiO2/WO3) 30
1.4 光触媒の薄膜形成技術 32
1.5 光触媒の応用製品開発 32
1.6 おわりに 33
2. 加工技術(髙濱孝一) 34
2.1 はじめに 34
2.2 無機コーティング材 34
2.3 光触媒コーティング材 34
2.4 光触媒コーティング材のセルフクリーニング効果 38
2.5 光触媒コーティング材の実例 39
2.6 光触媒コーティング材の課題とその対策 41
2.7 まとめ 42
3. 抗菌効果とその評価方法(砂田香矢乃,橋本和仁) 44
3.1 はじめに 44
3.2 光触媒による抗菌効果 44
3.3 抗菌効果の評価方法 45
3.3.1 抗菌評価の対象サンプル作製 46
3.3.2 評価方法 46
3.3.3 評価結果 46
3.4 抗菌効果のメカニズム 48
3.4.1 スフェロプラストの酸化チタン薄膜上での生存率変化 48
3.4.2 細胞壁構成成分の濃度変化 49
3.4.3 殺菌過程 50
3.5 微弱光下での抗菌効果 51
3.5.1 酸化チタン薄膜と銅を組み合わせた材料の作製 51
3.5.2 暗所下での抗菌活性 51
3.5.3 微弱光(蛍光灯)下での抗菌活性 51
3.5.4 Cu/TiO2材料の抗菌メカニズム 53
3.6 おわりに 53
4. 光触媒の実用化例 55
4.1 光触媒の実用化技術とその応用例(佐伯義光) 55
4.1.1 はじめに 55
4.1.2 光触媒の基本作用と防汚機能 55
4.1.3 実用化のための機能設計とハイブリット化 56
4.1.4 光触媒の薄膜形成技術 57
4.1.5 光触媒の応用製品開発 58
4.1.6 おわりに 63
4.2 照明機器(石崎有義) 65
4.2.1 はじめに 65
4.2.2 照明製品の汚れ 65
4.2.3 照明製品用光触媒膜の種類と構造 66
4.2.4 光触媒応用照明製品の例 67
4.2.5 光触媒を励起する屋内光について 71
4.2.6 励起用照明ランプ,器具 72
4.2.7 まとめ 73
4.3 空気清浄(山下貢) 75
4.3.1 はじめに 75
4.3.2 さまざまな空気汚染物質 75
4.3.3 ガス状汚染物質と光触媒技術 76
4.3.4 生物系汚染物質と光触媒技術 83
4.4 外壁ガラスの現場コーティング技術(加藤大二郎) 89
4.4.1 はじめに 89
4.4.2 外壁ガラスの現場施工現況 89
4.4.3 光触媒コーティングガラスの防汚効果メカニズム 90
4.4.4 現場ガラスコート施工仕様 91
4.4.5 おわりに 97
第3章 高分子材料によるコーティング技術
1. アクリルシリコン樹脂(松尾陽一,園田健) 99
1.1 はじめに 99
1.2 低汚染性の考え方 99
1.2.1 汚染の認識 99
1.2.2 汚染物質 100
1.2.3 汚染のメカニズム 100
1.2.4 低汚染性付与技術 101
1.2.5 分析 102
1.3 低汚染弱溶剤ハイブリッド架橋型アクリルシリコン樹脂 105
1.3.1 架橋形態 105
1.3.2 主剤および硬化剤の設計 105
1.3.3 低汚染弱溶剤ハイブリッド架橋型アクリルシリコン樹脂塗料の塗膜性能 106
1.4 水系2液低汚染型アクリルシリコン樹脂 109
1.4.1 主材および硬化剤の設計 110
1.4.2 塗料化配合 111
1.4.3 光沢 111
1.4.4 接触角 113
1.4.5 屋外曝露試験での耐汚染性 113
1.4.6 耐候性 114
1.5 まとめ 115
2. フッ素材料(森田正道) 117
2.1 はじめに 117
2.2 実験 118
2.2.1 試料 118
2.2.2 ポリマーの布への処理 119
2.2.3 SR性試験 120
2.2.4 表面自由エネルギーの算出 120
2.2.5 撥油性 121
2.3 結果および考察 121
2.3.1 残存CB量と残存TO量の関係 121
2.3.2 低表面自由エネルギー性とSR性能の関係 122
2.3.3 CB/TO複合汚れの洗浄過程 124
2.3.4 FAホモポリマーのSR性能 124
2.3.5 flip-flop性とSR性能の関係 125
2.3.6 FA/BA共重合体,FA/BMA共重合体のSR性能 127
2.3.7 処理を施す基質が異なる場合 128
2.3.8 複合汚れ中の油性成分の極性が異なる場合 129
2.4 総括 131
第4章 帯電防止技術の応用
1. 帯電防止(村田雄司) 133
1.1 はじめに 133
1.2 静電気の発生 133
1.2.1 静電気の発生原因 133
1.2.2 接触・摩擦帯電現象 134
1.3 帯電防止 136
1.3.1 帯電防止の基本原理 136
1.3.2 帯電しにくい材料 136
1.3.3 導電化による帯電防止 139
1.3.4 微弱放電を利用した帯電防止 143
1.4 おわりに 143
2. 帯電防止による防汚コーティング技術に代わる新しい技術の動向(板野俊明) 146
2.1 はじめに 146
2.2 帯電防止塗料 146
2.3 最近のクリーンルーム用塗料 147
3. 粒子汚染への静電気の影響と制電技術(稲葉仁) 152
3.1 はじめに 152
3.2 粒子汚染を促進する作用力の特性 152
3.3 帯電清浄面への粒子付着の実態 153
3.4 粒子汚染防止のための制電技術 157
3.4.1 制電技術基礎 157
3.4.2 帯電列を指標とした素材の選定の有効性 158
3.4.3 加湿による抵抗値制御の有効性 159
3.4.4 有機汚染制御による帯電防止 160
3.4.5 イオナイザの特徴と使用上の注意点 160
3.4.6 空気中での高速除電技術“極軟X線(USX)除電装置”の特徴と適用例 166
3.4.7 減圧雰囲気での除電技術“真空紫外線(VUV)除電装置”の特徴 170
3.4.8 除電に利用されるイオンの組成と清浄面への影響 172
3.5 まとめ 173
4. クリーンルーム内における静電気(藤江明雄) 175
4.1 はじめに 175
4.2 電子産業分野における静電気課題概要 175
4.2.1 クリーンルーム内での発麈の課題 175
4.2.2 クリーンルーム内での微粒子吸着の過程 176
4.2.3 粒子付着の色々な形態 178
4.3 静電気課題への対応の基本 180
4.4 クリーンルーム内の製造工程で遭遇する静電気発生機構と工程 180
4.5 クリーンルーム内空気のイオンバランス異常 181
4.6 洗浄システムにおける静電気 183
4.6.1 高絶縁材料製配管へ乾燥空気流入時の流動帯電 184
4.6.2 洗浄システム内の電気絶縁性配管と純水の帯電 185
4.7 電子産業分野における静電気課題の対応現況 188
4.7.1 半導体分野での静電気課題 188
4.7.2 HDD分野 189
4.7.3 LCDパネル分野 190
4.8 おわりに 190
第5章 実際の応用例
1. 半導体工場のケミカル汚染対策(平田順太) 193
1.1 はじめに 193
1.2 ケミカル汚染対象物質とクリーンルーム内外の濃度 193
1.3 有機汚染対策 194
1.3.1 揮発性有機物のSiウェーハへの吸脱着挙動 195
1.3.2 各種部材からのアウトガス測定法と測定事例 196
1.3.3 有機汚染対策 198
1.4 酸汚染対策 200
1.5 塩基性ガス汚染対策 201
1.6 ドーパント汚染対策 202
1.7 おわりに 203
2. 抗菌性プラスチック材料の複雑表面被覆(入倉鋼) 204
2.1 一般的な抗菌性プラスチックの被覆方法 204
2.2 複雑形状へのプラスチック被覆方法 204
2.3 抗菌性ポリイミドの成膜 205
2.4 抗菌性能 207
2.5 応用例 209
3. 半導体プロセスにおける防汚技術(久禮得男,鈴木道夫) 210
3.1 はじめに 210
3.2 半導体プロセスの概要と汚染 210
3.3 半導体プロセスにおける防汚の取組み 213
3.4 クリーンルームにおける防汚技術 215
3.4.1 粒子汚染の挙動と対策 215
3.4.2 分子汚染(ケミカル汚染)の挙動と対策 219
3.4.3 金属汚染の挙動と対策 221
3.4.4 局所清浄化 224
3.5 洗浄技術 225
4. 超精密ウェーハ表面加工における防汚(服部毅) 228
4.1 半導体ウェーハ表面のクリーン化 228
4.2 ウェーハ表面加工プロセスにおける汚染防止 229
4.3 半導体ウェーハの洗浄による汚染除去 233
4.4 多層配線工程での汚染除去(最近のトピックスとして) 238
4.4.1 ポリマー除去 240
4.4.2 ポストCMP洗浄 241
4.4.3 裏面ベベル洗浄 241
4.5 おわりに 241
5. 光触媒による環境浄化技術(仙波裕隆) 243
5.1 はじめに 243
5.2 光触媒とは 243
5.2.1 光触媒機構 243
5.2.2 光触媒の用途 244
5.3 大気浄化への適用例 245
5.3.1 製品設計 245
5.3.2 NOx除去機構 246
5.3.3 NOx除去性能 247
5.4 応用例 249
5.4.1 STコート 249
5.4.2 フォトロード工法 253
5.5 今後の展望 256
5.5.1 JIS化 256
5.5.2 STコートの展開 256
6. 機械加工分野(間宮富士雄) 258
6.1 はじめに 258
6.2 工作機械の種類 258
6.2.1 施盤(Lathe) 258
6.2.2 ボール盤(Drilling Machine) 258
6.2.3 中ぐり盤(Boring Machine) 258
6.2.4 フライス盤(Milling Machine) 258
6.2.5 その他の機械 259
6.3 コンタミネーション・コントロール 259
6.3.1 液体清浄度測定法 260
6.3.2 空気清浄度測定法 260
6.3.3 個体表面清浄度測定法 260
6.4 工作機械の保守・点検 260
6.5 欠陥の種類とその対策 264
6.5.1 腐食(コロージョン) 264
6.5.2 よごれ 264
6.5.3 漏れ 265
6.5.4 その他 266
第1章 防汚技術の基礎(角田光雄)
1. 汚れるということ 1
1.1 汚染のモデル 1
81.
図書
東工大
松原望著
出版情報:
東京 : 東京図書, 2011.10 vii, 207p ; 24cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第1章 確率の意味 1
1-1 確率ってなに? 2
1-2 順列と組み合わせ 4
1-2-1 順列とは 4
1-2-2 組み合わせとは 5
1-2-3 組み合わせの計算ルール 7
1-2-4 順列の計算ルール 8
1-2-5 かんたんな確率の計算 9
1-3 集合 11
1-3-1 集合とは 11
1-3-2 集合の演算 12
1-3-3 部分集合 16
1-4 事象と確率空間 18
1-4-1 確率空間 18
1-4-2 事象 20
1-4-3 事象の確率 21
コラム 「お話にならない」話…「計算した結果」でなければ,「確率」でない? 23
1-5 確率のたし算・ひき算 24
1-5-1 確率のひき算 25
1-5-2 確率のたし算?! 269
1-5-3 すべての事象が起きる確率 27
1-5-4 排反な事象と確率の和 29
1-6 確率のかけ算・わり算―条件付き確率とベイズの定理 30
1-6-1 確率のかけ算 30
1-6-2 確率のわり算―条件付き確率 32
1-6-3 ベイズの定理 36
第2章 確率変数と確率分布 43
2-1 確率変数,それから,確率分布 44
2-1-1 確率変数とは 45
2-1-2 確率分布とは 47
2-2 期待値と標準偏差 49
2-2-1 期待値とは 49
2-2-2 総和を表わす記号∑ 52
2-2-3 期待値の性質 53
2-2-4 分散と標準偏差 57
2-2-5 分散の性質 61
2-3 いろいろな確率分布 64
2-4 二項分布とポアソン分布 66
2-4-1 ベルヌーイ試行 66
2-4-2 二項定理と二項分布 67
2-4-3 二項定理の期待値と分散の出し方 70
2-4-4 ポアソン分布とはどういうものか 73
2-4-5 ポアソン分布と二項分布 76
2-4-6 ポアソン分布の期待値と分散 80
2-5 正規分布 83
2-5-1 正規分布の有用性 83
2-5-2 コイン投げと正規分布 84
2-5-3 離散型分布と連続型分布 90
2-6 中心極限定理と大数の法則 94
2-6-1 中心極限定理 94
2-6-2 大数の法則 101
コラム 指数関数超入門 105
第3章 確率過程(1) ランダム・ウォーク,待ち行列,マルコフ過程 117
3-1 ランダム・ウォーク 118
3-1-1 単純ランダム・ウォーク 118
3-1-2 単純ランダム・ウォークのモデル 119
3-1-3 単純ランダム・ウォークのシミュレーション 121
3-1-4 単純ランダム・ウォークの期待値と分散 123
3-1-5 ギャンブラーの破産問題 126
3-2 待ち行列 133
3-2-1 幾何分布 135
3-2-2 指数分布 140
3-2-3 ATMの待ち行列 142
3-3 マルコフ過程 147
3-3-1 マルコフ過程とマルコフ性 147
3-3-2 条件付き確率と推移確率 149
3-3-3 嘘つきのマルコフ過程 150
3-3-4 行列のn乗と固有値 153
3-3-5 遺伝学からのモデル 160
第4章 確率過程(2) ブラウン運動,伊藤の補題,ブラック=ショールズ方程式 163
4-1 ランダム・ウォークからブラウン運動へ 164
4-1-1 離散時間から連続時間へ 164
4-1-2 ドリフト係数とゆらぎ係数 165
4-2 微分積分ミニマム・エッセンス 167
4-2-1 微分積分のスピリット 167
4-2-2 微分の具体的な手続き 169
4-2-3 2階微分からテイラー展開へ 170
4-2-4 2変数の場合の近似式 173
4-2-5 微分積分学の基本定理 174
4-3 伊藤の補題 176
4-3-1 ブラウン運動の微分 176
4-3-2 幾何ブラウン運動 177
4-3-3 伊藤の補題,登場 178
4-4 ブラック=ショールズ方程式への案内 179
4-4-1 確率微分方程式 179
4-4-2 コール・オプション 181
4-4-3 ブラック=ショールズ方程式の導出 182
4-5 ブラック=ショールズ方程式を解き明かす 185
4-6 プット・オプション 191
コラム 株価デリバティブからリアル・オプションへ―基礎知識ミニマム・エッセンス 195
参考文献 202
標準正規分布表 203
索引 204
第1章 確率の意味 1
1-1 確率ってなに? 2
1-2 順列と組み合わせ 4
82.
図書
東工大
越田信義監修
出版情報:
東京 : シーエムシー出版, 2010.6 vi, 245p ; 27cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
序章 ナノシリコン応用の最新動向(越田信義)
1. はじめに 1
2. ナノシリコンの形成と機能 2
3. 表面終端制御の重要性 4
4. 可視発光とフォトニック応用 5
5. 弾道電子放出 7
6. 熱誘起超音波発生 7
7. 生体との適合性 8
8. まとめ 9
第1章 フォトニクス
1. シリコンフォトニクス(和田一実) 11
1.1 はじめに 11
1.2 素子研究の現状 12
1.3 ITへの応用 14
1.4 終わりにかえて 15
2. シリコンフォトニック結晶(冨士田誠之,野田進) 18
2.1 はじめに 18
2.2 シリコンフォトニック結晶からの発光現象 19
2.3 シリコン光ナノ共振器からの発光現象 21
2.4 おわりに 25
3. ナノシリコン発光材料・デバイス(B.Gelloz,小山英樹) 27
3.1 はじめに 27
3.2 Siナノ結晶材料の作製 27
3.2.1 ポーラスシリコンの作製法と構造 27
3.2.2 その他のSiナノ結晶材料 27
3.3 フォトルミネッセンス 28
3.3.1 S発光の特性 28
3.3.2 酸化に起因した青色発光 29
3.3.3 発光効率の改善 29
3.3.4 PLの安定化 31
3.4 エレクトロルミネッセンス 32
3.4.1 PSiのEL 32
3.4.2 その他のSiナノ結晶材料のEL 33
3.5 興味深い現象と応用 33
3.5.1 負性抵抗効果と不揮発性メモリー効果 33
3.5.2 PLを利用したセンサーとイメージング 33
3.5.3 光学異方性 33
3.5.4 レーザー色素とのコンポジット材料 34
3.6 まとめ 35
4. シリコン量子構造の光増幅(諏訪雄二,斎藤慎一) 38
4.1 シリコン発光と光吸収 38
4.2 シリコン発光素子の光増幅実験 39
4.3 シリコン(001)薄膜の光増幅 41
4.4 まとめ 45
5. ナノ構造シリコンの光導電(平野喜之) 47
5.1 はじめに 47
5.2 ナノ構造シリコンで期待される光導電特性 48
5.3 ナノ構造シリコン光導電膜の作製方法 49
5.4 ナノ構造シリコンの光導電特性 51
5.5 おわりに 54
6. シングルフォトン検出(田部道晴,Moraru Daniel Ioan) 56
6.1 はじめに 56
6.2 量子構造フォトン検出器(化合物半導体の例) 57
6.2.1 量子ドット型フォトン検出器 57
6.2.2 量子ポイントコンタクト型フォトン検出器 58
6.3 量子構造Si系フォトン検出器 58
6.3.1 Si単電子トランジスタによるフォトン吸収の効果 58
6.3.2 Si多重接合単電子(単正孔)トランジスタによるフォトン検出 59
6.3.3 単電子フォトン位置検出器 63
6.3.4 赤外線検出器 63
7. ナノシリコンの光増感作用(藤井稔) 66
7.1 はじめに 66
7.2 ナノシリコンの酸素分子に対する光増感作用(一重項酸素の生成) 66
7.3 ナノシリコンの希土類イオンに対する光増感作用 69
第2章 エレクトロニクス
1. キャリア輸送(森伸也) 74
1.1 はじめに 74
1.2 キャリア輸送の基礎 74
1.2.1 電子状態 74
1.2.2 散乱機構 75
1.3 ナノシリコン列のキャリア輸送 77
1.3.1 ナノシリコン列 77
1.3.2 電子状態 77
1.3.3 散乱機構 78
1.3.4 準弾道電子輸送 79
2. 単電子デバイス(高橋庸夫) 82
2.1 はじめに 82
2.2 単電子トランジスタ(SET)の動作原理 83
2.3 単電子デバイスの特徴 84
2.4 単電子デバイスの作製方法 85
2.5 単電子デバイスの応用 87
2.5.1 SETを用いた論理機能応用 87
2.5.2 電子1個を用いた応用 88
2.6 まとめ 90
3. 強磁性ホイスラー合金の原子層制御エピタキシャル成長とSiGeスピントロニクス(安藤裕一郎,宮尾正信) 93
3.1 はじめに 93
3.2 強磁性シリサイドの原子層制御エピタキシャル成長 94
3.3 ショットキー障壁の制御とスピン注入 97
3.4 混晶エンジニアリングによるハーフメタル材料の創成 98
3.5 おわりに 99
4. ナノCMOSデバイス(内田建) 102
4.1 はじめに 102
4.2 (100)および(110)バルクMOSトランジスタ 102
4.2.1 (110)MOSトランジスタ 102
4.2.2 (100)/(110)MOSトランジスタにおける歪み技術 103
4.3 3次元構造トランジスタ 105
4.4 まとめ 106
5. NEMSとナノデバイス(水田博,土屋良重) 108
5.1 技術的な背景 108
5.2 サスペンデッドゲートFET(SGFET) 109
5.3 高速・不揮発性NEMSメモリ 112
5.4 NEM-MOSハイブリッドセンサー 116
5.5 NEMSハイブリッドデバイスの微細化と将来展望 118
6. トンネルデバイス(須田良幸) 122
6.1 トンネルデバイスの基本構造と動作原理 122
6.2 Si/Ge系のバンドエンジニアリング 124
6.3 Type IIヘテロ構造のための歪緩和 127
6.4 Si系ITD,RTD,RITD 128
7. 弾道電子エミッタによる並列EBリソグラフィ(小島明,大井英之) 134
7.1 一括電子線露光開発の背景 134
7.2 ナノシリコンと弾道電子 135
7.3 シリコンナノワイヤアレイ弾道電子エミッタについて 136
7.4 弾道電子面放出素子による一括電子線露光方式の概要 136
7.5 パターン化されたナノシリコン弾道電子面放出素子の作製 139
7.6 弾道電子面放出素子の放出電子速度分布特性 141
7.7 一括露光実験の結果 142
7.8 結論 143
8. 弾道電子エミッタの気体中動作による真空紫外光発生(櫟原勉) 145
8.1 はじめに 145
8.2 弾道電子エミッタ 145
8.2.1 作製方法 145
8.2.2 弾道電子エミッタの特徴 146
8.2.3 ナノ構造解析 147
8.3 弾道電子エミッタの直接励起発光デバイスへの応用 147
8.3.1 真空紫外光の測定 147
8.3.2 直接励起発光 148
8.3.3 平面光源の試作 150
8.4 まとめ 151
9. 弾道電子エミッタの超高感度撮像への応用(根岸伸安) 152
9.1 はじめに 152
9.2 冷陰極HARP撮像板 152
9.3 撮像用エミッタアレイの要件 153
9.4 撮像用弾道電子エミッタアレイ Active-matrix HEED 154
9.5 HEED冷陰極HARP撮像板 156
9.6 まとめ 158
10. ナノシリコン電子源の水溶液中動作(太田敢行,越田信義) 160
10.1 はじめに 160
10.2 水溶液中における動作特性 161
10.3 むすび 163
第3章 アコースティクス
1. 熱誘起超音波発生(越田信義) 166
1.1 はじめに 166
1.2 動作原理 166
1.2.1 nc-PS層の熱的性質 166
1.2.2 動作機構と特徴 167
1.3 デバイスの作製と基礎特性 169
1.3.1 基本プロセスと素子構成 169
1.3.2 素子の駆動と音響出力の基本特性 170
1.3.3 温度上昇の高速性と一様性 172
1.3.4 指向性 173
1.3.5 長期安定性 174
1.4 応用開発に関わる特性 175
1.4.1 放射圧力の発生 175
1.4.2 超音波信号の再生能力 175
1.4.3 デジタル駆動への適合性 176
1.5 むすび 177
2. 超音波素子応用(渡部祥文) 180
2.1 はじめに 180
2.2 2層ポーラスシリコン構造による超音波発生の経時特性向上 180
2.3 空中3次元超音波センサ 183
2.4 超音波デジタル情報伝送の試み 185
2.5 おわりに 188
第4章 バイオ応用
1. タンパク質分析用基板(木原隆) 189
1.1 はじめに 189
1.2 DIOSの評価 191
1.2.1 DIOSとは 191
1.2.2 DIOSプレートによる質量分析 192
1.2.3 DIOS評価からの課題 193
1.3 nc-Siプレートの評価 193
1.3.1 nc-Siプレートとは 193
1.3.2 nc-Siプレートによる質量分析 194
1.4 まとめと今後の課題 195
2. 生体適合性と応用可能性(佐藤慶介) 198
2.1 はじめに 198
2.2 シリコンナノ粒子分散溶液の製造とその諸特性 201
2.2.1 シリコンナノ粒子分散溶液の製造方法 201
2.2.2 粒子表面状態 203
2.2.3 溶液内における粒子分散性 203
2.2.4 粒子サイズと光学的特性の相関 204
2.3 癌細胞ラベリングしたシリコンナノ粒子の毒性試験とイメージング特性 206
2.3.1 シリコンナノ粒子による癌細胞へのラベリング方法 207
2.3.2 細胞毒性試験 207
2.3.3 癌細胞イメージング特性 208
2.4 シリコンナノ粒子による生体内でのイメージング特性 208
2.4.1 生体内イメージング特性 209
2.5 おわりに 211
第5章 プロセス技術
1. プラズマ技術によるナノシリコンドットの作製(小田俊理) 213
1.1 はじめに 213
1.2 ナノシリコンドット作製の課題 213
1.3 VHFプラズマセルによるナノシリコンドットの作製 214
1.4 ナノシリコン界面の制御 216
1.5 ナノシリコンの集積配列・位置制御 217
1.5.1 グローバル集積配列 217
1.5.2 ローカル位置制御 220
1.6 まとめ 220
2. ナノシリコン構造形成SPM技術(白樫淳一) 222
2.1 はじめに 222
2.2 SPM局所酸化ナノリソグラフィー法 222
2.2.1 動的探針制御手法によるSPM局所酸化ナノリソグラフィー 222
2.2.2 10nm以下級SPM局所酸化ナノリソグラフィー 224
2.2.3 SPM局所酸化ナノリソグラフィーにおける酸化反応モデル 225
2.3 SPMスクラッチナノリソグラフィー法 229
2.3.1 20nm以下級SPMスクラッチナノリソグラフィー 229
2.3.2 SPMスクラッチナノリソグラフィーでの制御パラメータと加工痕サイズの関係 230
2.3.3 SPMスクラッチナノリソグラフィーにおける摩耗係数の評価とナノスケール構造体の作製 232
2.4 まとめ 233
3. シリコンナノワイヤ・チェインの作製技術(竹田精治,河野日出夫) 236
3.1 はじめに 236
3.2 金属ナノ粒子を利用した自己形成 236
3.3 シリコンナノワイヤ 237
3.3.1 水素終端面を利用する成長法 237
3.3.2 シリコンナノワイヤ成長の活性化エネルギー 239
3.4 シリコンナノチェイン 240
3.4.1 構造 240
3.4.2 生成の方法と機構 240
3.4.3 テンプレートとしてのシリコンナノチェイン 242
3.5 おわりに 244
序章 ナノシリコン応用の最新動向(越田信義)
1. はじめに 1
2. ナノシリコンの形成と機能 2
83.
図書
東工大
JST CREST日比チーム編
出版情報:
東京 : 共立出版, 2011.9 xii, 557p ; 22cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第1章 グレブナー基底の伊呂波 日比孝之 1
1.1 多項式環 2
1.1.1 単項式と多項式 2
1.1.2 Dicksonの補題 3
1.1.3 イデアル 5
1.1.4 単項式順序 9
1.1.5 グレブナー基底 12
1.1.6 Hilbert基底定理 13
1.2 割り算アルゴリズム 16
1.2.1 割り算アルゴリズム 16
1.2.2 被約グレブナー基底 20
1.3 Buchberger判定法とBuchbergerアルゴリズム 21
1.3.1 S多項式 22
1.3.2 Buchberger判定法 23
1.3.3 Buchbergerアルゴリズム 29
1.4 消去理論 33
1.4.1 消去定理 33
1.4.2 連立方程式の解法 37
1.5 トーリックイデアル 41
1.5.1 配置行列 42
1.5.2 二項式イデアル 42
1.5.3 トーリックイデアル 43
1.5.4 トーリック環 45
1.6 多項式環の剰余環とHilbert函数 50
1.6.1 剰余類と剰余環 50
1.6.2 Macaulayの定理 56
1.6.3 Hilbert函数 57
1.7 歴史的背景 61
参考文献 65
第2章 数学ソフトウェア受身稽古 清田龍義 68
2.1 KNOPPIX/Mathの利用 69
2.1.1 KNOPPIX/Mathの取得と作成 69
2.1.2 KNOPPIX/Mathの起動と終了 69
2.1.3 数学ソフトウェア関連について 70
2.2 ファイル操作 : PCManファイルマネージャの利用 71
2.2.1 新規フォルダの作成 73
2.2.2 新規テキストファイル 73
2.3 端末の利用 74
2.3.1 ファイルー覧,ディレクトリの作成,移動 75
2.3.2 テキストファイルの表示 77
2.3.3 入出力の切り替え 78
2.3.4 文字コードの変換 79
2.3.5 nkf:Network Kanji Filter 82
2.4 数学ドキュメントの作成 85
2.4.1 TEXソースコードの作成 85
2.4.2 DVIファイルの作成 86
2.4.3 PDFファイルの作成 88
2.4.4 TEXソースコードの解説 88
2.4.5 数式の入力 89
2.4.6 TEXに画像を入れる 91
2.5 様々な数学ソフトウェア 92
2.5.1 動的幾何学ソフトウェアKSEG 93
2.5.2 動的数学ソフトウェアGeoGebra 99
2.5.3 実代数幾何学のための可視化surfファミリー 106
2.5.4 汎用数式処理システムMaxima 108
2.5.5 統計処理ソフトR 112
2.6 テキストエディタの活用 : Emacs入門 113
2.6.1 Emacsの起動 113
2.6.2 テキストの削除,挿入 116
2.6.3 複数行の編集 117
2.6.4 削除ふたたび 120
2.6.5 ポイント/マーク/リージョン 120
2.6.6 編集操作のキャンセル 122
2.6.7 その他 122
2.6.8 日本語の取扱い 122
2.6.9 命令の実行,シェルの起動 123
2.6.10 数学ソフトウェア環境 124
2.7 仮想マシンの利用 124
2.7.1 種々の仮想マシン 125
2.8 USB-KNOPPIX/Mathの作成 126
2.8.1 f1ash-knoppixの起動 127
2.8.2 USBメモリーディスクの用意 127
2.8.3 USB起動KNOPPIXの作成手順 127
2.8.4 USBメモリーディスクからの起動 129
2.8.5 knoppix-data.imgの作成 129
2.8.6 USB-KNOPPIX/Mathへの追加 130
参考文献 130
第3章 グレブナー基底の計算法 野呂下行 132
3.1 この章の読み方 133
3.1.1 この章の構成 133
3.1.2 この章を読むための予備知識 133
3.2 Buchbergerアルゴリズムの効率化 134
3.2.1 不必要なペアの消去 136
3.2.2 ペアの選択方法 138
3.2.3 斉次化 139
3.2.4 Buchbergerアルゴリズム(改良された形) 140
3.3 数学ソフトウェアのためのソフトウェア環境 142
3.3.1 Linux 143
3.3.2 Windows 143
3.4 Macaulay2,SINGULAR,CoCoA上での計算 143
3.4.1 起動方法,へルプ,マニュアル 144
3.4.2 パッケージ,ライブラリの読み込み,ファイルの読み書き 147
3.4.3 基礎環の宣言,項順序と多項式の入力 149
3.4.4 グレブナー基底の計算 152
3.4.5 イニシャルイデアルの計算 155
3.4.6 商および剰余の計算 157
3.5 グレブナー基底を用いた種存のイデアル操作 160
3.5.1 消去順序 160
3.5.2 イデアルの和,積,共通部分 163
3.5.3 根基所属判定 164
3.5.4 イデアル商,saturation 166
3.5.5 根基計算 168
3.6 項順序変換 170
3.6.1 FGLM アルゴリズム 170
3.6.2 Hilbert drivenアルゴリズム 173
3.7 加群のグレブナー基底計算 174
3.7.1 多項式環上の自由加群における項順序 174
3.7.2 加群におけるBuchberger アルゴリズム 176
3.7.3 syzygyの計算 176
3.8 Risa/Asir上での計算 178
3.8.1 起動方法 178
3.8.2 へルプ,マニュアル 178
3.8.3 ファイルの読み書き 179
3.8.4 多項式の入力い 179
3.8.5 項順序 180
3.8.6 グレブナー基底の計算 181
3.8.7 イニシャルイデアルの計算 183
3.8.8 剰余計算 183
3.8.9 消去法 184
3.8.10 最小多項式の計算 184
3.8.11 0次元イデアルの項順序変換 185
3.8.12 イデアル演算 185
3.9 Macaulay2によるプログラミングの例 187
3.9.1 イデアルの準素分解 188
3.9.2 SYCIアルゴリズム 189
3.9.3 Macaulay2上での実装 191
3.10 章末問題 198
3.11 問題の略解 199
3.11.1 本文中の問題 199
3.11.2 章末問題 201
参考文献 202
第4章 マルコフ基底と実験計画法 青木敏・竹村彰通 204
4.1 分割表の条件付検定 205
4.1.1 十分統計量 205
4.1.2 2x2分割表 209
4.1.3 相似検定 217
4.1.4 I×J分割表 221
4.2 マルコフ基底 234
4.2.1 マルコフ基底 234
4.2.2 マルコフ基底の例 239
4.2.3 マルコフ基底とイデアル 244
4.3 実験計画法とマルコフ基底 249
4.3.1 2水準実験 249
4.3.2 組合せ配置データの解析 251
4.3.3 一部実施計画データの解析 261
4.4 研究課題 265
4.4.1 3元分割表の無3因子交互作用のマルコフ基底に関する話題 265
4.4.2 マルコフ基底の計算アルゴリズムとその改良に関する話題 266
4.4.3 実験計画データのモデリングに関する話題 268
参考文献 268
第5章 凸多面体とグレブナ 基底 大杉英史 271
5.1 凸多面体 272
5.1.1 凸多面体,凸多面錐 272
5.1.2 凸多面体の面 274
5.1.3 多面体的複体,扇 279
5.2 イニシャルイデアル 279
5.2.1 イニシャルイデアル 280
5.2.2 重みベクトルと単項式順序 280
5.2.3 普遍グレブナー基底 283
5.3 グレブナー扇とステイト多面体 284
5.3.1 単項イデアルのグレブナー扇 284
5.3.2 斉次イデアルのグレブナー扇とステイト多面体 287
5.4 トーリックイデアルのステイト多面体 294
5.4.1 サーキット集合とGraver基底 295
5.4.2 次数の上限 296
5.4.3 Lawrence持ち上げ 301
5.4.4 ステイト多面体の計算法 303
5.5 凸多面体の三角形分割とグレブナー基底 304
5.5.1 単模三角形分割 304
5.5.2 正則三角形分割 306
5.5.3 イニシャル複体 308
5.5.4 2次多面体とステイト多面体 314
5.6 配置行列にまつわる環論的性質と三角形分割 316
5.6.1 辞書式三角形分割と単模配置行列 316
5.6.2 逆辞書式三角形分割と圧搾配置行列 320
5.6.3 トーリック環の正規性 322
5.7 配置行列の例 325
5.7.1 有限グラフに付随する配置 325
5.7.2 分割表に付随する配置行列 328
参考文献 330
第6章 微分作用素環のグレブナー基底とその応用 高山信毅 332
6.1 有理式係数の微分作用素環Rにおけるグレブナー基底 333
6.2 Rの0次元イデアルとPfaffian方程式 340
6.3 Pfaffin方程式の解 343
6.4 ホロノミック関数 352
6.5 ホロノミック関数に対する勾配降下法 354
6.6 多項式係数の微分作用素環Dにおけるグレブナー基底 359
6.7 フィルター付けと重みベクトル 366
6.8 ホロノミック系 369
6.9 DとRの関係 372
6.10 積分アルゴリズム 374
6.11 積分で定義される関数の最小値問題 383
6.12 A-超幾何系 387
6.13 おわりに 399
参考文献 400
第7章 例題と解答 中山洋将・西山絢太 403
7.1 ソフトウェアに関する注意 404
7.2 マルコフ基底と実験計画法 : 例題と解答 405
7.2.1 分割表の条件付検定(41節) 405
7.2.2 マルコフ基底(4.2節) 408
7.2.3 実験計画法とマルコフ基底(4.3節) 424
7.3 凸多面体とグレブナー基底 : 例題と解答 429
7.3.1 凸多面体(5.1節) 429
7.3.2 イニシャルイデアル(5.2節) 440
7.3.3 グレブナー扇とステイト多面体(5.3節) 443
7.3.4 トーリックイデアルのステイト多面体(5.4節) 448
7.3.5 凸多面体の三角形分割とグレブナー基底(5.5節) 456
7.3.6 配置行列にまつわる環論的性質と三角形分割(5.6節) 469
7.3.7 配置行列の例(5.7節) 474
7.4 微分作用素環のグレブナー基底とその応用 : 例題と解答 480
7.4.1 Rにおけるグレブナー基底(6.1節) 481
7.4.2 Rの0次元イデアルとPね髄an方程式(6.2節) 496
7.4.3 Pfaffan方程式の解(63節) 503
7.4.4 ホロノミック関数(6.4節) 510
7.4.5 ホロノミック関数に対する勾配降下法(6.5節) 511
7.4.6 Dにおけるグレブナー基底(65節) 513
7.4.7 ホロノミック系(6.8節) 518
7.4.8 DとRの関係(69節) 523
7.4.9 積分アルゴリズム(610節) 526
7.4.10 積分で定義される関数の最小値問題(6.11節) 539
参考文献 543
索引 545
第1章 グレブナー基底の伊呂波 日比孝之 1
1.1 多項式環 2
1.1.1 単項式と多項式 2
84.
図書
総務省統計局編
85.
図書
東工大
佐藤功著
出版情報:
東京 : 森北出版, 2011.11 v, 129p ; 22cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
1章 プラスチックとは 1
1.1 プラスチックという言葉 1
1.2 高分子ということ 3
1.2.1 高分子とは 3
1.2.2 高分子の特徴 4
1.2.3 プラスチックの分子構造 5
1.3 なぜプラスチックは伸びたか 8
1.3.1 特性の良さ 8
1.3.2 原料のコストダウンと安定供給 10
1.3.3 旺盛な応用開発 11
1.3.4 加工業界の形成 12
1.3.5 まとめ 12
2章 優れた特性を実現させるさまざまな工夫 14
2.1 分子構造上の工夫 14
2.2 結晶化による工夫 17
2.2.1 結晶化制御 20
2.2.2 結晶化の役割 21
2.3 立体規則性による工夫 23
2.4 分岐,共重合の工夫 25
2.4.1 共重合 25
2.4.2 分枝 26
2.5 分子量,分子量分布の工夫 28
2.6 混合による工夫 29
2.6.1 ポリマーアロイ 30
2.6.2 無機系強化剤 31
2.6.3 可塑剤 32
2.6.4 その他の添加剤 33
2.7 延伸,配向による工夫 33
2.7.1 延伸 34
2.7.2 配向 36
3章 いろいろなプラスチック 38
3.1 プラスチックの種類と分類法 38
3.2 オレフィン系プラスチック 40
3.2.1 最も身近なプラスチック 40
3.2.2 物性を変えるもの 42
3.2.3 ポリオレフィンの用途と使い分け 45
3.2.4 特殊なポリオレフィン 48
3.3 スチレン系プラスチック 50
3.3.1 ポリスチレン 50
3.3.2 ポリスチレンの仲間 52
3.4 その他の汎用プラスチック 55
3.4.1 塩化ビニール 55
3.4.2 アクリル樹脂 58
3.5 汎用プラスチックのまとめ 59
3.6 エンジニアリングプラスチック 60
3.7 熱可塑性エラストマー 63
3.7.1 ゴムとプラスチック 63
3.7.2 ゴムのようなプラスチック 64
4章 プラスチックの特性と製品設計法 68
4.1 プラスチックの特性 68
4.1.1 変形挙動 68
4.1.2 温度特性 70
4.1.3 クリープと疲労 70
4.1.4 その他 71
4.2 プラスチック製品の設計法 75
4.2.1 材料力学の適用と限界 75
4.2.2 形状設計 76
5章 用途の広がり 81
5.1 さまざまな用途 81
5.1.1 プラスチック時代 81
5.1.2 電気製品 83
5.1.3 自動車部品 84
5.1.4 包装材料 85
5.1.5 産業資材 87
5.1.6 家庭用品 88
5.2 材料の選び方 89
5.2.1 材料選びの難しさ 89
5.2.2 材料選定法 89
6章 プラスチックの加工法 97
6.1 成形加工(一次加工) 97
6.1.1 さまざまな加工 97
6.1.2 押出成形 98
6.1.3 射出成形 101
6.1.4 中空物の成形 104
6.2 二次加工 106
6.2.1 二次加工の意義 106
6.2.2 賦形 106
6.2.3 組立て 107
6.2.4 表面装飾 110
6.2.5 改質 111
6.3 プロセス設計法 111
7章 プラスチックの課題 114
7.1 資源問題とプラスチック 114
7.1.1 問題と現状 114
7.1.2 問題の本質と考え方 114
7.2 環境問題とプラスチック 116
7.2.1 6 大地球環境問題 116
7.2.2 環境問題の多面的な性質 118
7.2.3 3Rと3E 119
7.2.4 技術者のスタンス 120
7.3 プラスチックの安全性 120
7.4 わが国のプラスチック産業の課題 122
7.4.1 産業構造の変化とわが国のプラスチック産業 122
7.4.2 消費者アプローチ 122
7.4.3 技術レベルの維持 123
さらにプラスチックを学ぶ人のための参考書 125
さくいん 126
COLUMN
1. 高分子論争 7
2. 日本型商品開発法 13
3. モンテ詣 27
4. 対応グレードについて 50
5. ポリ袋の話 59
6. ポリアセタールの不思議 62
7. プラスチック廃棄物 66
8. 不思議な計算 79
9. 生分解性プラスチック 86
10. 家庭用品品質表示法 88
11. 材料代替ルート 96
12. 薄型テレビ 105
13. プラスチックのメッキ 113
14. サッチャーとプラスチック 117
15. 追い矢マーク 123
1章 プラスチックとは 1
1.1 プラスチックという言葉 1
1.2 高分子ということ 3
86.
図書
東工大
小川浩平編
出版情報:
東京 : 朝倉書店, 2011.10 v, 168p ; 26cm
シリーズ名:
シリーズ「新しい化学工学」 ; 1
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
1.運動量移動の基礎
1.1 レオロジー 1
1.1.1 レオロジーの基礎 1
1.1.2 種々の流体のレオロジー 3
1.2 応力テンソルと変形速度テンソル 5
1.2.1 応力テンソル 5
1.2.2 変形速度テンソル 7
1.2.3 粘性応力テンソルと変形速度テンソルの関係 8
1.3 流体静力学 19
1.3.1 圧力 9
1.3.2 パスカルの原理 10
1.3.3 浮力 10
1.4 流れの状態の観察・表現・分類 11
1.4.1 流速・流量の定義 11
1.4.2 流れの状態の観察 12
1.4.3 流れの状態の表現 12
1.4.4 流れの状態の分類 13
1.4.5 層流と乱流 13
1.5 移動現象の相似性と基礎方程式 14
1.5.1 分子効果による移動 14
1.5.2 対流による移動 15
1.5.3 移動現象を記述する基礎方程式 15
1.5.4 流体質量の移動 : 連続の式 15
1.5.5 熱,物質移動の式 17
1.5.6 運動量移動の式 18
1.5.7 エネルギー収支の式 20
1.6 速度分布 22
1.6.1 1次元定常の速度分布 24
1.6.2 1次元非定常の速度分布 28
1.7 管内流れにおける機械的エネルギー収支 31
1.7.1 ベルヌイの定理 31
1.7.2 円管内流れの速度分布 32
1.7.3 管摩擦係数とファニングの式 33
1.7.4 機械的エネルギー収支の式 36
1.8 流れ関数と速度ポテンシャル 38
1.8.1 流れ関数 39
1.8.2 速度ポテンシャル 43
1.8.3 複素速度ポテンシャル 43
1.9 境界層理論 45
1.9.1 境界層方程式 46
1.9.2 層流境界層における移動現象 48
1.9.3 乱流境界層 49
1.10 粒子のまわりの流れ 51
1.10.1 流体中の単一粒子の運動 51
1.10.2 流体中の粒子群の運動部 52
1.10.3 固定層 54
1.10.4 流動層 57
1.11 非ニュートン流体の流れ 58
1.11.1 層流速度分布 58
1.11.2 円管内流れにおける圧力損失 60
2.乱流現象
2.1 乱流の基礎 61
2.1.1 乱流運動方程式 61
2.1.2 乱流運動エネルギー式 62
2.1.3 レイノルズ応力と乱流拡散係数 62
2.1.4 乱流運動エネルギースペクトル 63
2.2 乱流構造 64
2.2.1 エネルギースペクトル密度分布関数(ESD関数) 64
2.2.2 乱れのスケールと乱流拡散 67
2.2.3 スケールアツプ 67
a. 撹拌槽のスケールアップ 68
b. 円管のスケールアップ 69
2.2.4 非ニュートン流体の場合のエネルギースペクトル密度関数 69
3.混相流
3.1 気-液温相流 71
3.1.1 垂直管内の流動様式 71
3.1.2 水平管内の流動様式 72
3.2 液-液温相流 73
4.機械的混合・分離操作
4.1 混合操作 75
4.1.1 混合操作の基礎 75
a. 固-固混合 75
b. 撹拌操作 76
c. 混合性能/混合度 79
d. スケールアップ則 80
4.1.2 混合分離操作の評価 80
a. 従来の評価指標 80
b. 情報エントロピーに基づく評価指標 82
4.2 分離操作 90
4.2.1 粒子群の特徴 90
4.2.2 粒子径分布と平均粒子径 91
4 2.3 粒子径分布を表す関数 93
4.2.4 分離操作における部分回収率と分離効率 94
4.2.5 機械的分離操作の分類 95
4.2.6 沈降分離 96
4.2.7 連続沈降槽 97
4.2.8 遠心分離 98
4.2.9 サイクロン 100
4.2.10 濾過 101
5.運動量移動の数値シミュレーション
5.1 差分法の基礎 106
5.1.1 打切り誤差 105
5.1.2 差分スキームの安定性 107
5.1.3 風上差分とクーラン条件 108
5.1.4 保存系スキームと非保存系スキーム 109
5.2 流体解析手法の概要 111
5.2.1 流体解析で用いる基礎方程式系 111
5.2.2 代表的な流体解析手法 111
5.3 乱流解析 113
5.3.1 直接数値シミュレーション(DNS) 113
5.3.2 レイノルズ平均乱流モデル(RANS) 113
5.3.3 κ-εモデル 113
5.3.4 スカラー場に対する乱流モデル 114
5.3.5 壁面境界条件 115
5.3.6 ラージ・エデイ・シミュレーション‐(LES) 115
5.4 混相流解析 116
5.4.1 混相流解析手法の分類 116
5.4.2 連続相に対する定式化 117
5.4.3 オイラー-オイラー法 118
5.4.4 オイラー-ラグランジュ法 119
5.5 撹拌槽内の流動解析 121
5.5.1 バッフル付き撹拌槽内の流動解析 121
5.5.2 多段翼撹拌槽 121
6.相似則
6.1 流動状態の相似則 127
6.2 エネルギー散逸の相似則 128
6.3 ファニングの式 130
6.4 球の流体抵抗 131
6.5 撹拌所要動力 132
7.流体測定法
7.1 流れの可視化 134
7.2 レオロジーの測定 135
7.2.1 レオロジー測定法の種類 135
7.2.2 キャピラリー粘度計による非ニュートン流体の粘度測定 136
7.3 圧力の測定 137
7.3.1 圧力測定法の種類 137
7.3.2 2次変換器 137
7.4 流速の測定 138
7.5 流量の測定 140
7.5.1 流量測定法の種類 140
7.5.2 オリフィス流量計 140
8.機械的操作の今後の展開
8.1 化学工学の歩みと一貫した視点 143
8.1.1 粒子径分布表示式 144
8.1.2 不安度および期待度の表示式 147
8.2 流量と数値シミュレーション 148
8.3 スケールアップ 149
8.4 移動現象および反応と流動 149
8.5 粉粒体 150
補足 151
索引 165
1.運動量移動の基礎
1.1 レオロジー 1
1.1.1 レオロジーの基礎 1
87.
図書
東工大
森永正彦, 古原忠, 戸田裕之編
出版情報:
東京 : 共立出版, 2010.3 x, 220p ; 26cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第1章 材料のマクロな変形挙動
1.1 応力とひずみ 2
1.1.1 単軸引張変形における応力とひずみ 2
1.1.2 応力とひずみの3次元表記 7
1.2 弾性変形 15
1.2.1 フックの法則 15
1.2.2 弾性ひずみエネルギー 17
1.3 塑性変形と変形抵抗 18
1.3.1 塑性変形 18
1.3.2 相当応力と相当ひずみ 19
1.3.3 降伏条件 21
1.3.4 加工硬化 24
1.3.5 変形抵抗に及ぼす各種条件の効果 28
1.3.6 くびれ・座屈とその発生条件 28
1.4 クリープ変形 31
1.4.1 クリープ変形とクリープ曲線 31
1.4.2 クリープの構成則 32
演習問題 33
参考文献 34
第2章 結晶格子と欠陥
2.1 結晶・点欠陥 36
2.1.1 ブラベー格子 36
2.1.2 規則・不規則構造 37
2.1.3 代表的な金属の結晶構造 38
2.1.4 方位と面の表記法(ミラー指数) 38
2.2 点欠陥 40
2.2.1 点欠陥とその種類 40
2.2.2 点欠陥の濃度 41
2.2.3 点欠陥の形成 42
2.3 転位 43
2.3.1 転位の概念,種類と特徴付け 43
2.3.2 転位の応力場とひずみエネルギー 47
2.3.3 転位の運動と転位に作用する力 52
2.3.4 転位の分解 54
2.3.5 降伏と加工硬化,転位の増殖と蓄積 56
2.3.6 転位と材料の強化機構 61
2.4 面欠陥 64
2.4.1 結晶粒界 64
2.4.2 異相界面 72
演習問題 74
参考文献 74
第3章 集合組織
3.1 回復と再結晶の転位論 78
3.1.1 転位による内部エネルギー(ひずみエネルギー) 78
3.1.2 回復 78
3.1.3 再結晶 80
3.2 動的回復と動的再結晶 83
3.3 集合組織とは 83
3.3.1 種類と成因 83
3.3.2 集合組織の表示 85
3.3.3 塑性変形による方位変化 92
3.3.4 変形集合組織 94
3.3.5 再結晶集合組織 98
演習問題 100
参考文献 100
第4章 金属材料の塑性加工
4.1 主な実用的塑性加工法 102
4.1.1 鍛造 102
4.1.2 圧延 106
4.1.3 押出・引抜き 114
4.1.4 板成形 117
4.1.5 超塑性加工 123
4.2 加工欠陥 125
4.2.1 くびれ 125
4.2.2 座屈・しわ 125
4.2.3 折込み 126
4.2.4 表皮引込み 126
4.2.5 へこみ,引け 127
4.2.6 割れ 127
4.3 塑性加工性の試験法 128
4.3.1 ランクフォード値(r値) 129
4.3.2 エリクセン試験 130
4.3.3 コニカルカップ試験 131
4.3.4 その他の成形性試験法 131
4.4 強加工法 132
4.4.1 各種強加工法の概要 132
4.4.2 強加工による結晶粒微細化 135
演習問題 139
参考文献 139
第5章 加工による材料の特性向上と機能発現例
5.1 鉄鋼材料 142
5.1.1 加工による強度と延性の変化 142
5.1.2 超強加工バルク材の疲労特性 144
5.1.3 超強加工バルク材の耐食性 145
5.1.4 表層超強加工 146
5.2 アルミニウム合金 146
5.2.1 強度と延性の同時向上 147
5.2.2 超塑性の出現 149
5.2.3 原子拡散の促進 149
5.3 マグネシウム合金 150
5.3.1 熱間加工による高強度・高延性化および異方性低減 151
5.3.2 塑性加工により強化される長周期積層構造型マグネシウム合金 154
5.4 チタン基合金 156
5.4.1 チタンおよびチタン合金の基礎知識および加工熱処理の概要 156
5.4.2 純チタンおよびα型チタン合金 158
5.4.3 α+β型合金 159
5.4.4 β型チタン合金 161
5.5 形状記憶・超弾性合金 165
5.5.1 形状記憶・超弾性効果 166
5.5.2 実用形状記憶合金の種類と加工性 168
5.5.3 形状記憶・超弾性処理の原理 169
5.5.4 Ti-Niの加工熱処理 170
5.5.5 集合組織形成による特性改善 170
5.6 コバルト合金 172
5.6.1 コバルト合金の結晶学 172
5.6.2 コバルト合金の転位構造 176
5.6.3 実用コバルト合金の転位拡張 177
5.6.4 コバルト合金の組織制御 179
演習問題 185
参考文献 186
第6章 計算科学
6.1 加工における計算科学 190
6.2 状態図計算と加工 191
6.2.1 状態図とは 191
6.2.2 計算状態図と熱力学モデル 192
6.2.3 状態図計算の材料開発への応用 193
6.3 材料組織形成計算と加工 196
6.3.1 フェーズフィールド法の概要 197
6.3.2 応用例 198
6.4 結晶塑性理論による計算 200
演習問題 205
参考文献 205
演習問題解答 207
索引 215
第1章 材料のマクロな変形挙動
1.1 応力とひずみ 2
1.1.1 単軸引張変形における応力とひずみ 2
88.
図書
東工大
鈴木善孝著
出版情報:
東京 : 東京電機大学出版局, 2010.1 viii, 301p ; 21cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第1章 化学工業と化学工学 1
1.1 単位反応と単位操作 2
1.2 単位と次元 2
1.3 物質収支とエネルギー収支 9
1.3.1 物質収支 9
1.3.2 エネルギー収支 10
1.3.3 内部エネルギーとエンタルピー 10
数学のしおり 15
練習問題① 24
略解① 25
第2章 流動 27
2.1 流体 27
2.1.1 層流と乱流 27
2.2 流動の物資収支とエネルギー収支 33
2.2.1 連続の式と物質収支 33
2.2.2 流動のエネルギー収支 34
2.2.3 流体輸送 38
2.2.4 流量測定 46
2.2.5 流体輸送機器 50
練習問題② 55
略解② 56
第3章 伝熱 59
3.1 熱伝導 59
3.2 対流伝熱 64
3.3 対流伝熱の主な要素 67
3.3.1 境膜伝熱係数hの主な決定事項 67
3.3.2 その他の事項 69
3.4 放射伝熱 74
3.5 熱交換器 78
練習問題③ 82
略解③ 82
第4章 蒸発と晶出 85
4.1 蒸発 86
4.1.1 沸点上昇 86
4.1.2 蒸発の熱収支と物質収支 89
4.1.3 蒸発缶の留意点 92
4.1.4 蒸発装置(蒸発缶) 94
4.1.5 蒸発缶の付属装置 94
4.2 多重効用蒸発
4.2.1 多重効用蒸発の物質と熱収支および伝熱速度 98
4.3 晶出 102
練習問題④ 104
略解④ 104
第5章 蒸留 107
5.1 気-液の平衡 108
5.1.1 蒸留の基礎理論 108
5.2 各種蒸留方法と操作 113
5.3 精留 116
5.3.1 精留装置と操作 117
5.3.2 還流比および物質収支と熱収支 121
5.3.3 3成分および多成分系の精留 127
5.4 主な特殊蒸留 128
5.4.1 共沸蒸留と抽出蒸留 128
練習問題⑤ 133
略解⑤ 134
第6章 ガス吸収 137
6.1 吸収の基本理論 138
6.1.1 ヘンリーの法則とx-y線図 138
6.1.2 吸収の速度 140
6.1.3 吸収の物質収支 142
6.2 主な吸収装置 144
6.2.1 装置の種類と選択留意 144
6.2.2 気泡式吸収装置 144
6.2.3 充填塔式吸収装置 147
練習問題⑥ 152
略解⑥ 153
第7章 抽出 155
7.1 抽出装置 155
7.1.1 固体抽出装置 155
7.1.2 液体抽出装置 157
7.2 抽出の理論 159
7.2.1 抽剤の条件 159
7.2.2 固-液抽出 159
7.2.3 液-液抽出 162
練習問題⑦ 171
略解⑦ 173
第8章 調湿 177
8.1 湿り空気(湿潤空気) 177
8.1.1 湿度 177
8.1.2 湿り空気特性の表示法 179
8.1.3 湿度図表 184
8.2 調湿と冷水 190
8.2.1 増湿 190
8.2.2 減湿 192
8.2.3 冷水 193
練習問題⑧ 196
略解⑧ 196
第9章 乾燥 199
9.1 乾燥の理論 199
9.2 乾燥操作 208
9.2.1 乾燥速度を変える影響 208
9.2.2 乾燥操作における留意点 209
9.2.3 多段加熱乾燥 210
9.2.4 向流乾燥と並流乾燥 211
9.3 主要乾燥装置 211
9.3.1 乾燥装置の分類 211
9.3.2 箱式乾燥装置 212
9.3.3 トンネル乾燥装置 213
9.3.4 バンド乾燥装 213
9.3.5 回転乾燥装置 214
9.3.6 攪拌乾燥器 215
9.3.7 円板乾燥器 215
9.3.8 気流乾燥装置 216
9.3.9 噴霧乾燥器 216
9.3.10 円筒乾燥装置 216
9.3.11 乾燥装置の選択例 217
9.4 真空乾燥と凍結乾燥 218
9.4.1 真空乾燥 218
9.4.2 凍結乾燥 219
練習問題⑨ 220
略解⑨ 221
第10章 粉砕と篩分け 223
10.1 粉砕 223
10.1.1 粉砕の方式 226
10.1.2 砕料の性質 228
10.1.3 砕料の粉砕能(粉砕の基本法則) 230
10.2 篩分け 232
10.2.1 篩 232
練習問題⑩ 237
略解⑩ 239
第11章 混合・攪拌・捏和 241
11.1 混合 241
11.1.1 混合機 244
11.2 攪拌と捏和 246
11.2.1 攪拌機と捏和機 247
練習問題⑪ 251
略解⑪ 251
第12章 機械的分離 253
12.1 分離と分離効率 253
12.2 濾過 253
12.2.1 濾材と濾過助剤 257
12.2.2 濾過の理論 259
12.2.3 濾過機 261
12.3 遠心分離 266
12.4 分級 271
12.4.1 沈降の理論 271
12.4.2 分級装置 275
12.5 集塵 278/
12.5.1 微粒子の主な性質 278
12.5.2 集塵装置 280
練習問題⑫ 284
略解⑫ 285
付録 287
参考文献 294
索引 295
第1章 化学工業と化学工学 1
1.1 単位反応と単位操作 2
1.2 単位と次元 2
89.
図書
東工大
加藤正直, 内山一美, 鈴木秋弘共著
出版情報:
東京 : 森北出版, 2010.3 v, 121p ; 26cm
シリーズ名:
物質工学入門シリーズ
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第1章 機器分析の概要 1
1.1 機器分析法とは 1
1.1.1 どんな機器分析法があるか 1
1.1.2 機器分析法の長所と短所 - 数値は得られるが万能ではない 3
演習問題1 3
第2章 紫外可視分光法と蛍光光度法 4
2.1 紫外可視分光法 4
2.1.1 紫外可視分光法の原理 4
2.1.2 紫外可視分光装置のしくみ 5
2.1.3 ランベルト-ベール則 7
2.1.4 紫外可視分光法による分析 8
2.1.5 分子による紫外可視光の吸収 9
2.1.6 紫外可視分光法の適用例 11
2.2 蛍光光度法 13
2.2.1 蛍光の原理 13
2.2.2 蛍光光度計装置 13
2.2.3 蛍光光度測定法 13
2.2.4 定量分析法 14
2.2.5 応用例 15
演習問題2 15
第3章 原子吸光分析法と発光分析法 17
3.1 原子吸光分析法 17
3.1.1 原子吸光分析装置 17
3.1.2 原子吸光分析法による定量分析 19
3.2 発光分析法 21
3.2.1 フレームによる発光(炎光分析法) 21
3.2.2 ICPによる発光(ICP発光分析法) 22
3.2.3 ICP発光分析装置の概要 22
3.2.4 ICP発光分析法による定量分析 23
演習問題3 24
第4章 X線分析法 25
4.1 X線の性質 25
4.1.1 X線の原理 25
4.1.2 X線の発生 25
4.1.3 固有X線と連続X線 26
4.1.4 X線の吸収 28
4.2 X線回折分析法 30
4.2.1 X線回折の原理 30
4.2.2 単結晶と粉末によるX線の回折 34
4.2.3 X線回折装置 36
4.2.4 応用 : 定性分析とICDD(JCPDS)カード 37
4.3 蛍光X線分析法 40
4.3.1 蛍光X線の原理 40
4.3.2 蛍光X線測定装置 40
4.3.3 定量分析 41
演習問題4 43
第5章 赤外線吸収スペクトル 44
5.1 赤外線吸収スペクトル 44
5.1.1 赤外線吸収スペクトルの原理 44
5.1.2 振動の位置と強度 45
5.1.3 振動の種類(伸縮振動と変角振動) 46
5.1.4 測定装置とスペクトル(FT-IR) 46
5.1.5 試料の調製と測定方法 47
5.1.6 スペクトルの解析 48
5.1.7 吸収位置と強度に変化を及ぼす因子 51
5.2 ラマン散乱 52
5.2.1 ラマン分光法 52
5.2.2 測定装置と測定方法 53
5.2.3 ラマン活性にかかわる振動 54
演習問題5 55
第6章 核磁気共鳴スペクトル 56
6.1 核磁気共鳴スペクトル 56
6.1.1 はじめに 56
6.1.2 磁気共鳴スペクトル 57
6.1.3 測定装置のしくみと試料の調製 58
6.1.4 化学シフト 59
6.1.5 シグナル強度(積分曲線) 61
6.1.6 シグナルの分裂 : スピン-スピン結合 61
6.1.7 結合定数(カップリング定数) 62
6.1.8 化学交換 63
6.1.9 シューレリーの加成則 63
6.2 核磁気共鳴スペクトル(炭素核 : 13C) 64
6.2.1 13C-NMRスペクトル 64
6.2.2 13Cの化学シフト 64
6.2.3 測定(測定方法と測定条件) 65
演習問題6 67
第7章 質量分析法 68
7.1 質量スペクトル 68
7.1.1 質量スペクトル測定の概要 68
7.1.2 測定装置のしくみと試料の調製 69
7.1.3 イオン化と開裂 69
7.1.4 スペクトルの見方(チャートの見方とピークの種類) 70
7.1.5 スペクトルの解析方法 72
7.1.6 開裂の様式 72
7.1.7 官能基による開裂の様式 73
7.1.8 転位イオン生成物 76
演習問題7 78
第8章 電気化学的測定法 80
8.1 電気化学的測定法の基礎 80
8.1.1 電気量 80
8.1.2 電気化学反応の基礎 81
8.1.3 電極電位 82
8.1.4 電極の種類 83
8.2 主な電気化学的測定法 85
8.2.1 電位差測定法 86
8.2.2 電気電導度分析法 89
8.2.3 電解分析法 90
8.2.4 ボルタンメトリー 91
演習問題8 94
第9章 クロマトグラフィー 95
9.1 クロマトグラフィーの基本概念 95
9.2 クロマトグラフィーの分類 96
9.2.1 移動相の種類による分類 96
9.2.2 分配機構による分類 97
9.3 ガスクロマトグラフィー 97
9.3.1 ガスクロマトグラフィーの概要 97
9.3.2 カラム 98
9.3.3 検出器 99
9.3.4 ガスクロマトグラフのパラメーター 100
9.3.5 分離特性 101
9.3.6 ガスクロマトグラフィーによる定量分析 101
9.4 液体クロマトグラフィー 103
9.4.1 高速液体クロマトグラフィーの原理および装置 103
9.4.2 検出器の特徴 104
9.4.3 実際の分析 105
9.5 薄層クロマトグラフィー 108
9.5.1 固定相 108
9.5.2 移動相 109
9.5.3 展開 109
9.5.4 検出 110
演習問題9 111
付表 113
演習問題解答 114
参考文献 119
さくいん 120
第1章 機器分析の概要 1
1.1 機器分析法とは 1
1.1.1 どんな機器分析法があるか 1
90.
図書
東工大
井関文一, 金武完, 森口一郎共著
出版情報:
東京 : コロナ社, 2010.6 vi, 223p ; 21cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
1章 ネットワークと標準化
1.1 標準化 1
1.1.1 デファクトスタンダードとISO
1.1.2 その他の標準化組織
1.2 RFC 3
1.3 OSI参照モデルとTCP/IP 4
1.3.1 OSI参照モデルの簡単な説明
1.3.2 OSI参照モデルと郵便との対比
1.3.3 カプセル化とカプセル化の解除
1.4 ネットワーク上の中継器 9
1.4.1 物理層での中継器
1.4.2 データリンク層での中継器
1.4.3 ネットワーク層での中継器
1.4.4 アプリケーション層での中継器
2章 メディア(ケーブル)と物理層
2.1 物理層の機能 11
2.2 LANにおけるメディアのトポロジー(形状) 11
2.2.1 バス型
2.2.2 リング(ループ)型
2.2.3 スター型
2.3 中継器(リピータハブ) 14
2.4 物理層のプロトコル 15
3章 データリンク層
3.1 データリンク層の機能 16
3.1.1 LLC副層の機能
3.1.2 MAC副層の機能
3.2 MACアドレス 18
3.3 メディアアクセス方式 20
3.3.1 CSMA/CD
3.3.2 トークンリング
3.4 中継器(スイッチングハブ) 22
3.4.1 コリジョンドメインの分割
3.4.2 半二重と全二重通信
3.4.3 スパニングツリープロトコル【中級】
3.4.4 ポートトランキング【中級】
3.4.5 スイッチングハブによるフロー制御【中級】
3.4.6 ポートミラーリング【中級】
3.5 データリンク層のプロトコル 27
3.5.1 HDLC
3.5.2 PPP
3.6 イーサネット 29
3.6.1 イーサネットの概要
3.6.2 DIXイーサネットとIEEE802.3
3.6.3 イーサネットフレームのスイッチング
3.7 誤り検出 33
3.7.1 パリティチェック
3.7.2 チェックサム
3.7.3 巡回冗長検査
3.8 VLAN【中級】 35
3.8.1 ポートVLANとVLANタギング
3.8.2 VLAN環境でのルーティング
3.9 無線LAN【中級】 37
3.9.1 無線LANの概要
3.9.2 無線LAN規格(IEEE802.11 シリーズ)
3.9.3 衝突検出
3.9.4 ESS-ID(SS-ID)
3.9.5 無線LANの通信モード
3.9.6 無線LANのセキュリティ
4章 ネットワーク層
4.1 ネットワーク層(インターネット層)の機能 47
4.2 IPアドレス 48
4.2.1 IPアドレスの構造とサブネットマスク
4.2.2 ネットワークアドレスとブロードキャストアドレス
4.2.3 IPアドレスの分類
4.2.4 サブネットマスクの再定義
4.2.5 ARP
4.3 IPパケットの構造【中級】 57
4.4 CIDRを使用した場合のIPアドレスの計算【中級】 58
4.4.1 CIDRとプレフィックス長表記
4.4.2 CIDR例題
4.5 マルチキャスト通信【中級】 62
4.6 ICMP 64
4.6.1 pingコマンド
4.6.2 traceroute(tracert)コマンド
4.7 ネットワークコマンドの操作【中級】 67
4.7.1 MACアドレスとIPアドレスの表示
4.7.2 pingコマンド
4.7.3 traceroute(tracert)コマンド
4.7.4 ARPテーブルの表示
4.8 ルーティング 72
4.8.1 ルーティングプロトコルの分類
4.8.2 代表的なルーティングプロトコル
4.8.3 小規模ネットワークでの設定例【中級】
4.8.4 経路情報の集約【中級】
4.8.5 論理ネットワークの定義とルータの役割
4.9 VPN 85
4.9.1 VPNとは
4.9.2 トンネリング技術
4.9.3 レイヤ2VPNとレイヤ3VPN
4.9.4 VPNの問題点
4.9.5 代表的なVPNとその基本プロトコル
4.10 IPv6 92
4.10.1 IPv4の問題点
4.10.2 IPv6のアドレス表記と構造
4.10.3 IPv6のアドレスの割り当て【中級】
4.10.4 ルーティングアドレスの集約【中級】
4.10.5 Plug and Play【中級】
4.10.6 IPsec【中級】
4.10.7 QoS
4.10.8 IPv6パケットの構造【中級】
4.10.9 IPv4からIPv6への移行
5章 トランスポート層(TCPとUDP)
5.1 トランスポート層の機能 104
5.2 TCP 105
5.2.1 TCPにおけるコネクションの確立
5.2.2 TCPにおけるコネクションの終了【中級】
5.2.3 TCPセグメントの構造【中級】
5.3 UDP 110
5.3.1 UDPのコネクションレス指向通信
5.3.2 UDPセグメントの構造【中級】
5.4 ポート番号 111
5.4.1 ポート番号によるプロセスの識別
5.4.2 ポート番号の割り当て
5.4.3 クライアント・サーバ(C/S)モデルでのポート番号
5.5 ポートスキャン 114
5.5.1 ポートスキャナ
5.5.2 telnetコマンドによる手動TCPポートスキャン【中級】
5.6 NAPT 117
5.6.1 NATとNAPT
5.6.2 NAPTによるアドレス・ポート番号変換【中級】
5.6.3 NAT(NAPT)越えの問題【中級】
6章 アプリケーション層のプロトコル
6.1 サーバプロセス 124
6.1.1 クライアント・サーバ(C/S)モデル
6.1.2 デーモン
6.2 DNS 125
6.2.1 FQDN
6.2.2 FQDNの形式
6.2.3 DNSの階層構造
6.2.4 再帰モードと非再帰モード【中級】
6.2.5 DNSレコード【中級】
6.2.6 nslookupコマンド【中級】
6.2.7 digコマンド【中級】
6.3 SMTPとPOP3 135
6.3.1 SMTP
6.3.2 エンベロープ【中級】
6.3.3 MIME【中級】
6.3.4 OP25B【中級】
6.3.5 POP3
6.4 HTTPとHTTPS 141
6.4.1 HTTP
6.4.2 HTTPS
6.5 TELNETとSSH 142
6.5.1 TELNET
6.5.2 SSH
6.6 その他のネットワークアプリケーション 143
6.6.1 FTP
6.6.2 DHCP
6.6.3 SIP
6.6.4 RTP,RTCP
6.6.5 NFS
6.6.6 SAMBA
6.6.7 LDAP
6.6.8 NTP
6.6.9 Proxyサーバ
6.6.10 スーパーデーモン
6.7 パケットアナライズ 151
7章 Webとメール
7.1 HTTP 152
7.1.1 HTTPの基本
7.1.2 動的Webページ
7.1.3 Cookie
7.2 Webサービス 168
7.2.1 Webサービスの構成
7.2.2 Webサービスの技術
7.3 メール : SMTP,POP3 176
7.3.1 1対1コミュニケーションツールとしての電子メール
7.3.2 SMTP
7.3.3 POP3
7.4 電子メールシステムの問題点と対策 183
8章 P2Pとグリッド
8.1 P2Pネットワーク 186
8.1.1 P2Pネットワークの特徴
8.1.2 ファイルの共有・交換サービス
8.2 グリッド 191
8.2.1 グリッドコンピューティング
8.2.2 グリッドミドルウェア
8.2.3 AD-POWERsを用いたPCグリッド
9章 リアルタイムアプリケーション
9.1 ストリーミング 195
9.1.1 ストリーミングの基本構成
9.1.2 情報圧縮技術
9.1.3 リアルタイム通信技術
9.2 IP電話 205
9.2.1 回線交換技術による電話サービス
9.2.2 IP電話の基本構成
9.2.3 シグナリング用プロトコルH.323
9.2.4 音声品質
9.3 SIP 213
9.3.1 SIPの基本
9.3.2 SIPを用いたアプリケーションの実現
索引 220
1章 ネットワークと標準化
1.1 標準化 1
1.1.1 デファクトスタンダードとISO
91.
図書
東工大
鈴木陽一 [ほか] 共著 ; 日本音響学会編
目次情報:
続きを見る
第Ⅰ部─縦糸編─(1章~7章)
1. ピタゴラスから携帯電話までの音響学
1.1 私たちの暮らしと音 2
1.2 音響学の変遷と展開 3
1.3 現代の音響学 7
1.4 音響学,その基礎の基礎 8
1.4.1 音と音波 8
1.4.2 音の伝搬によって生じる現象 10
1.4.3 音の強さのレベルと音圧レベル 13
1.4.4 音とその周波数スペクトル 15
1.4.5 聴覚の感度特性を考慮した音のレベルの表現法 19
2. 音を聞く仕組み
2.1 音源方向の知覚 23
2.1.1 音源の方向と左右耳の強度差 23
2.1.2 音源の方向と左右耳の時間差 24
2.1.3 音の到来方向と頭部での反射 24
2.1.4 ヒトの方向定位能力 26
2.2 聴覚を支える聴器 26
2.2.1 外耳 27
2.2.2 中耳 28
2.2.3 内耳 29
2.2.4 脳幹 31
2.2.5 中脳および聴覚野 36
2.3 聴覚による知覚 36
2.3.1 ラウドネスの知覚 37
2.3.2 マスキング 37
2.3.3 聴覚フィルタと臨界帯域 38
2.3.4 音の高さ知覚のらせん構造とピッチ 39
2.3.5 音色 41
2.4 音の選択的聴取 42
2.4.1 カクテルパーティ効果 42
2.4.2 時間軸上の現象(イベント)の取得 42
2.4.3 音脈の形成 43
2.5 難聴 44
3. 音の収録と再生
3.1 音から電気信号への変換-マイクロフォン- 47
3.1.1 マイクロフォンの仕組み 47
3.1.2 マイクロフォンの電気特性 53
3.1.3 指向特性 54
3.2 電気信号から音への変換 57
3.2.1 スピーカの動作原理 57
3.2.2 スピーカの再生周波数帯域とマルチウェイスピーカ 60
3.2.3 スピーカエンクロージャ 62
3.2.4 ヘッドフォン 63
3.3 音を楽しむためのシステムと信号処理方式 65
3.3.1 音の方向感の制御に基づく技術 66
3.3.2 聴取点における音圧の制御に基づく技術 67
3.3.3 空間的な音場の制御に基づく技術 68
3.4 音を分離する技術 70
4. 音声の発話と認識
4.1 音声の発話 75
4.1.1 声帯と声道 75
4.1.2 音声の波形とフォルマント 77
4.1.3 音韻と音素 80
4.2 音声の符号化 81
4.2.1 音声の符号化とは 82
4.2.2 PCM とADPCM 82
4.2.3 線形予測による符号化 85
4.3 音声合成・認識・対話 88
4.3.1 音声の合成 88
4.3.2 音声の認識 90
4.3.3 音声の理解と応用システム 93
4.4 音声の知覚 94
4.4.1 言語,パラ言語,非言語 95
4.4.2 音声の「聞こえ」を測る 95
4.4.3 音韻の知覚 95
4.4.4 単語と文の知覚 97
4.4.5 音声のパラ言語情報の知覚 99
4.4.6 音声の非言語情報の知覚 99
5. 音楽と音響
5.1 音階と和音 103
5.1.1 響きあう音の条件 103
5.1.2 音階 104
5.2 楽器の音 108
5.2.1 楽器が音を出す仕組み 108
5.2.2 楽器から出る音の特徴 110
5.3 音楽の情報処理 113
5.3.1 音を作る 114
5.3.2 音を聞き分ける 115
5.4 音楽の符号化と伝送 116
5.4.1 CDの音 117
5.4.2 高能率音楽符号化 117
5.4.3 CDを超える音 119
6. 暮らしの中の音
6.1 音の伝搬と室内音響 122
6.1.1 直接音と反射音 122
6.1.2 壁による反射と吸音 122
6.1.3 残響音と残響時間 123
6.1.4 インパルス応答の測定 125
6.2 室内音響の評価と設計 126
6.2.1 室内音響の評価 126
6.2.2 壁面の形と反射音 126
6.2.3 壁面の凹凸と反射音 127
6.2.4 室形と響き 127
6.2.5 響きのコントロールと音響設計 128
6.3 騒音 131
6.3.1 騒音とは 131
6.3.2 騒音の分類 133
6.3.3 騒音の測定 133
6.3.4 騒音のオクターブバンド分析 136
6.4 騒音の伝搬と遮音 137
6.4.1 壁の遮音性能 137
6.4.2 隣室間の音の伝搬 138
6.4.3 固体音の伝搬 139
6.4.4 床衝撃音 139
6.5 屋外における騒音 140
6.5.1 屋外における騒音の伝搬 140
6.5.2 屋外騒音の評価と規制基準 140
6.6 よりよい音環境をめざして 141
6.6.1 静けさの確保 141
6.6.2 シグナルとしての「騒音」 142
6.6.3 子育て,教育と音空間 143
6.6.4 高齢者および障害者のための音環境 143
7. 超音波
7.1 超音波の特徴 146
7.1.1 超音波の定義 146
7.1.2 縦波超音波と横波超音波 146
7.1.3 直進性と高強度の利用 148
7.2 超音波の発生と検出 148
7.2.1 発生方法・超音波トランスデューサ 148
7.2.2 検出方法 153
7.3 超音波の計測応用 154
7.4 超音波のパワー応用 160
7.4.1 超音波キャビテーション 160
7.4.2 音響放射力と音響流 160
7.4.3 非線形現象とパラメトリックスピーカ 162
7.4.4 大きな振動加速度と振動応力の効果 163
7.5 超音波応用デバイス 165
7.5.1 高周波フィルタ,弾性表面波フィルタ 165
7.5.2 振動ジャイロ,センサ技術 166
7.5.3 圧電トランス 166
7.5.4 超音波モータ 167
7.5.5 光学素子 169
第Ⅱ部─横糸編─(8章,9章)
8. 音の物理
8.1 ばねとおもりの振動 171
8.2 共振 175
8.3 伝わる振動 178
8.4 音速 180
8.5 空気中の音波 181
8.6 音波の波動方程式とその解 185
8.7 音響インピーダンスと音の反射・透過 188
8.8 音の伝わり方の性質 191
8.9 固体中の振動 197
8.10 共振と固有モード 202
9. 音のディジタル信号処理
9.1 アナログ・ディジタル変換とディジタル・アナログ変換 206
9.2 離散フーリエ変換 210
9.2.1 フーリエ級数 211
9.2.2 フーリエ級数の離散化 215
9.2.3 高速フーリエ変換 217
9.3 窓関数 219
9.4 インパルス応答とたたみ込み演算 223
9.4.1 インパルス応答 223
9.4.2 たたみ込み演算 224
9.5 ディジタルフィルタ 227
9.5.1 非再帰型ディジタルフィルタ 227
9.5.2 非再帰型ディジタルフィルタの実例 228
付録 230
索引 239
第Ⅰ部─縦糸編─(1章~7章)
1. ピタゴラスから携帯電話までの音響学
1.1 私たちの暮らしと音 2
92.
図書
東工大
浅野正二著
出版情報:
東京 : 朝倉書店, 2010.2 viii, 267p ; 21cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
1章 放射の基本則と伝達過程 1
1.1 放射量の定義 1
1.1.1 放射の名称 1
1.1.2 放射の波動性と粒子性 3
1.1.3 放射の基本量 3
(1)立体角 3
(2)放射輝度 4
(3)放射束密度・放射フラックス 5
1.1.4 大気中での放射過程 5
1.2 黒体放射の法則 9
1.2.1 プランクの法則 9
1.2.2 ウィーンの変位則 11
1.2.3 ステファン・ボルツマンの法則 12
1.2.4 キルヒホッフの法則 12
1.2.5 レイリー・ジーンズ近似 14
1.2.6 輝度温度 14
1.3 放射伝達過程の定式化 14
1.3.1 放射伝達方程式 14
1.3.2 散乱位相関数 16
1.3.3 放射源関数 18
1.3.4 ビーア・ブーゲー・ランバートの法則 19
1.3.5 光学的厚さ 20
1.4 平行平面大気近似 21
1.4.1 平行平面大気の放射伝達方程式 21
1.4.2 形式解 23
1.4.3 放射による気層の加熱・冷却 24
1.4.4 非散乱大気の放射伝達への応用 25
2章 太陽と地球の放射パラメータ 28
2.1 太陽放射と太陽定数 28
2.1.1 太陽放射スペクトル 28
2.1.2 太陽定数 30
2.1.3 太陽定数の変動 31
2.2 太陽-地球の位置関係 32
2.2.1 地球の軌道 32
2.2.2 大気外日射量の分布 34
2.2.3 大気光路 37
2.3 地球大気の放射特性 38
2.3.1 大気の鉛直構造 38
2.3.2 分子大気の放射特性 39
2.3.3 エーロゾルと雲の光学特性 41
2.4 地表面の放射特性 45
2.4.1 地表面熱収支 45
2.4.2 地表面の反射特性 46
(1)地表面の反射パターン 46
(2)双方向反射関数 47
(3)地表面アルベド 47
(4)分光アルベド 49
(5)地表面アルベドの広域分布 51
2.4.3 地表面の赤外射出率 53
(1)光線射出率 53
(2)フラックス射出率 54
3章 気体吸収帯 56
3.1 気体分子の吸収帯 56
3.2 エネルギー準位と双極子モーメント 58
3.3 吸収線の形成 61
3.3.1 2原子分子の回転遷移 61
3.3.2 2原子分子の振動遷移 63
3.3.3 2原子分子の振動-回転遷移 64
3.3.4 多原子分子の振動-回転帯 66
3.3.5 2原子分子の電子遷移 69
3.4 吸収線形 71
3.4.1 吸収線の表現 71
3.4.2 吸収線の広がり 73
(1)ドップラー効果による広がり 73
(2)分子衝突による広がり 74
(3)ドップラー効果と分子衝突による線幅の比較 75
(4)吸収線パラメータ 76
3.5 連続吸収帯 77
3.5.1 水蒸気の連続吸収帯 77
3.5.2 太陽放射連続スペクトル 79
3.6 局所熱力学的平衡 81
4章 気体吸収帯における赤外放射伝達 84
4.1 赤外放射フラックスの計算 84
4.2 波数積分 88
4.2.1 波数帯放射フラックス 88
4.2.2 ライン-バイ-ライン計算法 89
4.2.3 バンド透過関数法 90
(1)散光透過関数 90
(2)透過関数の積の法則 91
4.3 透過関数のバンドモデル 94
4.3.1 孤立した吸収線モデル 94
(1)吸収線等価幅 94
(2)弱吸収近似 95
(3)ローレンツ線形吸収線の等価幅 96
(4)強吸収近似 96
4.3.2 重合した線群の透過関数モデル 97
(1)バンドモデル 97
(2)レギュラーバンドモデル 97
(3)ランダム(統計)モデル 98
4.3.3 不均質大気への適用 100
(1)スケーリング近似 100
(2)カーティス・ゴドソン近似 101
4.4 相関k分布法 102
4.4.1 k分布法 102
4.4.2 相関k分布法 104
4.5 晴天大気の赤外放射伝達 107
4.5.1 赤外放射冷却率 107
4.5.2 モデル大気の赤外放射冷却率 109
5章 大気微粒子による光散乱 112
5.1 大気粒子と散乱過程 112
5.2 光散乱過程の定式化 115
5.3 レイリー散乱 119
5.3.1 レイリー散乱理論 119
5.3.2 空気分子によるレイリー散乱 122
5.4 ミー散乱 125
5.4.1 ミー散乱理論 125
5.4.2 ミー散乱の特性 128
(1)ミー散乱光の角度分布 128
(2)消散係数,散乱係数,吸収係数 131
5.4.3 非球形粒子による散乱との比較 135
5.5 幾何光学近似 136
5.6 多分散粒子系による散乱 140
6章 散乱大気における太陽放射の伝達 144
6.1 散乱大気の放射伝達方程式 144
6.2 放射伝達方程式の近似解法 151
6.2.1 2流近似 151
6.2.2 相似則 154
6.3 数値解法 158
6.3.1 離散座標法 158
6.3.2 倍増-加算法 160
6.3.3 モンテカルロ法 165
6.4 散乱大気の放射伝達特性 166
7章 大気リモートセンシングへの応用 172
7.1 大気リモートセンシングとは 172
7.2 直達太陽光の分光測定によるリモートセンシング 174
7.2.1 ドブソン法によるオゾン全量の推定 174
7.2.2 エーロゾル粒径分布の抽出 176
7.3 反射太陽光の分光測定による大気リモートセンシング 180
7.4 赤外地球放射の分光測定による大気リモートセンシング 185
7.5 マイクロ波放射による大気リモートセンシング 190
7.5.1 マイクロ波リモートセンシングの特徴 190
7.5.2 宇宙からのマイクロ波リモートセンシングの原理 193
8章 放射平衡と放射強制力 197
8.1 全球の放射平衡 197
8.1.1 放射平衡温度 197
8.1.2 大気の温室効果 199
8.1.3 全球熱収支 202
8.2 放射平衡大気の温度分布 205
8.2.1 灰色大気の温度分布 205
8.2.2 現実的大気の温度分布 205
8.2.3 温室効果気体による気温変化 208
8.3 放射強制力 210
8.3.1 放射強制力と気候感度 210
8.3.2 温室効果気体の放射強制力 213
8.3.3 人間活動に起因する放射強制力 215
8.4 雲とエーロゾルの放射強制力 217
8.4.1 雲の放射強制力 217
8.4.2 エーロゾルの放射強制力 220
(1)直接放射効果 220
(2)間接放射効果 224
補章A 電磁波と偏光 227
補章B 複素屈折率と反射・屈折の法則 235
補章C 放射フラックスの測定 242
さらに学ぶための参考書 247
引用文献 250
索引 259
1章 放射の基本則と伝達過程 1
1.1 放射量の定義 1
1.1.1 放射の名称 1
93.
図書
東工大
黒田和男, 山本和久, 栗村直編
出版情報:
東京 : オプトロニクス社, 2010.2 xiv, 303p ; 22cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第1章 総説 [山本和久] 2
1. レーザーディスプレイの歴史と特徴 2
2. レーザーディスプレイの主要技術 4
2.1 レーザー投射光学系 4
2.2 スペックルノイズ除去 6
2.3 レーザー光源 8
2.3.1 半導体レーザー 8
2.3.2 半導体レーザーの波長変換 9
2.4 安全性確保 11
3. レーザーディスプレイ装置の応用 12
3.1 レーザーリアプロジェクションTV 13
3.2 超小型プロジェクタ 14
3.3 その他のレーザーディスプレイ 15
4. まとめ 16
第2章 光源技術
2.1 半導体レーザー
2.1.1 赤色半導体レーザー [八木哲哉] 20
1. はじめに 20
2. 小型プロジェクタ用赤色LD 21
3. 大型ディスプレイ向け赤色LDアレイ 27
4. まとめ 29
2.1.2 青色・緑色半導体レーザー [長濱慎一] 31
1. はじめに 31
2. 青色半導体レーザー 32
3. 緑色半導体レーザー 37
2.1.3 面発光半導体レーザー [宮本智之] 43
1. はじめに 43
2. 面発光レーザーの特徴 43
3. 面発光レーザーの応用分野 44
4. 研究開発の歴史 45
5. 面発光レーザーの構成法 45
6. 様々な波長の面発光レーザー 49
7. 外部共振器型面発光レーザー 52
8. 面発光レーザーの新しい構成技術 53
2.1.4 有機半導体レーザー-その材料を中心に- [安達千波矢] 56
1. はじめに 56
2. 有機発光ダイオードのメカニズムと到達点 57
3. レーザー活性材料(蛍光・リン光材料)(低閾値での反転分布形成) 59
4.電流励起可能なデバイス構造への展開 63
2.2 波長変換
2.2.1 波長変換デバイス [栗村 直] 68
1. はじめに 68
2. 波長変換材料 70
3. デバイスの形態 72
4. 緑色SHGの進展 74
5. 高効率小型グリーンレーザーへの挑戦 79
6. まとめ 82
2.2.2 マイクロチップ固体レーザー [平等拓範] 84
1 はじめに 84
2. 基本特性 85
2.1 希土類イオンの分光特性 85
2.2 遷移分岐比と最小励起率 88
2.3 熱機械特性 91
2.4 内部共振器SHG特性 93
3. レーザー発振基本特性 95
3.1 基本波発振特性 95
3.2 SHG特性 97
4. まとめ 102
2.2.3 SHG用高出力基本波レーザー [尾松孝茂] 105
1. はじめに 105
2. 半導体レーザー励起固体レーザー 106
2.1 Yb系レーザー 106
2.2 Nd系レーザー 108
2.2.1 Nd系レーザーの分光学的特性 108
2.3 Ndドープバナデートレーザー 110
2.4 熱レンズ効果 110
2.5 側面励起レーザー 111
3. ファイバーレーザー 113
4. 光励起型面発光半導体レーザー 115
5. ディスプレイ用高出力レーザーの展開とまとめ 116
2.2.4 高出力緑色SHGレーザー [岡美智雄] 119
1. はじめに 119
2. 緑色レーザー発生の方式 120
3. 高出力SHG緑色レーザーの構成と出力特性 124
4. おわりに 128
2.2.5 超小型緑色SHGレーザー [岡田 明、関口修利] 129
1. はじめに 129
2. 超小型緑色SHGレーザーの概要 130
3. 技術要素 132
4. 超小型緑色SHGレーザーの効率 139
5. 応用面からの考察 141
6. まとめ 143
2.2.6 光励起半導体レーザーとその波長変換 [金田有史] 145
1. はじめに 145
2. 0PSLとは 146
3. 0PSLの構成と特徴 146
4. 0PSLデバイスの作成 151
5. 0PSLのディスプレイ光源としての適性 152
6. 報告例 155
7. まとめと展望 157
第3章 スペックル除去
3.1 スペックル入門-レーザーディスプレイの画質向上に向けて- [黒田和男] 162
1. スペックルとは 162
1.1 粗面による散乱 162
1.2 分布関数 163
1.3 特性関数とモーメント 165
1.4 コントラスト 167
2. 相関関数 167
2.1 振幅相関関数と強度相関関数 167
2.2 位相因子の相関関数と共分散 167
2.3 表面形状の相関関数と波面の相関関数 168
3. 平均化 170
3.1 スペックルの重畳 170
3.1.1 互いに独立の場合 170
3.1.2 完全に相関がある場合 171
3.2 スペックルによる照明 171
3.2.1 強度の一様な照明 173
3.2.2 スペックル照明 173
3.3 空間平均 174
3.4 時間平均 175
4. 相関関数の伝搬 176
4.1 点像分布関数 176
4.2 像面での相関関数 177
4.3 フレネル回折 178
5. 補足:モーメント定理 179
3.2 スペックル除去方式 [久保田重夫] 180
1. はじめに 180
2. 観側系としての目の特性 180
3. レーザープロジェクターにおけるスペックル低減法 183
第4章 投射技術
4.1 2次元空間変調素子 [竹田圭吾] 194
1. はじめに 194
2. プロジェクターの歴史 194
2.1 CRTプロジェクター 194
2.2 光書き込み式プロジェクター 195
2.3 マイクロデイスプレイベースプロジェクター 195
3. プロジェクターの基本原理と特長 196
3.1 プロジェクターの分類 196
3.2 HTPS方式 197
3.3 LCOS方式 198
3.4 DLPR(R)方式 199
4. プロジェクター用光源の特長と課題 202
4.1 超高圧水銀ランプ 202
4.2 LED光源 202
4.3 レーザー光源 203
5. プロジェクターの市場と技術動向 204
5.1 プロジェクターの市場規模 204
5.2 データ系プロジェクター 204
5.3 ビデオ系プロジェクター 205
5.4 超小型プロジェクター 205
6. 今後の展望 206
4.2 1次元空間変調素子-Grating Light VaIve Projector- [久保田重夫] 208
1. はじめに 208
2. スキャン投射方式の特質 208
3. 一次元SLMとしての回折格子型MEMS 210
3.1 変調原理と階調特性 210
3.2 高速応答性 212
4.3 ラスタースキャン
4.3.1 MEMS [年吉 洋] 216
1. MEMS光学系 216
2. MEMS光スキャナの性能指数 218
3. 圧電駆動MEMS光スキャナの例 220
4. 電磁駆動MEMS光スキャナの例 222
5. 通電加熱駆動MEMS光スキャナの試作例 223
6. 静電駆動MEMS光スキャナの試作例 224
7. MEMS光スキャナの検討課題 225
4.3.2 変調 [村田博司] 231
1. はじめに 231
2. 光変調方式 233
3. 位相変調による光パルス生成 235
4. 光変調とスペックル 238
5. むすび 239
4.3.3 偏向 [藤浦和夫] 240
1 はじめに 240
2. 可動ミラー方式 241
2.1 ポリゴンミラー 242
2.2 ガルバノスキャナ 243
3. 屈折率変調型スキャナ 244
3.1 音響光学効果スキャナ 245
3.2 電気光学効果スキャナ 246
3.2.1 プリズム型電気光学効果スキャナ 246
3.2.2 屈折率分布型電気光学効果スキャナ 248
4. 終わりに 251
第5章 ディスプレイ装置
5.1 超小型プロジェクター-ラスタースキャン方式- [乙幡大輔] 254
1. はじめに 254
2. レーザースキャン方式の表示原理 255
2.1 表示原理 255
2.2 レーザースキャン方式の特長 256
3. プロジェクターの構成 256
4. 光学部 257
4.1 RGBレーザー 258
4.2 光スキャナー 258
4.2.1 光スキャナーの周波数 258
4.2.2 光スキャナーの駆動方式 259
4.2.3 ミラー位置の検知 259
5. スキャナー制御部 260
6. レーザー制御部 261
7. 日本信号(株)のMEMS光スキャナー“ECOSCAN”の特長 261
7.1 “ECOSCAN”の特長 262
7.2 1軸スキャナータイプと2軸スキャナータイプの比較 262
7.3 実装の小型化 263
7.4 外観と仕様 264
8. 課題 265
9. おわりに 265
5.2 レーザーTV [笹川智広] 267
1. はじめに 267
2. 「レーザTV : LASERVUE(R)」 267
3. 「レーザTV]のレーザー光源 270
4. 「レーザTV」の光学系 271
5. 「レーザTV」の画像処理 274
6. まとめ 275
5.3 直視型液晶デイスプレイ [藤枝一郎] 277
1. はじめに 277
2. 最近のバックライトの研究 278
2.1 諸性能の向上 278
2.2 新機能の付与 279
3. レーザーを利用したバックライト 280
3.1 青色LDと蛍光体を用いる構成 282
3.2 3色レーザーを用いる構成 284
3.3 大面積化に向けて 286
4. まとめ 287
5.4 ヘッドマウントディスプレイ-ラスタースキャン方式- [山田祥治] 290
1. はじめに 290
2. 動作原理 290
3. 構成例と動作の詳細 291
4. MEMS走査器とHMDの試作例 294
5. 奥行き変調の可能性 295
6. おわりに 298
索引 299
第1章 総説 [山本和久] 2
1. レーザーディスプレイの歴史と特徴 2
2. レーザーディスプレイの主要技術 4
94.
図書
東工大
佐藤佳晴監修
目次情報:
続きを見る
<課題編(基礎,原理,解析)>
序章 有機EL技術の現状と課題(佐藤佳晴)
1. はじめに 3
2. 高効率化 3
3. 長寿命化 8
4. 今後の展望 9
第1章 長寿命化技術
1. 材料からのアプローチ(佐藤佳晴) 14
1.1 劣化原因 14
1.2 有機材料の改善 15
1.2.1 ガラス転移温度 15
1.2.2 電気化学的安定性 16
1.3 有機EL材料の使いこなし技術 16
1.3.1 ドーピング 16
1.3.2 混合ホスト 17
1.4 電極界面の制御 19
2. マルチフォトン有機EL素子(松本敏男) 22
2.1 概説 22
2.1.1 マルチフォトン素子の構造と利点 22
2.2 マルチフォトン構造に至る開発経緯 24
2.2.1 「化学ドーピング層」 24
2.2.2 透明電極で複数の有機ELを直列接続したマルチフォトン素子 29
2.2.3 絶縁性電荷発生層の探索 31
2.3 マルチフォトン構造が解決する課題 35
2.3.1 耐久性 35
2.3.2 白色化 37
2.3.3 均一発光 37
2.4 おわりに 38
3. 有機EL素子駆動方法(照元幸次) 40
3.1 はじめに 40
3.2 有機EL素子特性 40
3.2.1 電気・光学特性 40
3.2.2 等価回路 41
3.2.3 駆動回路の特徴 41
3.3 PM駆動方式 41
3.3.1 PM駆動方法 41
3.3.2 有機EL素子の特長を考慮したPM駆動方法 42
3.3.3 陰極リセット 42
3.3.4 大電流駆動 43
3.4 AM駆動方式 44
3.4.1 AM駆動方法 44
3.4.2 有機EL素子の特長を考慮したAM駆動方法 45
3.4.3 電流指定方式 45
3.5 おわりに 47
第2章 高発光効率化技術
1. リン光EL素子の原理と発光機構(河村祐一郎,合志憲一,安達千波矢) 48
1.1 Introduction 48
1.2 Ir系リン光材料 49
1.3 Ir(ppy)3のPL機構(I) : 低温におけるIr(ppy)3の特異な発光特性 51
1.4 PL絶対量子収率の測定と濃度依存性 52
1.5 Ir(ppy)3の三重項励起状態の閉じ込めと散逸過程 53
1.6 高強度励起光下におけるIr(ppy)3 : CBP共蒸着膜の光物性 55
1.7 Direct excition形成機構 56
2. 光取り出し効率(三上明義) 58
2.1 内部量子効率と外部量子効率 58
2.1.1 内部量子効率 58
2.1.2 外部量子効率と光取り出し効率 60
2.2 発光特性と光学的効果 62
2.3 光学理論とシミュレーション解析技術 63
2.4 光取り出し効率の向上技術 66
第3章 駆動回路技術
1. TFT技術性能比較(服部励治) 71
1.1 はじめに 71
1.2 TFT寸法 71
1.3 輝度ムラと焼きつき 73
1.4 駆動方法 74
1.5 ディスプレイ寿命 75
1.6 消費電力 76
1.7 製造コスト 77
1.8 おわりに 78
2. ポリシリコン薄膜トランジスタ駆動の有機ELディスプレイ(木村睦) 80
2.1 はじめに 80
2.2 駆動方式の比較 80
2.2.1 基本要素 80
2.2.2 単純駆動法 81
2.2.3 ダイオード接続法 81
2.2.4 電圧プログラム法 82
2.2.5 電流プログラム法 83
2.2.6 カレントミラー法 83
2.2.7 面積階調法 84
2.2.8 時間階調法 84
2.3 駆動方式の分類 85
2.4 新しい駆動方式の提案 86
2.5 有機ELディスプレイのシステムオンパネル 87
2.6 おわりに 89
3. a‐Si技術及びトップエミッション構造(辻村隆俊) 92
3.1 TFTオン電流問題の克服 93
3.1.1 TFTオン電流の設計上制約について 93
3.1.2 トップエミッション構造による設計制約の緩和 94
3.1.3 アモルファスシリコン形成手法によるモビリティー向上 95
3.2 TFT特性変動問題の克服 96
3.2.1 TFT特性変動の設計上制約について 96
3.2.2 電流集中型TFT特性劣化の解明と解決 96
3.2.3 TFTの駆動最適化による特性劣化の最小化 97
3.2.4 有機ELデバイス構造によるTFTストレスの最小化 97
3.2.5 画素補償回路によるTFT特性変動の吸収 98
3.3 世界最大20インチ有機ELディスプレイの実現 99
第4章 プロセス技術
1. ホットウォール(柳雄二) 101
1.1 はじめに 101
1.2 ホットウォール蒸着法の原理 101
1.3 小型ホットウォール蒸着法 103
1.4 大型ホットウォール蒸着法 105
1.5 素子特性 107
1.6 おわりに 107
2. インクジェット(佐藤竜一,吉森幸一,中茂樹,柴田幹,岡田裕之,女川博義,宮林毅,井上豊和) 110
2.1 背景 110
2.2 IJP法による種々のデバイス作製 111
2.2.1 高分子分散系デバイス-デバイスの基礎検討 114
2.2.2 種々の高分子ホスト材料系での発光 117
2.2.3 IJP法による自己整合隔壁有機ELデバイス 121
2.3 結論と今後の展開 126
3. スプレイ塗布(越後忠洋,中茂樹,岡田裕之,女川博義) 129
3.1 背景 129
3.2 スプレイ塗布による有機薄膜の作製 129
3.3 均一成膜のためのシミュレーション 131
3.4 スプレイ膜の形成状態 134
3.5 デバイス特性 136
3.5.1 RGB発光 136
3.5.2 白色発光の試み 137
3.5.3 デュアルスプレイ法の提案と特性 138
3.5.4 低分子化の試み 138
3.6 結論と今後の課題 139
4. Barix Multi-Layer barriers as thin film encapsulation of Organic Light Emitting Diodes(R.J.Visser) 141
4.1. Introduction 141
4.2. Experimental details 144
4.2.1 BarixTM encapsulation 144
4.2.2 Sample Description 145
4.2.3 Sample Testing 145
4.2.4 Accelerated aging and Thermal Shock Testing 146
4.3. Results and Discussion 147
4.3.1 Building and testing of a robust barrier structure and process, results on Calcium test samples 147
4.3.2 Encapsulation of OLED bottom emission test samples 149
4.3.3 Top Emission pixels 150
4.3.4 Passive matrix displays 151
4.3.5 Industrialisation Conclusion 152
<材料編(課題を克服する材料)>
第5章 電荷輸送材料
1. 正孔注入材料(佐藤佳晴) 157
1.1 はじめに 157
1.2 高分子正孔注入材料 158
1.3 高分子正孔注入層を用いた素子の発光特性 519
1.4 まとめと今後の材料開発 162
2. 正孔輸送材料(榎田年男) 164
2.1 はじめに 164
2.2 有機EL素子の動作原理 164
2.3 低分子正孔輸送材料 166
2.4 おわりに 170
3. 電子輸送材料(内田学) 171
3.1 はじめに 171
3.2 電子輸送材料開発 171
3.3 チッソ(株)の電子輸送材料 172
3.3.1 シロール系電子輸送材料 172
3.3.2 最近の開発 172
3.4 おわりに 176
第6章 発光材料
1. 低分子発光材料の現状(細川地潮) 178
1.1 はじめに 178
1.2 低分子有機EL材料の到達点 178
1.3 出光での開発の現状 181
1.3.1 正孔材の改良 181
1.3.2 青色ホスト材料の改良 182
1.3.3 フルカラー用純青材料 183
1.4 青色以外の発光材料の開発 184
1.4.1 緑色 184
1.4.2 赤色 184
1.4.3 橙色 185
1.4.4 混合ホスト 185
1.4.5 黄色 185
1.5 白色発光材料 186
1.6 おわりに 188
2. 蛍光ドーパント(皐月真,菅貞治) 190
2.1 はじめに 190
2.2 ドーパントとしてのクマリン色素の開発 190
2.2.1 緑色ドーパント 190
2.2.2 赤色,青色ドーパント 194
2.3 おわりに 196
3. 共役高分子材料(坂本正典) 197
3.1 はじめに 197
3.2 共役系発光材料 198
3.2.1 PPV系材料 198
3.2.2 PF系材料 198
3.2.3 Poly-Spiro系材料 198
3.3 共役高分子有機ELの発光色 199
3.4 共役高分子有機ELの寿命 199
3.4.1 共役系高分子発光素子の寿命 199
3.4.2 発光高分子の寿命の原因 200
3.4.3 発光高分子材料の長寿命化 201
3.5 共役高分子有機EL素子の長寿命化 202
3.5.1 共役高分子有機ELデバイスの寿命原因 202
3.5.2 界面の課題 202
3.5.3 ホール輸送材料(HTL)の課題 203
3.5.4 電極と電荷バランス 203
3.6 おわりに 204
第7章 リン光用材料
1. リン光ドーパント(岡田伸二郎) 206
1.1 リン光性発光ドーパントの特徴 206
1.2 これまでに発表されたリン光ドーパント 208
1.3 発光色の制御 208
1.4 金属錯体の安定性 210
1.5 量子収率の設計 212
1.6 おわりに 213
2. リン光ホスト材料(都築俊満,時任静士) 215
2.1 はじめに 215
2.2 ホスト材料の役割と求められる特性 215
2.3 赤~緑色リン光素子用の低分子ホスト材料 217
2.4 青色リン光素子用の低分子ホスト材料 219
2.5 高分子ホスト材料 222
2.6 おわりに 222
3. 正孔阻止材料(佐藤佳晴) 225
3.1 リン光発光素子 225
3.2 正孔阻止層 225
3.3 今後 227
第8章 周辺材料
1. ダイニック(株)の水分ゲッター材「HGS(Humidity Getter Sheet)」(内堀輝男) 229
1.1 はじめに 229
1.2 有機ELのダークスポットについて 230
1.3 ダイニックの水分ゲッター材HGS 231
1.3.1 水分ゲッターの反応機構 231
1.3.2 水分ゲッターシートの構造 232
1.3.3 水分ゲッターシートの吸湿特性 232
1.3.4 シートの厚さ 234
1.3.5 水分以外の劣化成分の除去 235
1.3.6 酸素に対する特性 235
1.3.7 水分ゲッターの供給形態 236
1.4 今後の動向 237
2. 有機EL用透明薄膜捕水剤“OleDry(R)”の開発(鶴岡誠久) 239
2.1 概要 239
2.2 まえがき 239
2.3 OleDry(R)とは? 240
2.4 OleDry(R)を使用することによる薄型パッケージの実現 240
2.5 OleDry(R)の特性 241
2.5.1 OleDry(R)の水分吸着能力 241
2.5.2 OleDry(R)によるダークスポット抑制効果 241
2.5.3 OleDry(R)塗布量と保存寿命の改善効果 241
2.5.4 OleDry(R)の電気的,光学的特性に及ぼす影響 242
2.6 OleDry(R)の応用 242
2.7 まとめ 243
3. 封止材料(堀江賢一) 244
3.1 はじめに 244
3.2 シール材に求められる特性 244
3.3 紫外線硬化性樹脂とは 245
3.4 有機EL用シール剤 247
3.5 有機EL用シール剤の今後の課題 250
3.6 固体封止について 251
3.7 おわりに 252
4. アルカリメタルディスペンサー~陰極材料としてのアルカリ金属蒸発源(前田千春) 253
4.1 はじめに 253
4.2 陰極材料としてのアルカリ金属 253
4.3 バッファー層としてのアルカリ金属ドープ層とその効果 254
4.4 アルカリメタルディスペンサー(AMD)の特長 255
4.5 おわりに 258
第9章 各社ディスプレイ技術
1. 東芝モバイルディスプレイ(株)(旧東芝松下ディスプレイテクノロジー(株))における有機ELディスプレイ技術(羽成淳) 259
1.1 はじめに 259
1.2 低温ポリシリコン技術の活用 259
1.3 低分子有機ELディスプレイの開発 260
1.4 高分子有機ELディスプレイの開発 261
1.5 有機ELディスプレイの駆動技術 262
1.6 有機ELディスプレイの開発例 263
1.7 おわりに 264
2. 日立における有機ELディスプレイ技術(秋元肇) 266
2.1 はじめに 266
2.2 有機ELディスプレイの駆動方式 266
2.3 発光期間変調を実現する画素回路 267
2.4 ピーク輝度 269
2.5 おわりに 270
3. ロームにおける有機ELディスプレイ技術(高村誠) 272
3.1 はじめに 272
3.2 ロームの有機ELディスプレイ 272
3.2.1 CEATECジャパン2001,2002出展品 272
3.2.2 CEATECジャパン2003出展品 274
3.3 有機ELディスプレイの技術課題 275
3.3.1 素子寿命 275
3.3.2 絶縁破壊(輝線)およびダークスポット(暗点) 277
3.3.3 技術的なコスト 278
3.4 まとめ 278
<課題編(基礎,原理,解析)>
序章 有機EL技術の現状と課題(佐藤佳晴)
1. はじめに 3
95.
図書
東工大
遠藤剛編 ; 澤本光男 [ほか] 著
出版情報:
東京 : 講談社, 2010.4 xii, 458, 9p ; 22cm
シリーズ名:
高分子の合成 ; 上
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
発刊にあたって ⅲ
第1編 ラジカル重合 1
1章 ラジカル重合とは 3
2章 ラジカル重合に用いられるモノマーと得られるポリマー 7
2.1 エチレン 7
2.2 一置換エチレン 7
2.3 1.1-二置換エチレン 10
2.4 1.2-二置換エチレン 11
2.5 その他の置換エチレン 12
2.6 ジエン化合物 12
2.7 その他のラジカル重合性モノマー 13
2.8 共重合体 14
3章 フリーラジカル重合の素反応 17
3.1 開始反応 17
3.1.1 開始剤 19
3.1.2 開始反応速度と末端基の検出 26
3.2 生長反応 27
3.2.1 生長反応速度定数の決定 27
3.2.2 種々のモノマーの生長反応速度定数 28
3.2.3 生長反応の熱力学的平衡 30
3.2.4 立体規則性 32
3.2.5 頭-頭付加および頭-尾付加 35
3.2.6 共役ジエンの生長反応 36
3.2.7 生長ラジカルの転位・異性化 37
3.2.8 特殊な生長反応 38
3.3 停止反応 39
3.3.1 生長反応と停止反応 40
3.3.2 不均化と再結合 42
3.3.3 不均一系における停止反応 44
3.3.4 重合の禁止と抑制 44
3.3.5 重合の禁止とリビング重合 46
3.4 連鎖移動反応 47
3.4.1 モノマーおよびポリマーに対する連鎖移動反応 48
3.4.2 開始剤に対する連鎖移動反応 50
3.4.3 溶媒に対する連鎖移動反応 51
3.4.4 連鎖移動剤 51
3.4.5 付加-開裂型連鎖移動反応 53
3.4.6 触媒的連鎖移動反応 55
3.4.7 連鎖移動定数の決定と分子量 55
3.4.8 連鎖移動反応とリビング重合 57
4章 ラジカル共重合 59
4.1 共重合の分類 59
4.2 ランダム共重合 60
4.3 共重合組成曲線とモノマー反応性比 63
4.4 モノマー反応性比の決定 65
4.5 交互共重合 68
4.6 種々のモノマー反応性の予測 69
5章 種々の反応場における重合反応およびポリマー製造プロセス 73
5.1 塊状重合 74
5.2 溶液重合 74
5.3 懸濁重合 75
5.4 乳化重合 76
5.5 沈殿重合,分散重合 77
5.6 固相重合 78
5.7 その他の重合方法 78
6章 リビングラジカル重合 81
6.1 リビングラジカル重合の概念 81
6.2 リビングラジカル重合の方法 84
6.3 ニトロキシドを用いた重合 87
6.4 遷移金属触媒を用いた重合 89
6.5 ジチオエステルを用いた重合 95
6.6 その他のリビングラジカル重合系 98
7章 リビングラジカル重合を用いた精密高分子合成 99
7.1 末端官能性ポリマー 100
7.1.1 開始剤法 100
7.1.2 停止剤法あるいは末端基変換法 102
7.2 ランダム共重合体およびグラジエント共重合体 104
7.3 ブロック共重合体 105
7.4 グラフトボリマー 108
7.5 星型ポリマー 110
7.6 リビングラジカル重合の精密高分子合成へのその他の展開 113
8章 ラジカル重合における立体構造の制御 : 立体特異性ラジカル重合 115
8.1 拘束空間内での重合 115
8.1.1 結晶状態での重合 115
8.1.2 包接重合 116
8.1.3 多孔性物質内での重合 118
8.1.4 テンプレート重合 118
8.2 モノマー設計に基づく立体構造制御 119
8.2.1 かさ高いモノマーの重合 119
8.2.2 キラル補助基をもつモノマーの重合 122
8.2.3 自己会合性基をもつモノマーの重合 123
8.3 溶媒および添加物に基づく立体構造制御 123
8.3.1 溶媒による立体特異性ラジカル重合 124
8.3.2 ルイス酸による立体特異性ラジカル重合 126
8.3.3 イオン相互作用を用いた立体特異性ラジカル重合 127
8.3.4 多重水素結合を用いた立体特異性ラジカル重合 128
9章 まとめと展望 131
参考書・文献 135
第II編 カチオン重合 147
1章 カチオン重合とは 149
2章 カチオン重合の基礎 155
2.1 カチオン重合の特徴と他の重合系との比較 155
2.1.1 求電子付加反応とカチオン重合 155
2.1.2 カチオン重合の素反応 156
2.1.3 ラジカル重合およびアニオン重合との違い 156
2.2 カチオン重合で用いられるモノマー 158
2.2.1 カチオン重合で使用されるビニルモノマー 158
2.2.2 各種モノマーの反応性 159
2.2.3 ビニルモノマーの構造と反応性 161
2.2.4 多置換不飽和化合物の構造と反応性 161
2.3 カチオン重合で用いられる開始剤と開始反応 163
2.3.1 プロトン酸 163
2.3.2 ハロゲン化金属 165
2.3.3 ハロゲン 170
2.3.4 光・熱潜在性触媒 : 光照射や加熱によるカチオン重合泉 171
2.3.5 その他の開始剤系 173
2.4 生長反応 174
2.4.1 カルボカチオンと生長種の解離状態 174
2.4.2 ポリマーの構造 177
2.4.3 異性化重合 178
2.4.4 ポリマーの立体構造 181
2.4.5 共重合 183
2.5 停止反応 186
2.5.1 カチオン重合における停止反応 187
2.5.2 停止反応を考慮したカチオン重合の速度式 188
2.6 連鎖移動反応 189
2.6.1 連鎖移動反応とは 189
2.6.2 連鎖移動反応の機構 192
2.6.3 連鎖移動反応の速度論 : 連鎖移動定数比 193
2.7 選択的オリゴメリゼーションとそれを用いたポリマー合成 194
2.7.1 石油樹脂 195
2.7.2 選択的2量化および選択的オリゴマー生成 195
2.7.3 連鎖移動反応を利用した高分子合成 197
3章 リビングカチオン重合 201
3.1 リビングカチオン重合の反応機構の概略 201
3.1.1 開始反応 201
3.1.2 生長反応 202
3.2 リビングカチオン重合の方法論 203
3.2.1 求核性の強い対アニオン+比較的弱いルイス酸 203
3.2.2 求核性の強い対アニオン+強いルイス酸+添加物 203
3.2.3 その他の開始剤系 204
3.3 リビング重合の開始剤系 205
3.3.1 ビニルエーテル 205
3.3.2 イソブテン 215
3.3.3 スチレン類 220
3.3.4 リビング重合発見までの経緯 226
3.4 リビング重合のまとめと展望 232
4章 新しいモノマーのカチオン重合 235
4.1 自然界に存在する化合物およびその誘導体 235
4.2 ジエン類 236
4.3 種々の官能基を有するビニルエーテル,スチレン誘導体 237
4.3.1 官能基を有するビニルエーテル 237
4.3.2 官能基を有するスチレン誘導体 239
5章 刺激応答性ポリマー 241
5.1 温度応答性ポリマー 242
5.2 刺激応答性ブロック共重合体 246
6章 ブロック共重合体 249
6.1 ブロック共重合体の合成法 249
6.1.1 ビニルエーテルを有するブロック共重合体 250
6.1.2 イソブテンを有するブロック共重合体 252
6.2 重合末端変換によるブロック共重合体合成 253
6.2.1 ラジカル重合 253
6.2.2 アニオン重合,グループトランスファー重合 255
6.2.3 開環重合 257
6.3 分子量分布とシークエンスの制御されたポリマーの合成 : 連続重合を用いた方法258
6.3.1 分子量分布の制御 258
6.3.2 組成分布の制御 : グラジエント共重合体の合成 260
6.4 新規多分岐ポリマーの合成 261
7章 末端官能性ポリマー 263
7.1 官能基を有する開始剤を用いる方法 263
7.2 官能基を有する停止剤を用いたキャッピング法 264
7.3 テレケリックポリマーの合成 267
8章 官能基を有する星型ポリマーの精密合成 269
8.1 精密構造を有する星型ポリマーの高選択的合成 269
8.2 ナノカプセルとしての星型ポリマー 272
8.3 ナノ反応場としての星型ポリマー : 触媒金属微粒子の担持 273
9章 まとめと展望 275
参考書・文献 277
第III編 アニオン重合 297
1章 アニオン重合とは 299
2章 アニオン重合に用いられるモノマー,開始剤,および溶媒 303
2.1 モノマーの分類 303
2.1.1 ビニルモノマー 303
2.1.2 ヘテロ多重結合を有するモノマー 310
2.1.3 環状モノマー 313
2.2 開始剤の分類 316
2.3 溶媒の選択 319
3章 アニオン重合の素反応 321
3.1 開始反応 321
3.2 生長反応 325
3.3 停止反応 327
3.4 連鎖移動反応 331
4章 ポリマーの構造規制と立体制御 335
4.1 1,3-ブタジエンとイソプレンのアニオン重合 335
4.2 メタクリル酸メチルの立体規則性重合 339
5章 アニオン重合の工業的利用 343
6章 リビングアニオン重合 345
6.1 リビング重合とは 345
6.2 炭化水素系モノマー類 348
6.3 極性モノマー類 353
6.4 官能基を有するモノマー類 357
6.5 環状モノマー-類 366
6.6 リビングアニオン重合の特色とまとめ 368
7章 リビングアニオン重合を用いたarchitectural polymerの精密合成 371
7.1 architectural polymer合成とは 371
7.2 末端官能性ポリマー 374
7.3 ブロック共重合体 381
7.4 グラフトボリマー 387
7.5 櫛型ポリマー 390
7.6 環状ポリマー 393
7.7 星型ポリマー 395
7.8 樹木状多分岐ポリマー 402
7.9 混合型分岐ポリマー 409
8章 ポリマーの表面構造 415
8.1 親水性セグメントと疎水性セグメントからなるブロック共重合体 416
8.2 パーフルオロアルキルセグメントを有するブロック共重合体 418
9章 ミクロ相分離構造を利用したナノ材料 425
9.1 異相系ポリマーのミクロ相分離構造 425
9.2 ミクロ相分離構造を利用したナノ多孔質材料 431
9.3 ミクロ相分離構造とナノ微細加工を用いたナノ物質433
10章 まとめと展望 441
参考書・文献 445
発刊にあたって ⅲ
第1編 ラジカル重合 1
1章 ラジカル重合とは 3
96.
図書
東工大
東山三樹夫著
目次情報:
続きを見る
1. 本書の概要
2. 振動とその周期
2.1 運動の法則とばねの自由振動 14
2.1.1 ばねと質量の振動系 14
2.1.2 自由振動 16
2.2 自由振動のエネルギーと固有振動数 17
2.2.1 位置エネルギーと運動エネルギー 17
2.2.2 エネルギー保存則と自由振動の角振動数 19
2.3 減衰する自由振動 20
2.3.1 減衰振動の表現 20
2.3.2 減衰振動の振動数 21
2.4 共鳴現象とエネルギー平衡の原理 22
2.4.1 持続する外力による振動 22
2.4.2 共鳴現象 24
2.4.3 エネルギー平衡の原理 26
2.5 連成振動 26
2.5.1 振り子の振動 27
2.5.2 結合振子の固有振動数 28
2.5.3 結合の強さによる振動の変化 28
2.5.4 うなり 30
2.5.5 防振・耐震と共鳴現象 31
3. 共鳴器と気体の性質
3.1 共鳴器 33
3.1.1 体積弾性率 33
3.1.2 共鳴器の固有振動数 34
3.1.3 スピーカとスピーカ箱による共鳴器 36
3.2 気体の法則 39
3.2.1 気体の圧力と体積 39
3.2.2 熱量と比熱 41
3.2.3 断熱変化における体積と温度 42
3.2.4 体積弾性率 43
4. 音の速さと波が伝わる仕組み
4.1 ばねの連鎖と振動の伝搬 45
4.1.1 ばね振動とエネルギーの伝搬 45
4.1.2 振動が伝わる速さ 48
4.1.3 波動方程式とその解 49
4.2 音・振動の伝搬に伴うエネルギーと音の速さ 52
4.2.1 音の速さ 55
4.2.2 弦を伝わる波の速さ 57
4.3 波源と平面波の伝搬 58
4.3.1 平面波の音圧と振動速度 58
4.3.2 音の大きさと音圧レベル 64
4.3.3 平面波を伝えるエネルギー 65
4.3.4 速度駆動音源と平面波の伝搬 66
4.4 波の速さと音の放射 66
4.4.1 振動体からの音の放射 67
4.4.2 移動音源による音の放射と衝撃波 69
5. 弦を伝わる振動と波
5.1 長い弦を伝わる波 72
5.1.1 初期変位が伝わる波 72
5.1.2 初期速度が伝わる波 73
5.1.3 初期条件と波の伝搬 74
5.2 有限な長さをもつ弦を伝わる波 76
5.2.1 一端が固定された弦と反射波 76
5.2.2 両端固定弦の振動 78
5.2.3 波の図解 79
5.3 弦の自由振動 81
5.3.1 弦の発音条件 81
5.3.2 基本周期と倍音 82
5.3.3 自由振動を構成する波の形と固有振動 83
5.3.4 固有振動の重ね合せと倍音の抑制 86
5.4 音律を構成する倍音列 87
5.4.1 オクターブの計算 87
5.4.2 ピタゴラス音律の構成 88
6. 音響管を伝わる波動現象
6.1 管内を往復する平面波 91
6.1.1 管内を進む波 91
6.1.2 音響管の基本振動数と倍音 92
6.1.3 音響管内の固有振動姿態 95
6.1.4 固有振動姿態の音圧と振動速度 97
6.2 駆動音源とその働き 98
6.2.1 音の発振現象(ハウリング) 98
6.2.2 エッジトーン 99
6.2.3 音響管の駆動方式 102
6.3 音響管から放射される音のエネルギー 104
6.3.1 開口端の音響条件 104
6.3.2 開口端補正 105
6.4 円錐形音響管 106
6.4.1 円錐形音響管の固有振動数 106
7. 平面波の伝搬
7.1 平面波の入射と反射 108
7.1.1 ホイヘンスの原理と平面波の反射 109
7.1.2 最小作用の原理と反射の法則 110
7.1.3 境界条件と反射係数 110
7.2 平面波の透過と屈折 113
7.2.1 入射角と透過角 113
7.2.2 屈折とスネルの法則 115
7.2.3 屈折現象に関する最小作用の原理 115
7.2.4 音波の屈折と音の聞こえ方 116
7.3 波の干渉 117
7.3.1 同一振動数を有する波の加算 117
7.3.2 逆向き平面進行波の重畳 119
7.3.3 波の干渉によって生じる音圧分布(干渉縞) 120
7.3.4 バスレフ形スピーカシステムによる音の干渉 122
7.3.5 反射音による音の干渉 126
7.3.6 平面波の不規則重畳 128
8. 球面波の伝搬
8.1 球面波による音圧と振動速度 131
8.1.1 呼吸球と対称球面波 132
8.1.2 点音源による音圧と振動速度 133
8.1.3 媒質の非圧縮性効果 136
8.2 音源の音響出力 138
8.2.1 点音源の強さと球面波のエネルギー 138
8.2.2 点音源の音響出力 139
8.2.3 反射壁による音源の音響出力の変化 141
8.2.4 位相差をもって振動する一組の音源対による音響出力 143
8.3 初期変位と球面波の伝搬 144
8.3.1 初期条件と球面波の伝搬 144
8.3.2 前方波面と後方波面 148
8.4 音波の回折と散乱 149
8.4.1 フレネルゾーン 149
8.4.2 フレネルゾーンと回折現象 151
8.4.3 音波の散乱 154
9. 室内を伝わる音
9.1 室内を伝わる音のエネルギー 156
9.1.1 室内音場におけるエネルギー平衡 156
9.1.2 定常状態における室内の音のエネルギー 157
9.1.3 音源が停止した後の音のエネルギー変化 158
9.2 室内の固有振動数 160
9.2.1 固有振動数の表現 160
9.2.2 固有振動数の分布 161
9.2.3 固有振動の縮退 162
9.2.4 固有振動数と固有振動姿態 163
9.2.5 固有振動数の数と密度 165
9.3 エネルギー伝達特性 167
9.3.1 音源音響出力の振動数による変化 167
9.3.2 室内残響時間と共鳴特性 169
9.3.3 固有振動の密度とエネルギー伝達特性 170
9.4 室内音場の直接音と反射音 172
9.4.1 音源から発するインパルス音 172
9.4.2 室内音場における反射音の数とエネルギー 173
9.4.3 直接音が室内における音のエネルギーに占める割合 177
9.4.4 反射音の図解と音のカオス 178
付録 182
引用・参考文献 184
結び : 共鳴現象をめぐって 188
索引 190
1. 本書の概要
2. 振動とその周期
2.1 運動の法則とばねの自由振動 14
97.
図書
東工大
田中賢一著
出版情報:
東京 : 共立出版, 2010.1 ix, 168p, 図版 [8] p ; 21cm
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第1章 画像工学の歴史的概観 1
1.1 印象派芸術と物理学 1
1.2 印刷技術から印写技術へ 4
1.2.1 印象派芸術の時代までの印刷技術 4
1.2.2 写真技術からホログラフィへの発展 4
1.3 電子印刷への発展 4
1.4 点描の手法と電子印刷との関連 6
1.5 近年の動き 6
第2章 画像入力デバイス 8
2.1 半導体素子について 8
2.1.1 半導体とは何か 8
2.1.2 pn 接合ダイオード 10
2.1.3 バイポーラトランジスタ 12
2.1.4 J-FE 14
2.1.5 MOS-FE 15
2.1.6 マイクロコンピュータ 17
2.2 カメラ 17
2.2.1 カメラの結像光学系 17
2.2.2 カメラの撮像素子 18
2.3 スキャナ 23
2.4 指紋センサ 25
第3章 テレビジョン 28
3.1 ディジタル放送システムとは 28
3.2 ディジタル放送のしくみ 31
3.2.1 圧縮符号化 32
3.2.2 多重化 33
3.2.3 伝送路符号化 33
3.3 地上ディジタル放送 35
3.4 ハイビジョンの諸元 39
3.5 ディジタル信号の伝送 39
第4章 電子ディスプレイ 43
4.1 液晶ディスプレイ 43
4.2 プラズマディスプレイ 47
4.2.1 カラーPDP の構造 47
4.2.2 カラーPDP の表示 49
4.3 有機EL ディスプレイ 50
4.4 CRT ディスプレイ 52
4.5 電子ディスプレイの画質評価 55
第5章 プリンタ 56
5.1 サーマル記録 56
5.1.1 サーマル記録とは 56
5.1.2 サーマルプリンタ 57
5.2 電子写真記録 59
5.3 インクジェットプリンタ 63
5.3.1 インクジェットプリンタの原理 64
5.3.2 インクジェットヘッド 64
第6章 光と画像 68
6.1 レンズのフーリエ変換作用 68
6.1.1 ホイヘンス―フレネルの式とフレネル回折 69
6.1.2 レンズのフーリエ変換作用 70
6.2 光の干渉 72
6.3 可干渉性(コヒーレンス 75
6.4 色 76
6.4.1 加法混色 77
6.4.2 減法混色 78
6.4.3 表色系 78
6.4.4 コンピュータ画像処理における色空間 79
第7章 画像処理の基礎 83
7.1 階調変換 83
7.1.1 ネガ・ポジ変換 83
7.1.2 ヒストグラムの均一化 84
7.1.3 ガンマ補正 84
7.2 画像のフィルタリング 84
7.2.1 平均値フィルタ 86
7.2.2 ガウシアンフィルタ 86
7.2.3 メディアンフィルタ 88
7.2.4 画像の1 次微分 88
7.2.5 ラプラシアンフィルタ 91
7.3 ハーフトーン処理 93
7.3.1 画像の2 値化 94
7.3.2 ディザ法 94
7.3.3 誤差拡散法 95
7.4 画像の評価 98
第8章 画像のフォーマットならびに画像符号化103
8.1 各種画像フォーマット 103
8.1.1 静止画 103
8.1.2 動画 106
8.2 画像符号化 109
8.2.1 静止画の符号化(JPEG 109
8.2.2 動画の符号化(MPEG 111
8.2.3 MPEG-1, MPEG-2 の概要 113
第9章 パターン認識 118
9.1 マッチングの原理 118
9.2 テンプレートマッチング 121
9.3 位相限定相関法 123
第10章 CG,VR,立体映像 126
10.1 コンピュータグラフィックス 126
10.1.1 2次元コンピュータグラフィックス 127
10.1.2 3次元コンピュータグラフィックス 128
10.2 バーチャルリアリティ 130
10.2.1 ヘッドマウンテッドディスプレイ 131
10.2.2 プロジェクション型没入ディスプレイ 132
10.3 3次元ディスプレイ 133
10.3.1 立体メガネ 134
10.3.2 レンチキュラ方式 134
10.3.3 ホログラフィックディスプレイ 134
第11章 セキュリティ・知的所有権への応用 139
11.1 情報セキュリティ・知的所有権の保護 139
11.1.1 電子透かし 140
11.1.2 ディジタル放送の録画 140
11.1.3 コピーコントロール 141
付録A フーリエ変換 142
A.1 1次元のフーリエ変換 142
A.2 2次元のフーリエ変換 143
A.3 フーリエ変換の性質 143
A.4 計算機上でのフーリエ変換 144
付録B 用語集 145
参考文献 157
索引 158
コラム
オートフォーカス 23
SDT 30
ワンセグ放送 38
アナログテレビジョン受像器とディジタルテレビジョン受像器を同時に視聴すると 41
タッチパネル 47
ドットインパクトプリンタ 66
視力 82
シミ・しわの除去 93
Len 101
符号化における画質の劣化 116
DP マッチング 123
リモートセンシング 125
芸術としてのメディア技術 130
アミューズメント機器 138
第1章 画像工学の歴史的概観 1
1.1 印象派芸術と物理学 1
1.2 印刷技術から印写技術へ 4
98.
図書
瀧本往人著
出版情報:
東京 : 工学社, 2016.3 159p ; 21cm
シリーズ名:
I/O books
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第1章 「IoT」「M2M」の概要 : 組み込み機器の現在と未来
「IoT」と「M2M」
人工知能
ロボット
第2章 「IoT」「M2M」のネットワークの基本構造 : 収集 / センサ
伝送 / 通信
解析
実行
第3章 「IoT」「M2M」の事例と課題 : 移動媒体
ドローン
電力
「脅威」と「セキュリティ」
第1章 「IoT」「M2M」の概要 : 組み込み機器の現在と未来
「IoT」と「M2M」
人工知能
概要:
「IoT」とは「Internet of Things」の略で、「モノのインターネット」を意味する言葉で、よく似た言葉として、「M2M」(Machine to Machine)という言葉もあります。これら2つのキーワードは、何が同じで、どこが
…
違うのでしょうか。本書では、「IoT」「M2M」の成り立ちや仕組み、それぞれの共通事項や相違点、「クラウド」「ビッグデータ」「ロボット」「人工知能」「深層学習」といった先端技術との関わり方、「IoT」「M2M」の実例と解決すべき課題などを詳しく解説しています。
続きを見る
99.
図書
東工大
吉原利一編
出版情報:
東京 : オーム社, 2010.3 xii, 345p, 図版[2]p ; 21cm
シリーズ名:
地球環境テキストブック
子書誌情報:
loading…
所蔵情報:
loading…
目次情報:
続きを見る
第1章 環境とは,環境汚染とは何か 吉原利一
1.1 環境とは? 2
1.1.1 環境という言葉の定義,類似の言葉 2
1.1.2 環境認識の拡大と有限性 4
1.1.3 さまざまな環境と環境要因 6
1.1.4 地球という環境 7
1.2 環境問題とは? 8
1.2.1 なぜ環境問題が生じるのか? 8
1.2.2 環境問題の変遷と直面する課題 9
演習問題 10
参考文献 10
ウェブサイト 11
第2章 環境を形作るもの-元素と物質- 大山聖一
2.1 環境を構成するもの 14
2.2 元素と原子の構造 14
2.3 周期律と周期表 16
2.3.1 典型元素と遷移元素 16
2.3.2 金属元素と非金属元素 16
2.4 原子の結合様式(化学結合) 18
2.4.1 一次結合 18
2.4.2 二次結合(分子間力) 19
2.5 物質量を数えるために-単位系について- 20
2.5.1 物質量,原子量,分子量 20
2.5.2 SI単位系 21
2.5.3 濃度の表し方 23
2.6 有機化合物と無機化合物 24
2.6.1 無機化合物と有機化合物の違い 24
2.6.2 有機化合物の構造と分類 25
2.6.3 環境問題と関わりの深い化合物 31
2.7 生命を形作る重要物質 33
2.7.1 タンパク質 34
2.7.2 糖質 35
2.7.3 核酸 36
演習問題 39
参考文献 39
ウェブサイト 39
第3章 環境を形作るもの-生態系- 阿部聖哉
3.1 生態系とは 42
3.1.1 生物の分布と環境 42
3.1.2 生態系の物質生産 44
3.1.3 植物群落の時間的な発達 46
3.1.4 食物連鎖とエネルギー 48
3.1.5 生態系の物質循環 51
3.2 生物と生態系の多様性 54
3.2.1 競争と種の共存 54
3.2.2 種多様性を維持するメカニズム 56
3.2.3 生態系の多様性 59
3.2.4 遺伝的変異と種分化 61
3.2.5 個体群の空間分布と遺伝的多様性 63
3.3 生態系と生物多様性の保全 66
3.3.1 生態系の直接的・間接的価値 66
3.3.2 生態系の破壊と生物多様性の危機 68
3.3.3 生態系保全のための方策 70
演習問題 74
参考文献 74
ウェブサイト 75
第4章 大気の汚染 吉原利一
4.1 大気 78
4.1.1 大気の組成-現在の大気と太古の大気- 78
4.1.2 大気圏の層構造 81
4.1.3 生物圏における炭素と窒素及びその化合物の循環と蓄積 82
4.2 地球環境問題以前の大気の環境問題 85
4.2.1 煙害 86
4.2.2 粒子状物質 90
4.2.3 光化学スモッグ 92
4.2.4 微量大気汚染物質 95
4.2.5 主な大気汚染物質排出の現状と国際比較 97
演習問題 99
参考文献 99
ウェブサイト 100
第5章 オゾン層の破壊と地球温暖化問題 吉原利一
5.1 オゾン層の破壊 104
5.1.1 オゾンとオゾン層の形成 104
5.1.2 フロンとオゾン層破壊のメカニズム,オゾンホール 105
5.1.3 オゾン層が破壊されると何が起こるか 109
5.1.4 現状と将来予測 109
5.2 地球温暖化問題 110
5.2.1 地球の表面温度をきめるメカニズム 110
5.2.2 温室効果と温暖化 114
5.2.3 温暖化に関する疑念 118
5.2.4 温暖化とその被害を予想する 118
5.2.5 温暖化への取組み 121
演習問題 124
参考文献 124
ウェブサイト 125
第6章 水の汚染 上野大介
6.1 水の性質と水の循環 128
6.1.1 水の特殊な性質 128
6.1.2 水の循環 129
6.2 水環境の汚染 130
6.2.1 富栄養化に関連した水質汚濁 130
6.2.2 化学物質に関連した水質汚濁 138
6.3 水質汚染対応のこれから 157
演習問題 158
参考文献 158
ウェブサイト 158
第7章 酸性雨 河野吉久
7.1 酸性雨とは? 162
7.1.1 酸性雨の定義と生成メカニズム 162
7.1.2 酸性雨の歴史 164
7.1.3 欧米の状況 164
7.1.4 日本の状況 165
7.1.5 東アジアの状況 167
7.2 降雨の組成 168
7.3 河川・湖沼への影響 169
7.3.1 流域単位でみた場合の酸の収支 169
7.3.2 河川・湖沼水のアルカリ度 170
7.3.3 酸性化に伴う水棲生物相の変化 172
7.4 植物影響 172
7.4.1 農作物に対する影響 172
7.4.2 森林の衰退とその原因 175
7.5 土壌の酸性化と酸中和能 179
7.6 コンクリート構造物の劣化 180
7.6.1 劣化因子 181
7.6.2 酸性雨による炭酸化の促進 182
7.7 大陸からの越境汚染とわが国における酸性雨問題の会後の展望 182
演習問題 185
参考文献 186
第8章 土の汚染 長谷川功・川東正幸・野口章
8.1 環境媒体としての土 188
8.1.1 土の成り立ち 188
8.1.2 物質としての土の構成 189
8.1.3 土の反応性 194
8.1.4 土の機能と土壌汚染 196
8.2 重金属による土壌汚染 198
8.2.1 重金属による土壌汚染 198
8.2.2 重金属による土壌汚染の現状 203
8.2.3 重金属による土壌汚染問題への対応 205
8.3 有機汚染物質による土壌汚染 206
8.3.1 化学物質による土壌汚染の歴史的経過 206
8.3.2 有害化学物質の定義と汚染の特徴 209
8.3.3 残留性有機汚染物質(POPs)による土壌汚染 211
8.3.4 有害化学物質による土壌汚染の影響と生物による汚染浄化の試み 214
演習問題 217
参考文献 217
第9章 環境と食の問題 服部浩之
9.1 環境問題が食料生産に及ぼす影響 220
9.1.1 地球温暖化と食料生産 220
9.1.2 砂漠化と食料生産 224
9.1.3 バイオマスエネルギー生産と食料生産 226
9.2 環境汚染が食に及ぼす影響 229
9.2.1 重金属汚染が食に及ぼす影響 229
9.2.2 カドミウムが食に及ぼす影響 230
9.2.3 有機化学物質が食に及ぼす影響 232
9.2.4 食の安全性の担保 233
演習問題 234
参考文献 234
第10章 バイオレメディエーション・ファイトレメディエーション 水野隆文
10.1 バイオレメディエーション 236
10.1.1 バイオレメディエーションとはなにか? 236
10.1.2 バイオレメディエーションに利用される物生物の機能 238
10.1.3 バイオレメディエーションの実用例 239
10.2 ファイトレメディエーション 240
10.2.1 ファイトレメディエーションとはなにか? 240
10.2.2 植物による土壌浄化 242
10.2.3 ファイトレメディエーションによる水・大気の浄化 243
10.2.4 実用化への取組み 244
10.3 分子生物学的な手法を用いた環境浄化用植物・微生物の育種 246
10.3.1 組み換え微生物を用いたバイオレメディエーション研究例 246
10.3.2 植物の育種 247
演習問題 249
参考文献 249
ウェブサイト 250
第11章 環境汚染に対する行政上の対応 山崎邦彦
11.1 環境汚染への対応と化学物質の管理 254
11.1.1 個別汚染への対応と化学物質の包括的管理の視点 254
11.1.2 リスク評価の視点 256
11.2 環境基準 257
11.2.1 環境基準の位置づけ 257
11.2.2 大気環境基準 258
11.2.3 水質環境基準 260
11.2.4 土壌環境基準 262
11.2.5 ダイオキシン類の環境基準 263
11.2.6 指針値等 265
11.3 環境汚染の状況把握 265
11.3.1 法律による常時監視 266
11.3.2 化学物質環境実態調査 268
11.3.3 その他の調査 269
11.4 環境汚染への対応 270
11.4.1 環境規制の基本とその体系 270
11.4.2 大気汚染対策 271
11.4.3 水質汚濁対策 274
11.4.4 土壌汚染対策 275
11.4.5 ダイオキシン類対策 276
11.5 化学物質の管理 277
11.5.1 化学物質の管理の視点 277
11.5.2 化学物質の製造に対する審査と規制 278
11.5.3 化学物質の排出状況の把握 281
11.5.4 化学物質のリスクの評価 282
11.6 国際的な協力 285
11.6.1 POPs条約 285
11.6.2 OECDプログラム 286
11.7 行政関連情報を捜す場合の留意点 287
ウェブサイト 288
第12章 環境問題解決のための新技術 島田浩章
12.1 江戸時代のエコに学ぶ 292
12.2 脱化石エネルギー 295
12.2.1 バイオマスに由来するエネルギー 295
12.2.2 太陽エネルギー 300
12.2.3 その他の自然エネルギー 301
12.2.4 水素エネルギーと燃料電池 303
12.2.5 原子力エネルギー 306
12.3 良好な環境を維持するための新技術 309
12.3.1 グリーン・サスティナブル・ケミストリー 309
12.3.2 バイオプラスチックと生分解性プラスチック 311
12.3.3 廃棄物の無害化とリサイクル技術 313
12.3.4 光触媒による汚染物質の分解 316
12.3.5 二酸化炭素の回収と貯留 317
12.4 生物機能を高度利用した環境技術 319
12.4.1 生物機能とのハイブリッド技術 319
12.4.2 生物工学を利用した物質生産 320
12.4.3 遺伝子組み換えと環境浄化 325
参考文献 327
ウェブサイト 328
演習問題解答例 331
索引 339
第1章 環境とは,環境汚染とは何か 吉原利一
1.1 環境とは? 2
1.1.1 環境という言葉の定義,類似の言葉 2
100.
図書
東工大
上田和夫著
目次情報:
続きを見る
1. 磁性の古典論と量子論
1.1 物質の磁気的性質 1
1.1.1 ローレンツ力と磁場の定義 1
1.1.2 マクスウェル方程式 3
1.1.3 磁気モーメント 7
1.1.4 磁化と磁化率 11
1.2 古典力学における常磁性と反磁性 13
1.2.1 常磁性モーメント 13
1.2.2 古典的磁気モーメントの示すキュリー則 14
1.2.3 古典力学による反磁性 16
1.3 磁性に関する古典力学の破綻 18
1.3.1 古典力学のハミルトン形式 18
1.3.2 ファン・リューエンの定理 20
1.4 量子力学による磁性の記述 21
演習問題 23
2. 原子・イオンの磁性
2.1 孤立した磁性イオン 25
2.1.1 ラーモアの定理 25
2.1.2 ラーモア反磁性 31
2.1.3 不完全殻の基底多重項-フントの規則- 33
2.1.4 LS結合 37
2.1.5 局在モーメントのキュリー則 38
2.2 結晶中の磁性イオン 40
2.2.1 1電子に対する結晶場の効果 40
2.2.2 多電子状態に対する結晶場の効果 45
演習問題 47
3. 遍歴電子のモデル
3.1 自由電子の磁性 48
3.1.1 パウリ常磁性 48
3.1.2 ランダウ反磁性 50
3.1.3 電子ガスの強磁性 54
3.2 格子上の伝導電子系 56
3.2.1 拡張されたハバードモデル 56
3.2.2 金属絶縁体転移と超交換相互作用 58
3.2.3 一般化されたハイゼンベルクハミルトニアン 63
演習問題 64
4. 磁性絶縁体の理論
4.1 分子場理論 66
4.1.1 強磁性体の分子場近似 67
4.1.2 反強磁性体の分子場近似 69
4.1.3 ヘリカルスピン構造に対する分子場近似 73
4.2 スピン波理論 77
4.2.1 強磁性体のスピン波理論 77
4.2.2 反強磁性体のスピン波理論 82
4.3 臨界現象 87
4.3.1 ギンツブルク-ランダウ(GL)理論 87
4.3.2 相関関数 91
4.3.3 繰り込み群とスケーリング則 94
4.4 量子相転移 97
4.4.1 量子相転移と分子場理論 97
4.4.2 マジャンダー-ゴーシュモデル 100
4.4.3 ホールデンギャップ 104
4.4.4 直交ダイマー系 106
演習問題 110
5. 遍歴電子系の磁性理論
5.1 金属磁性の分子場近似 111
5.1.1 金属強磁性の分子場近似 111
5.1.2 金属反強磁性の分子場近似 116
5.2 動的磁化率 119
5.2.1 線形応答理論 119
5.2.2 動的磁化率のRPA近似 123
5.3 スピンのゆらぎの理論 129
5.3.1 パラマグノンの理論 129
5.3.2 自己無撞着なスピンのゆらぎの理論(SCR理論) 133
5.3.3 金属磁性体の量子臨界現象 138
演習問題 143
6. 磁性と超伝導-結びに代えて- 145
参考文献 150
演習問題解答 153
索引 162
1. 磁性の古典論と量子論
1.1 物質の磁気的性質 1
1.1.1 ローレンツ力と磁場の定義 1