| 1.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
佐藤正雄[等]著
目次情報:
続きを見る
| 1.緒言 1 |
| 2.電気メッキの基礎 3 |
| 2.1 電気メッキの本質 3 |
| 2.2 電気メッキ浴の特性 4 |
| 2.2.1 電離および活量 5 |
| 2.2.2 溶液の電導性 7 |
| 2.2.3 イオン移動度と輸率 9 |
| 2.3 ファラデーの法則と電流効率 13 |
| 2.3.1 ファラデーの法則 13 |
| 2.3.2 電流密度の概念と電流効率 14 |
| 2.3.3 メッキ厚さの計算 15 |
| 2.4 電極の静的特性 17 |
| 2.4.1 電極電位 17 |
| 2.4.2 電極電位の実際上の応用例 21 |
| 2.5 電極の動的特性 29 |
| 2.5.1 浴電圧と過電圧の関係 29 |
| 2.5.2 過電圧の成因 31 |
| 2.5.3 ガス過電圧と分解電圧 34 |
| 2.6 電極反応の速度論的考え方 37 |
| 2.6.1 平衡状態 37 |
| 2.6.2 非平衡状態 41 |
| 2.7 電流分布とメッキ分布 46 |
| 2.7.1 一次電流分布 47 |
| 2.7.2 一次電流分布の改善 48 |
| 2.7.3 二次電流分布と均一電着性 52 |
| 2.7.4 陰極効率の影響 55 |
| 2.7.5 被覆力 56 |
| 2.8 電着現象 57 |
| 2.8.1 電着のメカニズムと光沢理論 57 |
| 2.8.2 レベリング作用 59 |
| 2.8.3 錯イオンからの電着 62 |
| 2.9 陽極現象 65 |
| 2.9.1 金属のアノード溶解と不働態化現象 65 |
| 2.9.2 メッキにおける陽極管理 66 |
| 3.電着物の性質 71 |
| 3.1 電着条件と電着物の性状 71 |
| 3.1.1 陰極電流密度の影響 71 |
| 3.1.2 電解液の濃度 72 |
| 3.1.3 電解液の温度の影響 72 |
| 3.1.4 電解液の種類 72 |
| 3.1.5 素地金属の影響 73 |
| 3.2 各種電着物の性質 73 |
| 3.2.1 銅メッキ 73 |
| 3.2.2 ニッケルメッキ 79 |
| 3.2.3 クロム 83 |
| 3.2.4 亜鉛およびカドミウム 93 |
| 4.各論 99 |
| 4.1 金属メッキ 99 |
| 4.1.1 銅メッキ 99 |
| 4.1.2 ニッケルメッキ 119 |
| 4.1.3 クロムメッキ 136 |
| 4.1.4 亜鉛・カドミウムメッキ 149 |
| 4.1.5 金および金合金 159 |
| 4.1.6 銀 164 |
| 4.1.7 インジウム 166 |
| 4.1.8 アルミニウム 167 |
| 4.1.9 鉛 168 |
| 4.1.10 スズ 169 |
| 4.1.11 ビスマス 170 |
| 4.1.12 アンチモン 170 |
| 4.1.13 ヒ素 171 |
| 4.1.14 モリブデン 171 |
| 4.1.15 レニウム 171 |
| 4.1.16 マンガン 172 |
| 4.1.17 白金 172 |
| 4.1.18 イリジウム 173 |
| 4.1.19 パラジウム 174 |
| 4.1.20 ロジウム 175 |
| 4.1.21 ルテニウム 178 |
| 4.1.22 コバルト 178 |
| 4.1.23 鉄 179 |
| 4.2 合金メッキ 180 |
| 4.2.1 はじめに 180 |
| 4.2.2 合金メッキの基本条件 180 |
| 4.2.3 合金メッキの陽極 182 |
| 4.2.4 電析合金組成に影響を及ぼす因子 183 |
| 4.2.5 電析合金組成の理論的計算 190 |
| 4.2.6 陰極拡散層内の金属濃度の測定 193 |
| 4.2.7 黄銅(銅-亜鉛)メッキ 195 |
| 4.2.8 青銅(銅-スズ)メッキ 197 |
| 4.2.9 鉛-スズ合金メッキ 199 |
| 4.2.10 スズ-亜鉛合金メッキ 200 |
| 4.2.11 スズ-カドミウム合金メッキ 203 |
| 4.2.12 スズ-ニッケル合金メッキ 205 |
| 4.2.13 鉄-ニッケル合金メッキ 206 |
| 4.2.14 コバルトーニッケル合金メッキ 209 |
| 4.2.15 その他の合金メッキ 211 |
| 5.用語解説 217 |
| 索引 223 |
| 1.緒言 1 |
| 2.電気メッキの基礎 3 |
| 2.1 電気メッキの本質 3 |
|
| 2.
|
 図書
図書
|
河田敬義著
|
| 3.
|
 図書
図書
|
北海道廳 ; 北海道
| 出版情報: |
[札幌] : 北海道廳, 1889- 冊 ; 26cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 4.
|
 図書
図書
|
ア・ゲ・クローシュ著 ; 吉崎敬夫訳
| 出版情報: |
東京 : 商工出版社, 1960-1961 2冊 ; 22cm |
| シリーズ名: |
数学選書 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 5.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
安達三郎執筆
目次情報:
続きを見る
| 1. 電磁波 |
| 1.1 基礎電磁方程式 1 |
| 1.1.1 電磁法則 1 |
| 1.1.2 マクスウェルの方程式 3 |
| 1.1.3 構成方程式 4 |
| 1.1.4 境界条件 5 |
| 1.1.5 電磁エネルギーとポインチングベクトル 6 |
| 1.2 波動方程式 9 |
| 1.2.1 ベクトル波動方程式 9 |
| 1.2.2 ポテンシャル 11 |
| 1.3 平面波 15 |
| 1.3.1 波動方程式の解 15 |
| 1.3.2 正弦状平面波 18 |
| 1.3.3 平面波の反射と屈折 24 |
| 1.3.4 幾何光学近似とWKB近似 27 |
| 1.3.5 群速度 31 |
| 演習問題 32 |
| 2. 電磁波の放射 |
| 2.1 源と界 34 |
| 2.1.1 一次波源と二次波源 34 |
| 2.1.2 電流と磁流による界 35 |
| 2.1.3 ホイゲンス・フレネルの原理 36 |
| 2.1.4 遠方界 37 |
| 2.1.5 電磁界の双対性と可逆性 39 |
| 2.2 素電磁流からの放射 41 |
| 2.2.1 電気ダイポールからの放射 41 |
| 2.2.2 磁気ダイポール(微小ループ電流)からの放射 43 |
| 2.3 開口面からの放射 44 |
| 2.3.1 大きな開口面からの放射 44 |
| 2.3.2 フレネル領域とフラウンホーファー領域 45 |
| 2.4 電磁波の散乱と回折 49 |
| 2.4.1 散乱波と回折波 49 |
| 2.4.2 散乱断面積 49 |
| 2.4.3 散乱・回折の例 51 |
| 演習問題 54 |
| 3. アンテナ |
| 3.1 アンテナとは 56 |
| 3.2 アンテナの基本性質 57 |
| 3.2.1 指向性と指向性利得 57 |
| 3.2.2 アンテナのインピーダンス 60 |
| 3.2.3 アンテナの利得と効率 63 |
| 3.2.4 ベクトル実効長 65 |
| 3.2.5 受信特性 67 |
| 3.2.6 アンテナ温度 72 |
| 3.3 基本的なアンテナ素子 74 |
| 3.3.1 直線状アンテナ 74 |
| 3.3.2 非直線状線状アンテナ 84 |
| 3.3.3 板状アンテナ 86 |
| 3.3.4 開口面アンテナ 92 |
| 3.3.5 進行波形アンテナ 100 |
| 3.4 アンテナアレイ 104 |
| 3.4.1 均一等間隔アレイ 104 |
| 3.4.2 不均一・不等間隔直線アレイ 107 |
| 3.4.3 アレイアンテナの利得 109 |
| 3.4.4 アレイアンテナの指向性合成 113 |
| 3.4.5 フェイズドアレイ 118 |
| 3.4.6 アダプティブアレイアンテナ 121 |
| 3.4.7 電波干渉計と開口面合成法 122 |
| 演習問題 124 |
| 4. 電磁波の伝搬 |
| 4.1 地上波の基本伝搬 126 |
| 4.1.1 地上波伝搬様式 126 |
| 4.1.2 平面大地上の伝搬 126 |
| 4.1.3 球面大地上の伝搬 128 |
| 4.1.4 山岳回折とフレネルゾーン 131 |
| 4.2 大気中の伝搬 135 |
| 4.2.1 大気中伝搬の減衰 135 |
| 4.2.2 中性大気による屈折 136 |
| 4.2.3 ダクト伝搬 140 |
| 4.2.4 見通し内伝搬 142 |
| 4.2.5 見通し外伝搬 144 |
| 4.3 電離大気中の伝搬 146 |
| 4.3.1 磁気プラズマの誘電率 146 |
| 4.3.2 磁気プラズマ中の平面波の伝搬 149 |
| 4.3.3 電離層伝搬特性 153 |
| 4.4 フェージング 155 |
| 4.4.1 フェージングの種類と性質 155 |
| 4.4.2 フェージングの統計的性質 157 |
| 4.4.3 ダイバーシチ受信 162 |
| 演習問題 164 |
| 5. 無線通信とアンテナ・伝搬 |
| 5.1 無線通信 165 |
| 5.2 無線通信回線の設計 166 |
| 5.2.1 周波数の有効利用 166 |
| 5.2.2 回線設計とアンテナ・伝搬特性 167 |
| 5.3 電波雑音と無線通信 169 |
| 5.4 衛星通信 171 |
| 5.4.1 衛星通信の特徴 171 |
| 5.4.2 衛星通信の最適周波数帯 172 |
| 付録 174 |
| 参考文献 178 |
| 演習問題解答 179 |
| 索引 187 |
| 1. 電磁波 |
| 1.1 基礎電磁方程式 1 |
| 1.1.1 電磁法則 1 |
|
| 6.
|
 図書
図書
|
山形縣第一部庶務課[編]
| 出版情報: |
[山形] : [山形縣], 1887.11- 冊 ; 25-27cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 7.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
西巻正郎著
目次情報:
続きを見る
| 1. 序説 |
| 2. 音と聴覚 |
| 2・1 音の強さと周波数 5 |
| 2・2 聴覚とその範囲 8 |
| 2・3 聴覚器官 9 |
| 2・4 聴覚の諸相 11 |
| 2・4・1 音の大きさ 11 |
| 2・4・2 音の高さ 15 |
| 2・4・3 音質(音色) 16 |
| 2・4・4 マスキング 16 |
| 2・4・5 音の協和 18 |
| 2・4・6 主観音 19 |
| 2・5 両耳聴効果 19 |
| 2・6 音の種類と性質 24 |
| 2・6・1 音の種類 24 |
| 2・6・2 周期音 25 |
| 2・6・3 非周期音 27 |
| 2・6・4 音声と楽器の音 28 |
| 2・7 音声 29 |
| 2・7・1 発声器官 29 |
| 2・7・2 音声とその周波数スペクトル 31 |
| 2・7・3 音声のパワ 33 |
| 2・7・4 忠実度,明瞭度,了解度 34 |
| 2・7・5 音声の伝送条件と明瞭度 35 |
| 2・8 騒音 37 |
| 3. 音響・振動の物理 |
| 3・1 音波の伝搬 40 |
| 3・1・1 音波 40 |
| 3・1・2 波動方程式 41 |
| 3・1・3 平面波 45 |
| 3・1・4 球面波 49 |
| 3・1・5 音波の反射と透過 51 |
| 3・2 音波の放射 56 |
| 3・2・1 微小音源 56 |
| 3・2・2 正負二重音源 58 |
| 3・2・3 面音源からの放射 59 |
| 3・2・4 放射インピーダンス 63 |
| 3・3 ホーン 66 |
| 3・3・1 ホーン 66 |
| 3・3・2 指数ホーン(エクスポネンシャルホーン) 68 |
| 3・4 物体の振動 70 |
| 3・4・1 板の厚み振動 70 |
| 3・4・2 棒の縦振動 71 |
| 3・4・3 棒の横振動 71 |
| 3・4・4 円板の振動 73 |
| 3・4・5 円形膜の振動 74 |
| 3・4・6 棒のねじり振動 75 |
| 3・4・7 弾性表面波 76 |
| 問題 77 |
| 4. 機械系・音響系の電気回路対応 |
| 4・1 機械系と電気回路との対応 79 |
| 4・1・1 機械要素と電気回路要素との対応 79 |
| 4・1・2 機械系の電気の等価回路 85 |
| 4・2 力-電流法による電気的等価回路 97 |
| 4・2・1 機械要素と電気回路要素との対応 98 |
| 4・2・2 機械系の電気的等価回路 99 |
| 4・3 音響系と電気回路との対応 103 |
| 4・3・1 音響要素と電気回路要素との対応 104 |
| 4・3・2 音響系の電気的等価回路 106 |
| 4・3・3 機械系と音響系との組合せ 113 |
| 4・4 分布定数等価回路 115 |
| 4・4・1 分布定数機械系の電気的等価回路による扱い 115 |
| 4・4・2 分布定数音響系の電気的等価回路による扱い 118 |
| 問題 121 |
| 5. 電気音響変換器の機構と性質 |
| 5・1 電気音響変換器の分類 123 |
| 5・2 電磁形変換器 124 |
| 5・2・1 電磁形変換器の一般的性質 124 |
| 5・2・2 動電変換器 128 |
| 5・2・3 電磁変換器 129 |
| 5・2・4 磁気ひずみ変換器 132 |
| 5・3 静電形変換器 134 |
| 5・3・1 静電形変換器の一般的性質 134 |
| 5・3・2 静電変換器 137 |
| 5・3・3 圧電変換器,電気ひずみ変換器 141 |
| 5・4 非可逆変換器 144 |
| 5・4・1 機械→電気変換器 145 |
| 5・4・2 電気→機械変換器 146 |
| 問題 147 |
| 6. マイクロホン |
| 6・1 マイクロホンの分類 150 |
| 6・1・1 駆動力の受け方による分類 150 |
| 6・1・2 指向性による分類 150 |
| 6・1・3 変換機構による分類 151 |
| 6・1・4 用途による分類 151 |
| 6・2 マイクロホンの特性 152 |
| 6・2・1 感度 152 |
| 6・2・2 感度(レスポンス)周波数特性 153 |
| 6・2・3 指向特性 153 |
| 6・2・4 振幅特性 153 |
| 6・2・5 過渡特性 154 |
| 6・2・6 雑音 154 |
| 6・2・7 電気インピーダンス 154 |
| 6・2・8 その他 155 |
| 6・3 圧力マイクロホン 155 |
| 6・3・1 圧力マイクロホンの構成と一般的性質 155 |
| 6・3・2 動電圧力マイクロホン 158 |
| 6・3・3 静電圧力マイクロホン 161 |
| 6・3・4 圧電圧力マイクロホン 165 |
| 6・3・5 抵抗変化圧力マイクロホン 167 |
| 6・4 圧力傾度マイクロホン 168 |
| 6・4・1 圧力傾度マイクロホンの一般的性質 168 |
| 6・4・2 動電圧力傾度(速度)マイクロホン 171 |
| 6・4・3 静電圧力傾度マイクロホン 173 |
| 6・5 単一指向性マクロホン 174 |
| 6・5・1 圧力マイクロホンと圧力傾度マイクロホンとの組合せ 174 |
| 6・5・2 圧力マイクロホンに漏れ孔を設けるもの 175 |
| 6・5・3 集音用マイクロホン 176 |
| 問題 177 |
| 7. イヤホン |
| 7・1 イヤホンの種類と特性 178 |
| 7・1・1 イヤホンの種類 178 |
| 7・1・2 感度 179 |
| 7・1・3 感度周波数特性 179 |
| 7・1・4 振幅特性 179 |
| 7・1・5 過渡特性 179 |
| 7・2 イヤホンの動作 180 |
| 7・3 イヤホンの構造 182 |
| 7・3・1 電磁イヤホン 182 |
| 7・3・2 動電イヤホン 184 |
| 7・3・3 静電イヤホン 185 |
| 7・3・4 圧電イヤホン 186 |
| 問題 187 |
| 8. スピーカ |
| 8・1 スピーカの分類 188 |
| 8・2 スピーカの特性 189 |
| 8・2・1 音圧周波数特性 189 |
| 8・2・2 効率 189 |
| 8・2・3 振幅特性 189 |
| 8・2・4 指向特性 190 |
| 8・2・5 過渡特性 190 |
| 8・2・6 インピーダンス特性 190 |
| 8・2・7 無ひずみ出力と入力定格 190 |
| 8・3 直接放射スピーカ 191 |
| 8・3・1 剛体振動板の直接放射スピーカの動作 191 |
| 8・3・2 動電直接放射スピーカ 196 |
| 8・3・3 バフル 205 |
| 8・3・4 その他の変換器を用いた直接放射スピーカ 208 |
| 8・4 ホーンスピーカ 209 |
| 8・4・1 指数ホーンの長さと口径 209 |
| 8・4・2 ホーンスピーカの構成と動作 211 |
| 8・4・3 ホーンスピーカの構造例 214 |
| 8・5 複合スピーカ 215 |
| 問題 216 |
| 9. 音響測定 |
| 9・1 音の強さの測定 218 |
| 9・1・1 せまい容器中の音圧の測定 218 |
| 9・1・2 自由音場での音圧の測定 218 |
| 9・1・3 自由音場での粒子速度の測定 218 |
| 9・2 音の周波数の測定および周波数分析 219 |
| 9・2・1 音の周波数の測定 219 |
| 9・2・2 音の周波数分析 220 |
| 9・3 音の大きさの測定 220 |
| 9・3・1 耳を用いる方法 220 |
| 9・3・2 指示騒音計を用いる方法 221 |
| 9・4 マイクロホンの校正 221 |
| 9・4・1 マイクロホンの音圧校正 221 |
| 9・4・2 マイクロホンの音場校正 223 |
| 9・5 イヤホンの測定 224 |
| 9・6 スピーカの測定 224 |
| 9・6・1 測定場所 224 |
| 9・6・2 効率 224 |
| 9・6・3 音圧周波数特性 225 |
| 9・6・4 振幅特性 226 |
| 9・6・5 過渡特性 226 |
| 9・7 機械インピーダンスの測定 226 |
| 9・7・1 動インピーダンスを側る方法 226 |
| 9・7・2 バイブロメータを用いる方法 227 |
| 9・8 音響インピーダンスの測定 228 |
| 9・8・1 近接法 228 |
| 9・8・2 反射法 229 |
| 10. 電気音響装置 |
| 10・1 音響装置の種類 231 |
| 10・2 録音と再生 234 |
| 10・2・1 機械的録音及び再生 234 |
| 10・2・2 磁気録音及び再生 239 |
| 10・3 音響補強装置 240 |
| 11. 超音波の応用 |
| 11・1 超音波の応用上の特質 243 |
| 11・2 超音波の情報的応用 245 |
| 11・2・1 水中音響装置 245 |
| 11・2・2 超音波探傷器 246 |
| 11・2・3 超音波診断装置 247 |
| 11・2・4 弾性表面波の利用 248 |
| 11・2・5 その他 249 |
| 11・3 超音波のエネルギー的利用 249 |
| 11・3・1 超音波加工 249 |
| 11・3・2 超音波切削 250 |
| 11・3・3 超音波塑性加工 250 |
| 11・3・4 超音波溶接 251 |
| 11・3・5 超音波洗浄 251 |
| 11・3・6 乳化,分散,凝集 252 |
| 11・3・7 その他 252 |
| 参考書 253 |
| 問題解答 255 |
| 索引 263 |
| 1. 序説 |
| 2. 音と聴覚 |
| 2・1 音の強さと周波数 5 |
|
| 8.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
柳井久義, 酒井善雄著
| 出版情報: |
東京 : コロナ社, 1969.5 xi, 342p ; 22cm |
| シリーズ名: |
標準電気工学講座 ; 5 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 第1章 序論 |
| 第2章 導電材料 |
| 2・2 導電材料および電気伝導現象 8 |
| 2・1・1 導電材料 8 |
| 2・1・2 電子のふるまい 9 |
| 2・1・3 電子散乱と導電率 12 |
| 2・1・4 交流電界による電気伝導 14 |
| 2・1・5 超電導現象 17 |
| 2・2 金属材料の種類と性質 19 |
| 2・2・1 純金属の種類と性質 19 |
| 2・2・2 銅 20 |
| 2・2・3 アルミニウム 21 |
| 2・2・4 合金 22 |
| 2・2・5 銅合金 23 |
| 2・2・6 アルミニウム合金 24 |
| 2.・3 半導体材料およびその現象 25 |
| 2・3・1 半導体の導電機構 25 |
| 2・3・2 半導体の界面現象 28 |
| 2・3・3 半導体における諸現象 30 |
| 2・3・4 半導体の精製と単結晶の作成 33 |
| 2・3・5 半導体材料の種類と特性 36 |
| 2・3・6 半導体材料の使用法 39 |
| 2・3・7 半導体材料試験法 47 |
| 2・4 抵抗材料 49 |
| 2・4・1 概説 49 |
| 2・4・2 金属抵抗材料 50 |
| 2・4・3 非金属抵抗材料 56 |
| 2・4・4 液体抵抗材料 57 |
| 2・5 特殊導電材料 58 |
| 2・5・1 ヒューズ 58 |
| 2・5・2 ろう付け材料 60 |
| 2・5・3 金属薄膜 61 |
| 2・5・4 超電導材料その他 62 |
| 問題 63 |
| 第3章 接点材料および接触子材料 |
| 3・1 接触子面における導電 66 |
| 3・1・1 皮膜抵抗 67 |
| 3・1・2 集中抵抗 67 |
| 3・1・3 接触抵抗に及ぼす影響 67 |
| 3・2 接点材料 68 |
| 3・2・1 接点材料の具備条件 68 |
| 3・2・2 各種接点材料 70 |
| 3.・3 ブラシ材料 71 |
| 3・3・1 ブラシ材料の具備条件 71 |
| 3・3・2 炭素および炭素ブラシ 71 |
| 問題 73 |
| 第4章 磁性材料 |
| 4・1 磁性材料の種類と磁気特性 74 |
| 4・1・1 磁性体の分類 74 |
| 4・1・2 磁気モーメント 76 |
| 4・1・3 常磁性と逆磁性 78 |
| 4・1・4 強磁性 81 |
| 4・1・5 フェリ磁性と反強磁性 83 |
| 4・1・6 鉄損 84 |
| 4・1・7 結晶形と磁性,磁気ひずみ作用,磁化の遅れ 85 |
| 4・1・8 磁性材料の製造 87 |
| 4・1・9 磁性材料の分類 88 |
| 4・2 高周波における磁性材料の特性 89 |
| 4・3 金属磁性材料 93 |
| 4・3・1 鉄 94 |
| 4・3・2 けい素鋼 95 |
| 4・3・3 Fe-Al,Fe-Si-Al系合金 99 |
| 4・3・4 Fe-Ni合金 100 |
| 4・3・5 恒透磁率材料 103 |
| 4・4 圧粉磁心材料および管フェライト 103 |
| 4・4・1 圧粉磁心材料 104 |
| 4・4・2 フェライト 105 |
| 4・5 永久磁石材料 107 |
| 4・5・1 永久磁石材料の具備条件 107 |
| 4・5・2 焼入れ硬化材料 109 |
| 4・5・3 析出硬化材料 109 |
| 4・5・4 焼結材料 109 |
| 4・5・5 その他の永久磁石材料 112 |
| 4・6 特殊磁性材料 112 |
| 4・6・1 角形ヒステリシス曲線材料 112 |
| 4・6・2 整磁材料,非磁性鉄鋼 113 |
| 4・6・3 磁気ひずみ材料 113 |
| 4・6・4 磁気録音材料 114 |
| 4・6・5 その他 114 |
| 4・7 磁性材料試験法 114 |
| 4・7・1 磁化特性 115 |
| 4・7・2 鉄損試験 115 |
| 4・7・3 高周波試験 117 |
| 4・7・4 永久磁石材料の試験 121 |
| 問題 122 |
| 第5章 絶縁材料 |
| 5・1 絶縁材料の種類と電気の特性 125 |
| 5・1・1 絶縁材料の種類と要求される性質 125 |
| 5・1・2 絶縁物での電気伝導 128 |
| 5・1・3 絶縁破壊現象と絶縁耐力 131 |
| 5・1・4 誘電分極と誘電特性 135 |
| 5・1・5 誘電体現象とその説明 143 |
| 5・1・6 物質構造と誘電特性 151 |
| 5・1・7 絶縁材料の劣化 153 |
| 5・2 気体絶縁材料 156 |
| 5・2・1 気体による絶縁 156 |
| 5・2・2 火花放電 156 |
| 5・2・3 各種気体絶縁物 158 |
| 5・3 液体絶縁材料 160 |
| 5・3・1 絶縁油の種類と特性 160 |
| 5・3・2 鉱物性絶縁油 162 |
| 5・3・3 合成絶縁油 165 |
| 5・4 無機固体絶縁材料 166 |
| 5・4・1 天然無機固体絶縁材料 167 |
| 5・4・2 ガラス 171 |
| 5・4・3 磁器 174 |
| 5・4・4 無機薄膜材料 181 |
| 5・5 有機固体絶縁材料 182 |
| 5.・5・1 天然有機固体絶縁材料 182 |
| 5・5・2 高分子材料概説 188 |
| 5・5・3 熱可塑性合成樹脂 192 |
| 5・5・4 熱硬化性合成樹脂 198 |
| 5・5・5 ゴムおよび合成ゴム 206 |
| 5・5・6 ろう類 212 |
| 5・6 絶縁ワニスおよびコンパウンド 215 |
| 5・6・1 ワニスの種類と特性 215 |
| 5・6・2 絶縁コンパウンド 217 |
| 5・6・3 ワニス処理品 217 |
| 5・7 絶縁材料試験法 219 |
| 5・7・1 固体材料 219 |
| 5・7・2 気体材料 227 |
| 5・7・3 液体材料 227 |
| 問題 229 |
| 第6章 強誘電材料および圧電材料 |
| 6・1 強誘電体および圧電現象 233 |
| 6・2 強誘電材料および圧電材料 236 |
| 6・2・1 水晶 236 |
| 6・2・2 ロシェル塩 237 |
| 6・2・3 りん酸アンモンおよびりん酸カリ 238 |
| 6・2・4 EDTおよびDKT 238 |
| 6・2・5 チタン酸バリウムおよび固溶体 238 |
| 6・2・6 ジルコン酸鉛固溶体 242 |
| 6・2・7 ニオブ酸塩 242 |
| 問題 243 |
| 第7章 電線,ケーブル |
| 7・1 裸電線 244 |
| 7・1・1 電線の製法 244 |
| 7・1・2 裸電線の種類 244 |
| 7・1・3 主要な裸電線 245 |
| 7・1・4 裸電線の電流容量 247 |
| 7・2 絶縁電線 247 |
| 7・2・1 巻線類 248 |
| 7・2・2 塗覆線 248 |
| 7・2・3 通信機器配線用被覆線 248 |
| 7・2・4 綿絶縁電線 249 |
| 7・2・5 ゴム絶縁電線 249 |
| 7・2・6 合成樹脂絶縁電線 251 |
| 7・2・7 絶縁電線の許容電流 252 |
| 7・3 電力ケーブル 252 |
| 7・3・1 種類と構造 252 |
| 7・3・2 各種ケーブル 253 |
| 7・3・3 最高使用温度と許容電漢 255 |
| 7・4 電気通信用ケーブル 255 |
| 7・4・1 市内ケーブル 256 |
| 7・4・2 市外ケーブル 258 |
| 7・4・3 局内ケーブル 259 |
| 7・4・4 同軸ケーブル 259 |
| 7・4・5 特殊ケーブル 261 |
| 7・4・6 ケーブルの電気的特性 264 |
| 7・4・7 高周波伝送線路 264 |
| 問題 268 |
| 第8章 電子回路部品 |
| 8・1 抵抗器 270 |
| 8・1・1 抵抗器の種類と特性 270 |
| 8・1・2 巻線抵抗器 272 |
| 8・1・3 炭素系体抵抗器 273 |
| 8・1・4 炭素系皮膜抵抗器 278 |
| 8・1・5 金属皮膜抵抗器 281 |
| 8・1・6 酸化金属皮膜抵抗器その他 283 |
| 8・2 コンデンサ 284 |
| 8・2・1 コンデンサの種類と特性 284 |
| 8・2・2 真空および空気コンデンサその他 289 |
| 8・2・3 紙コンデンサ 292 |
| 8・2・4 プラスチックフィルムコンデンサ 295 |
| 8・2・5 雲母コンデンサ,ガラスコンデンサ 298 |
| 8・2・6 磁器コンデンサ 299 |
| 8・2・7 電解コンデンサ 302 |
| 8・2・8 薄膜コンデンサ 306 |
| 8・3 コイルおよび変成器 306 |
| 8・4 半導体回路素子 309 |
| 8・4・1 半導体ダイオード 310 |
| 8・4・2 トランジスタ 311 |
| 8・4・3 サイリスタ 314 |
| 8・4・4 その他 315 |
| 8・5 集積回路 316 |
| 8・5・1 集積化と集積回路 316 |
| 8・5・2 集積回路の種類 317 |
| 8・5・3 半導体集積回路 318 |
| 8・5・4 薄膜および厚膜集積回路 323 |
| 8・5・5 半導体および薄膜あるいは厚膜集積回路と大規模集積化 327 |
| 8・5・6 集積回路の特長 328 |
| 問題 331 |
| 解答 333 |
| 索引 335 |
| 第1章 序論 |
| 第2章 導電材料 |
| 2・2 導電材料および電気伝導現象 8 |
|
| 9.
|
 図書
図書
|
全国大学国語国文学会
| 出版情報: |
東京 : 三省堂, 1968-1969 11冊 ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 10.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
石原研而著
| 出版情報: |
東京 : 丸善, 1988.9 vii, 297p ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 第1章 土の基本的性質 |
| 1.1 土の基本的物理量 1 |
| 1.1.1 基本的物理量の定義 1 |
| 1.1.2 基本的物理量の間の関係 4 |
| 1.1.3 基本的物理量の測定法 6 |
| 1.2 土の粒度 8 |
| 1.2.1 粒径による区分 8 |
| 1.2.2 粒度分布 9 |
| 1.3 土のコンシステンシー 13 |
| 1.3.1 コンシステンシーの意義 13 |
| 1.3.2 液性限界と塑性限界の求め方 15 |
| 1.3.3 液性限界,塑性限界,塑性指数の物理的意味 17 |
| 1.3.4 粘土の活性度 21 |
| 1.3.5 鋭敏比 23 |
| 1.4 砂の相対密度 25 |
| 1.5 土の工学的分類 26 |
| 1.5.1 統一分類法 26 |
| 第2章 不飽和土の諸性質 |
| 2.1 毛管作用とサクション 33 |
| 2.1.1 土中の毛管作用 34 |
| 2.1.2 毛管圧力と結合力 35 |
| 2.1.3 サクションの測定 38 |
| 2.1.4 サクションと含水比の関係 39 |
| 2.1.5 不飽和領域への浸透 40 |
| 2.2 土の凍結凍上 43 |
| 2.2.1 土の熱的性質 43 |
| 2.2.2 凍結の進行 47 |
| 2.2.3 凍上現象 49 |
| 第3章 土の締固め |
| 3.1 締め固めた土の性質 53 |
| 3.1.1 締固め曲線と最適含水比 53 |
| 3.1.2 土の締固め試験 54 |
| 3.1.3 土の種類と締固め曲線 57 |
| 第4章 透水 |
| 4.1 Darcyの法則 63 |
| 4.2 透水係数 64 |
| 4.2.1 透水係数の求め方 64 |
| 4.2.2 透水係数の値 66 |
| 4.3 透水力と透水安定性 75 |
| 4.3.1 透水力 75 |
| 4.3.2 透水に対する安定性 78 |
| 4.3.3 フィルター 82 |
| 4.4 地下水の流れ 83 |
| 4.4.1 連続の方程式 83 |
| 4.4.2 2次元の透水 85 |
| 4.4.3 フローネットによる簡易解法 88 |
| 4.5 浸潤面をもつ地下水流 92 |
| 4.5.1 Dupuitの仮定 92 |
| 4.5.2 平面内2次元透水の一般式 94 |
| 4.5.3 アースダム内の定常透水 97 |
| 4.6 揚水 98 |
| 4.6.1 定常的揚水 98 |
| 4.6.2 非定常揚水 101 |
| 4.6.3 定常揚水と非定常揚水の比較 105 |
| 第5章 有効応力,ダイレタンシーと間隙水圧 |
| 5.1 有効応力と間隙水圧 107 |
| 5.2 外力によって生ずる間隙水圧 110 |
| 5.2.1 圧縮応力による間隙水圧 112 |
| 5.2.2 せん断時のダイレタンシーによる間隙水圧 115 |
| 第6章 粘土の圧密 |
| 6.1 土の圧縮 121 |
| 6.1.1 飽和粘土の圧密過程 121 |
| 6.1.2 間隙比と有効応力との関係 123 |
| 6.1.3 粘土の圧縮曲線の特性 126 |
| 6.2 圧密理論 132 |
| 6.2.1 圧密方程式の誘導 132 |
| 6.2.2 圧密方程式の解 136 |
| 6.2.3 圧密度 140 |
| 6.2.4 圧密試験と整理法 147 |
| 6.3 圧密現象の種類 153 |
| 第7章 土のせん断強度 |
| 7.1 組合せ応力 157 |
| 7.1.1 応力の変換 157 |
| 7.1.2 Mohrの応力円表示 162 |
| 7.2 Mohr-Coulombの破壊規準 164 |
| 7.2.1 すべり面上の応力による表示 164 |
| 7.2.2 主応力による破壊規準の表示 165 |
| 7.2.3 最大せん断応力面上の応力による表示 169 |
| 7.2.4 x,y-面上の応力による表示 170 |
| 7.2.5 破壊規準の表示方法についてのまとめ 170 |
| 7.3 粘性土のせん断強度 171 |
| 7.3.1 応力履歴の再現と載荷環境 171 |
| 7.3.2 三軸せん断試験 173 |
| 7.3.3 三軸圧縮せん断試験結果 175 |
| 7.4 粘土の非排水せん断強度 177 |
| 7.4.1 正規圧密粘土の非排水せん断強度 177 |
| 7.4.2 過圧密粘土の非排水せん断強度 182 |
| 7.4.3 Hvorslevの破壊規準 185 |
| 7.4.4 過庄密比とせん断強度との関係 189 |
| 7.4.5 粘土の一軸圧縮強度 192 |
| 7.5 粘土の排水せん断強度 194 |
| 7.5.1 エネルギー補正 194 |
| 7.5.2 排水せん断強度 197 |
| 7.5.3 粘土の残留強度 200 |
| 第8章 地盤内の応力と変位 |
| 8.1 半無限弾性体内の応力 207 |
| 8.1.1 単一集中荷重 207 |
| 8.1.2 線状荷重 212 |
| 8.1.3 帯状荷重 213 |
| 8.1.4 正弦波荷重 215 |
| 8.1.5 圧力球根 218 |
| 8.2 地盤の表面沈下 220 |
| 8.2.1 弾性沈下 220 |
| 8.2.2 不等沈下に対する適用 222 |
| 8.2.3 地盤反力係数 224 |
| 8.3 盛土内の応力と変位 226 |
| 8.3.1 アースフィルによる変位 226 |
| 第9章 土圧 |
| 9.1 土圧 231 |
| 9.1.1 土圧の定義と特徴 231 |
| 9.1.2 Rankineの土圧 234 |
| 9.1.3 鉛直自立高さ 237 |
| 9.1.4 Coulomb土圧 237 |
| 9.1.5 静止土圧 242 |
| 9.1.6 壁の変形パターンと土圧分布 245 |
| 9.2 設計用の土圧公式 246 |
| 9.2.1 擁壁の土庄 246 |
| 9.2.2 矢板土留壁に作用する土圧 247 |
| 9.3 埋設管に作用する鉛直土圧 250 |
| 9.3.1 鉛直土圧 251 |
| 9.3.2 埋設管の設計用土圧 252 |
| 第10章 地盤の支持力 |
| 10.1 支持力論 255 |
| 10.1.1 地盤の弾塑性変形 255 |
| 10.1.2 Rankine塑性域に基づく支持力 257 |
| 10.1.3 塑性過渡領域を考慮した支持力 262 |
| 10.2 地盤の支持力 268 |
| 10.2.1 Terzaghiの支持力式 268 |
| 10.2.2 その他の支持力式 271 |
| 第11章 斜面の安定 |
| 11.1 斜面の安定度 273 |
| 11.1.1 直線斜面の安定性 273 |
| 11.1.2 円弧すべり面による安定解析法 276 |
| 11.1.3 水浸斜面の安定解析法 283 |
| 11.1.4 任意のすべり面に対する安定解析法 287 |
| 11.1.5 急速水位降下時の安定解析 289 |
| 11.2 全応力解析と有効応力解析 291 |
| 索引 295 |
| 第1章 土の基本的性質 |
| 1.1 土の基本的物理量 1 |
| 1.1.1 基本的物理量の定義 1 |
|
| 11.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
海野肇, 中西一弘, 白神直弘著
| 出版情報: |
東京 : 講談社, 1992.4 x, 228p ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| はじめに |
| 1. バイオプロセスとその構成 1 |
| 1.1 バイオプロセスと生物化学工学 1 |
| 1.1.1 バイオプロセス 1 |
| 1.1.2 生物化学工学 2 |
| 1.1.3 バイオプロセスと生物化学工学の役割 2 |
| 1.2 バイオプロセスの構成 18 |
| 1.2.1 上流プロセス 18 |
| 1.2.2 プロダクションプロセス 19 |
| 1.2.3 下流プロセス 19 |
| 1.3 遺伝子組換え細胞利用プロセス 21 |
| 演習問題 23 |
| 2. 生体触媒の特性 25 |
| 2.1 酵素の特性 25 |
| 2.1.1 酵素の分類と名称 25 |
| 2.1.2 酵素活性 26 |
| 2.1.3 酵素活性に必須な要件 27 |
| 2.1.4 補酵素 27 |
| 2.2 微生物の特性 33 |
| 2.2.1 微生物の分類 33 |
| 2.2.2 微生物の化学組成 36 |
| 2.2.3 微生物の物理的性質 36 |
| 2.2.4 微生物の環境と生理特性 37 |
| 2.2.5 微生物の培養 38 |
| 2.3 動物細胞の特性 39 |
| 2.4 植物細胞の特性 41 |
| 2.5 昆虫細胞の特性 43 |
| 2.6 分子育種 44 |
| 2.6.1 分子育種の手法 45 |
| 2.6.2 発現系の選択 47 |
| 2.6.3 組換え体遺伝子の安定性 49 |
| 2.7 代謝 52 |
| 2.7.1 生体内代謝反応の相互関係 52 |
| 2.7.2 物性基準の収率因子 55 |
| 2.7.3 増殖の生物化学量論 58 |
| 2.7.4 反応熱 59 |
| 2.7.5 エネルギー基準の収率因子 60 |
| 2.7.6 ATP成基準の収率因子 61 |
| 2.7.7 代謝工学 63 |
| 演習問題 65 |
| 3. 生体触媒の反応速度論 68 |
| 3.1 酵素反応速度論 68 |
| 3.1.1 初速度 68 |
| 3.1.2 Michaelis-Menten 式 69 |
| 3.1.3 動力学定数の算出法 72 |
| 3.1.4 可逆的阻害剤が存在する場合の速度式 73 |
| 3.1.5 不可逆的阻害剤が存在する場合の速度式 78 |
| 3.1.6 基質阻害が存在する場合の速度式 78 |
| 3.1.7 アロステリック酵素に対する速度式 80 |
| 3.1.8 二基質反応の速度論 81 |
| 3.2 酵素反応の経時変化 84 |
| 3.2.1 生成物阻害の無視できる不可逆反応に対する反応の経時変化 84 |
| 3.2.2 生成物阻害の無視できない場合 87 |
| 3.2.3 二基質反応の場合 88 |
| 3.3 酵素の失活速度 89 |
| 3.4 反応速度のpH依存性 90 |
| 3.5 細胞が関連する生化学反応速度 91 |
| 3.5.1 増殖モデル 92 |
| 3.5.2 増殖速度 92 |
| 3.5.3 基質消費速度 94 |
| 3.5.4 代謝産物生成速度 94 |
| 3.6 固定化生体触媒の速度論 97 |
| 3.6.1 生体触媒の固定化法 98 |
| 3.6.2 固定化生体触媒の性能に及ぼす諸因子 102 |
| 3.6.3 固定化酵素の失活速度に及ぼす諸因子 108 |
| 演習問題 111 |
| 4. バイオリアクターの設計と操作 115 |
| 4.1 バイオリアクターの形式と操作 115 |
| 4.2 バイオリアクター設計の基礎 119 |
| 4.2.1 槽型バイオリアクターの一般的な設計方程式 120 |
| 4.2.2 管型バイオリアクターの一般的な設計方程式 121 |
| 4.3 酵素を用いるバイオリアクター 123 |
| 4.3.1 遊離酵素を用いるバイオリアクター 123 |
| 4.3.2 固定化酵素を用いるバイオリアクター 124 |
| 4.3.3 滞留時間分布 129 |
| 4.3.4 固定化酵素バイオリアクターの安定性 132 |
| 4.4 微生物を用いるバイオリアクター 134 |
| 4.4.1 回分培養 134 |
| 4.4.2 流加培養 138 |
| 4.4.3 連続培養操作 140 |
| 4.5 物質移動の影響 144 |
| 4.5.1 酸素移動の影響 145 |
| 4.5.2 菌体ペレットの場合の酸素移動の影響 146 |
| 4.6 遺伝子組換え菌の培養工学 146 |
| 4.7 動植物細胞の培養工学 147 |
| 4.8 スケールアップ, スケールダウン 149 |
| 4.9 バイオリアクターの計測ならびに動特性と制御 152 |
| 4.9.1 バイオプロセスにおける計測と制御の役割 152 |
| 4.9.2 バイオリアクターの状態変数とその計測 152 |
| 4.9.3 バイオリアクターの制御方式と動特性および制御のためのアルゴリズム 155 |
| 演習問題 159 |
| 5. バイオプロセスの操作要素 163 |
| 5.1 バイオプロセスを構成する基本操作 163 |
| 5.2 レオロジー特性 164 |
| 5.2.1 ニュートン流体と非ニュートン流体 164 |
| 5.2.2 培養液のレオロジー特性 166 |
| 5.3 滅菌操作 168 |
| 5.3.1 加熱滅菌 168 |
| 5.3.2 フィルター滅菌 173 |
| 5.3.3 高圧滅菌 174 |
| 5.4 撹拌操作 175 |
| 5.4.1 撹拌装置 176 |
| 5.4.2 撹拌槽内の流れ 177 |
| 5.4.3 撹拌に必要な動力 177 |
| 5.5 通気操作 179 |
| 5.5.1 細胞の酸素摂取速度 179 |
| 5.5.2 バイオリアクター内での酸素移動 180 |
| 5.5.3 バイオリアクター内での気泡の挙動 183 |
| 5.5.4 酸素移動容量係数に及ぼす因子 185 |
| 5.5.5 酸素移動容量係数の測定法 185 |
| 5.6 分離精製を目的とした操作 186 |
| 5.6.1 遠心分離操作 187 |
| 5.6.2 ろ過操作 190 |
| 5.6.3 細胞破砕操作 193 |
| 5.6.4 膜分離操作 196 |
| 演習問題 199 |
| 6. バイオプロセスの実際 204 |
| 6.1 固定化酵素プロセス 204 |
| 6.2 固定化細胞の利用 209 |
| 6.2.1 能動的固定化 210 |
| 6.2.2 受動的固定化 214 |
| 6.3 動物細胞利用プロセス 216 |
| 6.4 生物機能を利用する廃水処理 221 |
| 6.5 バイオプロセス技術のこれから 224 |
| 演習問題 225 |
| 付録A 解糖系, TCAサイクル, 酸化的リン酸化 227 |
| 付録B King-Altmanの図解法 232 |
| 演習問題の略解とヒント 235 |
| 参考書 244 |
| 索引 247 |
| topics |
| 進化分子工学 32 |
| 養子免疫療法 51 |
| 有機溶媒中で生体触媒を用いる反応 97 |
| タンパク質以外の酵素 110 |
| 酵素固定化研究の行方 133 |
| マイクロバイオリアクター 145 |
| ダウンストリームとアップストリームの融合 187 |
| はじめに |
| 1. バイオプロセスとその構成 1 |
| 1.1 バイオプロセスと生物化学工学 1 |
|
| 12.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
中嶋正之, 藤代一成編著
目次情報:
続きを見る
| 第1章 序論 1 |
| 1.1 発展の経緯 1 |
| 1.2 学界の動向 3 |
| 1.3 本書の構成 4 |
| 参考文献 5 |
| 第2章 CGとビジュアリゼーション 7 |
| 2.1 ビジュアリゼーションについて 7 |
| 2.1.1 サイエンティフィックビジュアリゼーション 7 |
| 2.1.2 エンジニアリングビジュアリゼーション 9 |
| 2.2 コンピュータビジュアリゼーションについて 9 |
| 2.2.1 コンピュータビジュアリゼーションとは 9 |
| 2.2.2 システム環境構成 11 |
| 2.3 カラービジュアリゼーションの技法 12 |
| 2.3.1 カラー情報の利用 12 |
| 2.3.2 色空間の構成 13 |
| 2.3.3 アラー系列による表示技法 14 |
| 2.3.4 カラーの利用における問題点 15 |
| 2.4 2次元ビジュアリゼーション技法 17 |
| 2.4.1 2次元スカラデータの階調表示 18 |
| 2.4.2 線成分による表示 19 |
| 2.5 2次元空間の立体表示法 21 |
| 2.5.1 3次元CGについて 21 |
| 2.5.2 3次元CGの基礎技法 21 |
| 2.6 ベクトルデータのビジュアリゼーション 25 |
| 2.6.1 2次元上でのベクトル場の表示法 25 |
| 2.6.2 3次元空間内でのベクトル場表示 27 |
| 2.7 アニメーション表示 29 |
| 参考文献 29 |
| 第3章 ボリュームビジュアリゼーション 31 |
| 3.1 背景と目的 31 |
| 3.2 ボクセル集合モデル 32 |
| 3.3 処理のフレームワーク 34 |
| 3.4 間接方式の手法 37 |
| 3.4.1 断面 37 |
| 3.4.2 等値面 37 |
| 3.4.3 区間型ボリューム 41 |
| 3.5 直接方式の手法 43 |
| 3.6 研究開発の動向 46 |
| 3.6.1 利用可能なソフトウェア 46 |
| 3.6.2 描画速度の改善 46 |
| 3.6.3 適用対象の拡大 47 |
| 3.6.4 ボリュームデータマイニング 48 |
| 3.6.5 ボリュームグラフィックス 49 |
| 参考文献 49 |
| 第4章 フロービジュアリゼーション 52 |
| 4.1 はじめに 52 |
| 4.2 プリミティブ挿入法 54 |
| 4.2.1 矢印表示法 54 |
| 4.2.2 流線法 55 |
| 4.2.3 流跡線法と粒子追跡法 56 |
| 4.2.4 流脈線法 58 |
| 4.2.5 タイムライン法 58 |
| 4.2.6 サーフェースパーティクル法 58 |
| 4.3 テクスチャベース法 58 |
| 4.3.1 スポットノイズ法 59 |
| 4.3.2 LIC法 60 |
| 4.4 特徴をベースとする可視化技法 65 |
| 4.4.1 プローブ 65 |
| 4.4.2 ベクトルフィールドトポロジー 67 |
| 4.5 3次元壁面上の流れの可視化 68 |
| 参考文献 73 |
| 第5章 バイオメディカルビジュアリゼーション 77 |
| 5.1 はじめに 77 |
| 5.2 平滑化とノイズ除去 77 |
| 5.3 異種データの重ね合わせと領域処理 83 |
| 5.4 脳機能の可視化 87 |
| 5.5 将来のバイオメディカルビジュアリゼーション 90 |
| 5.6 おわりに 91 |
| 参考文献 92 |
| 第6章 インフォメーションビジュアリゼーション 基本概念と研究開発動向 94 |
| 6.1 誕生の経緯 94 |
| 6.2 3つの技術の背景 95 |
| 6.2.1 データベース技術との統合問題 96 |
| 6.2.2 デスクトップメタファからの脱却 96 |
| 6.2.3 インターネット時代の標準的な資源アクセス法の模索 98 |
| 6.3 情報可視化研究開発の動向 98 |
| 6.3.1 サイエンティフィックビジュアリゼーションからの継承 98 |
| 6.3.2 情報可視化技法の体系化 99 |
| 6.3.3 インフォメーションリアライゼーション 100 |
| 6.4 思想の晶化を目指して 100 |
| 参考文献 102 |
| 第7章 データベース技術とビジュアリゼーション技術 104 |
| 7.1 内容に基づく検索 107 |
| 7.1.1 フーリエ変換による類似判定 107 |
| 7.1.2 特徴空間 109 |
| 7.1.3 空間索引 109 |
| 7.1.4 検索システムの構成 112 |
| 7.2 情報可視化 115 |
| 7.2.1 情報の可視化とその利用 115 |
| 7.2.2 情報可視化システムの構成 119 |
| 7.3 情報可視化手法の分類と可視化設計 122 |
| 7.3.1 GADGET 122 |
| 7.3.2 情報可視化技術のデータベース化とユーザ支援 124 |
| 7.3.3 GADGET/IV 127 |
| 参考文献 133 |
| 第8章 3次元ユーザインタフェースパラダイム 136 |
| 8.1 はじめに 136 |
| 8.2 古典的プロジェクト例 137 |
| 8.2.1 SemNet 137 |
| 8.2.2 Information Visualizer 138 |
| 8.2.3 VOGUE 140 |
| 8.3 階層構造の可視化 143 |
| 8.3.1 FSN 143 |
| 8.3.2 Fractal Tree 144 |
| 8.3.3 Information Cube 144 |
| 8.3.4 H3 145 |
| 8.3.5 NattoView 146 |
| 8.4 応用システム 147 |
| 8.4.1 多次元データの可視化 147 |
| 8.4.2 STARLIGHT 147 |
| 8.4.3 ZASH 148 |
| 8.4.4 WebBook 149 |
| 8.4.5 Pad++ 149 |
| 8.5 3次元対話技法 149 |
| 8.5.1 2次元マウスによるインタラクション 151 |
| 8.5.2 特殊デバイスによるインタラクション 152 |
| 8.6 3次元ユーザインタフェース実用化への課題 152 |
| 8.6.1 適切なインタフェース設計 152 |
| 8.6.2 GUIからPUIへ 153 |
| 8.6.3 画面のスケール 153 |
| 8.6.4 3次元音の導入 153 |
| 8.7 まとめ 154 |
| 参考文献 154 |
| 第9章 AVS/Express 158 |
| 9.1 データフロー型アプリケーションの特徴 158 |
| 9.1.1 可視化手順のオブジェクト化 158 |
| 9.1.2 データフローの動作ルール 160 |
| 9.1.3 代表的なデータフロー可視化システムの紹介 162 |
| 9.1.4 データフロー型可視化システムの利点 163 |
| 9.2 可視化システムAVS/Expressにおける実装例 164 |
| 9.2.1 AVS/Expressの紹介 164 |
| 9.2.2 モジュールの構成 165 |
| 9.2.3 ビジュアルプログラミングによる組立て 166 |
| 9.2.4 プログラムの実行 167 |
| 9.2.5 内部アーキテクチャ 169 |
| 9.3 可視化事例の紹介 172 |
| 9.3.1 代表的な可視化事例 172 |
| 9.3.2 ステアリングとトラッキング 173 |
| 9.3.3 並列分散処理 175 |
| 参考文献 176 |
| 第10章 可視化ツールとしてのVRML 178 |
| 10.1 なぜVRMLなのか? 178 |
| 10.2 インターネット上での可視化 179 |
| 10.2.1 シナリオ1 179 |
| 10.2.2 シナリオ2 179 |
| 10.2.3 シナリオ3 179 |
| 10.3 VRMLについて 180 |
| 10.3.1 対話機能 181 |
| 10.3.2 アニメーション機能 182 |
| 10.3.3 データ圧縮機能 184 |
| 10.4 VRMLを用いた可視化 185 |
| 10.4.1 流れ場における渦中心表示 185 |
| 10.4.2 速度ボリュームデータの流線表示 186 |
| 10.4.3 ボリュームデータの断面表示 187 |
| 10.4.4 等値面表示 189 |
| 10.4.5 ボリュームレンダリング表示 190 |
| 10.4.6 サーバ側への情報伝達 191 |
| 参考文献 192 |
| 第11章 VisIT/In3D 193 |
| 11.1 オブジェクト階層 195 |
| 11.2 ランドスケープの構成 196 |
| 11.3 対話機能 198 |
| 参考文献 198 |
| 索引 199 |
| 第1章 序論 1 |
| 1.1 発展の経緯 1 |
| 1.2 学界の動向 3 |
|
| 13.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
野依良治 [ほか] 編
目次情報:
続きを見る
| 第I部 有機合成化学: 有機合成反応 |
| 1. 有機合成反応における選択性 5 |
| 1.1 選択性発現の要因 5 |
| 1.1.1 速度支配と熱力学支配 5 |
| 1.1.2 Hammondの仮説 6 |
| 1.1.3 フロンティア軌道 7 |
| 1.1.4 静電相互作用 8 |
| 1.1.5 立体効果 8 |
| 1.1.6 溶媒効果,隣接基関与,エントロピー効果 9 |
| 1.2 位置選択性 12 |
| 1.2.1 エノラートのアルキル化における位置選択性 12 |
| 1.2.2 環化反応における位置選択性とBaldwin則 13 |
| 1.3 官能基選択性 15 |
| 1.4 立体選択性 15 |
| 1.4.1 立体特異的反応 16 |
| 1.4.2 立体選択的反応 17 |
| 2. 骨格形成反応 29 |
| 2.1 C=X型結合への付加反応 29 |
| 2.1.1 炭素求核種の調製 29 |
| 2.1.2 有機金属化合物のカルボニル化合物への付加反応 33 |
| 2.1.3 有機金属化合物のアシル化反応 35 |
| 2.1.4 α位にヘテロ原子基をもつ有機金属化合物の付加反応 36 |
| 2.1.5 カルボニル化合物のアルキリデン化反応 37 |
| 2.1.6 エノラートおよびエノールのカルボニル化合物への付加反応 42 |
| 2.1.7 アリル金属化合物のカルボニル化合物への付加反応 52 |
| 2.1.8 C=N二重結合への付加反応 54 |
| 2.2 C=C結合への付加反応 56 |
| 2.2.1 求電子反応 56 |
| 2.2.2 求核反応 59 |
| 2.2.3 ラジカル反応 65 |
| 2.2.4 カルベンおよびカルベノイドの反応 68 |
| 2.2.5 有機金属化合物を利用する反応 70 |
| 2.2.6 芳香族化合物の反応 71 |
| 2.3 sp3炭素上の置換反応 74 |
| 2.3.1 有機金属化合物のアルキル化 74 |
| 2.3.2 エノラートのアルキル化 79 |
| 2.3.3 酸性条件下でのアルキル化反応 86 |
| 2.4 sp2,sp炭素における結合生成反応 87 |
| 2.4.1 酸化的カップリング 87 |
| 2.4.2 還元的カップリング 90 |
| 2.4.3 有機金属化合物との交差カップリング 97 |
| 2.5 π電子系の協奏的反応 105 |
| 2.5.1 [4+2]付加環化反応 105 |
| 2.5.2 1,3双極付加環化反応 116 |
| 2.5.3 [2+2]付加環化反応 118 |
| 2.5.4 エン反応 119 |
| 2.5.5 シグマトロピー転位 121 |
| 2.5.6 電子環状反応 125 |
| 2.5.7 キレトロピー反応 126 |
| 2.6 転位,離脱,開裂,および光化学反応 126 |
| 2.6.1 電子不足中心への転位反応 126 |
| 2.6.2 電子豊富中心が関与する転位反応 129 |
| 2.6.3 Wolff転位 130 |
| 2.6.4 その他の転位反応 130 |
| 2.6.5 開裂反応 131 |
| 2.6.6 光化学反応 132 |
| 2.7 複素還化合物反応 136 |
| 2.7.1 π電子受容性複素環化合物の反応 136 |
| 2.7.2 π電子供与性複素環化合物の反応 139 |
| 2.8 重合反応 140 |
| 2.8.1 逐次重合 141 |
| 2.8.2 連鎖重合 143 |
| 3. 官能基変換 157 |
| 3.1 還元 157 |
| 3.1.1 カルボニル化合物の還元 157 |
| 3.1.2 炭素-炭素多重結合の還元 163 |
| 3.1.3 有機ハロゲン化物,アルコール,オキシランの還元 167 |
| 3.2 酸化 168 |
| 3.2.1 アルコールの酸化 168 |
| 3.2.2 アルケンの酸化 174 |
| 3.2.3 ベンゼン環の酸化 177 |
| 3.2.4 脱水素反応 177 |
| 3.2.5 飽和炭化水素の酸化 178 |
| 3.2.6 ケトンの酸化 179 |
| 3.3 酸素官能基の変換 180 |
| 3.3.1 カルボン酸とその誘導体 180 |
| 3.3.2 カルボニル化合物 185 |
| 3.3.3 アルコール 186 |
| 4. 不斉合成反応 189 |
| 4.1 定義および分類 189 |
| 4.2 エナンチオマー過剰率の決定法 191 |
| 4.3 金属化合物を用いる方法 192 |
| 4.3.1 カルボニル化合物の還元とアルキル化 192 |
| 4.3.2 カルボニル化合物のアリル化 197 |
| 4.3.3 アルドール反応 197 |
| 4.3.4 アザエノラートのアルキル化 198 |
| 4.3.5 ニトロアルドール反応 199 |
| 4.3.6 水素化 200 |
| 4.3.7 オレフィン類のエポキシ化とジヒドロキシル化 203 |
| 4.3.8 オレフィン類の異性化 206 |
| 4.4 有機化合物を触媒に用いる方法 206 |
| 4.5 酵素や微生物を触媒に用いる方法 208 |
| 4.6 抗体触媒反応 209 |
| 4.7 速度論的光学分割 209 |
| 4.8 絶対不斉合成 212 |
| 第II部 有機合成化学: 多段階合成 |
| 5. 多段階合成のデザイン 217 |
| 5.1 逆合成解析の基礎 217 |
| 5.1.1 逆合成 217 |
| 5.1.2 トランスフォームとレトロン 217 |
| 5.1.3 種々のレトロンとトランスフォーム 219 |
| 5.1.4 結合の切断 219 |
| 5.1.5 合成等価体 220 |
| 5.1.6 前躯体としての反応中間体 221 |
| 5.1.7 極性転換 221 |
| 5.1.8 直線型合成と収束型合成 222 |
| 5.2 官能基変換に基づく逆合成 223 |
| 5.2.1 Robinson環化反応 223 |
| 5.2.2 ニトリルオキシドを用いる1,3双極付加環化反応 225 |
| 5.2.3 アシルアニオン等価体 226 |
| 5.2.4 ハロラクトン化反応 228 |
| 5.3 官能基付加に基づく逆合成 229 |
| 5.3.1 Dieckmann縮合 229 |
| 5.3.2 含硫黄複素環を活用する立体化学の制御 231 |
| 5.4 官能基移動に基づく逆合成 233 |
| 5.4.1 カルボニル基の移動 233 |
| 5.4.2 オレフィン結合の移動 234 |
| 5.5 骨格転位に基づく逆合成 234 |
| 5.5.1 [2,3]Wittig転位 234 |
| 5.5.2 ビニルシクロプロパン転位 236 |
| 5.5.3 ピナコール転位 237 |
| 5.5.4 Beckmann転位 238 |
| 5.5.5 Claisen転位 239 |
| 5.5.6 Cope転位とオキシCope転位 241 |
| 5.6 連続型結合生成に基づく逆合成 242 |
| 5.6.1 連続型シグマトロピー転位 242 |
| 5.6.2 Michael付加-エノラート捕捉反応 243 |
| 5.6.3 連続型ポリエン還化反応 243 |
| 5.6.4 連続型ラジカル環化反応 244 |
| 5.6.5 連続型Heck反応 245 |
| 5.7 光学活性体構築に向けた逆合成 245 |
| 5.7.1 カイロンに基づく逆合成 246 |
| 5.7.2 不斉合成法に基づく逆合成 247 |
| 5.8 理論計算による合成中間体の設計 249 |
| 5.8.1 分子力場計算 249 |
| 5.8.2 初期入力座標の自動発生 250 |
| 2.8.3 安定配座解析 252 |
| 5.8.4 熱力学的に抑制された反応の立体選択性予測 254 |
| 5.8.5 速度論的に制御された反応の立体選択性予測 254 |
| 5.9 保護基 258 |
| 5.9.1 アルコールの保護 263 |
| 5.9.2 ジオールの保護 269 |
| 5.9.3 アミノ基の保護 271 |
| 5.9.4 その他の保護基 273 |
| 5.9.5 保護基の開発 273 |
| 6. 標的化合物の全合成 275 |
| 6.1 カリオフィレン 275 |
| 6.2 キュバン 281 |
| 6.3 トロンボキサンA2 283 |
| 6.4 ロイコトリエン類 285 |
| 6.5 1β-メチルカルバペネム抗生物質 288 |
| 6.6 ギンゴライド 292 |
| 6.7 タキソール 299 |
| 6.8 カリチェアミシン 308 |
| 6.9 FK506 323 |
| 6.10 パリトキシン 330 |
| コラム コンビナトリアル合成 340 |
| 第III部 生物有機化学 |
| 7. 一次代謝産物 347 |
| 7.1 アミノ酸,ペプチド,タンパク質 347 |
| 7.1.1 アミノ酸 347 |
| 7.1.2 ペプチド 349 |
| 7.1.3 タンパク質 351 |
| 7.1.4 ペプチド合成 355 |
| 7.2 核酸 359 |
| 7.2.1 核酸の構造 360 |
| 7.2.2 核酸の機能 361 |
| 7.2.3 遺伝子操作 366 |
| 7.3 糖質 369 |
| 7.3.1 糖質 369 |
| 7.3.2 単糖 369 |
| 7.3.3 単純糖質 371 |
| 7.3.4 複合糖質 372 |
| 7.3.5 糖鎖の化学合成 376 |
| 8. 二次代謝産物 381 |
| 8.1 脂肪酸,ポリケチド 381 |
| 8.1.1 脂肪酸,脂質 382 |
| 8.1.2 エイコサノイド 383 |
| 8.1.3 ポリケチド芳香族化合物 384 |
| 8.1.4 マクロリド抗生物質 385 |
| 8.1.5 ポリエーテル化合物 385 |
| 8.2 イソプレノイド 387 |
| 8.2.1 メバロン酸と生体内イソプレン単位 387 |
| 8.2.2 イソプレン単位の結合反応: テルペン基本鎖化合物の生成 387 |
| 8.2.3 モノテルペン 389 |
| 8.2.4 セスキテルペン 390 |
| 8.2.5 ジテルペン 391 |
| 8.2.6 セスタテルペン 393 |
| 8.2.7 トリテルペン,ステロイド 393 |
| 8.2.8 テトラテルペン 398 |
| 8.3 フェニルプロパノイド 398 |
| 8.4 アルカロイド 401 |
| 8.4.1 オルニチン由来のアルカロイド 401 |
| 8.4.2 リシン由来のアルカロイド 402 |
| 8.4.3 チロシン由来のアルカロイド 403 |
| 8.4.4 インドールアルカロイド 405 |
| 9. 生物活性発現の分子機構 409 |
| 9.1 発がんと制がんの化学: DNAの化学修飾 409 |
| 9.1.1 突然変異の化学 409 |
| 9.1.2 発がんの化学 411 |
| 9.1.3 制がんの化学 414 |
| 9.2 遺伝子発現の化学制御: ステロイドホルモンの分子作用機構 420 |
| 9.2.1 核内受容体とそのリガンド 420 |
| 9.2.2 核内受容体の構造と機能 421 |
| 9.2.3 受容体-リガンド相互作用 426 |
| 9.3 生物応答の化学制御: 免疫抑制剤の分子作用機構 427 |
| 9.3.1 免疫賦活剤 427 |
| 9.3.2 非特異的免疫抑制剤 428 |
| 9.3.3 特異的免疫抑制剤 428 |
| 略号表 433 |
| 索引 441 |
| 第I部 有機合成化学: 有機合成反応 |
| 1. 有機合成反応における選択性 5 |
| 1.1 選択性発現の要因 5 |
|
| 14.
|
 図書
図書
|
奥村晴彦著
| 出版情報: |
東京 : 技術評論社, 2000.12 xii, 363p ; 23cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 15.
|
 図書
図書
|
清水英男著
|
| 16.
|
 図書
図書
|
三井斌友著
|
| 17.
|
 図書
図書
|
東京天文台編纂
| 出版情報: |
東京 : 丸善, 1975- 冊 ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 暦部 |
| 天文部 |
| 気象部 |
| 物理/化学部 |
| 地学部 |
| 生物部 |
| 環境部 |
| 附録 |
概要:
科学知識のデータブック。世界各地で猛威をふるう異常気象や自然災害、「記録的」「観測史上初」「前例にない」といった言葉が躍るなか、その目安となる基礎データが満載。<br />世界の地震分布図を最近20年のデータに更新、地震分布とプレートとの相
…
関がわかる。ロシアの隕石落下、小惑星探査等で注目の「隕石」「小惑星」情報を充実。「海洋酸性化」観測データを新規掲載。<br />「重力波」「ニュートリノ」「ニホニウム」「人工知能(AI)」注目キーワードをトピックスにて解説(物理/化学部に初掲載)。地学部:最近70年間に噴火した日本の火山、1億7000万年前から現在までの地磁気逆転の歴史がわかる項目を新設。生物部:最新の分類表に基づき「動物の基本型」イラストを拡充。<br />「日本付近のおもな被害地震年代表」大改訂、西暦416年から現在に至るまでの被害地震記録を再調査、全面的に見直し。アジア圏初の発見で話題となった113番元素「ニホニウム」。同時決定したモスコビウム、テネシン、オガネソンとともに新4元素のデータを掲載。<br />科学知識のデータブック。2020年版には科学のニュースが盛りだくさん。科学の基礎データも満載の理科年表、火山や地震の表も大改訂。
続きを見る
|
| 18.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
岩下恒雄〔ほか〕著
| 出版情報: |
東京 : 実教出版, 1982.2 221p ; 22cm |
| シリーズ名: |
構造物の理論 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 1章 弾性学および塑性学の基礎理論 |
| 1.1 弾性体の力学 1 |
| 1.1.1 応力(1) |
| 1.1.2 ひずみ(15) |
| 1.1.3 弾性基礎方程式(24) |
| 1.1.4 平面応力と平面ひずみ(32) |
| 1.1.5 曲線座標による関係式(44) |
| 1.1.6 三次元問題の例題(59) |
| 1.1.7 エネルギ原理(65) |
| 1.1.8 近似解法(81) |
| 1.1.9 有限要素法(84) |
| 1.2 降伏条件 98 |
| 1.2.1 Trescaの条件(99) |
| 1.2.2 von Misesの条件(99) |
| 1.2.3 Mohrの条件(101) |
| 1.2.4 各種の条件の特徴(102) |
| 1.2.5 平面応力での各種の条件の特徴(105) |
| 1.3 応力増分とひずみ増分の関係および硬化法則 108 |
| 1.3.1 等方弾性体の応力増分とひずみ増分の関係(108) |
| 1.3.2 Prandtl-Reussの式(108) |
| 1.3.3 塑性ポテンシャルの理論(111) |
| 1.3.4 硬化法則(116) |
| 2章 材料の力学的性質 |
| 2.1 鋼 119 |
| 2.1.1 1軸単調引張りにおける鋼の性質(119) |
| 2.1.2 ひずみ履歴を受ける鋼の性質(121) |
| 2.1.3 鋼の降伏条件(121) |
| 2.2 コンクリート 122 |
| 2.2.1 1軸圧縮応力下のコンクリートの性質(122) |
| 2.2.2 コンクリートの引張強度(125) |
| 2.2.3 多軸応力下のコンクリートの強度(126) |
| 2.3 土 128 |
| 2.3.1 圧密特性(129) |
| 2.3.2 せん断特性(132) |
| 2.3.3 有効応力(136) |
| 2.3.4 降伏条件(143) |
| 3章 部材の挙動とその解析例 |
| 3.1 円孔縁に環状荷重が作用する場合の有孔無限板の応力と変形 156 |
| 3.1.1 理論解析(157) |
| 3.1.2 積分計算(167) |
| 3.1.3 数値計算(172) |
| 3.1.4 結果の検討と考察(179) |
| 3.1.5 厳密解の近似化(182) |
| 3.1.6 実験による検証(186) |
| 3.2 曲げおよびせん断を受ける鉄筋コンクリート部材の解析 187 |
| 3.2.1 鉄筋コンクリート部材の有限要素へのモデル化(187) |
| 3.2.2 コンクリートの解析(187) |
| 3.2.3 鉄筋の解析(190) |
| 3.2.4 鉄筋とコンクリートの相互作用の解析(190) |
| 3.2.5 剛性行列(191) |
| 3.2.6 解析結果(201) |
| 3.3 密な砂中の浅基礎の支持力解析 204 |
| 3.3.1 拡張されたKotter式(205) |
| 3.3.2 数値解析法(211) |
| 3.3.3 砂中の浅基礎の支持力(215) |
| 索引 220 |
| 1章 弾性学および塑性学の基礎理論 |
| 1.1 弾性体の力学 1 |
| 1.1.1 応力(1) |
|
| 19.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
三町勝久著
| 出版情報: |
東京 : 日本評論社, 2006.11 v, 208p ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| まえがき |
| 第1章 多変数函数の微分法 1 |
| 1.偏微分の計算に慣れよう 2 |
| 1.1 多変数の函数 2 |
| 1.2 偏微分 5 |
| 2.函数のクラスを理解しよう 13 |
| 2.1 微分可能な函数 13 |
| 2.2 微分可能函数の性質 18 |
| 2.3 偏微分の順序 20 |
| 2.4 函数のクラス 22 |
| 3.合成函数の微分法を理解しよう 25 |
| 3.1 写像と函数 25 |
| 3.2 合成函数の微分 29 |
| 4.曲面の接平面や法線を調べよう 37 |
| 4.1 曲面の接乎面と法線 37 |
| 4.2 陰函数と接平面 39 |
| 4.3 位相空間論の基礎 45 |
| 5.函数の極値を調べよう 49 |
| 5.1 函数の極値 49 |
| 5.2 テイラーの定理 51 |
| 6.条件付きの極値問題を調べよう 61 |
| 6.1 有界閉集合との連続函数 61 |
| 6.2 条件付きの極値間題 63 |
| 章末間題 73 |
| 第2章 多変数函数の積分法 75 |
| 1.多重積分を理解しよう 76 |
| 1.1 積分 76 |
| 2.多重積分の変数変換に習熟しよう 91 |
| 2.1 重積分の変数変換 91 |
| 2.2 体積の計算 99 |
| 2.3 変換公式の証明 102 |
| 3.広義積分を理解しよう 105 |
| 3.1 広義積分 105 |
| 3.2 逆三角函数 110 |
| 3.3 表面積の計算 113 |
| 章末問題 119 |
| 第3章 微分積分の基礎 121 |
| 1.微積分の基礎を理解しよう 122 |
| 1.1 点列の収束・発散 122 |
| 1.2 濃度 125 |
| 1.3 函数の連続性 128 |
| 1.4 実数の連続性 129 |
| 2.一様収束性を使いこなそう 136 |
| 2.1 函数列の一様収束 136 |
| 2.2 積分記号下の微分積分 142 |
| 2.3 応用例 146 |
| 3.級数表示された函数の理解を深めよう 150 |
| 3.1 無限級数 150 |
| 3.2 函数項級数 155 |
| 3.3 特殊函数への応用 161 |
| 章末問題 167 |
| 補遺1 微分(differential)につりいて 170 |
| 補遺2 積分の計算について 174 |
| 参考文献 182 |
| 章末問題の解答 184 |
| 索引 207 |
| まえがき |
| 第1章 多変数函数の微分法 1 |
| 1.偏微分の計算に慣れよう 2 |
|
| 20.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
西山静男 [ほか] 共著
| 出版情報: |
東京 : コロナ社, 1979.4 ix, 255p ; 22cm |
| シリーズ名: |
大学講義シリーズ |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 1 音波の物性と音響用語 |
| 1.1 音波 1 |
| 1.2 音圧,粒子速度,体積速度 3 |
| 1.3 音響インピーダンス 4 |
| 1.4 機械インピーダンス 5 |
| 1.5 音の強さ 5 |
| 1.6 音圧レベル,音の強さレベル 6 |
| 1.7 音響パワー,音響パワーレベル 7 |
| 1.8 音の大きさ,音の大きさのレベル 8 |
| 1.9 騒音レベル 8 |
| 1.10 デシベルの計算 9 |
| 1.11 音波の伝搬 11 |
| 1.11.1 距離減衰 11 |
| 1.11.2 音波の吸収 12 |
| 1.11.3 音波の反射・屈折 12 |
| 1.11.4 音波の回折 14 |
| 1.11.5 吸音としゃ音 14 |
| 演習問題 16 |
| 2 聴覚と音声 |
| 2.1 聴覚機構 17 |
| 2.1.1 外耳 17 |
| 2.1.2 中耳 18 |
| 2.1.3 内耳および聴神経系 19 |
| 2.2 聴覚の心理特性 20 |
| 2.2.1 可聴範囲 20 |
| 2.2.2 弁別限 21 |
| 2.2.3 音の大きさおよび高さ 23 |
| 2.2.4 マスキング 24 |
| 2.2.5 両耳効果 26 |
| 2.3 発声機構 27 |
| 2.3.1 発声器官 27 |
| 2.3.2 声帯振動および声道の特性 27 |
| 2.4 音声の物理特性 28 |
| 2.4.1 母音と子音 28 |
| 2.4.2 音声勢力 30 |
| 2.4.3 長時間平均スペクトル 31 |
| 2.5 口と耳による品質評価 31 |
| 2.5.1 正調通話レスポンス 31 |
| 2.5.2 明りょう度 33 |
| 2.5.3 AENおよびRE 37 |
| 演習問題 39 |
| 3 波動理論 |
| 3.1 波動方程式 40 |
| 3.1.1 連続の方程式 40 |
| 3.1.2 運動の方程式 42 |
| 3.1.3 気体の法則 42 |
| 3.1.4 波動方程式 43 |
| 3.2 一次元における波動方程式の解 45 |
| 3.3 平面進行波 47 |
| 3.4 閉管中の音波 49 |
| 3.5 球音源 53 |
| 3.6 音源の指向特性 56 |
| 3.6.1 二重音源 57 |
| 3.6.2 直線配列音源と線音源 59 |
| 3.6.3 ダプレット音源 61 |
| 3.6.4 剛壁上のピストン音源 63 |
| 3.6.5 指向性利得 64 |
| 3.7 音源の放射インピーダンス 65 |
| 3.8 音波の回折 68 |
| 3.9 音響ホーン 69 |
| 演習問題 73 |
| 4 機械振動系 |
| 4.1 単振動 74 |
| 4.2 一自由度系の自由動振 77 |
| 4.3 一自由度系の強制振動 80 |
| 4.4 弾性体の振動 83 |
| 4.4.1 弦の振動 83 |
| 4.4.2 棒の縦振動 85 |
| 4.4.3 棒の横振動 86 |
| 4.4.4 膜の振動 90 |
| 4.4.5 板の振動 93 |
| 演習問題 94 |
| 5 電気・機械・音響系の対応 |
| 5.1 等価回格 95 |
| 5.2 機械素子 96 |
| 5.2.1 質量要素 96 |
| 5.2.2 機械コンプライアンス 98 |
| 5.2.3 機械抵抗 100 |
| 5.3 音響素子 100 |
| 5.3.1 音響質量 100 |
| 5.3.2 音響コンプライアンス 102 |
| 5.3.3 音響抵抗 103 |
| 演習問題 104 |
| 6 電気・機械・音響変換 |
| 6.1 電気音響変換器の分類 105 |
| 6.2 変換理論 106 |
| 6.2.1 動電変換 106 |
| 6.2.2 電磁変換 108 |
| 6.2.3 磁気ひずみ変換 113 |
| 6.2.4 静電変換 113 |
| 6.2.5 圧電変換と電気ひずみ変換 115 |
| 6.2.6 抵抗変化変換 117 |
| 6.3 変換方式と等価回路 118 |
| 6.3.1 電磁方式の等価回路 119 |
| 6.3.2 静電方式の等価回路 123 |
| 6.4 制御方式 126 |
| 6.4.1 変換の分解 126 |
| 6.4.2 抵抗・質量およびスチフネス制御 126 |
| 演習問題 128 |
| 7 マイクロホンと 送話器 |
| 7.1 音響→電気変換器の分類 130 |
| 7.1.1 受音から電気出力までの変換 130 |
| 7.1.2 指向特性による分類 131 |
| 7.2 一般的性質 131 |
| 7.2.1 感度 131 |
| 7.2.2 指向特性 132 |
| 7.2.3 自由音場における形状の影響 133 |
| 7.3 マイクロホンと送話器各論 133 |
| 7.3.1 動電圧力マイクロホン 134 |
| 7.3.2 静電圧力マイクロホン 136 |
| 7.3.3 炭素送話器 140 |
| 7.3.4 音圧傾度マイクロホン 142 |
| 7.3.5 単一指向性マイクロホン 144 |
| 7.4 マイクロホン感度の測定 146 |
| 7.4.1 標準器との比較 146 |
| 7.4.2 標準器の校正 147 |
| 演習問題 147 |
| 8 受話器とスピーカ |
| 8.1 電気→音響変換器の分類 149 |
| 8.2 受話器各論 150 |
| 8.2.1 受話器の一般的性質 150 |
| 8.2.2 電磁受話器 152 |
| 8.3 スピーカ各論 154 |
| 8.3.1 分類 154 |
| 8.3.2 一般的性質 155 |
| 8.3.3 直接放射振動板の一般的性質 155 |
| 8.3.4 動電直接放射スピーカ 159 |
| 8.3.5 バフルとキャビネット 165 |
| 8.3.6 スピーカ用ホーンの特性 166 |
| 8.3.7 ホーンスピーカの構造と特性 169 |
| 8.4 バイブロメータ 171 |
| 8.5 受話器・スピーカ感度の校正 173 |
| 8.5.1 周波数レスポンス 173 |
| 8.5.2 相互校正法 173 |
| 演習問題 176 |
| 9 騒音とその制御 |
| 9.1 騒音の影響 178 |
| 9.2 騒音の発生 180 |
| 9.3 騒音の評価 183 |
| 9.3.1 騒音レベル 183 |
| 9.3.2 等価騒音レベル 185 |
| 9.3.3 PNL 185 |
| 9.3.4 SIL,NC曲線 186 |
| 9.3.5 NRN 189 |
| 9.3.6 EPNL,WECPNL 191 |
| 9.4 騒音測定法 195 |
| 9.4.1 騒音レベルの測定 196 |
| 9.4.2 周波数分析 201 |
| 9.4.3 残響時音の測定 204 |
| 9.4.4 透過損失の測定 207 |
| 9.5 騒音防止対策 208 |
| 9.5.1 音源対策 208 |
| 9.5.2 伝搬経路対策 210 |
| 9.5.3 消音器 213 |
| 9.5.4 吸音材料 216 |
| 9.5.5 防振 219 |
| 9.6 振動測定法 220 |
| 演習問題 225 |
| 10 超音波とその応用 |
| 10.1 超音波の性質 227 |
| 10.2 電気-機械変換材料とその性質 229 |
| 10.2.1 磁気ひずみ材料 230 |
| 10.2.2 圧電材料 230 |
| 10.2.3 電気ひずみ材料 231 |
| 10.3 超音波振動子 232 |
| 10.3.1 磁気ひずみ振動子 232 |
| 10.3.2 電気ひずみ振動子 233 |
| 10.3.3 固体伝送体付き振動子 235 |
| 10.4 強力超音波の応用 235 |
| 10.4.1 気体中での応用 235 |
| 10.4.2 液体中での応用 236 |
| 10.4.3 固体への応用 236 |
| 10.5 超音波の通信的応用 238 |
| 10.5.1 超音波による計測 238 |
| 10.5.2 超音波による通信とシミュレーション 239 |
| 10.6 超音波を用いた電子回路部品 240 |
| 10.6.1 フィルタ 240 |
| 10.6.2 遅延線 240 |
| 10.6.3 弾性表面波デバイス 240 |
| 演習問題 242 |
| 演習問題解答 |
| 参考文献 |
| 索引 |
| 1 音波の物性と音響用語 |
| 1.1 音波 1 |
| 1.2 音圧,粒子速度,体積速度 3 |
|
| 21.
|
 図書
図書
|
丸山和博, 田隈三生 [編集]
|
| 22.
|
 図書
図書
|
J.W.ゲワルトウスキー, H.A.ワトソン著 ; 山本賢三監訳
| 出版情報: |
東京 : 広川書店, 1966.12-1967.2 2冊 ; 27cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 23.
|
 図書
図書
|
田中芳雄, 喜多源逸共著
| 出版情報: |
東京 : 丸善, 1949-1953 冊 ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 24.
|
 図書
図書
|
山崎四朗編纂
| 出版情報: |
[東京] : 桂川電力, 1913-1922 2冊 ; 16x23cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 25.
|
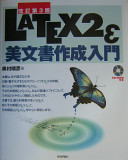 図書
図書
|
奥村晴彦著
| 出版情報: |
東京 : 技術評論社, 2004.2 xii, 403p ; 23cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 26.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
港湾学術交流会編
| 出版情報: |
東京 : 朝倉書店, 2009.11 vi, 266p ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 1 港湾の役割と特徴 |
| 1.1 港をつくるとは [新井洋一] 1 |
| 1.1.1 港とは 1 |
| 1.1.2 港湾技術者の活躍する風景 6 |
| 1.2 日本の港湾の変遷 [山根隆行] 10 |
| 1.2.1 日本の港湾の特色 10 |
| 1.2.2 古代から近代国家形成期の港湾 11 |
| 1.2.3 経済高度成長期の港湾 15 |
| 1.2.4 経済安定成長期の港湾 19 |
| 1.3 日本の港湾の特徴と将来 [山根隆行] 22 |
| 1.3.1 港湾を特徴づけることがら 22 |
| 1.3.2 港湾を取り巻く環境の変化と将来 25 |
| 1.4 港湾の管理,計画,整備 [村田利治] 28 |
| 1.4.1 港湾における活動と港湾管理 28 |
| 1.4.2 港湾計画 31 |
| 1.4.3 港湾の整備制度と事業評価 42 |
| 2 港湾を取り巻く自然 |
| 2.1 海象 [高山知司] 49 |
| 2.1.1 潮汐 49 |
| 2.1.2 長周期波と副振動 53 |
| 2.1.3 波浪 55 |
| 2.1.4 沿岸の流れ 68 |
| 2.2 地盤と地震 70 |
| 2.2.1 地盤 70 [小林正樹] |
| 2.2.2 地震 75 [野田節男] |
| 2.2.3 地盤の液状化 80 |
| 2.2.4 土圧および水圧 82 |
| 3 港湾施設の計画と設計 [山本修司] |
| 3.1 港湾施設の計画 87 |
| 3.1.1 外郭施設の計画 87 |
| 3.1.2 水域施設の計画 91 |
| 3.1.3 係留施設の計画 95 |
| 3.2 港湾施設の設計 102 |
| 3.2.1 設計の基本 102 |
| 3.2.2 防波堤の設計 106 |
| 3.2.3 係留施設の設計 110 |
| 4 港湾施設の建設 |
| 4.1 築造工事 [大内久夫] 115 |
| 4.1.1 防波堤 115 |
| 4.1.2 岸壁 122 |
| 4.2 浚渫と埋立 [寺内 潔] 130 |
| 4.2.1 浚渫 130 |
| 4.2.2 埋立 136 |
| 4.3 地盤改良[柳生忠彦] 138 |
| 4.3.1 サンドドレイン工法 139 |
| 4.3.2 サンドコンパクションパイル工法 142 |
| 4.3.3 深層混合処理工法 144 |
| 5 港湾と防災 |
| 5.1 高潮・高波対策 [高山知司] 147 |
| 5.1.1 高潮の発生原因 147 |
| 5.1.2 過去の高潮災害の特徴 148 |
| 5.1.3 大阪湾における高潮対策の歴史 153 |
| 5.1.4 これからの高潮・高波対策 156 |
| 5.2 津波対策 [高山知司] 159 |
| 5.2.1 津波の発生原因と伝播 159 |
| 5.2.2 津波の増幅 160 |
| 5.2.3 津波災害の特徴 163 |
| 5.2.4 津波対策 166 |
| 5.3 海岸保全 [高山知司] 168 |
| 5.3.1 漂砂 168 |
| 5.3.2 海浜変形予測 171 |
| 5.3.3 飛砂 172 |
| 5.3.4 侵食軽減対策 174 |
| 5.4 大規模地震対策 [野田節男] 178 |
| 5.4.1 港湾に求められる防災機能 179 |
| 5.4.2 大規模地震対策施設の整備 179 |
| 6 港湾と環境 [細川恭史] |
| 6.1 環境からみた港湾の特性 183 |
| 6.1.1 港の地理的特徴 183 |
| 6.1.2 環境の検知 184 |
| 6.1.3 水質を左右する要素 189 |
| 6.2 港湾における環境配慮 196 |
| 6.2.1 水質を左右する要素と水質改善の手法 196 |
| 6.2.2 底質の改善 200 |
| 6.2.3 景観やアクセスの改善 206 |
| 6.3 港湾における生物との共生 208 |
| 6.3.1 港湾における生物生息場とその劣化 208 |
| 6.3.2 劣化環境の修復技術 215 |
| 6.3.3 干潟の造成事例 220 |
| 7 港湾技術者の役割 [新井洋一] |
| 7.1 建国以来続く港づくり 225 |
| 7.1.1 中世 : 平清盛の本格的人工港築造 225 |
| 7.1.2 近世 : 日本の海のネットワークを作った河村瑞賢の着想 227 |
| 7.1.3 近代 : 港湾技術の開祖,広井勇 228 |
| 7.1.4 近代 : 浅野総一郎の偉業 230 |
| 7.1.5 現代 : 高度経済成長生みの親,鈴木雅次 232 |
| 7.1.6 日本の港づくり 233 |
| 7.2 港湾技術者に必要な資質 235 |
| 7.2.1 リーダーシップの能力・プロフェッショナルの自覚 235 |
| 7.2.2 信頼を得る能力・倫理規定の実践 236 |
| 7.2.3 職人への回帰能力・個別課題への適応 238 |
| 付録 |
| 1. 混成堤の設計事例 [山本修司] 241 |
| 2. 矢板式係船岸の設計事例 248 |
| 索引 263 |
| 1 港湾の役割と特徴 |
| 1.1 港をつくるとは [新井洋一] 1 |
| 1.1.1 港とは 1 |
|
| 27.
|
 図書
図書
|
山崎圭次郎著
|
| 28.
|
 図書
図書
|
伊勢幹夫著
|
| 29.
|
 図書
図書
|
東京大学社会科学研究所編
| 出版情報: |
東京 : 東京大学出版会, 1968.5-1969.3 5冊 ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 30.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
正田誠著
| 出版情報: |
京都 : 化学同人, 2003.3 xi, 178p ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 第1章 生物 1 |
| 1.1 地球には三種類の生物がいる 2 |
| 1.2 生物は食物でつながっている 4 |
| 1.2.1 食物連鎖 4 |
| 1.2.2 狂牛病は自然の法則を破った罰(?) 6 |
| 1.3 人口が増加しつづけている 7 |
| 1.4 食糧の増産を支えた技術 8 |
| 1.4.1 灌漑技術と水の管理 9 |
| 1.4.2 アンモニア合成による化学肥料の生産 9 |
| 1.4.3 化学農薬の開発 12 |
| 1.4.4 品種改良 13 |
| 1.5 食糧の供給能力はどれくらいあるか 14 |
| 1.5.1 穀物の生産量 14 |
| 1.5.2 畜産と漁業 16 |
| 1.6 農作物の生産性を阻害する因子は何か 18 |
| 1.6.1 耕作面積は限界 18 |
| 1.6.2 水が不足する 18 |
| 1.6.3 安価なエネルギーで成り立つ農業 19 |
| 1.6.4 地力の低下と病害の発生 20 |
| 1.6.5 地球の温暖化 22 |
| 1.7 グローバルな環境問題 22 |
| 1.8 生物についての基礎知識 25 |
| 1.8.1 生物の種類と細胞 25 |
| 1.8.2 微生物とは 28 |
| 1.8.3 細胞の成分 30 |
| 1.8.4 酵素と遺伝子 33 |
| 1.8.5 がん 39 |
| 1.8.6 有害物質に対する体の防御メカニズム 43 |
| 1.8.7 生体へ害作用を及ぼす物質の例 44 |
| 1.9 化学物質の毒性の判定 47 |
| 第2章 水 49 |
| 2.1 水の特異な性質が地球環境を維持している 50 |
| 2.2 水の性質を決めている水素結合とは 51 |
| 2.3 使える水はどれくらいあるか 52 |
| 2.3.1 世界の水資源 52 |
| 2.3.2 日本の水資源 54 |
| 2.4 水の汚染 55 |
| 2.5 水の汚れを判定する方法 57 |
| 2.5.1 臭い,色,味 58 |
| 2.5.2 Ph 58 |
| 2.5.3 浮遊物質 58 |
| 2.5.4 溶存酸素 58 |
| 2.5.5 BOD 59 |
| 2.5.6 COD 59 |
| 2.5.7 全有機炭素量 59 |
| 2.5.8 機器分析 60 |
| 2.5.9 指標生物 60 |
| 2.6 どこまできれいにするか-環境基準と排出基準 61 |
| 2.7 水を汚染する物質の例 63 |
| 2.7.1 重金属 63 |
| 2.7.2 化学農薬 66 |
| 2.7.3 ダイオキシン類 70 |
| 2.7.4 環境ホルモン 71 |
| 2.7.5 リン 72 |
| 2.7.6 窒素 73 |
| 2.8 水の処理法 74 |
| 2.8.1 活性汚泥法 74 |
| 2.8.2 活性汚泥法では窒素とリンが除去できない 76 |
| 2.9 窒素およびリンの第三次処理 77 |
| 2.9.1 化学処理 77 |
| 2.9.2 生物処理 79 |
| 2.10 海洋の汚染 80 |
| 第3章 大気 83 |
| 3.1 現在の大気はどのように形成されたか 83 |
| 3.2 温室効果と二酸化炭素 86 |
| 3.3 二酸化炭素を排出する国 88 |
| 3.4 二酸化炭素以外の温室効果ガス 91 |
| 3.5 温暖化防止のむずかしさ 93 |
| 3.6 温室効果が進むとどうなるか 94 |
| 3.7 大気の構造とオゾン層 97 |
| 3.8 オゾン層の破壊 99 |
| 3.8.1 フロンとは 99 |
| 3.8.2 フロンによるオゾン層の破壊 100 |
| 3.8.3 フロンに代わる物質 101 |
| 3.8.4 一酸化二窒素によるオゾン層の破壊 102 |
| 3.8.5 オゾンホール 103 |
| 3.9 オゾン層が破壊されるとその弊害は? 104 |
| 3.9.1 紫外線には三種類ある 104 |
| 3.9.2 紫外線の皮膚に対する作用 104 |
| 3.10 大気汚染 106 |
| 3.10.1 酸性雨と硫黄酸化物 106 |
| 3.10.2 酸性雨と窒素酸化物 108 |
| 3.10.3 自動車の排ガス 110 |
| 3.10.4 光化学スモッグ 112 |
| 3.10.5 浮遊粒子状物質 114 |
| 第4章 エネルギー 117 |
| 4.1 太陽エネルギーが地球環境を維持している 117 |
| 4.2 人間はどのようなエネルギーを使ってきなか 118 |
| 4.3 石油 119 |
| 4.3.1 石油はどれくらいあるか 119 |
| 4.3.2 石油の問題点 120 |
| 4.4 石炭 122 |
| 4.4.1 石炭のガス化 123 |
| 4.4.2 石炭の液化 124 |
| 4.4.3 石炭の問題点 125 |
| 4.5 原子力エネルギー 126 |
| 4.5.1 原子核とは 126 |
| 4.5.2 原子力発電 128 |
| 4.5.3 高速増殖炉とは何か 131 |
| 4.5.4 原子力発電の問題点 133 |
| 4.6 天然ガス 139 |
| 4.7 核融合 140 |
| 4.8 新しいエネルギー源 141 |
| 4.8.1 オイルシェール 141 |
| 4.8.2 オイルサンド 141 |
| 4.8.3 メタンハイドレート 141 |
| 4.8.4 水素エネルギー 142 |
| 4.8.5 燃料電池 143 |
| 4.9 再生エネルギー 146 |
| 4.9.1 太陽エネルギー 146 |
| 4.9.2 風力エネルギー 148 |
| 4.9.3 水力エネルギー 149 |
| 4.9.4 潮汐エネルギーと海洋温度差発電 150 |
| 4.10 バイオマスエネルギー 150 |
| 4.11 省エネルギー 154 |
| 4.11.1 自家用車よりも公共の交通機関を 154 |
| 4.11.2 日本の省エネルギー 156 |
| 4.11.3 エネルギーの効率とは 157 |
| 4.11.4 豊かさとエネルギー 159 |
| 終章 まとめに代えて 161 |
| 付録 165 |
| 付録A 諸単位の記号 165 |
| 付録B タンパク質構成アミノ酸の構造と名称 166 |
| 付録C DNAを構成する四つの塩基の構造 168 |
| 付録D 環境ホルモンの作用(内分泌撹乱作用)を有すると疑われる化学物質 169 |
| 参考文献 171 |
| 索引 175 |
| 第1章 生物 1 |
| 1.1 地球には三種類の生物がいる 2 |
| 1.2 生物は食物でつながっている 4 |
|
| 31.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
掘越弘毅 [ほか] 著
| 出版情報: |
東京 : 講談社, 1993.6 x, 148p ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 序文 iii |
| 1 はじめに 1 |
| 2 培地の作成と滅菌法 5 |
| 2.1 培地の組成 5 |
| 2.2 別滅菌の注意事項 7 |
| 2.3 プレートとスラント 8 |
| 2.4 液体培地 9 |
| 2.5 オートクレーブ滅菌 11 |
| 2.6 濾過滅菌 13 |
| 2.7 乾熱滅菌 13 |
| 2.8 その他の滅菌法 13 |
| 3 無菌操作と菌株保存法 15 |
| 3.1 無菌操作 15 |
| 3.2 開放系における無菌操作 16 |
| 3.3 クリーンベンチと安全キャビネット 16 |
| 3.4 純粋分離 17 |
| 3.5 集積培養 19 |
| 3.6 植菌と単コロニー分離 19 |
| 3.7 菌株の保存法 22 |
| 3.7.1 継代培養法 22 |
| 3.7.2 軟寒天保存法 23 |
| 3.7.3 流動パラフィン重層法 23 |
| 3.7.4 凍結保存法 24 |
| 3.7.5 凍結乾燥保存法 24 |
| 4 微生物の増殖 26 |
| 4.1 微生物増殖の理論式 26 |
| 4.2 バッチ培養における微生物の増殖曲線 29 |
| 4.2.1 誘導期 29 |
| 4.2.2 対数増殖期 30 |
| 4.2.3 定常期 30 |
| 4.2.4 死滅期 30 |
| 4.3 微生物の培養方法 30 |
| 4.3.1 前培養 31 |
| 4.3.2 本培養 32 |
| 4.4 増殖過程の測定 34 |
| 4.4.1 乾燥重量 34 |
| 4.4.2 濁度 35 |
| 4.4.3 全細胞数 37 |
| 4.4.4 生菌数 38 |
| 5 顕微鏡観察 41 |
| 5.1 顕微鏡の原理と解像度 41 |
| 5.2 位相差顕微鏡 43 |
| 5.3 顕微鏡の取り扱い法 44 |
| 5.3.1 照明 44 |
| 5.3.2 試料の調製 44 |
| 5.3.3 レンズについて 45 |
| 5.3.4 マイクロメーター 45 |
| 5.3.5 保守点検 46 |
| 5.4 顕微鏡写真の撮影法 46 |
| 5.5 蛍光顕微鏡 47 |
| 5.6 電子顕微鏡 49 |
| 5.7 その他の顕微鏡 52 |
| 6 突然変異株の取得 54 |
| 6.1 突然変異体とは 54 |
| 6.2 突然変異株の種類 55 |
| 6.3 変異原処理 57 |
| 6.3.1 紫外線 58 |
| 6.3.2 化学物質 58 |
| 6.3.3 生物的突然変異誘発法 59 |
| 6.4 スクリーニング 61 |
| 6.5 突然変異体の濃縮 63 |
| 6.5.1 ペニシリンスクリーニング法 63 |
| 6.5.2 トリチウム自殺法 64 |
| 6.5.3 比重濃縮法 64 |
| 7 タンパク質の濃縮と分析 66 |
| 7.1 菌体と培地の分離 66 |
| 7.2 タンパク質の抽出と回収 67 |
| 7.2.1 超音波処理 67 |
| 7.2.2 リゾチーム処理 69 |
| 7.2.3 ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)処理 69 |
| 7.3 タンパク質の濃縮と回収 69 |
| 7.3.1 有機溶媒沈殿 70 |
| 7.3.2 硫安沈殿 70 |
| 7.3.3 トリクロロ酢酸(TCA)による沈殿 71 |
| 7.3.4 限外濾過 71 |
| 7.3.5 ポリエチレングリコール(PEG)による濃縮 72 |
| 7.4 脱塩操作 72 |
| 7.5 タンパク質の定量法 73 |
| 7.5.1 ローリー(Lowry)法 73 |
| 7.5.2 ブラッドフォード(Bradford)法 74 |
| 7.6 電気泳動法 75 |
| 7.6.1 ポリアクリルアミドゲル電気泳動法 75 |
| 7.6.2 SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動法 76 |
| 7.6.3 ポリアクリルアミドゲル等電点電気泳動法 77 |
| 8 遺伝子工学的手法 81 |
| 8.1 遺伝子工学で用いられる酵素 81 |
| 8.1.1 制限酵素 83 |
| 8.1.2 DNAリガーゼ 84 |
| 8.1.3 DNAポリメラーゼ 85 |
| 8.1.4 その他の酵素 85 |
| 8.2 染色体DNAの抽出 86 |
| 8.3 大腸菌のためのベクター 87 |
| 8.3.1 宿主とベクター 87 |
| 8.3.2 プラスミドベクター 88 |
| 8.3.3 ファージベクター 88 |
| 8.4 大腸菌への遺伝子導入 88 |
| 8.4.1 プラスミドによる形質転換 88 |
| 8.4.2 ファージを用いた形質導入 89 |
| 8.5 遺伝子ライブラリーのスクリーニング 89 |
| 8.6 DNA塩基配列の決定法 90 |
| 8.6.1 ジデオキシ法(Sanger法) 90 |
| 8.6.2 化学分解法(Maxam-Gilbert法) 92 |
| 8.7 PCR法による遺伝子の増幅 92 |
| 9 免疫学的手法 95 |
| 9.1 抗体の調製 96 |
| 9.1.1 抗血清とモノクローナル抗体 96 |
| 9.1.2 抗血清の調製 96 |
| 9.1.3 モノクローナル抗体の調製 97 |
| 9.2 抗体による抗原の検出と定量 98 |
| 9.2.1 免疫拡散法 98 |
| 9.2.2 免疫凝集反応 99 |
| 9.2.3 ELISA 100 |
| 9.2.4 ウェスタンブロット法 100 |
| 9.3 抗体を用いた抗原の精製 102 |
| 10 微生物の同定 103 |
| 10.1 微生物の命名法 103 |
| 10.2 原核生物と真核生物 104 |
| 10.3 微生物の分類 104 |
| 10.4 形態観察I(肉眼所見) 107 |
| 10.5 形態観察II(顕微鏡観察) 107 |
| 10.6 真菌類の分類 109 |
| 10.7 細菌の分類・同定 111 |
| 11 バイオハザード 116 |
| 11.1 病原性微生物取り扱いの安全対策 117 |
| 11.1.1 病原体などの危険度分類 117 |
| 11.1.2 物理的封じ込め 117 |
| 11.2 組換えDNA実験の安全対策 119 |
| 11.2.1 組換えDNA実験指針 119 |
| 11.2.2 物理的封じ込め 119 |
| 11.2.3 生物学的封じ込め 120 |
| 11.2.4 組換えDNA実験の実施 122 |
| 12 各種機器の取り扱い 123 |
| 12.1 天びん 123 |
| 12.2 pHメーター 124 |
| 12.2.1 ガラス電極の原理 124 |
| 12.2.2 ガラス電極pHメーターの使用法 126 |
| 12.3 遠心分離機 126 |
| 12.4 分光光度計 129 |
| 12.4.1 ランバート・ベールの法則 129 |
| 12.4.2 分光光度計の構成 130 |
| 12.4.3 吸光度の測定 131 |
| 12.5 マイクロピペット 131 |
| 13 付録 133 |
| 索引 139 |
| 序文 iii |
| 1 はじめに 1 |
| 2 培地の作成と滅菌法 5 |
|
| 32.
|
 図書
図書
|
河田敬義著
|
| 33.
|
 図書
図書
|
藤崎源二郎著
|
| 34.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
日本建築学会編
| 出版情報: |
東京 : 技報堂出版, 1998.7 vii, 208p ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 1 概説 1 |
| 1.1 人工知能 1 |
| 1.2 ファジィ理論 3 |
| 1.3 人工生命 4 |
| 1.3.1 生命に学ぶ 4 |
| 1.3.2 ニューラルネットワークモデル 4 |
| 1.3.3 遺伝的アルゴリズム 5 |
| 1.3.4 人工生命 5 |
| 2 人工知能の応用 7 |
| 2.1 計画 7 |
| 2.1.1 開発プロジェクトを支援する土地利用企画提案システム 7 |
| (1) はじめに |
| (2) 開発の目的 |
| (3) CANDLEの構成 |
| (4) 開発の手順 |
| 2.1.2 建物の耐震信頼性評価のためのエキスパートシステム 12 |
| (2) システムの概要 |
| (3) 評価結果の信頼性の検討 |
| (4) まとめ |
| 2.1.3 防災計画と避難シミュレーション 16 |
| (2) 既往の避難シミュレーションモデルの概観 |
| (3) オブジェクト指向と避難シミュレーション |
| (4) 避難安全性評価と避難シミュレーション |
| (5) おわりに |
| 2.2 設計 20 |
| 2.2.1 オブジェクト指向と設計 20 |
| (2) 設計の知識 |
| (3) オブジェクト指向 |
| (4) 設計のモデル |
| (5) 知的システムの将来像 |
| 2.2.2 建築モデル 24 |
| (1) 構築のモデリング |
| (2) 意味の体系 |
| (3) おわりに |
| 2.2.3 IFCによるCADデータ共有と相互運用 28 |
| (2) IFCの概要 |
| (3) IFCにおける高度情報技術への対応 |
| (4) IFC準拠のCAD機能 |
| (5) 今後のIFCの課題 |
| (6) おわりに |
| 2.2.4 設計計画とコラボレーション 33 |
| (1)はじめに |
| (2) 他分野におけるコラボレーション |
| (3) 建築分野での先験的なコラボレーション例 |
| (4) 建築設計分野のコラボレーション |
| 2.2.5 エージェント指向 38 |
| (1) エージェント指向とは |
| (2) エージェントとは |
| (3) エージェント指向問題解決 |
| (4) 可動(モバイル)エージェント |
| (5) まとめ |
| 2.2.6 エージェント指向と構造解析 42 |
| (1) 複雑化と巨大化 |
| (2) エージェント指向の分散型計算システム |
| (3) 可動エージェント指向コミュニティMAOC |
| (4) 構造解析におけるエージェント指向システム |
| 2.2.7 協調型設計活動支援 47 |
| (1) 建築分野のCSCW |
| (2) VDS'96 Kumamoto Artpolis Project |
| 2.3 生産 51 |
| 2.3.1 統合化建築生産システム 51 |
| (2) PDBの管理情報 |
| (3) システムの運用 |
| (4) おわりに |
| 2.3.2 工程計画の立案における知的推論システム 55 |
| (1) 工程計画の知的支援 |
| (2) 工程計画の推論機構 |
| (3) 割付方式による工程計画のプロトタイプシステム |
| 2.3.3 建築工事におけるプロジェクト管理 59 |
| (2) 建築工事のプロジェクト管理 |
| 3 ファジィ理論の応用 63 |
| 3.1 診断 63 |
| 3.1.1 コンクリートのひび割れ原因検索 63 |
| (1) 異常診断におけるあいまいな条件命題 |
| (2) 条件命題の診断への応用 |
| (3) 計算例 |
| 3.1.2 避難シミュレーション 68 |
| (2) ファジィ化の意義 |
| (3) ファジィ適用のモデル |
| (4) 人の動きの決定方法 |
| (5) 数式的なアプローチ |
| (6) ファジィ的なアプローチ |
| (7) メンバーシップ関数 |
| (8) ファジィ推論 |
| (9) シミュレーションの結果 |
| (10) おわりに |
| 3.2 評価 74 |
| 3.2.1 室内空間の高さ感の評価 74 |
| (2) 分割型ファジィ積分 |
| (3) 室内空間の高さ感に対する評価問題への適用 |
| 3.2.2 高層ビルの外観(デザイン)評価 78 |
| (1) ファジィ測度による評価モデル |
| (2) ファジィ測度の同定 |
| (3) 超高層建築の外観デザイン |
| 3.3 制御 83 |
| 3.3.1 ラーメン構造の振動制御 83 |
| (2) 制振システム |
| (3) 最適制御変数の決定(最大化決定) |
| (4) 結果と考察 |
| 3.3.2 シェル構造の振動制御 87 |
| (2) シェルの基礎式 |
| (3) 裾梁の基礎式 |
| (4) 裾梁付き回転体シェルの振動方程式 |
| (5) 制御理論 |
| (6) 解析モデル |
| (7) 解析結果 |
| (8) 結論 |
| 3.3.3 大空間空調制御 91 |
| (2) 大空間空調方式の概要 |
| (3) ファジィ空調制御システムの概要 |
| (4) 実験結果 |
| 3.4 最適化 95 |
| 3.4.1 インテリジェントネットワークを用いた建築物の最適耐震構造計画 95 |
| (2) ファジィネットワーク |
| (3) ニューラルネットワークを用いた主観的評価の同定 |
| (4) ファジィネットワークの解法 |
| (5) 構造計画への応用 |
| 3.4.2 耐震壁の最適配置計画 ファジィ制約下の最適化問題 100 |
| (1) 耐震壁の最適配置問題 |
| (2) ファジィ制約条件の導入 |
| (3) 設計例 |
| 3.4.3 ファジィクラスタリングによる構造物の荷重 変形曲線の折れ線近似法 105 |
| (2) 解析手法の概要 |
| (3) 数値計算例と解析手法の適用性 |
| 4 人工生命の応用 109 |
| 4.1 人工生命 109 |
| 4.1.1 セルオートマトンによる都市の土地利用パターンの形成 109 |
| (2) モデル |
| (3) シミュレーション結果 |
| (4) 考察・まとめ |
| 4.1.2 セルオートマトンによる構造物の形態形成 113 |
| (2) 基礎理論 |
| (3) CAを用いた構造物の形態形成 |
| (4) 3次元CAを用いた柱梁構造物の形態形成 |
| (5) 2次元CAを用いた構造物の形態形成 |
| (6) 結果 |
| (7) おわりに |
| 4.1.3 LシステムとGAを利用した構造形態の形成手法 117 |
| (2) Lシステムと形態形成 |
| (3) 遺伝的アルゴリズム(GA)と形態の変化 |
| 4.2 遺伝的アルゴリズム(GA) 122 |
| 4.2.1 逆解析による地盤構造の推定 122 |
| (2) 微動のアレイ観測 |
| (3) GAを用いた逆解析による地盤構造の推定 |
| 4.2.2 トラスのトポロジー・節点位置最適化 126 |
| (2) トラスのトポロジー最適化 |
| (3) 平面トラスのトポロジー・節点位置同時最適化 |
| 4.2.3 形態創生 130 |
| (1) ホモロガス構造の形態解析 |
| (2) 目的関数と適応度 |
| (3) 設計パラメータのコード化 |
| (4) ホモロガス構造の解析結果 |
| (5) 曲面形態生成への応用 |
| (6) まとめ |
| 4.2.4 制振構造物の設計 134 |
| (2) 対象構造物と設計変数 |
| (3) GAによる探索結果 |
| 4.2.5 遺伝的アルゴリズムを用いた地域施設配置手法 138 |
| (2) 施設配置案のコーディング方法 |
| (3) 配置案の評価関数の定義 |
| (4) 数値例の施設配置問題への適用と効率性 |
| (5) 実際の地域施設計画での適用 |
| 4.3 ニューラルネットワーク 143 |
| 4.3.1 逆問題 性能設計法への新しい展開 143 |
| (1) 理論と現実問題とのギャップ |
| (2) ニューラルネットワークによる性能指定設計法 |
| (3) ニューラルネットワークの構成と学習結果 |
| (4) 結論 |
| 4.3.2 トラスの最適断面設計 147 |
| (2) 解析手法 |
| (3) トラスの最適断面設計 |
| 4.3.3 ニューラルネットワークによる質点系構造物の振動制御 152 |
| (2) 制御対象 |
| (3) 制御シミュレーションの流れ |
| (4) シミュレーション結果 |
| (5) 結論 |
| 4.3.4 設計者の意図を考慮した配置評価方法 156 |
| (1) スキーマグラマーとニューラルネットワーク |
| (2) ケーススタディと評価モデルの構築 |
| (3) 中間層の解釈と今後の可能性 |
| 4.3.5 建築空間構成へのニューラルネットワークの適用 161 |
| (1) 空間配置の最適化について |
| (2) 満足化および最適化について |
| (3) 解の探索について |
| (4) 応用手法の概念 |
| (5) 図形操作のシミュレーション |
| 5 知的システム 165 |
| 5.1 知的システムを用いた建築構造物の最適アクティブ制御システム 165 |
| 5.1.1 はじめに 165 |
| 5.1.2 基本仮定 166 |
| 5.1.3 地震動入力予測と構造物応答予測(構造同定) 167 |
| 5.1.4 最大化決定による適制御変数の決定 168 |
| 5.1.5 ディジタルシミュレーション 168 |
| 5.1.6 おわりに 169 |
| 5.2 ファジィニューロによる地震動予測 171 |
| 5.2.1 初期微動による主要動の予測 171 |
| 5.2.2 最大加速度予測モデル 171 |
| 5.2.3 地震発生地域の推定 173 |
| 5.2.4 構造化最大加速度予測モデル 175 |
| 5.2.5 まとめ 176 |
| 5.3 知命共創進化システム 177 |
| 5.3.1 生命体進化システムの3原理 177 |
| 5.3.2 知命共創進化システム 178 |
| 5.3.3 多重最適化システム 179 |
| 5.3.4 複雑系モデルを目指して 180 |
| 6 付録 183 |
| 付録-1 ファジィ理論の基本概念 183 |
| (1) ファジィ理論 |
| (2) ファジィクラスタリング |
| (3) ファジィ推論 |
| (4) ファジィ数 |
| (5) ファジィ測度 |
| (6) ファジィ積分 |
| (7) ファジィ論理 |
| (8) 言語的真理値 |
| (9) 最大化決定 |
| (10) ファジィ制御 |
| (11) ファジィ集合 |
| (12) ファジィ演算 |
| (13) ファジィ関係 |
| (14) 拡張原理 |
| (15) タイプ2およびレベル2のファジィ集合 |
| (16) ファジィ意思決定 |
| (17) AHP |
| 付録-2 人工生命の基本概念 193 |
| 2.1 人工生命の基本概念 193 |
| (1) 人工生命 |
| (2) 創発 |
| (3) 自己組織化 |
| (4) セルオートマトン |
| (5) L-システム |
| (6) 進化 |
| (7) 複雑系 |
| 2.2 遺伝的アルゴリズム 197 |
| (1) 遺伝的アルゴリズムの基本概念 |
| (2) 遺伝的操作 |
| 2.3 ニューラルネットワークの基本概念 201 |
| (1) 基本原理 |
| (2) 階層型ネットワーク |
| (3) バックプロバーゲーションアルゴリズム |
| (4) 相互結合型ネットワーク |
| (5) ホップフィールドネットワーク |
| (6) ボルツマンマシン |
| 索引 205 |
| 1 概説 1 |
| 1.1 人工知能 1 |
| 1.2 ファジィ理論 3 |
|
| 35.
|
 図書
図書
|
ジェリー・B.マリオン著 ; 伊原千秋訳
| 出版情報: |
東京 : 紀伊国屋書店, 1972.9-1973.5 2冊 ; 22cm |
| シリーズ名: |
現代基礎物理学選書 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 36.
|
 図書
図書
|
藤田重文, 東畑平一郎編
| 出版情報: |
東京 : 東京化学同人, 1963 4冊 ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 37.
|
 図書
図書
|
東京電力
| 出版情報: |
[東京] : [東京電力], 1990 754p, 図版4枚 ; 31cm |
| シリーズ名: |
柏崎刈羽原子力 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 38.
|
 図書
図書
|
星野芳郎著
| 出版情報: |
東京 : 勁草書房, 1977.3-1978.7 2冊 ; 19cm |
| シリーズ名: |
星野芳郎著作集 ; 第1巻,第2巻 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 39.
|
 図書
図書
|
A.G.クローシュ著 ; 吉崎敬夫訳
| 出版情報: |
東京 : 東京図書, 1963.5-1963.8 2冊 ; 22cm |
| シリーズ名: |
数学選書 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 40.
|
 図書
図書
|
ブルバキ [著] ; 前原昭二編 ; 前原昭二訳
|
| 41.
|
 図書
図書
|
藤田重文 [ほか] 著
| 出版情報: |
東京 : 岩波書店, 1956.4-1963.11 3冊 ; 18cm |
| シリーズ名: |
岩波全書 ; 216, 254, 255 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 42.
|
 図書
図書
|
R. クーラン, D. ヒルベルト著 ; 斎藤利弥監訳 ; 丸山滋弥訳
| 出版情報: |
東京 : 商工出版社, 1959.3-1968.8 4冊 ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 43.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
F.R.コナー原著 ; 関口利男, 辻井重男監訳 ; 荒木純道訳
目次情報:
続きを見る
| 序文 |
| 1. はじめに 1 |
| 1.1 平行2線(レッヘル線) 2 |
| 1.2 同軸ケーブル 3 |
| 1.3 ストリップ線路とマイクロストリップ 5 |
| 1.4 導波管 8 |
| 1.5 光ファイバ 11 |
| 2. 伝送線路 |
| 2.1 一般的な伝送線路 13 |
| 2.2 線路の2次定数 15 |
| 2.3 無限長線路 16 |
| 2.4 ハイパボリック解 17 |
| 2.5 実際の線路 19 |
| 2.6 一般の終端条件 19 |
| 2.7 特別な場合 20 |
| 2.8 線路の分類 23 |
| 2.9 位相遅延と群遅延 27 |
| 2.10 線路の反射 31 |
| 2.11 反射係数 33 |
| 2.12 電圧定比波比(VSWR) 34 |
| 2.13 スミス図表 35 |
| 2.14 代表的な例 40 |
| 3. 電磁波 |
| 3.1 電磁界 43 |
| 3.2 電磁界理論 45 |
| 3.3 境界条件 51 |
| 3.4 反射波と屈折波 54 |
| 4. 導波管理論 59 |
| 4.1 導波管伝送 59 |
| 4.2 位相速度および群速度 61 |
| 4.3 導波管方程式 62 |
| 4.4 矩形導波管 65 |
| 4.5 矩形モード 66 |
| 4.6 円形導波管 71 |
| 4.7 円形モード 71 |
| 4.8 高次モード 73 |
| 4.9 導波管モードの減衰 75 |
| 4.10 導波管モードの励振 79 |
| 5. マイクロ波工学 81 |
| 5.1 マイクロ波発振器 81 |
| 5.2 マイクロ波コンポーネント 86 |
| 5.3 マイクロ波測定 93 |
| 6. 光通信 102 |
| 6.1 発光源 102 |
| 6.2 ファイバケーブル 105 |
| 6.3 検出器と受光器 114 |
| 6.4 最近の進展 120 |
| 問題 123 |
| 解答 129 |
| 参考文献 131 |
| 付録 133 |
| A. ストリップ線路とマイクロストリップ 133 |
| B. フェライト 135 |
| C. 空胴共振器 138 |
| D. ファイバモード理論 143 |
| さくいん 146 |
| 序文 |
| 1. はじめに 1 |
| 1.1 平行2線(レッヘル線) 2 |
|
| 44.
|
 図書
図書
|
I. プリゴジーヌ, R. デフェイ [著] ; 妹尾学訳
| 出版情報: |
東京 : みすず書房, 1966.5-1966.10 2冊 ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 45.
|
 図書
図書
|
斎藤利弥著
|
| 46.
|
 図書
図書
|
ア・イ・マリツェフ著 ; 柴岡泰光訳
| 出版情報: |
東京 : 商工出版社, 1960.3-1961.6 2冊 ; 21cm |
| シリーズ名: |
数学選書 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 47.
|
 図書
図書
|
川上正光著
|
| 48.
|
 図書
図書
|
武藤俊之助 [ほか] 執筆
目次情報:
| 1: 物性論概説 / 武藤俊之助 |
| 統計力学序論 / 橋爪夏樹 |
| 量子力学序論 / 有山兼孝 |
| 1: 物性論概説 / 武藤俊之助 |
| 統計力学序論 / 橋爪夏樹 |
| 量子力学序論 / 有山兼孝 |
|
| 49.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
門田和雄著
| 出版情報: |
東京 : 技術評論社, 2001.4 x, 356p ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| Chapter1 材料の強さと種類 |
| 1-1 材料の強さ 2 |
| 1. 応力とひずみ 2 |
| 2. 材料試験 13 |
| 3. はりの曲げと断面係数 22 |
| 4. トラス 39 |
| 5. ねじりと座屈 47 |
| 6. 材料の破壊 56 |
| 1-2 機械材料 64 |
| 1. 金属の組織 64 |
| 2. 鉄鋼材料 70 |
| 3. アルミニウム材料 79 |
| 4. その他の金属材料 82 |
| 5. セラミックス材料 85 |
| 6. 複合材料 88 |
| Chapter2 流体力学と流体機械 |
| 2-1 流体力学 94 |
| 1. 流体の性質94 |
| 2. 流体の静力学 106 |
| 3. 流体の動力学 113 |
| 4. 層流と乱流 125 |
| 5. 流体の測定 127 |
| 6. 流体抵抗 138 |
| 2-2 流体機械 146 |
| 1. 風車 146 |
| 2. 水車 152 |
| 3. ポンプ 157 |
| 4. 空気圧システム 163 |
| Chapter3 熱力学と熱機関 |
| 3-1 熱力学 172 |
| 1. 熱と仕事 172 |
| 2. 気体の状態方程式 175 |
| 3. 熱力学の第1法則 183 |
| 4. 理想気体の状態変化 190 |
| 5. 熱力学の第2法則 197 |
| 3-2 熱機関 203 |
| 1. ガソリン機関 203 |
| 2. 蒸気原動機 216 |
| 3. ガスタービン 230 |
| Chapter4 機構と制御 |
| 4-1 機構 246 |
| 1. リンク装置 246 |
| 2. カム装置 257 |
| 3. 歯車 263 |
| 4. ベルト・チェーン 275 |
| 5. その他の機械部品 279 |
| 4-2 制御 283 |
| 1. 電気回路 283 |
| 2. シーケンス制御 296 |
| Chapter5 創造耕作室 |
| 5-1 計測編 314 |
| 1. 計測とは 314 |
| 2. 長さの測定 315 |
| 3. 質量、力の計測 320 |
| 4. 時間、回転数の計測 322 |
| 5-2 工具編 324 |
| 5-3 工作編 327 |
| 1. 手仕上げ 327 |
| 2. 旋盤 335 |
| 3. 溶接 339 |
| 4. 鋳造 334 |
| COLUMN |
| [MPa]から[N/mm2]への換算 4 |
| 円の断面積の求め方 7 |
| 金属材料の縦弾性係数Eと横弾性係数G 9 |
| ロバート・フック 13 |
| ダイヤモンドは何で削るか 19 |
| 鳥吸い込み試験 21 |
| 2次曲線の最大値の求め方 28 |
| 三角法 42 |
| 力の大きさを計算で求めよう 47 |
| 生物の形と強さ 55 |
| 粘弾性 63 |
| 日本の硬貨の材質 83 |
| 運動の法則 105 |
| 水中翼船 110 |
| ポンプの応用 162 |
| 火星探査 242 |
| 機械工学で使う微分 262 |
| 実験 |
| 実験1-1 フックの法則の検証実験 11 |
| 実験1-2 引張試験 15 |
| 実験1-3 ショア硬さ試験 18 |
| 実験1-4 シャルピー衝撃試験 20 |
| 実験1-5 ばねを伸ばす 56 |
| 実験2-1 空気天秤の実験 95 |
| 実験2-2 ペットボトルから飛び出す水 101 |
| 実験2-3 缶ペコ 102 |
| 実験2-4 ラップ破裂 103 |
| 実験2-5 逆さまコップ 103 |
| 実験2-6 ホースの流速 113 |
| 実験2-7 蛇口の流れ 125 |
| 実験2-8 タービンデザイン・コンテスト 149 |
| 実験2-9 車輪を利用した風車 151 |
| 実験3-1 熱気球の製作 130 |
| 実験3-2 蒸気タービンの製作と性能試験 225 |
| 実験3-3 ペットボトルロケット 239 |
| Chapter1 材料の強さと種類 |
| 1-1 材料の強さ 2 |
| 1. 応力とひずみ 2 |
|
| 50.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
古川静二郎執筆
目次情報:
続きを見る
| 1.半導体の基礎 |
| 1.1 結晶とエネルギー帯域構造 1 |
| 1.1.1 結晶と非晶質 1 |
| 1.1.2 結晶構造 2 |
| 1.1.3 半導体結晶のエネルギー帯構造 3 |
| 1.1.4 半導体材料の多様性 7 |
| 1.2 キャリヤ密度 8 |
| 1.2.1 2種類のキャリヤと有効質量 8 |
| 1.2.2 真性半導体と外因性半導体 10 |
| 1.2.3 キャリヤ密度とフェルミ準位 11 |
| 1.3 半導体中の電気伝導 17 |
| 1.3.1 ドリフト現象 17 |
| 1.3.2 拡散現象 19 |
| 1.3.3 電流の式 20 |
| 1.3.4 キャリヤの熱的発生と再結合 21 |
| 1.3.5 電流連続の式 26 |
| 演習問題 28 |
| 2.接合と障壁 |
| 2.1 pn接合と整流特性 30 |
| 2.1.1 pn接合の重要性 30 |
| 2.1.2 階段接合の整流作用 31 |
| 2.2 空間電荷層の特性 34 |
| 2.2.1 階段接合の場合 34 |
| 2.2.2 傾斜形pn接合 37 |
| 2.3 理想pn接合の静的電圧・電流特性 39 |
| 2.3.1 解析の仮定 39 |
| 2.3.2 過剩キャリヤ密度 40 |
| 2.3.3 中性領域を流れる電流 41 |
| 2.4 金属-半導体接触の電気伝導 45 |
| 2.4.1 理想整流接触 45 |
| 2.4.2 理想金属-半導体整流接触の電圧電流特性 47 |
| 2.4.3 金属-半導体オーミック接触 49 |
| 演習問題 50 |
| 3.半導体デバイスの製作法 |
| 3.1 半導体の精製 52 |
| 3.2 結晶成長 53 |
| 3.2.1 バルク結晶成長 53 |
| 3.2.2 エピタキシアル成長 54 |
| 3.3 不純物導入法 55 |
| 3.3.1 結晶成長過程の不純物導入法とpn接合形成 55 |
| 3.3.2 熱拡散法 56 |
| 3.3.3 イオン打込み法 57 |
| 3.4 プレーナ技術 59 |
| 3.4.1 酸化膜の形成 59 |
| 3.4.2 ホトリングラフィと化学エッチング 60 |
| 3.4.3 電極付着 61 |
| 3.4.4 プレーナダイオードの製作 62 |
| 演習問題 63 |
| 4.半導体ダイオードとその実際 |
| 4.1 pnダイオードの直流特性の実際 64 |
| 4.1.1 キャリヤの発生と再結合効果 65 |
| 4.1.2 降伏現象 67 |
| 4.1.3 直列抵抗効果 71 |
| 4.1.4 高水準注入効果 72 |
| 4.2 薄いベース層を有するpn接合ダイオードの直流特性 73 |
| 4.2.1 npp+形ダイオードの電流・電圧特性 74 |
| 4.2.2 キャリヤのベース走行時間 75 |
| 4.3 pn接合ダイオードの動特性 77 |
| 4.3.1 少数キャリヤ蓄積効果 77 |
| 4.3.2 拡散容量と接合容量 77 |
| 4.3.3 スイッチング特性の過渡特性 78 |
| 4.4 半導体ダイオードの回路モデル 80 |
| 4.4.1 微小信号モデル 80 |
| 4.4.2 大信号直流モデル 81 |
| 4.5 半導体ダイオードの応用 82 |
| 4.5.1 整流ダイオード 82 |
| 4.5.2 検波ダイオード 84 |
| 4.5.3 スイッチングダイオード 86 |
| 4.5.4 ステップレカバリダイオード 88 |
| 4.5.5 pinダイオード 88 |
| 4.5.6 可変容量ダイオード 88 |
| 4.5.7 定電圧ダイオード 89 |
| 演習問題 90 |
| 5.トランジスタ構造とその増幅作用 |
| 5.1 増幅用デバイスの分類 91 |
| 5.2 動作原理 92 |
| 5.2.1 ベース接地トランジスタの増幅作用 92 |
| 5.2.2 エミッタ接地トランジスタの増幅作用 95 |
| 5.2.3 電流駆動形増幅デバイス 97 |
| 5.3 電流伝送率 98 |
| 5.3.1 注入効率 99 |
| 5.3.2 輸送効率 100 |
| 5.3.3 コレクタ効率 101 |
| 5.3.4 電流伝送率αとドーピング分布 101 |
| 5.4 バイポーラトランジスタの小信号等価回路 102 |
| 5.4.1 ベース接地T形等価回路 103 |
| 5.4.2 エミッタ接地T形等価回路 103 |
| 5.4.3 コレクタ接地T形等価回路 104 |
| 5.4.4 トランジスタ応用の多様性 105 |
| 5.5 四端子パラメータ 106 |
| 演習問題 109 |
| 6.バイポーラトランズスタの動作の実際 |
| 6.1 高周波動作 111 |
| 6.1.1 電流伝送率の遮断周波数 111 |
| 6.1.2 高周波等価回路 113 |
| 6.1.2 エミッタ接地回路の利得帯域幅積 115 |
| 6.2 トランジスタの雑音特性 118 |
| 6.2.1 雑音に関する基礎事項 118 |
| 6.2.2 トランジスタの雑音 119 |
| 6.3 トランジスタに見られる諸効果 120 |
| 6.3.1 ドリフト効果 120 |
| 6.3.2 電流増幅率のエミッタ電流依存性とキャリヤ再結合効果 121 |
| 6.3.3 電子雪崩効果 122 |
| 6.3.4 アーリー効果 122 |
| 6.3.5 残留抵抗効果 123 |
| 6.3.6 カーク効果 123 |
| 6.3.7 電流集中効果 123 |
| 6.4 スイッチング動作 124 |
| 6.4.1 スイッチングの基本回路 124 |
| 6.4.2 トランジスタの動作状態 125 |
| 6.4.3 スイッチング速度 126 |
| 6.5 各種トランジスタの実際と応用 128 |
| 6.5.1 バイポーラトランジスタ増幅回路とバイアス回路 128 |
| 6.5.2 大電力トランジスタ 130 |
| 6.5.3 マイクロ波用トランジスタ 133 |
| 6.5.4 スイッチングトランジスタ 134 |
| 6.6 モノリシックバイポーラトランジスタ集積回路 135 |
| 6.6.1 集積回路の特徴 135 |
| 6.6.2 IC構成法 136 |
| 6.6.3 バイポーラICの実例 137 |
| 演習問題 138 |
| 7.金属・絶縁物・半導体構造とその増幅作用 |
| 7.1 増幅作用の物理的意味 140 |
| 7.2 理想MIS構造の性質 142 |
| 7.2.1 理想MIS構造の基本特性 143 |
| 7.2.2 誘導電荷密度のゲート電圧依存性 147 |
| 7.3 しきい電圧に与えるその他の諸効果 149 |
| 7.3.1 仕事関数差 149 |
| 7.3.2 絶縁膜の電荷 150 |
| 7.3.3 界面準位密度 151 |
| 7.4 MISトランジスタの基本特性 153 |
| 7.4.1 線形領域の動作 153 |
| 7.4.2 ピンチオフ領域の動作 155 |
| 7.4.3 エンハンスメント形およびデプレション形FET 156 |
| 7.4.4 nチャネルとpチャネル形FET 157 |
| 演習問題 158 |
| 8.電界効果トランジスタと関連デバイス |
| 8.1 MIS FETの動特性 160 |
| 8.1.1 動的モデルと徴小信号等価回路 160 |
| 8.1.2 利得帯域幅積 162 |
| 8.2 MIS FET における諸効果 164 |
| 8.2.1 基板バイアス効果 164 |
| 8.2.2 チャネル長変調効果 165 |
| 8.2.3 突抜けと電子雪崩降伏効果 165 |
| 8.2.4 二次元キャリヤドリフト効果と強電界効果 166 |
| 8.2.5 ソース残留抵抗効果 166 |
| 8.3 MIS FETの実際と応用 167 |
| 8.3.1 MOS FETの小信号パラメータ 167 |
| 8.3.2 交流増幅回路 168 |
| 8.3.3 大電力MIS FET増幅回路 169 |
| 8.3.4 ディジタル回路 169 |
| 8.3.5 スイッチング回路 170 |
| 8.4 MOS集積回路(IC) 171 |
| 8.4.1 MOSインバータ 171 |
| 8.4.2 MOSメモリ 173 |
| 8.4.3 電荷転送デバイス(CTD) 175 |
| 8.5 接合およびショットキー障壁FET 177 |
| 8.5.1 pn接合FET 177 |
| 8.5.2 ショットキー障壁(SB)FET 180 |
| 8.6 静電誘導形トランジスタ(SIT) 181 |
| 8.6.1 原理と構造 182 |
| 8.6.2 SITの応用と実祭 185 |
| 演習問題 186 |
| 9.能動二端子デバイス |
| 9.1 負性抵抗と不安定性 188 |
| 9.2 サイリスタ 189 |
| 9.2.1 ショックレーダイオード 189 |
| 9.2.2 SCRにおけるトリガ機構 191 |
| 9.2.3 SCRの応用 192 |
| 9.2.4 サイリスタの実際と変種 194 |
| 9.3 ユニジャンクショントランジスタ 197 |
| 9.3.1 UJTの構造と原理 197 |
| 9.3.2 UJTの応用 198 |
| 9.4 マイクロ波能動デバイス 199 |
| 9.4.1 エサキダイオード 199 |
| 9.4.2 ガンダイオード 200 |
| 9.4.3 インパットダイオード 202 |
| 9.4.4 その他の走行時間ダイオード 203 |
| 演習問題 204 |
| 10.電気・光変換デバイス |
| 10.1 半導体の光物性 205 |
| 10.1.1 半導体による吸収 205 |
| 10.1.2 半導体における発光現象 206 |
| 10.2 光検出デバイス 208 |
| 10.2.1 光導電セル 208 |
| 10.2.2 ホトダイオード 211 |
| 10.2.3 雪崩ホトダイオード 213 |
| 10.2.4 ホトトランジスタ 214 |
| 10.3 太陽電池 215 |
| 10.4 発光素子 218 |
| 10.4.1 発光ダイオード 218 |
| 10.4.2 半導体レーザ 219 |
| 演習問題 222 |
| 付録 224 |
| 演習問題解答 225 |
| 索引 227 |
| 1.半導体の基礎 |
| 1.1 結晶とエネルギー帯域構造 1 |
| 1.1.1 結晶と非晶質 1 |
|

















