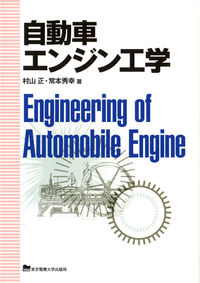| 1.
|
 図書
図書
|
ブライアン・コックス, ジェフ・フォーショー [著] ; 柴田裕之訳
| 出版情報: |
東京 : 紀伊國屋書店, 2011.9 329p ; 20cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 2.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
宗宮重行[ほか]編
| 出版情報: |
東京 : 技報堂出版, 2002.8 xv, 384p ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 共通基礎データ ⅷ |
| 第Ⅰ編 環境・リサイクル分野 |
| 第Ⅰ-1章 総 論 3 |
| 1.1 はじめに 3 |
| 1.2 環境問題 3 |
| 1.3 材料技術の応用分野 4 |
| 1.4 セラミックスの応用 5 |
| 1.4.1 構造的なメリット 5 |
| 1.4.2 機能的なメリット 6 |
| 1.4.3 セラミックスのデメリット 6 |
| 1.5 おわりに 7 |
| 第Ⅰ-2章 各 論 9 |
| 2.1 ろ過機能 9 |
| 2.1.1 ディーゼルパティキュレートフィルター(DPF) 9 |
| 2.1.2 高温集塵フィルター 12 |
| 2.1.3 排水処理用セラミックス膜フィルター 19 |
| 2.2 ケミカルセンター 22 |
| 2.2.1 可燃性ガスセンサー 22 |
| 2.2.2 有害ガスセンサー 26 |
| 2.3 セラミックス担体 34 |
| 2.3.1 セラミックスハニカム 34 |
| 2.3.2 バイオリアクター 37 |
| 2.4 表面機能性セラミックス 39 |
| 2.4.1 抗菌部材 39 |
| 2.4.2 親水性部材(半導体の光励起反応を利用した機能薄膜材料) 44 |
| 2.4.3 ゼオライトとNOx分解触媒 54 |
| 2.5 リサイクル関連技術 59 |
| 2.5.1 リサイクルとは 59 |
| 2.5.2 リサイクルの目的 59 |
| 2.5.3 廃棄物総合対策の中でのリサイクルの位置付け 62 |
| 2.5.4 セラミックス産業関連リサイクル 62 |
| 2.6 そ の 他 64 |
| 2.6.1 セラミックス吸音材 64 |
| 2.6.2 セラミックス電波吸収体 69 |
| 第Ⅰ-3章 基礎データ 73 |
| 第Ⅱ編 情報・通信分野 |
| 第Ⅱ-1章 総 論 79 |
| 1.1 エレクトロニクスの動向と機能性セラミックスの進歩 79 |
| 1.1.1 エレクトロニクスの動向 79 |
| 1.1.2 機能性セラミックスの進歩 80 |
| 1.1.3 機能性セラミックスの分類と用途 82 |
| 第Ⅱ-2章 各 論 85 |
| 2.1 絶縁性セラミックス 85 |
| 2.1.1 セラミックス多層配線基板 85 |
| 2.1.2 IC基板について 90 |
| 2.2 半導性セラミックス 94 |
| 2.2.1 サーミスター(NTC,PTC) 94 |
| 2.2.2 バリスタ 102 |
| 2.2.3 各種センサー 106 |
| 2.3 イオン導電性セラミックス 113 |
| 2.3.1 リチウムイオン電池 113 |
| 2.3.2 酸素センサー 117 |
| 2.4 圧電性セラミックス 121 |
| 2.4.1 セラミックスフィルター 121 |
| 2.4.2 圧電振動ジャイロ 124 |
| 2.4.3 圧電トランス 129 |
| 2.4.4 薄膜デバイス 133 |
| 2.5 誘電性セラミックス 139 |
| 2.5.1 積層コンデンサー 139 |
| 2.5.2 誘電体フィルター 143 |
| 2.6 磁性セラミックス 147 |
| 2.6.1 MR,GMRヘッド 147 |
| 2.6.2 高周波電源用フェライト 152 |
| 2.7 酸化物化学結晶 157 |
| 2.7.1 固体レーザー 157 |
| 第Ⅱ-3章 基礎データ 167 |
| 第Ⅲ編 エネルギー分野 |
| 第Ⅲ-1章 総 論 173 |
| 1.1 はじめに 173 |
| 1.2 物理学の階層構造 173 |
| 1.3 古典場における物理量の相関関係 175 |
| 1.3.1 示強性物理量と示量性物理量 176 |
| 1.3.2 物質定数の定義 176 |
| 1.3.3 物質から材料へ 熱的・機械的機能に及ぼす諸因子 178 |
| 1.4 おわりに 179 |
| 第Ⅲ-2 各 論 181 |
| 2.1 機械的機能 181 |
| 2.1.1 高弾性エネルギー(ばね) 181 |
| 2.1.2 高硬度(工具,コーティング) 185 |
| 2.1.3 耐摩耗性(軸受,摺動部品) 189 |
| 2.1.4 潤滑性(固体潤滑剤) 193 |
| 2.1.5 複合材 198 |
| 2.2 熱的機能 204 |
| 2.2.1 高温強度(タービン用材料) 204 |
| 2.2.2 耐熱性・耐熱衝撃性 207 |
| 2.2.3 断熱性(断熱材) 212 |
| 2.3 耐 食 性 217 |
| 2.3.1 高温耐食性(炉材) 217 |
| 2.3.2 耐薬品性(耐酸性ポンプ) 227 |
| 2.4 エネルギー変換効率 232 |
| 2.4.1 熱電変換 232 |
| 2.4.2 燃料電池 239 |
| 2.4.3 原 子 力 243 |
| 2.5 加工・接合 247 |
| 2.5.1 研削加工 247 |
| 2.5.2 砥粒加工 251 |
| 2.5.3 ビーム加工 254 |
| 2.5.4 接合 259 |
| 第Ⅲ-3章 基礎データ 279 |
| 第Ⅳ編 バイオ分野 |
| 第Ⅳ-1章 総 論 287 |
| 1.1 生体修復セラミックスの最新の動向 287 |
| 1.1.1 はじめに 287 |
| 1.1.2 高強度,高耐摩性セラミックス 287 |
| 1.1.3 生体活性セラミックス 288 |
| 1.1.4 吸収性セラミックス 289 |
| 1.1.5 生体活性セメント 289 |
| 1.1.6 生体活性セラミックス金属複合体 290 |
| 1.1.7 生体活性セラミックス高分子複合体 291 |
| 1.1.8 がん治療用セラミックス 291 |
| 1.1.9 おわりに 292 |
| 1.2 生体材料の臨床応用の基礎 293 |
| 1.2.1 生体材料の使用目的 293 |
| 1.2.2 期待する特性 294 |
| 1.2.3 セラミックスと生体内環境 296 |
| 第Ⅳ-2章 各 論 299 |
| 2.1 バイオイナートセラミックス 299 |
| 2.1.1 アルミナセラミックス 299 |
| 2.1.2 ジルコニアセラミックス 306 |
| 2.2 バイオアクティブセラミックス 310 |
| 2.2.1 ハイドロキシアパタイト(HA) 310 |
| 2.3 人口歯・人口歯根 314 |
| 2.3.1 人口歯・人口歯根用セラミックス 314 |
| 2.4 バイオセラミックスコーティング 320 |
| 2.4.1 ハイドロキシアパタイト(HA)コーティング 320 |
| 2.5 バイオアクティブセラミックスの臨床応用 342 |
| 2.5.1 バイオアクティブ結晶化ガラス(A-W) 342 |
| 2.5.2 ハイドロキシアパタイト(HA) 346 |
| 2.5.3 バイオセラミックス複合体 350 |
| 2.5.4 人口歯・人口歯根 354 |
| 2.5.5 ガン治療用セラミックス 362 |
| 第Ⅳ-3章 基礎データ 369 |
| 索 引 375 |
| 共通基礎データ ⅷ |
| 第Ⅰ編 環境・リサイクル分野 |
| 第Ⅰ-1章 総 論 3 |
|
| 3.
|
 図書
図書
|
Amy Yamada 著
| 出版情報: |
東京 : 講談社, 2000.1 239p ; 20cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 4.
|
 図書
図書
|
タンディラジオシャック編
| 出版情報: |
東京 : 工学図書, 1979.2 1冊 ; 27cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 5.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
長井寿編著
| 出版情報: |
東京 : 化学工業日報社, 1995.11 xii, 208p ; 21cm |
| シリーズ名: |
エコマテリアルシリーズ |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 1. リサイクル設計の必要性 3 |
| 1.1 持続型社会構築と環境調和型製品・素材開発(山本良一) 3 |
| 1.1.1 持続可能な発展は実現可能か 3 |
| 1.1.2 物質文明に内在する矛盾 4 |
| 1.1.3 エコマテリアル開発の必要性 5 |
| 1.1.4 ライフサイクル・アセスメント(Life Cycle Assessment) 6 |
| 1.1.5 エコラベルの威力 7 |
| 1.1.6 欧米諸国の先進的な取り組み 9 |
| 1.1.7 持続可能製品開発の課題 10 |
| 1.2 廃棄物をリサイクルする社会システムの構築(土肥義治) 13 |
| 1.2.1 新しい産業体系の構築 14 |
| 1.2.2 廃棄物のリサイクルシステムの構築 14 |
| 1.3 材料のリサイクラブル設計の基本概念とその意義(古林英一) 17 |
| 1.3.1 リサイクラブル設計の特質 17 |
| 1.3.2 リサイクル技術の普遍性 18 |
| 1.3.3 再生不能資源の再生は 19 |
| 1.3.4 閉回路技術としてのリサイクルの意義 20 |
| 1.3.5 材料のリサイクラブル設計の方法 21 |
| 1 3.6 金属・合金の問題 22 |
| 2. リサイクルの現状とリサイクル設計から見た問題点 27 |
| 2.1 鉄鋼材料 27 |
| 2.1.1 プロセスから見た分析(雀部 実) 27 |
| 2.1.1.1 はじめに 27 |
| 2.1.1.2 鉄鋼スクラップの問題点 27 |
| 2.1.1.3 研究の現状 28 |
| 2.1.1.4 まとめ 30 |
| 2.1.2 材質から見た分析(秋末 治) 31 |
| 2.1.2.1 はじめに 31 |
| 2.1.2.2 鉄鋼材料のリサイクル推進のための課題 34 |
| 2.1.2.3 リサイクルのための鉄鋼材料設計 35 |
| 2.1.2.4 おわりに 38 |
| 2.2 非鉄金属材科(黒柳 卓) 39 |
| 2.2.1 銅および銅合金(宮内理夫) 42 |
| 2.2.1.1 プロセスからみた分析 42 |
| 2.2.1.2 材質からみた分析 46 |
| 2.2.1.3 リサイクルから見た課題 47 |
| 2.2.1.4 有害金属 48 |
| 2.2.2 アルミニウムとその合金(大園智哉) 49 |
| 2.2.2.1 プロセスからみた分析 49 |
| 2.2.2.2 リサイクルの課題 54 |
| 2.2.2.3 材質から見た分析 54 |
| 2.2.2.4 不純物への一般的な対応方法 55 |
| 2.2.3 リサイクル設計への一考察(黒柳 卓) 57 |
| 2.3 高分子材料 59 |
| 2.3.1 塩化ビニル(鈴木正保) 59 |
| 2.3.1.1 塩化ビニルをとりまく社会情勢 59 |
| 2.3.1.2 PVCのリサイクル 60 |
| 2.3.1.3 今後の課題 63 |
| 2.3.2 PET,ナイロン,ポリアセタールおよびアクリル樹脂のリサイクル(草川紀久) 65 |
| 2.3.2.1 はじめに 65 |
| 2.3.2.2 PET 66 |
| 2.3.2.3 ナイロン 72 |
| 2.3.2.4 ポリアセタール(POM) 77 |
| 2.3.2.5 アクリル樹脂(PMMA) 82 |
| 2.3.2.6 おわりに 85 |
| 2.3.3 ポリオレフィン系プラスチック(富川昌美) 86 |
| 2.3.3.1 総論 86 |
| 2.3.3.2 マテリアルリサイクル 88 |
| 2.3.3.3 ケミカルリサイクル 88 |
| 2.3.3.4 サーマルリサイクル(エネルギー回収) 90 |
| 2.4 無機材料 91 |
| 2.4.1 コンクリート(小沼栄一) 91 |
| 2.4.1.1 はじめに 91 |
| 2.4.1.2 リサイクル設計の概念 91 |
| 2.4.1.3 マテリアルフロー上で生じる問題点 94 |
| 2.4.1.4 問題解決の視点 95 |
| 2.4.1.5 問題解決を阻害する科学技術上の未解決点 96 |
| 2.4.1.6 おわりに 97 |
| 2.4.2 セラミックス(若井史博) 97 |
| 2.4.2.1 はじめに 97 |
| 2.4.2.2 天然資源 99 |
| 2.4.2.3 他産業の廃棄物・副生物の再資源化 99 |
| 2.4.2.4 製造プロセスと産業廃棄物 100 |
| 2.4.2.5 リサイクルとリユース 101 |
| 2.4.2.6 地球環境保全におけるセラミックスの役割 101 |
| 2.5 静脈からみた現状と問題点 103 |
| 2.5.1 金属スクラップ回収業(長井 寿) 103 |
| 2.5.1.1 スクラップ回収業者のクレーム 103 |
| 2.5.1.2 スクラップ回収業者の「経済原則」 105 |
| 2.5.1.3 鉄,アルミニウムスクラップリサイクル 105 |
| 2.5.1.4 金属スクラップリサイクルをマテリアルフローの中に位置づけるために 107 |
| 2.5.2 廃棄物処理(村田徳治) 108 |
| はじめに 108 |
| 2.5.2.1 廃棄物処理の現状 109 |
| 2.5.2.2 不合理な現行の廃棄物処理 111 |
| 2.5.2.3 廃棄物の資源化と発生抑制 114 |
| 2.5.2.4 清掃事業から肝腎産業へ 116 |
| 3.リサイクル設計の本格的取組みのために 121 |
| 3.1 製品設計 121 |
| 3.1.1 電子情報機器(吉見幸一) 121 |
| 3.1.1.1 はじめに 121 |
| 3.1.1.2 環境調和を考慮した製品の現状 121 |
| 3.1.1.3 本格的リサイクル設計への展望 124 |
| 3.1.1.4 おわりに 126 |
| 3.1.2 電気機器(大橋敏二郎) 127 |
| 3.1.2.1 はじめに 127 |
| 3.1.2.2 背景と目的 127 |
| 3.1.2.3 分解性評価法の概念 128 |
| 3.1.2.4 分解性評価の手順 130 |
| 3.1.2.5 おわりに 131 |
| 3.1.3 OA機器(谷 達雄) 132 |
| 3.1.3.1 リサイクルの概念 132 |
| 3.1.3.2 OA機器のリサイクル対応設計 134 |
| 3.1.3.3 プラスチックのマテリアルリサイクル 136 |
| 3.1.3.4 実験結果 140 |
| 3.1.3.5 おわりに 142 |
| 3.1.4 自動車(羽鳥之彬) 143 |
| 3.1.4.1 自動車の一生とリサイクル 143 |
| 3.1.4.2 クルマ再資源化の問題点 144 |
| 3.1.4.3 再生資源利用促進を目指した事前評価 145 |
| 3.1.4.4 リサイクル推進に向けた取組み 145 |
| 3.1.4.5 今後の自動車リサイクルの課題 149 |
| 3.1.5 農業機械(大内久平) 151 |
| 3.1.5.1 はじめに 151 |
| 3.1.5.2 リサイクル及びリサイクル設計の現状 152 |
| 3.1.5.3 今後のリサイクル設計のあり方 156 |
| 3.1.5.4 環境保全型農業機械の例 156 |
| 3.1.5.5 おわりに 157 |
| 3.1.6 処理処分面からみたECP設計(和田安彦) 158 |
| 3.1.6.1 はじめに 158 |
| 3.1.6.2 処理処分面からみたECP設計の考え方 159 |
| 3.1.6.3 おわりに 170 |
| 3.2 材料設計 171 |
| 3.2.1 金属材料(友田 陽) 171 |
| 3.2.1.1 金属材料の特徴-人工的循環システムを必要とする材料- 171 |
| 3.2.1.2 金属リサイクルに向けての社会的問題と科学技術的問題 172 |
| 3.2.1.3 従来の材料設計とリサイクル指向材料設計 174 |
| 3.2.1.4 リサイクル指向設計の提案 177 |
| 3.2.1.5 おわりに 180 |
| 3.2.2 高分子 180 |
| 3.2.2.1 高分子材料(小林英一) 180 |
| 3.2.2.2 DFD(Design For Disassembly)(上野晃史) 186 |
| 3.2.3 セラミックス(若井史博) 190 |
| 3.2.4 半導体(吉見幸一) 193 |
| 3.2.4.1 はじめに 193 |
| 3.2.4.2 半導体製造プロセスにイけるリサイクル設計 193 |
| 3.2.4.3 半導体製品のリサイクル 196 |
| 3.2.4.4 おわりに 197 |
| おわりに 199 |
| 索引 203 |
| 1. リサイクル設計の必要性 3 |
| 1.1 持続型社会構築と環境調和型製品・素材開発(山本良一) 3 |
| 1.1.1 持続可能な発展は実現可能か 3 |
|
| 6.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
眞溪歩著
| 出版情報: |
東京 : 昭晃堂, 2004.3 ii, iv, iv, 225p ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 1.1複素数の取り扱い 1 |
| 1.1.1複素数の表記 1 |
| 1.1.2オイラーの公式 2 |
| 1.1.3複素数の四則演算 4 |
| 1.2ベクトルの取り扱い 9 |
| 1.2.1ベクトル空間 9 |
| 1.2.2ノルム 10 |
| 1.2.3内積 12 |
| 1.2.4固有値と固有関数 14 |
| 1.32つの関数・数列間の演算 16 |
| 1.3.1たたみ込み 17 |
| 1.3.2循環たたみ込み 19 |
| 1.3.3有限長の数列のたたみ込み 22 |
| 1.3.4相関関数 23 |
| 1.4特殊な関数 26 |
| 1.4.1ステップ関数 26 |
| 1.4.2デルタ関数 26 |
| 2.1最小2乗近似 29 |
| 2.1.1実験における最小2乗法 29 |
| 2.1.2最小2乗近似 30 |
| 2.1.3直交性 32 |
| 2.1.4直交関数展開 36 |
| 2.2フーリエ級数 38 |
| 2.2.1収束性 38 |
| 2.2.2直交関数系 39 |
| 2.2.3フーリエ級数の定義 41 |
| 2.2.4フーリエ級数の性質 46 |
| 2.2.5ギプス現象 48 |
| 演習問題 55 |
| 3.1フーリエ変換 57 |
| 3.1.1フーリエ変換の定義 57 |
| 3.1.2フーリエ変換の性質 61 |
| 3.2離散時間フーリエ変換 69 |
| 3.2.1連続時間信号の離散化 69 |
| 3.2.2離散時間フーリエ変換の定義 70 |
| 3.2.3離散時間フーリエ変換の性質 73 |
| 3.2.4サンプリング定理 75 |
| 3.2.5アンチエリアシング 81 |
| 3.3離散フーリエ変換 86 |
| 3.3.1離散フーリエ変換の定義 86 |
| 3.3.2離散フーリエ変換の性質 90 |
| 3.4高速フーリエ変換 97 |
| 3.4.1高速フーリエ変換の導出 97 |
| 3.4.2高速フーリエ変換の利用 103 |
| 3.5窓フーリエ変換 106 |
| 3.5.1離散窓フーリエ変換 106 |
| 3.5.2短時間フーリエ変換 112 |
| 演習問題 116 |
| 4.1z変換 118 |
| 4.1.1z変換の定義 118 |
| 4.1.2逆z変換 122 |
| 4.1.3z変換の性質 124 |
| 4.2離散時間線形時不変システム 129 |
| 4.2.1離散時間システムの表し方 129 |
| 4.2.2時不変性 130 |
| 4.2.3線形性 132 |
| 4.2.4インパルス応答 133 |
| 4.2.5因果性 134 |
| 4.2.6伝達関数 135 |
| 4.2.7ブロック線図 136 |
| 4.2.8差分方程式 138 |
| 4.2.9BIBO安定性 142 |
| 4.2.10周波数応答 143 |
| 4.2.11最小・最大位相システム 151 |
| 4.2.12線形位相システム 159 |
| 4.2.13.全域通過システム 165 |
| 4.2.14非因果的システム 166 |
| 演習問題 167 |
| 5.1フィルタの分類 169 |
| 5.1.1システムによる分類 169 |
| 5.1.2利用目的による分類 169 |
| 5.2FIRフィルタの設計 172 |
| 5.2.1最小2乗近似による設計 172 |
| 5.2.2窓関数による設計 176 |
| 5.2.3周波数変換 181 |
| 5.3IIRフィルタの設計 185 |
| 5.3.1インパルス不変変換 185 |
| 5.3.2双線形変換 187 |
| 5.3.3周波数変換 190 |
| 5.4ディジタルフィルタの実際 195 |
| 5.4.1フィルタの誤差 195 |
| 5.4.2過渡現象 196 |
| 5.4.3FIRフィルタとIIRフィルタ 196 |
| 5.4.4フィルタ設計ツールの利用 197 |
| 演習問題 198 |
| 6.1ラプラス変換 199 |
| 6.1.1ラプラス変換の定義 199 |
| 6.1.2ラプラス変換の性質 200 |
| 6.2連続時間線形時不変システム 201 |
| 6.2.1連続時間線形時不変システムの記述と性質 201 |
| 6.2.2エリアシング再考 205 |
| 6.2.3各種変換のまとめ 206 |
| 6.3アナログフィルタ 207 |
| 6.3.1バターワースフィルタ 207 |
| 6.3.2チェビシェフフィルタ 210 |
| 6.3.3周波数変換 213 |
| 演習問題略解 215 |
| 参考書 216 |
| 索引 217 |
| 1.1複素数の取り扱い 1 |
| 1.1.1複素数の表記 1 |
| 1.1.2オイラーの公式 2 |
|
| 7.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
相良紘著
| 出版情報: |
東京 : 日刊工業新聞社, 2008.6 viii, 210p ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| プロローグ 1 |
| 第1章 固体の混ざったものを分離する 5 |
| 1.1 固体の混ざり方を眺める 5 |
| 1.2 固体どうしの混ざったものを分離する 6 |
| 1.2.1 分離法を概観する 6 |
| 1.2.2 ふるい分け 7 |
| 1.2.3 風力分級 9 |
| 1.2.4 水力分級 11 |
| 1.2.5 起泡分離 13 |
| 1.2.6 磁気分離 15 |
| 1.2.7 静電分離 16 |
| 1.3 固体と液体の混ざったものを分離する 18 |
| 1.3.1 分離法を概観する 18 |
| 1.3.2 沈降分離 19 |
| 1.3.3 ろ過 23 |
| 1.3.4 精密ろ過 27 |
| 1.3.5 限外ろ過 30 |
| 1.4 固体と気体の混ざったものを分離する 35 |
| 1.4.1 分離法を概観する 35 |
| 1.4.2 エアフィルター 36 |
| 1.4.3 バグフィルター 38 |
| 1.4.4 サイクロン 39 |
| 1.4.5 スクラバー 42 |
| 1.4.6 電気集じん 44 |
| 第2章 液体に含まれる成分を分離する 47 |
| 2.1 液体の混ざり方を眺める 47 |
| 2.2 蒸留で分離する 48 |
| 2.2.1 分子間力と沸点 48 |
| 2.2.2 気液平衡と比揮発度 52 |
| 2.2.3 異種分子間力と沸点変化 55 |
| 2.2.4 単蒸留 56 |
| 2.2.5 フラッシュ蒸留 58 |
| 2.2.6 再蒸留とバッチ精留 60 |
| 2.2.7 連続精留 61 |
| 2.2.8 共沸蒸留 68 |
| 2.2.9 抽出蒸留 70 |
| 2.2.10 水蒸気蒸留 72 |
| 2.2.11 反応蒸留 73 |
| 2.2.12 その他(気体や固体の分離精製) 74 |
| 2.3 晶析で分離する 75 |
| 2.3.1 結合力と融点 76 |
| 2.3.2 固体の溶解度 78 |
| 2.3.3 液体の凝固点降下 79 |
| 2.3.4 固液平衡 80 |
| 2.3.5 共晶型混合物と固溶体型混合物 82 |
| 2.3.6 再結晶法 84 |
| 2.3.7 溶融結晶化法 85 |
| 2.3.8 帯溶融法 86 |
| 2.3.9 異性体の分離 87 |
| 2.3.10 連続晶析と結晶精製 89 |
| 2.4 液液抽出で分離する 93 |
| 2.4.1 分子間力と溶解性 93 |
| 2.4.2 溶解性とエントロピー 94 |
| 2.4.3 溶媒和と配位結合 96 |
| 2.4.4 液液平衡と分配係数 98 |
| 2.4.5 単抽出 100 |
| 2.4.6 連続多段抽出 103 |
| 2.4.7 芳香族の抽出 106 |
| 2.4.8 酢酸の分離 109 |
| 2.4.9 ウランの濃縮 109 |
| 2.5 膜で分離する 110 |
| 2.5.1 分離法を概観する 110 |
| 2.5.2 膜透過のメカニズム 111 |
| 2.5.3 半透膜と浸透圧 113 |
| 2.5.4 逆浸透と逆浸透膜 115 |
| 2.5.5 浸透気化と浸透気化膜 117 |
| 2.5.6 電解質水溶液とイオン交換体 119 |
| 2.5.7 イオン交換膜とイオン交換透析 120 |
| 2.5.8 液体膜とエマルションの安定化 123 |
| 2.5.9 逆浸透膜による海水の淡水化 126 |
| 2.5.10 浸透気化膜によるアルコールの脱水 127 |
| 2.5.11 イオン交換膜による海水の濃縮 128 |
| 2.5.12 液体膜による金属の回収 129 |
| 2.6 液相吸着で分離する 130 |
| 2.6.1 吸着相互作用 130 |
| 2.6.2 化学吸着と物理吸着 132 |
| 2.6.3 吸着剤の構造と吸着特性 133 |
| 2.6.4 吸着平衡と吸着等温線 134 |
| 2.6.5 固定層吸着と吸着速度 136 |
| 2.6.6 吸着帯と破過曲線 137 |
| 2.6.7 液体クロマトグラフィー 139 |
| 2.6.8 移動層吸着 141 |
| 2.6.9 擬似移動層吸着装置 142 |
| 2.6.10 イオン交換樹脂による純水の製造 143 |
| 2.7 包接化で分離する 145 |
| 2.7.1 尿素の包接化合物 145 |
| 2.7.2 直鎖状炭化水素の分離 146 |
| 2.7.3 チオ尿素の包接化合物 147 |
| 2.7.4 分枝状化合物の分離 147 |
| 2.7.5 無機錯化合物による芳香族化合物の分離 149 |
| 第3章 気体に含まれる成分を分離する 151 |
| 3.1 ガス吸収で分離する 151 |
| 3.1.1 気体の溶解度 151 |
| 3.1.2 物質移動と二重境膜モデル 153 |
| 3.1.3 吸収操作と吸収装置 155 |
| 3.1.4 吸収塔の必要高さ 158 |
| 3.1.5 吸収プロセス 161 |
| 3.2 膜(気体分離膜)で分離する 163 |
| 3.2.1 気体透過のメカニズム 164 |
| 3.2.2 2成分系混合気体の分離 165 |
| 3.2.3 気体分子の径 167 |
| 3.2.4 水素の分離 168 |
| 3.3 気相吸着で分離する 169 |
| 3.3.1 圧力スイング吸着 169 |
| 3.3.2 窒素と酸素の吸着等温線 170 |
| 3.3.3 窒素と酸素の吸着速度 171 |
| 3.3.4 空気分離プロセス 172 |
| 3.3.5 ガスクロマトグラフィー 173 |
| 3.4 昇華(逆昇華)で分離する 174 |
| 3.4.1 昇華現象と昇華圧 175 |
| 3.4.2 昇華法の長所と短所 176 |
| 3.4.3 無水フタル酸の製造 177 |
| 3.4.4 テレフタル酸の製造 178 |
| 3.4.5 高機能性膜の製造 178 |
| 第4章 固体に含まれる成分を分離する 181 |
| 4.1 固液抽出で分離する 181 |
| 4.1.1 固液抽出装置 181 |
| 4.1.2 植物油脂の採油 184 |
| 4.1.3 香料の抽出 185 |
| 4.2 超臨界流体抽出で分離する 185 |
| 4.2.1 臨界温度と臨界圧力 186 |
| 4.2.2 超臨界流体 187 |
| 4.2.3 超臨界流体抽出プロセス 188 |
| 第5章 ウランの同位体を分離する 191 |
| 5.1 わずかな差を見分ける 191 |
| 5.2 分離の原理と方法を概説する 193 |
| 5.2.1 ガス拡散法 193 |
| 5.2.2 熱拡散法 195 |
| 5.2.3 遠心分離法 197 |
| 5.2.4 ノズル分離法 198 |
| 5.2.5 化学交換法 200 |
| エピローグ 203 |
| 参考図書 205 |
| 索引 207 |
| プロローグ 1 |
| 第1章 固体の混ざったものを分離する 5 |
| 1.1 固体の混ざり方を眺める 5 |
|
| 8.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
高専土質実験教育研究会編
| 出版情報: |
東京 : 鹿島出版会, 2007.4 viii, 189p ; 26cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| まえがき |
| 第1章 土質試験の基本 |
| 1.1 土質試験の重要性とその心構え 1 |
| 1.1.1 土質試験の重要性 1 |
| 1.1.2 土の複雑さと土質試験の範囲 2 |
| 1.1.3 現場の土になじむこと 2 |
| 1.2 土質試験の種類 3 |
| 1.2.1 実験室内での土質試験 3 |
| 1.2.2 現場における土質試験 6 |
| 1.3 土質試験用機器 6 |
| 1.3.1 JIS規格の器具 6 |
| 1.3.2 その他の共通機器 6 |
| 第2章 物理試験 |
| 2.1 試料調整(試料の準備)(JISA1201) 9 |
| 2.1.1 試験の目的 9 |
| 2.1.2 試験用具 9 |
| 2.1.3 試料の準備 9 |
| 2.1.4 粒度調整 9 |
| 2.2 土の含水比試験(JISA1203) 11 |
| 2.2.1 試験の目的 11 |
| 2.2.2 試験用具・薬品 11 |
| 2.2.3 試料の準備 11 |
| 2.2.4 試験方法 11 |
| 2.2.5 試験結果の整理 12 |
| 2.2.6 結果の利用 12 |
| 2.2.7 関連知識 12 |
| 2.3 土粒子の密度試験(JISA1202) 13 |
| 2.3.1 試験の目的 13 |
| 2.3.2 試験用具 13 |
| 2.3.3 試料の準備 13 |
| 2.3.4 試験方法 13 |
| 2.3.5 試験結果の整理 14 |
| 2.3.6 結果の利用 15 |
| 2.3.7 関連知識 15 |
| 2.4 土の粒度試験(JISA1204) 16 |
| 2.4.1 試験の目的 16 |
| 2.4.2 試験用具・薬品 16 |
| 2.4.3 試料の準備と試験方法 17 |
| 2.4.4 試験結果の整理 20 |
| 2.4.5 結果の利用 21 |
| 2.5 土の液性限界試験(JISA1205) 25 |
| 2.5.1 試験の目的 25 |
| 2.5.2 試験用具 25 |
| 2.5.3 試料の準備 25 |
| 2.5.4 試験方法 25 |
| 2.5.5 試験結果の整理 26 |
| 2.5.6 結果の利用 26 |
| 2.5.7 関連知識 26 |
| 2.6 土の塑性限界試験(JISA1205) 28 |
| 2.6.1 試験の目的 28 |
| 2.6.2 試験用具 28 |
| 2.6.3 試料の準備 28 |
| 2.6.4 試`験方法 28 |
| 2.6.5 試験結果の整理 28 |
| 2.6.6 結果の利用 28 |
| 2.7 土の収縮定数試験(JISA1209) 31 |
| 2.7.1 試験の目的 31 |
| 2.7.2 試験用具 31 |
| 2.7.3 試料の準備 31 |
| 2.7.4 試験方法 31 |
| 2.7.5 試験結果の整理 32 |
| 2.7.6 結果の利用 33 |
| 2.7.7 関連知識 34 |
| 2.8 砂の最小密度ぴ最大密度試験(JISA1224) 36 |
| 2.8.1 試験の目的 36 |
| 2.8.2 試験用具 36 |
| 2.8.3 試料の準備 36 |
| 2.8.4 試験方法 36 |
| 2.8.5 試験結果の整理 37 |
| 2.8.6 結果の利用 37 |
| 2.9 土の湿潤密度試験(JISA1225) 39 |
| 2.9.1 試験の目的 39 |
| 2.9.2 試験用具 39 |
| 2.9.3 供試体の作製 39 |
| 2.9.4 試験方法 40 |
| 2.9.5 試験結果の整理 40 |
| 2.9.6 結果の利用 41 |
| 2.9.7 関連知識 42 |
| 2.10 土の保水性試験(JGS0051) 43 |
| 2.10.1 試験の目的 43 |
| 2.10.2 試験用具 43 |
| 2.10.3 試験方法 43 |
| 2.10.4 試験結果の整理 43 |
| 2.10.5 結果の利用 43 |
| 2.11 地盤材料の工学的分類方法(JGS0051) 44 |
| 2.11.1 分類の目的 44 |
| 2.11.2 分類のための試験 44 |
| 2.11.3 地盤材料の分類 44 |
| 2.11.4 試験結果の整理 47 |
| 2.11.5 結果の利用 47 |
| 第3章 化学試験 |
| 3.1 土懸濁液のpH試験(JGS0211) 51 |
| 3.1.1 試験の目的 51 |
| 3.1.2 試験用具・試薬 51 |
| 3.1.3 試科 51 |
| 3.1.4 試験方法 52 |
| 3.1.5 試験結果の整理 53 |
| 3.1.6 結果の利用 53 |
| 3.1.7 関連知識 53 |
| 3.2 土懸濁液の電気伝導率試験(JGS0212) 54 |
| 3.2.1 試験の目的 54 |
| 3.2.2 試験用具・試薬 54 |
| 3.2.3 試科 54 |
| 3.2.4 試験方法 54 |
| 3.2.5 試験結果の整理 55 |
| 3.2.6 結果の利用 56 |
| 3.2.7 関連知識 56 |
| 3.3 土の強熱減量試験(JISA1226) 57 |
| 3.3.1 試験の目的 57 |
| 3.3.2 試験用具・試薬 57 |
| 3.3.3 試科 57 |
| 3.3.4 試験方法 57 |
| 3.3.5 試験結果の整理 58 |
| 3.3.6 結果の利用 58 |
| 3.3.7 関連知識 59 |
| 第4章 力学的試験 |
| 4.1 突固めによる土の締固め試験(JISA1210) 63 |
| 4.1.1 試験の目的 63 |
| 4.1.2 試験用具 63 |
| 4.1.3 試験方法の種類とその選択 64 |
| 4.1.4 試料の準備 64 |
| 4.1.5 試験方法 65 |
| 4.1.6 試験結果の整理 66 |
| 4.2 土の透水試験(JISA1210) 69 |
| 4.2.1 試験の目的 69 |
| 4.2.2 使用機器 69 |
| 4.2.3 試料の準備 69 |
| 4.2.4 試験方法 70 |
| 4.2.5 試験結果の整理 72 |
| 4.2.6 参考資料 73 |
| 4.3 土の多段階載荷による圧密試験(JISA1217) 76 |
| 4.3.1 試験の目的 76 |
| 4.3.2 誠験用具 76 |
| 4.3.3 供試体の準備および試験方法 76 |
| 4.3.4 試験結果の整理 78 |
| 4.3.5 参考資料 83 |
| 4.4 一面せん断試験(JGSO560) 87 |
| 4.4.1 試験の目的 87 |
| 4.4.2 試験用具 87 |
| 4.4.3 供試体作成 88 |
| 4.4.4 試験方法 90 |
| 4.4.5 試験結果の整理 90 |
| 4.4.6 結果の利用・関連知識 91 |
| 4.5 一軸圧縮試験(JISA1216) 97 |
| 4.5.1 試験の目的 97 |
| 4.5.2 試験用具 97 |
| 4.5.3 供試体作成 97 |
| 4.5.4 試験方法 98 |
| 4.5.5 試験結果の整理 99 |
| 4.5.6 結果の利用・関連知識 100 |
| 4.6 三軸圧縮試験(JAFT520~524) 104 |
| 4.6.1 試験の目的 104 |
| 4.6.2 使用機器 104 |
| 4.6.3 供試体の作製 104 |
| 4.6.4 試験方法 105 |
| 4.6.5 試験結果の整理 108 |
| 4.6.6 結果の利用 109 |
| 4.6.7 関連知識 110 |
| 4.7 CBR試験(JISA1211) 119 |
| 4.7.1 試験の目的 119 |
| 4.7.2 使用機器 119 |
| 4.7.3 供試体の作製方法 120 |
| 4.7.4 試験方法 121 |
| 4.7.5 試験結果の整理 122 |
| 4.7.6 参考資料 123 |
| 第5章 現場における試験 |
| 5.1 砂置換法による土の密度試験(JISA1214) 131 |
| 5.1.1 試験の目的 131 |
| 5.1.2 試験用具 131 |
| 5.1.3 試験方法 132 |
| 5.1.4 試験結果の整理 135 |
| 5.1.5 結果の利用・関連知識 135 |
| 5.2 現場CBR試験(JISA1222) 139 |
| 5.2.1 試験の目的 139 |
| 5.2.2 試験用具 139 |
| 5.2.3 試験方法 140 |
| 5.2.4 試験結果の整理 140 |
| 5.3 道路の平板載荷試験(JISA1215) 142 |
| 5.3.1 試験の目的 142 |
| 5.3.2 試験用具 142 |
| 5.3.3 試験方法 142 |
| 5.3.4 試験結果の整理 143 |
| 5.3.5 結果の利用 143 |
| 5.3.6 関連知識 |
| 5.4 ポータブルコーン貫入試験(JGSA1431) 147 |
| 5.4.1 試験の目的 147 |
| 5.4.2 試験用具 147 |
| 5.4.3 試験方法 147 |
| 5.4.4 試験結果の整理 148 |
| 5.4.5 結果の利用 148 |
| 5.4.6 関連知識 149 |
| 5.5 原位置ベーンせん断試験(JGSA1411) 154 |
| 5.5.1 試験の目的 154 |
| 5.5.2 試験用具 154 |
| 5.5.3 試験方法 155 |
| 5.5.4 試験結果の整理 155 |
| 5.5.5 関連知識 156 |
| 5.6 スウェーデン式サウンディング試験(JISA1221) 158 |
| 5.6.1 試験の目的 158 |
| 5.6.2 試験用具 158 |
| 5.6.3 試験方法 158 |
| 5.6.4 試験結果の整理 159 |
| 5.6.5 結果の利用 159 |
| 第6章 模型実験、その他の試験 |
| 6.1 砂の土圧模型実験 163 |
| 6.1.1 試験の目的 163 |
| 6.1.2 試験用具 163 |
| 6.1.3 試験の準備、土層の作製 163 |
| 6.1.4 試験方法 164 |
| 6.1.5 試験結果の整理 164 |
| 6.1.6 結果の利用 165 |
| 6.1.7 関連知識 165 |
| 6.2 流線網可視化試験 168 |
| 6.2.1 試験の目的 168 |
| 6.2.2 試験用具・試薬 168 |
| 6.2.3 試科 168 |
| 6.2.4 試験方法 168 |
| 6.2.5 試験結果の整理 169 |
| 6.2.6 結果の利用 170 |
| 6.2.7 関連知識 170 |
| 第7章 測定値の整理方法 |
| 7.1 測定値の表示方法 173 |
| 7.2 統計量の表示方法 173 |
| 7.3 測定値の棄却と検定方法 174 |
| 7.3.1 異常値の棄却 174 |
| 7.3.2 平均値の差の検定 178 |
| 7.4 試験結果の表示方法 179 |
| 7.4.1 回帰分析 179 |
| 7.4.2 相関係数 181 |
| 索引 183 |
| まえがき |
| 第1章 土質試験の基本 |
| 1.1 土質試験の重要性とその心構え 1 |
|
| 9.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
柴田里程著
目次情報:
続きを見る
| 第1章 データサイエンス |
| 1.1 データサイエンスがめざすもの 1 |
| 1.2 データの上流から下流まで 2 |
| 1.2.1 データサンプリング 2 |
| 1.2.2 データとその記述の一体化 3 |
| 1.2.3 DandDルール 6 |
| 1.2.4 データのブラウジング 7 |
| 1.2.5 データに含まれる情報量 7 |
| 1.2.6 データモデリング 8 |
| 1.2.7 モデルヴァリデーション 10 |
| 1.2.8 ソフトウェア 11 |
| 1.3 データエンジニアリング 12 |
| 1.3.1 データの同化 12 |
| 1.3.2 データマイニング 13 |
| 1.3.3 データ学習アルゴリズム 13 |
| 1.4 データリテラシー 14 |
| 1.4.1 データの型 14 |
| 1.4.2 データの属性と構造 14 |
| 1.4.3 日時の表現 15 |
| 1.4.4 背景情報 18 |
| 1.4.5 ランダム性と非ランダム性 19 |
| 1.4.6 変量 22 |
| 1.4.7 平均,分散,標準偏差 22 |
| 1.4.8 相関と関係 24 |
| 1.4.9 偏差値 25 |
| 第2章 データ |
| 2.1 データベクトル 27 |
| 2.1.1 値 29 |
| 2.1.2 属性 30 |
| 2.2 データベクトルの構造化 44 |
| 2.2.1 配列形式 45 |
| 2.2.2 関係形式 46 |
| 2.2.3 その他の形式 53 |
| 2.3 特別な意味をもつ構造 54 |
| 2.3.1 グラフ,関連度表 55 |
| 2.3.2 並べ替え 56 |
| 2.3.3 時系列 56 |
| 2.3.4 点過程データ 57 |
| 2.3.5 意図しない観測打切り 57 |
| 2.3.6 制約 58 |
| 2.3.7 区間 59 |
| 2.3.8 基数系 59 |
| 2.3.9 座標 61 |
| 2.4 データ取得計画 64 |
| 2.4.1 ランダム化 64 |
| 2.4.2 システマティックな抽出,意図的な抽出 69 |
| 2.4.3 実験計画 72 |
| 2.5 背景情報 76 |
| 2.5.1 改訂の記録 77 |
| 2.5.2 参考文献 77 |
| 第3章 データの浄化と組織化 |
| 3.1 事例研究 79 |
| 3.1.1 実験データ 79 |
| 3.1.2 地震データ 82 |
| 3.1.3 気象観測データ 86 |
| 3.1.4 マーケティングデータ 92 |
| 3.1.5 給油記録データ 95 |
| 3.1.6 高血圧症研究データ 98 |
| 3.1.7 商品先物取引データ 100 |
| 3.2 データの浄化 105 |
| 3.2.1 人為的なミスの訂正 105 |
| 3.2.2 表現の統一 105 |
| 3.2.3 1次データへの絞り込み 106 |
| 3.2.4 冗長な変量の削除 106 |
| 3.2.5 単位の統一 106 |
| 3.2.6 コーディング 106 |
| 3.3 データの組織化 107 |
| 3.3.1 新たな変量の導入 107 |
| 3.3.2 関係形式と配列形式 107 |
| 3.3.3 時間の扱い 107 |
| 3.4 背景情報の記述 109 |
| 3.4.1 データベクトルの属性 109 |
| 3.4.2 関係形式や配列形式の背景情報 109 |
| 3.4.3 文章での記述 110 |
| 第4章 データのブラウジング |
| 4.1 データを数値として眺める 112 |
| 4.2 データをグラフィカルに眺める 113 |
| 4.2.1 散布図 114 |
| 4.2.2 時系列図 119 |
| 4.2.3 箱型図 128 |
| 4.2.4 累積分布図 134 |
| 4.2.5 Q-Qプロマット 137 |
| 4.3 関係を探る 143 |
| 4.3.1 補間と平滑化 144 |
| 4.3.2 独立性と無相関 146 |
| 4.4 データを変換する 149 |
| 4.5 データを分解する 149 |
| 第5章 データの流通と蓄積 |
| 5.1 データの源泉 151 |
| 5.2 データの公開 153 |
| 5.2.1 データ公開の形式 156 |
| 5.2.2 データの著作権 156 |
| 5.2.3 データの価値 157 |
| 5.3 インターデータベース 158 |
| 5.3.1 フローティングDandDインスタンス 159 |
| 5.3.2 データの蓄積 160 |
| 5.3.3 モデルの蓄積 161 |
| 5.4 データの流通と蓄積のもたらす未来 161 |
| 参考文献 163 |
| 索引 165 |
| 第1章 データサイエンス |
| 1.1 データサイエンスがめざすもの 1 |
| 1.2 データの上流から下流まで 2 |
|
| 10.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
喜多恵子著
目次情報:
続きを見る
| 1 総論 |
| 1.1 酵素資源 2 |
| 1.2 酵素の生産 6 |
| 1.2.1 菌株の改良 6 |
| 1.2.2 培地および培養条件 7 |
| 1.2.3 培養法 9 |
| 1.3 抽出と精製 9 |
| 1.3.1 抽出法 10 |
| 1.3.2 濃縮および脱塩 12 |
| 1.3.3 精製法 13 |
| 1.4 酵素のリサイクルと回収 15 |
| 1.4.1 固定化 16 |
| 1.4.2 二相系 19 |
| 1.4.3 濾過 19 |
| 1.5 酵素タンパク質の分子工学 20 |
| 1.5.1 理論的分子設計 21 |
| 1.5.2 定方向進化 21 |
| 1.5.3 大量迅速処理スクリーニング技術 22 |
| 引用・参考文献 22 |
| 2 酵素各論 |
| 2.1 酸化還元酵素 24 |
| 2.1.1 CH-OHを供与体とする酸化還元酵素(EC1.1群) 24 |
| 2.1.2 アルデヒドを供与体とする酸化還元酵素(EC1.2群) 26 |
| 2.1.3 CH-NH2を供与体とする酸化還元酵素(EC1.4群) 27 |
| 2.1.4 窒素化合物を供与体とする酸化還元酵素(EC1.7群) 29 |
| 2.1.5 ペルオキシダーゼ(peroxidase)(EC1.11.1群) 29 |
| 2.1.6 オキシゲナーゼ(oxygenase) 31 |
| 2.2 転移酵素 31 |
| 2.2.1 メチルトランスフェラーゼ(methyltransferase,EC2.1.1群) 31 |
| 2.2.2 (アミノアシルトランスフェラーゼ(aminoacyltransferase,EC2.3.2群) 32 |
| 2.2.3 グリコシルトランスフェラーゼ(glycosyltransferase,EC2.4群) 33 |
| 2.2.4 トランスアミナーゼ(transaminase,EC2.6.1群) 35 |
| 2.2.5 ホスホトランスフェラーゼ(phosphotransferase,EC2.7.1群) 37 |
| 2.2.6 ヌクレオチジルトランスフェラーゼ(nucleotidyltransferase,EC2.7.7群) 38 |
| 2.3 加水分解酵素 39 |
| 2.3.1 糖質分解酵素(glycosylase)(EC3.2群) 39 |
| 2.3.2 プロテアーゼ(protease)(EC3.4群) 47 |
| 2.3.3 脂質分解酵素(EC3.1群) 51 |
| 2.3.4 ヌクレアーゼ(nuclease)(EC3.1群) 53 |
| 2.3.5 ペプチド結合以外のC-N結合を加水分解する酵素(EC3.5群) 56 |
| 2.3.6 その他の加水分解酵素 58 |
| 2.4 リアーゼ 59 |
| 2.4.1 C-Cリアーゼ(EC4.1群) 60 |
| 2.4.2 C-Oリアーゼ(EC4.2群) 61 |
| 2.4.3 C-Nリアーゼ(EC4.3群) 62 |
| 2.4.4 C-Sリアーゼ(EC4.4群) 63 |
| 2.5 異性化酵素 63 |
| 2.6 リガーゼ 65 |
| 2.7 補酵素 68 |
| 引用・参考文献 73 |
| 3 酵素の応用 |
| 3.1 食品加工での利用 74 |
| 3.1.1 デンプン加工 74 |
| 3.1.2 デンプン以外の糖の加工 82 |
| 3.1.3 タンパク質加工 84 |
| 3.1.4 果実,野菜,穀類などの加工 88 |
| 3.1.5 アルコール飲料製造への利用 92 |
| 3.1.6 製パン・製菓への利用 96 |
| 3.1.7 乳製品の加工 98 |
| 3.1.8 卵の加工 98 |
| 3.1.9 茶の加工 99 |
| 3.1.10 油脂の加工 99 |
| 3.2 食品関連工業での利用 101 |
| 3.2.1 アミノ酸の製造 101 |
| 3.2.2 呈味性ヌクレオチドの製造 107 |
| 3.2.3 その他 110 |
| 3.3 化学工業での利用 110 |
| 3.3.1 洗剤用酵素 111 |
| 3.3.2 繊維加工用酵素 116 |
| 3.3.3 紙・パルプ関連酵素 119 |
| 3.3.4 飼料用酵素 120 |
| 3.3.5 有機合成への応用 122 |
| 3.4 分析・計測への利用 132 |
| 3.4.1 目的物質の定量分析 132 |
| 3.4.2 酵素活性の定量 139 |
| 3.4.3 センサー 146 |
| 3.4.4 酵素免疫検定法 149 |
| 3.5 医薬・化粧品としての利用 150 |
| 3.5.1 治療用酵素 150 |
| 3.5.2 化粧品への応用 158 |
| 3.6 研究試薬 159 |
| 3.6.1 遺伝子解析 160 |
| 3.6.2 タンパク質の解析 165 |
| 3.6.3 その他 166 |
| 3.7 環境保全への利用 166 |
| 3.7.1 有害物質の分解除去 166 |
| 3.7.2 未利用バイオマスの活用 167 |
| 引用・参考文献 173 |
| 付録 EC番号別酵素 174 |
| 索引 179 |
| 1 総論 |
| 1.1 酵素資源 2 |
| 1.2 酵素の生産 6 |
|
| 11.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
R.M.シャファート著 ; 井上英一監訳
| 出版情報: |
東京 : 共立出版, 1973 361p ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 第I部 電子写真プロセスと技術 |
| I 序論 3 |
| 1.1 歴史的概観 4 |
| 1.2 電子写真における潜像 7 |
| 1.2.1 静電像(ゼログラフィー) 7 |
| 1.2.2 持続性内部分極像(光エレクトレット) 8 |
| 1.2.3 持続導電性像 8 |
| 1.3 プロセスの用語 9 |
| II ゼログラフィー 11 |
| 2.1 ゼログラフィーの原理 11 |
| 2.1.1 感光性表面 11 |
| 2.1.2 潜像の形成 12 |
| 2.1.3 潜像の現象 13 |
| 2.1.4 像の転写と定着 13 |
| 2.2 プロセスに関する技術 14 |
| 2.3 帯電または感光化 14 |
| 2.4 露光 15 |
| 2.5 現像 16 |
| 2.5.1 現像電極 16 |
| 2.5.2 カスケード現像法 17 |
| 2.5.3 ファーブラシ現像法 18 |
| 2.5.4 磁気ブラシ現像法 19 |
| 2.5.5 加圧現像法 19 |
| 2.5.6 パウダークラウド現像法 20 |
| 2.5.7 液体スプレー現像法 21 |
| 2.5.8 液体現像法 21 |
| 2.5.9 加熱現像法 22 |
| 2.5.10 オイルフィルム現像法 24 |
| 2.6 反転現像法 25 |
| 2.6.1 線画像コピーの反転法 25 |
| 2.6.2 現像電極を用いる反転法 25 |
| 2.7 現像速度 26 |
| 2.8 像転写 26 |
| 2.9 プリントの定着 27 |
| 2.10 感光板のクリーニング 28 |
| 2.11 プリントの複製 29 |
| 2.12 ゼログラフィー材料 29 |
| 2.13 光導電層 30 |
| 2.13.1 光感度 30 |
| 2.13.2 スペクトル特性 32 |
| 2.13.3 受容電位 32 |
| 2.13.4 電荷保持性 33 |
| 2.13.5 残留電位 33 |
| 2.13.6 疲労 33 |
| 2.14 ゼログラフフィーの現像剤 34 |
| 2.15 ゼログラフィーのセンシトメトリー 36 |
| 2.15.1 パウダークラウド現像法による階調の再現 36 |
| 2.15.2 磁気ブラシ現像法による階調の再現 38 |
| 2.15.3 ハーフトーンの再現 39 |
| 2.15.4 線画像の再現性 42 |
| 2.15.5 解像力 44 |
| III 持続性内部分極 45 |
| 3.1 持続性内部分極の説明 45 |
| 3.2 内部分極による像形成 47 |
| 3.3 持続性内部分極の材料 51 |
| IV 持続導電性 55 |
| 4.1 持続導電性の説明 55 |
| 4.2 持続導電性による像形成 55 |
| 4.3 持続導電性に用いられる材料 58 |
| 4.4 永久導電性像 61 |
| V その他の電子写真プロセス 62 |
| 5.1 同時に露光と現像を行なうプロセス 62 |
| 5.1.1 Berchtoldのプロセス 62 |
| 5.1.2 Jacobs-Frerichsのプロセス 63 |
| 5.1.3 エレクトロカタリティックフォトグラフィー 63 |
| 5.1.4 スモークプリンター 64 |
| 5.1.5 ゼネラルダイナミックスのプロセス 65 |
| 5.2 光導電性粉末を利用したプロセス 66 |
| 5.3 エレクトロサーモグラフィー 67 |
| 5.4 光導電性サーモグラフィー 68 |
| VI 特殊な問題 69 |
| 6.1 ゼログラフィーにおける補助技術 69 |
| 6.1.1 逆極性帯電 69 |
| 6.1.2 補助照射 70 |
| 6.2 ゼログラフィーの潜像転写(TESI法) 70 |
| 6.3 あらかじめ形成された静電像を利用するTESI法 71 |
| 6.3.1 TESI法No.1 71 |
| 6.3.2 TESI法No.2 72 |
| 6.3.3 TESI法No.3 73 |
| 6.3.4 TESI法No.4 74 |
| 6.4 像形成を含むTESI法 75 |
| 6.4.1 TESI法No.5 76 |
| 6.4.2 TESI法No.6 76 |
| 6.4.3 TESI法No.7 77 |
| 6.5 表面電荷像の直接転写 78 |
| VII カラー電子写真プロセス 80 |
| 7.1 画像転写を用いるカラープロセス 81 |
| 7.2 電子写真紙を用いるカラープロセス 83 |
| 7.3 カラー電子写真についての一般的注意 84 |
| VIII エレクトロラジオグラフィープロセス 86 |
| 8.1 ゼロラジオグラフィー 86 |
| 8.1.1 ゼロラジオグラフィー用材料 86 |
| 8.1.1.1 光導電板 86 |
| 8.1.1.2 現像剤 88 |
| 8.1.2 感光板の帯電 89 |
| 8.1.3 X線曝射の方法 89 |
| 8.1.4 X線像の現像 90 |
| 8.1.5 ゼロラジオグラフィー用の光導電体塗布 91 |
| 8.2 イオノグラフィー 92 |
| IX 電子プリンティングプロセス 95 |
| 9.1 静電エレクトログラフィー 95 |
| 9.1.1 放電による静電記録 96 |
| 9.1.2 電子ビームを用いた静電記録 97 |
| 9.1.3 ゼロプリンティング 99 |
| 9.1.4 静電気現象を用いたステンシル印刷 101 |
| 9.2 電解エレクトログラフィー 102 |
| 9.2.1 電解記録の化学 102 |
| 9.2.2 電解記録の物理 104 |
| 9.3 放電プリンティング 106 |
| 9.4 磁気プリンティング 107 |
| X 電子写真の応用 110 |
| 10.1 アメリカにおける製品の開発 110 |
| 10.2 等倍率事務用複写機 111 |
| 10.2.1 ゼロックス914コピア 111 |
| 10.2.2 ブルーニングコピートロン2000 114 |
| 10.2.3 アペコエレクトロスタット 115 |
| 10.2.4 SCMモデル33エレクトロスタティックコピア 115 |
| 10.2.5 他の等倍率複写機 116 |
| 10.3 マイクロフィルムのハードコピー化 116 |
| 10.3.1 ゼロックスコピーフロー機 117 |
| 10.3.2 ブルーニングコピートロン1000 120 |
| 10.3.3 マイクロフィルムリーダープリンター 120 |
| 10.3.4 その他の引伸しおよびプリント装置 121 |
| 10.4 印刷およびデュプリケーティング 121 |
| 10.4.1 コピーデュプリケーティング 121 |
| 10.4.2 平版印刷用のオフセット版 123 |
| 10.4.3 写真食刻 124 |
| 10.4.4 直接的電子写真印刷 124 |
| 10.5 ゼロラジオグラフィー装置の製品 125 |
| 10.5.1 基本装置 125 |
| 10.5.2 付属装置 126 |
| 10.5.3 材料 128 |
| 10.6 特殊な応用 128 |
| 10.6.1 マイクロゼログラフィー 128 |
| 10.6.2 ゼログラフィー写真焼付機 130 |
| 10.6.3 計算機出力のプリント 131 |
| 10.6.4 ゼログラフィーによるファクシミリ 133 |
| 10.6.5 高速ディスプレー 134 |
| 10.6.6 オッシログラフの記録 136 |
| 10.6.7 他の応用 136 |
| 10.7 他の国々における製品の開発 137 |
| 10.7.1 日本 137 |
| 10.7.2 ヨーロッパおよびイギリス 141 |
| 10.7.3 オーストラリア 142 |
| 10.7.4 ソビエト連邦 142 |
| 第I部 引用文献 145 |
| 第II部 電子写真プロセスの理論 |
| I 光導電効果を用いる静電像の形成 153 |
| 1.1 感光材料の基本的な特性 153 |
| 1.1.1 実験方法 154 |
| 1.1.1.1 表面電荷量とその減衰の測定 154 |
| 1.1.1.2 比誘電率と膜厚の測定 157 |
| 1.1.2 光導電性絶縁膜のコロナ帯電 159 |
| 1.1.2.1 コロトロンによる帯電 162 |
| 1.1.2.2 スコロトロンによる帯電 167 |
| 1.1.3 光導電性絶縁膜による電荷の減衰 170 |
| 1.1.3.1 電荷減衰データの解析 171 |
| 1.1.4 光感度とその測定 173 |
| 1.1.4.1 暗減衰に対する補正 177 |
| 1.1.4.2 ゼログラフィーにおける相反則 178 |
| 1.1.5 疲労とその測定 179 |
| 1.2 光導電性絶縁材料 179 |
| 1.2.1 無定形セレン 181 |
| 1.2.1.1 構造 181 |
| 1.2.1.2 電気的性質 182 |
| 1.2.1.2.1 電気抵抗 182 |
| 1.2.1.2.2 チャージキャリアの移動度 182 |
| 1.2.1.2.3 比誘電率 183 |
| 1.2.1.3 光学的性質 183 |
| 1.2.1.3.1 吸収および反射 183 |
| 1.2.1.3.2 屈折率 185 |
| 1.2.1.3.3 活性化エネルギー 185 |
| 1.2.1.4 化学的性質 185 |
| 1.2.1.5 その他の性質 186 |
| 1.2.1.6 光導電特性 186 |
| 1.2.1.7 ゼログラフィー特性 188 |
| 1.2.1.7.1 暗減衰特性 189 |
| 1.2.1.7.2 光減衰特性 190 |
| 1.2.1.7.3 分光感度 192 |
| 1.2.1.7.4 相反則 195 |
| 1.2.1.7.5 量子効率 196 |
| 1.2.1.7.6 製造条件の影響 198 |
| 1.2.1.7.7 支持板表面の影響 200 |
| 1.2.1.7.8 不純物および添加物の影響 202 |
| 1.2.1.7.9 多層セレン感光板 205 |
| 1.2.1.8 ゼロラジオグラフィー特性 206 |
| 1.2.2 顔料-樹脂系の光導電体 208 |
| 1.2.2.1 顔料-樹脂系光導電体の作製 208 |
| 1.2.2.2 顔料-樹脂系光導電体の特性 209 |
| 1.2.2.3 ZnO-樹脂系フィルム 210 |
| 1.2.2.3.1 ZnOの特性 210 |
| 1.2.2.3.2 ZnO-樹脂系感光層の帯電 212 |
| 1.2.2.3.3 帯電ZnO-樹脂系感光層の暗および光減衰特性 216 |
| 1.2.2.3.4 分光感度 224 |
| 1.2.2.3.5 相反則 228 |
| 1.2.2.4 ZnO以外の顔料-樹脂系光導電性フィルム 228 |
| 1.2.2.4.1 亜鉛-カドミウムの硫化物 228 |
| 1.2.2.4.2 硫化第2水銀 230 |
| 1.2.2.4.3 セレン顔料 231 |
| 1.2.2.4.4 酸化チタン 231 |
| 1.2.3 有機物光導電体 232 |
| II 光導電性絶縁体の電荷輸送現象 235 |
| 2.1 暗減衰と電荷受容性 235 |
| 2.2 光導電性絶縁体における再結合,トラップ,および障壁の役割 238 |
| 2.3 ゼログラフィーにおける光導電性放電 241 |
| 2.4 光導電性放電理論 242 |
| 2.4.1 無定形セレン層に対するモデル 245 |
| 2.4.2 ZnO-樹脂系感光層に対するモデル 249 |
| 2.4.3 有機物の光導電感光層 255 |
| III 静電像の性質 256 |
| 3.1 静電像に関する電場 257 |
| 3.2 静電像の数学的取り扱い 258 |
| 3.2.1 自由空間における像の電場構造 258 |
| 3.2.2 現像電極を有するときの像の電場構造 261 |
| 3.2.3 像面の上に誘電体層を有するときの静電像の電場構造 262 |
| 3.2.4 例I,II,IIIの比較 262 |
| 3.3 電場の解像性と静電像の振幅 266 |
| 3.3.1 例Iに対する電場の解像性 267 |
| 3.3.2 例IIに対する電場の解像性 269 |
| 3.4 像電場に対する現像電極の効果 273 |
| 3.5 静電像電場のまとめ 279 |
| 3.6 付録A:誘電体表面上の正弦波的電荷分布に対する電場の式の導出 280 |
| 3.7 付録B:電気力線を描くための式の導出 284 |
| IV 静電潜像の誘電体表面への転写 286 |
| 4.1 静電気的考察 286 |
| 4.2 Paschen曲線と放電 288 |
| 4.3 修正Paschen曲線 290 |
| 4.4 広い空隙における放電 292 |
| 4.5 転移電荷の計算 293 |
| 4.5.1 一定の空隙における電荷転移 295 |
| 4.5.2 誘電体面の剥離時の電荷転移 295 |
| 4.5.2.1 剥離中におこる階段状転移 298 |
| 4.5.2.2 フィルムの剥離の間に転移する電荷の観測 300 |
| 4.5.3 電場放出領域における電荷転移 300 |
| 4.5.3.1 電場放出による転移電荷の観測方法 301 |
| 4.5.4 空隙がない場合の電荷転移 304 |
| 4.6 実験方法 306 |
| 4.6.1 装置 307 |
| 4.6.2 実験結果 308 |
| 4.6.2.1 剥離法の実験 310 |
| 4.6.2.2 接触法の実験 314 |
| 4.6.2.3 理論と実験についての一般的事項 316 |
| 4.6.2.4 圧着転写法の実験 316 |
| 4.6.2.4.1 電荷転移に対する圧力の効果 320 |
| 4.6.3 マイラー中の内部分極 320 |
| 4.7 実用上の考察 321 |
| 4.8 放電による電荷転移の機構 323 |
| 4.8.1 一定電場下での空隙幅による電流変化 324 |
| 4.8.2 一定電圧下での空隙幅による電流変化 325 |
| 4.8.3 静電像転写に要する電流の大きさ 327 |
| 4.9 直接電荷転移の機構 328 |
| V ゼログラフィー画像の現像理論 329 |
| 5.1 小粒子の帯電 329 |
| 5.1.1 乾式粉末現像の摩擦帯電現象 329 |
| 5.1.2 液体現像剤の電気泳動特性 333 |
| 5.1.2.1 懸濁液体中の粒子帯電の性質 334 |
| 5.1.2.2 懸濁液の安定性 336 |
| 5.1.2.3 誘電泳動による粒子移動 337 |
| 5.2 現像における粒子付着の動力学 339 |
| 5.2.1 液体現像法 339 |
| 5.2.2 エアロゾル現像 344 |
| 5.2.3 カスケードと磁気ブラシ現像 346 |
| 5.2.4 センシトメトリーに関する考慮 347 |
| 第II部 引用文献 348 |
| 索引 355 |
| 第I部 電子写真プロセスと技術 |
| I 序論 3 |
| 1.1 歴史的概観 4 |
|
| 12.
|
 図書
図書
|
日本建築学会編
| 出版情報: |
東京 : 丸善, 1977.12-1980.2 2冊 ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 13.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
太田次郎著
| 出版情報: |
東京 : 裳華房, 1996.10 xi, 240p ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 1 生命の単位 |
| 1.1 生体を構成する物質 2 |
| 1.1.1 生体を構成する元素 2 |
| 1.1.2 生体の化学成分 3 |
| 1.2 細胞の構造と機能 10 |
| 1.2.1 細胞の形態 10 |
| 1.2.2 細胞の内部構造 13 |
| 1.2.3 細胞小器官の構造と機能 14 |
| 1.3 細菌とウイルス 30 |
| 1.3.1 細菌の構造 30 |
| 1.3.2 ウイルス 31 |
| 2 物質代謝とエネルギー代謝 |
| 2.1 生体反応の特性 39 |
| 2.1.1 酵素とそのはたらき 39 |
| 2.1.2 化学エネルギーとATP 41 |
| 2.2 生体のエネルギー獲得 43 |
| 2.2.1 光合成 43 |
| 2.2.2 窒素同化 49 |
| 2.2.3 発酵と解糖 51 |
| 2.2.4 呼吸 54 |
| 2.3 生体のエネルギー消費 57 |
| 2.3.1 筋肉の収縮 57 |
| 2.3.2 能動輸送 62 |
| 2.3.3 生体物質の合成 64 |
| 3 生物の恒常性と調節 |
| 3.1 神経による調節 66 |
| 3.1.1 神経細胞と興奮の伝達 66 |
| 3.1.2 ヒトの神経系 69 |
| 3.2 ホルモンによる調節 77 |
| 3.2.1 ヒトの内分泌器官とホルモン 77 |
| 3.2.2 ホルモンの相互作用 80 |
| 3.2.3 ホルモンの作用機構 82 |
| 3.3 ホメオスタシス―恒常性の維持 84 |
| 3.3.1 血糖量の維持 84 |
| 3.3.2 体温の調節 86 |
| 3.3.3 その他の恒常性と調節 87 |
| 3.3.4 バイオリズムと体内時計 88 |
| 3.4 免疫 89 |
| 3.4.1 抗原と抗体 89 |
| 3.4.2 抗体産生の機構 90 |
| 3.4.3 細胞性免疫 91 |
| 3.5 植物の調節 91 |
| 3.5.1 植物の成長と調節 92 |
| 3.5.2 光周性 97 |
| 4 生命の連続性-その(1)生殖と発生 |
| 4.1 生殖 100 |
| 4.1.1 無性生殖と有性生殖 100 |
| 4.1.2 細胞分裂 102 |
| 4.1.3 配偶子の形成 111 |
| 4.1.4 受精 113 |
| 4.2 発生 114 |
| 4.2.1 動物の発生の経過 115 |
| 4.2.2 動物の発生のしくみ 115 |
| 4.2.3 ヒトの発生 120 |
| 4.2.4 植物の発生 131 |
| 5 生命の連続性-その(2)遺伝と変異 |
| 5.1 遺伝 133 |
| 5.1.1 遺伝の法則 133 |
| 5.1.2 遺伝子と染色体 136 |
| 5.1.3 遺伝子の本体 141 |
| 5.1.4 遺伝子の形質発現 114 |
| 5.1.5 遺伝子工学とバイオテクノロジー 153 |
| 5.1.6 細胞質と遺伝 156 |
| 5.1.7 ヒトの遺伝 157 |
| 5.2 変異 164 |
| 5.2.1 環境変異 165 |
| 5.2.2 突然変異 165 |
| 6 生物の集団 |
| 6.1 個体群 169 |
| 6.1.1 個体群の密度 169 |
| 6.1.2 個体群の変動 171 |
| 6.1.3 個体群の構造 173 |
| 6.1.4 個体群の相互作用 175 |
| 6.2 生物群集 177 |
| 6.2.1 食物連鎖と食物網 178 |
| 6.2.2 生態的地位 179 |
| 6.2.3 生物群集の構造 180 |
| 6.2.4 生物群集における物質経済 181 |
| 6.3 生態系 183 |
| 6.3.1 生態系の構造と種類 183 |
| 6.3.2 生態系の遷移 190 |
| 6.3.3 生態系におけるエネルギーの流れ 192 |
| 6.3.4 生態系における物質の循環 194 |
| 6.4 生物圏と人類 199 |
| 6.4.1 生物圏 199 |
| 6.4.2 物質循環におよぼす人類の影響 200 |
| 6.4.3 自然保護 202 |
| 7 生命の変遷 |
| 7.1 生命の起源 204 |
| 7.1.1 自然発生説とその否定 204 |
| 7.1.2 生命の出現 206 |
| 7.1.3 物質代謝と細胞の進化 210 |
| 7.2 生物の進化 214 |
| 7.2.1 地質時代の生物の進化 214 |
| 7.2.2 人類の起源と進化 220 |
| 7.3 進化のしくみ 224 |
| 7.3.1 進化論の確立 224 |
| 7.3.2 現代の進化に関する研究 226 |
| 1 生命の単位 |
| 1.1 生体を構成する物質 2 |
| 1.1.1 生体を構成する元素 2 |
|
| 14.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
松井勇 [ほか] 著
| 出版情報: |
東京 : 井上書院, 2010.4 271p ; 26cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| Ⅰ編 構造材料 11 |
| 序 12 |
| 1 木質構造(材料)の特徴 14 |
| 1-1 木質構造の特徴とディティール 14 |
| 1-1-1 全般的な特徴 14 |
| 1-2 構造・材料の長所・短所 18 |
| 1-2-1 長所 18 |
| 1-2-2 短所とその対策 18 |
| 1-3 材料の種類および性質・選択 18 |
| 1-3-1 樹種と用途 18 |
| 1-3-2 木質材料の種類と特徴 20 |
| 2 鉄骨構造(材料)の特徴 22 |
| 2-1 鉄骨構造の特徴とディテール 22 |
| 2-1-1 全般的な特徴 22 |
| 2-2 構造・材料の長所・短所 23 |
| 2-2-1 長所 23 |
| 2-2-2 短所とその対策 23 |
| 2-3 材料の種類および性質・選択 23 |
| 2-3-1 鋼材の種類と表記 23 |
| 2-3-2 鉄鋼製品 24 |
| 2-3-3 鋼材の形状・寸法表示 24 |
| 2-3-4 鋼材の接合 27 |
| 2-3-5 架構 28 |
| 3 鉄筋コンクリート構造(材料)の特徴 31 |
| 3-1 鉄筋コンクリート構造の特徴とディテール 31 |
| 3-1-1 全般的な特徴 31 |
| 3-2 構造・材料の長所・短所 32 |
| 3-2-1 長所 32 |
| 3-2-2 短所とその対策 33 |
| 3-3 材料の種類および性質・選択 34 |
| 3-3-1 コンクリートと鉄筋 34 |
| 3-3-2 コンクリートの設計基準強度およびそのワーカビリティー 34 |
| 3-3-3 鉄筋の種類と接合 36 |
| 3-3-4 構造体の総合的耐久性 37 |
| 4 組積造(材料)の特徴 39 |
| Ⅱ編 部位と材料 43 |
| 序 44 |
| 1 屋根 45 |
| 1-1 要求条件 45 |
| 1-1-1 屋根に要求される条件 45 |
| 1-1-2 屋根材料に要求される性能 45 |
| 1-2 勾配屋根 46 |
| 1-2-1 勾配屋根の材料構成 47 |
| 1-2-2 屋根葺き材料の種類および特徴 47 |
| 1-3 陸屋根 48 |
| 1-3-1 陸屋根の材料構成 48 |
| 1-3-2 防水材の種類および特徴 49 |
| 2 外壁 50 |
| 2-1 要求条件 50 |
| 2-1-1 外壁に要求される条件 50 |
| 2-1-2 外壁仕上材料に要求される性能 50 |
| 2-2 外壁の材料構成 51 |
| 2-3 材料の種類および特徴 53 |
| 3 内壁 55 |
| 3-1 要求条件 55 |
| 3-1-1 内壁に要求される条件 55 |
| 3-1-2 内壁仕上材料に要求される性能 55 |
| 3-2 内壁の材料構成 56 |
| 3-3 材料の種類および特徴 57 |
| 4 天井 |
| 4-1 要求条件 59 |
| 4-1-1 天井に要求される条件 59 |
| 4-1-2 天井仕上材料に要求される性能 59 |
| 4-2 天井の材料構成 60 |
| 4-3 材料の種類および特徴 61 |
| 5 床 62 |
| 5-1 要求条件 62 |
| 5-1-1 床に要求される条件 62 |
| 5-1-2 床仕上材料に要求される性能 62 |
| 5-2 床の材料構成 63 |
| 5-3 材料の種類および特徴 64 |
| 6 建具 66 |
| 6-1 要求条件 66 |
| 6-1-1 建具に要求される条件 66 |
| 6-1-2 建具材料に要求される性能 67 |
| 6-2 建具の材料構成 67 |
| 6-2-1 建具の材料構成 67 |
| 6-2-2 建具のおもな部材名称 68 |
| 6-2-3 建具の種類 68 |
| 6-3 材料の種類および特徴 69 |
| 6-3-1 建具に用いられる材料分類 69 |
| 7 衛生器具 70 |
| 7-1 要求条件 70 |
| 7-1-1 衛生器具に要求される条件 70 |
| 7-1-2 材料に要求される性能 70 |
| 7-2 衛生器具の種類 71 |
| 7-3 材料の種類および特徴 71 |
| Ⅲ編 材料の機能 73 |
| 序 74 |
| 1 防水性 76 |
| 1-1 水分の挙動 76 |
| 1-2 水分と材料の性質 77 |
| 1-3 防水工法と材料 77 |
| 1-3-1 隔壁(材料)表面を不透水性の材料で覆って水分を遮断する工法 77 |
| 1-3-2 隔壁(材料)自体の吸水・吸湿性を低下させて,透水・透湿が生じにくい性質に変える工法 77 |
| 1-3-3 材料や部材のすきまに不透水性の材料を詰める工法 78 |
| 2 防火性 79 |
| 2-1 構造,建築物および材料の分類 79 |
| 2-1-1 構造の分類 79 |
| 2-1-2 建築物の分類 81 |
| 2-1-3 材料の分類 81 |
| 2-2 材料の燃焼と種類 82 |
| 2-2-1 材料の燃焼 82 |
| 2-2-2 不燃・難燃材料の種類 82 |
| 3 断熱・保温性 85 |
| 3-1 機能と原理 85 |
| 3-1-1 熱の移動と性質 85 |
| 3-1-2 断熱材の性質 86 |
| 3-2 断熱材の種類と断熱工法 88 |
| 3-2-1 断熱材の種類 88 |
| 3-2-2 断熱工法 89 |
| 4 音響特性 90 |
| 4-1 機能と原理 90 |
| 4-2 吸音方法と材料 90 |
| 4-2-1 多孔質材料による方法 90 |
| 4-2-2 板状材料の振動による方法 91 |
| 4-2-3 膜状材料による方法 91 |
| 4-2-4 あなあき板による方法 91 |
| 4-2-5 成形吸音板による方法 91 |
| 4-3 遮音方法と材料 92 |
| 5 接着性・接合性 93 |
| 5-1 機能と性能 93 |
| 5-2 物理化学的接合 93 |
| 5-2-1 接着 93 |
| 5-2-2 溶接 97 |
| 5-2-3 自着 99 |
| 5-3 機械的接合 101 |
| 5-3-1 仕口・継手による接合 101 |
| 5-3-2 接合金物による接合 101 |
| 5-3-3 補強金物による接合 102 |
| 5-3-4 ラスによる接合 103 |
| 6 保護・仕上げ性 104 |
| 6-1 機能と性能 104 |
| 6-2 塗科 104 |
| 6-2-1 概説 104 |
| 6-2-2 種類 104 |
| 6-2-3 塗料の機能と素地 107 |
| 6-2-4 用途と製品 108 |
| 6-3 建築用仕上塗材 110 |
| 6-3-1 概説 110 |
| 6-3-2 薄付け仕上塗材 111 |
| 6-3-3 厚付け仕上塗材 111 |
| 6-3-4 複層仕上塗材 111 |
| 6-3-5 可とう形改修用仕上塗材 112 |
| 6-3-6 軽量骨材仕上塗材 112 |
| 6-3-7 建築用下地調整塗材 112 |
| 6-4 表面含浸材 113 |
| 6-4-1 概説 113 |
| 6-4-2 シラン系表面含浸材 113 |
| 6-4-3 ケイ酸塩系表面含浸材 114 |
| 6-5 塗り床材 115 |
| 6-5-1 概説 115 |
| 6-5-2 塗布型塗り床材 115 |
| 6-5-3 一体型塗り床材 116 |
| 7 水密・気密性 118 |
| 7-1 機能と原理 118 |
| 7-2 シーリング材・コーキング材 118 |
| 7-2-1 建築用シーリング材 118 |
| 7-2-2 建築用油性コーキング材 120 |
| 7-2-3 金属製建具用ガラスパテ 120 |
| 7-2-4 補修用注入エポキシ樹脂 120 |
| 7-3 ガスケット 121 |
| 7-3-1 建築用発泡体ガスケット 121 |
| 7-3-2 建築用ガスケット 121 |
| 8 材料の感覚的性能 123 |
| 8-1 概説 123 |
| 8-2 温冷感触 123 |
| 8-3 凹凸感触 124 |
| 8-4 べたつき感触 125 |
| 8-5 よごれの程度 126 |
| 8-6 打音感触 126 |
| 9 環境負荷と建築材料 128 |
| 9-1 概説 128 |
| 9-2 環境負荷低減のための建築材料のあり方 129 |
| 9-2-1 環境基本法とその関係法令に示される建築材料 129 |
| 9-2-2 長寿命と建築材料 130 |
| 9-2-3 自然共生と建築材料 130 |
| 9-2-4 省エネルギーと建築材料 130 |
| 9-2-5 省資源・循環と建築材料 131 |
| 9-2-6 室内空気汚染と建築材料 131 |
| Ⅳ編 基本材料 133 |
| 序 134 |
| 1 金属材料 135 |
| 1-1 鉄鋼 135 |
| 1-1-1 製法 135 |
| 1-1-2 炭素鋼 137 |
| 1-1-3 特殊鋼 139 |
| 1-1-4 鋳鋼 140 |
| 1-1-5 用途と製品 140 |
| 1-2 アルミニウムおよびその合金 141 |
| 1-2-1 製法 141 |
| 1-2-2 種類・特徴 142 |
| 1-2-3 性質 142 |
| 1-2-4 用途と製品 144 |
| 1-3 銅およびその合金 145 |
| 1-3-1 製法 145 |
| 1-3-2 種類・特徴 145 |
| 1-3-3 性質 146 |
| 1-3-4 用途と製品 146 |
| 1-4 チタンおよびその合金 146 |
| 1-4-1 製法 146 |
| 1-4-2 種類・特徴 147 |
| 1-4-3 性質 147 |
| 1-4-4 用途と製品 148 |
| 1-5 亜鉛・スズ・鉛 148 |
| 1-5-1 製法 148 |
| 1-5-2 種類・特徴 149 |
| 1-5-3 性質 149 |
| 1-5-4 用途と製品 150 |
| 1-6 銀・金・白金 151 |
| 1-6-1 製法 151 |
| 1-6-2 種類・特徴 151 |
| 1-6-3 性質 152 |
| 1-6-4 用途と製品 152 |
| 1-7 耐久性 153 |
| 2 無機材料 156 |
| 2-1 石材 156 |
| 2-1-1 概説 156 |
| 2-1-2 種類および組成 156 |
| 2-1-3 一般的性質 156 |
| 2-1-4 製品 158 |
| 2-2 セメント 161 |
| 2-2-1 概説 161 |
| 2-2-2 ポルトランドセメントの製造 161 |
| 2-2-3 ポルトランドセメントの成分 161 |
| 2-2-4 ポルトランドセメントの水和 164 |
| 2-2-5 混和材 165 |
| 2-2-6 性質 167 |
| 2-3 コンクリート 170 |
| 2-3-1 コンクリート用材料 170 |
| 2-3-2 調合 181 |
| 2-3-3 フレッシュコンクリートの性質 188 |
| 2-3-4 初期性状 190 |
| 2-3-5 硬化コンクリートの性質 193 |
| 2-3-6 各種コンクリート 204 |
| 2-3-7 コンクリート製品 205 |
| 2-3-8 鉄筋コンクリート構造物の耐久性 208 |
| 2-4 石灰,せっこう,プラスター 215 |
| 2-4-1 概説 215 |
| 2-4-2 種類および組織,基本的性質 215 |
| 2-4-3 用途と製品 216 |
| 2-5 陶磁器 218 |
| 2-5-1 概説 218 |
| 2-5-2 素地の種類と性質 218 |
| 2-5-3 製品と用途 219 |
| 2-5-4 陶磁器の耐久性 222 |
| 2-6 ガラス 223 |
| 2-6-1 概説 223 |
| 2-6-2 種類・製法および加工法 223 |
| 2-6-3 一般的性質 224 |
| 2-6-4 製品と用途 225 |
| 3 有機材料 227 |
| 3-1 木材 227 |
| 3-1-1 構造と組織・木理・欠点 228 |
| 3-1-2 製材による種類 229 |
| 3-1-3 水分 230 |
| 3-1-4 一般的な性質 231 |
| 3-1-5 木材の耐久性 235 |
| 3-1-6 木質材料 238 |
| 3-2 プラスチック・ゴム 243 |
| 3-2-1 概要 243 |
| 3-2-2 種類 243 |
| 3-2-3 成形法・現場施工 244 |
| 3-2-4 性質 245 |
| 3-2-5 用途と製品 248 |
| 3-3 アスファルト 254 |
| 3-3-1 概説 254 |
| 3-3-2 種類と性質・用途 254 |
| Ⅴ編 材料の基本的物性と単位 257 |
| 1 質量・重量・密度・比重 258 |
| 2 強度・応力度・ひずみ度 258 |
| 3 温度・熱に関する物性値と単位 260 |
| 4 水に関する物性値と単位 261 |
| 5 音に関する物性値と単位 262 |
| 6 光・照明に関する物性値と単位 263 |
| 7 表色・光沢 264 |
| 索引 267 |
| Ⅰ編 構造材料 11 |
| 序 12 |
| 1 木質構造(材料)の特徴 14 |
|
| 15.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
小竹進著
| 出版情報: |
東京 : 丸善, 2005.8 viii, 115p ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 1.美の始まり 1 |
| 1.1美の歴史 2 |
| 1.2美の解釈 3 |
| 1.3美の展開 5 |
| 2.美と知覚 9 |
| 2.1知覚の機構 10 |
| 2.1.1記憶・知識との照合過程 11 |
| 2.1.2属性の階層性とその認識過程 14 |
| 2.2知覚のエネルギー 17 |
| 2.2.1知覚・認識の生物学的機構 17 |
| 2.2.2事象の知覚・認識過程とエネルギー 21 |
| 2.3知覚のエントロピー 25 |
| 2.3.1神経細胞の伝達パターンとエントロピー 25 |
| 2.3.2属性の確定性とエントロピー 28 |
| 3.美とエントロピー 31 |
| 3.1秩序と調和 32 |
| 3.1.1美とエントロピー最小の条件 32 |
| 3.1.2調和と共鳴 33 |
| 3.1.3調和と秩序 34 |
| 3.2階層調和のエントロピー 35 |
| 3.2.1階層構造と調和 35 |
| 3.2.2黄金比 36 |
| 3.3集合調和のエントロピー 43 |
| 3.3.1「感性」と「徳性」 43 |
| 3.3.2生物の行動にみる集合調和のエントロピー 43 |
| 4.美の事象:エントロピーの対象 53 |
| 4.1静的事象 54 |
| 4.1.1詩歌 54 |
| 4.1.2絵画 56 |
| 4.1.3工芸 57 |
| 4.1.4建物 62 |
| 4.1.5庭園 79 |
| 4.2動的事象 84 |
| 4.2.1音楽 85 |
| 4.2.2舞蹄 88 |
| 4.2.3動物 90 |
| 4.2.4鳥・魚 93 |
| 4.2.5航空機 99 |
| 参考文献 109 |
| 1.美の始まり 1 |
| 1.1美の歴史 2 |
| 1.2美の解釈 3 |
|
| 16.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
NTTコムウェア株式会社研究開発部著
| 出版情報: |
東京 : 電気通信協会 , 東京 : オーム社 (発売), 2005.12 v, 130p ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| はじめに |
| 第1章RFIDの現状 1 |
| 1.1RFIDとは 2 |
| 1.2RFIDタグの形状 4 |
| 1.3RFIDタグの分類 5 |
| 1.4パッシブタグの概要 6 |
| 1.5アクティブタグの概要 7 |
| 1.6RFIDタグのアンテナの種類とその特長 8 |
| 1.7RFIDタグのアンテナの形状と材質 9 |
| 1.8リーダ/ライタの種類 10 |
| 第2章RFIDの標準化動向 13 |
| 2.1周波数の動向 14 |
| 2.2UHF帯の周波数割当て状況 17 |
| 2.3RFIDの主な標準化動向 18 |
| 2.3.1EPCglobalの動向 18 |
| 2.3.1.1EPCglobalの概要 18 |
| 2.3.1.2EPCglobaの日本での活動20l |
| 2.3.1.3EPCglobal組織体制と標準化までの流れ 21 |
| 2.3.1.4EPCglobalネットワークのアーキテクチャ概要 25 |
| 2.3.1.4.1EPCの概要 28 |
| 2.3.1.4.2EPCタグの概要 31 |
| 2.3.1.4.3EPCミドルウェアの概要 32 |
| 2.3.1.4.4EPCISの概要 32 |
| 2.3.1.4.5NamingServicesの概要 34 |
| 2.3.1.5EPCglobalネットワークシステムの導入メリットや適応分野 35 |
| 2.3.2ユビキタスIDセンターの動向 36 |
| 2.3.2.1ユビキタスIDセンターの概要 36 |
| 2.3.2.2T-Engineフォーラム 37 |
| 2.3.2.3ユビキタスIDの概要 38 |
| 2.3.2.4ユビキタスIDアーキテクチャ概要 39 |
| 2.3.2.4.1ucode概要 41 |
| 2.3.2.4.2ucodeタグの体系 42 |
| 2.3.2.4.3UC(UbiquitousCommunicator) 44 |
| 2.3.2.4.4ucode解決サーバ 45 |
| 2.3.2.4.5情報サービスサーバ 46 |
| 2.3.2.4.6uTAD 47 |
| 2.3.2.4.7eTRONCA 47 |
| 2.3.2.4.8T-Engine 48 |
| 2.3.2.4.9nT-Engine・pT-Engineを利用したセンサーネットワーク 51 |
| 2.3.2.5アジアにおけるユビキタスIDセンター 52 |
| 2.3.3EPCglobalとユビキタスIDセンターの比較 53 |
| 2.4ISO/IECの動向 55 |
| 2.5Gen2の動向 56 |
| 2.6欧米のEPCGlobalNetworkの導入計画 58 |
| 2.6.1Wal*Mart 58 |
| 2.6.2Gillete 58 |
| 2.6.3Michelin 59 |
| 2.6.4米国国防総省(DoD : Department of Defense) 59 |
| 2.6.5米国食品医薬品局(FDA : Food and Drug Administration) 61 |
| 2.6.6Tesco(英) 62 |
| 2.6.7Metro(独) 62 |
| 2.6.8Carrefour(仏) 63 |
| 2.6.9米国パスポートにおける取組み 63 |
| 2.6.10航空業界での利用 63 |
| 2.6.11SUNテストセンタ 64 |
| 2.7アジアの事例 64 |
| 2.8ユビキタスID : 国土交通省「自律移動支援プロジェクト」概要 65 |
| 2.9RFIDタグの価格 66 |
| 2.10響プロジェクトの概要 67 |
| 2.11マーケット情報 68 |
| 第3章非接触ICカードの動向 71 |
| 3.1非接触ICカードの概要と動向 72 |
| 3.2FeliCaの概要と動向 75 |
| 3.3FeliCaの特徴 76 |
| 3.3.1マルチアプリケーションを実現 76 |
| 3.3.2ファイルことに鍵やアクセル権が設定可能なファイルシステム 76 |
| 3.3.3高い通信セキュリティを実現 77 |
| 3.3.4業界最高速の処理スピードを実現 78 |
| 3.4Suica(JR東日本) 78 |
| 3.5Suicaの利用者数 79 |
| 3.6おサイフケータイ(NTTドコモ) 80 |
| 3.7おサイフケータイのアプリケーション 81 |
| 第4章システム構築時の留意点 83 |
| 4.1RFIDの課題 84 |
| 4.1.1プライバシ(経済産業省ガイドライン、EPCglobalガイドライン) 84 |
| 4.1.2RFIDタグのコスト 85 |
| 4.1.3周波数 85 |
| 4.1.4タギング 85 |
| 4.2システム導入における検討項目 86 |
| 4.2.1RFIDタグの選定 86 |
| 4.2.2リーダ/ライタの選定 86 |
| 4.2.3RFIDタグの通信の検証 87 |
| 第5章国内の事例 89 |
| 5.1国内での主な事例 90 |
| 5.1.1総務省による実験 90 |
| 5.1.2経済産業省平成16年度電子タグ実証実験事業 91 |
| 5.1.3食品トレーサビリティ実証実験 92 |
| 5.2NTTコムウェアの取組み 94 |
| 5.2.1EPCglobalNetworkプラットフォームの開発 94 |
| 5.2.2パレット循環モデル 98 |
| 5.2.3店頭在庫モデル 99 |
| 5.2.4資産管理モデル 99 |
| 5.2.5ユビキタスIDを用いたIndoorPositioningシステム 102 |
| 5.2.6アクティブタグを用いたプレゼンス管理モデル 104 |
| 5.2.7InfoorNavigationモデル 105 |
| 5.2.8無線LANによる位置情報サービス 107 |
| 5.2.9パソコン所在管理 108 |
| 5.2.10重要文書管理 109 |
| 5.2.11入館者動線管理 110 |
| 5.2.12工場備品管理 111 |
| 5.2.13レンタル物品管理 112 |
| 5.2.14日配食品の共同配送 113 |
| 5.2.15物流品質管理 114 |
| 5.2.16フューチャーストア 115 |
| 5.2.17部品管理 116 |
| 第6章付録 119 |
| 6.1国内のRFIDタグ導入・実験事例 120 |
| 6.2電子タグに関するプライバシ保護ガイドライン 123 |
| 6.3Guidelines on EPC for Consumer Productr 127 |
| 参考文献 129 |
| あとがき |
| はじめに |
| 第1章RFIDの現状 1 |
| 1.1RFIDとは 2 |
|
| 17.
|
 図書
図書
|
電気学会第2次M2M技術調査専門委員会編
| 出版情報: |
東京 : 森北出版, 2016.3 vi, 183p ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 第1章 : M2Mシステムとは |
| 第2章 : M2Mのアプリケーション事例 |
| 第3章 : M2Mシステム構築技術 |
| 第4章 : M2Mプラットフォーム |
| 第5章 : M2Mネットワーク |
| 第6章 : M2Mセキュリティ |
| 第1章 : M2Mシステムとは |
| 第2章 : M2Mのアプリケーション事例 |
| 第3章 : M2Mシステム構築技術 |
概要:
M2M/IoTにかかわるハードウェア、ソフトウェア、通信の全体像を解説。これからシステム構築に取り組む技術者におすすめです。
|
| 18.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
土木学会
目次情報:
続きを見る
| 【Ⅴ編 ダムの耐震設計と動的解析】 |
| 1. 耐震設計基準と耐震設計法 3 |
| 1.1 日本における考え方 3 |
| 1.2 米国における考え方 4 |
| 1.3 動的解析への移行 5 |
| 2. ダムの動的挙動の研究 7 |
| 2.1 動的解析手法の変遷 7 |
| 2.2 地震観測による研究 8 |
| 2.2.1 ダムの地震応答特性 8 |
| 2.2.2 日本のダムの地震時挙動 9 |
| 2.2.3 外国のダムの地震時挙動 14 |
| 2.3 振動実験による研究 17 |
| 2.3.1 フィルダム 17 |
| 2.3.2 重力ダム 18 |
| 2.3.3 アーチダム 21 |
| 2.4 動水圧・動的相互作用理論 23 |
| 2.4.1 動水圧 23 |
| 2.4.2 ダム-貯水-地盤系の動的解析 25 |
| 3. フィルダムの動的解析と実例 29 |
| 3.1 概要 29 |
| 3.2 静的初期状態解析 30 |
| 3.2.1 築堤解析 30 |
| 3.2.2 湛水解析 34 |
| 3.3 動的解析 37 |
| 3.3.1 入力地震動の選定 37 |
| 3.3.2 動的物性 38 |
| 3.3.3 動的解析の適用 47 |
| 3.4 安全性の評価 52 |
| 3.4.1 すべりに対する安全率 52 |
| 3.4.2 Newmarkによる剛体すべり量 53 |
| 3.4.3 Makdisi-Seedによる剛体すべり量 55 |
| 3.4.4 渡辺・馬場によるすべり量 56 |
| 3.4.5 液状化に対する検討 57 |
| 3.5 動的解析の実例 61 |
| 3.5.1 牧尾ダムの動的解析 61 |
| 3.5.2 岩屋ダムの動的解析 65 |
| 4. コンクリートダムの動的解析と実例 72 |
| 4.1 概要 72 |
| 4.1.1 重力ダム 72 |
| 4.1.2 アーチダム 73 |
| 4.2 動的解析に用いる物性 74 |
| 4.2.1 動的変形特性 74 |
| 4.2.2 動的強度 77 |
| 4.3 重力ダムの動的解析例 80 |
| 4.3.1 コンクリートの非線形物性 80 |
| 4.3.2 地震によるクラックの解析 84 |
| 4.4 アーチダムの動的解析例 86 |
| 4.4.1 Pacoimaダムの動的解析 86 |
| 4.4.2 奈川渡ダムの動的解析 90 |
| 5. 今後の課題 98 |
| 文献 103 |
| 【Ⅵ編 産業施設の耐震設計と動的解析】 |
| 1. 原子力発電所の地盤および土木構造物 109 |
| 1.1 耐震設計の基本的考え方 109 |
| 1.2 地質および地盤調査 113 |
| 1.3 安全性評価に必要な物性 116 |
| 1.4 耐震安全性の評価手法 120 |
| 1.4.1 原子炉建屋基礎地盤と周辺斜面 120 |
| 1.4.2 屋外重要土木構造物 123 |
| 1.5 耐震性評価の事例 125 |
| 1.5.1 原子炉建屋基礎地盤 125 |
| 1.5.2 周辺斜面 130 |
| 1.5.3 屋外重要土木構造物 136 |
| 2. 送・変電施設 143 |
| 2.1 変電施設 143 |
| 2.1.1 耐震設計法 143 |
| 2.1.2 動的解析の事例 147 |
| 2.2 送電鉄塔 155 |
| 2.2.1 耐震設計法 155 |
| 2.2.2 動的解析の事例 159 |
| 2.2.3 今後の検討課題 170 |
| 3. 地上貯槽および配管 171 |
| 3.1 地上貯槽 171 |
| 3.1.1 はじめに 171 |
| 3.1.2 耐震設計法 174 |
| 3.1.3 動的解析の方法と事例 185 |
| 3.1.4 今後の検討課題 190 |
| 3.2 配管 192 |
| 3.2.1 はじめに 192 |
| 3.2.2 耐震設計法 192 |
| 3.2.3 動的解析の方法と事例 197 |
| 3.2.4 今後の検討課題 203 |
| 4. 免震・防振構造 205 |
| 4.1 免震構造 205 |
| 4.1.1 免震設計法 205 |
| 4.1.2 動的解析の方法と事例 209 |
| 4.1.3 今後の課題 216 |
| 4.2 防振設計と弾性支持法 217 |
| 4.2.1 防振設計の考え方と振動絶縁理論 217 |
| 4.2.2 弾性支持法 221 |
| 4.2.3 弾性支持法の適用例 225 |
| 文献 227 |
| 【Ⅴ編 ダムの耐震設計と動的解析】 |
| 1. 耐震設計基準と耐震設計法 3 |
| 1.1 日本における考え方 3 |
|
| 19.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
日本機械学会著
| 出版情報: |
東京 : 日本機械学会 , [東京] : 丸善 (発売), 1999.2-2008.12 2冊 ; 31cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 第1章 材料力学 |
| 1.1 緒言 1 |
| 1.2 棒の断面に伝わっている荷重 1 |
| 1.2.1 平衡条件 1 |
| 1.2.2 棒の横断面に伝わっている力および偶力の種類 2 |
| 1.2.3 応力とひずみ 2 |
| 1.3 直線棒の応力と変形 3 |
| 1.3.1 引張力による応力と変形 3 |
| 1.3.2 曲げモーメントによる応力と変形 4 |
| 1.3.3 ねじりモーメントによる応力と変形 15 |
| 1.3.4 引張力、曲げモーメントおよびねじりモーメントによる応力と変形の統一的取扱い 18 |
| 1.4 細長い曲線棒の応力と変形 22 |
| 1.4.1 重ね合わせの原理による変形の求め方 22 |
| 1.4.2 カスティリアーノの定理による変形の求め方 24 |
| 1.5 太く短い曲線棒の引張りと曲げ 26 |
| 1.5.1 応力と変形 26 |
| 1.5.2 断面定数kの計算 28 |
| 1.6 細長い直線棒の圧縮による座屈 28 |
| 1.6.1 安定な釣合いと不安定な釣合い 28 |
| 1.6.2 ばねで支えられた剛体棒の座屈荷重 29 |
| 1.6.3 オイラーの座屈荷重 29 |
| 1.7 材料力学と弾性力学の関係 31 |
| 第2章 弾性力学 |
| 2.1 弾性学の基礎式 33 |
| 2.1.1 応力成分とひずみ成分 33 |
| 2.1.2 応力・ひずみ成分の座標変換 35 |
| 2.1.3 弾性基礎式 38 |
| 2.2 二次元弾性理論 42 |
| 2.2.1 二次元弾性基礎式 42 |
| 2.2.2 直角座標における平面応力理論 43 |
| 2.2.3 極座標における平面応力理論 48 |
| 2.2.4 半無限板に関する混合境界値問題 56 |
| 2.2.5 複素応力関数による平面応力問題 61 |
| 2.2.6 等角写像関数を用いた平面応力問題 69 |
| 2.3 一様断面棒のねじり 72 |
| 2.3.1 一様断面棒のねじり 72 |
| 2.3.2 薄肉断面棒のねじり 76 |
| 2.3.3 複素関数による解法(単連結領域) 78 |
| 2.4 一様断面ばりの曲げ 79 |
| 2.4.1 片持ちばりの曲げ 79 |
| 2.4.2 せん断中心 81 |
| 2.4.3 薄肉断面材の曲げ 82 |
| 2.5 平板の曲げ 84 |
| 2.5.1 たわみの基礎方程式(直角座標) 84 |
| 2.5.2 たわみの基礎方程式(極座標) 90 |
| 2.6 三次元弾性理論 91 |
| 2.6.1 三次元弾性基礎式と変位関数 91 |
| 2.6.2 軸対称ねじり 97 |
| 2.6.3 ねじりなし軸対称応力状態 100 |
| 2.6.4 半無限体に関する混合境界値問題 111 |
| 2.7 弾性接触論 114 |
| 2.7.1 ヘルツの弾性接触論 114 |
| 2.7.2 摩擦を考慮した弾性接触問題 118 |
| 2.8 熱応力 121 |
| 2.8.1 熱弾性基礎式 121 |
| 2.8.2 棒の定常熱応力 124 |
| 2.8.3 円板・中空円板の熱応力 124 |
| 2.8.4 厚板の熱応力 126 |
| 2.8.5 円柱および円筒の熱応力 127 |
| 2.8.6 球・中空球の熱応力 128 |
| 2.9 衝撃応力 130 |
| 2.9.1 棒の縦衝撃理論(一次元動弾性理論) 130 |
| 2.9.2 二次元動弾性理論と三次元動弾性理論 133 |
| 2.9.3 はりの曲げ衝撃 136 |
| 2.9.4 ヘルツの弾性接触論に基づく衝撃荷重の解析 137 |
| 2.10 付録 139 |
| 2.10.1 調和関数と重調和関数 139 |
| 2.10.2 フーリエ変換 141 |
| 2.10.3 アーベル変換 142 |
| 2.10.4 ヒルベルト問題 143 |
| 2.10.5 連立積分方程式 144 |
| 2.10.6 材料力学の歴史 146 |
| 第3章 塑性・クリープ力学 |
| 3.1 単軸応力下の塑性変形 149 |
| 3.1.1 引張応力-ひずみ曲線 149 |
| 3.1.2 真応力と真ひずみ 149 |
| 3.1.3 応力-ひずみ曲線の数式表示 151 |
| 3.1.4 バウシンガ効果 151 |
| 3.2 塑性構成式 151 |
| 3.2.1 初期降伏曲面 151 |
| 3.2.2 von Misesの降伏条件 152 |
| 3.2.3 Tresca の降伏条件 153 |
| 3.2.4 後続降伏条件 154 |
| 3.2.5 Druckerの仮説と最大塑性仕事の原理 160 |
| 3.2.6 関連流れ則 160 |
| 3.2.7 繰返し塑性 163 |
| 3.3 単軸応力下のクリープ変形 165 |
| 3.3.1 クリープ現象と機構 165 |
| 3.3.2 単軸クリープの数式化 167 |
| 3.3.3 線形単軸粘弾性モデル 169 |
| 3.4 クリープ構成式 172 |
| 3.4.1 クリープポテンシャルと流れ則 172 |
| 3.4.2 定常クリープの構成式 172 |
| 3.4.3 非定常クリープの構成式 174 |
| 3.4.4 応力反転時のクリープ則 176 |
| 3.4.5 異方性クリープの構成式 176 |
| 3.4.6 粘塑性構成式 177 |
| 3.4.7 クリープ破断の構成式 179 |
| 第4章 応力解析法 |
| 4.1 ひずみエネルギー 185 |
| 4.1.1 エネルギー原理 185 |
| 4.2 近似解法 189 |
| 4.2.1 リッツの方法とガラーキンの方法 189 |
| 4.2.2 塑性近似解法 191 |
| 4.3 数値解析法 198 |
| 4.3.1 有限要素法 198 |
| 4.3.2 境界要素法 208 |
| 4.3.3 体積力法 222 |
| 第1章 材料力学 |
| 1.1 緒言 1 |
| 1.2 棒の断面に伝わっている荷重 1 |
|
| 20.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
| 出版情報: |
東京 : シーエムシー出版, 2008.2 xiii, 223p ; 26cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 第1章 総論 1 |
| 1 ナノテクノロジーとナノマテリアル 1 |
| 2 技術体系 3 |
| 3 ナノテクノロジーの公的プロジェクト 5 |
| 3.1 内閣府「科学技術基本計画」 5 |
| 3.2 経済産業省「ナノテクノロジープログラム」 7 |
| 第2章 ナノマテリアル市場 9 |
| 1. カーボンナノチューブ 9 |
| 1.1 概要 9 |
| 1.2 用途 9 |
| 1.3 市場規模 12 |
| 1.4 企業動向 12 |
| 1.4.1 日機装,産業技術総合研究所 12 |
| 1.4.2 住友商事 13 |
| 1.4.3 独バイエル 13 |
| 1.4.4 日立造船 14 |
| 1.4.5 昭和電工 14 |
| 2. フラーレン 15 |
| 2.1 概要 15 |
| 2.2 用途 16 |
| 2.3 市場規模 17 |
| 2.4 企業動向 17 |
| 3. ナノコンポジット 18 |
| 3.1 概要 18 |
| 3.2 用途 18 |
| 3.3 市場規模 19 |
| 3.4 企業動向 19 |
| 3.4.1 ユニチカ 19 |
| 3.4.2 日本触媒 20 |
| 4. ナノゼオライト 21 |
| 4.1 概要 21 |
| 4.2 用途 21 |
| 4.3 市場規模 22 |
| 4.4 企業動向 22 |
| 5. ナノガラス 23 |
| 5.1 概要 23 |
| 5.2 用途 23 |
| 5.3 市場規模 24 |
| 5.4 企業動向 25 |
| 6. 高張力鋼板 26 |
| 6.1 概要 26 |
| 6.2 用途 26 |
| 6.3 市場規模 27 |
| 6.4 企業動向 27 |
| 7. ナノ磁性材料 29 |
| 7.1 概要 29 |
| 7.2 用途 30 |
| 7.3 市場規模 30 |
| 7.4 企業動向 31 |
| 7.4.1 日立金属 31 |
| 7.4.2 富士フイルム 32 |
| 7.4.3 物質・材料研究機構 32 |
| 8. ナノ粒子 34 |
| 8.1 概要 34 |
| 8.2 用途 35 |
| 8.3 市場規模 37 |
| 8.4 企業動向 37 |
| 8.4.1 ホソカワミクロン 37 |
| 8.4.2 英ナノコ・テクノロジーズ社 38 |
| 8.4.3 産業技術総合研究所 39 |
| 8.4.4 大阪大学 39 |
| 9. ナノ繊維 40 |
| 9.1 概要 40 |
| 9.2 用途 40 |
| 9.3 市場規模 40 |
| 9.4 企業動向 41 |
| 9.4.1 東レ 41 |
| 9.4.2 帝人 42 |
| 10. フォトニック結晶 43 |
| 10.1 概要 43 |
| 10.2 用途 44 |
| 10.3 市場規模 44 |
| 10.4 企業動向 44 |
| 10.4.1 フォトニツクラティス 44 |
| 10.4.2 松下電器産業 45 |
| 11. 光触媒 46 |
| 11.1 概要 46 |
| 11.2 用途 46 |
| 11.3 市場規模 49 |
| 11.4 企業動向 51 |
| 11.4.1 石原産業 51 |
| 11.4.2 テイカ 51 |
| 11.4.3 日本エクスランエ業 52 |
| 第3章 ナノ加工・計測装置市場 54 |
| 1. CVD 54 |
| 1.1 概要 54 |
| 1.2 用途 54 |
| 1.2.1 半導体製造分野 55 |
| 1.2.2 DLC(ダイヤモンドライクカーボン) 55 |
| 1.2.3 カーボンナノチューブ 56 |
| 1.2.4 薄膜シリコン太陽電池 57 |
| 1.3 市場規模 58 |
| 1.4 企業動向 58 |
| 1.4.1 アルバック 58 |
| 1.4.2 キヤノンアネルバ 59 |
| 1.4.3 米アプライドマテリアルズ社 59 |
| 2. PVD 61 |
| 2.1 概要 61 |
| 2.2 用途 62 |
| 2.3 市場規模 62 |
| 2.4 企業動向 63 |
| 2.4.1 ルネサステクノロジ 63 |
| 2.4.2 住友電工ハードメタル 64 |
| 3. ドライエッチング装置 65 |
| 3.1 概要 65 |
| 3.2 用途 65 |
| 3.3 市場規模 66 |
| 3.4 企業動向 66 |
| 3.4.1 住友精密工業 67 |
| 3.4.2 スイスUnaxis(ユナクシス)社 67 |
| 4. FIB装置 69 |
| 4.1 概要 69 |
| 4.2 用途 69 |
| 4.3 市場規模 69 |
| 4.4 企業動向 70 |
| 4.4.1 日立ハイテクノロジーズ 70 |
| 4.4.2 日本電子 71 |
| 5. ナノインプリント装置 72 |
| 5.1 概要 72 |
| 5.2 用途 72 |
| 5.3 市場規模 73 |
| 5.4 企業動向 73 |
| 5.4.1 SCIVAX 73 |
| 5.4.2 アイトリツクス,ナノニクス 74 |
| 6. ナノ粒子分散機 75 |
| 6.1 概要 75 |
| 6.2 用途 75 |
| 6.3 市場規模 75 |
| 6.4 企業動向 76 |
| 6.4.1 三井鉱山 76 |
| 6.4.2 その他のメーカー 76 |
| 7. 粒度分布測定装置 77 |
| 7.1 概要 77 |
| 7.2 種類 77 |
| 7.3 用途 78 |
| 7.4 市場規模 78 |
| 7.5 企業動向 79 |
| 7.5.1 日機装 79 |
| 7.5.2 堀場製作所 80 |
| 8. TEM 81 |
| 8.1 概要 81 |
| 8.2 用途 81 |
| 8.3 市場規模 82 |
| 8.4 企業動向 82 |
| 9. SEM 83 |
| 9.1 概要 83 |
| 9.2 用途 84 |
| 9.3 市場規模 84 |
| 9.4 企業動向 84 |
| 第4章 通信・エレクトロニクス分野での応用 85 |
| 1. 有機半導体 85 |
| 1.1 概要 85 |
| 1.2 用途 86 |
| 1.3 市場規模 86 |
| 1.4 企業動向 86 |
| 1.4.1 旭化成 86 |
| 1.4.2 日立製作所,旭化成など 87 |
| 1.4.3 E-Ink 87 |
| 1.4.4 フィリップス 87 |
| 1.4.5 サムスン電子 88 |
| 2. CMOSセンサー 89 |
| 2.1 概要 89 |
| 2.2 用途 90 |
| 2.3 市場規模 90 |
| 2.4 企業動向 90 |
| 2.4.1 東芝 91 |
| 2.4.2 半導体テクノロジーズ(セリート)91 |
| 3. 有機EL 92 |
| 3.1 概要 92 |
| 3.2 用途 94 |
| 3.3 市場規模 95 |
| 3.4 企業動向 95 |
| 3.4.1 東北パイオニア 96 |
| 3.4.2 TDK 96 |
| 3.4.3 ソニー 97 |
| 3.4.4 サムスンSDI 97 |
| 3.4.5 オプトロレックス,日本精機 98 |
| 3.4.6 京セラ 98 |
| 3.4.7 住友化学 98 |
| 3.4.8 セイコーエプソン 98 |
| 3.4.9 出光興産 99 |
| 4. 電子ペーパー 100 |
| 4.1 概要 100 |
| 4.2 種類 101 |
| 4.2.1 電気泳動方式 102 |
| 4.2.2 ツイストボール方式 103 |
| 4.2.3 トナーディスプレイ方式 104 |
| 4.2.4 磁気粒子回転方式 105 |
| 4.2.5 磁気泳動方式 105 |
| 4.2.6 サーマル/ケミカル・リライタブル方式 105 |
| 4.2.7 液晶方式 106 |
| 4.2.8 電気化学方式 107 |
| 4.3 用途 107 |
| 4.4 市場規模 107 |
| 4.5 企業動向 108 |
| 4.5.1 E-Ink,ルーセントテクノロジー 108 |
| 4.5.2 ソニー 108 |
| 4.5.3 凸版印刷 109 |
| 4.5.4 キヤノン 109 |
| 4.5.5 NOK 110 |
| 4.5.6 蘭フィリップス 110 |
| 4.5.7 ブリヂストン 110 |
| 4.5.8 スタンレー電気 111 |
| 4.5.9 米モトローラ,米E-Ink 111 |
| 4.5.10 富士ゼロックス 111 |
| 4.5.11 コニカミノルタ 111 |
| 4.5.12 その他 112 |
| 5. 磁気へツド 113 |
| 5.1 概要 113 |
| 5.2 用途 113 |
| 5.3 市場規模 114 |
| 5.4 企業動向 115 |
| 5.4.1 TDK 115 |
| 5.4.2 富士通グループ 116 |
| 5.4.3 束芝 116 |
| 5.4.4 日立製作所 117 |
| 6. FED 118 |
| 6.1 概要 118 |
| 6.2 用途 122 |
| 6.3 市場規模 123 |
| 6.4 企業動向 123 |
| 6.4.1 双葉電子工業 123 |
| 6.4.2 ソニー(エフ・イー・テクノロジーズ) 124 |
| 6.4.3 キヤノン 124 |
| 6.4.4 松下電工 125 |
| 6.4.5 その他のメーカー 125 |
| 7. DMD 126 |
| 7.1 概要 126 |
| 7.2 用途 127 |
| 7.3 市場規模 127 |
| 7.4 企業動向 128 |
| 8. 光ディスク 129 |
| 8.1 概要 129 |
| 8.2 用途 132 |
| 8.3 市場規模 132 |
| 8.4 企業動向 133 |
| 8.4.1 東芝 134 |
| 8.4.2 ソニー 134 |
| 8.4.3 三菱化学メディア 135 |
| 8.4.4 日立マクセル 135 |
| 9. 量子ドット 136 |
| 9.1 概要 136 |
| 9.2 用途 138 |
| 9.2.1 単電子トランジスタ 138 |
| 9.2.2 量子コンピュータ 139 |
| 9.2.3 量子テレポーテーション 140 |
| 9.2.4 量子ドットレーザー 141 |
| 9.2.5 量子ドット型太陽電池 141 |
| 9.2.6 バイオ研究(蛍光色素) 142 |
| 9.3 市場規模 142 |
| 9.4 企業動向 143 |
| 9.4.1 富士通研究所 143 |
| 9.4.2 富士通 143 |
| 9.4.3 NEC 144 |
| 9.4.4 英ナノコ・テクノロジーズ 145 |
| 第5章 エネルギー分野での応用 146 |
| 1. 燃料電池 146 |
| 1.1 概要 146 |
| 1.2 種類 147 |
| 1.3 用途 148 |
| 1.3.1 燃料電池自動車 148 |
| 1.3.2 定置用燃料電池 148 |
| 1.4 市場規模 149 |
| 1.4.1 PAFC 149 |
| 1.4.2 MCFC 149 |
| 1.4.3 SOFC 150 |
| 1.4.4 PEFC 151 |
| 1.4.5 DMFC 153 |
| 2. リチウムイオン電池 155 |
| 2.1 概要 155 |
| 2.2 用途 156 |
| 2.3 市場規模 156 |
| 2.4 企業動向 157 |
| 2.4.1 三洋電機 157 |
| 2.4.2 束芝 158 |
| 2.4.3 昭和電工 158 |
| 2.4.4 KRI 159 |
| 3. 薄膜シリコン太陽電池 160 |
| 3.1 概要 160 |
| 3.2 用途 160 |
| 3.3 市場規模 161 |
| 3.4 企業動向 162 |
| 3.4.1 シャープ 163 |
| 3.4.2 三菱重工業 163 |
| 4. 色素増感太陽電池 165 |
| 4.1 概要 165 |
| 4.2 用途 166 |
| 4.3 市場規模 166 |
| 4.4 企業動向 167 |
| 4.4.1 フジクラ 167 |
| 4.4.2 TDK 167 |
| 4.4.3 昭和電工 168 |
| 5. 電気二重層キャパシタ 170 |
| 5.1 概要 170 |
| 5.2 用途 170 |
| 5.3 市場規模 173 |
| 5.4 企業動向 173 |
| 5.4.1 NECトーキン 174 |
| 5.4.2 松下電子部品 175 |
| 5.4.3 オムロン 176 |
| 5.4.4 明電舎 176 |
| 5.4.5 北川精機 176 |
| 5.4.6 FDK 176 |
| 5.4.7 日清紡,日本無線 177 |
| 第6章 バイオ分野での応用 178 |
| 1. バイオチップ 178 |
| 1.1 概要 178 |
| 1.2 種類・用途 179 |
| 1.2.1 DNAチップ 179 |
| 1.2.2 プロテインチップ 180 |
| 1.2.3 糖鎖チップ 181 |
| 1.2.4 細胞・微生物チップ 182 |
| 1.3 市場規模 182 |
| 1.4 企業動向 183 |
| 1.4.1 タカラバイオ 183 |
| 1.4.2 東洋紡 184 |
| 1.4.3 日立ソフトエンジニアリング 184 |
| 1.4.4 理化学研究所 184 |
| 1.4.5 日立製作所 184 |
| 1.4.6 山武 185 |
| 1.4.7 NEC 185 |
| 1.4.8 その他 186 |
| 2. バイオセンサー 188 |
| 2.1 概要 188 |
| 2.2 種類 190 |
| 2.2.1 酸化還元酵素センサー 191 |
| 2.2.2 その他の酵素センサー 191 |
| 2.2.3 微生物センサー 191 |
| 2.2.4 免疫物質センサー 192 |
| 2.2.5 遺伝子センサー 192 |
| 2.2.6 細胞・器官センサー 193 |
| 2.2.7 その他の生体物質センサー 194 |
| 2.2.8 脂質・脂質膜センサー 194 |
| 2.2.9 感覚模倣センサー 195 |
| 2.2.10 トランスデューサ等 195 |
| 2.3 用途 195 |
| 2.3.1 医療分野 195 |
| 2.3.2 環境分野 196 |
| 2.3.3 食品分野 197 |
| 2.4 市場規模 198 |
| 2.5 企業動向 198 |
| 2.5.1 大阪工業大学 198 |
| 2.5.2 日本無線,英オーラ・プロテイン・テクノロジーズ 199 |
| 2.5.3 アンデス電気 199 |
| 第7章 医療・健康・生活分野での応用 201 |
| 1. DDS 201 |
| 1.1 概要 201 |
| 1.2 用途 202 |
| 1.3 市場規模 203 |
| 1.4 企業動向 204 |
| 1.4.1 バイオメッドコア 205 |
| 1.4.2 富士フイルム 206 |
| 1.4.3 日油(旧日本油脂) 207 |
| 2. 再生医療 208 |
| 2.1 概要 208 |
| 2.1.1 生体親和性材料 208 |
| 2.1.2 組織再生技術 208 |
| 2.2 用途 209 |
| 2.3 市場規模 210 |
| 2.4 企業動向 210 |
| 2.4.1 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 210 |
| 2.4.2 三菱化学メディエンス(旧三菱化学ビーシーエル) 211 |
| 2.4.3 オリンパス,テルモ 211 |
| 3. ナノ化粧品 213 |
| 3.1 概要 213 |
| 3.2 用途 213 |
| 3.3 市場規模 214 |
| 3.4 企業動向 214 |
| 4. ナノ食品 216 |
| 4.1 概要 216 |
| 4.2 用途 218 |
| 4.2.1 有機ナノチューブ 218 |
| 4.2.2 カーボンナノケージ 219 |
| 4.3 市場規模 220 |
| 4.4 企業動向 221 |
| 4.4.1 沖縄発酵化学 221 |
| 4.4.2 林原生物化学研究所 221 |
| 4.4.3 日清ファルマ 222 |
| 4.4.4 味の素 223 |
| 4.4.5 扶桑化学工業 223 |
| 第1章 総論 1 |
| 1 ナノテクノロジーとナノマテリアル 1 |
| 2 技術体系 3 |
|
| 21.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
谷口雅彦著
| 出版情報: |
東京 : 培風館, 2005.11 v, 166p ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 1 1変数の解析学 1 |
| 1.1 いろいろな関数 1 |
| 1.1.1 基本的事柄の復習 1 |
| 1.1.2 多項式と分数関数 4 |
| 1.1.3 無理関数 6 |
| 1.1.4 指数関数と対数関数 8 |
| 1.1.5 三角関数と逆三角関数 10 |
| 1.1.6 極限と連続関数 12 |
| 1.1節の問題 14 |
| 1.2 微分 15 |
| 1.2.1 初等関数の微分 15 |
| 1.2.2 対数微分と逆関数の微分 18 |
| 1.2.3 ロピタルの定理 20 |
| 1.2.4 ランダウ記号 22 |
| 1.2.5 極大・極小 24 |
| 1.2.6 高次導関数 26 |
| 1.2.7 有限テイラー展開 28 |
| 1.2節の問題 30 |
| 1.3 積分 31 |
| 1.3.1 初等関数の積分 31 |
| 1.3.2 置換積分法 34 |
| 1.3.3 部分積分法 36 |
| 1.3.4 面積計算 38 |
| 1.3.5 フーリエ級数 40 |
| 1.3.6 広義積分 42 |
| 1.3.7 ラプラス変換 44 |
| 1.3.8 不定積分の技法 : 補足 46 |
| 1.3節の問題 48 |
| 2 1変数の解析学続論 51 |
| 2.1 続いろいろな関数 51 |
| 2.1.1 ガンマ関数とベータ関数 51 |
| 2.1.2 定積分への応用 54 |
| 2.1.3 ゼータ関数 56 |
| 2.1節の問題 58 |
| 2.2 ベキ級数 59 |
| 2.2.1 収束半径 59 |
| 2.2.2 項別微分と項別積分 62 |
| 2.2.3 テイラーの定理 64 |
| 2.2.4 複素数と複素平面 66 |
| 2.2.5 フーリエ変換 68 |
| 2.2節の問題 70 |
| 2.3 常微分方程式 71 |
| 2.3.1 変数分離形 71 |
| 2.3.2 1階線型微分方程式 74 |
| 2.3.3 定数係数2階線型微分方程式 76 |
| 2.3.4 演算子とラプラス変換 78 |
| 2.3.5 ベキ級数による解法 80 |
| 2.3節の問題 82 |
| 3 2変数の解析学 85 |
| 3.1 微分 85 |
| 3.1.1 極限と連続関数 85 |
| 3.1.2 偏微分 88 |
| 3.1.3 ベクトル場と合成関数の微分公式Ⅰ 90 |
| 3.1.4 合成関数の微分公式Ⅱ 92 |
| 3.1.5 全微分 94 |
| 3.1.6 有限テイラー展開 96 |
| 3.1.7 グラフの追跡 98 |
| 3.1節の問題 100 |
| 3.2 積分 101 |
| 3.2.1 重積分と累次積分 101 |
| 3.2.2 極座標変換 104 |
| 3.2.3 その他の変数変換 106 |
| 3.2.4 曲面で囲まれる部分の体積 108 |
| 3.2.5 曲線の長さと囲む部分の面積 110 |
| 3.2.6 グリーンの定理 112 |
| 3.2.7 広義重積分 114 |
| 3.2節の問題 117 |
| 3.3 偏微分方程式 119 |
| 3.3.1 平面でのラプラス方程式 119 |
| 3.3.2 1次元熱方程式 122 |
| 3.3.3 1次元波動方程式 124 |
| 3.3.4 1次元シュレディンガー方程式 126 |
| 3.3節の問題 128 |
| 4 3変数の解析学入門 131 |
| 4.1 微分 131 |
| 4.1.1 勾配とナブラ 131 |
| 4.1.2 ヘッシアンとラプラシアン 134 |
| 4.1.3 極大・極小とラグランジュの不定乗数法 136 |
| 4.1.4 曲率とねじれ 138 |
| 4.1節の問題 140 |
| 4.2 積分 141 |
| 4.2.1 重積分と累次積分 141 |
| 4.2.2 座標変換 144 |
| 4.2.3 曲面積 146 |
| 4.2.4 ガウスの定理とストークスの定理 148 |
| 4.2節の問題 150 |
| 不定積分の公式集 152 |
| 解答 155 |
| 索引 163 |
| 1 1変数の解析学 1 |
| 1.1 いろいろな関数 1 |
| 1.1.1 基本的事柄の復習 1 |
|
| 22.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
日本化学会編
目次情報:
続きを見る
| 基礎編I実験・情報の基礎 目次 |
| 単位関係諸表(xuii) |
| 基本的な実験器具(xx) |
| 1 実験例 |
| 化学実験室に入ってから出るまで 1 |
| 1.1 水の分析 3 |
| 1.1.1 分析項目 5 |
| 1.1.2 精製水 6 |
| 1.1.3 水の採取 8 |
| 1.1.4 pH測定と緩衝液 9 |
| 1.1.5 酸塩基滴定 15 |
| 1.1.6 COD測定 酸化還元滴定 21 |
| 1.1.7 DO測定 酸化還元滴定 24 |
| 1.1.8 硬度測定 キレート滴定 27 |
| 1.1.9 塩化物イオン測定 銀滴定 31 |
| 1.1.10 電気伝導度 32 |
| 1.2 陽イオン・陰イオンの定性分析 34 |
| 1.2.1 陽イオンの定性分析 34 |
| 1.2.2 陰イオンの定性分析 37 |
| 1.3 無機塩の合成と定量分析 40 |
| 1.3.1 硫酸カリウムアルミニウム十二水和物(カリウムミョウバン)の合成 40 |
| 1.3.2 アルミニウムおよび硫酸イオンの定量 重量分析 41 |
| 1.4 無機錯体の合成 49 |
| 1.4.1 ペンタアンミンクロロコバルト(III)塩化物[CoCl(NH3)5]Cl2の合成 50 |
| 1.4.2 テトラアンミンカルボナトコバルト(III)硝酸塩[CoCO3(NH3)4]NO3の合成 51 |
| 1.4.3 金属錯体の可視-紫外吸収スペクトル 52 |
| 1.5 有機化合物の合成 53 |
| 1.5.1 酢酸エチルの合成 53 |
| 1.5.2 アセトアニリドのニトロ化 58 |
| 1.5.3 ニトロベンゼンの還元によるアニリンの合成 67 |
| 1.6 天然物からの分離 お茶からカフェエンの抽出 73 |
| 1.7 クロマトグラフィーによる分離 76 |
| 1.7.1 ガスクロマトグラフィー 76 |
| 1.7.2 液体クロマトグラフィー 83 |
| 1.8 モンテカルロ法によるパーコレションの計算実験 94 |
| 1.8.1 パーコレションとは 94 |
| 1.8.2 プログラミングの実際 95 |
| 1.8.3 コンパイルと実行 105 |
| 1.8.4 充?率とパーコレーションの確率分布 106 |
| 2 実験例に付随する基本操作 |
| 2.1 実験器具の取扱い 109 |
| 2.1.1 ガラス器具の取扱い 109 |
| 2.1.2 器具の連結・接合 117 |
| 2.1.3 ガラス器具以外の基礎器材 121 |
| 2.2 計量 124 |
| 2.2.1 質量 124 |
| 2.2.2 体積 128 |
| 2.2.3 濃度の表示 139 |
| 2.2.4 容量分析標準物質 141 |
| 2.3 溶解と撹拌 143 |
| 2.3.1 溶解 143 |
| 2.3.2 撹拌 144 |
| 2.4 加熱と冷却 147 |
| 2.4.1 加熟 147 |
| 2.4.2 冷却 152 |
| 2.5 濾過 154 |
| 2.5.1 濾紙,ガラス濾過器(フィルター)の規格 154 |
| 2.5.2 器具の選び方と組立て 155 |
| 2.5.3 自然濾過 157 |
| 2.5.4 吸引濾過 158 |
| 2.5.5 濾過操作の工夫 161 |
| 2.6 再結晶 162 |
| 2.6.1 再結晶溶媒の選択 163 |
| 2.6.2 再結晶の実験操作 溶解と結晶の生成 163 |
| 2.6.3 油状析出に対する対策 165 |
| 2.6.4 熱濾過 166 |
| 2.7 蒸留 167 |
| 2.7.1 蒸留の原理 167 |
| 2.7.2 常圧単蒸留 170 |
| 2.7.3 分別蒸留(精留) 175 |
| 2.7.4 固体蒸留 176 |
| 2.7.5 減圧蒸留 176 |
| 2.7.6 水蒸気蒸留 185 |
| 2.2.7 ロータリーエバポレーターによる溶媒の除去・濃縮 188 |
| 2.8 抽出 189 |
| 2.8.1 抽出の原理 189 |
| 2.8.2 分液漏斗を使う抽出操作 190 |
| 2.8.3 ソックスッレー抽出器を使う抽出 192 |
| 2.9 昇華 194 |
| 2.9.1 昇華の原理 194 |
| 2.9.2 昇華による分離・精製 195 |
| 2.10 不均一触媒による接触水素化 196 |
| 2.10.1 接触水素化反応 197 |
| 2.10.2 水素化触媒の調製 199 |
| 2.11 液体クロマトグラフィー 202 |
| 2.11.1 原理と分類 202 |
| 2.11.2 高速液体クロマトグラフ 205 |
| 2.11.3 吸着クロマトグラフィー 208 |
| 2.11.4 分配クロマトグラフィー 210 |
| 2.11.5 イオン交換クロマトグラフィー 211 |
| 2.11.6 サイズ排除クロマトグラフィー 215 |
| 2.11.7 平面クロマトグラフィー 217 |
| 2.12 物質の同定と純度の確認 223 |
| 2.12.1 同定と純度 223 |
| 2.12.2 融点測定 224 |
| 2.12.3 沸点測定 226 |
| 2.12.4 試料表示ラベル 227 |
| 2.12.5 微量物質の物性測定順序 227 |
| 2.13 ガラス細工 227 |
| 2.13.1 ガラスの種類 228 |
| 2.13.2 ガラス細工の道具 228 |
| 2.13.3 ガラス細工の素材準備 230 |
| 2.13.4 ガラス管を切る 230 |
| 2.13.5 ガラス管を引く 232 |
| 2.13.6 ガラス管をつなぐ・曲げる 234 |
| 2.13.7 置き継ぎ(真空配管) 237 |
| 2.13.8 アニーリング 239 |
| 2.13.9 安全作業の注意 239 |
| 2.14 コンピュータープログラム 240 |
| 2.14.1 プログラムと言語 240 |
| 2.14.2 プログラム作成環境 241 |
| 2.14.3 プログラムの作成 Fortranの約束事 244 |
| 2.14.4 プログラムの作成例 248 |
| 3 化学情報の流れ |
| 3.1 化学情報 255 |
| 3.2 化学情報の受信 インターネットの利用 259 |
| 3.2.1 化学情報の調査 259 |
| 3.2.2 新しいテーマの探索 262 |
| 3.2.3 あるテーマに関連する過去の文献の調査 270 |
| 3.2.4 ある化合物に関する調査 279 |
| 3.2.5 特定の化合物の物性データの調査 286 |
| 3.2.6 ある化合物の合成法や反応の調査 290 |
| 3.2.7 特定テーマの専門家および機関の調査 292 |
| 3.2.8 特定テーマについての研究動向の調査 296 |
| 3.2.9 ある著者の文献の探索 302 |
| 3.3 化学情報の発信 308 |
| 3.3.1 実験の記録 308 |
| 3.3.2 レポートと論文 312 |
| 3.3.3 口頭発表とポスター 316 |
| 3.3.4 PowerPointの使い方 321 |
| 3.3.5 学術論文の一例(日本語と英語) 333 |
| 3.3.6 学術論文の書き方 348 |
| 4 化学情報の基礎 |
| 4.1 物質の命名 355 |
| 4.1.1 物質命名の規則 355 |
| 4.1.2 元素名と元素記号 359 |
| 4.1.3 無機化合物の式と名称 360 |
| 4.1.4 有機化合物の構造式と名称 367 |
| 4.2 化学で使われる量の単位と表記法 378 |
| 4.2.1 国際単位系SI 379 |
| 4.2.2 非SI単位 383 |
| 4.2.3 単位の書き方 385 |
| 4.2.4 量の計算 387 |
| 4.2.5 物理・化学で使う量の用語 389 |
| 4.2.6 化学で使う定数 392 |
| 4.2.7 数学記号と数字 393 |
| 4.3 測定データの統計処理 398 |
| 4.3.1 測定と誤差 398 |
| 4.3.2 測定データとデータのばらつき 400 |
| 4.3.3 偶然誤差の処理 最小二乗法 403 |
| 4.3.4 パソコンソフトのおもな統計関数 408 |
| 4.4 パソコンによる図・表の作成 409 |
| 4.4.1 ChemDrawによる化学構造式の作成 410 |
| 4.4.2 WordまたはExcelによる表の作成 424 |
| 4.4.3 Excelによるグラフの作成 427 |
| 4.5 海外留学申請 429 |
| 4.5.1 海外留学計画 429 |
| 4.5.2 海外留学希望者への助言(英文) 433 |
| 4.6 研究評価 436 |
| 4.6.1 研究の社会性 436 |
| 4.6.2 研究の提案・申請そしてその審査 437 |
| 4.6.3 研究の質とピア審査 439 |
| 4.6.4 研究指標 440 |
| 4.6.5 研究プロジェクトの論理図 443 |
| 索引 445 |
| 基礎編I実験・情報の基礎 目次 |
| 単位関係諸表(xuii) |
| 基本的な実験器具(xx) |
|
| 23.
|
 図書
図書
|
勝部幸輝 [ほか] 編
| 出版情報: |
東京 : 東京化学同人, 1987.10-1988.4 冊 ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 24.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
編集委員長 小野昌孝
| 出版情報: |
東京 : 日本規格協会, 2008.6 359p ; 21cm |
| シリーズ名: |
JIS使い方シリーズ |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| まえがき |
| 1. 総論 |
| 1.1 接着剤,粘着剤及びシーリング材の生産と用途(三重野) 13 |
| 1.1.1 接着剤の生産と用途 13 |
| 1.1.2 粘着テープ類の生産と用途 17 |
| 1.1.3 シーリング材の生産と用途 21 |
| 1.2 接着剤の位置付け(若林) 22 |
| 1.2.1 接着及び接着剤の定義 22 |
| 1.2.2 粘着及び粘着剤の定義 24 |
| 1.2.3 シーリング及びシーリング材の定義 24 |
| 1.2.4 接着の理論 25 |
| 1.3 接着剤の構成(若林) 30 |
| 1.3.1 接着剤の主成分 31 |
| 1.3.2 溶剤 32 |
| 1.3.3 粘着付与剤 32 |
| 1.3.4 可塑剤 32 |
| 1.3.5 充てん剤 32 |
| 1.3.6 老化防止剤 33 |
| 1.3.7 接着促進剤 33 |
| 2. 接着剤 |
| 2.1 接着剤の種類と分類(若林) 37 |
| 2.1.1 主成分による分類 37 |
| 2.1.2 固化および硬化方法による分類 37 |
| 2.1.3 形態による分類 39 |
| 2.1.4 接着強さによる分類 40 |
| 2.1.5 その他の分類 40 |
| 2.2 系統別接着剤の概説(若林) 41 |
| 2.2.1 エラストマー系接着剤 41 |
| 2.2.2 合成樹脂系接着剤 45 |
| 2.2.3 混合系接着剤 56 |
| 2.3 機能別接着剤(柳津) 59 |
| 2.3.1 構造用接着剤 59 |
| 2.3.2 耐熱性接着剤 66 |
| 2.3.3 導電性接着剤 72 |
| 2.3.4 電気絶縁性接着剤 78 |
| 2.3.5 弾性接着剤 80 |
| 2.3.6 水中硬化接着 86 |
| 2.3.7 油面用接着剤 89 |
| 2.3.8 光硬化形接着剤 90 |
| 2.3.9 解体性接着剤 94 |
| 3. 接着剤の選び方 |
| 3.1 被着材(岩田・永田) 102 |
| 3.1.1 木材 103 |
| 3.1.2 金属類 120 |
| 3.1.3 プラスチック 121 |
| 3.1.4 加硫ゴム 126 |
| 3.1.5 ガラス 128 |
| 3.1.6 紙 129 |
| 3.1.7 繊維・皮革 129 |
| 3.1.8 その他(コンクリート,セラミックスなど) 131 |
| 3.1.9 その他 131 |
| 3.2 実用条件を調べる(永田) 132 |
| 3.2.1 外力 132 |
| 3.2.2 高温 132 |
| 3.2.3 低温 133 |
| 3.2.4 真空 133 |
| 3.2.5 クリーン性 134 |
| 3.2.6 透明性 135 |
| 3.2.7 導電性 135 |
| 3.2.8 伝熱性(熱伝導性) 136 |
| 3.2.9 絶縁性 136 |
| 3.2.10 難燃性 136 |
| 3.2.11 制振性 137 |
| 3.2.12 耐水・耐湿性 137 |
| 3.2.13 耐薬品性 138 |
| 3.2.14 耐衝撃性 138 |
| 3.2.15 応力緩和性 138 |
| 3.2.16 耐久性 139 |
| 3.2.17 分解性 139 |
| 3.2.18 その他 140 |
| 3.3 作業性を考える(永田) 140 |
| 3.3.1 塗布性 140 |
| 3.3.2 硬化性 141 |
| 3.4 コストほか(岩田) 142 |
| 4. 接着向上技術 |
| 4.1 表面処理(柳津) 149 |
| 4.1.1 表面とぬれ 149 |
| 4.1.2 金属の表面処理 151 |
| 4.1.3 プラスチックの表面処理 151 |
| 4.1.4 ゴム・エラストマーの表面処理 156 |
| 4.2 プライマー(柳津) 160 |
| 4.2.1 プライマーの目的 160 |
| 4.2.2 プライマーの種類 160 |
| 4.3 接着助剤(柳津) 161 |
| 4.3.1 シラン系カップリング剤 161 |
| 4.3.2 チタネート系カップリング剤 163 |
| 5. 接着剤の使い方 |
| 5.1 被着材の準備(永田) 171 |
| 5.1.1 表面処理 171 |
| 5.1.2 処理効果の確認 172 |
| 5.1.3 プレフィッティング(仮合せ) 173 |
| 5.2 接着剤の準備(永田) 174 |
| 5.2.1 かくはん 174 |
| 5.2.2 低粘化 174 |
| 5.2.3 充てん 174 |
| 5.2.4 2液性接着剤の準備 175 |
| 5.3 接着剤の適用(永田) 175 |
| 5.3.1 片面塗布 176 |
| 5.3.2 両面塗布 176 |
| 5.3.3 点塗布,部分塗布 176 |
| 5.4 張り合せ(永田) 177 |
| 5.5 接着硬化(永田) 177 |
| 5.5.1 圧力 177 |
| 5.5.2 加熱 178 |
| 5.6 養生(永田) 179 |
| 5.7 検査(永田) 180 |
| 5.7.1 購買仕様書の決定 180 |
| 5.7.2 社内品質認定試験 181 |
| 5.7.3 工場における材料管理 181 |
| 5.7.4 現場検査員の責務 181 |
| 5.7.5 工程内検査 181 |
| 6. 接合部(継手)の設計 |
| 6.1 接着接合部に働く応力の基本形(若林) 183 |
| 6.2 つき合せ接着(butt joint)(若林) 186 |
| 6.3 重ね継ぎ(lap joint)(若林) 187 |
| 6.4 アングル及びコーナーの接合(若林) 193 |
| 6.5 フランジの接合(若林) 194 |
| 6.6 接着接合部設計上の注意点(若林) 194 |
| 7. 製品(品質)規格にみる接着の実際 |
| 7.1 木質製品(岩田) 197 |
| 7.1.1 地球環境問題への木質製品の対応 197 |
| 7.1.2 合板 203 |
| 7.1.3 集成材 211 |
| 7.1.4 木製品における接着 219 |
| 7.1.5 WPCへの木質廃材リサイクル 233 |
| 7.2 建築(永田) 238 |
| 7.2.1 内装下地工事用接着剤 239 |
| 7.2.2 床仕上げ工事用接着剤 241 |
| 7.2.3 壁・天井仕上げ工事用接着剤 248 |
| 7.2.4 断熱材取付け工事用接着剤 250 |
| 7.2.5 内装陶磁器質タイルエ事用接着剤 256 |
| 7.2.6 外装タイル張り工事用接着剤 256 |
| 7.2.7 注入材料 259 |
| 7.2.8 その他 260 |
| 7.3 包装(葛良) 262 |
| 7.3.1 ラミネート包装材料 263 |
| 7.3.2 段ボール 281 |
| 7.3.3 紙器 283 |
| 7.3.4 紙袋 285 |
| 7.3.5 封緘材料 286 |
| 7.3.6 ラベル 286 |
| 7.4 電気・電子(永田・若林) 287 |
| 7.4.1 マグネット 287 |
| 7.4.2 スピーカ 290 |
| 7.4.3 液晶ディスプレイ 292 |
| 7.5 輸送(柳津) 293 |
| 7.5.1 ブレーキ 296 |
| 7.5.2 ダイレクトグレージング 306 |
| 7.5.3 接着絶縁レール 309 |
| 8. 環境側面 |
| 8.1 環境対応のための基礎知識(岩田) 319 |
| 8.1.1 世界の流れ 319 |
| 8.1.2 日本の流れ 322 |
| 8.2 環境性能基準(岩田) 324 |
| 9. 接着試験方法 |
| 9.1 規格体系(小野) 333 |
| 9.1.1 はじめに 333 |
| 9.1.2 国際規格 333 |
| 9.1.3 国家規格 334 |
| 9.1.4 地域規格 335 |
| 9.1.5 団体規格 336 |
| 9.2 接着剤の試験,測定方法(小野) 337 |
| 9.2.1 試験,測定方法の定義 337 |
| 9.2.2 試験,測定方法 339 |
| 付録 349 |
| 索引 357 |
| まえがき |
| 1. 総論 |
| 1.1 接着剤,粘着剤及びシーリング材の生産と用途(三重野) 13 |
|
| 25.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
足立勝重 [ほか] 著
| 出版情報: |
東京 : 朝倉書店, 2008.3 vii, 180p ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 第1章 機械加工概説 |
| 1.1 機械加工の位置づけ 1 |
| 1.2 除去加工の分類 3 |
| 第2章 切削加工 |
| 2.1 切削加工法概説 5 |
| 2.1.1 切削加工の分類 5 |
| 2.1.2 従来と最近の切削加工法の違い 7 |
| 2.2 切削加工の基礎 10 |
| 2.2.1 切削機構 10 |
| 2.2.2 切りくずの生成形態 12 |
| 2.2.3 2次元切削における切りくず生成 15 |
| 2.2.4 2次元切削における切りくず生成の力学 15 |
| 2.3 切削加工用工具 18 |
| 2.3.1 切削工具の基本形状 18 |
| 2.3.2 バイトの形状 18 |
| 2.3.3 フライスの形状 21 |
| 2.3.4 ドリルの形状 22 |
| 2.4 切削抵抗 24 |
| 2.4.1 バイトによる切削抵抗 24 |
| 2.4.2 切削抵抗の計算 26 |
| 2.4.3 フライスによる切削抵抗 28 |
| 2.4.4 ドリルによる切削抵抗 31 |
| 2.5 切削速度 34 |
| 2.5.1 切削速度と工具寿命 34 |
| 2.5.2 工具寿命と寿命予測 34 |
| 2.5.3 経済切削速度 37 |
| 2.5.4 切削温度 39 |
| 2.5.5 切削速度が「0」となる加工 40 |
| 2.6 切削工具材料 41 |
| 2.6.1 高速度工具鋼(ハイス) 43 |
| 2.6.2 超硬合金 43 |
| 2.6.3 サーメット 44 |
| 2.6.4 セラミックス 45 |
| 2.6.5 コーテッド工具 46 |
| 2.6.6 立方晶窒化ホウ素(CBN) 47 |
| 2.6.7 ダイヤモンド 48 |
| 2.6.8 工作物材質と切削工具材料 49 |
| 2.7 工具の損耗 50 |
| 2.7.1 工具損耗の種類 50 |
| 2.7.2 切削速度と工具損耗の関係 53 |
| 2.7.3 ホーニング 56 |
| 2.8 切削仕上げ面の性質 56 |
| 2.8.1 仕上げ面の幾何学的特性 57 |
| 2.8.2 仕上げ面の物理的・化学的特性 59 |
| 2.8.3 仕上げ加工の要点 61 |
| 2.9 切削油剤 61 |
| 2.9.1 切削油剤使用の目的と効果 61 |
| 2.9.2 切削油剤の種類 62 |
| 2.9.3 切削油剤の問題点 63 |
| 2.9.4 新しい切削油剤供給方法 64 |
| 2.10 特殊加工 67 |
| 2.10.1 高速切削 67 |
| 2.10.2 高温切削 68 |
| 2.10.3 低温切削 70 |
| 2.10.4 振動切削 71 |
| 2.10.5 弾性切削 72 |
| 第3章 研削加工 |
| 3.1 はじめに 75 |
| 3.2 研削加工の概要 76 |
| 3.2.1 研削のメカニズム 76 |
| 3.2.2 研削の特徴 77 |
| 3.2.3 研削抵抗 78 |
| 3.3 研削といし 79 |
| 3.3.1 といしの構成 79 |
| 3.3.2 と粒の種類 80 |
| 3.3.3 結合剤の種類 81 |
| 3.3.4 といしの形状 82 |
| 3.4 研削加工の形態 84 |
| 3.4.1 といしの自生作用 84 |
| 3.4.2 といしのトラブル 84 |
| 3.4.3 といしの調整 84 |
| 3.4.4 研削加工の種類 85 |
| 3.5 研削盤の種類 86 |
| 3.5.1 円筒研削盤 87 |
| 3.5.2 内面研削盤 88 |
| 3.5.3 芯なし研削盤 88 |
| 3.5.4 平面研削盤 89 |
| 3.6 最近の研削の動向 90 |
| 3.6.1 グラインディングセンター 90 |
| 3.6.2 高能率加工 90 |
| 3.6.3 新材料の加工 91 |
| 第4章 研磨加工 |
| 4.1 はじめに 93 |
| 4.2 強制加工と加圧加工 95 |
| 4.2.1 加圧加工の特性 96 |
| 4.2.2 加圧加工の機構 98 |
| 4.3 固定と粒による研磨加工 99 |
| 4.3.1 ホーニング加工 99 |
| 4.3.2 超仕上げ加工 106 |
| 4.4 半固定と粒による加工 112 |
| 4.4.1 研磨布紙加工 112 |
| 4.4.2 バレル加工 117 |
| 4.5 遊離と粒による加工 121 |
| 4.5.1 噴射加工 121 |
| 4.5.2 バフ研磨 122 |
| 4.5.3 ラッピング 124 |
| 4.5.4 ポリッシング 130 |
| 第5章 特殊加工 |
| 5.1 はじめに 133 |
| 5.2 電気・熱的加工法 133 |
| 5.2.1 放電加工 133 |
| 5.2.2 電子ビーム加工 135 |
| 5.2.3 レーザー加工 135 |
| 5.2.4 プラズマジェット加工 139 |
| 5.3 電気・化学的加工法 140 |
| 5.3.1 電解加工 140 |
| 5.3.2 電解研削 140 |
| 5.3.3 電解研磨 141 |
| 5.4 化学的加工法 142 |
| 5.4.1 化学研磨 142 |
| 5.4.2 腐食加工 142 |
| 第6章 機械加工システムの自動化 |
| 6.1 はじめに 144 |
| 6.2 機械加工システムの構成とその発展 145 |
| 6.3 工作機械の自動化 146 |
| 6.3.1 工作機械の発達の歴史 146 |
| 6.3.2 NC工作機械 148 |
| 6.3.3 NCプログラミング 150 |
| 6.3.4 マシニングセンター 154 |
| 6.3.5 適応制御工作機械 155 |
| 6.3.6 CNC,DNC 155 |
| 6.4 マテリアルハンドリングの自動化 157 |
| 6.4.1 マテリアルハンドリング 157 |
| 6.4.2 産業用ロボット 158 |
| 6.4.3 無人搬送車 160 |
| 6.4.4 自動倉庫 162 |
| 6.5 FMC,FMS,FA 163 |
| 演習問題解答とヒント 167 |
| 索引 172 |
| 第1章 機械加工概説 |
| 1.1 機械加工の位置づけ 1 |
| 1.2 除去加工の分類 3 |
|
| 26.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
太田健一郎 [ほか] 著
| 出版情報: |
東京 : 朝倉書店, 2002.9 viii, 218p ; 21cm |
| シリーズ名: |
応用化学シリーズ ; 1 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 1. 酸・アルカリ工業 〔太田健一郎〕 1 |
| 1.1 酸の工業 3 |
| 1.1.1 硫酸 3 |
| 1.1.2 塩酸 9 |
| 1.1.3 硝酸 13 |
| 1.1.4 リン酸 15 |
| 1.2 アルカリ工業 19 |
| 1.2.1 水酸化ナトリウム 19 |
| 1.2.2 アンモニア 25 |
| 2 電気化学とその工業 〔仁科 辰夫〕 30 |
| 2.1 電気化学の基礎的事項 30 |
| 2.1.1 電気化学系とは 30 |
| 2.1.2 平衡電気化学 32 |
| 2.1.3 電極反応速度 34 |
| 2.2 電池工業 37 |
| 2.2.1 電気化学エネルギー変換 37 |
| 2.2.2 電池活物質の化学 38 |
| 2.2.3 1次電池 42 |
| 2.2.4 2次電池 46 |
| 2.2.5 燃料電池 54 |
| 2.3 電気化学表面処理 59 |
| 2.3.1 表面処理の目的と用途 59 |
| 2.3.2 腐食の種類 59 |
| 2.3.3 腐食の平衡論 62 |
| 2.3.4 腐食の速度論 63 |
| 2.3.5 防食技術 66 |
| 2.3.6 表面の装飾 70 |
| 2.3.7 表面の耐食性・耐摩耗性処理 76 |
| 2.3.8 表面の高機能化 78 |
| 3. 金属工業化学 〔佐々木 健〕 85 |
| 3.1 金属工業 85 |
| 3.1.1 金属の利用 85 |
| 3.1.2 金属工業 85 |
| 3.2 金属製錬の化学 86 |
| 3.2.1 金属の製錬 86 |
| 3.2.2 金属製錬反応 87 |
| 3.2.3 金属の精製 98 |
| 3.2.4 電解製錬 101 |
| 3.3 金属の製造 106 |
| 3.3.1 鉄 106 |
| 3.3.2 銅 110 |
| 3.3.3 鉛 111 |
| 3.3.4 亜鉛 111 |
| 3.3.5 アルミニウム 112 |
| 3.3.6 チタン 113 |
| 3.3.7 希土類元素 113 |
| 3.4 金属のリサイクル 115 |
| 3.4.1 リサイクルの背景 115 |
| 3.4.2 金属リサイクルの現状 116 |
| 3.4.3 金属のリサイクルと金属工業 118 |
| 4. 無機合成 〔三宅 通博〕 121 |
| 4.1 無機合成の基礎 122 |
| 4.1.1 基本化学反応 122 |
| 4.1.2 平衡状態図 124 |
| 4.2 固相からの合成 125 |
| 4.2.1 固相反応法 125 |
| 4.2.2 熱分解法 126 |
| 4.3 液相からの合成 127 |
| 4.3.1 水溶液法 128 |
| 4.3.2 ゾルーゲル法 131 |
| 4.3.3 水熱法 134 |
| 4.3.4 フラックス法 136 |
| 4.3.5 溶融法 137 |
| 4.3.6 膜作製法 139 |
| 4.4 気相からの合成 141 |
| 4.4.1 化学蒸着法 141 |
| 4.4.2 化学輸送法 142 |
| 4.4.3 膜作製法 143 |
| 4.5 高温超高圧下での合成 145 |
| 4.5.1 静的超高圧発生法 146 |
| 4.5.2 ダイヤモンドと立方晶窒化ホウ素の合成 146 |
| 4.6 ソフト化学法による合成 148 |
| 4.6.1 イオン交換法 149 |
| 4.6.2 インターカレーション法 151 |
| 5. 窒業と伝統セラミックス 〔佐々木義典〕 155 |
| 5.1 セメント 155 |
| 5.1.1 焼成炉 : ロータリーキルン 155 |
| 5.1.2 焼成反応とプロセス 156 |
| 5.1.3 排熱の利用 : サスペンションプレヒーター 160 |
| 5.1.4 セメントの水和と硬化 161 |
| 5.1.5 種類と用途 164 |
| 5.1.6 コンクリート 168 |
| 5.1.7 鉄筋コンクリート内での化学反応 : 崩壊のプロセス 169 |
| 5.2 ガラス 173 |
| 5.2.1 ガラス状態 173 |
| 5.2.2 ケイ酸イオン 176 |
| 5.2.3 ガラスの構造 178 |
| 5.2.4 製造法 181 |
| 5.2.5 ケイ酸系ガラスの性質と用途 185 |
| 5.3 ほうろう, 陶磁器, 耐火物 190 |
| 5.3.1 ほうろう 190 |
| 5.3.2 陶磁器 193 |
| 5.3.3 耐火物 197 |
| 演習問題解答 205 |
| 付表 212 |
| 索引 215 |
| 1. 酸・アルカリ工業 〔太田健一郎〕 1 |
| 1.1 酸の工業 3 |
| 1.1.1 硫酸 3 |
|
| 27.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
井上恭著
| 出版情報: |
東京 : 森北出版, 2008.2 vi, 185p ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 第1章 光子の存在 1 |
| 1.1 空洞放射 2 |
| 1.1.1 レイリー・ジーンズの公式 2 |
| 1.1.2 ブランクの仮説 7 |
| 1.2 光電効果 11 |
| 1.3 コンプトン効果 13 |
| 1.3.1 X線の散乱現象 13 |
| 1.3.2 光子の運動量 14 |
| 1.3.3 光子と電子の衝突 15 |
| 1.4 粒子性と波動性 16 |
| 第2章 量子光学の基礎 17 |
| 2.1 量子力学的考え方 17 |
| 2.1.1 光子の出射状態 17 |
| 2.1.2 光子の偏波状態 21 |
| 2.2 量子状態の記述法 24 |
| 2.2.1 ヒルベルト空間 24 |
| 2.2.2 ケット状態 27 |
| 2.2.3 物理量演算子 28 |
| 2.2.4 固有値・固有状態 28 |
| 2.2.5 エルミート演算子 29 |
| 2.2.6 固有関数の直交性 31 |
| 2.2.7 正規直交完全系 32 |
| 2.2.8 重ね合わせ状態の表記法 33 |
| 2.2.9 観測量の平均値 36 |
| 2.2.10 観測量が連続的である場合 36 |
| 2.3 不確定性原理 39 |
| 2.3.1 二つの物理量に対する確定状態と確率状態 39 |
| 2.3.2 二つの物理量のゆらぎ 40 |
| 2.4 状態の時間変化 42 |
| 2.4.1 シュレディンガー方程式 42 |
| 2.4.2 ユニタリー変換 43 |
| 2.4.3 シュレディンガー表示とハイゼンベルグ表示 44 |
| 演習問題 45 |
| 第3章 電磁場の量子化 46 |
| 3.1 正準量子化 46 |
| 3.2 調和振動子 47 |
| 3.2.1 古典的エネルギー 48 |
| 3.2.2 エネルギー演算子 49 |
| 3.2.3 生成・消滅演算子 50 |
| 3.2.4 エネルギー固有値 51 |
| 3.3 電磁場の量子化 52 |
| 3.3.1 古典的エネルギー 52 |
| 3.3.2 電磁場の量子化 53 |
| 演習問題 55 |
| 第4章 コヒーレント状態とスクイズド状態 56 |
| 4.1 コヒーレント状態 56 |
| 4.1.1 コヒーレント状態とは 56 |
| 4.1.2 単一周波数光はコヒーレント状態 57 |
| 4.1.3 平均光子数および光子数ゆらぎ 58 |
| 4.1.4 振幅ゆらぎ 60 |
| 4.1.5 コヒーレント状態の表示 63 |
| 4.1.6 量子雑音と古典雑音 64 |
| 4.2 スクイズド状態 68 |
| 4.2.1 直交位相スクイズド状態 68 |
| 4.2.2 直交位相スクイズド状態の発生方法 73 |
| 4.2.3 光子数スクイズド状態 74 |
| 4.2.4 損失の影響 75 |
| 演習問題 79 |
| 第5章 自然放出 80 |
| 5.1 誘導吸収と誘導放出 80 |
| 5.1.1 物質系のエネルギー準位 80 |
| 5.1.2 物質系の基本方程式 81 |
| 5.1.3 共鳴過程 84 |
| 5.2 自然放出 87 |
| 5.2.1 光と物質系の量子状態 88 |
| 5.2.2 時間発展 89 |
| 5.2.3 遷移確率 90 |
| 5.3 自然放出光パワー 93 |
| 演習問題 95 |
| 第6章 光パラメトリック増幅 97 |
| 6.1 光非線形性 97 |
| 6.2 四光波混合 98 |
| 6.2.1 非線形分極 98 |
| 6.2.2 非線形波動方程式 99 |
| 6.2.3 位相整合 104 |
| 6.3 スクイズド状態生成 106 |
| 6.4 パラメトリック増幅における自然放出 107 |
| 6.5 2次パラメトリック増幅 111 |
| 演習問題 113 |
| 第7章 単一光子の量子状態 114 |
| 7.1 1光子の重ね合わせ状態 114 |
| 7.2 1光子の不確定性 116 |
| 7.2.1 物理量演算子の表し方 116 |
| 7.2.2 不確定性 118 |
| 7.3 偏波の場合 121 |
| 7.3.1 物理量演算子の表式 121 |
| 7.3.2 不確定性 121 |
| 演習問題 124 |
| 第8章 光子の干渉 125 |
| 8.1 ヤングの干渉 125 |
| 8.2 ハンブリー・ブラウン・ツイストの干渉 127 |
| 8.2.1 電磁波の場合 128 |
| 8.2.2 光子の場合 129 |
| 8.2.3 古典と量子の違い 130 |
| 8.3 ビームスプリッタでの2光子干渉 131 |
| 8.4 パラメトリック自然放出光の2光子干渉 136 |
| 8.4.1 計測系の構成 136 |
| 8.4.2 電磁波の場合 137 |
| 8.4.3 光子の場合 138 |
| 8.4.4 古典と量子の違い 140 |
| 演習問題 141 |
| 第9章 量子もつれ 142 |
| 9.1 量子もつれ状態 142 |
| 9.1.1 量子もつれとは 142 |
| 9.1.2 もつれ状態の測定 148 |
| 9.1.3 量子もつれにまつわる議論 150 |
| 9.2 量子もつれ発生法 153 |
| 9.2.1 2次パラメトリック過程の角度位相整合による発生法 153 |
| 9.2.2 時間位置もつれ発生法 154 |
| 9.2.3 単一光子とビームスプリッタによる生成法 156 |
| 演習問題 158 |
| 第10章 量子情報通信 159 |
| 10.1 量子暗号 159 |
| 10.1.1 量子鍵配送 159 |
| 10.1.2 BB84プロトコル 161 |
| 10.1.3 その他のプロトコル 164 |
| 10.2 量子テレボーテーション 165 |
| 10.2.1 重ね合わせ状態の転送 165 |
| 10.2.2 定式的取り扱い 166 |
| 10.2.3 ベル測定について 168 |
| 10.3 量子コンピュータ 169 |
| 10.3.1 数の表し方 170 |
| 10.3.2 重ね合わせの並列処理 170 |
| 10.3.3 適用領域 172 |
| 10.3.4 実現に向けて 172 |
| 演習問題 173 |
| 問題の解答 174 |
| 索引 184 |
| 第1章 光子の存在 1 |
| 1.1 空洞放射 2 |
| 1.1.1 レイリー・ジーンズの公式 2 |
|
| 28.
|
 図書
図書
|
スミルノフ [著] ; 彌永昌吉 [ほか] 飜訳監修 ; 福原満洲雄訳者代表
| 出版情報: |
東京 : 共立出版, 1958.5-1962.10 12冊 ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 29.
|
 図書
図書
|
日本規格協会編集
目次情報:
続きを見る
| 用語 |
| 資格及び認証 |
| 金属材料の試験 |
| 鉄鋼材料の試験 |
| 原材料 |
| 機械構造用炭素鋼・合金鋼 |
| 特殊用途鋼 |
| クラッド鋼 |
| 鋳鍛造品 |
| 電気用材料 |
| 関連 |
| 参考 |
| 棒鋼・形鋼・鋼板・鋼帯 |
| 鋼管 |
| 線材・線材二次製品 |
概要:
用語/資格及び認証/金属材料の試験/鉄鋼材料の試験/原材料/機械構造用炭素鋼・合金鋼/特殊用途鋼(ステレンス鋼・耐熱鋼・超合金、工具鋼、ばね鋼、快削鋼、軸受鋼)/クラッド鋼/鋳鍛造品(鍛鋼金、鋳鋼品、鋳鉄品)/電気用材料/参考。<br />
…
棒鋼・形鋼・鋼板・鋼帯(構造用、一般加工用、圧力容器用、厚さ方向特性、寸法・質量・許容差、土木・建築用、鉄道用)/鋼管(配管用、熱伝達用、構造用、特殊用途鋼管・合金管)/線材・線材二次製品/参考。
続きを見る
|
| 30.
|
 図書
図書
|
河田敬義著
|
| 31.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
土木学会編
目次情報:
続きを見る
| 【Ⅲ編 動的解析の手法】 |
| 1. 数値計算法の種類と特徴 3 |
| 1.1 概説 3 |
| 1.2 分布質量系と集中質量系 4 |
| 1.2.1 分布質量系 4 |
| 1.2.2 集中質量系 7 |
| 1.3 有限要素法 9 |
| 1.3.1 仮想仕事の原理による運動方程式の定式化 9 |
| 1.3.2 各種の有限要素 13 |
| 1.4 差分法 16 |
| 1.4.1 差分近似 17 |
| 1.4.2 弾性体の運動方程式の差分化 19 |
| 1.4.3 境界条件 21 |
| 1.4.4 安定性 22 |
| 1.4.5 任意形状境界の処理 23 |
| 1.4.6 仮想境界の処理 24 |
| 1.5 境界要素法 25 |
| 1.5.1 積分変換法 25 |
| 1.5.2 時間ステップ法 30 |
| 1.5.3 数値解析法 33 |
| 2. 基本的な応答計算法 38 |
| 2.1 概説 38 |
| 2.2 固有値解析 38 |
| 2.2.1 固有値問題の定式化 38 |
| 2.2.2 実行列の固有値計算法 41 |
| 2.2.3 複素行列の固有値計算法 41 |
| 2.3 モード解析法 43 |
| 2.3.1 離散系の場合 43 |
| 2.3.2 連続系の場合 45 |
| 2.4 運動方程式の直接積分法 47 |
| 2.4.1 中央差分法 48 |
| 2.4.2 陽解法と陰解法 49 |
| 2.4.3 標準形による積分計算法 51 |
| 2.4.4 運動方程式の陰解法 54 |
| 2.4.5 直接積分法に関するまとめ 57 |
| 2.5 振動数領域での解析 57 |
| 2.5.1 単位衝撃応答と周波数応答関数 58 |
| 2.5.2 任意の外乱が作用するときの応答 59 |
| 2.5.3 フーリエスペクトル 59 |
| 2.5.4 高速フーリエ変換(FFT) 61 |
| 2.6 不規則応答解析 65 |
| 2.6.1 不規則応答解析の基礎 65 |
| 2.6.2 パワースペクトルとスペクトル密度関数 66 |
| 2.6.3 自己相関関数とパワースペクトル密度関数 67 |
| 2.6.4 外乱と応答のパワースペクトル密度関数の関係 69 |
| 2.6.5 相互相関関数と振動系の応答 69 |
| 2.6.6 物理スペクトル 70 |
| 2.7 応答スペクトル 71 |
| 2.7.1 線形応答スペクトル 71 |
| 2.7.2 非弾性応答スペクトル 73 |
| 3. 非線形問題 75 |
| 3.1 非線形振動の概要 75 |
| 3.2 等価線形化法 76 |
| 3.2.1 等価線形化法の背景 76 |
| 3.2.2 Krylov-Bogoljubovの定常強制振動解 78 |
| 3.2.3 任意の粘弾性復元力をもつ振動系の減衰定数 80 |
| 3.2.4 任意の履歴型復元力をもつ振動系の等価粘性減衰定数 82 |
| 3.2.5 等価線形ばねの定義の違いが応答に及ぼす影響 88 |
| 3.2.6 等価線形化法の具体的手順 90 |
| 3.2.7 等価線形化法における減衰定数の振動論的な意味 92 |
| 3.2.8 等価線形化法の妥当性についての検討例 95 |
| 3.3 材料非線形を伴う動的解析 99 |
| 3.3.1 非線形弾性 99 |
| 3.3.2 弾塑性および粘弾性 102 |
| 3.3.3 クラックもしくは損傷による剛性変化 105 |
| 3.3.4 ガタ・剥離・接触・滑り 106 |
| 3.3.5 材料非線形性を有する運動方程式の解法 106 |
| 3.4 有限変形を伴う動的解析 108 |
| 3.4.1 Lagrange法とEuler法 108 |
| 3.4.2 全Lagrange法と更新Lagrange法 109 |
| 4. 地盤-構造物系の動的解析 111 |
| 4.1 動的相互作用の定式化 111 |
| 4.1.1 相対座標による支配方程式 112 |
| 4.1.2 絶対座標による支配方程式 115 |
| 4.2 有限要素法による解析 117 |
| 4.2.1 仮想境界の境界条件の設定 117 |
| 4.2.2 地盤-構造物相互作用系の全体解析 121 |
| 4.2.3 すべり・剥離を生じる地盤-構造物系の解析 123 |
| 4.3 境界要素法による解析 126 |
| 4.3.1 直接法 126 |
| 4.3.2 間接法 129 |
| 4.4 有限要素法と境界要素法のハイブリッド解析 131 |
| 4.4.1 境界法 132 |
| 4.4.2 容積法(変位グリーン関数法) 134 |
| 4.5 全体解析法と動的サブストラクチャー解析法 138 |
| 4.5.1 全体解析法 140 |
| 4.5.2 動的サブストラクチャー解析法 145 |
| 文献 152 |
| 【Ⅳ編 地盤と基礎の動的解析】 |
| 1. 入力地震動 165 |
| 1.1 地震基盤 165 |
| 1.1.1 地震基盤の考え方 165 |
| 1.1.2 地震基盤の設定例 166 |
| 1.1.3 地震基盤への入射波およびそのスペクトル 168 |
| 1.2 地中の震動分布 171 |
| 1.2.1 地中震動の観測例 171 |
| 1.2.2 波動理論による地中震動分布特性 178 |
| 1.3 地表における地震動の強さ 181 |
| 1.3.1 地震動の最大値と応答スペクトル 181 |
| 1.3.2 Far-fieldにおける地震動の最大値 183 |
| 1.3.3 Near-fieldにおける地震動の最大値 184 |
| 1.4 地震波の伝播と位相差 186 |
| 1.4.1 地盤震動の位相差 186 |
| 1.4.2 アレー観測の例 189 |
| 1.4.3 耐震設計における地震動位相差の取扱い 192 |
| 2. 地盤・土構造物の震動解析 194 |
| 2.1 水平多層地盤の動的応答解析法と地震時挙動 194 |
| 2.1.1 伝達マトリックスによるSH波の重複反射解析 195 |
| 2.1.2 P波とSV波を含む場合の重複反射理論 198 |
| 2.1.3 表面波に対する解析 198 |
| 2.1.4 等価線形化法による1次元地盤震動解析 199 |
| 2.1.5 成層地盤の地震応答特性に影響する要因 201 |
| 2.1.6 成層地盤の非線形応答解析例 202 |
| 2.1.7 表層地盤の非線形増幅特性のモデル化 204 |
| 2.2 不整形地盤の震動解析 206 |
| 2.2.1 震害と不整形性の関係 206 |
| 2.2.2 地震観測例よりみた不整形地盤の特徴 207 |
| 2.2.3 解析手法の特徴と解析事例 212 |
| 2.2.4 不整形地盤のモデル化の注意事項 220 |
| 2.3 土構造物の震動解析 223 |
| 2.3.1 典型的な振動モード 223 |
| 2.3.2 等価逸散減衰 227 |
| 2.3.3 動的応答特性 228 |
| 3. 地震による地盤の破壊と予測 230 |
| 3.1 地盤の破壊の種類 230 |
| 3.2 砂地盤の液状化 230 |
| 3.2.1 予測法の種類 230 |
| 3.2.2 液状化発生の予測方法 231 |
| 3.2.3 動的解析による液状化発生の予測方法 232 |
| 3.2.4 有効応力解析プログラムの例 235 |
| 3.2.5 有効応力解析および全応力解析による液状化予測例 236 |
| 3.3 斜面崩壊 238 |
| 3.3.1 予測方法の種類 238 |
| 3.3.2 ある地域内の複数の斜面に対する予測方法 238 |
| 3.3.3 個々の斜面に対する予測方法 239 |
| 3.3.4 震度法によるすべりの安定性予測 239 |
| 3.3.5 すべりに対する安定性の詳細な解析方法(その1,土塊全体の安全率を求める方法) 240 |
| 3.3.6 すべりに対する安定性の詳細な解析方法(その2,局所安全率を求める方法) 241 |
| 3.3.7 変形量を解析するための簡便法 242 |
| 3.3.8 変形量を詳細に解析する方法 244 |
| 3.3.9 斜面崩壊の解析例 245 |
| 4. 地盤と構造物基礎の動的相互作用解析 248 |
| 4.1 動的相互作用 248 |
| 4.1.1 地盤と構造物における観測記録 248 |
| 4.1.2 動的相互作用の定義と動力学的特性 250 |
| 4.1.3 簡単な歴史的流れ 252 |
| 4.2 解析モデルと考え方 254 |
| 4.2.1 解析モデルの基本 254 |
| 4.2.2 線形モデルと非線形モデル 256 |
| 4.2.3 複素剛性(インピーダンス)の特性 257 |
| 4.2.4 複素剛性と付加質量 259 |
| 4.2.5 振動数に依存しない複素剛性の仮定 260 |
| 4.2.6 有効地震動の特性 261 |
| 4.3 動的相互作用の効果 262 |
| 4.4 設計指針と動的相互作用 266 |
| 4.4.1 設計指針の現状 266 |
| 4.4.2 ATC-3における考え方 266 |
| 4.4.3 簡便な解析方法1 267 |
| 4.4.4 簡便な解析方法2 270 |
| 4.4.5 杭基礎の動的相互作用 271 |
| 4.4.6 基礎の設計 272 |
| 4.5 具体的解析例と略算式 273 |
| 4.5.1 根入れ効果と有効地震動の効果 273 |
| 4.5.2 複素剛性 276 |
| 4.5.3 有効地震動 281 |
| 文献 283 |
| 【Ⅲ編 動的解析の手法】 |
| 1. 数値計算法の種類と特徴 3 |
| 1.1 概説 3 |
|
| 32.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
日本機械学会編
目次情報:
続きを見る
| 機械設計と機械要素・トライボロジー |
| 機械研究の歴史と機械要素 1 |
| 機械を取り巻く学問 1 |
| 機械の設計と設計者の心構え l |
| 展望 2 |
| 第Ⅰ部 機械要素 |
| 第1章 機械の機能と機械要素 |
| 1・1 機械の構造と機械要素 5 |
| 1・2 機械要素の機能 5 |
| 1・3 機械要素への要求 6 |
| 第2章 締結要素 |
| 2・1 ねじ 8 |
| 2・1・1 ねじの用途 8 |
| 2・1・2 ねじに関するおもな用語とその意味 8 |
| 2・1・3 ねじの力学 8 |
| 2・1・4 トルク法によるねじの締付け 10 |
| 2・1・5 ねじの緩み 11 |
| 2・1・6 ねじの強度設計 12 |
| 2・1・7 ねじ締結体の強度設計 13 |
| 2・1・8 ねじの強度区分 14 |
| 2・2 キー,スプライン 14 |
| 2・2・1 キー 14 |
| 2・2・2 スプライン 16 |
| 2・3 止め輪 17 |
| 2・4 ピン,コッタ 19 |
| 2・4・1 ピン 19 |
| 2・4・2 コッタ 20 |
| 2・5 溶接継手,接着継手 20 |
| 2・5・1 溶接継手 20 |
| 2・5・2 接着継手 21 |
| 2・6 リベット 23 |
| 2・6・1 リベットの種類 23 |
| 2・6・2 リベット継手の種類 23 |
| 2・6・3 リベット継手の設計 23 |
| 2・7 焼きばめ,冷やしばめ 25 |
| 2・7・1 締結力 25 |
| 2・7・2 締結体の強度 26 |
| 2・8 スナップフィッ卜 26 |
| 2・8・1 スナップフィット 26 |
| 2・8・2 スナップフィットの利点 26 |
| 2・8・3 スナップフィッ卜の材質 27 |
| 2・8・4 スナップフィットの形状 27 |
| 2・8・5 スナップフィットの分類 27 |
| 2・8・6 スナップフィッ卜形状設計の要領 28 |
| 2・8・7 スナップフィットの形状設計 29 |
| 第3章 軸・軸受要素 |
| 3・1 軸 31 |
| 3・1・1 軸の材料 31 |
| 3・1・2 軸の応力 31 |
| 3・1・3 軸の変形 31 |
| 3・1・4 軸の設計式 31 |
| 3・1・5 キー溝付き軸の設計 33 |
| 3・1・6 軸の危険速度 33 |
| 3・1・7 各種の軸 34 |
| 3・2 滑り軸受 36 |
| 3・2・1 滑り軸受の種類と選定 36 |
| 3・2・2 静荷重用動圧滑り軸受 36 |
| 3・2・3 動荷重用動圧滑り軸受 41 |
| 3・2・4 静圧軸受 43 |
| 3・2・5 気体軸受 44 |
| 3・2・6 磁気軸受 45 |
| 3・2・7 そのほかの軸受 46 |
| 3・3 転がり軸受 48 |
| 3・3・1 転がり軸受の種類と選択 48 |
| 3・3・2 回転用転がり軸受 48 |
| 3・3・3 直動玉軸受 52 |
| 3・4 案内 54 |
| 3・4・1 滑り案内 54 |
| 3・4・2 転がり案内 55 |
| 3・5 シール 57 |
| 3・5・1 シールの種類と選択 57 |
| 3・5・2 静止シール 57 |
| 3・5・3 接触式運動用シール 57 |
| 3・5・4 非接触式シール 65 |
| 3・6 軸継手 67 |
| 3・6・1 軸継手の種類 67 |
| 3・6・2 フランジ形固定軸継手 67 |
| 3・6・3 フランジ形たわみ軸継手 68 |
| 3・6・4 オールダム軸継手 68 |
| 3・6・5 歯車形軸継手 68 |
| 3・6・6 ローラチェーン軸継手 68 |
| 3・6・7 ゴム軸継手 69 |
| 3・6・8 金属ばね軸継手 69 |
| 3・6・9 摩擦締結軸継手 69 |
| 3・6・10 フック形自在軸継手 69 |
| 3・6・11 こま形自在軸継手 70 |
| 3・6・12 等速形自在軸継手 70 |
| 第4章 伝動要素 |
| 4・1 歯車 72 |
| 4・1・1 歯車の種類 72 |
| 4・1・2 インボリュート円筒歯車 72 |
| 4・1・3 かざ歯車,ハイポイドギヤ 78 |
| 4・1・4 ウォームギヤ 79 |
| 4・1・5 その他の歯車 81 |
| 4・2 歯車伝動装置 82 |
| 4・2・1 平行軸歯車装置 82 |
| 4・2・2 遊星歯車装置 89 |
| 4・2・3 かさ歯車装置 91 |
| 4・2・4 ウォーム減速装置 92 |
| 4・2・5 内接式跨星歯車減速機 93 |
| 4・2・6 波動歯車装置 94 |
| 4・2・7 歯車装置の潤滑 94 |
| 4・3 ベルト伝動装置 95 |
| 4・3・1 平ベルト伝動 96 |
| 4・3・2 Vベルト伝動 97 |
| 4・3・3 歯付ベルト伝動 99 |
| 4・3・4 そのほかのベルトによる伝動 101 |
| 4・4 チェーン伝動装置 101 |
| 4・4・1 ローラチェーン伝動 101 |
| 4・4・2 サイレントチェーン伝動 104 |
| 4・5 機械式無段変速機 104 |
| 4・5・1 エラストマベルトテンションドライブ 104 |
| 4・5・2 チェーンテンションドライブ 104 |
| 4・5・3 乾式複合ベルトテンションドライブ 104 |
| 4・5・4 スチールベルトコンプレッションドライブ 104 |
| 4・5・5 トラクションドライブ 105 |
| 4・6 トラクションドライブ式変速機 107 |
| 4・6・1 遊星ローラ変速機 107 |
| 4・6・2 ウェッジローラ減速機 107 |
| 4・7 ねじ伝動装置 108 |
| 4・7・1 送りねじの一般的特徴 108 |
| 4・7・2 各種ねじ伝動装置 108 |
| 4・8 クラッチ 110 |
| 4・8・1 クラッチの種類 110 |
| 4・8・2 かみあいクラッチ 111 |
| 4・8・3 摩擦クラッチ 111 |
| 4・8・4 自動クラッチ 113 |
| 4・9 ブレーキ 114 |
| 4・9・1 ブレーキの種類 114 |
| 4・9・2 摩擦ブレーキ 114 |
| 4・9・3 そのほかの制動装置 115 |
| 4・10 フライホイール 116 |
| 4・10・1 フライホイールの機能 116 |
| 4・10・2 エネルギー貯蔵用フライホイール 116 |
| 4・10・3 回転軸系の平滑化に用いるフライホイール 116 |
| 4・10・4 フライホールの強度 117 |
| 第5章 運動変換要素 |
| 5・1 リンク機構 119 |
| 5・1・1 リンク機構の構成 119 |
| 5・1・2 剛体の運動の表現 119 |
| 5・1・3 剛体の速度と加速度 119 |
| 5・1・4 機構の解析 120 |
| 5・1・5 機構の総合 122 |
| 5・2 カム機構 123 |
| 5・2・1 カム概説 123 |
| 5・2・2 カムの種類と用途 123 |
| 5・2・3 カム曲線 123 |
| 5・2・4 カムの特性値とその計算 126 |
| 5・2・5 カムの設計と加工 127 |
| 5・2・6 動特性を考慮したカム機構の設計 129 |
| 5・3 間欠運動機構 129 |
| 5・3・1 間欠運動の概要 129 |
| 5・3・2 ゼネバ機構 129 |
| 5・3・3 間欠歯車装置 130 |
| 5・3・4 カムによる間欠運動装置 130 |
| 5・3・5 つめ車 131 |
| 5・3・6 リンクによる間欠運動装置 131 |
| 5・4 不等速比歯車 132 |
| 第6章 緩衝・制振要素 |
| 6・1 ばね 133 |
| 6・2 緩衝器およびダンバ 135 |
| 6・2・1 緩衝器とダンパの機能 135 |
| 6・2・2 油圧緩衝器 135 |
| 6・2・3 摩擦緩衝器 136 |
| 6・2・4 ばね緩衝器 136 |
| 6・2・5 油圧ダンパ 136 |
| 6・2・6 粘性ダンパ 136 |
| 6・2・7 摩擦ダンパ 137 |
| 6・2・8 電磁ダンパ 137 |
| 第7章 配管要素 |
| 7・1 管と配管 138 |
| 7・1・1 管の種類 138 |
| 7・1・2 鋼管の外径寸法と肉厚 139 |
| 7・1・3 配管 139 |
| 7・2 管継手 139 |
| 7・2・1 管継手の種類 139 |
| 7・2・2 ねじ込み式管継手 139 |
| 7・2・3 メカニカル式管継手(くい込み式,パッキン式) 139 |
| 7・2・4 フランジ式管継手 140 |
| 7・3 弁およびコック 140 |
| 7・3・1 弁の種類 140 |
| 7・3・2 弁の材質 141 |
| 7・4 超高圧用配管と弁 142 |
| 第Ⅱ部 トライボロジー |
| 第1章 トライボロジーの基礎 |
| 1・1 接触面の機能と発生する事象 143 |
| 1・1・1 接触面の機能 143 |
| 1・1・2 接触面の特徴 143 |
| 1・1・3 固体接触 143 |
| 1・1・4 摩擦と表面損傷 143 |
| 1・1・5 潤滑と潤滑モード 143 |
| 1・2 トライボ設計 144 |
| 1・2・1 トライボ設計と潤滑モード 144 |
| 1・2・2 設計項目と設計ツール 144 |
| 1・2・3 流体潤滑モードにおけるトライボ設計 144 |
| 1・2・4 そのほかの潤滑モードにおけるトライボ設計 145 |
| 1・3 固体接触論 145 |
| 1・3・1 表面形状モデル 145 |
| 1・3・2 へルツ接触モデル 145 |
| 1・3・3 粗面の接触モデル 147 |
| 1・3・4 固体摩擦理論 148 |
| 1・3・5 摩耗理論 149 |
| 1・3・6 摩擦面温度上昇 150 |
| 1・4 流体潤滑 150 |
| 1・4・1 レイノルズ方程式 150 |
| 1・4・2 動圧ジャーナル軸受の流体潤滑理論 151 |
| 1・4・3 動圧スラスト軸受の流体潤滑理論 153 |
| 1・4・4 静圧軸受の流体潤滑理論 154 |
| 1・4・5 気体軸受の流体潤滑理論 155 |
| 1・4・6 乱流流体潤滑理論 157 |
| 1・4・7 熱流体潤滑理論 158 |
| 1・4・8 弾性流体潤滑理論 160 |
| 1・4・9 表面粗さを考慮した流体潤滑理論 160 |
| 1・5 混合潤滑,境界潤滑 162 |
| 1・5・1 潤滑モード 162 |
| 1・5・2 接触モデル 162 |
| 1・5・3 境界膜 162 |
| 1・5・4 有機吸着分子膜のレオロジー特性 163 |
| 1・5・5 境界潤滑理論 163 |
| 1・5・6 混合潤滑理論 163 |
| 第2章 潤滑剤 |
| 2・1 潤滑剤の種類と選択 165 |
| 2・1・1 潤滑剤の種類 165 |
| 2・1・2 潤滑剤の性能と選定基準 165 |
| 2・2 潤滑油 166 |
| 2・2・1 種類と特徴 166 |
| 2・2・2 用途別潤滑油 167 |
| 2・3 グリース 171 |
| 2・3・1 グリースの組成と性能 171 |
| 2・3・2 グリースの種類と用途 172 |
| 2・4 固体潤滑剤 172 |
| 2・4・1 固体潤滑剤の種類と特徴 172 |
| 2・4・2 固体潤滑剤の使用例 173 |
| 2・5 潤滑法 174 |
| 2・5・1 潤滑の目的と潤滑法 174 |
| 2・5・2 油潤滑法と潤滑系 174 |
| 2・5・3 グリース潤滑と潤滑系 174 |
| 2・5・4 固体潤滑と潤滑系 175 |
| 2・6 潤滑装置 176 |
| 2・6・1 集中潤滑装置 176 |
| 2・6・2 強制循環給油装置 177 |
| 2・6・3 噴霧給油装置 179 |
| 2・7 潤滑管理 180 |
| 2・7・1 異常の検出 180 |
| 2・7・2 潤滑系の管理とメンテナンス 181 |
| 2・7・3 潤滑油の劣化と診断 181 |
| 2・7・4 グリースの劣化と診断法 182 |
| 第3章 表面損傷 |
| 3・1 損傷の種類 184 |
| 3・1・1 摩耗 184 |
| 3・1・2 焼付き 184 |
| 3・1・3 疲労損傷 184 |
| 3・1・4 キャビテーションエロージョン 184 |
| 3・1・5 電食 184 |
| 3・1・6 そのほかの損傷 184 |
| 3・2 摩耗 184 |
| 3・2・1 凝着摩耗 184 |
| 3・2・2 アブレシブ摩耗 185 |
| 3・2・3 腐食摩耗 185 |
| 3・2・4 フレッチング 186 |
| 3・2・5 摩耗の評価方法および摩耗遷移 187 |
| 3・2・6 油潤滑下の摩耗 188 |
| 3・3 焼付き 188 |
| 3・3・1 臨界膜厚条件 188 |
| 3・3・2 臨界温度条件 188 |
| 3・3・3 臨界摩擦損失,臨界摩擦損失密度条件 188 |
| 3・3・4 熱的不安定条件 188 |
| 3・4 疲労損傷 189 |
| 3・4・1 滑り接触における疲れ 189 |
| 3・4・2 転がり接触における疲れ 190 |
| 3・5 キャビテーションエロージョン 192 |
| 3・5・1 軸受におけるキャビテーション 192 |
| 3・5・2 そのほかの機械要素におけるキャビテーション 192 |
| 3・6 電食 192 |
| 3・6・1 軸受における電食 192 |
| 3・6・2 そのほかの機械要素における電食 193 |
| 3・7 損傷の検出と診断 193 |
| 3・7・1 フェログラフィ 193 |
| 3・7・2 非破壊検査 194 |
| 3・7・3 故障予知技術 194 |
| 第4章 トライボ材料 |
| 4・1 トライボ材料の種類と選定 196 |
| 4・1・1 トライボ材料の選定基準 196 |
| 4・1・2 接触条件による選定 196 |
| 4・1・3 使用環境による選定 197 |
| 4・2 硬質材料 197 |
| 4・2・1 金属材料 197 |
| 4・2・2 非金属材料 198 |
| 4・3 軟質材料 198 |
| 4・3・1 金属材料 198 |
| 4・3・2 非金属材料 198 |
| 4・4 表面処理 199 |
| 4・4・1 物理的表面処理 199 |
| 4・4・2 化学的表面処理 199 |
| 4・4・3 そのほかの表面改質 200 |
| 第5章 マイクロトライボロジー |
| 5・1 マイクロ/ナノトライボロジー 201 |
| 5・2 極表面の物理・化学的同定 201 |
| 5・2・1 表面状態解析の必要性 201 |
| 5・2・2 物理的同定法 202 |
| 5・2・3 化学的同定法 202 |
| 5・3 コンピュータシミュレーション 202 |
| 5・3・1 分子動力学法 202 |
| 5・3・2 原子間力顕微鏡のシミュレーション 203 |
| 5・3・3 ダイヤモンド表面の摩擦現象のシミュレーション 203 |
| 5・3・4 スティックスリップ現象のシミュレーション 203 |
| 5・3・5 固体間に挟まれた液体分子のパッキング構造 203 |
| 5・3・6 せん断場における潤滑剤のシミュレーション 203 |
| 第Ⅲ部 機械要素設計の基礎と製図 |
| 第1章 標準化とはめあい |
| 1・1 標準化 205 |
| 1・1・1 工業規格 205 |
| 1・1・2 標準数 205 |
| 1・2 寸法公差 205 |
| 1・3 はめあい 206 |
| 第2章 製図と図面 |
| 2・1 製図の目的と基本条件 208 |
| 2・1・1 製図の目的 208 |
| 2・1・2 図面が具備しなければならない基本要件 208 |
| 2・2 製図規格 208 |
| 2・3 製図に用いる用紙,尺度,線および文字 208 |
| 2・3・1 製図用紙の大きさと様式 208 |
| 2・3・2 製図に用いる尺度 209 |
| 2・3・3 製図に用いる線 209 |
| 2・3・4 製図に用いる文字 209 |
| 2・4 製図における図形の表し方 210 |
| 2・4・1 製図に用いる投影法 210 |
| 2・4・2 投影図の表し方 210 |
| 2・4・3 図形の省略 210 |
| 2・4・4 断面図の示し方 212 |
| 2・4・5 特別な図示法 213 |
| 2・5 寸法および寸法の許容限界の記入方法 214 |
| 2・5・1 寸法および寸法の許容限界 214 |
| 2・5・2 寸法記入方法 214 |
| 2・5・3 特別な形体の寸法記入方法 215 |
| 2・5・4 寸法の許容限界記入方法 217 |
| 2・6 幾何公差 218 |
| 2・6・1 形体とデータム 218 |
| 2・6・2 幾何公差の種類とその記号 218 |
| 2・6・3 幾何公差の図示法 218 |
| 2・6・4 データム 219 |
| 2・6・5 幾何公差の適用を限定する図示方法 220 |
| 2・6・6 理論的に正確な寸法の図示方法 220 |
| 2・6・7 寸法と幾何特性の相互依存性 220 |
| 2・7 表面性状 221 |
| 2・7・1 表面性状の指示事項 221 |
| 2・7・2 表面性状の図示方法 221 |
| 2・8 ねじ,歯車,転がり軸受の図示法 223 |
| 2・8・1 ねじ製図 223 |
| 2・8・2 歯車製図 225 |
| 2・8・3 ばね製図 225 |
| 2・8・4 転がり軸受製図 227 |
| 2・9 溶接部の図示法 227 |
| 2・9・1 溶接記号 227 |
| 2・9・2 記号表示例 228 |
| 第3章 機械材料の標準形状と素材例 |
| 3・1 機械材料の標準形状 229 |
| 3・2 鉄鋼材料 229 |
| 3・2・1 炭素鋼と合金鋼 229 |
| 3・2・2 ステンレス鋼 229 |
| 3・2・3 軸受鋼,浸炭用鋼,耐熱鋼 229 |
| 3・2・4 鋳鉄 230 |
| 3・3 非鉄金属 230 |
| 3・3・1 非鉄金属記号の表し方 230 |
| 3・3・2 銅と銅合金 231 |
| 3・3・3 アルミニウムとアルミニウム合金 232 |
| 3・3・4 鉛と鉛合金 232 |
| 索引(日本語・英語) 巻末 |
| 機械設計と機械要素・トライボロジー |
| 機械研究の歴史と機械要素 1 |
| 機械を取り巻く学問 1 |
|
| 33.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
道家暎幸 [ほか] 著
| 出版情報: |
秦野 : 東海大学出版会, 2008.1 vii, 101p ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 注 : χ[2]の[2]は上つき文字 |
| 注 : σ[2]の[2]は上つき文字 |
| |
| 第1章 資料の整理 1 |
| 1.1 度数分布表 1 |
| 1.1.1 度数分布表の作成 2 |
| 1.1.2 ヒストグラムの作成 3 |
| 1.2 代表値と散布度 4 |
| 1.2.1 代表値 4 |
| 1.2.2 散布度 5 |
| 1.3 相関係数 7 |
| 1.4 回帰直線 11 |
| 演習問題 13 |
| 第2章 確率と確率分布 15 |
| 2.1 確率 15 |
| 2.2 現代的確率 16 |
| 2.2.1 事象 16 |
| 2.2.2 確率 17 |
| 2.3 確率変数と確率分布 19 |
| 2.3.1 離散型確率分布 19 |
| 2.3.2 連続型確率分布 20 |
| 2.4 平均と分散 22 |
| 2.4.1 平均 22 |
| 2.4.2 分散,標準偏差 23 |
| 2.4.3 確率変数の1次関数の平均,分散 23 |
| 2.5 順列,組合せ 25 |
| 2.5.1 順列 25 |
| 2.5.2 組合せ 26 |
| 2.6 二項分布 28 |
| 2.7 正規分布 30 |
| 2.7.1 正規確率密度関数 30 |
| 2.7.2 標準正規分布表 32 |
| 演習問題 34 |
| 第3章 標本分布 37 |
| 3.1 無作為抽出 37 |
| 3.2 標本平均の分布 39 |
| 3.3 χ[2]分布 41 |
| 3.4 t分布 42 |
| 3.5 F分布 44 |
| 演習問題 46 |
| 第4章 統計的推定 47 |
| 4.1 推定量 47 |
| 4.2 点推定 48 |
| 4.2.1 不偏推定量 48 |
| 4.2.2 一致推定量 48 |
| 4.2.3 有効推定量 49 |
| 4.3 区間推定 50 |
| 4.3.1 母平均μ(母分散が既知の場合) 50 |
| 4.3.2 母平均μ(母分散が未知の場合) 52 |
| 4.3.3 母比率p(大標本の場合) 53 |
| 4.3.4 母分散σ[2](母平均が既知の場合) 54 |
| 4.3.5 母分散σ[2](母平均が未知の場合) 55 |
| 演習問題 56 |
| 第5章 仮説検定 57 |
| 5.1 仮説検定 57 |
| 5.2 正規母集団の母平均μの仮説検定 58 |
| 5.2.1 母分散σ[2]が既知の場合 58 |
| 5.2.2 母分散σ[2]が未知の場合 61 |
| 5.3 母比率pの仮説検定 62 |
| 5.4 母分散σ[2]の仮説検定 64 |
| 5.5 2正規母集団の等平均,等分散の検定 66 |
| 5.5.1 2正規母集団の等平均の検定 66 |
| 5.5.2 2正規母集団の等分散の検定 67 |
| 5.6 適合度の検定 69 |
| 5.7 分割表の検定 71 |
| 演習問題 74 |
| 付録 各種分布表 77 |
| 二項分布表 77 |
| 標準正規分布表(I) 78 |
| 標準正規分布表(II) 79 |
| t分布表 80 |
| χ[2]分布表 81 |
| F分布表(I)(α=0.05) 82 |
| F分布表(II)(α=0.025) 84 |
| 演習問題の解答 87 |
| 事項索引 99 |
| 注 : χ[2]の[2]は上つき文字 |
| 注 : σ[2]の[2]は上つき文字 |
| |
|
| 34.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
後藤尚久著
目次情報:
続きを見る
| 1.静電界 |
| 1.1 電荷 2 |
| 1.1.1 電荷保存の法則 2 |
| 1.1.2 クーロンの法則 5 |
| 1.1.3 重ね合わせの理 7 |
| 1.2 電界 9 |
| 1.2.1 電界とは何か 9 |
| 1.2.2 電気力線 11 |
| 1.2.3 ガウスの定理 13 |
| 1.3 電位 17 |
| 1.3.1 電位と位置エネルギー 17 |
| 1.3.2 点電荷が作る電位 21 |
| 1.3.3 ダイポール 22 |
| 談話室 クーロンカと万有引力 27 |
| 本章のまとめ 28 |
| 理解度の確認 28 |
| 2.導体と誘電体 |
| 2.1 導体と電界 30 |
| 2.1.1 自由電子 30 |
| 2.1.2 導体内部の電界 33 |
| 2.1.3 なぜ逆2乗の法則になるか 34 |
| 2.2 コンデンサ 36 |
| 2.2.1 静電容量 36 |
| 2.2.2 静電容量の例 39 |
| 2.2.3 電界のエネルギー 46 |
| 2.3 誘電体 48 |
| 2.3.1 誘電率 48 |
| 2.3.2 電束密度 51 |
| 2.3.3 電界の決定 54 |
| 談話室 電流は硬い液体の流れ 58 |
| 本章のまとめ 59 |
| 理解度の確認 60 |
| 3.静磁界 |
| 3.1 クーロンの法則 62 |
| 3.1.1 磁荷 62 |
| 3.1.2 電気と磁気 65 |
| 3.1.3 磁界 66 |
| 3.2 磁石 67 |
| 3.2.1 小さい棒磁石 68 |
| 3.2.2 板磁石 69 |
| 3.2.3 磁位の山 71 |
| 3.3 磁束 74 |
| 3.3.1 磁性体 74 |
| 3.3.2 磁束密度 76 |
| 3.3.3 磁界の決定 78 |
| 本章のまとめ 82 |
| 理解度の確認 82 |
| 4.電流 |
| 4.1 オームの法則 84 |
| 4.1.1 電池の発明 84 |
| 4.1.2 オームの法則 85 |
| 4.1.3 抵抗率 86 |
| 4.2 電気回路 87 |
| 4.2.1 定常電流 87 |
| 4.2.2 連立一次方程式 89 |
| 4.2.3 電力 91 |
| 4.3 電荷の移動 93 |
| 4.3.1 等速度運動 93 |
| 4.3.2 導体中の電荷の移動 94 |
| 4.3.3 電気力線の移動 96 |
| 談話室 電気の量と電気の強さ 98 |
| 本章のまとめ 99 |
| 理解度の確認 100 |
| 5.電磁誘導 |
| 5.1 ローレンツ力 102 |
| 5.1.1 ローレンツ力とは 102 |
| 5.1.2 ローレンツ力の導出 103 |
| 5.1.3 電流の間に働く力 107 |
| 5.2 ビオ・サバールの法則 108 |
| 5.2.1 磁荷と運動する電荷の相互作用 108 |
| 5.2.2 ビオ・サバールの法則 110 |
| 5.2.3 電流ループが作る磁界 112 |
| 5.3 アンペアの法則 115 |
| 5.3.1 電束線の等速度運動 115 |
| 5.3.2 ガウスの定理 117 |
| 5.3.3 アンペアの法則 120 |
| 5.4 ファラデーの法則 123 |
| 5.4.1 電磁誘導の法則 123 |
| 5.4.2 ファラデーの法則の適用例 126 |
| 5.4.3 インダクタンス 127 |
| 談話室 ベクトル積 133 |
| 本章のまとめ 134 |
| 理解度の確認 135 |
| 6.電磁波 |
| 6.1 交流回路 138 |
| 6.1.1 電荷の加速度運動 138 |
| 6.1.2 交流理論 140 |
| 6.1.3 伝送線路 141 |
| 6.2 平面波 144 |
| 6.2.1 進行波と反射波 144 |
| 6.2.2 平行板線路 146 |
| 6.2.3 近接作用 147 |
| 6.3 マクスウェルの方程式 150 |
| 6.3.1 ベクトルの回転 151 |
| 6.3.2 変位電流 153 |
| 談話室 変位電流 154 |
| 本章のまとめ 155 |
| 理解度の確認 155 |
| 付録 |
| 1.ローレンツ力の導出 157 |
| 2.電流ループが作る磁界 159 |
| 3.電位の傾きとベクトルポテンシャル 162 |
| 談話室 ローレンツ収縮 165 |
| 引用・参考文献 168 |
| 理解度の確認;解説 169 |
| 索引 173 |
| 1.静電界 |
| 1.1 電荷 2 |
| 1.1.1 電荷保存の法則 2 |
|
| 35.
|
 図書
図書
|
内藤喜之著
| 出版情報: |
東京 : 森北出版, 1976-1977 2冊 ; 22cm |
| シリーズ名: |
電気・電子工学基礎講座 ; 6,7 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 36.
|
 図書
図書
|
庄野克房著
| 出版情報: |
東京 : 東京大学出版会, 1976.5 2冊 ; 21cm |
| シリーズ名: |
物理工学実験 ; 2-3 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 37.
|
 図書
図書
|
K.F.カイプル編 ; 酒井シヅ監訳
| 出版情報: |
東京 : 朝倉書店, 2005.12-2006.2 3冊 ; 22cm |
| シリーズ名: |
科学史ライブラリー |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 38.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
小澤丈夫, 吉田博久編
| 出版情報: |
東京 : 講談社, 2005.4 xii, 264p ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 最新 熱分析 |
| 序文 v |
| 基礎編 |
| 第1章 序論 3 |
| 1.1 熱分析とは 3 |
| 1.2 熱分析の種類 4 |
| 1.3 熱分析における温度制御方式 6 |
| 1.4 熱分析の限界 8 |
| 1.5 熱分析を支える基盤 8 |
| 参考文献 10 |
| 第2章 熱分析の原理と応用 11 |
| 2.1 共通原理 11 |
| 2.1.1 熱力学温度と国際温度目盛 11 |
| 2.1.2 温度測定 11 |
| 2.1.3 温度勾配 13 |
| 2.1.4 温度制御 14 |
| 2.2 示差熱分析と示差走査熱量測定 14 |
| 2.2.1 分類 15 |
| 2.2.2 基線(ベースライン) 16 |
| 2.2.3 ピーク面積 17 |
| 2.2.4 ピークの高さ 18 |
| 2.2.5 試料の温度 19 |
| 2.2.6 熱異常の前後における基線のくいちがい 20 |
| 2.3 熱膨脹と熱機械測定 22 |
| 2.3.1 熱膨張 22 |
| 2.3.2 熱機械測定 23 |
| 2.4 熱重量測定 26 |
| 2.4.1 装置と測定原理 26 |
| 2.4.2 測定上の問題と対処 29 |
| 2.4.3 測定結果から得られる情報 31 |
| 2.5 発生気体分析 32 |
| 2.5.1 TG-DTA-MS, TG-DTA-GC-MS 32 |
| 2.5.2 TG-DTA-IR 35 |
| 2.6 複合測定 37 |
| 2.6.1 DSC-XRD測定 38 |
| 2.6.2 DSC-FTIR測定 40 |
| 2.7 温度変調熱分析 42 |
| 2.7.1 温度変調とは何か 42 |
| 2.7.2 変調周波数と方法論 43 |
| 2.7.3 光交流法・光音響効果法 45 |
| 2.7.4 パルス刺激応答法 46 |
| 2.7.5 温度変調DSC 46 |
| 2.7.6 温度波熱分析法 48 |
| 2.7.7 等速昇温測定と周波数測定の関係 49 |
| 2.8 試料制御熱分析 51 |
| 2.8.1 試料制御熱分析の原理 51 |
| 2.8.2 試料制御熱分析の特徴と応用 53 |
| 2.9 微小領域と試料の熱分析 56 |
| 2.9.1 測定原理 57 |
| 2.9.2 応用例 58 |
| 参考文献 60 |
| 第3章 解析方法 64 |
| 3.1 標準物質と装置の較正 64 |
| 3.1.1 標準物質 64 |
| 3.1.2 装置の較正 66 |
| 3.2 熱容量測定 68 |
| 3.2.1 DSC測定の基本原理 68 |
| 3.2.2 実際の測定 70 |
| 3.2.3 動的熱容量 72 |
| 3.2.4 ナノマテリアルやガラスへの応用 73 |
| 3.3 組成分析 75 |
| 3.4 純度 77 |
| 3.4.1 DSCによる純度決定の原理 77 |
| 3.4.2 測定法 79 |
| 3.5 相図 81 |
| 3.5.1 相図と熱力学の基本 81 |
| 3.5.2 DSC曲線と相図 84 |
| 参考文献 86 |
| 第4章 速度論的解析 88 |
| 4.1 化学反応 88 |
| 4.1.1 固相反応速度論と反応機構モデル 88 |
| 4.1.2 反応速度式 90 |
| 4.1.3 速度論的解析のための熱分析 92 |
| 4.1.4 種々の速度論的解析法 97 |
| 4.1.5 速度論的パラメーターの実用性 106 |
| 4.2 結晶化 107 |
| 4.2.1 原理・解析 107 |
| 4.2.2 等温結晶化 108 |
| 4.2.3 定速降温(昇温)による結晶化 109 |
| 4.2.4 温度変調DSCの適用 110 |
| 4.2.5 実例 111 |
| 参考文献 111 |
| 応用編 |
| 第5章 無機物総論 115 |
| 5.1 熱分析と無機物 115 |
| 5.2 無機材料と熱的変化 116 |
| 5.2.1 熱容量と転移 116 |
| 5.2.2 熱膨脹 118 |
| 5.2.3 熱伝導 118 |
| 5.2.4 吸着と脱離 119 |
| 5.3 実際の測定 119 |
| 5.3.1 測定系(装置)の安定性 120 |
| 5.3.2 再現性の確認 120 |
| 5.3.3 精度(変動係数)と確度 121 |
| 5.4 熱分析の適用例 123 |
| 5.4.1 TG-DTA(DSC),TG-DTA-EGA(FTIRまたはMS),TMA,ディラトメトリー(DLT)の応用例 123 |
| 5.4.2 試料制御熱分析(SCTAまたはCRTA) 125 |
| 5.4.3 複合測定(特に発生気体分析) 128 |
| 参考文献 128 |
| 第6章 有機化合物総論 130 |
| 6.1 有機化合物の機能性 130 |
| 6.2 低分子化合物 131 |
| 6.3 高分子化合物 134 |
| 6.4 有機化合物の熱分析 134 |
| 6.4.1 実験装置と実験の準備 134 |
| 6.4.2 結晶多形と相関係の熱分析 135 |
| 6.4.3 分子間化合物の熱分析 137 |
| 参考文献 137 |
| 第7章 セラミックス材料 139 |
| 7・1 活性酵素を発生する導電性アルミナセメント 139 |
| 7・2 非酸化物セラミックス 141 |
| 7・3 脱バインダー 144 |
| 7・4 フラットパネルディスプレイ 145 |
| 7・5 触媒 147 |
| 7・6 ウッドセラミックス 149 |
| 7・7 粘土鉱物 150 |
| 7・8 ゼオライト 151 |
| 7・9 金属アルコキシド原料 152 |
| 7・10 その他のセラミックス 154 |
| 7.10.1 ガラス 154 |
| 7.10.2 セメント・コンクリート 154 |
| 7.10.3 環境汚染物質 154 |
| 7.10.4 セラミックス原料の気化 155 |
| 参考文献 157 |
| 第8章 電気・電子材料 159 |
| 8.1 無機材料 159 |
| 8.1.1 半導体 159 |
| 8.1.2 誘電体 161 |
| 8.1.3 二次電池 164 |
| 8.1.4 超伝導体 164 |
| 8.1.5 透明導電膜 165 |
| 8.2 高分子材料 168 |
| 8.2.1 実装材料 168 |
| 8.2.2 燃料電池用固体高分子電解質 171 |
| 8.2.3 電気絶縁用材料 172 |
| 8.3 液晶 175 |
| 8.3.1 液晶の分類 175 |
| 8.3.2 単成分サーモトロピック液晶の熱分析 176 |
| 8.3.3 混合系の相図 177 |
| 8.3.4 液晶化合物におけるアルキル鎖 178 |
| 参考文献 180 |
| 第9章 高分子 183 |
| 9.1 物性 183 |
| 9.1.1 融解 183 |
| 9.1.2 ガラス転移と緩和現象 190 |
| 9.1.3 多成分系 194 |
| 9.2 反応 197 |
| 9.2.1 高分子反応の特徴 197 |
| 9.2.2 硬化反応 197 |
| 9.2.3 熱分解 199 |
| 9.2.4 リサイクル性評価 201 |
| 9.2.5 劣化・熱安定性の評価 202 |
| 参考文献 205 |
| 第10章 医薬品の熱分析 207 |
| 10.1 医薬品の特性 207 |
| 10.1.1 結晶多形間のエネルギー差の決定 208 |
| 10.1.2 遅い反応速度の決定 209 |
| 10.2 熱分析による医薬品の物性評価 209 |
| 10.2.1 結晶多形の同定 209 |
| 10.2.2 結晶多形の転移挙動の解析 210 |
| 10.2.3 溶解和物・水和物 214 |
| 10.2.4 非晶質 216 |
| 10.2.5 結晶多形,結晶化度と溶解性 217 |
| 10.2.6 結晶多形の溶解熱と溶解速度との関係 217 |
| 10.2.7 医薬品の結晶化度と溶解速度との関係 219 |
| 10.3 装置の検定 219 |
| 10.3.1 溶解熱熱量計の検定 220 |
| 10.3.2 安定性試験のための標準系 220 |
| 10.4 応用例 221 |
| 10.4.1 実測できない反応エンタルピーの決定 221 |
| 10.4.2 結晶多形のエネルギーの決定 222 |
| 10.4.3 結晶化度の決定 223 |
| 10.4.4 吸着過程の観測 225 |
| 10.4.5 分解反応の観測 227 |
| 参考文献 229 |
| 第11章 生体物質・食品 232 |
| 11.1 生体物質 232 |
| 11.1.1 単量体タンパク質の二状態転移 233 |
| 11.1.2 単量体タンパク質の多状態転移 237 |
| 11.1.3 多量体タンパク質の熱転移 238 |
| 11.1.4 DNA二重らせんの熱転移 239 |
| 11.1.5 リン脂質膜の熱転移 240 |
| 11.2 食品 242 |
| 11.2.1 デンプン質食品 242 |
| 11.2.2 タンパク食品 245 |
| 11.2.3 ゲル 246 |
| 11.2.4 食品中の水 247 |
| 参考文献 251 |
| 第12章 品質管理と熱分析 253 |
| 12.1 JISに制定されている熱分析関連の規格 253 |
| 12.2 ISO,IEC規格に制定されている熱分析関連のおもな規格 255 |
| 12.3 その他 256 |
| 参考文献 258 |
| 索引 259 |
|
| 39.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
篠田正人編著
| 出版情報: |
東京 : 共立出版, 2008.4 v, 174p ; 21cm |
| シリーズ名: |
教育系学生のための数学シリーズ |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 第1章 確率論の始まり 1 |
| 1.1 生活の中の確率 1 |
| 1.1.1 偶然を扱う数学 1 |
| 1.1.2 様々な意味での確率 2 |
| 1.2 確率論の始まり 3 |
| 1.3 有限と無限 4 |
| 第2章 組合せ計算 8 |
| 2.1 個数の処理 8 |
| 2.1.1 場合の数,和の法則 8 |
| 2.1.2 直積集合と積の法則 11 |
| 2.2 順列と組合せ 13 |
| 2.2.1 順列 13 |
| 2.2.2 組合せ 14 |
| 2.2.3 順列と組合せの具体例 16 |
| 2.3 2項定理 18 |
| 第3章 確率とその計算 23 |
| 3.1 確率の定義 23 |
| 3.1.1 試行と事象 23 |
| 3.1.2 事象の確率 24 |
| 3.1.3 一般の確率の定義 28 |
| 3.2 確率の計算 29 |
| 第4章 独立試行と乗法定理 34 |
| 4.1 事象の独立 34 |
| 4.2 条件付き確率 39 |
| 4.3 ベイズの定理 44 |
| 第5章 確率変数と期待値 48 |
| 5.1 確率変数と確率分布 48 |
| 5.2 期待値 50 |
| 5.3 分散 52 |
| 5.4 重 要な確率分布 54 |
| 5.4.1 2項分布 54 |
| 5.4.2 2項分布の期待値 57 |
| 5.4.3 ポアソン分布 59 |
| 第6章 確率論の話題から 63 |
| 6.1 モンモールの問題 63 |
| 6.2 切手集めの問題 65 |
| 6.3 賞金の配分とランダムウォーク 68 |
| 6.3.1 賞金配分の問題 68 |
| 6.3.2 1次元ランダムウォーク 70 |
| 第7章 統計学の始まり 76 |
| 7.1 標本と母集団 76 |
| 7.2 標本データの整理 78 |
| 7.3 標本データの特性値 81 |
| 7.3.1 標本データの平均 81 |
| 7.3.2 標本データの標準偏差・分散 83 |
| 7.3.3 度数分布表・ヒストグラムと平均・標準偏差 85 |
| 第8章 確率分布と母集団 90 |
| 8.1 母集団から確率分布へ 90 |
| 8.2 確率分布の性質 92 |
| 8.2.1 確率分布での平均と標準偏差(分散) 92 |
| 8.2.2 連続型変数 93 |
| 8.2.3 和と定数倍の確率分布の性質 94 |
| 8.3 正規分布 98 |
| 8.3.1 正規分布での確率 98 |
| 8.4 2項分布と正規近似101 |
| 8.4.1 2項分布の平均と標準偏差 102 |
| 8.4.2 2項分布の正規近似 103 |
| 第9章 推定 107 |
| 9.1 標本平均の分布 107 |
| 9.2 母平均の推定 109 |
| 9.2.1 不偏推定 109 |
| 9.2.2 点推定と区間推定 110 |
| 9.2.3 母集団が正規分布で標準偏差がわかっているとき 111 |
| 9.2.4 大標本の場合 113 |
| 9.3 小標本の場合(スチューデントのt分布) 114 |
| 9.4 比率の推定 116 |
| 第10章 仮説の検定 119 |
| 10.1 仮説と2種類の誤り 119 |
| 10.2 平均値の検定 122 |
| 10.2.1 平均値の検定(両側検定) 122 |
| 10.2.2 平均値の検定(片側検定) 124 |
| 10.3 小標本の場合 125 |
| 10.4 比率の検定 126 |
| 10.5 平均値や比率の差の検定 128 |
| 第11章 相関と回帰 1 |
| 11.1 線形相関 132 |
| 11.1.1 相関係数 132 |
| 11.1.2 相関係数の推定と検定 136 |
| 11.2 直線回帰 138 |
| 第12章 確率・統計教育の概観と展望 143 |
| 12.1 確率教育の概観と展望 143 |
| 12.1.1 確率教育の歴史と現状 143 |
| 12.1.2 確率の指導内容 144 |
| 12.1.3 確率教育の課題と展望 146 |
| 12.2 統計教育の概観と展望 148 |
| 12.2.1 統計教育の歴史と現状 148 |
| 12.2.2 統計の指導内容 149 |
| 12.2.3 統計教育の課題と展望 152 |
| 練習問題解答 155 |
| 数表 168 |
| 参考文献 171 |
| 索引 172 |
| 第1章 確率論の始まり 1 |
| 1.1 生活の中の確率 1 |
| 1.1.1 偶然を扱う数学 1 |
|
| 40.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
石井彰三, 荒川文生著 ; 電気学会電気技術国産化の歴史調査専門委員会編
| 出版情報: |
東京 : 朝倉書店, 1999.6 vi, 198p ; 21cm |
| シリーズ名: |
インターレクチュアライブラリ ; 4 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 1 なぜ,技術史なのか ふたつの文化を結ぶ橋 2 |
| 1.1 技術史研究の意義 2 |
| 1.1.1 技術とは 2 |
| 1.1.2 未来を歴史に問う 4 |
| 1.1.3 現在と過去の対話 4 |
| 1.1.4 歴史は常に新しい 5 |
| 1.1.5 歴史家を見よ 8 |
| 1.1.6 客観的とは 9 |
| 1.1.7 パラダイムの変換 11 |
| 1.2 歴史研究の方法 13 |
| 1.2.1 史料の謎を解く 13 |
| 1.2.2 技術者にとって歴史とは 14 |
| 1.2.3 実際学としての歴史とは 16 |
| 1.2.4 世界へ向けての発信 17 |
| 1.2.5 歴史研究のモデル 19 |
| 1.2.6 技術と社会の連携モデル 20 |
| 1.2.7 ステージ・モデル 21 |
| 1.2.8 モデルの適用例 23 |
| 1.2.9 科学技術史としての電気技術史 25 |
| 1.2.10 工学としての技術史 27 |
| 1.3 歴史研究の成果 29 |
| 1.3.1 日本らしい技術とは 29 |
| 1.3.2 人間らしさとは 32 |
| 1.3.3 海の向こうでは 35 |
| 1.3.4 謎解きの成果は 37 |
| 2 電気技術はいかに国産化されたか エネルギーからエレクトロニクスまで 42 |
| 2.1 分析の視点としての国産化 42 |
| 2.1.1 「国産化」とは 42 |
| 2.1.2 謎解きの手がかり 43 |
| 2.2 技術の総合的進歩と国産化 44 |
| 2.2.1 変圧器技術の国産化 44 |
| 2.2.2 戦前における変圧器技術 45 |
| 2.2.3 戦後の海外導入技術と超高圧変圧器 49 |
| 2.2.4 500kV変圧器開発と技術の国産化 53 |
| 2.2.5 新技術への挑戦 56 |
| 2.2.6 まとめ 58 |
| 2.3 社会・経済的状況と国産化 58 |
| 2.3.1 電力系統技術の歴史 58 |
| 2.3.2 電力系統の形成 59 |
| 2.3.3 電力系統の発展 61 |
| 2.3.4 電力系統技術の新しい展開 64 |
| 2.3.5 電力系統技術の史実分析とモデル化 65 |
| 2.4 模倣から独自技術への展開 66 |
| 2.4.1 遮断器技術の国産化 66 |
| 2.4.2 油遮断器開発の歴史 67 |
| 2.4.3 空気遮断器開発の歴史 72 |
| 2.4.4 SF6ガス遮断器開発の歴史 74 |
| 2.4.5 遮断器国産化の分析とモデル化 77 |
| 2.5 計測器技術と海外技術の導入 80 |
| 2.5.1 計測と計測器 80 |
| 2.5.2 計測器と日本の電気計測器産業 81 |
| 2.5.3 電気計測器の国産化 82 |
| 2.5.4 積算電力計の起源 84 |
| 2.5.5 積算電力計の国産化 85 |
| 2.5.6 国産化に与えたさまざまな要素 90 |
| 2.5.7 まとめ 91 |
| 2.6 国策と産業の保護 91 |
| 2.6.1 電子計算機技術の国産化 91 |
| 2.6.2 電子計算機における技術開発の特徴 92 |
| 2.6.3 わが国の電子計算機国産化の歴史 93 |
| 2.6.4 電子計算機への産業政策 100 |
| 2.6.5 まとめ 104 |
| 2.7 民主・家電用途への特化 105 |
| 2.7.1 マグネトロンの発明と初期の研究 105 |
| 2.7.2 第二次世界大戦までにおけるマグネトロンの実用化 110 |
| 2.7.3 戦後におけるマグネトロンの開発と国産化 111 |
| 2.7.4 電子レンジ用連続波マグネトロンの開発 112 |
| 2.7.5 まとめ 116 |
| 2.8 海外技術の途絶と国産化 116 |
| 2.8.1 水車発電機技術開発の歴史 116 |
| 2.8.2 直流発電機と誘導発電機 117 |
| 2.8.3 明治時代の同期発電機 118 |
| 2.8.4 大正時代と海外技術の途絶 119 |
| 2.8.5 昭和初期における技術展開 121 |
| 2.8.6 戦後における発電機の技術開発 122 |
| 2.8.7 揚水発電と発電電動機 124 |
| 2.8.8 日本の電気鉄道における技術開発 126 |
| 3 技術はどのように発展すべきか 多様なシナリオを描く 130 |
| 3.1 問題提起は覆面で 130 |
| 3.2 日本らしい技術などあるのか 136 |
| 3.3 われわれに何が求められているか 142 |
| 3.4 技術を発展させたものは何か 151 |
| 3.5 科学と技術の原点を問う 160 |
| 3.6 技術と技術者のありかた 167 |
| 4 技術者は何を訴えるか メッセージを発信しよう 180 |
| 4.1 反省の中から 180 |
| 4.2 社会との協力 182 |
| 4.3 研究と教育の場 184 |
| 4.4 夢を育てる 185 |
| 参考文献 187 |
| 技術用語の解説 191 |
| おわりに 195 |
| 索引 196 |
| 1 なぜ,技術史なのか ふたつの文化を結ぶ橋 2 |
| 1.1 技術史研究の意義 2 |
| 1.1.1 技術とは 2 |
|
| 41.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
井上洋一[ほか]共著
| 出版情報: |
東京 : 日本規格協会, 2007.9 287p ; 21cm |
| シリーズ名: |
安全の国際規格 ; 3 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 第1章 安全に関する国際規格 |
| 1.1 国際規格の体系 13 |
| 1.1.1 電気安全と機械安全との関係 13 |
| 1.1.2 IEC61508の適用 15 |
| 1.2 電気安全に関する国際規格 18 |
| 1.3 制御システムの安全に関する国際規格 19 |
| 第2章 IEC60204-1機械の電気装置 |
| 2.1 規格の概要 23 |
| 2.2 適用範囲,引用規格,用語定義,配電系統(接地系統) 26 |
| 2.2.1 適用範囲 26 |
| 2.2.2 引用規格 26 |
| 2.2.3 定義 29 |
| 2.2.4 供給電源の電圧ざ周波数及び配電系統 29 |
| 2.3 一般要求事項 31 |
| 2.3.1 一般考慮事項 31 |
| 2.3.2 電源 34 |
| 2.3.3 物理的環境及び運転条件 37 |
| 2.4 入力電源導体の接続,断路器,スイッチングオフ機器 38 |
| 2.4.1 入力電源導体の接続 38 |
| 2.4.2 入力電源断路器 39 |
| 2.5 感電保護 41 |
| 2.5.1 直接接触に対する保護 42 |
| 2.5.2 間接接触に対する保護 45 |
| 2.5.3 PELV(保護特別低電圧)による保護 47 |
| 2.6 装置の保護 48 |
| 2.6.1 過電流保護 48 |
| 2.6.2 電動機の温度上昇保護 51 |
| 2.6.3 停電・電圧低下及び復旧時の保護 51 |
| 2.6.4 地絡電流(漏電電流)保護 52 |
| 2.6.5 相順の保護 52 |
| 2.6.6 雷サージ・開閉サージの過電圧保護 52 |
| 2.7 等電位ボンディング 52 |
| 2.7.1 保護ボンディング回路 54 |
| 2.7.2 機能ボンディング 55 |
| 2.8 制御回路及び制御機能 56 |
| 2.8.1 制御回路 56 |
| 2.8.2 制御機能 56 |
| 2.8.3 保護インターロック 62 |
| 2.8.4 故障時のリスクを最小にする方法 62 |
| 2.9 オペレータインタフェース,機械に取り付けた制御機器 64 |
| 2.9.1 手動操作の制御機器の配置,取付け 64 |
| 2.9.2 押しボタン 67 |
| 2.9.3 表示灯,表示器 68 |
| 2.1O 制御装置の配置・取付け,エンクロージャ 69 |
| 2.10.1 配置,取付け 69 |
| 2.10.2 保護等級 70 |
| 2.10.3 エンクロージャ,扉,開口部 71 |
| 2.10.4 通路のドア,電気設備Y区域の入り口のドア 72 |
| 2.11 導体及びケーブル 72 |
| 2.11.1 導体 72 |
| 2.11.2 絶縁被覆の耐電圧試験 72 |
| 2.11.3 定常使用時の電流容量 74 |
| 2.11.4 導体ワイヤ,導体バー,スリップリング機構 76 |
| 2.12 配線 77 |
| 2.12.1 接続及び経路 77 |
| 2.12.2 導体の識別 78 |
| 2.12.3 エンクロージャ内の配線 78 |
| 2.12.4 エンクロージャ外の配線 78 |
| 2.12.5 ダクト,接続箱 81 |
| 2.13 電動機及び関連装置 81 |
| 2.13.1 電動機のエンクロージャ 81 |
| 2.13.2 電動機の寸法 81 |
| 2.13.3 電動機の取付け及び電動機用区画 82 |
| 2.14 附属品及び照明 82 |
| 2.14.1 附属品用コンセント 82 |
| 2.14.2 機械及び装置の局部照明 82 |
| 2.14.3 電源 82 |
| 2.15 マーキング,警告標識,略号 84 |
| 2.15.1 警告標識 84 |
| 2.15.2 機能表示 86 |
| 2.15.3 装置のマーキング 86 |
| 2.15.4 略号 86 |
| 2.16 技術文書 90 |
| 2.16.1 提供情報 90 |
| 2.16.2 据付用文書 91 |
| 2.16.3 全体図及び機能線図 91 |
| 2.16.4 回路図 91 |
| 2.16.5 部品表 92 |
| 2.17 検証 92 |
| 2.17.1 電源自動遮断の条件の検証[検証項目b)] 92 |
| 2.17.2 絶縁抵抗試験[試験項目c)] 96 |
| 2.17.3 耐電圧試験[試験項目d)] 96 |
| 2.17.4 残留電圧に対する保護の検証[試験項目e)] 97 |
| 2.17.5 機能試験[試験項目f)] 97 |
| 第3章 ISO13849-1制御システムの安全関連部 |
| 3.1 ISO13849-1とは 99 |
| 3.2 ISO13849-1:2006の規定内容 104 |
| 3.3 ISO13849-1:2006の適用範囲 105 |
| 3.4 引用規格 108 |
| 3.5 定義,記号,略号など 109 |
| 3.6 設計における安全性の目標 114 |
| 3.6.1 検討のプロセス 114 |
| 3.6.2 設計のためのリスク低減の戦略 118 |
| 3.6.3 要求性能レベルの決定 121 |
| 3.6.4 制御システムの安全関連部(SRP/CS)の設計 123 |
| 3.6.5 構築(設計)された性能レベルの評価 124 |
| 3.6.6 ソフトウェアについての安全要求 138 |
| 3.6.7 PLがPLrを満たしていることの妥当性確認 142 |
| 3.6.8 設計における人間工学からの視点 142 |
| 3.7 安全機能の特性 143 |
| 3.7.1 安全機能の仕様 143 |
| 3.7.2 安全機能の詳細 143 |
| 3.8 カテゴリ 150 |
| 3.8.1 概要 150 |
| 3.8.2 各カテゴリの構造 153 |
| 3.8.3 異なるカテゴリに対する安全関連部の選択及び組合せ 158 |
| 3.9 不具合(障害)の考慮と除外 159 |
| 3.9.1 概要 159 |
| 3.9.2 障害への考慮事項 159 |
| 3.9.3 不具合(障害)の除外 159 |
| 3.10 妥当性確認 160 |
| 3.11 保全 161 |
| 3.12 技術資料 161 |
| 3.13 使用上の情報 162 |
| 第4章 IEC61508シリーズ 機能安全-電気・電子・プログラマブル安全関連系 |
| 4.1 電気・電子・プログラマブル電子安全関連システムの機能安全(IEC61508シリーズ) 165 |
| 4.2.1 IEC61508関連規格における基礎的用語とIEC61508-4の主要用語 173 |
| 4.2.1 IEC61508解説のための基礎的用語 173 |
| 4.2.2 1EC61508-4で示される用語例 178 |
| 4.3 IEC61508-1:一般的要求事項 184 |
| 4.3.1 規格の概要 184 |
| 4.3.2 規格の目的及び適用範囲,各部規定内容 185 |
| 4.3.3 安全ライフサイクル(条項7) 187 |
| 4.3.4 機能安全の管理(条項6) 199 |
| 4.3.5 機能安全管理の適用例 201 |
| 4.3.6 機能安全の査定(条項8) 206 |
| 4.4 IEC61508-2:E/E/PE安全関連系の要求事項 208 |
| 4.4.1 E/E/PE安全ライフサイクルの実現フェーズの概要 208 |
| 4.4.2 E/E/PES安全ライフサイクルフェーズ要求事項例(1) 210 |
| 4.4.3 E/E/PESハードウェアの安全性評価 214 |
| 4.4.4 E/E/PES安全ライフサイクルフェーズ要求事項例(2) 218 |
| 4.4.5 附属書A:E/E/PE安全関連系の技法と方策一故障の抑制 220 |
| 4.5 IEC61508-3:E/E/PE安全関連系ソフトウェアの要求事項 224 |
| 4.5.1 ソフトウェア安全ライフサイクルの実現フェーズ概要 224 |
| 4.5.2 ソフトウェアにおける安全管理 225 |
| 4.5.3 ソフトウェア安全ライフサイクルフェーズ要求事項 230 |
| 4.6 IEC61508-5:安全整合性水準(SIL)決定の方法例 236 |
| 4.6.1 附属書B:ALARP及び許容可能なリスクの概念 236 |
| 4.6.2 附属書C:安全整合性水準(SIL)の決定(定量的方法) 243 |
| 4.6.3 附属書C:安全整合性水準(SIL)の決定(定性的方法) 245 |
| 4.7 IEC61508-6:第2部及び第3部の適用に関する指針 251 |
| 4.7.1 附属書A:第2部及び第3部の適用 251 |
| 4.7.2 附属書B及びD:ハードウェア故障率評価の技法例 252 |
| 4.7.3 附属書E:ソフトウェア安全整合性の適用例 264 |
| 4.8 附属書(IEC61508-7) 266 |
| 第5章 電気と制御システム分野の今後 275 |
| 索引 279 |
| 第1章 安全に関する国際規格 |
| 1.1 国際規格の体系 13 |
| 1.1.1 電気安全と機械安全との関係 13 |
|
| 42.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
山本良一, 櫻井直樹共著
| 出版情報: |
東京 : オーム社, 2007.1 x, 235p ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 1 章 植物生理学とは |
| ■ 1.1 植物とその生理現象 1 |
| 1.1.1 植物と人間 3 |
| 1.1.2 植物生理学の誕生 3 |
| 1.1.3 農学との関係 4 |
| ■ 1.2 植物生理学という学問 5 |
| 1.2.1 環境 5 |
| 1.2.2 遺伝子 6 |
| 1.2.3 生長と分化 6 |
| 1.2.4 光合成と代謝 7 |
| 1.2.5 栄養 7 |
| ■ 1.3 植物生理学の将来 8 |
| 2 章 環境 |
| ■ 2.1 光 9 |
| 2.1.1 光形態形成 9 |
| 2.1.2 光と発芽 16 |
| 2.1.3 内生リズム 17 |
| ■ 2.2 水 21 |
| 2.2.1 水吸収における根の働き 21 |
| 2.2.2 維管束の働き 22 |
| 2.2.3 木部の中の水の流れ 23 |
| 2.2.4 水の凝集力 25 |
| 2.2.5 気孔は蒸散流の出口 25 |
| 2.2.6 蒸散は避けられない弊害 26 |
| 2.2.7 水ストレス 26 |
| 2.2.8 飾部を通る物質の移動 27 |
| 2.2.9 物質の転流 28 |
| ■ 2.3 温度 30 |
| 2.3.1 植物の生活と温度 30 |
| 2.3.2 春化とその機構 38 |
| 2.3.3 紅葉現象 42 |
| ■ 2.4 宇宙 46 |
| 2.4.1 微小重力 46 |
| 2.4.2 過重力 47 |
| 3 章 植物の遺伝子 |
| ■ 3.1 遺伝子の構造と機能 49 |
| 3.1.1 2種類の生物 49 |
| 3.1.2 ゲノムの構造とサイズ 50 |
| 3.1.3 DNA 52 |
| 3.1.4 RNA (転写) 54 |
| 3.1.5 タンパク質合成 (翻訳) 55 |
| 3.1.6 遺伝子の発現 (転写) 調節 57 |
| 3.1.7 遺伝子クローニング 58 |
| 3.1.8 PCR 法 60 |
| 3.1.9 RNA (RNA 干渉) 63 |
| 3.1.10 遺伝子の発現解析 64 |
| ■ 3.2 細胞培養と遺伝子改変植物 68 |
| 3.2.1 細胞培養の歴史 68 |
| 3.2.2 胚と不定胚 69 |
| 3.2.3 プロトプラスト 69 |
| 3.2.4 カルス 69 |
| 3.2.5 葯培養 70 |
| 3.2.6 植物への遺伝子導入 72 |
| 3.2.7 遺伝子改変農産物 77 |
| ■ 3.3 植物ホルモンと遺伝子応答 78 |
| 3.3.1 ホルモン結合タンパク質 78 |
| 3.3.2 ユビキチンの結合 79 |
| ■ 3.4 植物の生活環と生態形成にかかわる遺伝子発現 82 |
| 3.4.1 光環境 83 |
| 3.4.2 日長条件 83 |
| 3.4.3 温度 84 |
| 3.4.4 水 85 |
| ■ 3.5 生体防御の分子機構 85 |
| 4 章 生長 |
| ■ 4.1 植物の発生と生長 89 |
| 4.1.1 細胞周期 89 |
| 4.1.2 極性 90 |
| 4.1.3 植物の発生 91 |
| 4.1.4 種子の休眠 94 |
| 4.1.5 発芽 96 |
| 4.1.6 根の生長 97 |
| 4.1.7 葉の生長 98 |
| 4.1.8 茎の生長 99 |
| 4.1.9 側芽の生長 99 |
| ■ 4.2 水ポテンシャル 100 |
| 4.2.1 細胞の生長 100 |
| 4.2.2 浸透圧 101 |
| 4.2.3 浸透圧と溶質濃度 102 |
| 4.2.4 浸透圧と吸収力 103 |
| 4.2.5 水の蒸発 104 |
| 4.2.6 水ポテンシャルとは何か 105 |
| ■ 4.3 細胞壁の構造と細胞壁伸展 106 |
| 4.3.1 細胞壁の意義 106 |
| 4.3.2 細胞壁の役割 107 |
| 4.3.3 細胞壁の力学的性質の変化 108 |
| 4.3.4 細胞壁の化学的的性質 109 |
| ■ 4.4 運動 112 |
| 4.4.1 植物の運動 112 |
| 4.4.2 傾性 113 |
| 4.4.3 気孔の運動 115 |
| 4.4.4 光屈性 116 |
| 4.4.5 重力屈性 117 |
| ■ 4.5 植物ホルモン 120 |
| 4.5.1 植物ホルモンの働き 120 |
| 4.5.2 植物ホルモンとは 120 |
| 4.5.3 オーキシン 121 |
| 4.5.4 シベリン 128 |
| 4.5.5 気体のホルモン - エチレン 133 |
| 4.5.6 サイトカイニン 138 |
| 4.5.7 分化全能性(全形成能) 141 |
| 4.5.8 アブシジン酸 142 |
| 4.5.9 プラシノステロイド 145 |
| 4.5.10 ジャスモン酸 148 |
| ■ 4.6 開花 150 |
| 4.6.1 光周性 150 |
| 4.6.2 短日植物と長日植物 152 |
| 4.6.3 光受容体 156 |
| 4.6.4 花成ホルモン 158 |
| 5 章 光合成と代謝 |
| ■ 5.1 光合成 163 |
| 5.1.1 太陽エネルギーと光合成 163 |
| 5.1.2 葉の内部をのぞく 165 |
| 5.1.3 流れ込む二酸化炭素 168 |
| 5.1.4 陽葉と陰葉 170 |
| ■ 5.2 光による反応 172 |
| 5.2.1 葉緑体 172 |
| 5.2.2 クロロフィル 174 |
| 5.2.3 光化学反応のしくみ 179 |
| 5.2.4 光によらない反応 - 炭酸固定 - 181 |
| 5.2.5 C₄ 植物 182 |
| 5.2.6 C₃ 植物と C₄ 植物の比較 184 |
| 5.2.7 CAM 植物 187 |
| 5.2.8 環境要因と光合成量 189 |
| ■ 5.3 呼吸とエネルギー利用 193 |
| 5.3.1 代謝 193 |
| 5.3.2 呼吸作用 - 炭水化物の代謝 195 |
| 5.3.3 エネルギーの通貨 ATP 196 |
| 5.3.4 糖の分解 - 解糖系 198 |
| 5.3.5 トリカルボン酸回路 199 |
| 5.3.6 電子伝達系 200 |
| 5.3.7 脂肪やタンパク質からも ATP ができる 203 |
| 5.3.8 呼吸の調節 203 |
| 5.3.9 アミノ酸の生合成 204 |
| 5.3.10 芳香族化合物の合成 205 |
| 5.3.11 メバロン酸経路 207 |
| 5.3.12 ポルフィリン 208 |
| 5.3.13 核酸の合成 208 |
| 5.3.14 タンパク質の合成 211 |
| 5.3.15 多糖の合成 211 |
| 5.3.16 細胞壁の合成 212 |
| 6 章 栄養 |
| ■ 6.1 無機物資 215 |
| 6.1.1 必須元素とその他の重要元素 215 |
| 6.1.2 元素の生理作用と欠乏症 216 |
| 6.1.3 土壌の主成分ケイ素とアルミニウム 219 |
| 6.1.4 水と無機物資の移動、膜輸送 220 |
| 6.1.5 無機塩類の吸収と土壌 221 |
| 6.1.6 土壌液の水素イオン濃度 (pH) 221 |
| 6.1.7 塩分ストレス 222 |
| ■ 6.2 窒素代謝 222 |
| 6.2.1 窒素栄養 222 |
| 6.2.2 窒素固定 223 |
| 6.2.3 根粒 224 |
| 6.2.4 窒素の代謝 225 |
| 参考文献 227 |
| 索引 229 |
| 1 章 植物生理学とは |
| ■ 1.1 植物とその生理現象 1 |
| 1.1.1 植物と人間 3 |
|
| 43.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
宮崎浩一 , 向殿政男共著
| 出版情報: |
東京 : 日本規格協会, 2007.6 219p ; 21cm |
| シリーズ名: |
安全の国際規格 ; 2 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 第1章 ISO 12100 について |
| 1.1 ISO 12100 成立の背景と経緯 9 |
| 1.2 ISO 12100-1と ISO 12100-2 の概要と関係について 11 |
| 1.2.1 ISO 12100-1,-2 の概要 11 |
| 1.2.2 ISO 12100 の適用範囲 12 |
| 1.3 用 語 16 |
| 1.4 リスクアセスメント 18 |
| 1.4.1 機械類の制限の決定 19 |
| 1.4.2 危険源の同定 21 |
| 1.4.3 リスク見積り 24 |
| 1.4.4 リスクの評価 24 |
| 1.5 3ステップメソッド/保護方策 26 |
| 1.6 ISO 12100 とその他の規格との関係 29 |
| 第2章 本質的安全設計方策 |
| 2.1 制御システムへの本質的安全設計方策の適用 37 |
| 2.2 ISO 13849-1 に基づく制御システムの安全関連部設計方策 42 |
| 2.2.1 制御システム設計のためのプロセス 44 |
| 2.2.2 設計における考慮事項 46 |
| 2.2.3 安全機能特性 47 |
| 2.2.4 カテゴリ 52 |
| 2.2.5 カテゴリの選択 66 |
| 2.2.6 不具合(障害)の除外 67 |
| 2.2.7 ISO 13849-1:2006 (制御システムの安全関連部-第1部:設計のための一般原則) 67 |
| 2.3 本質的安全設計方策(非制御手段による方策) 74 |
| 2.3.1 幾何学的要因を考慮することによる本質的安全設計方策 74 |
| 2.3.2 物理的要因を考慮することによる本質的安全設計方策 86 |
| 2.3.3 構成品間のポジティブな機械的作用原理の適用 98 |
| 2.3.4 安定性に関する規定 100 |
| 2.3.5 保全性に関する規定 100 |
| 2.3.6 人間工学原則の遵守 101 |
| 2.3.7 電気的危険源の防止 107 |
| 第3章 安全防護策 |
| 3.1 機械安全における安全防護策の分類 115 |
| 3.2 安全防護物の選択について 116 |
| 3.3 ガード 118 |
| 3.3.1 ガード選択のためのアプローチ 119 |
| 3.3.2 ガードの設計及び製作原則 120 |
| 3.3.3 各種ガードの例 125 |
| 3.4 保護装置 127 |
| 3.4.1 進入・存在検知装置 127 |
| 3.4.2 進入・存在検知装置と安全距離について 137 |
| 3.4.3 保護装置-制御システムと連携する装置 140 |
| 3.4.4 インターロック装置と共同するガード(インターロックガード) 147 |
| 第4章 付加保護方策 157 |
| 第5章 使用上の情報 165 |
| 付録1 ISO 12100 の体系を構成する規格一覧 169 |
| 付録2 厚生労働省 ”機械の包括的な安全基準に関する指針” 181 |
| 用語集 197 |
| 索 引 213 |
| 第1章 ISO 12100 について |
| 1.1 ISO 12100 成立の背景と経緯 9 |
| 1.2 ISO 12100-1と ISO 12100-2 の概要と関係について 11 |
|
| 44.
|
 図書
図書
|
ソルジェニツィン [著] ; 小笠原豊樹訳
| 出版情報: |
東京 : 新潮社, 1969.2 2冊 ; 20cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 45.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
日本化学会編
目次情報:
続きを見る
| 1化学物質の安全な取扱い 1 |
| 2化学物質の潜在危険性 5 |
| 2.1はじめに 5 |
| 2.2化学物質の潜在危険性による分類 7 |
| 2.2.1国連危険物分類 7 |
| 2.2.2その他 12 |
| 2.3発火・爆発性物質 15 |
| 2.3.1発火と爆発 15 |
| 2.3.2発火・爆発性物質 34 |
| 2.3.3引火性・可燃性物質 39 |
| 2.3.4酸化性物質 41 |
| 2.4高圧ガス 42 |
| 2.4.1高圧状態のガスの危険性 43 |
| 2.4.2可燃性ガス 44 |
| 2.4.3支燃性ガス 45 |
| 2.4.4分解爆発性ガス 46 |
| 2.5有害性物質 46 |
| 2.5.1毒性 46 |
| 2.5.2化学物質の生体への侵入経路 47 |
| 2.5.3化学物質の生体への影響 49 |
| 2.5.4毒性試験法と基準値 50 |
| 2.5.5関連法規 52 |
| 2.6特殊材料ガス 54 |
| 2.6.1発火・爆発危険性 54 |
| 2.6.2毒性 57 |
| 2.7腐食性物質 59 |
| 2.7.1腐食性 59 |
| 2.7.2腐食性物質 60 |
| 2.8放射性物質 63 |
| 2.8.1放射線とその人体への影響 63 |
| 2.8.2放射性物質 69 |
| 2.9バイオハザード関連物質 72 |
| 2.9.1生物系実験とバイオハザード 72 |
| 2.9.2遺伝子組換え生物など 74 |
| 2.9.3放射性物質 75 |
| 2.9.4化学変異剤および発がん剤など 76 |
| 2.9.5有機溶媒 76 |
| 2.9.6その他 77 |
| 2.10環境汚染物質 77 |
| 2.10.1化学物質と環境汚染 77 |
| 2.10.2環境汚染物質 79 |
| 3化学反応の潜在危険性 83 |
| 3.1はじめに 83 |
| 3.2単位反応と潜在危険性 84 |
| 3.2.1単位反応 84 |
| 3.2.2単位反応の潜在危険性 84 |
| 3.3混合危険と混触発火 86 |
| 3.3.1混合危険・混触発火とは 86 |
| 3.3.2混合危険・混触発火の例 88 |
| 4化学物質および化学反応の事故例と教訓 91 |
| 4.1はじめに 91 |
| 4.2化学物質による事故例 93 |
| 4.2.1爆発性物質 93 |
| 4.2.2自然発火性物質 96 |
| 4.2.3自己発熱性物質 96 |
| 4.2.4禁水性物質 97 |
| 4.2.5引火性・可燃性物質 98 |
| 4.2.6酸化性物質 99 |
| 4.2.7高圧ガス・特殊材料ガス 101 |
| 4.2.8有害性物質 101 |
| 4.2.9腐食性物質 104 |
| 4.2.10放射性物質 104 |
| 4.2.11バイオハザード関連物質 105 |
| 4.2.12環境汚染物質 105 |
| 4.2.13その他 105 |
| 4.3化学反応の事故例 110 |
| 4.3.1単位反応 110 |
| 4.3.2混合による発火・発熱 117 |
| 4.3.3誤混合による有害性物質の発生 118 |
| 4.4事故例による教訓と事故防止 119 |
| 4.4.1化学物質の潜在危険性に関する知識 119 |
| 4.4.2化学物質の純度 120 |
| 4.4.3使用容器の強度材質 121 |
| 4.4.4実験規模 121 |
| 4.4.5ガラス器具 121 |
| 4.4.6その他 123 |
| 5化学物質の安全な取扱い 125 |
| 5.1はじめに 125 |
| 5.2化学物質の潜在危険性調査 126 |
| 5.2.1発火・爆発危険性 126 |
| 5.2.2有害危険性 140 |
| 5.2.3環境汚染性 143 |
| 5.3化学反応の潜在危険性調査 150 |
| 5.3.1単位反応 150 |
| 5.3.2混合危険反応 160 |
| 5.4化学物質各論 164 |
| 5.4.1発火・爆発性物質 164 |
| 5.4.2高圧ガス 171 |
| 5.4.3有害性物質 173 |
| 5.4.4特殊材料ガス 178 |
| 5.4.5腐食性物質 181 |
| 5.4.6放射性物質 183 |
| 5.4.7バイオハザード関連物質 194 |
| 5.4.8環境汚染物質 198 |
| 5.5化学反応各論 199 |
| 5.5.1単位反応 199 |
| 5.5.2混合危険反応 206 |
| 6化学物質の安全な廃棄 211 |
| 6.1はじめに 211 |
| 6.2化学物質の廃棄における危険性 211 |
| 6.2.1発火・爆発危険 211 |
| 6.2.2環境汚染危険 220 |
| 6.2.3放射性廃棄物 223 |
| 6.2.4バイオ関連廃棄物 225 |
| 6.3減量化(不要・不明薬品) 226 |
| 6.4廃棄物と排ガスの安全な取扱いと処理 227 |
| 6.4.1分別収集 227 |
| 6.4.2処理 232 |
| 6.4.3環境汚染防止のための分析 239 |
| 7予防と救急 241 |
| 7.1はじめに 241 |
| 7.2衛生管理 242 |
| 7.2.1健康管理 242 |
| 7.2.2環境管理(作業環境管理) 244 |
| 7.2.3作業管理 247 |
| 7.2.4保護具 248 |
| 7.3救急措置 252 |
| 7.3.1救急隊・病院への連絡 253 |
| 7.3.2事故の報告 253 |
| 7.3.3応急処置の一般的注意事項 253 |
| 7.3.4薬品による傷害のある応急処置 254 |
| 7.3.5外傷の処置 256 |
| 7.3.6熱傷 256 |
| 7.3.7骨折・ねんざ 257 |
| 7.3.8感電 257 |
| 7.3.9酸素欠乏 257 |
| 7.3.10心肺蘇生法 258 |
| 8実験環境の安全 259 |
| 8.1はじめに 259 |
| 8.2安全管理 260 |
| 8.3安全教育 263 |
| 8.3.1安全教育の目的 263 |
| 8.3.2法的要求 263 |
| 8.3.3実施方法 264 |
| 8.3.4実施内容とマニュアル 265 |
| 8.4安全点検 266 |
| 8.5実験室の安全設計 268 |
| 8.5.1リスク低減を考慮した実験室の設計 269 |
| 8.5.2化学物質の貯蔵と使用 270 |
| 8.5.3その他 272 |
| 8.6実験室の安全設備 272 |
| 8.6.1薬品の貯蔵と保管 272 |
| 8.6.2防災器具と機材 275 |
| 8.7実験室の安全作業環境 277 |
| 8.7.1作業環境管理 278 |
| 8.7.2作業管理 279 |
| 8.7.3健康管理 279 |
| 8.8化学物質の安全管理システム 280 |
| 8.8.1薬品管理体制 281 |
| 8.8.2薬品の性状把握 281 |
| 8.8.3薬品管理システム 282 |
| 8.9防火と消火 283 |
| 8.9.1可燃物の管理 283 |
| 8.9.2着火源の管理 284 |
| 8.9.3消防用設備と消防訓練 284 |
| 8.10地震対策 286 |
| 8.10.1地震と薬品出火 286 |
| 8.10.2化学物質の地震対策 289 |
| 8.10.3高圧ガスボンベの地震対策 291 |
| 8.10.4避難 292 |
| 8.11緊急時の措置 292 |
| 8.11.1人命救助 292 |
| 8.11.2通報連絡 293 |
| 8.11.3被害拡大阻止二次災害発生防止 293 |
| 9化学物質関連法規 295 |
| 9.1はじめに 295 |
| 9.2消防法危険物 295 |
| 9.2.1消防法危険物 295 |
| 9.2.2試験方法 298 |
| 9.3労働安全衛生法危険物 303 |
| 9.4毒物・劇物 306 |
| 9.4.1毒物及び劇物取締法 306 |
| 9.4.2保管管理方法 306 |
| 9.4.3管理体制 307 |
| 9.5高圧ガス・特殊材料ガス 308 |
| 9.5.1高圧ガス保安法 308 |
| 9.5.2特殊材料ガス 312 |
| 9.6火薬類 312 |
| 9.7放射性物質 313 |
| 9.7.1放射線防護の原則 313 |
| 9.7.2電離放射線に関する法令・規則 314 |
| 9.7.3実効線量限度および組織の等価線量限度 315 |
| 9.7.4場所による外部放射線の線量限度 315 |
| 9.7.5その他 316 |
| 9.8バイオハザード関連物質 317 |
| 9.8.1旧組換えDNA実験指針の法制化 317 |
| 9.8.2遺伝子組換え生物等規制法 317 |
| 9.8.3二種省令 318 |
| 9.9化審法対象物質 321 |
| 9.9.1対象化学物質 321 |
| 9.9.2試験方法 322 |
| 9.10PRTR法対象物質 322 |
| 9.10.1PRTR法の概要 323 |
| 9.10.2実験室におけるPRTR法 326 |
| 9.10.3PRTR法と他の法律などとの関連 327 |
| 9.11水質汚濁防止法対象物質 327 |
| 9.12大気汚染防止法対象物質 328 |
| 9.13化学物質安全管理の国際動向 328 |
| 9.14化学物質関連法規の調査 330 |
| 付表 335 |
| 付表1高圧ガスの諸性質 335 |
| 付表2引火性・可燃性物質の火災・爆発危険性 339 |
| 付表3危険性物質の取扱い方法 346 |
| 付表4有害物質の許容濃度 363 |
| 付表5発がん物質 377 |
| 付表6感作性物質 381 |
| 付表7法律により規制されている化学物質の例 383 |
| 付表8PRTR法対象物質 396 |
| 索引 413 |
| 1化学物質の安全な取扱い 1 |
| 2化学物質の潜在危険性 5 |
| 2.1はじめに 5 |
|
| 46.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
志村史夫, 小林久理眞著
| 出版情報: |
東京 : 朝倉書店, 2003.2 viii, 231p ; 21cm |
| シリーズ名: |
したしむ物理工学 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 1. 序論 1 |
| 1.1 自然科学と数学 2 |
| 1.2 数 14 |
| 1.2.1 数の歴史 14 |
| 1.2.2 数の種類 20 |
| チョット休憩●1 ピタゴラス 38 |
| 演習問題 39 |
| 2. 座標 41 |
| 2.1. 平面と空間の数量化 42 |
| 2.1.1 遠近法 42 |
| 2.1.2 座標の導入 44 |
| 2.1.3 座標変換 48 |
| 2.2 位相空間と図形の数量化 53 |
| 2.2.1 位相空間 53 |
| 2.2.2 図形の数量化 55 |
| チョット休憩●2 デカルト 57 |
| 演習問題 58 |
| 3. 関数とグラフ 59 |
| 3.1 関数の導入 60 |
| 3.1.1. 物体の運動の表現 60 |
| 3.1.2 関数発見の背景 63 |
| 3.2 n次関数 66 |
| 3.2.1 1次関数 66 |
| 3.2.2 2次関数 69 |
| 3.2.3 3次関数 73 |
| 3.2.4 4次関数 79 |
| 3.3 三角関数 80 |
| 3.4 指数関数と対数関数 83 |
| チョット休憩●3 アーベルとガロア 87 |
| 演習問題 89 |
| 4. 微分と積分 91 |
| 4.1 微分法と積分法 92 |
| 4.1.1 微分法 92 |
| 4.1.2 積分法 95 |
| 4.2 微分・積分計算 99 |
| 4.2.1 n次関数 99 |
| 4.2.2 三角関数 105 |
| 4.2.3 指数関数と対数関数 111 |
| 4.2.4 テイラー展開 121 |
| 4.3 偏微分と微分方程式 123 |
| 4.3.1 偏微分 123 |
| 4.3.2 微分方程式 126 |
| チョット休憩●4 ライプニッツとニュートン 128 |
| 演習問題 130 |
| 5. ベクトルとベクトル解析 131 |
| 5.1 ベクトルの基礎 132 |
| 5.1.1 スカラーとベクトル 132 |
| 5.1.2 ベクトルの表現 134 |
| 5.2 ベクトルの演算 136 |
| 5.2.1 和と差 136 |
| 5.2.2 積 139 |
| 5.2.3 ベクトルの微分 145 |
| 5.2.4 演算子 147 |
| 5.2.5 ベクトル演算と電磁気学 155 |
| チョット休憩●5 マックスウェル 161 |
| 演習問題 162 |
| 6. 線形代数 163 |
| 6.1 連立方程式と行列 164 |
| 6.1.1 連立方程式と解 164 |
| 6.1.2 行列 165 |
| 6.2 線形代数の物理的展開 172 |
| 6.2.1 連成振り子 172 |
| 6.2.2 量子力学 181 |
| チョット休憩●6 ケイリー 185 |
| 演習問題 187 |
| 7. 確率と統計 189 |
| 7.1 確率と統計の基礎 190 |
| 7.1.1 場合の数・順列・組み合わせ 190 |
| 7.1.2 確率と集合 194 |
| 7.1.3 確率の分布 200 |
| 7.2 物理学への応用 203 |
| 7.2.1 量子論的粒子の存在状態 203 |
| 7.2.2 スターリングの方式 208 |
| 7.2.3 ガウス分布とポアッソン分布 209 |
| チョット休憩●7 パスカル 218 |
| 演習問題 219 |
| 演習問題の解答 221 |
| 参考図書 226 |
| 索引 227 |
| 1. 序論 1 |
| 1.1 自然科学と数学 2 |
| 1.2 数 14 |
|
| 47.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
安居院猛, 中嶋正之共著
| 出版情報: |
東京 : 昭晃堂, 1990.3 2, 4, 189p ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 1 画像工学とは |
| 1.1 画像工学とは 1 |
| 1.1.1 画像工学の形成 1 |
| 1.1.2 画像工学の特徴 3 |
| 1.2 画像情報の取扱い 3 |
| 1.2.1 画像の表現 3 |
| 1.2.2 ディジタル画像について 5 |
| 1.2.3 ディジタル画像の情報量 10 |
| 演習問題 11 |
| 2 画像の表示 |
| 2.1 階調画像の表示 12 |
| 2.1.1 濃度変換について 12 |
| 2.1.2 階調画像の2値表示 16 |
| 2.2 階調画像の擬似表示 18 |
| 2.2.1 ディザ法 18 |
| 2.2.2 カラー画像の擬似表現 24 |
| 演習問題 28 |
| 3 画像の変換 |
| 3.1 空間フィルタ処理 29 |
| 3.1.1 画像の平滑化操作 30 |
| 3.1.2 画像の尖鋭化 32 |
| 3.1.3 特殊なフィルタ 35 |
| 3.2 画像のスペクトル変換 36 |
| 3.2.1 フーリエ変換について 36 |
| 3.2.2 高速フーリェ変換 41 |
| 3.2.3 多次元のフーリェ変換 41 |
| 3.2.4 画像処理への応用 43 |
| 3.3 画像のウォルシュ変換 47 |
| 3.3.1 離散的ウォルシュ変換 47 |
| 3.3.2 画像処理への応用 50 |
| 3.3.3 各種の直交変換 52 |
| 演習問題 54 |
| 4 画像の伝送 |
| 4.1 ディジタル画像信号の符号化 55 |
| 4.1.1 ディジタル信号の基本的な符号化法 55 |
| 4.1.2 線形予測法 58 |
| 4.2 テレビジョン信号の符号化法 64 |
| 4.2.1 テレビジョン信号 64 |
| 4.2.2 テレビジョン信号の高能率符号化法 68 |
| 4.3 ファクシミリ信号の符号化法 72 |
| 4.3.1 ファクシミリ装置の構成 72 |
| 4.3.2 2値ファクシミリ信号の符号化 75 |
| 4.4 線図形の符号化法 82 |
| 4.4.1 チェーンコード符号化法 82 |
| 4.4.2 直線近似化法 84 |
| 演習問題 88 |
| 5 画像の解析 |
| 5.1 線対応の画像解析 90 |
| 5.1.1 線成分の抽出 90 |
| 5.1.2 ディジタル図形の解析 93 |
| 5.1.3 輪郭線の抽出 100 |
| 5.1.4 閉曲線情報処理 102 |
| 5.2 領域対応の画像解析 105 |
| 5.2.1 テクスチャ解析 106 |
| 5.2.2 ピラミッド構造の利用 110 |
| 5.3 動画像の解析 114 |
| 5.3.1 動画像解析処理について 114 |
| 5.3.2 生物体の動きの解析 117 |
| 演習問題 121 |
| 6 画像の認識 |
| 6.1 パターン認識 123 |
| 6.1.1 パターン認識システム 123 |
| 6.1.2 パターンマッチング 125 |
| 6.1.3 画像間の距離 128 |
| 6.2 文字のパターン認識 129 |
| 6.2.1 文字の特徴を利用する方法 129 |
| 6.2.2 白地情報を用いる方法 131 |
| 6.3 図形の認識 133 |
| 6.3.1 線成分の認識 133 |
| 6.3.2 図面の認識 137 |
| 6.3.3 地図の認識 138 |
| 6.3.4 文書画像処理 141 |
| 6.4 画像のパターン認識 144 |
| 6.4.1 医用画像処理 144 |
| 6.4.2 産業応用 147 |
| 演習問題 149 |
| 7 画像情報機器 |
| 7.1 画像入力装置 152 |
| 7.1.1 画像入力システム 152 |
| 7.1.2 対話形入力装置 160 |
| 7.1.3 立体入力装置 162 |
| 7.2 画像出力装置 168 |
| 7.2.1 ハードコピー装置 168 |
| 7.2.2 ディスプレイ装置 172 |
| 7.3 動画像の記録装置 175 |
| 7.3.1 動画像記録装置 175 |
| 7.3.2 ディジタル画像記録装置 179 |
| 演習問題 180 |
| 演習問題解答 182 |
| 索引 185 |
| 1 画像工学とは |
| 1.1 画像工学とは 1 |
| 1.1.1 画像工学の形成 1 |
|
| 48.
|
 図書
図書
|
日本規格協会編集
目次情報:
続きを見る
| 基本 |
| ねじ |
| ボルト・ナット |
| バルブ |
| 管フランジ |
| シール |
| 試験 |
| その他 |
| 参考 |
| 管 |
| 管継手 |
| ストレーナ |
概要:
基本/ねじ/ボルト・ナット/バルブ/管フランジ/シール/試験/その他/参考。<br />管/管継手/管フランジ/バルブ/ストレーナ/参考。
|
| 49.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
アクチュエータシステム技術企画委員会編
| 出版情報: |
東京 : 養賢堂, 2004.12 8, 228p ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 1章 はじめに 1 |
| 1.1 圧電素子等の固体アクチュエータの発展 1 |
| 1.2 ナノメータの時代に入る 1 |
| 1.3 小形・薄形化・低価格化への対応 2 |
| 1.4 マイクロ化への挑戦 2 |
| 1.5 アクチュエータの薄形化 3 |
| 1.6 特殊環境用アクチュエータ 4 |
| 1.7 人工筋肉 4 |
| 2章 アクチュエータの原理 6 |
| 2.1 静電気力 6 |
| 2.1.1 静電アクチュエータとは 6 |
| 2.1.2 平行平板コンデンサモデル 7 |
| 2.1.3 平行平板コンデンサ型のアクチュエータ 8 |
| 2.1.4 より一般的な静電アクチュエータモデル 9 |
| 2.1.5 静電気力の限界 11 |
| 2.1.6 静電気力の寸法則 11 |
| 2.1.7 集積化アクチュエータ 12 |
| 2.1.8 パッシェンの法則 13 |
| 2.1.9 特殊雰囲気中での駆動 14 |
| 2.1.10 まとめ 14 |
| 2.2 電磁力 14 |
| 2.2.1 同期モータ 15 |
| 2.2.2 誘導モータ 15 |
| 2.2.3 リラクタンスモータ 16 |
| 2.2.4 回転磁界の生成 17 |
| 2.2.5 直流モータ 19 |
| 2.2.6 ステッピングモータ 20 |
| 2.2.7 DCおよびACサーボモータ 21 |
| 2.3 圧電効果と光圧電効果 21 |
| 2.3.1 圧電効果とその応用 22 |
| 2.3.2 圧電材料 23 |
| 2.3.3 アクチュエータからみた圧電特性 24 |
| 2.3.4 圧電アクチュエータの基本原理 27 |
| 2.3.5 圧電アクチュエータの応用 28 |
| 2.3.6 光圧電効果 30 |
| 2.4 流体圧アクチュエータ 31 |
| 2.4.1 油圧アクチュエータ 33 |
| 2.4.2 油圧サーボモータ 36 |
| 2.4.3 油圧伝動装置(HSU)およびHMT 38 |
| 2.4.4 空気圧アクチュエータ 39 |
| 2.5 機能性流体 42 |
| 2.5.1 機能性流体とは 42 |
| 2.5.2 ERF(電気粘性流体) 44 |
| 2.5.3 MRF(磁気粘性流体) 48 |
| 2.5.4 磁性流体 49 |
| 2.5.5 ECP(電界共役流体) 49 |
| 2.6 熱・相変態 51 |
| 2.6.1 相転移とアクチュエータ 51 |
| 2.6.2 固相変態と形状記憶効果 52 |
| 2.6.3 エントロピー弾性と形状記憶合金 56 |
| 2.6.4 共有結合性と形状記憶合金 58 |
| 2.7 化学変化 59 |
| 2.7.1 化学的刺激によるアクチュエータ 60 |
| 2.7.2 電気的刺激によるアクチュエータ 60 |
| 2.8 アクチュエータの基礎制御論 61 |
| 2.8.1 制御の基本的考え方 62 |
| 2.8.2 位置制御 65 |
| 2.8.3 位置制御におけるフィードバック補償例 67 |
| 2.8.4 速度制御 70 |
| 参考文献 71 |
| 3章 静電アクチュエータ 73 |
| 3.1 マイクロ静電アクチュエータ 73 |
| 3.2 高出力静電アクチュエータ 75 |
| 3.3 交流駆動両電極型静電モータ 76 |
| 3.4 高出力静電アクチュエータの特徴と期待される応用例 77 |
| 3.4.1 透明アクチュエータ 77 |
| 3.4.2 紙送り機構 78 |
| 3.4.3 フレキシブルアクチュエータ~人工筋肉~ 78 |
| 3.4.4 特殊環境用モータ 79 |
| 3.5 まとめ 80 |
| 参考文献 80 |
| 4章 球面電磁モータ 83 |
| 4.1 球面同期モータ 83 |
| 4.2 球面誘導モータ 84 |
| 4.3 球面リラクタンスモータ 84 |
| 4.4 回転磁界の生成 85 |
| 4.5 球面ステッピングモータ 86 |
| 4.6 球面モータの研究状況 89 |
| 4.6.1 球面同期モータ 89 |
| 4.6.2 球面誘導モータ 90 |
| 4.6.3 球面ステッピングモータ 91 |
| 4.7 おわりに 91 |
| 参考文献 92 |
| 5章 超音波モータ 93 |
| 5.1 超音波モータの原理 93 |
| 5.2 最近の研究動向 98 |
| 5.2.1 小型化の例(PZT薄膜を用いた円筒型マイクロモータ) 98 |
| 5.2.2 超精密制御の例(弾性表面波モータ) 99 |
| 5.2.3 大出力化の例(2組のボルト締め振動子によるリニアモータ) 102 |
| 5.2.4 多自由度化の例(多自由度超音波モータ) 103 |
| 5.3 おわりに 105 |
| 参考文献 105 |
| 6章 光アクチュエータ 107 |
| 6.1 フライバイライトの概念と光アクチュエータ 107 |
| 6.2 光アクチュエータの分類 108 |
| 6.3 直接型光アクチュエータ 109 |
| 6.3.1 光熱効果を利用した光アクチュエータその1(空気圧アクチュェータの応用) 109 |
| 6.3.2 光熱効果を利用した光アクチュエータその2(形状記憶合金の応用) 110 |
| 6.3.3 光圧電効果を利用した光アクチュエータ(PLZTセラミックスの応用) 112 |
| 6.4 自励型光アクチュエータ 115 |
| 6.5 あとがき 115 |
| 参考文献 116 |
| 7章 空気圧ラバーアクチュエータ 118 |
| 7.1 ソフトアクチュエータ 118 |
| 7.1.1 ソフトアクチュエータの概念 118 |
| 7.1.2 ソフトアクチュエータの開発 119 |
| 7.2 マイクロラバーアクチュエータ 123 |
| 7.2.1 空圧ラバーアクチュエータのマイクロ化 123 |
| 7.2.2 マイクロラバーアクチュエータの開発例 124 |
| 7.3 まとめ 129 |
| 参考文献 129 |
| 8章 機能性流体を応用したアクチュエータ 131 |
| 8.1 電界に反応する流体を応用したアクチュエータ 131 |
| 8.1.1 粒子分散系ERFアクチュエータ 131 |
| 8.1.2 粒子分散系ERPマイクロアクチュエータ 135 |
| 8.1.3 均一系ERPを応用したマイクロバルブ 137 |
| 8.2 磁界に反応する機能性流体アクチュエータ 138 |
| 8.2.1 磁性流体を応用したアクチュエータ 138 |
| 8.2.2 磁気粘性流体(MRF)を応用したアクチュエータ 139 |
| 8.2.3 MRFマイクロアクチュエータ 140 |
| 8.3 マイクロECFモータとECFアクチュエータ 142 |
| 8.4 マイクロポンプ 144 |
| 8.4.1 共振駆動型圧電マイクロポンプ 144 |
| 8.4.2 ECFジェット冷却型SMA駆動マイクロポンプ 145 |
| 8.4.3 薄形ぜん動管路型マイクロポンプ 145 |
| 8.5 まとめ 146 |
| 参考文献 147 |
| 9章 形状記憶合金アクチュエータ 149 |
| 9.1 形状記憶合金アクチュエータと動作原理 149 |
| 9.2 形状記憶合金アクチュエータの加熱駆動 156 |
| 9.3 寸法効果と形状記憶合金アクチュエータ 158 |
| 9.4 おわりに 158 |
| 参考文献 158 |
| 10章 メカノケミカルアクチュエータ 159 |
| 10.1 これまでに開発された化学的アクチュエータ材料 159 |
| 10.2 電気刺激性高分子アクチュエータ 159 |
| 10.3 イオン性高分子ゲルアクチュエータ 159 |
| 10.4 ICPFアクチュエータの特質と応用 162 |
| 10.5 ICPFアクチュエータのモデリング 165 |
| 10.4 おわりに 167 |
| 参考文献 167 |
| 11章 マイクロアクチュエータ 169 |
| 11.1 アクチュエータのスケール効果 169 |
| 11.2 加工方法 171 |
| 11.2.1 シリコンプロセス 172 |
| 11.2.2 LIGAプロセス 176 |
| 11.3 応用事例 180 |
| 11.3.1 マイクロロボット 181 |
| 11.3.2 機能性流体を応用したマイクロシステム 186 |
| 11.4 あとがき 194 |
| 参考文献 195 |
| 12章 アクチュエータの先端制御技術 198 |
| 12.1 インテリジェント制御 198 |
| 12.2 2自由度制御 200 |
| 12.3 予見学習制御 202 |
| 12.4 ロバストオブザーバ 205 |
| 12.5 おわりに 208 |
| 参考文献 208 |
| 13章 触覚ディスプレイ装置におけるアクチュエータ技術 209 |
| 13.1 触覚ディスプレイの分類 209 |
| 13.1.1 面呈示形と点提示形 209 |
| 13.1.2 スタティック形とダイナミック形 210 |
| 13.2 触覚ディスプレイ用アクチュエータ 210 |
| 13.2.1 液体圧アクチュエータ 211 |
| 13.2.2 電動モータ 211 |
| 13.2.3 圧電アクチュエータ 213 |
| 13.2.4 メカノケミカルアクチュエータ 214 |
| 13.2.5 MEMS利用アクチュェータ 215 |
| 13.2.6 電磁クラッチ 215 |
| 13.3 おわりに 216 |
| 参考文献 217 |
| あとがき―アクチュエータの研究開発について― 219 |
| 新機構アクチュエータの考案 219 |
| 製造法と使用法の研究 220 |
| 実用化への展開と課題 221 |
| 標準化と試験法の確立 221 |
| 索引 223 |
| 1章 はじめに 1 |
| 1.1 圧電素子等の固体アクチュエータの発展 1 |
| 1.2 ナノメータの時代に入る 1 |
|
| 50.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
渋谷道雄, 渡邊八一共著
| 出版情報: |
東京 : オーム社, 2003.3 xviii, 242p ; 24cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 監修のことば i |
| まえがき iii |
| 本書の使い方 iv |
| 本書を活用するための読み方の例 iv |
| 各章の概要 iv |
| 付属CD-ROMについて vi |
| CD-ROMの構成 vi |
| マクロを実行するためのセキュリティの設定 viii |
| 分析ツールのセットアップ x |
| 第1章 波とスペクトル 1 |
| 1.1 波 2 |
| 1.1.1 波のイメージ 2 |
| 1.1.2 縦波と横波 2 |
| 1.1.3 波の伝わる速さ 4 |
| 1.1.4 波の空間変化と時間変化 5 |
| 1.2 時間領域と周波数領域 8 |
| 1.2.1 波の時間変化 8 |
| 1.2.2 波の周波数 8 |
| 1.2.3 スペクトル 10 |
| 1.2.4 周波数と波長 11 |
| 第2章 フーリエ解析のための基礎知識 13 |
| 2.1 三角関数 14 |
| 2.1.1 基本となる三角関数 14 |
| 2.1.2 時間関数として取り扱う三角関数 16 |
| 2.2 関数の微分 19 |
| 2.2.1 関数の微分と差分の概念 19 |
| 2.2.2 関数の微分をExcelで確かめる 20 |
| 2.3 関数の不定積分と定積分 22 |
| 2.3.1 関数の不定積分 22 |
| 2.3.2 関数の定積分 23 |
| 2.3.3 区分求積法 24 |
| 2.4 関数の直交性 28 |
| 2.4.1 直交とは 28 |
| 2.4.2 関数の直交性の概念 29 |
| 2.4.3 関数の直交性を数値積分で確かめる 30 |
| 2.5 偶関数と奇関数 32 |
| 2.5.1 考慮すべき定義域 32 |
| 2.5.2 偶関数 32 |
| 2.5.3 奇関数 33 |
| 2.5.4 偶関数・奇関数の積 34 |
| 2.6 周期関数 36 |
| 2.6.1 周期関数の定義 36 |
| 2.6.2 関数の周期拡張 38 |
| 2.6.3 区分的に連続・区分的に滑らか 39 |
| 章末問題 42 |
| 第3章 フーリエ級数 43 |
| 3.1 三角関数による関数の合成 44 |
| 3.1.1 単一周期と位相 44 |
| 3.1.2 合成された関数の規格化 45 |
| 3.1.3 フーリエ級数 47 |
| 3.1.4 フーリエ係数 49 |
| 3.1.5 周波数成分と位相 50 |
| 3.2 ギッブス現象 52 |
| 3.2.1 ギッブス現象の具体例 52 |
| 3.2.2 ギッブス現象の大きさの推定 53 |
| 3.3 デルタ関数 55 |
| 3.3.1 デルタ関数の概念 55 |
| 3.3.2 周期的なデルタ関数列 56 |
| 3.4 フィルターとフーリエ級数 59 |
| 3.4.1 RCフィルター特性と位相情報 59 |
| 3.4.2 RCローパス・フィルターと波形 62 |
| 3.4.3 RCハイパス・フィルターの波形合成 64 |
| 3.5 フーリエ級数と数学公式 67 |
| 3.5.1 級数の和の値 67 |
| 章末問題 70 |
| 第4章 フーリエ変換(数値解析) 71 |
| 4.1 数値解析としてのフーリエ変換 72 |
| 4.1.1 サンプリング定理とナイキスト周波数 72 |
| 4.1.2 周期関数への拡張 78 |
| 4.2 スペクトルの振幅と位相情報 79 |
| 4.2.1 フーリエ解析とスペクトルの振幅 79 |
| 4.2.2 位相情報 79 |
| 4.2.3 DFTによるスペクトル 80 |
| 4.2.4 ポイント数の少ないフーリエ変換 83 |
| 4.3 非整数周期成分によるゴースト 86 |
| 4.3.1 サンプリングによる非整数周期波形の例 86 |
| 4.3.2 窓関数 87 |
| 章末問題 92 |
| 第5章 高速フーリエ変換(FFT) 93 |
| 5.1 オイラーの公式とド・モアブルの定理 94 |
| 5.1.1 虚数の性質 94 |
| 5.1.2 複素数の極座標表示 95 |
| 5.1.3 オイラーの公式 97 |
| 5.1.4 ド・モアブルの定理と1のn乗根 97 |
| 5.1.5 複素フーリエ級数 99 |
| 5.2 FFTの概念 102 |
| 5.2.1 FFTアルゴリズムの概要 102 |
| 5.2.2 16ポイントデータによるFFT 107 |
| 5.2.3 DFTとの結果の比較 112 |
| 5.2.4 Excelの分析ツールとしてのFFT 114 |
| 5.2.5 1,024、4,096ポイントへの拡張 114 |
| 章末問題 120 |
| 第6章 電気信号のフーリエスペクトル 121 |
| 6.1 方形波・台形波・三角波・のこぎり波 122 |
| 6.1.1 幾何学波形を作るワークシート 122 |
| 6.1.2 方形波 124 |
| 6.1.3 台形波 126 |
| 6.1.4 三角波 127 |
| 6.1.5 のこぎり波 128 |
| 6.2 変調信号 129 |
| 6.2.1 AM信号 129 |
| 6.2.2 FM信号 130 |
| 6.3 特殊な波形 132 |
| 6.3.1 単一パルス 132 |
| 6.3.2 単一sin波 134 |
| 6.3.3 トーンバースト 136 |
| 章末問題 138 |
| 第7章 さまざまな音のフーリエスペクトル 139 |
| 7.1 PCで扱うサウンドデータ 140 |
| 7.2 フーリエ級数による合成音 141 |
| 7.2.1 幾何学波形のWaveデータ 141 |
| 7.2.2 初期位相の異なる倍音の合成 144 |
| 7.2.3 疑似無限音階 147 |
| 7.3 サウンドデータのスペクトル 150 |
| 7.3.1 音のスペクトル 150 |
| 7.3.2 音叉のスペクトル 152 |
| 7.3.3 ハーモニカの音をスペクトルとして確かめる 156 |
| 7.3.4 声をスペクトルにして見る 158 |
| 7.3.5 鐘の音 162 |
| 7.3.6 水滴のはじける音のスペクトル 166 |
| 章末問題 172 |
| 付録A Excelの操作 173 |
| A.1 ワークシートの基本操作 174 |
| A.1.1 基本的な画面構成 174 |
| A.1.2 ヘルプの利用 175 |
| A.1.3 セルの移動とセル範囲の操作 175 |
| A.1.4 データの入力と操作 182 |
| A.2 Excelの関数 189 |
| A.2.1 関数の挿入 189 |
| A.2.2 分析ツールに含まれる関数やツール 191 |
| A.3 グラフ機能 197 |
| A.3.1 グラフ作成の概要 197 |
| A.3.2 グラフウィザードを使ったグラフの作成 198 |
| A.3.3 グラフ作成後の変更 205 |
| 付録B サウンドデータの取り扱い 209 |
| B.1 サウンド(音声)の録音 210 |
| B.1.1 PCで扱うサウンド 210 |
| B.1.2 ボリュームのコントロール 210 |
| B.1.3 サウンドレコーダーの概要 213 |
| B.2 Waveファイルをワークシートに取り込む 217 |
| B.3 ワークシートのデータからWaveファイルを作る 221 |
| 付録C 章末問題解答 225 |
| 第2章 章末問題解答 226 |
| 第3章 章末問題解答 230 |
| 第4章 章末問題解答 232 |
| 第5章 章末問題解答 234 |
| 第6章 章末問題解答 235 |
| 第7章 章末問題解答 238 |
| 索引 240 |
| 監修のことば i |
| まえがき iii |
| 本書の使い方 iv |
|
| 51.
|
 図書
図書
|
畠山史郎, 三浦和彦編著
| 出版情報: |
東京 : 成山堂書店, 2014.5 viii, 160p, 図版 [8] p ; 19cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 1 PM2.5とは? : PM2.5とはそもそも何なのでしょうか? |
| PM2.5とはどんな物質ですか? ほか |
| 2 PM2.5の発生と輸送 : PM2.5はどこから発生しているのでしょうか? |
| 森林もPM2.5の発生源となると聞きましたが本当ですか? ほか |
| 3 PM2.5の影響と対策 : PM2.5を吸入することによりどのような病気になるおそれがあるのですか? |
| PM2.5などの粒子状物質は植物に対して影響があるのでしょうか? ほか |
| 4 光化学スモッグ・黄砂・エアロゾル : 光化学スモッグとPM2.5は関係あるのでしょうか? |
| PM2.5と同じく中国から飛んでくる黄砂とはどう違うのですか? ほか |
| 1 PM2.5とは? : PM2.5とはそもそも何なのでしょうか? |
| PM2.5とはどんな物質ですか? ほか |
| 2 PM2.5の発生と輸送 : PM2.5はどこから発生しているのでしょうか? |
|
| 52.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
池田駿介著
| 出版情報: |
東京 : 技報堂出版, 1999.1 xiv, 435p ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 第1部 粘性を無視できる流れ |
| 第1章 基礎的事項 1 |
| 1.1 序 1 |
| 1.1.1 流体力学と水理学 1 |
| 1.1.2 流体の定義-連続体 1 |
| 1.1.3 流体の物性 2 |
| 1.1.4 完全流体と粘性流体 2 |
| 1.2 未知量と運動方程式・質量保存式 3 |
| 1.2.1 流れの未知量 3 |
| 1.2.2 運動方程式と質量保存式 3 |
| 1.2.3 ベクトル表示したEulerの運動方程式と質量保存式 8 |
| 1.2.4 流体の変形 9 |
| 1.2.5 渦度循環 11 |
| 1.2.6 渦の不生不滅 12 |
| 1.3 速度ポテンシャルと流れ関数 14 |
| 1.3.1 速度ポテンシャル 14 |
| 1.3.2 流線と流れ関数 14 |
| 1.3.3 共役関数 16 |
| 第2章 エネルギー保存則 19 |
| 2.1 一般化されたBernoulli(ベルヌーイ)の定理 19 |
| 2.2 一般化されたBernoulliの定理の簡単な応用例 20 |
| 2.2.1 静水圧 20 |
| 2.2.2 Torricelli(トリチェリー)の定理 22 |
| 2.2.3 Pitot(ピトー)管 25 |
| 2.3 流線に沿うBernoulliの定理 27 |
| 2.3.1 流線に沿うEulerの運動方程式と質量保存式 27 |
| 2.3.2 流線に沿うBernoulliの定理とエネルギーフラックス 30 |
| 2.3.3 流管に関する平均的エネルギー保存則 31 |
| 2.4 Bernoulliの定理の応用 33 |
| 2.4.1 U字管振動 33 |
| 2.2.2 Venture(ベンチュリ)管 35 |
| 2.2.3 スルースゲートからの流出 36 |
| 2.2.4 水面を伝わる波 38 |
| 2.5 比エネルギー 39 |
| 2.5.1 比エネルギーの定義 39 |
| 2.5.2 限界水深 42 |
| 2.6 比エネルギーの応用 45 |
| 2.6.1 突起上の流れの水面特性 45 |
| 2.6.2 ダムの流量公式 47 |
| 2.6.3 幅が変化する流れの水面形 47 |
| 第3章 速度ポテンシャルを持つ2次元流れ 49 |
| 3.1 複素速度ポテンシャル 49 |
| 3.2 複素速度ポテンシャルの簡単な応用 51 |
| 3.2.1 一様流 51 |
| 3.2.2 隅を曲がる流れ 52 |
| 3.2.3 角を曲がる流れ 53 |
| 3.2.4 渦(vortex) 54 |
| 3.2.5 湧き出しと吸い込み 56 |
| 3.2.6 二重湧き出し 56 |
| 3.2.7 円柱まわりの流れ 58 |
| 3.2.8 円柱に働く力 60 |
| 3.3 写像変換の利用 63 |
| 3.3.1 Schwartz・Christoffelの定理 63 |
| 3.3.2 Schwartz・Christoffelの定理の応用 64 |
| 3.3.3 Joukowski変換 70 |
| 3.3.4 Joukowski変換の応用 70 |
| 3.4 フローネット(flow net)の方法 76 |
| 3.4.1 フローネットの理論 76 |
| 3.4.2 フローネットの描き方 78 |
| 3.4.3 圧力 p の求め方 79 |
| 3.4.4 フローネットの応用 80 |
| 3.5 変数分離法の利用-波 82 |
| 3.5.1 波動運動の特性 82 |
| 3.5.2 波動運動の支配方程式 82 |
| 3.5.3 微小振幅波 83 |
| 3.5.4 変数分離法の適用 84 |
| 3.5.5 波の分類 87 |
| 3.5.6 水粒子の軌跡 88 |
| 3.5.7 群速度 90 |
| 3.5.8 波のエネルギー 91 |
| 3.5.9 重複波とセイシュ 93 |
| 第4章 運動量保存則 95 |
| 4.1 運動量保存則 95 |
| 4.2 運動量保存則とEulerの運動方程式の関係 96 |
| 4.3 流管における定常流の運動量保存則 98 |
| 4.4 流管に関する平均的運動量保存則 99 |
| 4.5 運動量保存則の応用 100 |
| 4.5.1 曲がった管に作用する力 100 |
| 4.5.2 水槽からの噴流 101 |
| 4.5.3 スルースケートからの流出 103 |
| 4.6 開水路への応用 104 |
| 4.6.1 比力 104 |
| 4.6.2 比力図 105 |
| 4.6.3 比力と比エネルギーの関係 106 |
| 4.6.4 跳水 107 |
| 4.6.5 段波 109 |
| 4.6.6 開水路の衝撃波 110 |
| 第2部 粘性がある流れ |
| 第5章 粘性がある流れの基礎的事項 115 |
| 5.1 運動方程式と質量保存式 115 |
| 5.1.1 運動方程式 115 |
| 5.1.2 内部応力の性質 116 |
| 5.1.3 Navier・Stokesの運動方程式と連続式 118 |
| 5.1.4 ベクトル表示したNavier・Stokesの運動方程式 118 |
| 5.2 Navier・Stokesの運動方程式の厳密解と粘性の役割 119 |
| 5.2.1 Rayleigh(レイリー)の第1問題-瞬間的に運動を始めた平板上の流れ 119 |
| 5.2.2 Rayleighの第2問題-振動平板による流れ 121 |
| 5.2.3 平行平板間の流れ 123 |
| 5.2.4 粘性によるエネルギー逸散 124 |
| 5.3 層流と乱流 126 |
| 5.3.1 層流と乱流の概念-Reynoldsの実験 126 |
| 5.3.2 層流から乱流への遷移-限界Reynolds数 127 |
| 5.3.3 Reynolds応力 127 |
| 5.3.4 壁乱流と自由乱流,Prandtl(プラントル)の混合距離理論 131 |
| 第6章 遅い流れと速い流れ 133 |
| 6.1 Navier・Stokesの運動方程式とReynolds数 133 |
| 6.2 遅い流れ 133 |
| 6.2.1 遅い流れの運動方程式 133 |
| 6.2.2 地下水の流れ 134 |
| 6.2.3 1次元の地下水流れ 136 |
| 6.2.4 2次元の地下水流れ 138 |
| 6.2.5 透水試験 142 |
| 6.2.6 Hele・Shaw(ヘル・ショー)流れ 143 |
| 6.2.7 球のまわりの遅い流れ-Stokes近似 145 |
| 6.3 速い流れ : 大きなReynolds数を持つ流れ 150 |
| 6.3.1 境界層の概念 150 |
| 6.3.2 層流境界層方程式一境界層近似 150 |
| 6.3.3 平板上の層流境界層Blasius(ブラジウス)の流れ 153 |
| 6.3.4 境界層の運動量方程式 157 |
| 6.3.5 層流から乱流への遷移-安定解析 159 |
| 6.3.6 滑らかな平板上の乱流境界層 161 |
| 6.4 流れの剥離 165 |
| 6.4.1 圧力勾配の影響 165 |
| 6.4.2 流れの剥離(separation) 166 |
| 6.4.3 Karman渦列 168 |
| 6.5 流体力 169 |
| 6.5.1 流体力のまとめ 169 |
| 6.5.2 定常流体力 169 |
| 6.5.3 非定常流体力 173 |
| 6.6 流体力による振動 174 |
| 6.6.1 渦励振 174 |
| 6.6.2 ギャロッピング(galloping) 175 |
| 6.6.3 フラッター(trosional galloping) 178 |
| 6.6.4 バフェッティング(buffeting)と不規則応答解析 179 |
| 第7章 管路の流れ 181 |
| 7.1 円管内の層流 : Hagen・Poiseuilleの流れ 181 |
| 7.2 円管内の乱流 183 |
| 7.2.1 圧力分布とせん断力分布 183 |
| 7.2.2 流速分布 185 |
| 7.3 円管内流れの摩擦抵抗と運動量およびエネルギー保存則 191 |
| 7.3.1 運動量保存則 191 |
| 7.3.2 エネルギー保存則 193 |
| 7.4 摩擦水頭損失 : Darcy・Weisbachの式 194 |
| 7.4.1 層流-Hagen・Poiseuille流れの摩擦抵抗係数(摩擦損失係数) 194 |
| 7.4.2 乱流の摩擦抵抗係数 195 |
| 7.4.3 一様砂を貼り付けた円管のf-Re関係 197 |
| 7.4.4 実用管のf-Re関係 197 |
| 7.5 摩擦水頭損失以外の水頭損失 201 |
| 7.5.1 一般的事項 201 |
| 7.5.2 断面変化による水頭損失 201 |
| 7.5.3 曲がりによる水頭損失 207 |
| 7.5.4 弁による水頭損失 208 |
| 7.5.5 その他の水頭損失 209 |
| 7.6 単一管路の流れ 209 |
| 7.6.1 水槽間をつなぐ管路の流れ 209 |
| 7.6.2 水槽から管路を経て空中に流れが放出している場合 210 |
| 7.6.3 サイフォン 211 |
| 7.6.4 エネルギーの供給,取り出しがある流れ 212 |
| 7.7 複合管路の流れ 213 |
| 7.8 管路の非定常流れ 214 |
| 7.8.1 円管内の層流振動流 214 |
| 7.8.2 円管内振動層流の乱流遷移と乱流摩擦抵抗則 216 |
| 7.8.3 水撃圧 217 |
| 7.8.4 その他の非定常流現象 229 |
| 第3部 やや複雑な乱流とモデリング |
| 第8章 自由乱流 235 |
| 8.1 自由乱流の性質と支配方程式 235 |
| 8.2 静止流体中に流出する2次元噴流 236 |
| 8.3 2次元後流 240 |
| 第9章 開水路の流れ 245 |
| 9.1 開水路流れの特徴と種類 245 |
| 9.2 開水路流れの抵抗則 246 |
| 9.2.1 平均流速公式 246 |
| 9.2.2 Manningの粗度係数と対数速度分布から得られる抵抗則の関係 250 |
| 9.3 等流 251 |
| 9.4 漸変流 : 緩やかに変化する不等流 252 |
| 9.4.1 基礎方程式率 252 |
| 9.4.2 水面形の方程式 253 |
| 9.4.3 水面形の分類 254 |
| 9.4.4 水面形の出現例 255 |
| 9.4.5 不等流計算-Bresseの公式 256 |
| 9.4.6 勾配が変わる流れ 257 |
| 9.4.7 不等流計算の応用 259 |
| 9.4.8 横流出・流入がある流れ 261 |
| 9.5 開水路の2次元流れ 266 |
| 9.5.1 開水路2次元流れの特徴 266 |
| 9.5.2 浅水流方程式 266 |
| 9.5.3 渦動粘性係数の値 270 |
| 9.5.4 平面2次元流れの例 272 |
| 9.5.5 湾曲部の2次流 282 |
| 9.6 開水路の非定常流 286 |
| 9.6.1 開水路非定常流の基礎方程式 286 |
| 9.6.2 洪水流 288 |
| 第10章 乱流理論と乱流のモデリング 299 |
| 10.1 乱れの表示法 299 |
| 10.1.1 相関係数 299 |
| 10.1.2 スペクトル 300 |
| 10.2 等方性乱流 300 |
| 10.2.1 等方性乱流の相関係数 301 |
| 10.2.2 Karman・Howarthの方程式 304 |
| 10.2.3 次元スペクトル 306 |
| 10.2.4 エネルギーの移行過程とスペクトル構造の決定 310 |
| 10.3 せん断乱流 313 |
| 10.3.1 せん断乱流の特徴 313 |
| 10.3.2 乱れのエネルギー方程式 314 |
| 10.3.3 円管内乱流のエネルギーバランス 316 |
| 10.4 乱流モデル 317 |
| 10.4.1 0方程式モデル 317 |
| 10.4.2 1方程式モデル 318 |
| 10.4.3 2方程式モデル 319 |
| 10.4.4 ラージ・エディー・シミュレーション(LES) 320 |
| 10.4.5 SDS-2DHモデル-浅水流の乱流モデル 324 |
| 第4部 自然界の流れと環境水理学 |
| 第11章 拡散と分散 327 |
| 11.1 Fickの拡散方程式 327 |
| 11.1.1 Fickの法則 327 |
| 11.1.2 拡散方程式 328 |
| 11.2 Taylorの拡散理論 329 |
| 11.3 相対拡散 329 |
| 11.2.1 拡散とLagrange相関 332 |
| 11.2.2 拡散とスペクトル 332 |
| 11.4 分散 334 |
| 11.4.1 開水路の分散現象 334 |
| 11.4.2 地下水の分散現象 337 |
| 第12章 密度差を伴う流れ 339 |
| 12.1 日射と熱 339 |
| 12.1.1 日射と熱収支 339 |
| 12.2 密度成層流の基礎方程式 341 |
| 12.2.1 Boussinesq近似 341 |
| 12.2.2 密度差の存在と渦度 342 |
| 12.2.3 密度流を支配する無次元数 342 |
| 12.2.4 成層流体のBernoulliの定理 345 |
| 12.3 2層流体の流れ 346 |
| 12.3.1 2層流体間の波-内部波 346 |
| 12.3.2 塩水くさび 348 |
| 12.3.3 界面抵抗係数 352 |
| 12.3.4 選択取水 354 |
| 12.3.5 内部跳水 356 |
| 12.4 連続成層流 358 |
| 12.4.1 線形密度成層からの2次元吸い込み 358 |
| 12.4.2 不安定成層流 360 |
| 12.5 その他の密度流 365 |
| 12.5.1 密度噴流,プルーム,サーマル 365 |
| 12.5.2 2次元表面密度噴流 366 |
| 第13章 移動床の水理学 371 |
| 13.1 土砂輸送形態と移動床形態 371 |
| 13.2 土砂輸送 373 |
| 13.2.1 限界掃流力 373 |
| 13.2.2 流下方向掃流砂量 377 |
| 13.2.3 有効せん断力 380 |
| 13.2.4 横断方向掃流砂量 380 |
| 13.2.5 浮遊砂 383 |
| 13.2.6 ウォッシュ・ロード 386 |
| 13.3 河床波 386 |
| 13.3.1 砂碓と反砂碓の形成機構 386 |
| 13.3.2 交互砂州 391 |
| 13.4 局所洗掘 392 |
| 13.4.1 橋脚付近の洗掘 393 |
| 13.4.2 一様湾曲部の河床形状 393 |
| 13.5 河道形状 395 |
| 13.5.1 蛇行流路の発達 395 |
| 13.5.2 礫河川の安定横断形状 400 |
| 第14章 その他の環境水理学 407 |
| 14.1 植生の水理学 407 |
| 14.1.1 沈水植物 407 |
| 14.1.2 抽水植物 409 |
| 14.2 不飽和浸透流 411 |
| 14.3 回転系の流体力学 412 |
| 14.3.1 回転系のNavier・Stokes方程式 412 |
| 14.3.2 Ekman流 413 |
| 14.3.3 地衡流 414 |
| 14.3.4 Rossby波 415 |
| 14.3.5 Kelvin波 417 |
| 参考文献 419 |
| 付録 422 |
| 付録1 水理学の分野でよく現れる物理量 422 |
| 付録2 Gaussの公式 425 |
| 付録3 Stokesの公式 425 |
| 付録4 円筒座標系におけるNavier・Stokesの方程式 426 |
| 付録5 球極座標系におけるNavier・Stokesの方程式 427 |
| 付録6 円筒座標系におけるReynoldsの方程式 428 |
| 索引 429 |
| 第1部 粘性を無視できる流れ |
| 第1章 基礎的事項 1 |
| 1.1 序 1 |
|
| 53.
|
 図書
図書
|
| 出版情報: |
東京 : サイエンスフォーラム, 1979-1982 4冊 ; 31 cm |
| シリーズ名: |
ライフサイエンスシリーズ |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 54.
|
 図書
図書
|
木田茂夫[等]著
|
| 55.
|
 図書
図書
|
ア・ゲ・クローシュ著 ; 吉崎敬夫訳
| 出版情報: |
東京 : 商工出版社, 1960-1961 2冊 ; 22cm |
| シリーズ名: |
数学選書 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 56.
|
 図書
図書
|
藤田宏, 今野礼二著
|
| 57.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
河村雄行著
| 出版情報: |
東京 : 海文堂出版, 1990.6 v, 141p ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 1 分子シミュレーション-無機擬集体科学との関連- 1 |
| 2 分子動力学法-相互作用モデルと計算アルゴリズム- |
| 2.1 基本原理と歴史 7 |
| 2.1.1 分子動力学法の基本概念 7 |
| 2.1.2 対象となる物質系 10 |
| 2.1.3 なぜ分子動力学法か 13 |
| 2.1.4 MD法の歴史 15 |
| 2.2 粒子間に働く作用-原子・分子間のポテンシャル 17 |
| 2.2.1 2体中心力ポテンシャル 18 |
| 2.2.2 酸化物擬縮体における原子間ポテンシャルとパラメータ 17 |
| 2.2.2 酸化物擬縮体における原子間ポテンシャルとパラメータ 20 |
| 2.2.3 より現実的な原子間ポテンシャルの必要性 28 |
| 2.3 MD法の基本式 32 |
| 2.3.1 エネルギーと力の計算 32 |
| 2.3.2 クーロンエネルギーと力の計算 32 |
| 2.3.3 粒子の動かし方 38 |
| 2.3.4 温度と圧力の計算と制御 44 |
| 2.4 結晶のMD計算 48 |
| 2.4.1 基本セルと部分座標 50 |
| 2.4.2 結晶構造データからの初期データ(座標)の生成 50 |
| 2.4.3 対称性と原子間ポテンシャル(酸化物ペロフスカイト) 56 |
| 2.4.4 位置の秩序-無秩序型相転移(Sio2多形の低温-高温転移) 58 |
| 2.4.5 今後の問題 61 |
| 2.5 計算可能な物理・化学量 63 |
| 2.5.1 構造と回折 63 |
| 2.5.2 熱力学的性質と物性 68 |
| 2.5.3 動的性質 68 |
| 2.6 MD法の発展のために 69 |
| 3 分子動力学実験装置-パソコンの能力の使い方- |
| 3.1 パソコンとMD計算 71 |
| 3.2 パソコンの能力 72 |
| 3.2.1 パソコンの能力と限界を規定するもの 73 |
| 3.2.2 基本ソフトウェア 78 |
| 3.2.3 パソコンとエンジニアリングワークステーション 80 |
| 3.2.4 計算機と言語の使い分け 81 |
| 3..3 パソコンMD計算手法 82 |
| 3.3.1 記憶領域の節約手法 82 |
| 3.3.2 高速化の手法 83 |
| 3.4 パソコングラフィックスを駆使した結果の解析 83 |
| 3.4.1 パソコングラフィックの機能 83 |
| 3.4.2 パソコングラフィックの実際 84 |
| 3.5 パソコンMD計算システムの設計 85 |
| 4 分子動力学実験の実際-プログラムの使い方と計算例- |
| 4.1 パソコンMD計算システム 87 |
| 4.1.1 特徴 87 |
| 4.1.2 MD計算のための計算機システム 88 |
| 4.1.3 システム構成 89 |
| 4.1.4 ソースプログラムの取り扱い 92 |
| 4.1.5 いくつかのBASICプログラム 95 |
| 4.2 外部ファイルと入出力情報 96 |
| 4.2.1 初期データの作成 96 |
| 4.1.2 MD計算の制御データと実行 99 |
| 4.2.3 データファイルの構造 102 |
| 4.2.4 標準出力ファイル(FILE06.DAT)の読み方 105 |
| 4.3 MD計算の実際 111 |
| 4.3.1 結晶のMD計算 111 |
| 4.3.2 融体/ガラスのMD計算 118 |
| 付録 MDORTOプログラムリスト(抜粋) 125 |
| 1 分子シミュレーション-無機擬集体科学との関連- 1 |
| 2 分子動力学法-相互作用モデルと計算アルゴリズム- |
| 2.1 基本原理と歴史 7 |
|
| 58.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
粉体工学会編
| 出版情報: |
東京 : 日刊工業新聞社, 2005.9 xiii, 184p ; 21cm |
| シリーズ名: |
粉体工学叢書 ; 第2巻 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 粉体工学叢書発刊のことば i |
| 粉体工学叢書序文 iii |
| 粉体工学叢書編集委員 v |
| 粉体工学叢書第2巻粉体の生成はじめに vii |
| 粉体工学叢書第2巻粉体の生成執筆者一覧 xiii |
| 1.1粒子の力学物性と単一粒子の破壊 2 |
| 1.1.1単粒子破壊の種類 3 |
| 1.1.2単粒子破壊の理論と実際 4 |
| 1.1.3単粒子の強度 7 |
| 1.1.4破壊に及ぼす荷重条件の影響 9 |
| 1.1.5単粒子破砕産物の破断面と粒子径分布 14 |
| 1.2粉砕 16 |
| 1.2.1エネルギー法則 16 |
| 1.2.2粉砕抵抗と粉砕効率 21 |
| 1.2.3粉砕速度論 26 |
| 1.2.4粉砕助剤 33 |
| 1.2.5乾式・湿式粉砕の比較 36 |
| 1.2.6摩耗現象 41 |
| 1.3粉砕装置 43 |
| 1.3.1粉砕原料の大きさによる分類 44 |
| 1.3.2材質による分類 52 |
| 1.3.3粉砕システム 59 |
| 参考・引用文献 61 |
| 2.1核生成による粒子の発生と成長 68 |
| 2.1.1核生成および成長機構の分類 69 |
| 2.1.2発生した微粒子の凝縮および凝集による成長 76 |
| 2.1.3微粒子性状の評価と制御 81 |
| 2.2気相プロセス 88 |
| 2.2.1CVD法による微粒子の製造 88 |
| 2.2.2PVD法による粒子製造 98 |
| 2.2.3CVD法により製造される微粒子の物性制御 100 |
| 2.3液相プロセス 105 |
| 2.3.1沈殿析出法による粒子の生成 105 |
| 2.3.2溶媒蒸発法による粒子の生成 114 |
| 2.3.3噴霧乾燥法 121 |
| 2.3.4凍結乾燥法 122 |
| 2.4固相プロセス 122 |
| 2.4.1固体の熱分解法 123 |
| 2.4.2固相反応法 125 |
| 2.4.3還元法 127 |
| 2.4.4固相結晶化法 128 |
| 2.4.5水中結晶化法 129 |
| 2.4.6水熱結晶化法 129 |
| 参考・引用文献 130 |
| 3.1基礎 138 |
| 3.1.1固体の活性 138 |
| 3.1.2固体の破壊と表面エネルギー 138 |
| 3.1.3破壊による固体表面の構造変化 140 |
| 3.1.4粉砕平衡とメカノケミカル効果の平衡 142 |
| 3.1.5粉砕と結晶構造変化 143 |
| 3.1.6メカノケミカル活性化に伴う諸現象 146 |
| 3.1.7複合化 150 |
| 3.2応用 152 |
| 3.2.1材料合成 152 |
| 3.2.2環境に優しい素材製造プロセス(ソフトソリューションプロセス) 155 |
| 参考・引用文献 161 |
| 4.1転動ミル 166 |
| 4.1.1ミル内媒体の運動 166 |
| 4.1.2消費動力と粉砕速度 167 |
| 4.1.3粉砕産物の粒子径分布予測 174 |
| 4.2その他のミル 176 |
| 参考・引用文献 179 |
| 索引 181 |
| 粉体工学叢書発刊のことば i |
| 粉体工学叢書序文 iii |
| 粉体工学叢書編集委員 v |
|
| 59.
|
 図書
図書
|
湯川秀樹, 豊田利幸編
| 出版情報: |
東京 : 岩波書店, 1978.2-1978.3 2冊 ; 22cm |
| シリーズ名: |
岩波講座現代物理学の基礎 ; 1-2 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 60.
|
 図書
図書
|
辻内順平著
| 出版情報: |
東京 : 朝倉書店, 1976.2-1979.2 2冊 ; 22cm |
| シリーズ名: |
理工学基礎講座 ; 11 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 61.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
小松原明哲, 辛島光彦著
| 出版情報: |
東京 : 朝倉書店, 2008.3 viii, 200p ; 21cm |
| シリーズ名: |
経営システム工学ライブラリー ; 10 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 1. 人間工学概論 1 |
| 1.1 人間工学とは 1 |
| 1.1.1 人間工学の歴史的経緯 1 |
| 1.1.2 人間工学の役割 3 |
| 1.1.3 設計プロセスに対する人間工学の関わり 3 |
| 1.2 人間の仕組み 4 |
| 1.2.1 身体的特性 5 |
| 1.2.2 生理的特性 6 |
| 1.2.3 認知的特性 8 |
| 1.2.4 心理的特性 11 |
| 2. 労働の場における人間工学 14 |
| 2.1 身体活動と作業管理 14 |
| 2.1.1 生活活動と健康 14 |
| 2.1.2 疲労と休養 18 |
| 2.1.3 標準時間 21 |
| 2.1.4 深夜労働と交代制勤務 22 |
| 2.2 作業の人間工学的設計 22 |
| 2.2.1 分業の利点と問題点 22 |
| 2.2.2 QWLの向上 24 |
| 2.2.3 動機づけモデル 26 |
| 2.2.4 作業条件の改善 27 |
| 2.2.5 作業環境の改善 39 |
| 2.2.6 保護具 40 |
| 2.3 技能と教育・訓練 40 |
| 2.3.1 技能 41 |
| 2.3.2 教育・訓練の設計 42 |
| 2.3.3 教育・訓練の理論 44 |
| 2.4 オフィス作業 45 |
| 2.4.1 オフィス環境 45 |
| 2.4.2 VDT作業 53 |
| 2.5 メンタルストレスとメンタルヘルス 57 |
| 2.5.1 メンタルストレス 57 |
| 2.5.2 ストレスコーピング 59 |
| 2.5.3 ストレスと性格 61 |
| 2.5.4 トータル・ヘルスプロモーション・プラン 62 |
| 2.5.5 行動変容モデル 63 |
| 2.5.6 健康増進法 64 |
| 2.6 システム開発の人間要因 65 |
| 2.6.1 システム開発の形態 65 |
| 2.6.2 プロジェクトチームとリーダーシップ 67 |
| 2.6.3 成熟度評価 69 |
| 2.6.4 ソフトウエアの作業品質と開発支援ツール 69 |
| 2.7 雇用促進への人間工学的対応 72 |
| 2.7.1 高年齢者の雇用促進 72 |
| 2.7.2 障害者の雇用促進 74 |
| 2.7.3 妊産婦への配慮 77 |
| 2.7.4 バリアフリーの推進 78 |
| 3. 製品設計の人間工学 82 |
| 3.1 人間中心設計プロセス 82 |
| 3.1.1 製品品質と人間工学 82 |
| 3.1.2 人間中心設計プロセス 83 |
| 3.1.3 人間中心設計プロセス実践のための手法 84 |
| 3.1.4 個人差への対応 89 |
| 3.1.5 ユーザビリテイ要求の優先順位づけ 90 |
| 3.1.6 官能評価 90 |
| 3.1.7 ユーザエクスペリエンス 91 |
| 3.2 マン・マシンシステム 92 |
| 3.2.1 マン・マシンシステム 93 |
| 3.2.2 表示(器)の見やすさ(情報受容のしやすさ) 93 |
| 3.2.3 操作器の操作のしやすさ(情報入力のしやすさ) 96 |
| 3.2.4 表示器・操作器の位置・配置 97 |
| 3.2.5 操作方法・使用手順 98 |
| 3.2.6 フィードバックと機械時間 100 |
| 3.2.7 漏洩物・発射物の防止 101 |
| 3.2.8 機器の設置使用環境 101 |
| 3.2.9 機器の使用時間および休憩方法 101 |
| 3.3 ユニバーサルデザインと製品安全 102 |
| 3.3.1 ユニバーサルデザイン 102 |
| 3.3.2 製造物責任法と製品安全 106 |
| 3.3.3 誤使用への人間工学対応 110 |
| 3.4 人間の認知・行動モデル 112 |
| 3.4.1 ユーザビリティ評価のためのモデル 112 |
| 3.4.2 ユーザレベルの記述モデル 117 |
| 3.4.3 意思決定のモデル 119 |
| 4. 安全と人間工学 123 |
| 4.1 ヒューマンエラーと事故防止 123 |
| 4.1.1 事故とヒューマンエラー 123 |
| 4.1.2 ヒューマンエラーの形態 126 |
| 4.1.3 ヒューマンエラーの背景 128 |
| 4.2 安全管理 130 |
| 4.2.1 産業安全のモデル 131 |
| 4.2.2 労働安全衛生マネジメントシステム 136 |
| 4.2.3 事故への対応 137 |
| 4.3 事故分析の方法 138 |
| 4.3.1 根本原因分析 138 |
| 4.3.2 事故分析の手法 139 |
| 5. 経営工学領域での人間工学の方法論 145 |
| 5.1 データの収集 145 |
| 5.1.1 主観評価法 145 |
| 5.1.2 観察法 153 |
| 5.1.3 人間工学の実験・調査倫理 155 |
| 5.2 生体情報の測定評価 156 |
| 5.2.1 自律神経を反映した生体情報 156 |
| 5.2.2 大脳活動を反映した生体情報 160 |
| 5.2.3 身体の動きを反映した生体情報 163 |
| 5.3 人間工学設計のためのデータ解析法 165 |
| 5.3.1 データ整理方法と基本統計量 165 |
| 5.3.2 傾向を知るためのデータ解析方法 173 |
| 5.3.3 条件間の差を検討する方法 178 |
| 5.3.4 多変量解析 184 |
| 付表 189 |
| 索引 195 |
| 1. 人間工学概論 1 |
| 1.1 人間工学とは 1 |
| 1.1.1 人間工学の歴史的経緯 1 |
|
| 62.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
長松昭男著
| 出版情報: |
鎌倉 : 長松昭男 , 東京 : コロナ社 (発売), 1993.7 xi, 505p, 図版[2]p ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| モード解析入門 |
| 1.はじめに 1 |
| 1.1振動が大切な理由 1 |
| 1.2今なぜ振動か 4 |
| 1.3振動の種類 5 |
| 1.4今なぜモード解析か 8 |
| 2.1自由度系 13 |
| 2.1なぜ振動するか 13 |
| 2.1.1物体の性質と力学モデル |
| 2.1.2力のつりあいと運動方程式 |
| 2.1.3振動のからくり |
| 2.1.4単位 |
| 2.2不減衰系の自由 20 |
| 2.2.1振動の数学表現 |
| 2.2.2固有振動数 |
| 2.2.3運動方程式の解 |
| 2.2.4エネルギー |
| 2.3減衰系の自由振動 33 |
| 2.3.1運動方程式 |
| 2.3.2無周期運動 |
| 2.3.3減衰自由振動 |
| 2.3.4減衰の働き |
| 2.3.5単位衝撃応答 |
| 2.4不減衰系の強制振動 42 |
| 2.4.1応答 |
| 2.4.2なぜ共振するのか |
| 2.4.3力のつりあい |
| 2.4.4振動数による応答振幅の変化 |
| 2.5減衰系の強制振動 50 |
| 2.5.1応答 |
| 2.5.2力のつりあい |
| 2.5.3仕事とエネルギー |
| 2.5.4なぜ共振するのか |
| 2.5.5基礎への伝達力 |
| 2.5.6基礎加振による応答 |
| 2.6周波数応答関数 66 |
| 2.6.1定義 |
| 2.6.2図示 |
| 2.6.3特別な現象を生じる振動数 |
| 3.多自由度系 79 |
| 3.1不減衰系の自由振動 79 |
| 3.1.1運動方程式 |
| 3.1.22自由度系 |
| 3.1.3多自由度系 |
| 3.1.4固有振動数と固有モード |
| 3.1.5固有モードの直交性 |
| 3.1.6モード質量とモード剛性 |
| 3.1.7質量正規固有モード |
| 3.1.8モード座標 |
| 3.2減衰系の自由振動 100 |
| 3.2.1運動方程式 |
| 3.2.2比例粘性減衰系 |
| 3.2.3等価1自由度系 |
| 3.2.4一般粘性減衰系 |
| 3.3強制振動 113 |
| 3.3.1運動方程式 |
| 3.3.2周波数応答関数 |
| 3.4数値例 130 |
| 3.4.12自由度系 |
| 3.4.23自由度系 |
| 4.信号処理 149 |
| 4.1はじめに 149 |
| 4.2フーリエ級数 155 |
| 4.3連続フーリエ変換 166 |
| 4.4離散フーリエ変換 170 |
| 4.5高速フーリエ変換 178 |
| 4.6フーリエ変換の例 188 |
| 4.6.1方形波と単位衝撃 |
| 4.6.2単位衝撃応答 |
| 4.6.3入出力波形と周波数応答関数 |
| 4.6.4運動方程式 |
| 4.7誤差 200 |
| 4.7.1入力誤差 |
| 4.7.2折り返し誤差 |
| 4.7.3量子化誤差 |
| 4.7.4分解能誤差 |
| 4.7.5漏れ誤差と窓関数 |
| 4.8相関 217 |
| 4.8.1自己相関関数 |
| 4.8.2パワースペクトル密度関数 |
| 4.8.3相互相関関数 |
| 4.8.4クロススペクトル密度関数 |
| 4.8.5周波数応答関数と関連度関数 |
| 5.振動試験 229 |
| 5.1はじめに 229 |
| 5.2対象物の支持 231 |
| 5.2.1自由境界または自由支持 |
| 5.2.2固定支持 |
| 5.2.3弾性支持 |
| 5.3加振器 237 |
| 5.3.1種類と特徴 |
| 5.3.2取付け |
| 5.3.3加振点 |
| 5.4加振方法 256 |
| 5.4.1定常波 |
| 5.4.2周期波 |
| 5.4.3不規則波 |
| 5.4.4非定常波 |
| 5.4.5自然加振 |
| 5.4.6比較 |
| 5.5打撃試験 293 |
| 5.5.1はじめに |
| 5.5.2長所と短所 |
| 5.5.3打撃ハンマ |
| 5.5.4現場校正 |
| 5.5.5過負荷 |
| 5.5.62度叩き |
| 5.5.7誤差と窓関数 |
| 5.5.8対象物の非線形 |
| 5.5.9対象物の減衰 |
| 5.5.10信号処理 |
| 5.5.11検証 |
| 5.6変換器 323 |
| 5.6.1必要事項 |
| 5.6.2較正 |
| 5.6.3加速度計の取付け |
| 5.7周波数応答関数の信頼性 333 |
| 6.モード特性の同定 339 |
| 6.1はじめに 339 |
| 6.21自由度法 343 |
| 6.2.1周波数応答関数の大きさを用いる方法 |
| 6.2.2周波数応答関数の虚部を用いる方法 |
| 6.2.3周波数応答関数の実部と虚部を用いる方法 |
| 6.2.4モード円適合 |
| 6.2.5自由振動による減衰の推定 |
| 6.2.6考察 |
| 6.3多自由度法 360 |
| 6.3.1偏分反復法 |
| 6.3.2プロニーの方法 |
| 6.3.3周波数領域法と時間領域法の比較 |
| 6.3.4混合法 |
| 付録A 375 |
| A1三角関数 375 |
| A1.1基本 |
| A1.2加法定理 |
| A1.3微分と積分 |
| A2複素指数関数 383 |
| A2.1複素数 |
| A2.2指数関数と対数関数 |
| A2.3テーラー展開 |
| A2.4複素指数関数 |
| A3ベクトルと行列 396 |
| A3.1定義 |
| A3.2ベクトルの演算 |
| A3.3ベクトルの相関と直交 |
| A3.4行列の演算 |
| A3.5行列式 |
| A3.6固有値と固有ベクトル |
| A3.7固有ベクトルの直交性 |
| A3.8正規直交座標系 |
| A3.9複素ベクトル |
| A4関数 443 |
| A4.1実関数の大きさ |
| A4.2実関数の相関と直交 |
| A4.3複素関数 |
| A4.4正規直交関数系 |
| A5最小自乗法 456 |
| A6積と除の微分と部分積分 462 |
| 付録B 464 |
| B11自由度系の減衰振動への初期条件の導入 464 |
| B21自由度粘性減衰系の強制振動 467 |
| B31自由度系の強制振動における共振振動 473 |
| B41自由度粘性減衰系の強制振動における仕事 477 |
| B5周波数応答関数における実部と虚部 480 |
| B5.1コンプライアンス |
| B5.2モビリティ |
| B62自由度系に関する補足 484 |
| B6.1g2-4dh>0の証明 |
| B6.2固有モードの直交性 |
| B7初期条件による1自由度系の応答 488 |
| B8ズーム処理 490 |
| B9モード円適合における減衰の推定 494 |
| 参考文献 497 |
| 索引 498 |
| モード解析入門 |
| 1.はじめに 1 |
| 1.1振動が大切な理由 1 |
|
| 63.
|
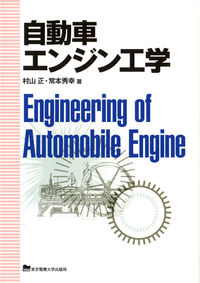 図書
図書
東工大
目次DB
|
村山正, 常本秀幸著
| 出版情報: |
東京 : 東京電機大学出版局, 2008.3 222p ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 第1章 内燃機関の歴史 |
| 1.1 ルノアールからオットーまで 15 |
| 1.1.1 ルノアールの発明まで 15 |
| 1.1.2 オットーの4サイクル機関 17 |
| 1.2 ダイムラー,ベンツの功績 19 |
| 1.2.1 ガソリンの利用 19 |
| 1.2.2 小形軽量高速機関の発明 20 |
| 1.3 ディーゼル機関の夜明け 22 |
| 1.4 内燃機関性能の歴史 23 |
| 第2章 サイクル計算,および出力 |
| 2.1 完全ガスサイクル 27 |
| 2.1.1 サイクルにおける仮定 27 |
| 2.1.2 サバテサイクル(2段燃焼サイクル) 27 |
| 1) 各行程における圧力・温度 28 |
| 2) 理論熱効率 30 |
| 3) 図示平均有効圧 30 |
| 2.1.3 オットーサイクル(定容燃焼サイクル) 30 |
| 2.1.4 ディーゼルサイクル(定圧燃焼サイクル) 31 |
| 2.1.5 各サイクルの圧力・温度 32 |
| 2.2 燃料・空気サイクル 32 |
| 2.2.1 サイクルにおける仮定 33 |
| 2.2.2 P-V線図の比較 34 |
| 1) 圧縮行程 35 |
| 2) 燃焼 35 |
| 3) 膨張行程 36 |
| 4) 放熱 36 |
| 5) 熱効率 36 |
| 2.3 実際のサイクル 36 |
| 2.3.1 サイクル損失 36 |
| 1) 時間損失 36 |
| 2) 冷却損失 37 |
| 3) 排気吹き出し損失 38 |
| 2.3.2 図示効率,および線図効率 38 |
| 1) 図示効率 38 |
| 2) 線図効率 38 |
| 2.3.3 正味効率,および機械効率 38 |
| 1) 正味効率 38 |
| 2) 機械効率 39 |
| 2.4 出力の計算 39 |
| 2.4.1 平均有効圧からの算出 39 |
| 1) 正味平均有効圧の定義 39 |
| 2) 正味出力の推定 40 |
| 2.4.2 出力の計測 40 |
| 1) 馬力の定義 40 |
| 2) 動力計の原理 41 |
| 2.5 燃費 43 |
| 2.5.1 燃費率 43 |
| 2.5.2 走行燃費 44 |
| 1) 定常走行燃費 44 |
| 2) モード燃費 44 |
| 2.6 ヒートバランス 44 |
| 2.6.1 有効仕事 44 |
| 2.6.2 冷却水損失 45 |
| 2.6.3 摩擦損 48 |
| 1) 吸排気損失(ポンプ損失) 48 |
| 2) 機械損失 50 |
| 第3章 燃料,および燃焼 |
| 3.1 内燃機関用燃料の特性 51 |
| 3.1.1 原油の精製 51 |
| 1) 分溜比率 51 |
| 2) 蒸留特性 52 |
| 3.1.2 ガソリン 52 |
| 1) 炭化水素の組成 52 |
| 2) オクタン価 53 |
| 3.1.3 軽油 55 |
| 1) 燃科組成 55 |
| 2) セタン価 56 |
| 3.2 炭化水素の燃焼 57 |
| 3.2.1 着火の瞬間 57 |
| 1) 熱爆発理論 57 |
| 2) 連鎖爆発理論 58 |
| 3.2.2 燃焼の進行 59 |
| 1) 予混合燃焼 59 |
| 2) 拡散燃焼 59 |
| 3.3 燃焼計算 61 |
| 3.3.1 炭化水素の燃焼反応と発熱量 61 |
| 1) 基礎式と発熱量 61 |
| 2) 燃焼に必要な空気量と燃焼ガス量 61 |
| 第4章 火花点火機関 |
| 4.1 混合気の形成 67 |
| 4.1.1 要求空燃比 67 |
| 4.1.2 微粒化現象 68 |
| 4.2 気化器 69 |
| 4.2.1 単純気化器 69 |
| 4.2.2 気化器の補助機構 70 |
| 4.2.3 気化器の種類 74 |
| 4.3 電子式燃料噴射装置 74 |
| 4.3.1 基本構成 74 |
| 1) 空気量検出方法 74 |
| 2) 噴射方式 75 |
| 4.3.2 制御機能 77 |
| 1) ラムダーセンサ 77 |
| 2) 水温センサ 77 |
| 3) 加速制御 78 |
| 4) 減速時制御 79 |
| 4.4 点火システム 79 |
| 4.4.1 バッテリー点火方式 79 |
| 4.4.2 スパークプラグ 81 |
| 1) 着火性能の向上 81 |
| 2) 熱価 82 |
| 4.4.3 点火時期の制御 83 |
| 1) 機械的制御 83 |
| 2) マップ制御 84 |
| 4.5 ガソリン機関の燃焼 86 |
| 4.5.1 燃焼の分類 86 |
| 4.5.2 正常燃焼 86 |
| 4.5.3 スパークノツク 88 |
| 1) 発生原因 88 |
| 2) スパークノックの防止技術 88 |
| 4.5.4 その他の異常燃焼 90 |
| 4.6 リーンバーン燃焼 91 |
| 4.6.1 エンジンモデイフイケーション方式 91 |
| 4.6.2 筒内噴射方式 95 |
| 第5章 ディーゼル機関 |
| 5.1 燃料噴射システム 99 |
| 5.1.1 列型噴射ポンプの噴射過程 100 |
| 1) 噴射の開始・終了 100 |
| 2) 噴射管内の脈動現象 100 |
| 5.1.2 その他の噴射システム 103 |
| 1) 分配型噴射ポンプ 103 |
| 2) 高圧噴射システム 103 |
| 5.1.3 噴射ノズ ル 104 |
| 1) 弁の作動 104 |
| 2) ノズル形式 105 |
| 5.1.4 噴射特性 107 |
| 1) 噴射時期 107 |
| 2) 噴射期間 107 |
| 3) 噴射率 107 |
| 5.1.5 噴霧特性 108 |
| 1) 粒径分布 108 |
| 2) 噴霧到達距離(貫通力) 109 |
| 3) 噴霧角 110 |
| 5.2 ディーゼル機関の分類 111 |
| 5.3 ディーゼル機関の燃焼 112 |
| 5.3.1 直接噴射式機関における混合気の形成 112 |
| 1) 噴射エネルギーによる混合気の形成 112 |
| 2) スワールによる混合気の形成 114 |
| 3) 燃焼室内スワール 117 |
| 5.3.2 直接噴射式機関の燃焼 118 |
| 1) 着火遅れ期間 118 |
| 2) 爆発燃焼期間 119 |
| 3) 制御燃焼期間 119 |
| 4) あと燃え期間 119 |
| 5.3.3 副室式機関における混合気の形成 120 |
| 1) 予燃焼室式機関 120 |
| 2) 渦流室式機関 120 |
| 5.3.4 副室式機関の燃焼 121 |
| 1) 予燃焼室式機関 121 |
| 2) 渦流室式機関 122 |
| 第6章 内燃機関による大気汚染 |
| 6.1 大気汚染の歴史と現状 125 |
| 6.1.1 日本における排ガス規制 125 |
| 1) ガソリン機関 125 |
| 2) ディーゼル機関128 |
| 6.1.2 外国における排ガス規制 130 |
| 1) アメリカの排ガス規制 130 |
| 2) ヨーロッパにおける排ガス規制 131 |
| 6.2 大気汚染物質の発生 131 |
| 6.2.1 COの発生 131 |
| 6.2.2 NOの発生 132 |
| 1) ガソリン機関におけるNOの生成 132 |
| 2) ディーゼル機関におけるNOの生成 134 |
| 6.2.3 HCの発生 134 |
| 1) ガソリン機関 134 |
| 2) ディーゼル機関 134 |
| 6.2.4 微粒子の発生 136 |
| 1) 黒煙(ドライスート) 136 |
| 2) S0F 136 |
| 6.3 排気ガスと健康 136 |
| 6.3.1 一酸化炭素(CO) 137 |
| 6.3.2 未燃炭化水素(HC) 138 |
| 6.3.3 窒素酸化物(Nox) 138 |
| 6.3.4 微粒子(パティキュレートPM) 139 |
| 6.3.5 オキシダント 139 |
| 6.4 ガソリン機関の排気対策 139 |
| 6.4.1 サーマルリアクター方式 139 |
| 6.4.2 三元触媒システム 140 |
| 6.4.3 酸化触媒とEGRの組み合わせ 142 |
| 6.4.4 リーンバーン方式 143 |
| 6.5 デイーゼル機関の排気対策 144 |
| 6.5.1 噴射時期の遅延 145 |
| 6.5.2 ディーゼル機関におけるEGR 146 |
| 6.5.3 高圧燃料噴射システム 147 |
| 6.5.4 パティキュレートトラップ 147 |
| 6.5.5 その他の排気対策 147 |
| 第7章 シリンダー内のガス交換 |
| 7.1 4サイクル機関の吸排気行程 153 |
| 7.2 吸入効率 154 |
| 7.2.1 体積効率 154 |
| 7.2.2 充填効率 155 |
| 7.3 体積効率の静的改善方法 156 |
| 7.3.1 流量係数 156 |
| 1) バルブとボートの傾斜角 159 |
| 2) バルブシート部付近の形状 160 |
| 3) バルブガイドおよびボート 160 |
| 7.3.2 吸気マッハ指数 160 |
| 1) 吸排気弁の多弁化 162 |
| 2) カム形状 162 |
| 7.3.3 等価管長 162 |
| 7.4 体積効率の動的改善 163 |
| 7.4.1 慣性効果 164 |
| 7.4.2 脈動効果 166 |
| 7.4.3 吸排気干渉 168 |
| 7.5 2サイクル機関の掃気過程 169 |
| 7.5.1 2サイクル機関の基本構造 170 |
| 7.5.2 2サイクル機関の各種効率 171 |
| 1) 掃気効率 171 |
| 2) 給気効率 172 |
| 3) 給気比 172 |
| 7.5.3 2サイクル機関の種類 173 |
| 1) 横断掃気 173 |
| 2) ループ掃気 173 |
| 3) ユニフロー掃気 173 |
| 4) 最近の2サイクル機関 173 |
| 7.6 過給システム 174 |
| 7.6.1 機械式過給方式 174 |
| 7.6.2 排気ターボ過給方式 175 |
| 7.7 吸排気騒音 176 |
| 7.7.1 消音の基本原理 176 |
| 1) レゾネーター 177 |
| 2) 拡張 178 |
| 3) 千渉 178 |
| 4) 吸収 178 |
| 5) 反射板 178 |
| 6) 紋り 178 |
| 7.7.2 実際の吸排気消音系 178 |
| 1) エアクリーナ 178 |
| 2) サイレンサー 178 |
| 第8章 冷却 |
| 8.1 冷却の基本 181 |
| 8.1.1 伝熱パターン 181 |
| 1) 熱伝導 182 |
| 2) 熱伝達 182 |
| 3) ふく射 184 |
| 8.1.2 エンジン各部の温度 184 |
| 1) ピストン,およびシリンダー 184 |
| 2) シリンダーヘッド 184 |
| 3) 吸排気弁 185 |
| 4) プラグ 185 |
| 8.2 冷却方式 185 |
| 8.2.1 液冷方式 185 |
| 8.2.2 空冷方式 187 |
| 8.2.3 蒸発冷却方式 187 |
| 第9章 潤滑 |
| 9.1 潤滑概論 189 |
| 9.1.1 固体潤滑 190 |
| 9.1.2 境界潤滑 190 |
| 9.1.3 流体潤滑 191 |
| 9.2 エンジンオイル 192 |
| 9.2.1 粘度 192 |
| 9.2.2 酸化 193 |
| 9.2.3 オイル分類 193 |
| 9.2.4 オイル交換 194 |
| 9.3 潤滑系 194 |
| 9.3.1 潤滑方式 194 |
| 1) 混合潤滑 194 |
| 2) 飛沫潤滑 196 |
| 3) 強制潤渦 194 |
| 9.3.2 潤滑経路 194 |
| 第10章 内燃機関の機械力学 |
| 10.1 バルブ機構 199 |
| 10.1.1 バルブ駆動方式 199 |
| 1) サイドバルブ方式(SV) 199 |
| 2) オーバーヘッドバルブ方式(OHV) 199 |
| 3) オーバーヘッドカム方式(OHC) 200 |
| 10.1.2 カム特 性 200 |
| 1) カム形状 201 |
| 2) バルブスプリング 201 |
| 10.2 ピストン・クランク機構の運動と慣性力 202 |
| 10.2.1 ピストンの運動 202 |
| 10.2.2 往復運動部分の慣性力 204 |
| 10.2.3 コネクテイングロッド(コンロッド)の慣性作用 205 |
| 10.3 平衡 206 |
| 10.3.1 単気筒機関の平衡 206 |
| 1) 回転質量の釣り合い 206 |
| 2) 往復質量の釣り合い 208 |
| 10.3.2 多気筒機関の平衡 209 |
| 1) 回転体の平衡 209 |
| 2) 往復質量の平衡(直列機関) 210 |
| 10.4 トルク変動とフライホイール 211 |
| 10.5 クランク軸系の握り振動とトーショナルダンパ 214 |
| 10.5.1 振り振動の基礎式 214 |
| 10.5.2 エンジンの場合 215 |
| 第1章 内燃機関の歴史 |
| 1.1 ルノアールからオットーまで 15 |
| 1.1.1 ルノアールの発明まで 15 |
|
| 64.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
日本画像学会編
| 出版情報: |
東京 : 東京電機大学出版局, 2008.6 xiii, 196p ; 21cm |
| シリーズ名: |
シリーズ「デジタルプリンタ技術」 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 第1章 電子ペーパーの定義・分類と表示方式 1 |
| 1.1 電子ペーパーとは 1 |
| 1.2 本書で扱う電子ペーパーの範囲 2 |
| 1.3 応用分野と表示技術の交差関係 3 |
| 1.4 電子ペーパーの目標と課題 4 |
| 1.5 電子ペーパーに用いられる表示技術 7 |
| 第2章 着色物質の移動・回転による反射型ディスプレイ技術 10 |
| 2.1 電気泳動表示方式 10 |
| 2.1.1 はじめに 10 |
| 2.1.2 電気泳動の原理 11 |
| 2.1.3 粒子の帯電メカニズム 12 |
| 2.1.4 拡散電気二重層 14 |
| 2.1.5 電気泳動表示方式 15 |
| 2.1.6 電気泳動用粒子とマイクロカプセル 18 |
| 2.1.7 電気泳動表示デバイスの表示特性 20 |
| 2.1.8 表示評価技術 22 |
| 2.1.9 まとめ 23 |
| 2.2 粒子移動方式 23 |
| 2.2.1 はじめに 23 |
| 2.2.2 パネル構造 24 |
| 2.2.3 表示のしくみ 26 |
| 2.2.4 駆動原理 27 |
| 2.2.5 特徴 29 |
| 2.2.6 カラー化 31 |
| 2.2.7 フレキシブル化 33 |
| 2.2.8 応用展開 34 |
| 2.2.9 課題と展望 34 |
| 2.3 ツイストボール方式 35 |
| 2.3.1 原理と製法 35 |
| 2.3.2 発明の経緯 36 |
| 2.3.3 電子ペーパーヘの展開試行 36 |
| 2.3.4 回転粒子の製法 37 |
| 2.3.5 粒子回転の理論 39 |
| 2.3.6 円筒型の検討 39 |
| 2.3.7 磁力回転の検討 40 |
| 2.3.8 ツイストボール方式の課題と展望 41 |
| 第3章 各種の反射型ディスプレイ技術 44 |
| 3.1 液晶方式 44 |
| 3.1.1 電子ペーパーに用いられる液晶の特質と分類 44 |
| 3.1.2 コレステリック液晶 46 |
| 3.1.3 双安定ネマティック液晶 51 |
| 3.1.4 ポリマーネットワーク液晶 52 |
| 3.1.5 ゲストホスト液晶 53 |
| 3.1.6 液晶方式の課題と展望 55 |
| 3.2 エレクトロクロミック方式 55 |
| 3.2.1 エレクトロクロミズム(EC)の原理,開発の歴史と経緯 55 |
| 3.2.2 開発動向 58 |
| 3.2.3 今後の課題ならびに展望 64 |
| 3.3 MEMS方式 65 |
| 3.3.1 MEMS方式の原理・開発の歴史と経緯 65 |
| 3.3.2 光干渉変調方式 65 |
| 3.3.3 片持ち梁可動フィルム方式 66 |
| 3.3.4 MEMS方式の課題と展望 68 |
| 3 4 エレクトロウェッティング方式 69 |
| 3.4.1 原理,開発の歴史と経緯 69 |
| 3.4.2 開発動向 71 |
| 3.4.3 課題と展望 72 |
| 第4章 書き換え表示技術と消色技術 75 |
| 4.1 サーマルリライタブル方式 75 |
| 4.1.1 サーマルリライタブル方式の開発の歴史と経緯 75 |
| 4.1.2 高分子/長鎖低分子分散型サーマルリライタブル方式 78 |
| 4.1.3 ロイコ染料/長鎖顕色剤型サーマルリライタブル方式 81 |
| 4.1.4 サーマルリライタブル記録の今後の方向 85 |
| 4.1.5 課題と展望 88 |
| 4.2 インク消色方式 88 |
| 4.2.1 開発の背景と消色インクの原理 88 |
| 4.2.2 開発と実用化の進行現状 90 |
| 4.2.3 インク消色方式の課題と展望 91 |
| 第5章 電子ペーパー用駆動回路技術 94 |
| 5.1 駆動技術の分類 94 |
| 5.1.1 パッシブマトリックス駆動方式 95 |
| 5.1.2 アクティブマトリックス駆動方式 96 |
| 5.2 各駆動方式における駆動技術 97 |
| 5.2.1 電気泳動 97 |
| 5.2.2 粉体移動 99 |
| 5.2.3 コレステリック液晶 99 |
| 5.3 駆動回路のフレキシブル化 100 |
| 5.3.1 回路転写 101 |
| 5.3.2 直接形成 102 |
| 5.3.3 有機TFT 103 |
| 第6章 電子ペーパーのヒューマンインタフェース 106 |
| 6.1 検討の背景 106 |
| 6.1.1 課題の背景と位置づけ 106 |
| 6.1.2 研究の経緯 107 |
| 6.1.3 課題の分類 108 |
| 6.1.4 作業比較実験の意義 108 |
| 6.2 紙とディスプレイの作業比較実験 109 |
| 6.2.1 紙と各種ディスプレイの作業比較(実験A) 109 |
| 6.2.2 紙とディスプレイでの文章校正作業比較(実験B) 110 |
| 6.2.3 画面の呈示形式(ページ/スクロール表示)の影響評価(実験C) 112 |
| 6.2.4 媒体の固定呈示作業と手持ち作業の比較(実験D) 114 |
| 6.3 実験結果のまとめ 116 |
| 第7章 電子ペーパーの用途展開 119 |
| 7.1 用途概論 119 |
| 7.1.1 用途の広がりと分類 119 |
| 7.1.2 電子ペーパー用の新表示技術と従来型表示技術の関係 120 |
| 7.1.3 応用分野の市場規模および立ち上がり時期 121 |
| 7.1.4 紙への置き換えをねらう技術的手段 122 |
| 7.2 電子書籍 123 |
| 7.2.1 読書専用端末の表示と機能 123 |
| 7.2.2 電子書籍の市場と現状 129 |
| 7.3 電子新聞 135 |
| 7.3.1 新聞の電子化についての整理 135 |
| 7.3.2 電子新聞の経緯と動向 139 |
| 7.4 オフィス・産業用途 148 |
| 7.4.1 オフィスや産業用途などにおける文書の現状と課題 148 |
| 7.4.2 リライタブル方式の適用事例 150 |
| 7.4.3 今後の展望と課題 155 |
| 7.5 広告・掲示用途 159 |
| 7.5.1 広告・掲示の現状と課題 159 |
| 7.5.2 広告・掲示用途への検討状況 160 |
| 7.5.3 値札・POP類への適用状況 165 |
| 7.6 携帯電話・時計・その他の応用分野 166 |
| 7.6.1 腕時計 166 |
| 7.6.2 設備時計 167 |
| 7.6.3 携帯電話 168 |
| 7.6.4 USBメモリ 170 |
| 7.6.5 その他 171 |
| 第8章 未来の電子ペーパーに期待すること 173 |
| 8.1 はじめに―伝えるということ― 173 |
| 8.2 書籍の手触りを楽しむ 174 |
| 8.3 今すぐにでもほしい電子ペーパーの機能 176 |
| 8.4 「ルイカ」という名にこめた思い 178 |
| 8.5 電子ペーパーのユニバーサルデザイン 182 |
| 第9章 電子ペーパーの展望 185 |
| 9.1 グーテンベルグ技術の恩恵と限界 185 |
| 9.2 デジタル技術の課題 187 |
| 9.3 電子ペーパーとユビキタスの関係 188 |
| 9.4 電子ペーパー技術の展望 189 |
| 第1章 電子ペーパーの定義・分類と表示方式 1 |
| 1.1 電子ペーパーとは 1 |
| 1.2 本書で扱う電子ペーパーの範囲 2 |
|
| 65.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
谷萩隆嗣著
目次情報:
続きを見る
| 1.1線形離散時間システムの状態推定アルゴリズム 1 |
| 1.1.1状態推定の概念 1 |
| 1.1.2状態推定問題 2 |
| 1.1.3ガウス過程の状態推定 3 |
| 1.1.4ガウス過程の状態推定アルゴリズム 9 |
| 1.1.5非ガウス過程の状態推定アルゴリズム(1) 12 |
| 1.1.6非ガウス過程の状態推定アルゴリズム(2) 16 |
| 1.1.7予測アルゴリズム 17 |
| 1.2カルマンフィルタのいくつかの性質 18 |
| 1.3カルマンフィルタの計算回数 21 |
| 1.4平方根アルゴリズム 24 |
| 1.4.1行列のLDU分解とコレスキー分解 25 |
| 1.4.2ハウスホルダー変換アルゴリズム 28 |
| 1.4.3修正グラム・シュミット変換アルゴリズム 30 |
| 1.4.4カルマンフィルタの平方根アルゴリズム 33 |
| 1.4.5平方根アルゴリズムの計算回数 38 |
| 1.5適応カルマンフィルタ 42 |
| 1.6拡張カルマンフィルタ 47 |
| 1.7アンセンテッドカルマンフィルタ 52 |
| 1.7.1アンセンテッド変換 52 |
| 1.7.2アンセンテッド交換の特徴 53 |
| 1.7.3アンセンテッドカルマンフィルタ 57 |
| 2.1パラメータ推定の基礎 60 |
| 2.1.1数学モデルとパラメータ推定 60 |
| 2.1.2パラメータ推定のための望ましい性質 61 |
| 2.2インパルス応答の推定 62 |
| 2.2.1IIRシステムとFIRシステム 62 |
| 2.2.2パラメータ推定のための評価関数 64 |
| 2.2.3インパルス応答の最小2乗推定 67 |
| 2.2.42段階最小2乗法 69 |
| 2.2.5相関アルゴリズム 72 |
| 2.2.6多入力多出力システムのインパルス応答 75 |
| 2.3IIRシステムの伝達関数の推定 77 |
| 2.3.1IIRシステムの最小2乗推定 77 |
| 2.3.2IIRシステムの再帰推定アルゴリズム 81 |
| 2.3.3多入力多出力システムの再帰推定アルゴリズム 85 |
| 2.3.4FIRシステムの再帰推定アルゴリズム 88 |
| 2.4最小2乗法の拡張アルゴリズム 89 |
| 2.4.1一般化最小2乗法 89 |
| 2.4.2拡大最小2乗法 92 |
| 2.4.3補助変数法 95 |
| 2.5全体最小2乗法の推定アルゴリズム 100 |
| 2.5.1全体最小2乗推定問題 100 |
| 2.5.2行列の特異値分解 103 |
| 2.5.3特異値分解による最適解 110 |
| 2.5.4全体最小2乗法の幾何学的意味 115 |
| 2.6カルマンフィルタによるパラメータ推定 118 |
| 2.6.11入力1出力線形時不変システム 118 |
| 2.6.21入力1出力線形時変システム 120 |
| 2.6.3多入力多出力システム 121 |
| 2.6.4最小2乗法との比較 122 |
| 2.7高速アルゴリズム 124 |
| 3.1適応ディジタルフィルタ 137 |
| 3.1.1適応FIRフィルタ 137 |
| 3.1.2適応IIRフィルタ 138 |
| 3.2確率近似法による推定アルゴリズム 140 |
| 3.2.1基本アルゴリズム 140 |
| 3.2.2FIRシステムの推定アルゴリズム(1) 142 |
| 3.2.3FIRシステムの推定アルゴリズム(2) 143 |
| 3.2.4IIRシステムの推定アルゴリズム 145 |
| 3.3LMS法による推定アルゴリズム 146 |
| 3.3.1最適アルゴリズム 146 |
| 3.3.2LMSアルゴリズム 148 |
| 3.3.3勾配雑音と誤調整 151 |
| 3.3.4LMSアルゴリズムの収束性 155 |
| 3.3.5最適なステップ幅 157 |
| 3.3.6正規化LMSアルゴリズムの収束性 161 |
| 3.3.7複素LMSアルゴリズム 169 |
| 3.4修正LMSアルゴリズム 170 |
| 3.4.1リーキーLMSアルゴリズム 170 |
| 3.4.2モーメンタムLMSアルゴリズム 172 |
| 3.4.3LMS+Fアルゴリズム 176 |
| 3.4.4LMS/Fアルゴリズム 180 |
| 3.4.5ブロックLMSアルゴリズム 181 |
| 3.4.6変換領域LMSアルゴリズム 183 |
| 3.4.7可変ステップ幅LMSアルゴリズム 188 |
| 4.1適応等化器 196 |
| 4.1.1等化器と適応等化器 196 |
| 4.1.2カルマンフィルタによる伝送路特性の推定 198 |
| 4.1.3確率近似法による伝送路特性の推定 204 |
| 4.1.4カルマンフィルタによる送信信号の推定 208 |
| 4.1.5確率近似法による送信信号の推定 213 |
| 4.1.6カルマンフィルタによる適応等化器の設計 215 |
| 4.1.7拡張カルマンフィルタによる適応等化器の設計 219 |
| 4.1.8確率近似法による適応等化器の設計 222 |
| 4.2エコーキャンセラ 226 |
| 4.2.1エコーキャンセラ 226 |
| 4.2.2並列形カルマンフィルタ1(PKF1) 228 |
| 4.2.3並列形カルマンフィルタ2(PKF2) 237 |
| 4.2.4シミュレーション結果の比較(1) 243 |
| 4.2.5PKFによるパラメータ推定値の収束性 252 |
| 4.2.6PKFの分割数と推定アルゴリズムの性質 255 |
| 4.2.7入力信号の有色性と推定アルゴリズムの性質 258 |
| 4.2.8変換領域PKFアルゴリズム 259 |
| 4.2.9シミュレーション結果の比較(2) 262 |
| 4.2.10多チャネルエコーキャンセラ 264 |
| 4.2.11シミュレーション結果の比較(3) 266 |
| 引用・参考文献 269 |
| 索引 277 |
| 1.1線形離散時間システムの状態推定アルゴリズム 1 |
| 1.1.1状態推定の概念 1 |
| 1.1.2状態推定問題 2 |
|
| 66.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
戸田不二緒 [ほか] 著
| 出版情報: |
東京 : 講談社, 1988.4 vii, 147p ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 序文 iii |
| 1 生体物質 |
| 1.1 アミノ酸 1 |
| 1.1.1 α-アミノ酸 1 |
| 1.1.2 その他のアミノ酸 5 |
| 1.2 タンパク質 7 |
| 1.2.1 ペプチド結合 7 |
| 1.2.2 タンパク質の分類と機能 8 |
| 1.2.3 タンパク質の構造 9 |
| 1.3 糖 11 |
| 1.3.1 糖質 12 |
| 1.3.2 単糖類 14 |
| 1.3.3 オリゴ糖類 16 |
| 1.3.4 多糖類 16 |
| 1.3.5 配糖体 17 |
| 1.4 核酸-遺伝情報 17 |
| 1.4.1 遺伝情報と核酸 17 |
| 1.4.2 DNAの複製 23 |
| 1.4.3 DNAの転写 25 |
| 1.4.4 遺伝コードと翻訳 26 |
| 1.4.5 遺伝子の構成と制御 28 |
| 1.5 機能性タンパク質 29 |
| 1.5.1 機能性タンパク質の分類 30 |
| 1.5.2 酵素 31 |
| 1.5.3 輸送タンパク質 45 |
| 1.5.4 その他の機能性タンパク質 52 |
| 問題 53 |
| 2 生体エネルギー論 |
| 2.1 自由エネルギー 55 |
| 2.2 代謝回路 56 |
| 2.2.1 エネルギー変換 56 |
| 2.2.2 解糖と発酵 58 |
| 2.2.3 クエン酸回路 61 |
| 2.2.4 電子伝達系 64 |
| 2.2.5 プロトンポンプ機構 66a |
| 2.3 光合成 67 |
| 2.3.1 光合成における物質の流れ 68 |
| 2.3.2 植物のCO2の固定 70 |
| 2.3.3 C4植物 71 |
| 2.3.4 電子・エネルギーの流れ 74 |
| 2.3.5 光合成器官 75 |
| 2.3.6 光合成色素 77 |
| 2.3.7 光合成単位 78 |
| 2.3.8 高等植物の2つの光化学系 78 |
| 2.3.9 光合成細菌 81 |
| 問題 83 |
| 3 細胞 |
| 3.1 細胞の形態と構造 84 |
| 3.1.1 細胞の組織 84 |
| 3.1.2 細胞をはかる 86 |
| 3.1.3 細胞を見る 87 |
| 3.2 細胞膜の構造と機能 90 |
| 3.2.1 細胞膜の組成 90 |
| 3.2.2 膜の流動性 92 |
| 3.2.3 細菌の細胞壁 93 |
| 3.2.4 細胞膜の輸送現象 95 |
| 3.3 細胞の増殖 97 |
| 3.3.1 細胞の周期 97 |
| 3.3.2 動植物細胞の培養 99 |
| 3.3.3 微生物の培養 99 |
| 3.4 細胞間情報伝達 100 |
| 3.4.1 細胞間信号伝達 100 |
| 問題 103 |
| 4 バイオプロセスによる物質生産 |
| 4.1 有用物質 104 |
| 4.1.1 発酵・醸造食品 104 |
| 4.1.2 精密化学品 113 |
| 4.2 ニューバイオテクノロジー 123 |
| 4.2.1 遺伝子工学 123 |
| 4.2.2 細胞工学 127 |
| 4.3 生産と分離 130 |
| 4.3.1 バイオリアクター 130 |
| 4.3.2 分離・精製 139 |
| 参考書 143 |
| 索引 144 |
|
| 67.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
原惟行, 松永秀章著
| 出版情報: |
東京 : 共立出版, 2007.10 v, 147p ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 第1章 複素数 1 |
| 1.1 複素数と複素平面 1 |
| 1.1.1 複素数 1 |
| 1.1.2 複素平面と極形式 3 |
| 1.1.3 複素数の演算の幾何学的意味 6 |
| 1.2 複素数列 11 |
| 第2章 複素関数と微分 16 |
| 2.1 複素関数 16 |
| 2.1.1 写像 16 |
| 2.1.2 極限値 25 |
| 2.1.3 連続関数 27 |
| 2.2 複素微分と正則関数 29 |
| 2.2.1 複素微分 29 |
| 2.2.2 正則関数 34 |
| 2.3 複素初等関数 41 |
| 2.3.1 指数関数 41 |
| 2.3.2 三角関数,双曲線関数 45 |
| 2.3.3 対数関数 48 |
| 2.3.4 べき関数 51 |
| 第3章 複素積分 56 |
| 3.1 複素積分 56 |
| 3.1.1 準備 56 |
| 3.1.2 曲線のパラメータ表示 58 |
| 3.1.3 平面上の領域 60 |
| 3.1.4 複素関数の積分 61 |
| 3.1.5 原始関数 66 |
| 3.1.6 線積分とグリーンの定理 67 |
| 3.1.7 コーシーの積分定理 69 |
| 3.2 正則関数の積分表示 72 |
| 3.2.1 積分表示 72 |
| 3.2.2 導関数 75 |
| 3.2.3 正則関数の性質 79 |
| 第4章 関数の級数展開 82 |
| 4.1 関数列の一様収束 82 |
| 4.2 テイラー展開 86 |
| 4.3 一致の定理 91 |
| 4.4 ローラン展開 95 |
| 4.5 孤立特異点 100 |
| 4.5.1 除去可能な特異点 101 |
| 4.5.2 極 103 |
| 4.5.3 孤立真性特異点 106 |
| 第5章 留数とその定積分への応用 108 |
| 5.1 留数と複素積分 108 |
| 5.1.1 留数 108 |
| 5.1.2 留数定理 114 |
| 5.2 定積分の計算 117 |
| 5.2.1 ∑2π 0 F(cosθ,sinθ)dθ 117 |
| 5.2.2 ∑∞ -∞ F(x)dx 119 |
| 5.2.3 ∑∞ -∞ F(x)e iλx dx(λ>0)の計算 122 |
| 5.2.4 その他の積分 125 |
| 付録A 極の位数と留数に関する注意 130 |
| 付録B 等角写像 133 |
| 問題略解 137 |
| 第1章 複素数 1 |
| 1.1 複素数と複素平面 1 |
| 1.1.1 複素数 1 |
|
| 68.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
岡部靖憲著
| 出版情報: |
東京 : 朝倉書店, 2005.11 viii, 310p, 図版[4]p ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 1. 実験数学 1 |
| 1.1 モデルの破綻とKMO_ランジュヴァン方程式論 1 |
| 1.1.1 アインシュタインのブラウン運動の理論 1 |
| 1.1.2 アルダー : ウェインライト効果 2 |
| 1.1.3 T-正値性とKMO_ランジュヴァン方程式論 3 |
| 1.1.4 ブラック・ショールズモデルと金融破綻 4 |
| 1.2 KMOの命名の経緯 5 |
| 1.3 般若心経と実験数学 7 |
| 1.4 揺動散逸原理とKM2O_ランジュヴァン方程式論 10 |
| 2. KM2O_ランジュヴァン方程式論 12 |
| 2.1 時系列とその標本空間 12 |
| 2.2 確率論の基礎的概念 15 |
| 2.3 関数解析学の基礎的概念 25 |
| 2.4 階数6の非線形変換 40 |
| 2.5 KM2O_ランジュヴァン方程式 42 |
| 2.5.1 非退化 43 |
| 2.5.2 退化 52 |
| 2.5.3 KM2Oの命名の経緯 62 |
| 2.6 弱定常性と揺動散逸定理 63 |
| 2.7 揺動散逸アルゴリズム 83 |
| 2.7.1 弱定常性を満たす場合 83 |
| 2.7.2 一般の場合 86 |
| 2.8 揺動散逸原理 94 |
| 2.8.1 弱定常性を満たす場合 94 |
| 2.8.2 一般の場合 95 |
| 2.9 非線形情報空間と生成系 95 |
| 2.9.1 非線形情報空間 96 |
| 2.9.2 階数有限の非線形変換のクラスT(q)(X) 101 |
| 2.9.3 非線形情報空間の多項式型の生成系 104 |
| 2.9.4 階数有限の非線形変換のクラスT(q,d)(X) 105 |
| 2.9.5 非線形情報空間の生成系 106 |
| 2.10 因果性 109 |
| 2.10.1 線形因果性と非線形因果性 109 |
| 2.10.2 因果関数 114 |
| 2.10.3 因果関数による因果性の特徴付け 123 |
| 2.10.4 弱定常過程に対する非線形因果性 125 |
| 2.11 決定性 126 |
| 2.11.1 決定性 126 |
| 2.11.2 決定性と定常性 128 |
| 2.12 非線形予測問題 130 |
| 2.12.1 非線形予測公式 130 |
| 2.12.2 予測誤差と因果関数 133 |
| 2.12.3 応用 : 非線形システムの予測問題 136 |
| 2.12.4 非線形予測問題の研究の歴史 140 |
| 3. 時系列解析 143 |
| 3.1 Test(S) 143 |
| 3.1.1 見本共分散関数 143 |
| 3.1.2 階数有限の非線形変換 144 |
| 3.1.3 見本共分散行列関数とそれに付随する見本KM2O_ランジュヴァン行列系 145 |
| 3.1.4 時系列における揺動散逸原理 150 |
| 3.1.5 Test(S) 152 |
| 3.2 Test(S) 154 |
| 3.2.1 トレーサビリティ 155 |
| 3.2.2 見本2点相関関数 156 |
| 3.2.3 階級有限の非線形変換 157 |
| 3.2.4 見本2点相関行列関数とそれに付随する見本KM2O_ランジュヴァン行列系 159 |
| 3.2.5 Test(EP) 161 |
| 3.3 Test(ABN) 164 |
| 3.3.1 定常性の破れとしての異常性 165 |
| 3.3.2 等確率性の破れとしての異常性 168 |
| 3.4 Test(CS) 169 |
| 3.4.1 見本因果関数と見本因果値 169 |
| 3.4.2 アルゴリズム 171 |
| 3.4.3 LN(q,d)-因果性と関数関係 173 |
| 3.5 Test(D) 178 |
| 3.5.1 LL-決定性とダイナミクス 178 |
| 3.5.2 LN(q,d)-決定性とダイナミクス 182 |
| 3.5.3 ランダムなダイナミクスとしての見本KM2O_ランジュヴァン方程式 183 |
| 4. 実証分析 185 |
| 4.1 地震波 185 |
| 4.1.1 P波とS波 186 |
| 4.1.2 Test(ABN)と地震波の初期位相の兆候 188 |
| 4.1.3 Test(D)と分離性 203 |
| 4.1.4 Test(D)と決定性 211 |
| 4.2 電磁波 214 |
| 4.2.1 オーロラ 215 |
| 4.2.2 磁気嵐 217 |
| 4.2.3 Test(ABN)とオーロラ・磁気嵐の発生 218 |
| 4.2.4 Test(D)と分離性 223 |
| 4.3 脳波 229 |
| 4.3.1 脳 231 |
| 4.3.2 大脳 231 |
| 4.3.3 1次運動野とその情報源 234 |
| 4.3.4 脳波 235 |
| 4.3.5 親指の随意運動と脳波の挙動(1) : Test(ABN)と異常性 239 |
| 4.3.6 親指の随意運動と脳波の挙動(2) : Test(D)と分離性 243 |
| 4.4 音声 248 |
| 4.4.1 日本語の母音 : Test(ABN),Test(D)と定常性,分離性 251 |
| 4.4.2 日本語の母音 : Test(D)と決定性 252 |
| 5. 分離性 255 |
| 5.1 時系列の分離性 255 |
| 5.1.1 分離性-0 255 |
| 5.1.2 分離性-0と共分散関数の挙動 256 |
| 5.1.3 分離性-iと共分散関数の挙動(1〓i〓18) 264 |
| 5.1.4 時系列の分離性の定義 269 |
| 5.2 確率過程の分離性 271 |
| 5.2.1 確率過程の分離性の定義 271 |
| 5.2.2 対称性と分離性 272 |
| 5.2.3 周波数域表現と対称性 277 |
| 5.2.4 対称性の破れと分離性 287 |
| 5.2.5 サインウェーブと深部低周波地震波 290 |
| 文献 294 |
| 索引 303 |
| 1. 実験数学 1 |
| 1.1 モデルの破綻とKMO_ランジュヴァン方程式論 1 |
| 1.1.1 アインシュタインのブラウン運動の理論 1 |
|
| 69.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
鈴木庸一, 真下清, 山口達明著
| 出版情報: |
東京 : 三共出版, 2002.4 vi, 236p ; 26cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 注 : C[4]の[4]は下つき文字 |
| 注 : C[5]の[5]は下つき文字 |
| 注 : CO[2]の[2]は下つき文字 |
| 注 : C[1]の[1]は下つき文字 |
| |
| 1. 有機資源 |
| 1.1 地球の進化と有機鉱床の形成 2 |
| 1.2 石炭資源 4 |
| 1.2.1 石炭鉱床の形成 4 |
| 1.2.2 石炭資源と埋蔵量 6 |
| 1.2.3 石炭の採掘・選炭 8 |
| 1.3 石油資源 10 |
| 1.3.1 石油鉱床の形成 10 |
| 1.3.2 石油資源埋蔵量 12 |
| 1.3.3 石油の採取 14 |
| 1.4 天然ガス資源 16 |
| 1.4.1 天然ガスの成因と分類 16 |
| 1.4.2 資源量と消費量 18 |
| 1.4.3 非在来型天然ガス 20 |
| 1.4.4 天然ガスの輸送 22 |
| 2. 石炭 |
| 2.1 石炭化学 26 |
| 2.1.1 石炭組織 26 |
| 2.1.2 無機鉱物質 28 |
| 2.1.3 石炭の分類 28 |
| 2.1.4 石炭の分析 30 |
| (1)工業分析 30 |
| (2)元素分析 32 |
| (3)発熱量 32 |
| 2.1.5 物理的性質 34 |
| (1)孔隙率と孔隙構造 34 |
| (2)密度 34 |
| (3)反射率 34 |
| (4)粘結性 36 |
| 2.1.6 化学的性質 36 |
| (1)官能基分析 36 |
| (2)溶媒抽出 36 |
| 2.1.7 石炭の化学構造 40 |
| (1)概論 40 |
| (2)溶媒抽出 40 |
| (3)単位構造 44 |
| (4)酸化生成物 44 |
| (5)赤外線吸収スペクトル 46 |
| (6)核磁気共鳴吸収スペクトル 48 |
| 2.1.8 分子構造モデル 50 |
| 2.2 石炭工業 58 |
| 2.2.1 石炭の利用 58 |
| 2.2.2 コークス化 60 |
| (1)歴史 60 |
| (2)原料石炭 62 |
| (3)コークス炉 64 |
| (4)コークスの形成機構 64 |
| (5)コークスの用途 68 |
| (6)副産物 70 |
| 2.2.3 ガス化 74 |
| (1)歴史 74 |
| (2)ガス化方式 76 |
| (3)基本反応 78 |
| (4)ガス化炉内の反応 80 |
| (5)原料石炭と触媒 80 |
| (6)ガス化技術の動向 82 |
| (7)ガス精製 84 |
| 2.2.4 液化 86 |
| (1)歴史 86 |
| (2)液化の基本反応 88 |
| (3)液化反応の機構 92 |
| (4)液化方式 92 |
| (5)原料石炭と液化触媒 102 |
| (6)液化油と石油の比較 104 |
| 2.2.5 スラリー化 106 |
| (1)COM 106 |
| (2)CWM 106 |
| (3)CMM 110 |
| 3. 石油精製 |
| 3.1 石油の利用 114 |
| 3.1.1 石油の分類 116 |
| 3.2 原油の組成 118 |
| 3.2.1 炭化水素化合物 118 |
| (1)パラフィン系炭化水素 118 |
| (2)ナフテン系炭化水素 118 |
| (3)芳香族炭化水素 120 |
| 3.2.2 非炭化水素化合物 120 |
| (1)硫黄化合物 120 |
| (2)窒素化合物 120 |
| (3)金属化合物 122 |
| 3.3 石油精製工業 122 |
| 3.3.1 石油精製 122 |
| (1)原油の蒸留 122 |
| (2)水素化精製 124 |
| (3)オクタン価 126 |
| (4)セタン価 128 |
| (5)硫黄の回収 130 |
| 3.3.2 石油の分解 132 |
| (1)熱分解法 132 |
| (2)接触分解 134 |
| (3)水素化分解法 138 |
| (4)接触改質 140 |
| (5)高オクタン価ガソリン基材の製造 142 |
| 3.3.3 石油製品 146 |
| (1)液化石油ガス 146 |
| (2)ガソリン 146 |
| (3)航空タービン燃料油 150 |
| (4)灯油 150 |
| (5)経由 150 |
| (6)重油 152 |
| (7)潤滑油 152 |
| (8)アスファルト 154 |
| 4. 石油化学工業 |
| 4.1 石油化学工業 158 |
| 4.2 石油化学原料 158 |
| (1)ナフサの熱分解 160 |
| (2)熱分解生成分の分離,精製 160 |
| (3)C[4]オレフィンの分離と製造 162 |
| (4)C[5]オレフィンの分離と製造 164 |
| (5)芳香族炭化水素の製造 164 |
| (6)芳香族炭化水素の製造系統図 172 |
| 4.3 石油化学製品 174 |
| 4.3.1 エチレンから得られる石油化学製品 174 |
| (1)重合 174 |
| (2)アルキル化 176 |
| (3)塩素化 178 |
| (4)酸化反応 180 |
| (5)水和反応 184 |
| 4.3.2 プロレンから得られる石油化学製品 186 |
| (1)重合 186 |
| (2)アルキル化 188 |
| (3)塩素化 188 |
| (4)酸化反応 188 |
| (5)ヒドロホルミル化反応 192 |
| (6)水和反応 194 |
| 4.3.3 C[4],C[5]オレフィンから得られる石油化学製品 194 |
| (1)プタジエン 194 |
| (2)イソブチレン 196 |
| (3)1,2-ブテン 196 |
| (4)イソプレン 198 |
| 4.3.4 芳香族炭化水素から得られる石油化学製品 198 |
| (1)ベンゼンから得られる石油化学製品 198 |
| (2)トルエンから得られる石油化学製品 202 |
| (3)キシレンから得られる石油化学製品 202 |
| 5. 天然ガス |
| 5.1 燃料としての利用 208 |
| 5.1.1 燃料としての天然ガスの評価 208 |
| (1)資源寿命 208 |
| (2)環境性 208 |
| 5.1.2 エネルギー利用(1) 210 |
| (1)都市ガス |
| (2)LNG火力発電 210 |
| (3)熱電併給システム 210 |
| 5.1.3 エネルギー利用(2) 212 |
| 5.2 化学工業原料としての利用 214 |
| 5.2.1 メタンの化学的性質 214 |
| (1)分子構造の対称性と安定性 214 |
| (2)結合エネルギーとイオン化ポテンシャル 214 |
| (3)反応性 214 |
| 5.2.2 天然ガス化学工業 216 |
| (1)天然ガス成分の化学的利用 216 |
| (2)メタンを原料とする化学品 216 |
| 5.2.3 天然ガスを原料とする合成ガス工業 218 |
| (1)合成ガス製造 218 |
| (2)水蒸気改質 218 |
| (3)酵素改質 218 |
| (4)CO[2]改質 218 |
| 5.2.4 メタノールおよびアンモニア合成 220 |
| (1)メタノール製造 220 |
| (2)アンモニア合成 220 |
| 5.2.5 C[1]化学プロジェクト 222 |
| (1)基礎化学品の原料転換 222 |
| (2)C2化学工業の原料 222 |
| (3)含窒素化合物合成と触媒技術 222 |
| (4)C[1]化学の現状 222 |
| 5.2.6 天然ガスから炭化水素製造法の開発 224 |
| (1)天然ガスから液体燃料の製造 224 |
| (2)メタンからエチレンの合成 226 |
| 5.2.7 原料用メタノール226 |
| (1)ホルムアルデヒドの製造とそれを中間原料とする製品 226 |
| (2)酢酸製造 226 |
| 5.2.8 メタノールの新しい利用法 228 |
| (1)DME 228 |
| (2)燃料用エタノール 228 |
| (3)輸送用メタノール 228 |
| 参考図書,文献,資料 231 |
| 索引 233 |
| 注 : C[4]の[4]は下つき文字 |
| 注 : C[5]の[5]は下つき文字 |
| 注 : CO[2]の[2]は下つき文字 |
|
| 70.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
粉体工学会編
| 出版情報: |
東京 : 日刊工業新聞社, 2009.3 xii, 234p ; 21cm |
| シリーズ名: |
粉体工学叢書 ; 第6巻 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 粉体工学叢書 発刊のことば i |
| 粉体工学叢書 序文 iii |
| 粉体工学叢書 編集委員 v |
| 粉体工学叢書 第6巻 粉体の成形 はじめに vii |
| 粉体工学叢書 第6巻 粉体の成形 執筆者一覧 xii |
| 第1章 原料の調製と評価 |
| 1.1 原料の乾燥と造粒 1 |
| 1.1.1 粉体乾燥の基礎 1 |
| 1.1.2 乾燥装置の分類と選定 10 |
| 1.1.3 乾燥方式と装置の種類 13 |
| 1.1.4 連続式熱風乾燥機の設計 27 |
| 1.1.5 造粒 31 |
| 1.2 スラリーの評価 34 |
| 1.2.1 スラリーの流動性評価 35 |
| 1.2.2 充填特性の評価法 40 |
| 1.2.3 粒子集合状態の評価 49 |
| 1.3 コンパウンドの調製と評価 53 |
| 1.3.1 コンパウンドのCPVC決定とその付近での流動挙動 56 |
| 1.3.2 表面改質によるコンパウンドのレオロジーに対する効果 59 |
| 1.3.3 混練による樹脂の劣化 65 |
| 1.3.4 練り土 67 |
| 参考・引用文献 69 |
| 第2章 成形法 |
| 2.1 製品形状と成形方法 75 |
| 2.1.1 セラミックスの成形法 76 |
| 2.1.2 成形における基本要件 79 |
| 2.1.3 製品形状による成形方法の選択 81 |
| 2.2 湿式成形 82 |
| 2.2.1 テープ成形 83 |
| 2.2.2 鋳込み成形 91 |
| 2.2.3 電気泳動成形 101 |
| 2.2.4 射出成形 104 |
| 2.2.5 押出し成形 115 |
| 2.3 乾式成形 126 |
| 2.3.1 原料調製 128 |
| 2.3.2 顆粒特性およびその評価法 132 |
| 2.3.3 成形特性 139 |
| 2.3.4 CIP成形 143 |
| 2.4 その他の成形法 144 |
| 2.4.1 新しい成形法への展開 144 |
| 2.4.2 熱間静水圧加圧(HIP)成形 146 |
| 2.4.3 ゲルキャスティング 151 |
| 2.5 多孔体の成形 161 |
| 参考・引用文献 170 |
| 第3章 乾 燥 |
| 3.1 基礎理論 182 |
| 3.1.1 乾燥収縮 182 |
| 3.1.2 熱と物質の成形体内部移動方程式 186 |
| 3.1.3 乾燥応力・変形モデル 190 |
| 3.2 成形体の乾燥 195 |
| 3.2.1 種々の材料の乾燥収縮解析法 195 |
| 3.2.2 乾燥機の設計法 200 |
| 3.2.3 乾燥機の種類と特徴 201 |
| 3.3 塗布膜の乾燥 206 |
| 参考・引用文献 208 |
| 第4章 シミュレーション |
| 4.1 鋳込み成形 215 |
| 4.1.1 鋳込み成形における着肉過程 215 |
| 4.1.2 着肉層形成過程のFEMシミュレーション 217 |
| 4.1.3 シミュレーションと実測の比較 218 |
| 4.2 加圧成形 220 |
| 4.2.1 有限要素法を用いた加圧粉体層内の応力分布の推算 220 |
| 4.2.2 顆粒粉体層の加圧過程のFEMシミュレーション 222 |
| 4.2.3 粉体および顆粒層の圧縮挙動のDEMシミュレーション 225 |
| 参考・引用文献 226 |
| 索引 229 |
| 粉体工学叢書 発刊のことば i |
| 粉体工学叢書 序文 iii |
| 粉体工学叢書 編集委員 v |
|
| 71.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
土木学会コンクリート委員会規準関連小委員会編集
| 出版情報: |
東京 : 土木学会 , 東京 : 丸善 (発売), 2007.5- 冊 ; 31cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| コンクリート標準示方書の適用について i |
| [第一部 維持管理] |
| 1章 総則 1 |
| 1.1 適用の範囲 1 |
| 1.2 維持管理の原則 3 |
| 1.3 用語の定義 5 |
| 2章 要求性能 9 |
| 2.1 原則 9 |
| 2.2 一般 9 |
| 3章 維持管理の方法 12 |
| 3.1 原則 12 |
| 3.2 維持管理計画 13 |
| 3.2.1 一般 13 |
| 3.2.2 維持管理の区分と内容 15 |
| 3.3 診断 16 |
| 3.3.1 一般 16 |
| 3.3.2 初期の診断 18 |
| 3.3.3 定期の診断 19 |
| 3.3.4 臨時の診断 20 |
| 3.4 対策 22 |
| 3.5 記録 22 |
| 4章 点検 23 |
| 4.1 原則 23 |
| 4.2 初期点検 26 |
| 4.3 日常点検 29 |
| 4.4 定期点検 30 |
| 4.5 臨時点検 32 |
| 4.6 緊急点検 33 |
| 4.7 点検における調査 34 |
| 4.7.1 一般 34 |
| 4.7.2 調査の項目 34 |
| 4.7.3 調査の方法 36 |
| 4.7.3.1 一般 36 |
| 4.7.3.2 書類による方法(書類調査) 39 |
| 4.7.3.3 目視による方法およびたたきによる方法 39 |
| 4.7.3.4 非破壊検査機器を用いる方法 40 |
| 4.7.3.5 局部的な破壊を伴う調査 42 |
| 4.7.3.6 実構造物の裁荷試験および振動試験による調査 43 |
| 4.7.3.7 荷重および環境作用を評価するための調査 43 |
| 4.7.3.8 補修材料および補強材料に関する試験 44 |
| 4.7.3.9 モニタリンクによる調査 45 |
| 5章 劣化機構の推定および劣化予測 46 |
| 5.1 原則 46 |
| 5.2 劣化機構の推定方法 48 |
| 5.3 劣化予測 53 |
| 6章 評価および判定 55 |
| 6.1 原則 55 |
| 6.2 初期の診断における評価および判定 56 |
| 6.2.1 一般 56 |
| 6.2.2 初期点検に基づく性能評価 57 |
| 6.2.3 初期点検に基づく対策の要否の判定 57 |
| 6.2.4 初期の診断に基づく維持管理計画の見直し 58 |
| 6.3 定期の診断における評価および判定 58 |
| 6.3.1 一般 58 |
| 6.3.2 日常点検に基づく評価および判定 59 |
| 6.3.3 定期点検に基づく性能評価 60 |
| 6.3.4 定期点検に基つく対策の要否の判定 61 |
| 6.4 臨時の診断における評価および判定 61 |
| 6.4.1 一般 61 |
| 6.4.2 臨時点検に基づく性能評価 61 |
| 6.4.3 臨時点検に基つく対策の要否の判定 62 |
| 6.4.4 緊急点検に基つく性能評価および対策の要否の判定 63 |
| 6.5 詳細調査に基づく性能評価および対策の要否の判定 63 |
| 7章 対策 66 |
| 7.1 原則 66 |
| 7.2 対策の種類と選定 67 |
| 7.2.1 一般 67 |
| 7.2.2 点検強化 68 |
| 7.2.3 補修 69 |
| 7.2.4 補強 69 |
| 7.2.5 機能向上 70 |
| 7.2.6 供用制限 70 |
| 7.2.7 解体・撤去 70 |
| 7.3 補修および補強 71 |
| 7.3.1 原則 71 |
| 7.3.2 補修および補強の設計 71 |
| 7.3.3 補修および補強の施工 75 |
| 7.3.4 補修および補強後の維持管理計画 76 |
| 8章 記録 78 |
| 8.1 原則 78 |
| 8.2 記録の方法 78 |
| 8.3 記録の項目 79 |
| 8.4 記録の保管 80 |
| [第二部 劣化機構別維持管理] |
| 9章 中性化に対する構造物の維持管理 81 |
| 9.1 総則 81 |
| 9.2 維持管理計画 83 |
| 9.2.1 計画策定の基本 83 |
| 9.2.2 維持管理区分の設定 84 |
| 9.2.3 維持管理マニュアルの作成 85 |
| 9.3 診断 85 |
| 9.3.1 一般 85 |
| 9.3.2 点検 86 |
| 9.3.2.1 一般 86 |
| 9.3.2.2 初期点検 87 |
| 9.3.2.3 日常点検 88 |
| 9.3.2.4 定期点検 88 |
| 9.3.2.5 詳細調査 89 |
| 9.3.3 構造物の性能低下の予測の方法 91 |
| 9.3.3.1 一般 91 |
| 9.3.3.2 中性化の進行予測 92 |
| 9.3.3.3 鋼材腐食の進行予測 94 |
| 9.3.3.4 予測の修正 96 |
| 9.3.4 評価および判定 96 |
| 9.4 対策 98 |
| 9.4.1 対策の選定 98 |
| 9.4.2 補修および補強 99 |
| 9.5 記録 100 |
| 10章 塩害に対する構造物の維持管理 101 |
| 10.1 総則 101 |
| 10.2 維持管理計画 103 |
| 10.2.1 計画策定の基本 103 |
| 10.2.2 維持管理区分の設定 103 |
| 10.2.3 維持管理マニュアルの作成 104 |
| 10.3 診断 105 |
| 10.3.1 一般 105 |
| 10.3.2 点検 105 |
| 10.3.2.1 一般 105 |
| 10.3.2.2 初期点検 106 |
| 10.3.2.3 日常点検 107 |
| 10.3.2.4 定期点検 107 |
| 10.3.2.5 詳細調査 108 |
| 10.3.3 構造物の性能低下の予測の方法 110 |
| 10.3.3.1 一般 110 |
| 10.3.3.2 塩化物イオンの拡散の予測 111 |
| 10.3.3.3 鋼材腐食の進行予測 114 |
| 10.3.3.4 予測の修正 116 |
| 10.3.4 評価および判定 116 |
| 10.4 対策 118 |
| 10.4.1 対策の選定 118 |
| 10.4.2 補修および補強 118 |
| 10.5 記録 120 |
| 11章 凍害に対する構造物の維持管理 121 |
| 11.1 総則 121 |
| 11.2 維持管理計画 123 |
| 11.2.1 計画策定の基本 123 |
| 11.2.2 維持管理区分の設定 124 |
| 11.2.3 維持管理マニュアルの作成 124 |
| 11.3 診断 125 |
| 11.3.1 一般 125 |
| 11.3.2 点検 125 |
| 11.3.2.1 一般 125 |
| 11.3.2.2 初期点検 126 |
| 11.3.2.3 日常点検 127 |
| 11.3.2.4 定期点検 127 |
| 11.3.2.5 詳細調査 128 |
| 11.3.3 構造物の性能低下の予測の方法 129 |
| 11.3.3.1 一般 129 |
| 11.3.3.2 凍害発生の予測 130 |
| 11.3.3.3 凍害深さの予測 131 |
| 11.3.3.4 予測の修正 132 |
| 11.3.4 評価および判定 132 |
| 11.4 対策 134 |
| 11.4.1 対策の選定 134 |
| 11.4.2 補修および補強 134 |
| 11.5 記録 136 |
| 12章 化学的侵食に対する構造物の維持管理 137 |
| 12.1 総則 137 |
| 12.2 維持管理計画 139 |
| 12.2.1 計画策定の基本 139 |
| 12.2.2 維持管理区分の設定 139 |
| 12.2.3 維持管理マニュアルの作成 140 |
| 12.3 診断 141 |
| 12.3.1 一般 141 |
| 12.3.2 点検 141 |
| 12.3.2.1 一般 141 |
| 12.3.2.2 初期点検 142 |
| 12.3.2.3 日常点検 143 |
| 12.3.2.4 定期点検 144 |
| 12.3.2.5 詳細調査 144 |
| 12.3.3 構造物の性能低下の予測の方法 146 |
| 12.3.3.1 一般 146 |
| 12.3.3.2 化学的侵食の進行予測 147 |
| 12.3.3.3 鋼材腐食の進行予測 149 |
| 12.3.3.4 予測の修正 150 |
| 12.3.4 評価および判定 151 |
| 12.4 対策 152 |
| 12.4.1 対策の選定 152 |
| 12.4.2 補修およひ補強 153 |
| 12.5 記録 154 |
| 13章 アルカソシリカ反応に対する構造物の維持管理 155 |
| 13.1 総則 155 |
| 13.2 維持管理計画 158 |
| 13.2.1 計画策定の基本 158 |
| 13.2.2 維持管理区分の設定 159 |
| 13.2.3 維持管理マニュアルの作成 159 |
| 13.3 診断 160 |
| 13.3.1 一般 160 |
| 13.3.2 点検 160 |
| 13.3.2.1 一般 160 |
| 13.3.2.2 初期点検 161 |
| 13.3.2.3 日常点検 162 |
| 13.3.2.4 定期点検 163 |
| 13.3.2.5 詳細調査 163 |
| 13.3.3 構造物の性能低下の予測の方法 166 |
| 13.3.3.1 一般 166 |
| 13.3.3.2 ASRによるコンクリートの膨張の進行予測 168 |
| 13.3.3.3 鋼材腐食の進行予測 169 |
| 13.3.3.4 鍛材の損傷発生の予測 169 |
| 13.3.3.5 予測の修正 170 |
| 13.3.4 評価および判定 170 |
| 13.4 対策 172 |
| 13.4.1 対策の選定 172 |
| 13.4.2 補修および補強 172 |
| 13.5 記録 176 |
| 14章 鉄筋コンクリート床版の疲労に対する維持管理 177 |
| 14.1 総則 177 |
| 14.2 維持管理計画 180 |
| 14.2.1 計画策定の基本 180 |
| 14.2.2 維持管理区分 180 |
| 14.2.3 維持管理マニュアルの作成 181 |
| 14.3 診断 181 |
| 14.3.1 一般 181 |
| 14.3.2 点検 181 |
| 14.3.2.1 一般 181 |
| 14.3.2.2 初期点検 183 |
| 14.3.2.3 日常点検 183 |
| 14.3.2.4 定期点検 184 |
| 14.3.2.5 詳細調査 184 |
| 14.3.3 構造物の性能低下の予測の方法 185 |
| 14.3.3.1 一般 185 |
| 14.3.3.2 予側の修正 186 |
| 14.3.4 評価および判定 187 |
| 14.4 対策 188 |
| 14.4.1 対策の選定 188 |
| 14.4.2 補修および補強 189 |
| 14.5 記録 190 |
| 15章 鉄筋コンクリートはり部材の疲労に対する維持管理 191 |
| 15.1 総則 191 |
| 15.2 維持管理計画 194 |
| 15.2.1 計画策定の基本 194 |
| 15.2.2 維持管理区分 194 |
| 15.2.3 維持管理マニュアルの作成 195 |
| 15.3 診断 195 |
| 15.3.1 一般 195 |
| 15.3.2 点検 195 |
| 15.3.2.1 一般 195 |
| 15.3.2.2 初期点検 196 |
| 15.3.2.3 日常点検 197 |
| 15.3.2.4 定期点検 198 |
| 15.3.2.5 詳細調査 199 |
| 15.3.3 はり部材の性能低下の予測の方法 200 |
| 15.3.3.1 一般 200 |
| 15.3.3.2 疲労の進行予測 201 |
| 15.3.3.3 予測の修正 202 |
| 15.3.4 評価および判定 203 |
| 15.4 対策 204 |
| 15.4.1 対策の選定 204 |
| 15.4.2 補修および補強 205 |
| 15.5 記録 206 |
| 16章 すり減りに対する構造物の維持管理 207 |
| 16.1 総則 207 |
| 16.2 維持管理計画 209 |
| 16.2.1 計画策定の基本 209 |
| 16.2.2 維持管理区分の設定 210 |
| 16.2.3 維持管理マニュアルの作成 211 |
| 16.3 診断 211 |
| 16.3.1 一般 211 |
| 16.3.2 点検 211 |
| 16.3.2.1 一般 211 |
| 16.3.2.2 初期点検 212 |
| 16.3.2.3 日常点検 213 |
| 16.3.2.4 定期点検 214 |
| 16.3.2.5 詳細調査 214 |
| 16.3.3 構造物の性能低下の予測の方法 215 |
| 16.3.3.1 一般 215 |
| 16.3.3.2 すり減りの進行予測 215 |
| 16.3.3.3 予測の修正 217 |
| 16.3.4 評価および判定 217 |
| 16.4 対策 219 |
| 16.4.1 対策の選定 219 |
| 16.4.2 補修および補強 219 |
| 16.5 記録 221 |
| 17章 耐震補強の基本 222 |
| 17.1 総則 222 |
| 17.2 耐震補強計画 222 |
| 17.3 耐震診断 223 |
| 17.3.1 一般 223 |
| 17.3.2 耐震診断のための調査 223 |
| 17.3.3 耐震性能の評価およひ耐震補強の要否の判定 224 |
| 17.4 耐震補強工法の選定 225 |
| 17.5 耐震補強設計 226 |
| 17.6 耐震補強の施工 226 |
| 17.7 耐震補強後の維持管理 228 |
| 17.8 記録 228 |
| コンクリート標準示方書の適用について i |
| [第一部 維持管理] |
| 1章 総則 1 |
|
| 72.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
粉体工学会編
| 出版情報: |
東京 : 日刊工業新聞社, 2007.1 xii, 233p ; 21cm |
| シリーズ名: |
粉体工学叢書 ; 第8巻 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 粉体工学叢書 発刊のことば i |
| 粉体工学叢書 序文 iii |
| 粉体工学叢書 編集委員 v |
| 粉体工学叢書 第8巻 粉体の反応 はじめに vii |
| 粉体工学叢書 第8巻 粉体の反応 執筆者一覧 xii |
| 第1章 粉体反応の概要 1 |
| 第2章 粉体の反応理論 |
| 2.1 反応基礎理論 5 |
| 2.1.1 未反応核モデル 6 |
| 2.1.2 グレインモデル 10 |
| 2.2 燃焼,爆発 14 |
| 2.2.1 着火 17 |
| 2.2.2 揮発分の熱分解・燃焼 17 |
| 2.2.3 固体の燃焼 18 |
| 2.2.4 爆発 19 |
| 2.3 焼成・焼結,固結,相転移 21 |
| 2.3.1 焼成・焼結 21 |
| 2.3.2 固結 29 |
| 2.3.3 相転移 31 |
| 2.4 吸収,吸着,触媒 35 |
| 2.4.1 吸収,吸着,触媒各種反応の原理 35 |
| 2.4.2 反応モデル 37 |
| 参考・引用文献 43 |
| 第3章 粉体反応に関わる諸因子 |
| 3.1 粒子の形態 47 |
| 3.2 伝熱 50 |
| 3.2.1 粉体内部の伝導伝熱と有効熱伝導度 52 |
| 3.2.2 充填層の伝熱 54 |
| 3.2.3 充填層の充填粒子と流体間の伝熱 58 |
| 3.2.4 流動層の流動粒子と流体間の伝熱 59 |
| 3.2.5 流動層の流動粒子と壁面間の伝熱 60 |
| 3.3 物質移動 65 |
| 3.3.1 粒子と流体間の物質移動 66 |
| 3.3.2 多孔質粒子内の物質移動 68 |
| 3.3.3 流動層における物質移動 70 |
| 参考・引用文献 73 |
| 第4章 反応装置 |
| 4.1 粉体の反応装置 75 |
| 4.2 固定層 77 |
| 4.2.1 原理と特徴 77 |
| 4.2.2 構造と形式 78 |
| 4.2.3 層内の反応モデル 79 |
| 4.2.4 代表的なプロセス 88 |
| 4.3 移動層 93 |
| 4.3.1 原理と特徴 93 |
| 4.3.2 構造と形式 94 |
| 4.3.3 層内の反応モデル 94 |
| 4.3.4 代表的なプロセス 99 |
| 4.4 流動層 101 |
| 4.4.1 流動化と各種流動状態 101 |
| 4.4.2 粒子の種類と流動化(Geldartによる粒子分類) 112 |
| 4.4.3 気泡の構造と気泡径 114 |
| 4.4.4 流動層の反応モデル 117 |
| 4.4.5 代表的なプロセス 128 |
| 4.5 気流層 136 |
| 4.5.1 原理と特徴 136 |
| 4.5.2 噴出部構造 139 |
| 4.5.3 反応器構造 142 |
| 4.5.4 反応メカニズムと各種モデル 145 |
| 4.5.5 代表的なプロセス 149 |
| 4.6 焼成炉 152 |
| 4.6.1 使用目的と機能 152 |
| 4.6.2 高温と制御機能 154 |
| 4.6.3 雰囲気の制御 155 |
| 4.6.4 製造方式への対応 156 |
| 4.6.5 圧力印加機能 157 |
| 4.6.6 焼成炉の種類 157 |
| 4.6.7 焼成炉の利用と周辺技術 162 |
| 参考・引用文献 166 |
| 第5章 粉体反応のシミュレーション |
| 5.1 燃焼のシミュレーション 171 |
| 5.1.1 燃焼シミュレーションの概要 171 |
| 5.1.2 燃焼シミュレーションの実例 172 |
| 5.2 相転移現象の分子シミュレーション 177 |
| 5.2.1 イジングモデルを用いたMC法による磁気相転移シミュレーション 178 |
| 5.2.2 MD法によるNaCl粒子の凝固シミュレーション 181 |
| 5.3 焼結挙動のシミュレーション 183 |
| 5.3.1 二粒子モデルによる焼結挙動のシミュレーション 183 |
| 5.3.2 焼結挙動のシミュレーション 192 |
| 5.4 流動層中の反応粒子挙動シミュレーション 199 |
| 5.4.1 計算方法 200 |
| 5.4.2 シミュレーションの実行と計算結果の紹介 207 |
| 参考・引用文献 211 |
| 記号表 217 |
| 索引 229 |
| 粉体工学叢書 発刊のことば i |
| 粉体工学叢書 序文 iii |
| 粉体工学叢書 編集委員 v |
|
| 73.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
秋山守, 有冨正憲監修
| 出版情報: |
東京 : コロナ社, 2002.1 viii, 261p ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 1. 基礎式と差分式 |
| 1.1気液二相流の数値解析と時間・空間スケール 1 |
| 1.1.1モデル選定の考え方 1 |
| 1.1.2実際に用いられている二相流モデル 2 |
| 1.1.3流動条件に特化した二相流モデル 5 |
| 1.2基礎式 8 |
| 1.2.1.瞬時・局所の式 9 |
| 1.2.2二流体モデルの基礎式 14 |
| 1.2.3気泡追跡法の基礎式 22 |
| 1.3差分式導出の考え方 24 |
| 1.3.1時間差分スキームと各項の評価時刻 24 |
| 1.3.2空間差分スキーム 25 |
| 1.4代表的な数値解法 28 |
| 1.4.1対象とする基礎式 28 |
| 1.4.2半陰解法 29 |
| 1.4.3完全陰解法 34 |
| 2. 構成式 |
| 2.1構成式の役割 38 |
| 2.2流動様式遷移条件 39 |
| 2.3流動様式様図 47 |
| 2.4気液相間での相互作用を記述するモデル 54 |
| 2.4.1気泡式 54 |
| 2.4.2スラグ流 56 |
| 2.4.3チャーン流 58 |
| 2.4.4環状噴霧流 59 |
| 2.4.5噴霧流 61 |
| 2.5壁面と流体との相互作用を記述するモデル 61 |
| 2.5.1壁面摩擦モデル 61 |
| 2.5.2壁面熱伝熱モデル 68 |
| 2.6まとめ 82 |
| 3. 二流体モデルによる多次元流動解析 |
| 3.1巨視的二流体モデル 83 |
| 3.1.1巨視的二流体モデルの特徴 84 |
| 3.1.2巨視的二流体モデルの基礎式と構成式 86 |
| 3.1.3解析事例 89 |
| 3.2微視的二流体モデル 97 |
| 3.2.1微視的二流体モデルの特徴 97 |
| 3.2.2微視的二流体モデルの基礎式と構成式 98 |
| 3.2.3解析事例 107 |
| 4. サブチャンネル解析 |
| 4.1二流体モデルによるサブチャンネル解析 114 |
| 4.1.1はじめに 114 |
| 4.1.2基礎式 115 |
| 4.1.3数値解法 117 |
| 4.1.4.構成式 120 |
| 4.1.5解析事例 125 |
| 4.2三流体モデルによるサブチャンネル解析 128 |
| 4.2.1はじめに 128 |
| 4.2.2基礎式 129 |
| 4.2.3構成式 133 |
| 4.2.4.解析事例 145 |
| 4.3まとめと今後の課題 148 |
| 5. 界面追跡法 |
| 5.1自由界面を含む気液二相流解析法 150 |
| 5.1.1はじめに 150 |
| 5.1.2一流体モデルに基づく運動方程式の導出 152 |
| 5.1.3Projection法 155 |
| 5.1.4表面張力モデル 157 |
| 5.1.5界面再構成法 164 |
| 5.2気泡追跡法 178 |
| 5.2.1Two-Way気泡追跡法 179 |
| 5.2.2One-Way気泡追跡法 191 |
| 5.2.3解析事例 200 |
| 6. 特別な流れ場の解析 |
| 6.1圧縮性が顕著な流れ場の解析 207 |
| 6.1.1はじめに 207 |
| 6.1.2HSMAC法を用いた気泡流中の圧力波伝播解析 209 |
| 6.1.3二流体モデルによる二相噴流解析 213 |
| 6.1.4おわりに 225 |
| 6.2物体まわりの噴霧流の解析 226 |
| 6.2.1液滴挙動解析における基礎方程式 226 |
| 6.2.2液滴-蒸気間、液滴間の相互作用 229 |
| 6.2.3壁面衝突液滴モデル 232 |
| 6.2.4乱流モデル 235 |
| 6.2.5解析事例 239 |
| 参考文献 242 |
| 索引 259 |
| 1. 基礎式と差分式 |
| 1.1気液二相流の数値解析と時間・空間スケール 1 |
| 1.1.1モデル選定の考え方 1 |
|
| 74.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
日本バーチャルリアリティ学会編
| 出版情報: |
東京 : 工業調査会, 2010.1 xiv, 384p, 図版 [7] p ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 口絵 |
| はじめに |
| 監修者・編集委員・執筆者一覧 |
| 第1章 バーチャルリアリティとは |
| 1.1 バーチャルリアリティとは何か 5 |
| 1.1.1 バーチャルの意味 2 |
| 1.1.2 バーチャルリアリティとその三要素 5 |
| 1.1.3 バーチャルリアリティと人間の認知機構 7 |
| 1.1.4 バーチャルリアリティの概念と日本語訳 8 |
| 1.1.5 道具としてのバーチャルリアリティ 10 |
| 1.2 VRの要素と構成 10 |
| 1.2.1 VRの基本構成要素 11 |
| 1.2.1 VR世界のいろいろ 12 |
| 1.2.3 VRをどうとらえるか 14 |
| 1.3 VRの歴史 16 |
| 第2章 ヒトと感覚 |
| 2.1 脳神経系と感覚・運動 24 |
| 2.1.1 脳神経系の解剖的構造と神経生理学の基礎 24 |
| 2.1.2 知覚・認知心理学の基礎 25 |
| 2.1.3 感覚と運動 26 |
| 2.2 視覚 27 |
| 2.2.1 視覚の受容器と神経系 27 |
| 2.2.2 視覚の基本特性 28 |
| 2.2.3 空間の知覚 30 |
| 2.2.4 自己運動の知覚 31 |
| 2.2.5 高次視覚 32 |
| 2.3 聴覚 33 |
| 2.3.1 聴覚系の構造 33 |
| 2.3.2 聴覚の問題と音脈分離(音源分離) 35 |
| 2.3.3 聴覚による高さ,大きさ,音色,時間の知覚 36 |
| 2.3.4 聴覚による空間知覚 38 |
| 2.4 体性感覚・内臓感覚 40 |
| 2.4.1 体性感覚・内臓感覚の分類と神経機構 40 |
| 2.4.2 皮膚感覚 40 |
| 2.4.3 深部感覚 44 |
| 2.4.4 内臓感覚 45 |
| 2.5 前庭感覚 46 |
| 2.5.1 前庭感覚の受容器と神経系 46 |
| 2.5.2 平衡機能の基本特性 47 |
| 2.5.3 身体運動と傾斜の知覚特性 48 |
| 2.5.4 動揺病 49 |
| 2.5.5 前庭感覚と視覚の相互作用 51 |
| 2.6 味覚・嗅覚 52 |
| 2.6.1 味覚の受容器と神経系 52 |
| 2.6.2 味覚の特性 54 |
| 2.6.3 嗅覚の受容器と神経系 56 |
| 2.6.4 嗅覚の特性 58 |
| 2.7 モダリティ間相互作用と認知特性 59 |
| 2.7.1 視覚と聴覚の相互作用 59 |
| 2.7.2 体性感覚とその他のモダリティの相互作用 60 |
| 2.7.3 思考、記憶と学習 61 |
| 2.7.4 アフォーダンス 64 |
| 第3章 バーチャルリアリティ・インタフェース |
| 3.1 バーチャルリアリティ・インタフェースの体系 66 |
| 3.2 入力インタフェース 69 |
| 3.2.1 物理的特性の計測 69 |
| 3.2.2 生理的特性の計測 75 |
| 3.2.3 心理的特性の計測 78 |
| 3.3 出力インタフェース 80 |
| 3.3.1 視覚ディスプレイ 81 |
| 3.3.2 聴覚ディスプレイ 86 |
| 3.3.3 前庭感覚ディスプレイ 88 |
| 3.3.4 味覚ディスプレイ 89 |
| 3.3.5 嗅覚ディスプレイ 90 |
| 3.3.6 体性感覚ディスプレイ 90 |
| 3.3.7 他の感覚との複合 94 |
| 3.3.8 神経系への直接刺激 95 |
| 3.4 入力と出力のループ 96 |
| 第4章 バーチャル世界の構成手法 |
| 4.1 総論 100 |
| 4.1.1 バーチャルリアリティのためのモデリング 100 |
| 4.1.2 レンダリング,シミュレーションとモデル 102 |
| 4.2.3 処理量とデータ量のトレードオフ 103 |
| 4.2 レンダリング 106 |
| 4.2.1 レンダリングのためのモデル 106 |
| 4.2.2 視覚レンダリングとモデル 107 |
| 4.2.3 聴覚レンダリングとモデル 110 |
| 4.2.4 力触覚レンダリングとモデル 114 |
| 4.3 シミュレーション 118 |
| 4.3.1 シミュレーションのためのモデル 118 |
| 4.3.2 空間のシミュレーション 119 |
| 4.3.3 物体のシミュレーション 124 |
| 剛体のシミュレーション 124 |
| 変形のシミュレーション 128 |
| 流体のシミュレーション 129 |
| 4.3.4 人物のシミュレーション 131 |
| 第5章 リアルとバーチャルの融合-複合現実感- |
| 5.1 複合現実感 138 |
| 5.1.1 概念 138 |
| 5.1.2 レジストレーション技術 139 |
| 5.1.3 実世界情報提示技術 145 |
| 5.1.4 実世界モデリング技術 152 |
| 5.2 ウェアラブルコンピュータ 156 |
| 5.2.1 概念 156 |
| 5.2.2 情報提示技術 157 |
| 5.2.3 入力インターフェース技術 161 |
| 5.2.4 コンテキスト認識技術 166 |
| 5.3 ユビキタスコンピューティング 171 |
| 5.3.1 概念 171 |
| 5.3.2 ユビキタス環境構築技術 172 |
| 第6章 テレイグジスタンスと臨場感コミュニケーション 178 |
| 6.1 テレイグジスタンス 178 |
| 6.1.1 テレイグジスタンスとは 178 |
| 6.1.2 標準型テレイグジスタンス 188 |
| 6.1.3 拡張型テレイグジスタンス 190 |
| 6.1.4 相互テレイグジスタンス 196 |
| 6.1.5 テレイグジスタンスシステムの構成 201 |
| 6.2 臨場感コミュニケーション 215 |
| 6.2.1 臨場感コミュニケーションと超臨場感コミュニケーション 215 |
| 6.2.2 臨場感の構成要素 221 |
| 6.2.3 臨場感コミュニケーションのインタフェース 226 |
| 6.2.4 臨場感コミュニケーションシステムの実際 232 |
| 6.2.5 時間を越えるコミュニケーション 238 |
| 第7章 VRコンテンツ |
| 7.1 VRコンテンツの要素 246 |
| 7.1.1 VRコンテンツを構成する要素 246 |
| 7.1.2 VRコンテンツの応用分野 249 |
| 7.1.3 VRコンテンツの日常生活 249 |
| 7.2 VRのアプリケーション 250 |
| 7.2.1 サイバースペースとコミュニケーション 250 |
| 7.2.2 医療 257 |
| 7.2.3 教育・訓練(シミュレータとその要素技術) 264 |
| 7.2.4 エンタテイメント 269 |
| 7.2.5 製造業 274 |
| 7.2.6 ロボティクス 278 |
| 7.2.7 可視化 286 |
| 7.2.8 デジタルアーカイブ,ミュージアム 292 |
| 7.2.9 地理情報システム 297 |
| 第8章 VRと社会 |
| 8.1 ヒト・社会の測定と評価 314 |
| 8.1.1 実験の計画 314 |
| 8.1.2 心理物理学的測定 315 |
| 8.1.3 統計的検定 318 |
| 8.1.4 調査的方法とその分析 319 |
| 8.1.5 VR心理学 321 |
| 8.2 システムの評価と設計 323 |
| 8.2.1 VRの人体への影響 323 |
| 8.2.2 福祉のためのVR 327 |
| 8.2.3 感覚の補綴と拡張 330 |
| 8.2.4 運動の補綴と拡張 332 |
| 8.3 文化と芸術を生み出すVR 337 |
| 8.3.1 メディアの進化 337 |
| 8.3.2 高臨場感メディアと超臨場感メディア 338 |
| 8.3.3 体感メディアと心感メディア 339 |
| 8.3.4 かけがえのあるメディアと、ないメディア 340 |
| 8.4 VR社会論 342 |
| 8.4.1 VRの社会的受容 342 |
| 8.4.2 VRの社会化 344 |
| 8.4.3 VRの乱用,悪用 346 |
| 8.4.4 VRにかかわる知的財産権 346 |
| 8.5 VR産業論 348 |
| 8.5.1 ゲームとVR 348 |
| 8.5.2 アートへの展開 350 |
| 8.5.3 省資源・省エネルギー・安心安全に貢献するVR 353 |
| 8.5.4 「いきがい」を生み出す産業むむけて 358 |
| 索引 363 |
| 日本バーチャルリアリティ学会とは 384 |
|
| 75.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
小柳光正監修
| 出版情報: |
東京 : シーエムシー出版, 2009.2 v, 302p ; 27cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 序章 半導体メモリの発展とDRAM最新技術(小柳光正) |
| 1. はじめに 1 |
| 2. DRAMの歴史と最新技術 2 |
| 3. DRAMの回路構成と高速化技術 10 |
| 4. eDRAMとキャパシタレス・セル 16 |
| 5. 3次元集積化技術と積層型DRAM 18 |
| 6. おわりに 21 |
| 第1章 フラッシュメモリの最新技術 |
| 1. NAND型フラッシュメモリーの最新動向(渡辺寿治) 28 |
| 1.1 フラッシュメモリーとその動作原理 28 |
| 1.2 NAND型フラッシュメモリーの動作原理 31 |
| 1.3 NAND型フラッシュメモリーの特徴と動向 34 |
| 1.4 NAND型フラッシュメモリーの微細化における問題点 36 |
| 1.5 NAND型フラッシュメモリーの微細化に対する解決手法 38 |
| 2. NOR型フラッシュメモリーの最新動向(田口眞男) 44 |
| 2.1 はじめに 44 |
| 2.2 フローティングゲートNOR型フラッシュメモリーの動作原理 44 |
| 2.2.1 プログラム方法 45 |
| 2.2.2 消去方法 47 |
| 2.2.3 メモリーセルアレー 49 |
| 2.3 チャージトラップNOR型フラッシュメモリー 50 |
| 2.3.1 メモリーセルアレー 50 |
| 2.3.2 動作原理 51 |
| 2.3.3 プログラム方法 52 |
| 2.3.4 消去方法 52 |
| 2.3.5 読み出し方法 54 |
| 2.3.6 ディスターブ 55 |
| 2.3.7 動作マージンの拡大 56 |
| 2.3.8 4ビット記憶方式 56 |
| 2.4 B4セル 57 |
| 2.5 フローティングナノドットセル 58 |
| 第2章 MRAMの最新技術 |
| 1. MRAMの最新動向(猪俣浩一郎) 61 |
| 1.1 はじめに 61 |
| 1.2 MRAMの動作原理と特徴 62 |
| 1.3 MRAMの開発状況 65 |
| 1.4 ギガビット級大容量MRAMの開発に向けて 68 |
| 1.4.1 スピン注入磁化反転 68 |
| 1.4.2 ハーフメタルの開発 73 |
| 1.5 おわりに 75 |
| 2. 磁気トンネル接合素子の技術開発(湯浅新治) 77 |
| 2.1 磁気トンネル接合素子のTMR効果 77 |
| 2.2 アモルファスAl-O障壁MTJ素子のデバイス応用とその限界 79 |
| 2.3 結晶MgO(001)トンネル障壁MTJ素子のTMR効果の理論予測 82 |
| 2.4 結晶MgO(001)障壁の作製と巨大TMR効果の実現 85 |
| 2.5 デバイス応用に適したCoFeB/MgO/CoFeB構造のMTJ素子の開発 88 |
| 2.6 CoFeB/MgO/CoFeB-MTJ素子の巨大TMR効果の機構 90 |
| 2.7 MgO障壁MTJ素子のデバイス応用 93 |
| 3. スピン注入書き込み型MRAM(鹿野博司) 97 |
| 3.1 まえがき 97 |
| 3.2 スピン注入磁化反転現象 98 |
| 3.3 スピン注入書き込み型MRAM 102 |
| 3.3.1 メモリの構成 102 |
| 3.3.2 Read/Write動作 105 |
| 3.3.3 保持特性 107 |
| 3.3.4 トンネル絶縁膜信頼性 109 |
| 3.4 まとめ 110 |
| 4. トグル書込み方式(鈴木哲広) 113 |
| 4.1 はじめに 113 |
| 4.2 トグル書込み方式の原理 113 |
| 4.3 16Mbトグル型MRAM 118 |
| 4.4 トグル型MRAMの書込み特性の改良 121 |
| 4.5 トグル型MRAMの製品とアプリケーション 126 |
| 4.6 おわりに 128 |
| 第3章 FeRAMの最新技術 |
| 1. FeRAMの最新動向(石原宏) 130 |
| 1.1 FeRAMの特徴と現状 130 |
| 1.2 キャパシタ型FeRAMの高集積化 131 |
| 1.3 トランジスタ型FeRAMのデータ保持時間の改善 133 |
| 1.4 有機強誘電体膜を用いたFeRAM 137 |
| 2. FeRAMの基本動作と信頼性(嶋田恭博) 141 |
| 2.1 はじめに 141 |
| 2.2 2T2C/1T1Cメモリ・セル : FeRAM 142 |
| 2.2.1 セル構成と動作原理 142 |
| 2.2.2 2T2C/1T1Cメモリ・セルの信頼性上の課題 146 |
| 2.3 強誘電体ゲート・トランジスタ : FeFET 153 |
| 2.3.1 セル構成と動作原理 154 |
| 2.3.2 FeFETの信頼性上の課題 159 |
| 2.4 おわりに 160 |
| 3. FRAMの市場展望(田中均) 163 |
| 3.1 はじめに 163 |
| 3.2 FRAMの特徴 166 |
| 3.2.1 高速の書換え速度 166 |
| 3.2.2 書換え回数の多さ 167 |
| 3.2.3 書換え時の低消費電力 168 |
| 3.2.4 CMOSロジックプロセスとの親和性 168 |
| 3.3 期待される適用分野 169 |
| 3.3.1 RFID 169 |
| 3.3.2 スマートカード 171 |
| 3.3.3 車載応用 173 |
| 3.3.4 FRAMマイコン 176 |
| 3.4 おわりに 178 |
| 第4章 PRAMの最新技術 |
| 1. PRAMの原理とその動向(保坂純男) 179 |
| 1.1 はじめに 179 |
| 1.2 相変化抵抗素子の原理,特徴と課題 180 |
| 1.3 相変化材料の抵抗率アニール温度特性と結晶構造 185 |
| 1.3.1 抵抗率アニール温度特性 185 |
| 1.3.2 結晶構造 186 |
| 1.3.3 結晶サイズおよび表面構造 187 |
| 1.3.4 窒素ドープと結晶サイズ制御 189 |
| 1.4 相変化抵抗素子 189 |
| 1.4.1 直列抵抗内蔵バーティカル型相変化抵抗素子 189 |
| 1.4.2 直列抵抗内蔵バーティカル型相変化抵抗素子の省エネ化 190 |
| 1.4.3 直列並列抵抗内蔵ラテラル型相変化抵抗素子 193 |
| 1.5 多値記録相変化抵抗素子 196 |
| 1.5.1 抵抗アレー方式相変化多値記録抵抗素子 197 |
| 1.5.2 多層膜方式相変化多値記録抵抗素子 197 |
| 1.6 相変化チャンネルトランジスタ 198 |
| 1.6.1 不揮発メモリ特性 199 |
| 1.6.2 相変化チャンネル電流制御 199 |
| 1.7 まとめ 200 |
| 2. ECD/Ovonyx社における相変化電子メモリーの開発動向(太田威夫) 202 |
| 2.1 はじめに 202 |
| 2.2 アモルファス材料のオボニックスイッチングおよびメモリー現象 204 |
| 2.3 オボニックスイッチング材料 205 |
| 2.4 相変化光メモリー(光ディスク)と相変化電気メモリー 207 |
| 2.5 ECD/OvonyxとIntel,STMicro electronicsが開発したPRAM(OUM)デバイス 209 |
| 2.5.1 ECD/Ovonyxのデバイス 209 |
| 2.5.2 Intelデバイスの構造と駆動 210 |
| 2.5.3 STMicro electronics-Ovonyxのμトレンチ構造 211 |
| 2.6 相変化不揮発性メモリーPRAM(OUM)の将来展開 213 |
| 2.6.1 相変化多値メモリー 213 |
| 2.6.2 相変化PRAMのスケーリング 213 |
| 2.6.3 新相変化Cognitive素子 : 入力信号記憶スイッチング機能(Cognitive function) 215 |
| 2.7 あとがき 216 |
| 第5章 ReRAMの最新技術 |
| 1. 不揮発性抵抗変化ランダムアクセスメモリ研究開発の動向(秋永広幸,島久) 220 |
| 1.1 抵抗スイッチ効果 220 |
| 1.2 抵抗スイッチ効果を用いた不揮発性メモリ開発 224 |
| 1.2.1 ペロブスカイト型酸化物を用いたReRAM研究の動向 226 |
| 1.2.2 2元系酸化物を用いたReRAM研究の動向 228 |
| 1.2.3 プロセス開発や理論研究など注目すべき話題 231 |
| 1.3 今後の研究開発への期待 232 |
| 2. 抵抗変化メモリRRAMの電気特性制御(粟屋信義,細井康成) 236 |
| 2.1 序 236 |
| 2.1.1 はじめに 236 |
| 2.1.2 フラッシュメモリの限界とポストフラッシュへの要求 236 |
| 2.2 RRAMの特性 237 |
| 2.2.1 RRAMの定義 237 |
| 2.2.2 金属酸化物の抵抗スイッチングの歴史的経緯 238 |
| 2.2.3 直流挿引による金属酸化物の抵抗スイッチング特性 239 |
| 2.2.4 チタン酸化物可変抵抗素子 241 |
| 2.2.5 電圧パルス印加による金属酸化物の抵抗スイッチング特性と抵抗制御 245 |
| 2.2.6 メモリセルの構成 249 |
| 2.2.7 メモリとして要求される特性と課題 249 |
| 3. 遷移金属酸化物の成膜プロセス(鄒弘綱,西岡浩) 253 |
| 3.1 はじめに 253 |
| 3.2 ReRAM研究の歴史 253 |
| 3.2.1 二元系酸化物の抵抗変化特性 253 |
| 3.2.2 三元系酸化物の抵抗変化特性 255 |
| 3.2.3 三元系酸化物によるReRAM作製 256 |
| 3.2.4 二元系酸化物によるReRAM作製 257 |
| 3.2.5 ReRAM作製プロセスの比較 258 |
| 3.3 ReRAM作製プロセスの開発 258 |
| 3.3.1 成膜技術開発 258 |
| 3.3.2 ReRAM開発用スパッタ装置 260 |
| 3.3.3 CuO成膜 261 |
| 3.3.4 TiOx 261 |
| 3.4 まとめ 262 |
| 第6章 その他のメモリ最新技術 |
| 1. シリコン系ナノ構造集積と機能メモリデバイス開発(宮崎誠一,池田弥央) 265 |
| 1.1 はじめに 265 |
| 1.2 シリコン量子ドットフローティングゲートMOSメモリの特徴 265 |
| 1.3 シリコン系量子ドットの自己組織化形成 266 |
| 1.4 シリコン系量子ドットの帯電状態評価 266 |
| 1.5 Si量子ドットフローティングゲートMOSキャパシタ 268 |
| 1.6 シリコン量子ドットフローティングゲートnMOSFET 270 |
| 1.7 おわりに 276 |
| 2. シリコンドットメモリー(古賀淳二) 278 |
| 2.1 はじめに 278 |
| 2.2 動作原理 278 |
| 2.2.1 単電子効果 278 |
| 2.2.2 基本メモリー動作 279 |
| 2.3 最新技術動向 281 |
| 2.3.1 技術課題 281 |
| 2.3.2 揮発メモリー応用 281 |
| 2.3.3 トンネル絶縁膜の厚膜化 282 |
| 2.3.4 ドット材料エンジニアリング 282 |
| 2.3.5 ドット構造エンジニアリング 283 |
| 2.3.6 トンネル絶縁膜の高誘電率化 284 |
| 2.4 シリコンドットメモリーの展望 284 |
| 3. 金属ナノドット不揮発性メモリ(田中徹,裴艶麗) 286 |
| 3.1 はじめに 286 |
| 3.2 金属ナノドットを有する新型不揮発性メモリ 287 |
| 3.3 金属ナノドット膜の作製と評価 287 |
| 3.4 金属ナノドットのメモリ特性 290 |
| 3.5 高密度金属ナノドットとHigh-k絶縁膜を有するMISキャパシタデバイス 294 |
| 3.6 おわりに 294 |
| 4. ナノギャップスイッチ(内藤泰久,清水哲夫) 297 |
| 4.1 はじめに 297 |
| 4.2 ナノギャップ電極の作製手法 297 |
| 4.3 ナノギャップ電極のメモリー効果 298 |
| 4.4 まとめ及び今後の展開 301 |
| 序章 半導体メモリの発展とDRAM最新技術(小柳光正) |
| 1. はじめに 1 |
| 2. DRAMの歴史と最新技術 2 |
|
| 76.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
高橋幸雄, 森村英典著
目次情報:
続きを見る
| |
| 1.混雑現象と待ち 1 |
| 1.1 混雑現象の例 1 |
| 1.1.1 行列のできる店 1 |
| 1.1.2 初詣 2 |
| 1.1.3 電車のラッシュアワー 4 |
| 1.1.4 車の渋滞 6 |
| 1.2 なぜ混雑は起こるのか 8 |
| 1.2.1 混雑の原因 8 |
| 1.2.2 ドリップコーヒー 10 |
| 1.3 イベントにおけるさまざまな混雑 11 |
| 1.3.1 イベント:混雑現象のデパート 11 |
| 1.3.2 前売り券の販売 11 |
| 1.3.3 開門待ちの行列 12 |
| 1.3.4 チケット窓口の混雑 12 |
| 1.3.5 パビリオンの前での行列 13 |
| 1.3.6 広場や通りでの雑踏 14 |
| 1.3.7 サービス施設での混雑 14 |
| 1.3.8 入場者数の把握と緊急避難 15 |
| 1.4 系内数と滞在時間 15 |
| 1.4.1 流入-流出グラフ 15 |
| 1.4.2 滞留量の計測 17 |
| 1.4.3 平均滞在時間 19 |
| 1.4.4 リトルの公式 20 |
| 1.4.5 窓口の数を増やす効果 21 |
| 1.4.6 流入・滞留・流出 用語について 23 |
| 2.待ち行列アラカルト 25 |
| 2.1 開門待ち型の混雑 25 |
| 2.1.1 開門待ち行列 25 |
| 2.1.2 幼稚園の入園申し込み 26 |
| 2.1.3 新幹線の行列 26 |
| 2.1.4 得られる利益と待ちコスト 27 |
| 2.2 ラッシュアワー型の混雑 29 |
| 2.2.1 ラッシュアワー 29 |
| 2.2.2 学生食堂の待ち行列 29 |
| 2.2.3 病院での待ち時間 31 |
| 2.2.4 チケットの電話予約 33 |
| 2.2.5 災害時の電話の異常輻輳 34 |
| 2.3 到着がランダムな待ち行列 35 |
| 2.3.1 個人医院における待ち 35 |
| 2.3.2 有料道路の料金所 37 |
| 2.3.3 券売機,スーパーのレジ,空港のチェックインカウンター 37 |
| 2.3.4 銀行の現金自動支払機 38 |
| 2.3.5 空港の滑走路 39 |
| 2.4 呼損系の待ち行列 41 |
| 2.4.1 電話の話中音 41 |
| 2.4.2 携帯電話 42 |
| 2.4.3 ホテル,駐車場,レストラン 43 |
| 2.4.4 オーバーブッキング 44 |
| 2.5 計算機における待ち行列 45 |
| 2.5.1 計算機システムの性能評価,セントラルサーバモデル 45 |
| 2.5.2 ジョブの処理方式 47 |
| 2.5.3 キャッシュメモリ割り当て 48 |
| 2.6 通信における待ち行列 49 |
| 2.6.1 インターネット 49 |
| 2.6.2 デジタル通信ネットワーク 50 |
| 2.6.3 LAN,イーサネット 53 |
| 2.6.4 ウィンドウ制御 53 |
| 2.6.5 動画像の伝送 54 |
| 3.交通における混雑アラカルト 57 |
| 3.1 歩行者と混雑 57 |
| 3.1.1 人間の専有空間 人体楕円 57 |
| 3.1.2 電車とエレベーターの定員 58 |
| 3.1.3 歩行者と専有面積 61 |
| 3.1.4 横断歩道 62 |
| 3.1.5 ホームや階段での混雑 66 |
| 3.1.6 緊急避難と非常口 67 |
| 3.1.7 エスカレーター 69 |
| 3.1.8 エレベーター 70 |
| 3.2 車の混雑 73 |
| 3.2.1 交差点における渋滞 73 |
| 3.2.2 首都高速道路の料金所 74 |
| 3.2.3 車のダンゴ運転 75 |
| 3.2.4 ウォードロップの法則 76 |
| 3.2.5 渋滞緩和策 77 |
| 3.3 救急車とタクシー 78 |
| 3.3.1 救急車の混雑 78 |
| 3.3.2 タクシーの実車率 79 |
| 3.4 鉄道における混雑 80 |
| 3.4.1 山手線電車の運行 80 |
| 3.4.2 中央線のダイヤ回復 82 |
| 3.4.3 貨物ヤード 83 |
| 3.5 水運 85 |
| 3.5.1 バース 85 |
| 3.5.2 船腹交換 85 |
| 3.5.3 水路交通容量 85 |
| 3.6 都市 86 |
| 3.6.1 建物の高さと都市の大きさ 86 |
| 3.6.2 コンパクト・シティ 87 |
| 4.滞留型混雑アラカルト 88 |
| 4.1 備蓄と在庫 88 |
| 4.1.1 石油,米,水の備蓄 88 |
| 4.1.2 図書館,博物館,データベース 89 |
| 4.1.3 流通のゆとりとしての在庫 91 |
| 4.1.4 押し込み,お中元,バレンタインデー 93 |
| 4.2 情報利用による在庫の圧縮 94 |
| 4.2.1 流れ作業 94 |
| 4.2.2 JIT生産システムとかんばん方式 95 |
| 4.2.3 サプライ・チェイン・マネジメント(SCM) 97 |
| 4.2.4 コンビニエンス・ストアの在庫管理 98 |
| 4.3 安全在庫と最適発注量 99 |
| 4.3.1 需要の変動 99 |
| 4.3.2 需要変動を考慮した発注量 100 |
| 4.3.3 発注量の決定 101 |
| 4.3.4 機会損失モデルと予備品在庫モデル 105 |
| 4.4 通い箱 106 |
| 4.4.1 図書館,レンタカー 106 |
| 4.4.2 通い箱 106 |
| 4.5 集中豪雨とダム 107 |
| 4.5.1 集中豪雨 107 |
| 4.5.2 洪水 108 |
| 4.5.3 ダム 109 |
| 4.6 環境問題 111 |
| 4.6.1 地球温暖化 111 |
| 4.6.2 塩害 112 |
| 4.6.3 ゴミ問題とリサイクル 113 |
| 4.6.4 電力需給 115 |
| 4.7 人事の停滞 116 |
| 4.7.1 団塊の世代 116 |
| 4.7.2 昇任 116 |
| 4.7.3 省事 117 |
| 4.8 キャッシュフロー 117 |
| 4.8.1 財布 117 |
| 4.8.2 貯蓄と借金 117 |
| 4.8.3 保険準備金 118 |
| 4.8.4 銀行の取り付け騒ぎ 119 |
| 4.8.5 貯蓄とキャッシュフロー 119 |
| 5.混雑と待ちの数理1 ランダム到着とダンゴ運転 122 |
| 5.1 電車やバスの待ち時間 122 |
| 5.1.1 等間隔運転の電車の待ち時間 122 |
| 5.1.2 急行と各駅停車のある電車の待ち時間 123 |
| 5.2 ランダムな到着 124 |
| 5.2.1 ランダム到着 124 |
| 5.2.2 指数分布の無記憶性 125 |
| 5.2.3 バス待ち時間のパラドックス 127 |
| 5.2.4 指数分布とランダムネス再考 130 |
| 5.2.5 ダンゴ運転 131 |
| 6.混雑と待ちの数理2 待ち行列モデルと利用率 134 |
| 6.1 待ち行列モデル 134 |
| 6.1.1 待ち行列 134 |
| 6.1.2 待ち行列モデル 135 |
| 6.1.3 確率分布の仮定 137 |
| 6.1.4 ケンドールの記号 138 |
| 6.1.5 待ち行列モデルにおける流入-流出グラフ 142 |
| 6.1.6 利用率 144 |
| 6.2 待ち行列の基本モデルM/M/c 146 |
| 6.2.1 系内数の分布 146 |
| 6.2.2 待ち行列モデルの基本量 148 |
| 6.2.3 単一窓口の場合 154 |
| 6.2.4 呼損系の場合 154 |
| 6.2.5 窓口数の影響 155 |
| 6.3 サービスの順番と待ち時間 158 |
| 6.3.1 並列待ち行列 159 |
| 6.3.2 最短順サービス 161 |
| 6.3.3 優先権 164 |
| 6.3.4 ポラチェック-ヒンチンの公式 169 |
| 7.混雑と待ちの数理3 待ち行列ネットワーク 172 |
| 7.1.1 ネットワークと待ち行列 172 |
| 7.1.2 ボトルネックの存在 173 |
| 7.2 ジャクソン型ネットワーク 174 |
| 7.2.1 開ネットワークと閉ネットワーク 174 |
| 7.2.2 ジャクソン型ネットワーク 175 |
| 7.2.3 開ネットワークと積形式解 176 |
| 7.2.4 閉ネットワークと積形式解 178 |
| 7.3 セントラルサーバモデル 180 |
| 7.3.1 2ディスクモデル 180 |
| 7.3.2 数値例 181 |
| 7.3.3 ボトルネックノードの利用 185 |
| 7.3.4 平均値解析法 185 |
| 8.混雑と待ちの数理4 流体モデルによる解析 187 |
| 8.1 窓口の数を増やす効果 ミニラッシュアワー 187 |
| 8.2 信号の周期 191 |
| 8.3 電車の遅れとダンゴ運転 195 |
| 8.4 エレベーターの配置と待ちの関係 197 |
| 8.5 機会損失を考慮した在庫モデル 203 |
| 8.5.1 新聞売り子の問題 203 |
| 8.5.2 定期発注方式 206 |
| 9.混雑と待ちへの対処 208 |
| 9.1 流入と流出のバランス 208 |
| 9.2 待ち行列減少の方法 212 |
| 9.3 結語 213 |
| 文献 215 |
| 索引 217 |
|
| 77.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
北野博巳, 功刀滋編著 ; 宮本真敏 [ほか] 共著
| 出版情報: |
東京 : 三共出版, 2008.3 x, 254p ; 26cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 第1章 高分子が高分子であること―序論に替えて |
| 1-1 高分子とは 1 |
| 1-2 高分子の分子量 2 |
| 1-2-1 高分子量の概念 2 |
| 1-2-2 分子量の分布 3 |
| 1-2-3 分子量の測定方法 5 |
| 1-3 高分子の分類 6 |
| 1-4 高分子をつくる結合 7 |
| 1-4-1 結合回りの回転 7 |
| 1-4-2 立体規則性 9 |
| 1-4-3 光学異性体 10 |
| 1-4-4 共重合 11 |
| 1-5 高分子の形 11 |
| 1-6 高分子化学の歩み 14 |
| 1-6-1 天然素材 14 |
| 1-6-2 合成高分子 15 |
| 参考文献 17 |
| 章末問題 18 |
| 第2章 高分子をつくる |
| 2-1 重合反応とその分類―連鎖重合と逐次重合 20 |
| 2-2 連鎖重合によるポリマーの生成 22 |
| 2-2-1 連鎖重合の素反応 22 |
| 2-2-2 重合の熱力学的要因 22 |
| 2-2-3 モノマー構造に基づく運鎖重合の分類 23 |
| 2-2-4 天井温度と平衡モノマー濃度 24 |
| 2-2-5 生長末端の性質に基づく連鎖重合の分類 24 |
| 2-3 ビニル重合 25 |
| 2-3-1 ビニル重合における置換基効果 25 |
| 2-4 ラジカル重合 32 |
| 2-4-1 開始反応 32 |
| 2-4-2 生長反応 35 |
| 2-4-3 停止反応と連鎖移動反応 36 |
| 2-4-4 ラジカル重合における速度論 39 |
| 2-4-5 重合手法 41 |
| 2-5 イオン重合 42 |
| 2-5-1 イオン重合の特徴 42 |
| 2-5-2 アニオン重合 43 |
| 2-5-3 カチオン重合 47 |
| 2-6 配位重合 49 |
| 2-6-1 Ziegler-Natta触媒 50 |
| 2-6-2 低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレン 51 |
| 2-6-3 Kaminsky-タイプ触媒 52 |
| 2-6-4 アルキン類の配竹重合 52 |
| 2-7 開環重合 52 |
| 2-7-1 環歪み 52 |
| 2-7-2 開環重合の熱力学的要因 54 |
| 2-7-3 エーテル類の開環重合 55 |
| 2-7-4 ラクトン類の開環重合 57 |
| 2-7-5 ラクタム類の開環重合 58 |
| 2-7-6 メタセシス開環重合 59 |
| 2-8 共重合 60 |
| 2-8-1 共重合組成式 60 |
| 2-8-2 モノマー反応性比 61 |
| 2-8-3 共重合組成曲線 63 |
| 2-8-4 Q,e-則 63 |
| 2-9 逐次重合 64 |
| 2-9-1 重縮合 65 |
| 2-9-2 重付加 70 |
| 2-9-3 付加縮合 71 |
| 参考文献 74 |
| 章末問題 74 |
| 第3章 高分子の化学反応 |
| 3-1 化学反応による新しい高分子の合成 77 |
| 3-1-1 セルロースの化学反応 77 |
| 3-1-2 ポリスチレンの化学反応 79 |
| 3-1-3 ポリビニルアルコールの合成と反応 81 |
| 3-1-4 ブロック共重合体とグラフト共重合体 82 |
| 3-2 高分子の架橋反応 86 |
| 3-2-1 ゴムの架橋反応 86 |
| 3-2-2 エポキシ樹脂の架橋反応 88 |
| 3-2-3 水架橋反応 88 |
| 3-3 高分子の分解反応 89 |
| 3-3-1 熱分解 89 |
| 3-3-2 熱酸化分解反応 90 |
| 3-3-3 生分解反応 91 |
| 3-4 高分子の光化学反応 92 |
| 3-4-1 光分解反応 93 |
| 3-4-2 光架橋反応 95 |
| 3-5 電子線照射による反応 96 |
| 3-6 高分子の電気化学反応 97 |
| 参考文献 98 |
| 章末問題 98 |
| 第4章 高分子の溶液 |
| 4-1 高分子鎖の大きさ 100 |
| 4-1-1 平均的な大きさの定義 101 |
| 4-1-2 高分子鎖モデルと実在鎖 102 |
| 4-2 高分子溶液の性質 109 |
| 4-2-1 溶液の熱力学 109 |
| 4-2-2 相変化と相平衡 114 |
| 4-3 平均分子量とその測定法 117 |
| 4-3-1 平均分子量と分子量分布 118 |
| 4-3-2 測定方法 119 |
| 参考文献 123 |
| 章末問題 123 |
| 第5章 高分子の固体 |
| 5-1 高分子鎖の凝集構造 126 |
| 5-2 結晶性高分子と無定型高分子 128 |
| 5-2-1 結晶性高分子とは 128 |
| 5-2-2 無定型高分子とは 128 |
| 5-3 高分子のガラス転移 130 |
| 5-3-1 ゴム状態とガラス状態 130 |
| 5-3-2 ガラス転移温度の解釈 130 |
| 5-3-3 ガラス状態の本質 131 |
| 5-3-4 ガラス転移温度を変化させるには 133 |
| 5-4 高分子の結晶 134 |
| 5-4-1 高分子の結晶構造の確認 134 |
| 5-4-2 高分子結晶のすがた 135 |
| 5-4-3 結晶化度の測定法 140 |
| 5-4-4 結晶性高分子の高次構造 143 |
| 5-4-5 伸び切り鎖の高次構造 147 |
| 5-4-6 高分子結晶の融解-融点 148 |
| 5-5 高分子の非晶 149 |
| 5-5-1 非晶鎖の結晶化 149 |
| 5-5-2 等温結晶化の機構と生成速度 151 |
| 5-5-3 延伸による結晶化と分子配向 152 |
| 5-6 高分子固体の変形 153 |
| 5-6-1 応力―ひずみ曲線 153 |
| 5-6-2 粘弾性とは 154 |
| 5-6-3 動的粘弾性 157 |
| 5-6-4 ゴム弾性 158 |
| 5-7 自由体積 159 |
| 5-7-1 自由体積の定義 159 |
| 5-7-2 自由体積理論 162 |
| 5-7-3 高分子表面のガラス転移温度と自由体積 164 |
| 参考文献 167 |
| 章末問題 168 |
| 第6章 機能性高分子 |
| 6-1 強い高分子 170 |
| 6-1-1 高強度繊維 170 |
| 6-1-2 液晶高分子 171 |
| 6-1-3 エンジニアリングプラスチック 172 |
| 6-1-4 カーボンファイバー 175 |
| 6-1-5 粘弾性力を利用する材料 175 |
| 6-2 働く高分子 176 |
| 6-2-1 衣料材料 176 |
| 6-2-2 感光性高分子 178 |
| 6-2-3 導電性高分子 179 |
| 6-2-4 電池・燃料電池 180 |
| 6-2-5 光学材料 182 |
| 6-2-6 イオン交換樹脂 183 |
| 6-2-7 高分子膜 183 |
| 6-2-8 高分子凝集剤 186 |
| 6-2-9 ゲルろ過と光学分割カラム 186 |
| 6-2-10 高吸水性材料 187 |
| 6-2-11 高分子触媒 188 |
| 6-2-12 高分子微粒子 188 |
| 6-3 かしこい高分子 189 |
| 6-3-1 力(圧力)に応答する高分子(圧電性高分子) 190 |
| 6-3-2 熱(温度変化)に応答する高分子 191 |
| 6-3-3 光に応答する高分子 194 |
| 6-3-4 電場に応答する高分子 197 |
| 参考文献 198 |
| 章末問題 199 |
| 第7章 生命と高分子 |
| 7-1 生体高分子 200 |
| 7-1-1 タンパク質 200 |
| 7-1-2 多糖類 209 |
| 7-1-3 核酸 212 |
| 7-2 生体材料高分子 218 |
| 7-2-1 生体分子の機能の利用 218 |
| 7-2-2 生体高分子をつくる 221 |
| 7-3 人工臓器 223 |
| 7-3-1 抗血栓性材料 223 |
| 7-3-2 人工腎臓 226 |
| 7-3-3 人工心臓 227 |
| 7-3-4 人工肝臓 227 |
| 7-3-5 人工膵臓 228 |
| 7-4 薬物送達システム 229 |
| 7-5 生分解性高分子 229 |
| 参考文献 232 |
| 章末問題 232 |
| 章末問題解答 233 |
| 索引 251 |
| 第1章 高分子が高分子であること―序論に替えて |
| 1-1 高分子とは 1 |
| 1-2 高分子の分子量 2 |
|
| 78.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
自動車工学編集委員会編著
| 出版情報: |
東京 : 東京電機大学出版局, 2008.3 vi, 186p ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 1.自動車一般 |
| 1.1 自動車とはなにか 1 |
| 1.2 自動車のスタイルと基本構造 2 |
| 1.2.1 スタイリング・デザイン 2 |
| 1.2.2 インテリア,デザインとパワー・プラント・レイアウト 5 |
| 2.エンジンの性能 9 |
| 2.1 ピストンエンジンの基本性能 9 |
| 2.1.1 出力特性 11 |
| 2.1.2 トルク特性 12 |
| 2.1.3 回転速度の実用範囲 13 |
| 2.1.4 シリンダ配列 15 |
| 2.1.5 重量と寸法 16 |
| 2.2 自動車用としての要求性能 16 |
| 2.2.1 吹上がり 17 |
| 2.2.2 低速の粘り17 |
| 2.2.3 高速伸び 18 |
| 2.2.4 吸排気系 19 |
| 2.2.5 燃費特性 21 |
| 2.3 エンジンのパワーアップ 24 |
| 2.3.1 ガソリン噴射 24 |
| 2.3.2 ターボ過給機 25 |
| 2.3.3 機械式過給機 29 |
| 2.3.4 可変システム 30 |
| 2.4 エンジン付属品 33 |
| 2.4.1 気化器(キャブレター) 33 |
| 2.4.2 点火システム 37 |
| 2.4.3 排出ガス処理 40 |
| 2.4.4 排気消音 45 |
| 2.5 オートバイ用エンジン 45 |
| 2.5.1 オートバイ用エンジンの特殊性 45 |
| 2.5.2 2サイクルと4サイクルの区別 47 |
| 2.5.3 冷却法とシリンダ数 48 |
| 2.6 特殊エンジン 49 |
| 2.6.1 特殊エンジンの概要 49 |
| 2.6.2 蒸気エンジン 49 |
| 2.6.3 熱空気エンジン 50 |
| 2.6.4 ガスタービン 51 |
| 2.6.5 フライホイール 52 |
| 2.6.6 電気モータ 53 |
| 2.6.7 ハイブリッドエンジン 53 |
| 2.6.8 アルコールエンジン 54 |
| 2.6.9 水素エンジン 56 |
| 2.6.10 LNGエンジン 57 |
| 3.トランスミッションの機能と特性 |
| 3.1 クラッチ 59 |
| 3.1.1 クラッチの必要性 59 |
| 3.1.2 クラッチの種類 60 |
| 3.1.3 クラッチ容量 61 |
| 3.2 トランスミッション 61 |
| 3.2.1 トランスミッションの必要性 61 |
| 3.2.2 トランスミッションの構造 62 |
| 3.3 運転操作の簡略化 64 |
| 3.3.1 自動変速機 64 |
| 3.4 変速比の決定 65 |
| 4.車体およびタイヤの力学 |
| 4.1 空気力学 69 |
| 4.1.1 自動車に作用する空気力 69 |
| 4.1.2 空気抵抗 70 |
| 4.1.3 空気力の操縦性と安定性への影響 72 |
| 4.1.4 空力特性の表示法 73 |
| 4.1.5 車体形状と空力特性 74 |
| 4.1.6 横風に対する空力特性 75 |
| 4.1.7 追越し時の空力的干渉 77 |
| 4.1.8 風洞試験 78 |
| 4.1.9 流れの可視化 80 |
| 4.2 車両重量と寸法 82 |
| 4.3 車体の安全構造 83 |
| 4.4 タイヤの力学 83 |
| 4.4.1 タイヤの動的特性 83 |
| 4.4.2 転がり抵抗 83 |
| 4.4.3 制動力と駆動力 85 |
| 4.4.4 スタンディングウェーブ 86 |
| 4.4.5 ハイドロプレーニング 87 |
| 4.4.6 コーナリングするタイヤの特性 88 |
| 5.サスペンションとステアリング |
| 5.1 サスペンション 90 |
| 5.1.1 サスペンションの働き 90 |
| 5.1.2 サスペンションの種類 90 |
| 5.1.3 ばれの種類 98 |
| 5.1.4 ショックアブソーバ 100 |
| 5.2 ステアリングシステム 101 |
| 5.2.1 ステアリングシステムのデザイン 101 |
| 5.2.2 ステアリングコラムの安全設計 101 |
| 5.2.3 ステアリングギヤの諸形式 102 |
| 5.2.4 パワーステアリングの安全設計 102 |
| 6.運動性能 |
| 6.1 動力性能 103 |
| 6.1.1 加速性能 103 |
| 6.1.2 発進加速性能の評価 103 |
| 6.1.3 追越し加速性能試験 104 |
| 6.1.4 加速性能の推定 104 |
| 6.1.5 最高速度 105 |
| 6.1.6 登坂性能 106 |
| 6.1.7 だ行試験 106 |
| 6.1.8 エンジンブレーキ 108 |
| 6.1.9 燃料消費率 108 |
| 6.2 ブレーキ性能 109 |
| 6.2.1 急制動時の問題点 109 |
| 6.2.2 ブレーキの力学 113 |
| 6.2.3 制動距離と停止距離 114 |
| 6.2.4 ブレーキシステム 115 |
| 7.操縦性と安定性 |
| 7.1 運動性能 119 |
| 7.2 タイヤの特性 119 |
| 7.2.1 タイヤと路面間の摩擦力 119 |
| 7.2.2 コーナリングフォース 120 |
| 7.2.3 コーナリングパワー 123 |
| 7.2.4 キャンバスラスト 124 |
| 7.2.5 タイヤに生ずるモーメント 125 |
| 7.2.6 駆動力,制動力とコーナリングフォース 126 |
| 7.3 定常円旋回運動 126 |
| 7.3.1 低速時の旋回運動 126 |
| 7.3.2 高速時の旋回運動 128 |
| 7.3.3 スタビリテイフアクタとスタティックマージン 130 |
| 7.3.4 ステア特性 131 |
| 7.3.5 ステア特性に及ぼす諸因子 133 |
| 7.4 過渡運動 135 |
| 7.4.1 動的方向安定性 135 |
| 7.4.2 外乱を受けた車両の運動 135 |
| 7.4.3 操舵,加速,制動時の車両の運動 136 |
| 7.5 限界性能 137 |
| 7.5.1 ドリフトアウトとスピンアウト 137 |
| 7.5.2 ジャッキアップとホイールリフト 138 |
| 7.5.3 横転 138 |
| 7.6 駆動方式別の旋回性能特性 139 |
| 7.6.1 前輪駆動車(FF車)と後輪駆動車(FR車) 139 |
| 7.6.2 タックイン現象 139 |
| 7.6.3 キックバック現象 140 |
| 7.6.4 トルクステア 141 |
| 7.6.5 コンプライアンスステア 141 |
| 7.7 4輪駆動車(4WD)の旋回特性 142 |
| 7.7.1 4WD車と2WD(FF,FR)車 142 |
| 7.7.2 4WD車の定常円旋回 142 |
| 7.7.3 Jターン特性 142 |
| 7.7.4 旋回中のパワーオンとパワーオフ 143 |
| 7.7.5 4WD車の駆動方式と運動性能 144 |
| 7.8 4輪操舵車(4WS) 145 |
| 7.8.1 2WSと4WS車 145 |
| 7.8.2 4WS機構 146 |
| 8.自動車の人間工学 |
| 8.1 人間-自動車-環境系 149 |
| 8.2 運転性能と操縦性,安定性のフィーリング 149 |
| 8.2.1 運転性能 149 |
| 8.2.2 操縦性,安定性のフィーリング 150 |
| 8.3 快適性 151 |
| 8.3.1 乗員の快適さ 151 |
| 8.3.2 乗心地 151 |
| 8.3.3 空気調和 153 |
| 8.3.4 居住性 153 |
| 9.オートバイ |
| 9.1 オートバイ 156 |
| 9.2 走行安定性 157 |
| 9.2.1 二輪車はなぜ倒れないか 157 |
| 9.2.2 オートバイの安定 159 |
| 9.3 タイヤの構造と特性 162 |
| 9.3.1 タイヤ断面形状とトレッド 162 |
| 9.3.2 キャンバスラスト 163 |
| 9.3.3 コーナリングフォースの変化 164 |
| 9.4 オートバイの動力性能 164 |
| 9.4.1 走行抵抗 164 |
| 9.4.2 馬力あたり車両重量 166 |
| 9.4.3 動力性能 166 |
| 9.5 操縦性と安定性 167 |
| 9.6 オートバイの振動と乗心地 170 |
| 9.7 走行性能のフィーリング評価 172 |
| 9.8 構造 173 |
| 9.8.1 動力を伝える 173 |
| 9.8.2 サスペンション 175 |
| 9.8.3 車体(フレーム) 177 |
| 9.8.4 大きなオートバイと小さなオートバイ 178 |
| 9.9 安全性と事故防止 180 |
| 9.9.1 安全性 180 |
| 9.9.2 事故防止対策 180 |
| 9.9.3 被害軽減対策 182 |
| 付録 |
| 索引 183 |
| 1.自動車一般 |
| 1.1 自動車とはなにか 1 |
| 1.2 自動車のスタイルと基本構造 2 |
|
| 79.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
英語論文作成研究会編
| 出版情報: |
東京 : 共立出版, 2011.10 viii, 220p ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 第1章 基礎編 Basic Course |
| 1.1 英語論文の作成要領 outline for writing scientific papers in English 2 |
| 1.1.1 論文の構成 construction of a paper 2 |
| 1.1.2和文英訳の例 examples of English translation 3 |
| 1.1.3 各章ごとの英作文の具体例 examples of English composition in each chapter 9 |
| 1.2式亜図亜ならびに表の書き方 how to write equations, figures, and tables 47 |
| 1.2.1 式を含む文章の例 examples of sentences including equations 47 |
| 1.2.2 図亜または表を含む文章の例 examples of sentences including figures and tables 59 |
| 1.2.3 式亜図亜ならびに表を含む文章の例 examples of sentences including equations, figures, and tables 69 |
| 第2章 応用編 Advance Course |
| 2.1 光利用の測定システム light measuring system 78 |
| 2.2 生体観測電子顕微鏡 bio-electron microscope 88 |
| 2.3 機械的刺激を印加する細胞培養装置 cell culture system for application of mechanical strain 98 |
| 2.4 血球の検出技術 sensing techniques for blood cells 115 |
| 2.4.1 電気的な検出法 electrical sensing method 116 |
| 2.4.2 光による検出方式 light sensing method 121 |
| 2.5 無線システムの例 examples of wireless systems 124 |
| 2.5.1 通信システム communication systems 124 |
| 2.5.2 GPS システム GPS system 128 |
| 2.6 テレビカラーマネージメントシステムの例 examples of color management systems on TVs 134 |
| 2.7 音声信号処理の例 examples of audio signal processing 146 |
| 2.7.1 音声/話者認識システム speech/speaker recognition systems 147 |
| 2.7.2 音声信号処理 audio signal processing 150 |
| 2.8 Eメールの書き方 how to write E-mails 154 |
| 第3章 実践編 Practical Course |
| 3.1 A Hybrid Sensor for the Optical Measurement of Surface Displacement 164 |
| 3.1.1 Introduction 165 |
| 3.1.2 Both methods and hybrid sensor 168 |
| 3.1.3 Experimental results by means of hybrid sensor 178 |
| 3.1.4 Conclusion 182 |
| 3.2 Noise Analysis and Noise Suppression with the Wavelet Transform for Low Contrast Urinary Sediment Images 184 |
| 3.2.1 Introduction 185 |
| 3.2.2 Noise Analysis 185 |
| 3.2.3 Algorithm for Noise Suppression 188 |
| 3.2.4 Discussion of Experimental Results 193 |
| 3.3 Charge-to-Mass Ratio Sensor for Toner Particles 197 |
| 3.3.1 Introduction 197 |
| 3.3.2Principle and Method 198 |
| 3.3.3 Experimental System 204 |
| 3.3.4 Improvement of the Toner Transportation System 206 |
| 3.4 A Pseudo-Super-Resolution Approach for TV Images 208 |
| 3.4.1 Introduction 208 |
| 3.4.2 Method and System 212 |
| 3.4.3 Experimental Results 217 |
| 3.4.4 Conclusion 219 |
| 第1章 基礎編 Basic Course |
| 1.1 英語論文の作成要領 outline for writing scientific papers in English 2 |
| 1.1.1 論文の構成 construction of a paper 2 |
|
| 80.
|
 図書
図書
|
日本規格協会編
目次情報:
続きを見る
| 一般 |
| 電線・ケーブル |
| 電線管・ダクト・附属品 |
| バッテリー |
| 参考 |
| 電気機械器具 |
| 低圧遮断器・配線器具 |
| 口金・受金・ソケット |
| 電球・ランプ |
| 安定器 |
| 照明器具 |
| 関連器具 |
| 関連機器・部材 |
概要:
一般/電線・ケーブル/電線管・ダクト・附属品/参考。<br />電気機械器具/低圧遮断器・配線器具/参考。<br />照明・関連器具(一般、口金・受金・ソケット、電球・ランプ、安定器、照明器具、関連器具)/参考。
|
| 81.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
松本哲夫, 辻谷將明, 和田武夫著
| 出版情報: |
東京 : 共立出版, 2005.10 vi, 217p ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 第1章 実験計画法の基礎 1 |
| 1.1 実験計画法とは 1 |
| 1.1.1 概要 1 |
| 1.1.2 従来の実験で犯しやすい誤り 9 |
| 1.1.3 因子の水準の選び方 10 |
| 1.1.4 実験に当たり,事前に考えておくべきこと 10 |
| 1.1.5 実験の一般的な手順 11 |
| 1.2 データの記述と確率分布 11 |
| 1.2.1 データの記述 11 |
| 1.2.2 確率変数 14 |
| 1.2.3 確率分布 17 |
| 1.3 正規母集団に関する推測 21 |
| 1.3.1 統計的推測(1標本のときの推定と検定) 22 |
| 1.3.2 2つの母分散の比の検定 32 |
| 1.3.3 2つの母平均の差の検定 35 |
| 第2章 要因(配置)実験 40 |
| 2.1 1元配置実験 40 |
| 2.1.1 データの構造と平方和の分解 41 |
| 2.1.2 分散分析 48 |
| 2.1.3 分散分析後の解析 51 |
| 2.2 2元配置実験 54 |
| 2.2.1 主効果と交互作用効果 55 |
| 2.2.2 データの構造と平方和の分解 55 |
| 2.2.3 分散分析 57 |
| 2.2.4 分散分析後の解析 62 |
| 2.2.5 繰り返しのない2元配置 67 |
| 第3章 直交表実験 69 |
| 3.1 2π型要因実験 72 |
| 3.2L4(23)直交表 77 |
| 3.2.1要因実験から直交表へ 77 |
| 3.3 2水準系直交表の性質と種類 78 |
| 3.4 2水準系直交表の割り付け 79 |
| 3.4.1 基本表示による方法 80 |
| 3.4.2 標準線点図を用いる方法 83 |
| 3.5 2水準系直交表の解析方法 85 |
| 3.6 多水準法,擬水準法 91 |
| 3.6.1 多水準法 91 |
| 3.6.2. 擬水準法の考え方 92 |
| 3.6.3 平方和の求め方 93 |
| 3.6.4 解析方法 94 |
| 3.7 その他の直交表 100 |
| 3.7.1 組み合わせ法 100 |
| 3.7.2 擬因子法 101 |
| 3.7.3 アソビ列法 103 |
| 3.7.4 直和法 104 |
| 3.7.5 3水準系直交表実験 105 |
| 第4章 ブロック因子と局所管理 113 |
| 4.1要因実験の完備型ブロック計画 113 |
| 4.1.1 ブロック因子が1つのときの完備型ブロック計画(乱塊法) 113 |
| 4.1.2 ブロック因子が2つ以上のときの完備型ブロック計画 118 |
| 4.2 要因実験の不完備型ブロック計画 120 |
| 4.2.1 ブロック因子が1つのときの不完備型ブロック計画(BIB) 120 |
| 4.2.2 直交表の不完備型ブロック計画 122 |
| 第5章 分割法 124 |
| 5.1要因実験の分割法 124 |
| 5.1.1単一分割法 124 |
| 5.1.2多段分割法 135 |
| 5.1.3 2方分割法 137 |
| 5.2 直交表による分割法 138 |
| 5.3 枝分かれ実験 144 |
| 第6章 線形推定・検定論 146 |
| 6.1 線形モデル 147 |
| 6.2 線形推定論 147 |
| 6.3 線形検定論 148 |
| 第7章 回帰分析 150 |
| 7.1 実験計画法と回帰分析 150 |
| 7.1.1 実験計画モデル(DEモデル)と回帰モデル. 150 |
| 7.1.2 回帰モデル 151 |
| 7.2 要因実験での回帰分析 151 |
| 7.2.1 1元配置と回帰分析 151 |
| 7.2.2 モデルの妥当性の評価 154 |
| 7.2.3 単回帰モデルによる推測 157 |
| 7.2.4 回帰分析の目的,分析結果の吟味 167 |
| 7.2.5 共分散分析 170 |
| 第8章計数値データの解析 172 |
| 8.1 適合度検定 172 |
| 8.2分割表の解析 174 |
| 8.2.1 カイ2乗検定(応答に順序がない場合) 174 |
| 8.2.2 応答に順序がある場合の解析 177 |
| 8.3 2項分布の近似 180 |
| 第9章 検出力と実験の大きさ 183 |
| 9.1 基本となる考え方 183 |
| 9.2 要因実験における検出力と実験回数 187 |
| 9.2.1 1元配置実験 187 |
| 9.2.2 2元配置実験 190 |
| 9.2.3 変量因子の1元配置実験 192 |
| 9.3 直交表実験における検出力 193 |
| 付表 195 |
| 付表I 正規分布表(1) U(P)から上側確率Pを求める表 196 |
| 付表II 正規分布表(2)上側確率PからU(P)を求める表 197 |
| 付表III X2分布表自由度φと上側確率PからX2(φ,P)を求める表 198 |
| 付表IV t分布表自由度φと両側確率Pからt(φ,P)を求める表 199 |
| 付表V-1 F分布表(P=0.05)自由度φ1,φ2と上側確率5%からF(φ1,φ2)を求める表 200 |
| 付表V-2 F分布表(P=0.01)自由度φ1,φ2と上側確率1%からF(φ1,φ2)を求める表 202 |
| 付表V-3 F分布表(P=0.025)自由度φ1,φ2と上側確率2.5%からF(φ1,φ2)を求める表 204 |
| 付表VI 2水準系直交表 206 |
| 付表VII 直交表の標準線点図 209 |
| 付表VIII BIB計画の例 212 |
| 付表IX ラテン方格の例 212 |
| 第1章 実験計画法の基礎 1 |
| 1.1 実験計画法とは 1 |
| 1.1.1 概要 1 |
|
| 82.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
高田和之 [ほか] 共著
| 出版情報: |
東京 : 森北出版, 2005.3 viii, 173p ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 1. 基本直流回路 |
| 1.1 電流と電圧 1 |
| 1.1.1 電流とは何か 1 |
| 1.1.2 電圧と電位差 3 |
| 1.1.3 起電力 3 |
| 1.1.4 オームの法則 3 |
| 1.2 電気抵抗 6 |
| 1.2.1 抵抗の計算 6 |
| 1.2.2 抵抗の温度変化 11 |
| 1.2.3 抵抗率 13 |
| 1.2.4 物質の形状と電気抵抗 14 |
| 1.2.5 導電率 15 |
| 1.2.6 コンダクタンス 16 |
| 1.3 倍率器と分流器 17 |
| 1.3.1 電流計と電圧計の特徴 17 |
| 1.3.2 電圧計と倍率器 17 |
| 1.3.3 電流計と分流器 19 |
| 1.3.4 分流の法則 22 |
| 1.4 ブリッジ回路 23 |
| 1.5 キルヒホッフの法則 25 |
| 1.5.1 キルヒホッフの第一法則 25 |
| 1.5.2 キルヒホッフの第二法則 26 |
| 1.5.3 キルヒホッフの法則による回路の解法 27 |
| 1.6 電気エネルギーと熱作用 31 |
| 1.6.1 電力 31 |
| 1.6.2 電力量 33 |
| 1.6.3 ジュールとは 33 |
| 1.6.4 ジュールの法則 34 |
| 演習問題 36 |
| 2. 正弦波交流の性質 |
| 2.1 交流の定義 43 |
| 2.2 正弦波交流の発生と瞬時値 44 |
| 2.3 周期,周波数,角周波数,回転数 46 |
| 2.3.1 周期,周波数,角周波数 46 |
| 2.3.2 磁極数,周波数,回転数 47 |
| 2.4 正弦波交流の表し方 49 |
| 2.4.1 瞬時値,最大値 49 |
| 2.4.2 平均値 50 |
| 2.4.3 実効値 51 |
| 2.5 波形率と波高率 54 |
| 2.6 位相角と位相差 56 |
| 2.7 正弦波交流のベクトル表示 57 |
| 2.7.1 交流のベクトル表示 58 |
| 2.7.2 ベクトルの合成(加減法) 59 |
| 2.7.3 ベクトル計算(正弦波交流の合成) 60 |
| 演習問題 65 |
| 3. 単相交流回路の基礎 |
| 3.1 基本回路とその性質 68 |
| 3.1.1 抵抗回路 68 |
| 3.1.2 自己インダクタンス回路(誘導リアクタンス) 70 |
| 3.1.3 静電容量回路(容量リアクタンス) 72 |
| 3.2 直列接続回路 75 |
| 3.2.1 R-L直列接続回路 75 |
| 3.2.2 R-C直列接続回路 78 |
| 3.2.3 R-L-C直列接続回路 80 |
| 3.2.4 合成リアクタンス 84 |
| 3.3 並列接続回路 85 |
| 3.3.1 R-L並列接続回路 85 |
| 3.3.2 R-C並列接続回路 87 |
| 3.3.3 R-L-C並列接続回路 89 |
| 3.4 交流電力 93 |
| 3.4.1 有効電力 93 |
| 3.4.2 皮相電力と力率 94 |
| 3.4.3 無効電力 94 |
| 演習問題 96 |
| 4. 記号法による交流回路の計算 |
| 4.1 複素数の性質 100 |
| 4.1.1 複素数 100 |
| 4.1.2 ベクトルの複素数表示 102 |
| 4.2 複素数によるベクトルの計算 107 |
| 4.2.1 ベクトルの和と差 107 |
| 4.2.2 ベクトルの積と商 108 |
| 4.2.3 jとベクトルの回転 112 |
| 4.3 記号法による回路計算 114 |
| 4.3.1 単独素子回路 114 |
| 4.3.2 直列接続回路 116 |
| 4.4 複素インピーダンスの接続 122 |
| 4.4.1 インピーダンスの直列接続 122 |
| 4.4.2 インピーダンスの並列接続 123 |
| 4.5 複素アドミタンス 124 |
| 4.5.1 アドミタンスによる計算 124 |
| 4.5.2 単独素子回路のアドミタンス 126 |
| 4.5.3 各種並列接続 127 |
| 4.6 交流ブリッジ回路 132 |
| 4.7 記号法による電力の計算 134 |
| 4.8 共振回路 136 |
| 4.8.1 直列共振接続 136 |
| 4.8.2 並列共振接続 143 |
| 演習問題 147 |
| 問題の解答 152 |
| 索引 202 |
| 1. 基本直流回路 |
| 1.1 電流と電圧 1 |
| 1.1.1 電流とは何か 1 |
|
| 83.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
角岡, 正弘 ; 白井, 正充(1948-)
目次情報:
続きを見る
| <第1編 高分子の架橋と分解の基礎と応用> |
| 第1章 高分子の架橋と分解 |
| 1. 架橋反応の理論(松本昭) 3 |
| 1.1 はじめに 3 |
| 1.2 ゲル化理論の展開 4 |
| 1.3 ゲル化理論のジビニル架橋重合系への応用 5 |
| 1.4 架橋樹脂の(不)均質性 7 |
| 2. 架橋反応の分類(白井正充) 10 |
| 2.1 はじめに 10 |
| 2.2 架橋体の分類 10 |
| 2.2.1 官能基を有する高分子から得られる架橋体 10 |
| 2.2.2 官能基を有する高分子と架橋剤のブレンド系から得られる架橋体 10 |
| 2.2.3 多官能性モノマーおよびオリゴマーから得られる架橋体 11 |
| 2.3 架橋反応の分類 11 |
| 2.3.1 熱架橋系 11 |
| 2.3.2 光架橋系 12 |
| (1) 光で直接架橋するタイプ 12 |
| (2) 感光剤が架橋剤として働くタイプ 12 |
| (3) 光ラジカル発生を利用するタイプ 12 |
| (4) 光酸発生を利用するタイプ 12 |
| (5) 光アミン発生を利用するタイプ 13 |
| 2.4 おわりに 13 |
| 3. 分解反応の理論(白井正充) 14 |
| 3.1 はじめに 14 |
| 3.2 分解反応の理論 14 |
| 3.2.1 ランダム分解反応 14 |
| 3.2.2 解重合型連鎖分解 15 |
| 3.2.3 架橋が併発する分解反応 16 |
| 3.3 おわりに 16 |
| 4. 分解反応の分類(白井正充) 18 |
| 4.1 はじめに 18 |
| 4.2 連鎖型分解反応 18 |
| 4.2.1 光による連鎖型分解反応 18 |
| 4.2.2 熱による連鎖型分解反応 18 |
| 4.3 非連鎖型分解反応 20 |
| 4.3.1 光による非連鎖型分解反応 20 |
| 4.3.2 熱による非連鎖型分解反応 22 |
| 4.4 おわりに 22 |
| 第2章 架橋剤と架橋反応(石倉慎一) |
| 1. はじめに 23 |
| 2. 常温または加熱による架橋反応 23 |
| 2.1 フェノール樹脂 23 |
| 2.2 エポキシ樹脂 24 |
| 2.2.1 アミンとの反応 25 |
| 2.2.2 酸触媒 25 |
| 2.2.3 カルボン酸との反応 25 |
| 2.2.4 カルボン酸無水物との反応 26 |
| 2.2.5 ジシアンジアミド(DICY)との反応 26 |
| 2.2.6 ケチミンとの反応 26 |
| 2.3 アミノ樹脂 26 |
| 2.4 イソシアナート 28 |
| 2.4.1 水との反応 28 |
| 2.4.2 水酸基含有樹脂との反応 29 |
| 2.4.3 アミン 29 |
| 2.4.4 環化三量化 29 |
| 2.4.5 ブロックイソシアナート 29 |
| 2.5 架橋剤と組み合わせる高分子化合物 30 |
| 2.5.1 不飽和ポリエステル樹脂 30 |
| 2.5.2 アルキド樹脂 31 |
| 2.5.3 シリコーン樹脂 31 |
| 2.5.4 アクリル樹脂 32 |
| (1) 水酸基官能性アクリル樹脂 33 |
| (2) カルボキシル官能性アクリル樹脂 33 |
| (3) アミド官能性共重合体 33 |
| (4) その他 33 |
| 2.5.5 ポリエステル樹脂,ウレタン樹脂 34 |
| 2.5.6 側鎖や主鎖に二重結合を持つ高分子化合物 34 |
| 3. キレート化剤 35 |
| 4. 光反応による架橋反応 35 |
| 4.1 光ラジカル重合 37 |
| 4.2 光カチオン重合 38 |
| 4.3 光架橋反応 39 |
| 第3章 架橋剤および架橋構造の解析(合屋文明) |
| 1. 架橋剤各種の分離と定性・定量 42 |
| 1.1 紫外線硬化樹脂 42 |
| 1.1.1 光重合開始剤 42 |
| 1.1.2 多官能モノマー 44 |
| 1.2 フォトレジスト用感光剤 44 |
| 1.3 化学増幅型レジスト光酸発生剤 45 |
| 1.4 エポキシ硬化剤 49 |
| 1.5 シランカップリング剤 50 |
| 2. 架橋構造の評価 51 |
| 2.1 粘弾性法による架橋点間分子量 51 |
| 2.2 FT-IRによる劣化架橋構造の評価 52 |
| 2.2.1 シリコーンゴム 52 |
| 2.2.2 フォトレジスト 52 |
| 2.2.3 ポリイミド 53 |
| 2.2.4 エポキシ樹脂 53 |
| 2.3 NMRによる架橋構造の評価 54 |
| 2.3.1 固体29Si-NMRによる評価 54 |
| 2.3.2 溶液29Si-NMR 57 |
| 2.3.3 ゲル状ポリマーの1H-NMR 58 |
| 2.4 熱分解GC/MSによる評価 58 |
| 2.4.1 プラレンズの分析 58 |
| 2.4.2 エポキシ樹脂の分析 60 |
| 2.4.3 紫外線硬化樹脂の分析 61 |
| 3. まとめ 62 |
| 第4章 架橋と分解性を利用する機能性高分子の合成(岡村晴之,白井正充) |
| 1. はじめに 63 |
| 2. 可逆的架橋・分解反応性を有する機能性高分子 63 |
| 3. 不可逆的架橋・分解反応性を有する高分子 64 |
| 3.1 熱架橋・熱分解系 64 |
| 3.2 熱架橋・光誘起熱分解系 66 |
| 3.3 熱架橋・試薬による分解系 67 |
| 3.4 光架橋・熱分解系 70 |
| 3.5 光架橋・試薬による分解系 73 |
| 4. おわりに 74 |
| <第2編 架橋および分解を利用する機能性材料開発の最近の動向> |
| 第5章 熱を利用した架橋反応 |
| 1. 高吸水性高分子ゲルの開発(伊藤耕三) 79 |
| 1.1 はじめに 79 |
| 1.2 ゲルの膨潤理論 80 |
| 1.2.1 Flory-Rhener理論 80 |
| 1.2.2 田中理論 82 |
| 1.3 環動ゲル 82 |
| 1.3.1 環動ゲルとは 82 |
| 1.3.2 環動ゲルの作成法 83 |
| 1.3.3 環動ゲルの応用 85 |
| 1.4 おわりに 86 |
| 2. 分子認識高分子ゲルの開発(浦上忠,宮田隆志) 88 |
| 2.1 はじめに 88 |
| 2.2 抗原-抗体高分子ゲル 89 |
| 2.2.1 抗原応答性高分子ゲルの調製 89 |
| 2.2.2 抗原応答性高分子ゲルの膨潤特性 90 |
| 2.3 抗原-抗体semi-IPNヒドロゲル 93 |
| 2.3.1 抗原-抗体semi-IPNヒドロゲルの調製 93 |
| 2.3.2 抗原-抗体semi-IPNヒドロゲルの可逆応答性 94 |
| 2.4 抗原応答性高分子ゲル膜の物質透過制御 97 |
| 2.5 分子インプリント高分子ゲル 98 |
| 2.5.1 分子インプリント法により生体分子をインプリントした高分子ゲルの調製 98 |
| 2.5.2 生体分子インプリント高分子ゲルの特性 99 |
| 2.5.3 内分泌攪乱物質をインプリントした高分子ゲルの調製 101 |
| 2.5.4 内分泌攪乱物質インプリント高分子ゲルの特性 102 |
| 2.6 おわりに 104 |
| 3. フェノール樹脂の最近の動向(松本明博) 107 |
| 3.1 はじめに 107 |
| 3.2 靭性の向上 107 |
| 3.2.1 ゴム成分やエラストマー成分を添加する方法 108 |
| 3.2.2 核間結合距離を長くする方法 108 |
| 3.2.3 弾性率が低い熱可塑性樹脂による変性 108 |
| 3.2.4 ナノコンポジット 109 |
| (1) ゾル-ゲル法によるコンポジット 109 |
| (2) 層間重合法(インターカレーション法)によるコンポジット 110 |
| 3.3 難燃性の向上 111 |
| 3.4 FRPへの展開 111 |
| 3.5 付加反応による硬化システム 112 |
| 3.5.1 種々の置換基の熱重合による硬化 112 |
| 3.5.2 ベンゾオキサジン環の開環重合による硬化 113 |
| 3.6 おわりに 114 |
| 4. エポキシ樹脂の高性能化の最近の動向(越智光一,原田美由紀) 116 |
| 4.1 はじめに 116 |
| 4.2 エポキシ樹脂の骨格構造と硬化物の物性 116 |
| 4.3 複合化によるエポキシ樹脂硬化物の高機能化・高性能化 121 |
| 5. エラストマーにおける架橋反応の最近の動向(池田裕子) 126 |
| 5.1 はじめに 126 |
| 5.2 加硫 126 |
| 5.3 パーオキシド架橋 128 |
| 5.4 シラノール基を利用した架橋 130 |
| 5.5 リサイクル可能な架橋反応とその脱架橋反応 131 |
| 5.6 物理的相互作用に基づく架橋 132 |
| 5.7 その他の架橋反応 135 |
| 5.8 おわりに 137 |
| 第6章 UV硬化システム |
| 1. UV硬化による相分離を利用した液晶相の形成(穴澤孝典) 139 |
| 1.1 はじめに 139 |
| 1.2 相図を用いたミクロ相分離構造の予測と制御 139 |
| 1.2.1 2元相図 140 |
| 1.2.2 3元相図 142 |
| 1.3 ミクロ相分離構造に影響するその他の因子 143 |
| 1.3.1 非平衡過程による相図からのずれ 143 |
| 1.3.2 ポリマーマトリクス相の構造 144 |
| 2. チオール-エンおよび開始剤フリーUV硬化(角岡正弘) 148 |
| 2.1 はじめに 148 |
| 2.2 チオール-エンUV硬化 150 |
| 2.2.1 チオールの構造と反応性 151 |
| 2.2.2 エンの構造と反応性 151 |
| 2.2.3 硬化時のゲル化点と体積収縮 152 |
| 2.2.4 最近の動向 153 |
| 2.3 開始剤フリーUV硬化 155 |
| 2.3.1 ドナー(ビニルエーテル類)とアクセプター(マレイミド誘導体)からの開始 156 |
| 2.3.2 励起マレイミド基の水素引き抜きによるラジカルの生成 156 |
| 2.3.3 励起マレイミド基とマレイミド基あるいはアクリロイル基からのラジカル生成 157 |
| 2.4 おわりに 158 |
| 3. 連鎖硬化型UVカチオン硬化システム(連鎖硬化システム)(林宣也) 160 |
| 3.1 はじめに 160 |
| 3.2 UVカチオン硬化 160 |
| 3.3 熱および光重合開始剤とカチオン重合性モノマー・オリゴマー 161 |
| 3.3.1 熱および光重合開始剤 161 |
| 3.3.2 カチオン重合性モノマー・オリゴマー 162 |
| 3.4 連鎖硬化型UVカチオン硬化システム 163 |
| 3.5 炭素繊維強化樹脂(CFRP)への適用 167 |
| 3.6 おわりに(今後の展望) 169 |
| 4. アニオンUV硬化システム(陶山寛志,白井正充) 171 |
| 4.1 アニオンUV硬化システムの特徴 171 |
| 4.2 光で生成するアニオンを利用したUV硬化システム 171 |
| 4.3 第一,二級アミン生成を利用したUV硬化システム 173 |
| 4.4 第三級アミン生成を利用したUV硬化システム 176 |
| 4.4.1 アンモニウム塩 176 |
| 4.4.2 ニフェジピン 177 |
| 4.4.3 α-アミノケトン 178 |
| 4.4.4 アミジン前駆体 178 |
| 4.4.5 アミンイミド 178 |
| 4.5 おわりに 178 |
| 5. 紫外線硬化型水分散ポリマー(大城戸正治) 180 |
| 5.1 はじめに 180 |
| 5.2 特徴 180 |
| 5.3 モデル構造 180 |
| 5.4 製品化タイプ 180 |
| 5.5 結果 181 |
| 5.5.1 硬度および密着性 181 |
| 5.5.2 耐溶剤性 182 |
| 5.5.3 二重結合導入量と硬化性の違いについて 183 |
| 5.5.4 熱硬化性テスト 184 |
| 5.6 結論 185 |
| 5.7 おわりに 185 |
| 第7章 光を利用する微細加工システム |
| 1. 酸・塩基の熱増殖とその化学増幅型微細加工への活用(市村國宏,青木健一) 186 |
| 1.1 はじめに 186 |
| 1.2 酸増殖型フォトポリマー 186 |
| 1.2.1 酸増殖剤 186 |
| 1.2.2 強酸分子の拡散挙動 187 |
| 1.2.3 酸増殖型フォトレジスト 191 |
| 1.2.4 酸増殖性ポリマー 193 |
| 1.3 塩基増殖型レジスト 194 |
| 1.3.1 塩基増殖反応と塩基増殖剤 194 |
| 1.3.2 エポキシポリマーのUV硬化促進 195 |
| 1.3.3 塩基増殖性オリゴマー 197 |
| 1.4 おわりに 198 |
| 2. ゾル・ゲル薄膜の微細パターニングへの応用(松川公洋) 200 |
| 2.1 はじめに 200 |
| 2.2 光2元架橋反応による有機無機ハイブリッドの作製 200 |
| 2.3 アクリル/シリカ有機無機ハイブリッドのネガ型レジストへの応用 202 |
| 2.4 有機無機ハイブリッドから電子線ポジ型アナログレジストへの展開 204 |
| 2.5 アクリル/シリカハイブリッド系電子線ポジ型アナログレジストへの特性 206 |
| 2.6 おわりに 207 |
| 3. 光架橋性高分子液晶による表面レリーフ形成とその応用(川月喜弘,小野浩司) 209 |
| 3.1 はじめに 209 |
| 3.2 光配向性高分子液晶 209 |
| 3.3 干渉露光の種類 : 強度変調と偏光状態の変調 209 |
| 3.4 分子配向パターンと表面レリーフの形成およびそれらの特性 211 |
| 3.4.1 強度変調露光 211 |
| 3.4.2 偏光状態を変調した露光 213 |
| 3.5 まとめ 214 |
| 第8章 電子線・放射線を利用した架橋反応 |
| 1. 低出力電子線の高分子機能化における利用(木下忍) 218 |
| 1.1 はじめに 218 |
| 1.2 EBの特長と物質への作用 219 |
| 1.3 高分子へのEB照射 221 |
| 1.4 応用例 223 |
| 1.4.1 電線照射 223 |
| (1) PVC(ポリ塩化ビニル)電線 223 |
| (2) PE(ポリエチレン)電線 223 |
| 1.4.2 発泡体への応用 224 |
| 1.4.3 熱収縮体への応用 224 |
| 1.4.4 天然ゴムラテックスへの応用 224 |
| 1.5 EB装置 225 |
| 1.5.1 小型低出力EB処理装置例 225 |
| (1) 実験用小型EB処理装置 225 |
| (2) EZCureTM装置 225 |
| (3) 円筒型EB処理装置 225 |
| 1.6 おわりに 228 |
| 2. 放射線を利用するポリテトラフルオロエチレンの機能化(鷲尾方一) 229 |
| 2.1 はじめに 229 |
| 2.2 架橋PTFE 229 |
| 2.3 放射光を用いたPTFEの機能化 231 |
| 2.3.1 放射光による架橋PTFEの微細加工 231 |
| 2.3.2 放射光によるVirginPTFEの架橋 234 |
| 2.4 架橋PTFEを基材としたイオン交換膜創製 234 |
| 3. 放射線を利用する架橋高分子の形状制御(関修平) 238 |
| 3.1 放射線による高分子の架橋・分解反応 238 |
| 3.2 放射線による架橋・分解反応の定量的評価法 238 |
| 3.3 放射線と物質との相互作用について 240 |
| 3.3.1 荷電粒子によるエネルギー付与の基礎過程 240 |
| 3.3.2 空間的に不均一なエネルギー付与についての理論的考察 241 |
| 3.4 不均一な化学反応の積極的な利用 242 |
| 3.4.1 高いLETを有するビームによる穿孔形成 242 |
| 3.4.2 高いLETを有するビームによる架橋高分子ナノ組織体の直接形成 242 |
| 第9章 リサイクルおよび機能性材料合成のための分解反応 |
| 1. プラスチックのケミカルリサイクル(佐藤芳樹) 249 |
| 1.1 はじめに 249 |
| 1.2 プラスチックの構造,合成法とリサイクル方法の関係 250 |
| 1.3 油化技術の現状 251 |
| 1.4 モノマーリサイクル技術 252 |
| 1.5 電気・電子製品のリサイクル 256 |
| 2. 架橋ポリエチレンのリサイクル : 超臨界アルコールの利用(後藤敏晴) 259 |
| 2.1 はじめに 259 |
| 2.2 架橋ポリエチレン 259 |
| 2.3 超臨界流体 260 |
| 2.4 超臨界流体によるXLPEの熱可塑化 261 |
| 2.4.1 XLPEへの超臨界流体の溶解 261 |
| 2.4.2 超臨界処理したXLPEの評価 261 |
| 2.4.3 超臨界アルコール処理したXLPEの構造 262 |
| 2.5 超臨界処理したXLPEの物性 266 |
| 2.6 おわりに 266 |
| 3. ポリプロピレンのリサイクル : 機能性化合物の合成(澤口孝志) 269 |
| 3.1 はじめに 269 |
| 3.2 テレケリックオリゴプロピレンの生成機構 270 |
| 3.3 キャラクタリゼーション 273 |
| 3.4 ブロック共重合 274 |
| 3.5 おわりに 277 |
| 4. 天然素材リグニンを利用する機能性材料の開発(舩岡正光,永松ゆきこ) 280 |
| 4.1 はじめに 280 |
| 4.2 リグニン高分子の形成と構造的特徴 280 |
| 4.3 天然リグニンを循環型機能性高分子へ 281 |
| 4.3.1 1次変換設計 281 |
| 4.3.2 選択的構造制御システム(相分離系変換システム) 282 |
| 4.3.3 分子内機能変換素子とその効果 283 |
| 4.3.4 高次構造制御 284 |
| 4.4 リグニンの逐次循環活用 287 |
| 4.4.1 セルロース複合系 287 |
| 4.4.2 無機質複合系 288 |
| 4.4.3 タンパク質複合系 288 |
| 4.4.4 ポリエステル複合系 288 |
| 4.5 おわりに 289 |
| 5. エンプラのフォトレジストへの応用(友井正男) 291 |
| 5.1 はじめに 291 |
| 5.2 反応現像画像形成法 : エンプラと求核試薬の反応 292 |
| 5.3 反応現像画像形成(RDP)法を基盤とする感光性エンプラの開発 293 |
| 5.4 微細パターン形成のメカニズム 294 |
| 5.5 エンプラおよび求核剤の構造と感光特性の関連 296 |
| 5.6 おわりに 298 |
| <第1編 高分子の架橋と分解の基礎と応用> |
| 第1章 高分子の架橋と分解 |
| 1. 架橋反応の理論(松本昭) 3 |
|
| 84.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
小泉光惠 [ほか] 編
| 出版情報: |
東京 : シーエムシー出版, 2007.7 ix, 321p ; 21cm |
| シリーズ名: |
CMCテクニカルライブラリー ; 264 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 刊行にあたって 小泉光恵 |
| 序章 佐々木正 |
| 1 はじめに 1 |
| 2 ナノテクノロジーとは何か 2 |
| 3 ナノマテリアルの製造法について 2 |
| 4 ナノマテリアルの限りない応用 4 |
| 5 今後の問題 4 |
| 第1編 ナノ粒子編 |
| 第1章 ナノ粒子の製造・物性・機能 |
| 1 ナノ粒子の特徴と研究開発状況 目 義雄 9 |
| 1.1 はじめに 9 |
| 1.2 ナノ粒子の特徴 10 |
| 1.3 ナノ粒子の研究状況と課題 11 |
| 2 ナノ粒子の製造 北修純一 13 |
| 2.1 はじめに 13 |
| 2.2 気相からの微粒子生成 14 |
| 2.3 液相からの微粒子生成 15 |
| 2.4 粒子のナノ複合化 17 |
| 2.5 おわりに 18 |
| 3 トピックス 20 |
| 3.1 ナノ粒子の粒径制御 奥山喜久夫 20 |
| 3.1.1 はじめに 20 |
| 3.1.2 気相反応法によるナノ粒子の製造 20 |
| 3.1.3 液相反応法によるナノ粒子の生成 22 |
| 3.1.4 噴霧法によるナノ粒子の製造 24 |
| 3.2 逆ミセル反応場を利用する単分散性ナノ粒子の合成 今野紀二郎 26 |
| 3.2.1 はじめに 26 |
| 3.2.2 水反応場のサイズと状態 26 |
| 3.2.3 粒子の生成プロセス 28 |
| 3.2.4 粒子特性の制御 28 |
| 3.3 超音波法によるナノ粒子の合成 前田泰昭,水越克彰 32 |
| 3.3.1 はじめに 32 |
| 3.3.2 金属カルボニルを出発物質とする金属アモルファス粒子の調製 32 |
| 3.3.3 超音波還元法による金属ナノ材料の調製 33 |
| 3.3.4 その他 33 |
| 3.3.5 おわりに 33 |
| 第2章 ナノ粒子の応用展開 |
| 1 分散,コーティングのためのナノ粒子 35 |
| 1.1 光バリア 増井敏行,足立吟也 35 |
| 1.1.1 はじめに 35 |
| 1.1.2 可視光バリア 35 |
| 1.1.3 紫外光バリ. 36 |
| 1.2 インクジェット材料 田中正夫 41 |
| 1.2.1 はじめに 41 |
| 1.2.2 顔料インクの課題と微粒子顔料の必要性 41 |
| 1.2.3 有機顔料の微粒子化 41 |
| 1.2.4 微粒子顔料の課題 43 |
| 1.2.5 顔料表面修飾技術としてのマイクロカプセル化 44 |
| 1.2.6 おわりに 45 |
| 1.3 ナノ粒子ペースト 小田正明 46 |
| 1.3.1 はじめに 46 |
| 1.3.2 ナノ粒子による膜の性質, 46 |
| 1.3.3 ナノ粒子膜の応用 47 |
| 1.4 研磨用スラリー 土肥俊郎 51 |
| 1.4.1 はじめに-スラリーの進歩- 51 |
| 1.4.2 研磨のメカニズム 52 |
| 1.4.3 CMPスラリーの分類と製法 52 |
| 1.4.4 研磨用スラリーの留意点 56 |
| 1.4.5 おわりに 57 |
| 1.5 情報・記録材料 川又肇 58 |
| 1.5.1 磁気記録の進歩 58 |
| 1.5.2 磁気記録媒体の高性能化 58 |
| 1.5.3 塗布型磁気記録媒体の構成と製造法 60 |
| 1.5.4 磁性粉の種類 60 |
| 1.5.5 超微粒子磁性粉の課題と求められる特性 63 |
| 1.5.6 高密度記録媒体の動向 64 |
| 1.6 光触媒特性 藤嶋 昭 66 |
| 1.6.1 酸化チタン光触媒が活躍する 66 |
| 1.6.2 光触媒には2つの特性がある 66 |
| 1.6.3 酸化チタン光触媒層の材料表面への固定 67 |
| 1.6.4 酸化チタンの一次原料をつくるには 69 |
| 1.6.5 光触媒の表面形状を工夫する 71 |
| 1.6.6 光触媒の機能を一段と発揮させるためのハイブリッドなどの工夫 72 |
| 1.6.7 新しい光触媒の作り方 74 |
| 1.6.8 光触媒のこれから 75 |
| 2 高比表面積材料 76 |
| 2.1 触媒 春田正毅 76 |
| 2.1.1 はじめに 76 |
| 2.1.2 金属ナノ粒子触媒の調製法 76 |
| 2.1.3 粒子径の効果 76 |
| 2.1.4 担体の効果 77 |
| 2.1.5 接合構造の効果 78 |
| 2.1.6 おわりに 78 |
| 2.2 吸脱着材料(自律型調湿材料の開発経緯と現状) 芝崎靖雄 80 |
| 2.2.1 はじめに 80 |
| 2.2.2 セラミック建材の1970年代の問題点 81 |
| 2.2.3 アロフェンの同定作業 81 |
| 2.2.4 自律型調湿壁の開発と提案 83 |
| 2.2.5 調湿材料の開発指針の設定と現状 84 |
| 2.3 ガスセンサ 三浦則雄,酒井剛 87 |
| 2.4 天然ガス貯蔵材料 関建司 91 |
| 2.4.1 はじめに 91 |
| 2.4.2 メタン吸着材としての必要条件 91 |
| 2.4.3 新規メタン吸着材である金属錯体 92 |
| 2.4.4 おわりに 94 |
| 2.5 リチウムイオン電池用負極材 徳満勝久 96 |
| 2.5.1 はじめに 96 |
| 2.5.2 炭素の構造 96 |
| 2.5.3 リチウムイオン電池用炭素材料 96 |
| 3 量子効果の利用 100 |
| 3.1 金ナノドット(単電子素子) 藤田大介 100 |
| 3.1.1 はじめに 100 |
| 3.1.2 極微SETの原理 100 |
| 3.1.3 ナノ構造創製評価プロセス 101 |
| 3.1.4 おわりに 106 |
| 3.2 レジスト材料 田島右副,武内一夫 108 |
| 3.2.1 はじめに 108 |
| 3.2.2 フラーレンを使ったレジスト材料 108 |
| 3.2.3 おわりに 112 |
| 第2編 ナノコンポジッ卜編 |
| 第1章 ナノコンポジット材料の構造・機能 |
| 1 ポリマー系ナノコンポジット 中條澄 115 |
| 1.1 ポリマー系ナノコンポジットの構造 115 |
| 1.2 ポリマー系ナノコンポジットの機能 117 |
| 2 半導体系ナノコンポジット 八百隆文 119 |
| 2.1 はじめに 119 |
| 2.2 自己組織化による量子ドットの形成 119 |
| 2.3 量子ドットによる新光物性 121 |
| 2.4 量子ドットレーザヘの応用 122 |
| 2.5 将来展望 123 |
| 3 セラミックス系ナノコンポジット 新原晧一 124 |
| 3.1 はじめに 124 |
| 3.2 ナノ複合化コンセプト 124 |
| 4 金属系ナノコンポジット 井上明久 128 |
| 第2章 ポリマー系ナンコンポジット材料の技術 |
| 1 ポリマー系ナノコンポジット材料の製造法・物性・応用・企業化状況 中篠澄 133 |
| 1.1 製造法 133 |
| 1.1.1 基本的原理 133 |
| 1.1.2 製造法の種類 133 |
| 1.1.3 層間挿入法の具体的方法 134 |
| 1.1.4 層間挿入法の改良 136 |
| 1.2 物性 137 |
| 1.3 応用 138 |
| 1.4 企業化状況 139 |
| 2 ポリマー系ナンコンポジット材料の物性・機能の向上 143 |
| 2.1 力学的機能の向上 加藤誠,臼杵有光 143 |
| 2.2 熱的機能の向上 安江健治 149 |
| 2.3 何年生機能の向上 武田邦彦 152 |
| 2.3.1 はじめに 152 |
| 2.3.2 ナノコンポジット系難燃材料の調整 152 |
| 2.3.3 ナンコンポジット系難燃材料の特徴 153 |
| 2.3.4 応用 155 |
| (補足)凝集擬分相法とそのナノコンポジットヘの応用 155 |
| 2.4 ガスバリアー性の向上 出口隆一 160 |
| 2.4.1 はじめに 160 |
| 2.4.2 粘土鉱物と有機材料のナノ複合化 160 |
| 2.4.3 ガスバリアー材料としての用途展開 160 |
| 2.4.4 おわりに 163 |
| 2.5 コーティング膜機能の向上 字加地孝志 164 |
| 2.5.1 はじめに 164 |
| 2.5.2 ナノコンポジット化の試み 164 |
| 2.5.3 UV硬化型有機/無機ハイブリッドハードコート材の主な特徴 165 |
| 2.6 その他の機能の向上 長谷川直樹,臼杵有光 170 |
| 2.6.1 はじめに 170 |
| 2.6.2 液晶クレイナノコンポジット 170 |
| 2.6.3 クレイによるポリマーのモルフォロジー制御 176 |
| 2.6.4 おわりに 177 |
| 第3章 半導体系ナノコンポジット材料の技術 |
| 1 半導体系ナノコンポジット材料の製造法・物性・応用 八百隆文 179 |
| 1.1 はじめに 179 |
| 1.2 量子構造の形成 179 |
| 1.2.1 量子井戸構造の形成法 179 |
| 1.2.2 量子細線構造の形成法 181 |
| 1.2.3 量子ドット形成法 184 |
| 1.3 量子ドットの物性とデバイス応用 188 |
| 1.4 おわりに 189 |
| 2 ナノコンポジットによる新機能付与 191 |
| 2.1 スピンエレクトロニクス(半導体と磁性体の複合薄膜,希薄磁性半導体) 岡泰夫 191 |
| 2.1.1 エレクトロニクスと電子スピン 191 |
| 2.1.2 スピントランジスター 191 |
| 2.1.3 スピン注入・輸送 192 |
| 2.1.4 半導体におけるスピン操作 193 |
| 2.1.5 希薄磁性半導体ナノ構造の作製 194 |
| 2.1.6 おわりに 196 |
| 2.2 短波長発光特性 長濱慎一 197 |
| 2.2.1 はじめに 197 |
| 2.2.2 MOCVDによるGaN系材料のエピタキシー 198 |
| 2.2.3 InGaN-LED 199 |
| 2.2.4 InGaN-LD 200 |
| 2.2.5 今後の展望 201 |
| 第4章 セラミックス系ナノコンポジット材料の技術 |
| 1 セラミックス系ナノコンポジット材料の製造法・物性・応用・企業化状況 新原晧一 203 |
| 1.1 セラミックス系ナノコンポジットの開発動向 203 |
| 1.2 ナノから分子レベルの材料設計へ 206 |
| 1.3 セラミックス系ナノコンポジット材料の将来展望 207 |
| 2 ナノコンポジットによる機能改善 209 |
| 2.1 力学的機能 関野徹 209 |
| 2.2 熱電変換機能 後藤孝 22 |
| 2.3 磁気的機能 山本孝夫 215 |
| 2.4 光学的機能 田中勝久 218 |
| 2.4.1 光機能材料としてのナノコンポジットの優位性 218 |
| 2.4.2 蛍光材料 218 |
| 2.4.3 非線形光学材料 219 |
| 2.4.4 その他の光機能ナノコンボジット 220 |
| 2.5 生体機能 春日敏宏 221 |
| 2.5.1 はじめに 221 |
| 2.5.2 セラミック系生体活性複合材料の設計 221 |
| 25.3 生体活性セラミックスの機械的性質の改善策 222 |
| 3 ナノコンポジットによる新機能付与 224 |
| 3.1 ナノ/ナノ複合化による新機能 若井史博 224 |
| 3.1.1 はじめに 224 |
| 3.1.2 ナノ/ナノ複合材料の組織安定性 224 |
| 3.1.3 微細結晶粒超塑性 224 |
| 3.2 IGC技術による新機能 中山忠親 226 |
| 3.2.1 はじめに 226 |
| 3.2.2 IGC技術によるナノ微粒子の作製法 226 |
| 3.2.3 IGC技術による新規な物理的化学的特性の付与 227 |
| 3.3 インターカレーション技術による新機能 山中昭司 228 |
| 3.3.1 はじめに 228 |
| 3.3.2 層間無限膨潤 228 |
| 3.3.3 層間架橋ミクロポア多孔体 228 |
| 3.3.4 二次電池電極材料 229 |
| 3.3.5 超伝導材料 229 |
| 3.4 テンプレート技術による新機能 古川博康,黒田一幸 231 |
| 3.4.1 テンプレートと多孔体 231 |
| 3.4.2 メソ構造体の種類 231 |
| 3.4.3 形態制御 232 |
| 3.4.4 機能 233 |
| 3.5 ゾルーゲル技術による新機能 松田厚範,忠永清治,南努 234 |
| 3.5.1 はじめに 234 |
| 3.5.2 アルミナ系ナノ微結晶複合体薄膜の超親水性および超撥水性 234 |
| 3.5.3 チタニア系ナノ微結晶複合体薄膜の低温合成と光触媒作用 235 |
| 第5章 金属系ナノコンボジッ卜材料の技術 |
| 1 金属系ナノコンポジット材料の製造法・物性・応用・企業化状況 井上明久 236 |
| 1.1 高比強度A1基合金 236 |
| 1.2 軟磁性Fe基合金 237 |
| 1.3 硬磁性Fe基合金 239 |
| 1.4 高強度・高弾性限・低ヤング率Zr基合金 240 |
| 2 ナノコンポジットによる機能改善 241 |
| 2.1 力学的機能 井上明久 241 |
| 2.2 磁気的機能 杉本論 244 |
| 2.2.1 はじめに 244 |
| 2.2.2 金属-非金属ナノグラニュラーソフト磁性材料 244 |
| 2.2.3 ナノコンポジット磁石(交換スプリング磁石) 245 |
| 2.3 熱電的機能 杉原淳 248 |
| 3 ナノコンポジットによる新機能付与 250 |
| 3.1 MA技術による新機能 木村博 250 |
| 3.1.1 MAナノ技術 250 |
| 3.1.2 バルクナノ結晶の超機能 251 |
| 3.2 くり返し圧延ナノ材料の新機能 新宮秀夫 253 |
| 3.3 アモルファス合金結晶化による新機能 河村能人 255 |
| 3.4 ポーラス金属の製法と新機能 中嶋英雄 257 |
| 3.4.1 はじめに 257 |
| 3.4.2 ポーラス金属の作製方法 257 |
| 3.4.3 ロータス金属の機械的性質 259 |
| 3.4.4 ポーラス金属の機能的性質 259 |
| 3.5 燃焼合成による新機能 東健司,馬渕守 261 |
| 3.5.1 燃焼合成法の概要 261 |
| 3.5.2 今後の研究展開 262 |
| 3.6 放電プラズマ焼結(SPS)法による新機能 鴇田正雄 263 |
| 3.6.1 はじめに 263 |
| 3.6.2 SPS法の加工原理と特徴 263 |
| 3.6.3 SPS法によるナノアルミナ粉末の固化成形実験 265 |
| 3.6.4 SPS法による新機能 266 |
| 3.6.5 おわりに 268 |
| 第3編 ナノマテリアルの新しい応用 |
| 第1章 カーボンナノチューブ 齋藤弥八 |
| 1 はじめに 273 |
| 2 ナノチューブ電子デバイス 274 |
| 3 走査プローブ顕微鏡用探針 274 |
| 4 カーボンナノチューブ電界放出電子源 275 |
| 5 水素貯蔵 276 |
| 第2章 新しい有機-無機センサー材料 新原晧一 |
| 1 有機-無機センサーの基本構想 278 |
| 2 導電原理および試料の調製 278 |
| 2.1 導電原理 278 |
| 2.2 試料の作製 279 |
| 2.3 電気的特性 279 |
| 2.4 機械的特性 280 |
| 3 課題と展望 280 |
| 第3章 次世代太陽光発電材料 柳田祥三,北村隆之 |
| 1 色素増感太陽電池 282 |
| 1.1 色素増感太陽電池の発電原理 282 |
| 2 ナノマテリアルとしての多孔質nano-TiO薄膜の作製と構造制御 283 |
| 2.1 nano-TiO多孔質膜電極の作製法 283 |
| 2.2 nano-TiOの結晶構造と電極特性 283 |
| 2.3 多孔質電極構造の制御 284 |
| 2.4 nano-TiO多孔質電極の電子輸送特性 285 |
| 3 今後の展開 285 |
| 第4章 磁性グラニュラー構造薄膜 高梨弘毅 |
| 1 はじめに 287 |
| 2 巨大磁気抵抗効果 287 |
| 3 硬磁性 289 |
| 4 軟磁性 290 |
| 第5章 スピンエレクトロニクス 猪俣浩一郎 |
| 1 スピンエレクトロニクスとは 292 |
| 2 スピンエレクトロニクスを支える物理現象 293 |
| 3 新しい不揮発性メモリMRAM 295 |
| 4 夢を拓くスピンエレクトロニクス 295 |
| 第6章 バイオマグネット 松永是,新垣篤史 |
| 1 はじめに 297 |
| 2 バクテリアの作るナノサイズ磁性粒子 298 |
| 3 磁性細菌粒子生成機構の解析 298 |
| 4 遺伝子組み換え機能性磁性細菌粒子の作製 299 |
| 5 磁性細菌粒子を利用した自動測定装置 301 |
| 6 磁気ビーズマイクロアレイ 301 |
| 7 おわりに 302 |
| 第7章 デンドマリー 横山士吉 303 |
| 第8章 フォトニクス材料 平尾一之 |
| 1 フオトニクス材料としてのナノマテリアル 308 |
| 2 ナノガラスとは 309 |
| 2.1 原子・分子レベルでの構造制御技術(1nm以下) 309 |
| 2.2 1~数10nmレベルでの超微粒子構造制御技術 310 |
| 2.3 数10nmレベル以上での高次構造制御技術 311 |
| 2.4 三次元光回路材料技術 311 |
| 第9章 リモートセンシング 淡野正信 |
| 1 構造-機能融合セラミックスへの期待 313 |
| 2 磁性ナノコンポジットによるリモートセンシング 313 |
| 3 合成プロセスと構造-機能特性 314 |
| 4 応力のリモートセンシング機能 315 |
| 5 磁性ナノコンポジットの将来応用 316 |
| 第10章 バイオミネラリゼーション 田中順三,佐藤公泰 |
| 1 はじめに 317 |
| 2 バイオミネラリゼーションの特徴 317 |
| 3 バイオミメティクスによる人工骨合成 318 |
| 4 自己組織化のメカニズム 320 |
| 刊行にあたって 小泉光恵 |
| 序章 佐々木正 |
| 1 はじめに 1 |
|
| 85.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
藤田英一, 杉山昌章著
| 出版情報: |
東京 : アグネ技術センター, 2009.12 vi, 264p ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 前書き |
| 博物館入口ホール 陶磁の起源 1 |
| A1 言葉の起源 1 |
| A2 焼き物の起源 3 |
| A3 焼き物の発展 8 |
| 第1章 粘土の生い立ち 13 |
| 1.1 岩石の種類と粘土鉱物 13 |
| 1.2 岩石・粘土の多様性 15 |
| 1.2.1 地殻を構成する多種類の酸化物 15 |
| 1.2.2 種々の原子配列と熱力学 16 |
| 1.2.3 相図(状態図)と相の自由エネルギー 18 |
| 1.3 代表的な酸化物の状態図 21 |
| 1.3.1 SiO2-Al2O3-MgO擬三元系相図 21 |
| 1.3.2 工業材料との接点 23 |
| 1.4 粘土の種類と産出地 25 |
| 1.4.1 粘土の種類 26 |
| 1.4.2 日本の六古窯その他の産地 27 |
| 第2章 陶磁器の製作と工夫 33 |
| 2.1 作陶の手順と準備 33 |
| 2.1.1 精製と土練り 33 |
| 2.1.2 粘土細工に必要な道具 36 |
| 2.2 陶磁器製作の実際-本焼きの手前まで- 37 |
| 2.2.1 成形法の色々 37 |
| 2.2.2 装飾法の色々 41 |
| 2.2.3 素焼きの効用と方法 43 |
| 2.2.4 絵付け 44 |
| 2.2.5 釉薬掛け 46 |
| 2.3 陶磁器製作の実際-本焼きへ- 48 |
| 2.3.1 本焼き 48 |
| 2.3.2 焼成に関する二三の追加 54 |
| 第3章 釉の多様性 59 |
| 3.1 焼成と釉薬の原理 59 |
| 3.1.1 焼結の機構 59 |
| 3.1.2 釉薬とガラス 66 |
| 3.2 釉薬の種類と日本の伝統 70 |
| 3.2.1 釉薬の種類あれこれ 70 |
| 第4章 釉と陶器の強度と破壊 81 |
| 4.1 胎土と釉薬の物理的・機械的性質 81 |
| 4.1.1 融液中の結晶核生成 81 |
| 4.1.2 貫入(ひび割れ) 85 |
| 4.2 セラミックスの脆性破壊と物理特性 90 |
| 4.2.1 脆性破壊の理論と実験 90 |
| 4.2.2 陶磁器の硬さ 94 |
| 4.2.3 熱伝導 98 |
| 第5章 東洋と西欧の陶磁 101 |
| 5.1 東洋の陶磁の歴史と技術 101 |
| 5.1.1 日本における初期の変遷 101 |
| 5.1.2 大陸伝来と日本陶磁の推移 103 |
| 5.1.3 茶陶 107 |
| 5.2 中国・朝鮮の陶磁の歴史と技術 110 |
| 5.2.1 中国における初期の変遷 110 |
| 5.2.2 中国の主な窯場と産出陶磁 112 |
| 5.2.3 朝鮮における陶磁の発展と日本 117 |
| 5.3 西洋陶磁の発展 120 |
| 5.3.1 先史の洞窟画と色 120 |
| 5.3.2 彩色染色の伝統と色の安定 122 |
| 5.3.3 陶磁の色 123 |
| 5.3.4 西洋陶磁の始まり 124 |
| 5.3.5 陶磁は東方より 129 |
| 5.3.6 近世ヨーロッパにおける陶器生産 130 |
| 5.3.7 ヨーロッパ磁器の誕生 134 |
| 第6章 近代社会の発展とセラミックス 141 |
| 6.1 産業革命と大衆性・芸術性 141 |
| 6.2 近代生活の中の陶器 142 |
| 6.2.1 屋根瓦と煉瓦と建築タイル 142 |
| 6.2.2 水廻りと衛生陶器 145 |
| 6.2.3 絶縁碍子その他 146 |
| 6.3 大砲製造と耐火煉瓦 148 |
| 6.3.1 反射炉と耐火煉瓦 148 |
| 6.3.2 近代製鉄に繋がる反射炉 150 |
| 第7章 新セラミックスの登場と工業化 153 |
| 7.1 新セラミックスの案内板 153 |
| 7.1.1 新セラミックスの特徴 153 |
| 7.1.2 工業用ファイン・セラミックス 154 |
| 7.2 代表的な原料の産地 155 |
| 7.3 ファイン・セラミックスの製造原理 157 |
| 7.3.1 種々の成形法と関連作業 157 |
| 7.3.2 常圧焼結法 163 |
| 7.3.3 真空焼結法 164 |
| 7.3.4 反応焼結法 166 |
| 7.3.5 加圧焼結法-ホットプレス 168 |
| 7.3.6 加圧焼結法-HIP 168 |
| 第8章 構造用セラミックスの発展 171 |
| 8.1 夢の高温材料 171 |
| 8.1.1 非酸化物系セラミックスの登場 171 |
| 8.1.2 高温材料開発への夢 172 |
| 8.1.3 高温部材の新しい仲間 176 |
| 8.1.4 構造用セラミックスの新たな応用 178 |
| 8.2 強靭なセラミックス 181 |
| 8.2.1 キュービックジルコニア 181 |
| 8.2.2 セラミックスの脆さの克服 182 |
| 8.2.3 相変態を利用した強靭化 187 |
| 8.2.4 身近なジルコニア・セラミックスの応用例 191 |
| 8.2.5 構造用セラミックスの現状 193 |
| 第9章 誘電体,導電性セラミックスの登場 195 |
| 9.1 電気石の謎から誘電性セラミックスへ 195 |
| 9.1.1 機能性セラミックスの案内板 195 |
| 9.1.2 帯電から始まる電気と力学の結合 196 |
| 9.1.3 強誘電体セラミックスの登場 199 |
| 9.1.4 誘電分極の振る舞い 202 |
| 9.2 身の回りの誘電体材料 207 |
| 9.2.1 コンデンサ(エネルギー蓄電器)材料 207 |
| 9.2.2 誘電体共振器 210 |
| 9.2.3 圧電素子(エネルギー変換器) 214 |
| 9.3 電気を伝えるセラミックス 220 |
| 9.3.1 チタニアの導電性の発見 220 |
| 9.3.2 導電性の起源と各種導電機構 222 |
| 9.3.3 導電性セラミックスの身近な応用 224 |
| 9.4 イオン導電性と酸素センサ 228 |
| 9.4.1 固体電解質としてのジルコニア 228 |
| 9.4.2 酸素センサとしての応用 231 |
| 第10章 磁性セラミックスと高温超伝導 235 |
| 10.1 磁石と羅針盤 235 |
| 10.1.1 磁石の始まり 236 |
| 10.1.2 電子の発見と磁性 236 |
| 10.2 磁性セラミックスを代表するフェライト 237 |
| 10.2.1 硬磁性と軟磁性 238 |
| 10.2.2 スピネル系フェライトの構造と磁性 241 |
| 10.2.3 強磁性体の磁区構造 244 |
| 10.3 磁性セラミックスの焼結と加工 247 |
| 10.3.1 フェライト磁石の製造方法 247 |
| 10.3.2 ソフトフェライトの焼結 247 |
| 10.4 磁性と超伝導のかけ橋 248 |
| 博物館の出口にて 255 |
| 索 引 256 |
| 後書き 263 |
| 前書き |
| 博物館入口ホール 陶磁の起源 1 |
| A1 言葉の起源 1 |
|
| 86.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
大沼俊朗著
| 出版情報: |
東京 : 朝倉書店, 1992.6 vii, 115p ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 1. 電気磁気学の基礎 1 |
| 1.1 電荷と電流 1 |
| 1.2 マクスウェルの式 2 |
| 1.2.1 マクスウェルの式 2 |
| 1.2.2 有限境界の条件 3 |
| 1.3 電磁工学の素材 3 |
| 1.3.1 導体・半導体・絶縁体 3 |
| 1.3.2 誘電体,磁性体 3 |
| 1.3.3 荷電粒子(プラズマ) 4 |
| 1.3.4 超伝導体 4 |
| 1.4 電磁工学の周波数 5 |
| 1.5 電磁工学のオーダー 7 |
| 2. 電気現象の基礎 9 |
| 2.1 クーロンの法則 9 |
| 2.1.1 クーロンの法則 9 |
| 2.1.2 電界強度と電束密度 9 |
| 2.2 ガウスの法則 10 |
| 2.2.1 ガウスの法則 10 |
| 2.2.2 ガウスの法則のベクトル表示 11 |
| 2.3 ポテンシャル(電位) 11 |
| 2.3.1 ポテンシャルと仕事 11 |
| 2.3.2 平行2線のポテンシャル分布 12 |
| 2.3.3 等ポテンシャル面 13 |
| 2.3.4 表面電荷による電界 14 |
| 2.3.5 電気影像(イメージ電荷) 14 |
| 2.4 ポアソンの式とラプラスの式 15 |
| 2.4.1 ポアソンの式とラプラスの式 15 |
| 2.4.2 平行平板内のポテンシャル・電界 16 |
| 2.5 キャパシタンス(容量) 18 |
| 2.5.1 電気容量 18 |
| 2.5.2 平行平板キャパシター 18 |
| 2.6 静電エネルギー 19 |
| 2.7 電気ダイポール(双極子) 20 |
| 2.7.1 ダイポール空間の電位と電界 20 |
| 2.7.2 ダイポールからの電磁波放射 21 |
| 3. 磁気現象の基礎 22 |
| 3.1 磁気誘導とファラデーの法則 22 |
| 3.2 磁束密度・磁界強度 23 |
| 3.2.1 磁束密度B 23 |
| 3.2.2 磁界強度H 24 |
| 3.3 アンペアの法則 25 |
| 3.3.1 アソペアの法則 25 |
| 3.3.2 電流要素に対するアンペアの法則 26 |
| 3.4 アンペアの作用の法則 26 |
| 3.4.1 アンペアの作用の法則 26 |
| 3.4.2 直線電流による磁界 27 |
| 3.5 磁気エネルギー 28 |
| 3.6 ベクターポテンシャル 29 |
| 3.6.1 ベクターポテンシャルの定義 29 |
| 3.6.2 長い直線電流近傍の磁界 30 |
| 3.6.3 磁気ダイポール 31 |
| 3.7 マグネトロン 32 |
| 3.7.1 直交電磁界中の電子 32 |
| 3.7.2 マグネトロン 33 |
| 4. 電磁光波工学 35 |
| 4.1 マクスウェルの式の意義 35 |
| 4.1.1 マクスウェルの式の特性 35 |
| 4.1.2 変位電流の導入 36 |
| 4.1.3 異種媒質境界の電磁的条件 37 |
| 4.2 電磁エネルギー(ポインティング・ベクトル) 38 |
| 4.2.1 ポインティソグベクトルの導出 38 |
| 4.2.2 同軸ケーブル中の電磁エネルギー流 39 |
| 4.3 電磁波・光波 40 |
| 4.3.1 マクスウェルの式よりの電磁波導出 40 |
| 4.3.2 電磁波の特性 41 |
| 4.3.3 位相速度・群速度・レイ速度 42 |
| 4.4 電磁光波の反射 45 |
| 4.4.1 完全導体による反射 45 |
| 4.4.2 2層媒質における反射 46 |
| 4.4.3 良導体における反射秀 49 |
| 4.5 電磁連波路 49 |
| 4.6 光ファイバー 51 |
| 4.6.1 光ファイバーとその特徴51 |
| 4.6.2 スネルの法則 52 |
| 4.6.3 ファイバー中の光波伝搬 53 |
| 4.6.4 集束型光ファイバー 54 |
| 4.7 八木アンテナ 55 |
| 5. プラズマ電磁工学 57 |
| 5.1 荷電粒子中のマクスウェルの式 57 |
| 5.1.1 外部電荷を有する荷電粒子中のマクスウェルの式 57 |
| 5.1.2 プラズマの誘電率 58 |
| 5.2 プラズマ中の電磁波動 59 |
| 5.2.1 電子波・イオン波・電磁波(B=O) 59 |
| 5.2.2 磁界中静電電子波 61 |
| 5.2.3 磁界中静電イオン波 62 |
| 5.2.4 磁界中電磁電子波・電磁イオン波(冷プラズマ) 64 |
| 5.2.5 磁界中電磁電子波・電磁イオン波(熱プラズマ) 67 |
| 5.3 プラズマ中の波動放射 68 |
| 5.3.1 電子プラズマ波の放射 68 |
| 5.3.2 イオン波の放射 70 |
| 5.3.3 磁界中の電子波の放射 71 |
| 5.4 レゾナンスコーン 73 |
| 5.4.1 点波源放射レゾナンスコーン 73 |
| 5.4.2 ダイポール放射レゾナンスコーン 75 |
| 5.5 プラズマ淳波路 76 |
| 5.5.1 プラズマ導波路(冷電子プラズマ) 76 |
| 5.5.2 プラズマ導波路(熱電子プラズマ) 77 |
| 5.6 粒子ビームアンテナ 77 |
| 5.6.1 粒子ビームアンテナ 79 |
| 5.6.2 磁界中の粒子ビームアンテナ 80 |
| 5.7 マグネトロン法による超伝導薄膜 81 |
| 6. 超伝導電磁工学 83 |
| 6.1 高温超伝導 83 |
| 6.1.1 ゼロ抵抗とマイスナー効果(完全導電性,完全反磁性) 83 |
| 6.1.2 臨界温度・臨界磁界・臨界電流密度 85 |
| 6.1.3 第1種超伝導・第2種超伝導 87 |
| 6.1.4 磁束量子(フラクソン)・特性長 88 |
| 6.1.5 高温超伝導 90 |
| 6.2 ロンドンの式 92 |
| 6.2.1 ロンドンの式 92 |
| 6.2.2 ロソドンの磁界侵入長 93 |
| 6.2.3 超伝導電流 94 |
| 6.3 高周波電磁現象 95 |
| 6.3.1 超伝導の高周波表面抵抗 95 |
| 6.3.2 超伝導への高周波電磁界浸透 96 |
| 6.4 超伝導の導電率 98 |
| 6.4.1 2流体モデルによる超伝導導電率 98 |
| 6.4.2 超伝導の表面イソピーダンス 99 |
| 6.5 ジョセフソン効果・スクィド 99 |
| 6.5.1 準粒子トンネル現象 100 |
| 6.5.2 直流ジョセフソン効果 100 |
| 6.5.3 交流ジョセフソン効果 102 |
| 6.5.4 DCスクィド 103 |
| 6.5.5 RFスクィド 106 |
| 6.6 テラヘルツ電磁波・光波検出 108 |
| 6.6.1 SISミキサー 108 |
| 6.6.2 シャピロステップ 108 |
| 6.6.3 超伝導アクティブアンテナ 109 |
| 6.6.4 テラヘルツ光波センサ 110 |
| 6.7 超伝導の電磁的応用 110 |
| 索引 113 |
| 1. 電気磁気学の基礎 1 |
| 1.1 電荷と電流 1 |
| 1.2 マクスウェルの式 2 |
|
| 87.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
松延宏一朗著
| 出版情報: |
京都 : 現代数学社, 2007.7 v, 313p ; 21cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 第1章 二項係数 1 |
| 1.1 Jordanの階乗記号 1 |
| 1.2 二項係数 2 |
| 1.2.1 二項係数の重要公式 3 |
| 1.2.2 Leibnizの微分公式 4 |
| 1.3 二項展開 6 |
| 第2章 関数のTaylor展開 9 |
| 2.1 Talorの定理 9 |
| 2.1.1 exを近似する2つの多項式 11 |
| 2.1.2 Taylor展開の他の例 15 |
| 2.1.3 Taylor展開の力学への応用例 16 |
| 2.1.4 Taylor展開が応用上重要なわけ 19 |
| 2.2 多変数関数の場合 20 |
| 2.2.1 多変数関数のTaylorの定理 20 |
| 2.2.2 多変数関数の極値問題 23 |
| 第3章 微分方程式 31 |
| 3.1 運動学の常微分方程式 31 |
| 3.1.1 変数分離法 35 |
| 3.1.2 解を求める 36 |
| 3.2 流体力学の偏微分方程式 40 |
| 3.2.1 大学入試問題から 40 |
| 3.2.2 数学的準備 41 |
| 3.2.3 物理的準備 48 |
| 3.2.4 回転流体の水面 51 |
| 第4章 Eulerの公式 53 |
| 4.1 Eulerの公式 53 |
| 4.1.1 複素数の表示形式 53 |
| 4.1.2 微分方程式からみた指数関数 55 |
| 4.1.3 Picardの逐次近似法 56 |
| 4.2 Eulerの公式の応用 68 |
| 4.2.1 周期的境界条件をもつ漸化式 68 |
| 4.2.2 直線に下ろした垂線の足 71 |
| 4.2.3 球対称場の中の粒子 73 |
| 第5章 重要な無限積分 77 |
| 5.1 Riemann積分とその拡張 77 |
| 5.1.1 1変数の場合 77 |
| 5.1.2 2変数の場合 78 |
| 5.2 無限積分∫∞ -∞dxex = √π 79 |
| 5.3 いくつかの派生積分公式 80 |
| 5.4 拡散方程式の解 85 |
| 第6章 線形波動方程式 89 |
| 6.1 Fourier展開 89 |
| 6.2 波動方程式の初期値問題 92 |
| 第7章 Diracのδ 97 |
| 7.1 デルタ関数 97 |
| 7.1.1 デルタ関数の定義と性質 98 |
| 7.1.2 量子力学とデルタ関数 101 |
| 7.2 デルタ関数の応用 110 |
| 7.2.1 Diracのδ関数とHeaviside関数 110 |
| 7.2.2 撃力 111 |
| 7.2.3 点粒子の電荷密度と電流密度 112 |
| 7.2.4 標本化定理 114 |
| 第8章 Markov連鎖 119 |
| 8.1 Markov連鎖 119 |
| 8.2 大学入試問題から 121 |
| 8.2.1 解答1 123 |
| 8.2.2 解答2 126 |
| 8.3 確率過程 129 |
| 第9章 実数のp進表記 131 |
| 9.1 Gauss記号 131 |
| 9.2 p進表記 133 |
| 9.2.1 整数[x]のp進表記 134 |
| 9.2.2 実数xのp進表記 135 |
| 9.2.3 Gauss記号の美しさ 136 |
| 第10章 離散力学系 139 |
| 10.1 離散力学系 139 |
| 10.2 連続関数の場合 141 |
| 10.2.1 N周期点を求める 142 |
| 10.2.2 N周期軌道に漸近する軌道 150 |
| 10.2.3 カオス 151 |
| 10.3 不連続関数の場合 154 |
| 10.3.1 周期点 160 |
| 10.3.2 周期的区間列に収まる軌道 164 |
| 10.3.3 不連続区間力学系と2次の無理数 166 |
| 10.4 無限次元離散力学系 _ .168 |
| 第11章 パソコンと数学 173 |
| 11.1 素因数分解のアルゴリズム 173 |
| 11.1.1 プログラムの解説 174 |
| 11.1.2 プログラムの改良 175 |
| 11.1.3 アルゴリズムの効率化 177 |
| 11.2 Bezier曲線 179 |
| 11.2.1 Bezier曲線の定義 179 |
| 11.2.2 Bezier曲線による補間 180 |
| 11.2.3 その他の補間多項式 184 |
| 11.3 Officeソフトと数学 187 |
| 11.3.1 関数電卓 187 |
| 11.3.2 表計算ソフト 191 |
| 11.3.3 リレーショナルデータベースと数学 196 |
| 11.3.4 Officeソフトで数学の問題を解く 203 |
| 第12章 相対性理論 215 |
| 12.1 Lorentz変換 216 |
| 12.1.1 時間の遅れ 216 |
| 12.1.2 Lorentz収縮 217 |
| 12.1.3 Minkowski時空における世界距離 218 |
| 12.1.4 世界距離と固有時間 219 |
| 12.1.5 特殊相対論的速度の合成 220 |
| 12.2 特殊相対論的力学 221 |
| 12.2.1 身近な相対論的現象 222 |
| 12.2.2 特殊相対論的等加速度運動 226 |
| 12.2.3 双子のパラドクス 228 |
| 12.2.4 瞬間加速度運動 230 |
| 12.2.5 もう一度,特殊相対論的等加速度運動 232 |
| 12.2.6 加速度運動すると時間は遅れる 236 |
| 12.3 電磁気学の4次元的定式化 241 |
| 12.3.1 基本テンソルと反変・共変ベクトル 242 |
| 12.3.2 電磁場中の荷電粒子の運動方程式 245 |
| 12.3.3 Maxwell方程式 247 |
| 12.3.4 エネルギー運動量テンソルと保存則 250 |
| 12.4 一般相対論の基本的な考え方 257 |
| 12.4.1 等価原理と一般相対性原理 257 |
| 12.4.2 時空の計量と重力ポテンシャル 258 |
| 12.4.3 重力場中の物体の運動方程式 260 |
| 12.5 重力場の方程式 263 |
| 12.5.1 曲率テンソル 267 |
| 12.5.2 等加速度時空 268 |
| 第13章 本格的に勉強するために 285 |
| 13.1 数学関係の本 286 |
| 13.2 物理学関係の本 294 |
| 13.3 情報科学関係の本 303 |
| 13.4 その他の本 306 |
| 第1章 二項係数 1 |
| 1.1 Jordanの階乗記号 1 |
| 1.2 二項係数 2 |
|
| 88.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
植月唯夫, 松原孝史, 箕田充志共著
| 出版情報: |
東京 : コロナ社, 2006.2 xii, 200p ; 21cm |
| シリーズ名: |
電気・電子系教科書シリーズ ; 26 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| 1. 高電圧工学とは |
| 1.1 自然界における高電圧 1 |
| 1.2 高電圧工学の役割 3 |
| 1.2.1 高電圧と絶縁 5 |
| 1.2.2 高電圧と応用 6 |
| 演習問題 7 |
| 2. 高電圧現象 |
| 2.1 気体粒子の運動 8 |
| 2.1.1 気体の状態方程式 8 |
| 2.1.2 粒子のエネルギー 9 |
| 2.1.3 粒子の速度分布・エネルギー分布 9 |
| 2.1.4 衝突断面積,衝突周波数および衝突損失割合 12 |
| 2.1.5 平均自由行程 13 |
| 2.2 励起・電離 15 |
| 2.2.1 原子のエネルギー準位 15 |
| 2.2.2 衝突による励起・電離 16 |
| 2.2.3 熱電離 17 |
| 2.2.4 光電離 18 |
| 2.2.5 階段励起,累積電離 19 |
| 2.2.6 電離電圧と放電開始電圧の関係 19 |
| 2.3 電離気体で起こる現象 19 |
| 2.3.1 電子温度と電子エネルギー分布 19 |
| 2.3.2 移動度 20 |
| 2.3.3 拡散 22 |
| 2.3.4 再結合と付着 25 |
| 演習問題 26 |
| 3. 電子放出 |
| 3.1 仕事関数 27 |
| 3.2 熱電子放出 28 |
| 3.2.1 熱のみによる電子放出 28 |
| 3.2.2 ショットキー効果 29 |
| 3.3 電界放出 30 |
| 3.4 光電子放出 31 |
| 3.5 電子ビームによる二次電子放出 31 |
| 3.6 粒子衝突による電子放出 32 |
| 演習問題 33 |
| 4. 気体の絶縁破壊 |
| 4.1 非自続放電と自続放電 34 |
| 4.2 タウンゼント理論 35 |
| 4.3 ストリーマ理論 36 |
| 4.4 火花放電への移行過程としてのコロナ放電 38 |
| 4.4.1 コロナ放電の発生条件 38 |
| 4.4.2 コロナ放電の形態 38 |
| 4.4.3 コロナ損・コロナ雑音 41 |
| 4.5 火花放電 43 |
| 4.5.1 火花放電の定義 43 |
| 4.5.2 火花放電の時間遅れ 43 |
| 4.5.3 火花放電に影響を与えるパラメータ 43 |
| 演習問題 50 |
| 5. 放電現象 |
| 5.1 定常放電 51 |
| 5.1.1 低気圧直流放電の電気特性 51 |
| 5.1.2 低圧放電の始動性(ペニング効果) 52 |
| 5.2 グロー放電 52 |
| 5.2.1 発光状態と電気特性 52 |
| 5.2.2 陰極降下領域 54 |
| 5.2.3 電極について 54 |
| 5.2.4 陽光柱理論 56 |
| 5.2.5 陽極降下領域 59 |
| 5.3 アーク放電 59 |
| 5.3.1 アーク放電の特徴 59 |
| 5.3.2 電極からの電子放出機構について 60 |
| 5.3.3 アーク放電の陽光柱 61 |
| 5.3.4 放電の応用 61 |
| 演習問題 61 |
| 6. プラズマの基礎 |
| 6.1 プラズマの定義と性質 62 |
| 6.1.1 プラズマの定義 62 |
| 6.1.2 プラズマの微視的な見方と巨視的な見方の境界 62 |
| 6.1.3 プラズマの集団としての性質 64 |
| 6.2 シース理論 66 |
| 6.2.1 プラズマと壁の境界 66 |
| 6.2.2 プラズマ計測(プローブ法) 68 |
| 6.2.3 プラズマの種類と計測法 70 |
| 演習問題 70 |
| 7. 液体の絶縁破壊 |
| 7.1 液体中の電気伝導特性 71 |
| 7.2 液体の絶縁破壊機構 72 |
| 7.2.1 電子的破壊 73 |
| 7.2.2 気泡破壊 73 |
| 7.3 不純物の影響 75 |
| 7.3.1 不純物による破壊 76 |
| 7.3.2 面積・体積効果 78 |
| 7.3.3 ワイブルプロツト 78 |
| 7.4 流動帯電 80 |
| 演習問題 80 |
| 8. 固体の絶縁破壊 |
| 8.1 固体中の電気伝導特性 81 |
| 8.1.1 イオン性伝導 82 |
| 8.1.2 電子性伝導 83 |
| 8.2 誘電分極 84 |
| 8.3 誘電損失 85 |
| 8.4 絶縁破壊理論 86 |
| 8.4.1 電子的破壊 87 |
| 8.4.2 熱的破壊 88 |
| 8.4.3 電気機械的破壊 89 |
| 8.4.4 破壊に影響を及ぼす要因 90 |
| 8.4.5 絶縁破壊の温度特性 92 |
| 演習問題 93 |
| 9. 複合系の絶縁破壊 |
| 9.1 複合誘電体における電界 94 |
| 9.2 ボイド内での部分放電 97 |
| 9.3 トリーイング 98 |
| 9.4 沿面放電 100 |
| 9.5 トラッキング 102 |
| 演習問題 104 |
| 10. 電界と絶縁 |
| 10.1 電界計算 105 |
| 10.1.1 静電界の方程式 105 |
| 10.1.2 電解計算法の種類 106 |
| 10.1.3 コンピュータによる電界計算法 107 |
| 10.2 電界緩和法 114 |
| 10.2.1 導体形状と配置 114 |
| 10.2.2 段絶縁 115 |
| 10.2.3 遮へい 116 |
| 10.3 絶縁協調 117 |
| 10.3.1 絶縁協調 117 |
| 10.3.2 絶縁階級と基準衝撃絶縁強度 117 |
| 演習問題 118 |
| 11. 高電圧の発生 |
| 11.1 交流高電圧の発生 119 |
| 11.2 直流高電圧の発生 121 |
| 11.3 インパルス高電圧の発生 124 |
| 演習問題 130 |
| 12. 高電圧と大電流の測定 |
| 12.1 実際の送配電系統で高電圧を測定する方法 131 |
| 12.1.1 計器用変圧器 131 |
| 12.1.2 コンデンサ形計器用変圧器 132 |
| 12.2 実験室で高電圧を測定する方法 133 |
| 12.2.1 静電電圧計 133 |
| 12.2.2 火花ギャップ法 134 |
| 12.2.3 倍率器と指示計器 135 |
| 12.2.4 分圧器と計測器 136 |
| 12.2.5 測定方法と測定対象(実験室) 138 |
| 12.2.6 光を利用した測定方法 139 |
| 12.2.7 空間電荷の測定方法 140 |
| 12.3 インパルス大電流の測定 141 |
| 12.3.1 分流器とオシロスコープ 141 |
| 12.3.2 ロゴウスキコイル 142 |
| 演習問題 143 |
| 13. 高電圧機器 |
| 13.1 がいし 145 |
| 13.1.1 懸垂がいし 145 |
| 13.1.2 長幹がいし 147 |
| 13.2 ブッシング 148 |
| 13.2.1 単一形ブッシング 148 |
| 13.2.2 油入ブッシング 148 |
| 13.2.3 コンデンサ形ブッシング 149 |
| 13.3 電力ケーブル 150 |
| 13.3.1 CVケーブル 150 |
| 13.3.2 油入ケーブル 151 |
| 13.3.3 圧力ケーブル 152 |
| 13.4 高電圧コンデンサ 152 |
| 13.5 高電圧整流素子 153 |
| 13.6 断路器 155 |
| 13.7 遮断器 155 |
| 13.8 ガス絶縁開閉装置 157 |
| 13.9 避雷器 158 |
| 演習問題 159 |
| 14. 高電圧絶縁試験 |
| 14.1 高電圧絶縁試験の種類 160 |
| 14.2 絶縁特性試験(非破壊試験) 161 |
| 14.2.1 直流高電圧試験 161 |
| 14.2.2 誘電正接試験 162 |
| 14.2.3 部分放電試験 163 |
| 14.3 交流高電圧試験 164 |
| 14.3.1 試験条件と試験回路 164 |
| 14.3.2 交流絶縁耐力試験 165 |
| 14.4 雷インパルス電圧試験 166 |
| 14.4.1 雷インパルス絶縁耐力試験 166 |
| 14.4.2 V-t曲線試験 167 |
| 演習問題 168 |
| 15. 高電圧応用 |
| 15.1 高電界の利用 169 |
| 15.1.1 粒子加速器 169 |
| 15.1.2 走査形電子顕微鏡 171 |
| 15.2 コロナ放電電荷の利用 171 |
| 15.2.1 電気集じん機 171 |
| 15.2.2 電子コピー機 173 |
| 15.2.3 静電塗装 174 |
| 15.3 放電の応角 175 |
| 15.3.1 オゾナイザ 175 |
| 15.3.2 気体レーザ 176 |
| 演習問題 178 |
| 付録 179 |
| 引用・参考文献 184 |
| 演習問題解答 188 |
| 索引 197 |
| 1. 高電圧工学とは |
| 1.1 自然界における高電圧 1 |
| 1.2 高電圧工学の役割 3 |
|
| 89.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
日本塑性加工学会編
| 出版情報: |
東京 : 日刊工業新聞社, 2000.5 x, 220p ; 26cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
目次情報:
続きを見る
| まえがき |
| 第1章 金属薄板材料の塑性変形特性と成形性試験法 |
| 1. はじめに 1 |
| 2. 応力とひずみの表示法 1 |
| 2.1 応力の表示法 1 |
| 2.2 ひずみの表示法 1 |
| 2.3 対数ひずみの特徴 2 |
| 2.3.1 ひずみの加算 2 |
| 2.3.2 変形の大きさとひずみの対応 2 |
| 2.3.3 非圧縮性の表示 2 |
| 3. 板材の塑性変形特性 3 |
| 3.1 一軸引張りにおける板材の変形 3 |
| 3.2 応力-ひずみ線図のモデル化 4 |
| 3.3 n値 4 |
| 3.4 γ値 5 |
| 3.5 バウシンガー効果 7 |
| 3.6 表面あれ 8 |
| 4. 板材プレス成形の分類 9 |
| 4.1 プレス成形品のひずみ状態 9 |
| 4.2 板材プレス成形の種類と基本的な変形 10 |
| 4.3 板材プレス成形における破断支配形態 10 |
| 4.4 基本的な変形と破断支配形態による板材プレス成形の区分 10 |
| 5. 板材の成形性試験 11 |
| 5.1 基礎的試験 11 |
| 5.1.1 一軸引張試験 11 |
| 5.1.2 平面ひずみ引張試験 12 |
| 5.1.3 液圧バルジ試験 12 |
| 5.2 模擬的試験 13 |
| 5.2.1 エリクセン試験 13 |
| 5.2.2 深絞り試験 14 |
| 5.2.3 コニカルカップ試験 14 |
| 5.2.4 穴広げ試験 15 |
| 5.3 成形限界線図および成形限界に影響を及ぼす因子 16 |
| 5.3.1 スクライブドサークルテスト 16 |
| 5.3.2 成形限界線図 16 |
| 5.3.3 成形限界に影響を及ぼす因子 17 |
| 第2章 プレス用材料の特性と主な用途-鉄系材料- |
| 1. はじめに 21 |
| 2. 物理的性質と化学成分 21 |
| 2.1 物理的性質 21 |
| 2.1.1 熱的性質 21 |
| 2.1.2 ヤング率 21 |
| 2.2 化学成分 22 |
| 3. 金属組織と材料特性値 23 |
| 3.1 金属組織 23 |
| 3.2 金属組織中のミクロな運動と塑性変形 23 |
| 3.3 機械的性質に及ぼす金属組織の影響 24 |
| 3.3.1 強度 24 |
| 3.3.2 延性 24 |
| 3.3.3 深絞り性 25 |
| 3.4 ひずみ時効現象 25 |
| 4. 普通鋼薄板の特性と用途 26 |
| 4.1 熱延鋼板 26 |
| 4.1.1 種類 26 |
| 4.1.2 プレス成形性 26 |
| 4.1.3 用途 27 |
| 4.2 冷延鋼板 27 |
| 4.2.1 種類と特徴 27 |
| 4.2.2 プレス成形性 28 |
| 4.2.3 用途と材料選択 28 |
| 4.3 高強度鋼板 28 |
| 4.3.1 パネル用高強度鋼板 29 |
| 4.3.2 強度部材用高強度鋼板 29 |
| 4.4 表面処理鋼板 29 |
| 4.4.1 種類と特徴 29 |
| 4.4.2 プレス成形性 30 |
| 4.5 制振鋼板 30 |
| 5. ステンレス鋼板の特性と用途 30 |
| 5.1 種類と特徴 30 |
| 5.2 オーステナイト系ステンレス鋼板の特性と用途 31 |
| 5.3 フェライト系ステンレス鋼板の特性と用途 32 |
| 第3章 プレス用材料の特性と主な用途-非鉄系材料- |
| 1. アルミニウム系材料 33 |
| 1.1 アルミニウム板材の現状 33 |
| 1.2 成形用アルミニウム板材の種類 33 |
| 1.3 展伸材の呼称と調質記号 34 |
| 1.4 工業用アルミニウム合金 34 |
| 1.4.1 1100系(純アルミニウム) 34 |
| 1.4.2 2000系合金(AI-Cu) 35 |
| 1.4.3 3000系合金(AI-Mn) 35 |
| 1.4.4 4000系合金(AI-Si) 35 |
| 1.4.5 5000系合金(AI-Mg) 35 |
| 1.4.6 6000系合金(AI-Mg-Si) 35 |
| 1.4.7 7000系合金(AI-Zn-Cu、Mg) 36 |
| 1.4.8 その他の合金 36 |
| 1.5 アルミニウム合金の成形特性 37 |
| 1.5.1 深絞り性 37 |
| 1.5.2 張出し性 38 |
| 1.5.3 伸びフランジ性 38 |
| 1.5.4 曲げ性 38 |
| 1.5.5 成形限界線図 39 |
| 1.5.6 しごき加工性 39 |
| 1.6 アルミニウム合金の成形事例 40 |
| 1.6.1 缶胴 40 |
| 1.6.2 缶蓋 40 |
| 1.6.3 熱交換器用フィン 41 |
| 1.6.4 箔容器 41 |
| 1.6.5 自動車ボディパネル 42 |
| 1.7 まとめ 43 |
| 2. 超塑性系材料 44 |
| 2.1 超塑性の特徴 44 |
| 2.1.1 変形抵抗の温度依存性 44 |
| 2.1.2 変形抵抗のひずみ速度依存性 44 |
| 2.1.3 伸びの温度依存性 44 |
| 2.1.4 伸びのひずみ速度依存性 45 |
| 2.2 超塑性材料 45 |
| 2.3 超塑性板材料の成形法 46 |
| 2.3.1 真空ブロー成形 46 |
| 2.3.2 深絞り法 47 |
| 2.3.3 管材のバルジ加工 48 |
| 2.3.4 超塑性成形/拡散接合 48 |
| 第4章 円筒・角筒容器の絞り加工 |
| 1. 絞り加工の概要 51 |
| 2. 絞り加工に影響を与える諸因子 51 |
| 2.1 しわ抑え力 51 |
| 2.2 ダイス肩半径 52 |
| 2.3 パンチ肩半径 53 |
| 2.4 パンチとダイスのクリアランス 54 |
| 2.5 素板寸法 54 |
| 2.6 素板の板厚 55 |
| 2.7 潤滑 55 |
| 2.8 温度 56 |
| 2.9 素板の機械的性質および異方性 56 |
| 3. 円筒絞りの塑性力学解析 56 |
| 3.1 フランジ部の応力の計算方法 57 |
| 3.2 ダイス肩部の応力の計算方法 58 |
| 3.3 パンチ荷重の計算方法 58 |
| 3.4 限界絞り比の数値計算法(n値とγ値の影響) 59 |
| 4. 四角筒容器の絞り加工 61 |
| 4.1 四角筒容器の成形性を支配する因子 61 |
| 4.1.1 素板寸法 61 |
| 4.1.2 コーナ半径一辺長比 62 |
| 4.1.3 長方形容器における辺長比 62 |
| 4.1.4 しわ抑え面圧分布 62 |
| 4.2 すべり線場理論による角筒絞りの変形解析法 63 |
| 5. 深い容器の成形法 65 |
| 5.1 再絞り 65 |
| 5.2 しごき 66 |
| 第5章 複雑形状部品のプレス成形 |
| 1. はじめに 69 |
| 2. 不良現象と成形限界 69 |
| 2.1 プレス成形における破断 70 |
| 2.2 プレス成形における面形状不良 73 |
| 2.3 寸法精度不良 74 |
| 2.4 成形不良現象に及ぼす材料特性の影響 76 |
| 3. 複雑形状部品の成形技術 76 |
| 3.1 ビード技術 77 |
| 3.2 しわ抑え技術 77 |
| 3.3 テーラードブランクの成形 79 |
| 3.4 ヘミング加工 80 |
| 4. おわりに 80 |
| 第6章 特殊絞り法 |
| 1. はじめに 83 |
| 2. 対向液圧深絞り法 83 |
| 2.1 成形法の原理と特徴 83 |
| 2.2 創成液圧 84 |
| 2.3 破断抑制効果と影響因子 85 |
| 2.3.1 液圧値 85 |
| 2.3.2 しわ抑え力 85 |
| 2.3.3 しわ抑え下板肩部半径γHL 85 |
| 2.3.4 しわ抑え上板肩部半径γHU 85 |
| 2.3.5 パンチ表面粗さ 86 |
| 2.4 成形実例と応用技術 86 |
| 3. 周辺加熱深絞り法 86 |
| 3.1 成形法の原理と特徴 86 |
| 3.2 成形方法 88 |
| 3.3 成形実例 89 |
| 4. その他の特殊深絞り法 90 |
| 4.1 ゴム圧成形法 90 |
| 4.2 摩擦援用深絞り法 91 |
| 4.3 超音波深絞り法 91 |
| 4.4 その他の深絞り法 92 |
| 第7章 インクリマンタルフォーミング |
| 1. はじめに 93 |
| 2. インクリメンタルフォーミングの原理・考え方 93 |
| 3. インクリメンタルフォーミングの方式 94 |
| 3.1 ハンマリング方式 94 |
| 3.1.1 古典的技法 94 |
| 3.1.2 数値制御方式 94 |
| 3.2 スピニング方式 95 |
| 3.3 多点プレス方式 96 |
| 3.4 加熱曲げ方式 96 |
| 4. インクリメンタルフォーミングの将来と課題 97 |
| 4.1 事例 97 |
| 4.2 特徴 97 |
| 4.3 問題点 97 |
| 5. おわりに 98 |
| 第8章 インテリジェントフォーミング |
| 1. はじめに 101 |
| 2. インテリジェントフォーミングの原理・考え方 101 |
| 3. インテリジェントフォーミングの適用事例と効果 103 |
| 3.1 曲げ加工の知的制御 103 |
| 3.1.1 ロールダイを用いたシミュレーションデータベース援用V曲げ加工 104 |
| 3.1.2 ニューラルネットワークを適用したV曲げ加工 104 |
| 3.1.3 データベースとファジィモデルを用いた知的V曲げ加工 105 |
| 3.1.4 シミュレーションデータベースとファジィモデルを用いた知的V曲げ加工 106 |
| 3.1.5 知能化工具を用いたL曲げ加工 107 |
| 3.2 深絞り加工の知的制御 108 |
| 3.2.1 ニュートラルネットワークを用いた材料特性と摩擦特性の同定とそれによる適応制御 108 |
| 3.2.2 ファジィ適応制御を用いた可変しわ抑え力深絞り加工 109 |
| 3.3 スピニングおよびその他の知的制御 110 |
| 4. インテリジェントフォーミングの将来と課題 111 |
| 5. おわりに 112 |
| 第9章 せん断加工機構 |
| 1. はじめに 113 |
| 2. せん断加工における製品の加工と精度 113 |
| 2.1 せん断切口面の生成機構 113 |
| 2.1.1 だれ 114 |
| 2.1.2 せん断面 115 |
| 2.1.3 破断面 115 |
| 2.1.4 かえり 116 |
| 2.2 せん断製品の寸法精度 116 |
| 2.2.1 わん曲 116 |
| 2.2.2 寸法精度 117 |
| 3. せん断加工の影響因子 118 |
| 3.1 工具クリアランス 118 |
| 3.2 材料の拘束条件 119 |
| 3.3 打抜き輪郭形状 120 |
| 3.4 打抜き速度 120 |
| 4. おわりに 123 |
| 第10章 曲げ加工 |
| 1. はじめに 125 |
| 2. スプリングバックとは 125 |
| 3. 均等曲げの解析 126 |
| 3.1 純曲げの単純理論 126 |
| 3.2 純曲げのスプリングバック解析 128 |
| 4. 不均等曲げ理論 129 |
| 5. スプリングバックを小さくする方法 130 |
| 5.1 曲げモーメントMを小さくする 130 |
| 5.2 曲げを受けている長さを小さくする 132 |
| 5.3 ヤング率の大きい材料を選ぶ 132 |
| 5.4 断面二次モーメントIを大きくする 132 |
| 6. 曲げの中立面と伸びひずみ 132 |
| 6.1 中立面の位置 132 |
| 6.2 曲げ割れ 133 |
| 第11章 積層板のプレス成形 |
| 1. はじめに 135 |
| 2. 金属クラッド板のプレス成形 135 |
| 2.1 一軸引張りにおける変形状態 135 |
| 2.1.1 変形抵抗(応力-ひずみ曲線) 135 |
| 2.1.2 γ値とカールの発生 135 |
| 2.2 曲げ 136 |
| 2.2.1 板厚の変化 136 |
| 2.2.2 引張曲げ破断荷重 137 |
| 2.2.3 スプリングバック 138 |
| 2.2.4 曲げ割れ 138 |
| 2.3 深絞り 139 |
| 2.4 成形限界ひずみ 139 |
| 3. 樹脂サンドイッチ板のプレス成形 140 |
| 3.1 曲げ 140 |
| 3.2 深絞り、成形限界ひずみなど 141 |
| 第12章 板材成形における塑性不安定・分岐現象 |
| 1. 不安定・分岐現象による板材の成形限界 143 |
| 1.1 分岐 143 |
| 1.2 不安定 144 |
| 2. 分岐の不安定の一般論 149 |
| 3. 分岐理論による成形限界評価 152 |
| 3.1 しわ発生限界 152 |
| 3.2 局所くびれ 155 |
| 第13章 板材成形におけるFEMシミュレーション |
| 1. はじめに 159 |
| 2. FEMシミュレーションとは 159 |
| 3. 連続体力学による成形過程のモデリング 160 |
| 4. 静解法有限要素法 161 |
| 4.1 平面応力弾性問題の基礎式 162 |
| 4.1.1 つり合い式 162 |
| 4.1.2 変位-ひずみ関係式 162 |
| 4.1.3 応力-ひずみ関係式 162 |
| 4.1.4 境界条件式 162 |
| 4.2 仮想仕事の原理式 162 |
| 4.3 要素 163 |
| 4.4 変位-ひずみマトリックス 164 |
| 4.5 剛性方程式 164 |
| 5. 動的陽解法有限要素法 165 |
| 6. 板成形シミュレーションに用いられている各種FEM手法の比較 168 |
| 6.1 動的陽解法 168 |
| 6.2 静的陽解法 169 |
| 6.3 静的陰解法 169 |
| 6.3.1 微小増分静的陰解法 169 |
| 6.3.2 大増分静的陰解法 169 |
| 6.3.3 1ステップ法 170 |
| 6.4 各種有限要素手法の評価 170 |
| 7. 板成形シミュレーションの事例 171 |
| 7.1 ディスクホイールの複数工程成形 171 |
| 7.2 フロントフェンダの絞り 172 |
| 8. おわりに 172 |
| 第14章 板材成形におけるトライボロジー |
| 1. 潤滑の目的と潤滑機構および潤滑剤 175 |
| 1.1 摩擦および潤滑の機構 175 |
| 1.2 摩耗と表面損傷 177 |
| 1.3 工具材料とそのトライボ特性 179 |
| 1.4 潤滑剤の効果 179 |
| 2. 各種加工技術と潤滑の特徴 182 |
| 2.1 深絞り加工 182 |
| 2.2 張出し加工 182 |
| 2.3 しごき加工 182 |
| 2.4 せん断加工 182 |
| 3. 各種被加工材と潤滑剤 183 |
| 3.1 軟鋼板・高強度鋼板 183 |
| 3.2 表面処理鋼板 183 |
| 3.3 潤滑鋼板・プレコート鋼板 183 |
| 3.4 ステンレス鋼板 184 |
| 3.5 アルミニウム、アルミニウム合金板 185 |
| 3.6 チタン 186 |
| 4. トライボロジーに関わる加工技術 186 |
| 5. トライボロジー試験法 187 |
| 6. おわりに 188 |
| 第15章 プレス機械 |
| 1. 成形品とプレス機械 191 |
| 2. プレス機械の種類と基本構造 191 |
| 2.1 機械プレス 191 |
| 2.2 油圧プレス 192 |
| 3. 機械プレスと油圧プレスの特徴 193 |
| 3.1 機械プレスの特徴 193 |
| 3.2 油圧プレスの特徴 193 |
| 4. 用途別に分けたプレス機械の種類 194 |
| 4.1 汎用プレス 194 |
| 4.2 高精度加工ができるプレス 194 |
| 4.3 鍛造を得意とするプレス 195 |
| 4.4 スライド速度可変のプレス機械 195 |
| 4.4.1 油圧プレス 196 |
| 4.4.2 リンクプレス(機械式および機械・油圧複合式) 196 |
| 4.4.3 サーボプレス(電気式、油圧式、電気-油圧複合式) 197 |
| 4.5 専用化プレス機械 197 |
| 4.5.1 折曲げプレス 197 |
| 4.5.2 タレットパンチプレス(タレパン) 197 |
| 4.5.3 レーザプレスとプラズマプレス 197 |
| 5. プレス機械の運転方法 198 |
| 5.1 単発加工方式(自動化されていないプレスで一行程運転で行う方式) 198 |
| 5.2 自動加工 198 |
| 5.2.1 断続自動運転方式 198 |
| 5.2.2 連続自動運転方式 198 |
| 5.3 自動化と材料供給方法 199 |
| 5.3.1 コイル材の場合 199 |
| 5.3.2 ブランク材の場合 199 |
| 5.3.3 スラグの場合 200 |
| 6. 加工内容とプレス 200 |
| 6.1 絞り加工用プレス 200 |
| 6.2 抜き加工用プレス 200 |
| 6.3 冷間鍛造用プレス 201 |
| 6.4 ヘッディング用プレス(ヘッダともいう) 201 |
| 7. プレス使用上の注意 201 |
| 7.1 公称加圧能力と実加工荷重の関係 201 |
| 7.2 集中荷重と偏心荷重 202 |
| 7.2.1 集中荷重 202 |
| 7.2.2 偏心荷重 202 |
| 7.3 ダイクッションの剛性と精度 202 |
| 7.4 断続運転回数とブレーキ 202 |
| 7.5 安全なプレス作業と安全装置 203 |
| 8. 新しいプレス機械とプレス機械の将来 203 |
| 8.1 新しいプレス機械 203 |
| 8.2 プレス機械の将来 203 |
| 9. おわりに 204 |
| 第16章 プレス金型 |
| 1. はじめに 205 |
| 2. プレス金型の構造 206 |
| 2.1 プレス金型の基本構成 206 |
| 2.2 加工様式と型構造 206 |
| 2.2.1 抜き型(せん断型) 206 |
| 2.2.2 曲げ型 206 |
| 2.2.3 絞り型 207 |
| 2.3 生産様式と型構造 208 |
| 2.3.1 単工程型 208 |
| 2.3.2 順送り型 208 |
| 2.3.3 複合型 209 |
| 2.3.4 トランスファ型 209 |
| 3. プレス金型材料 209 |
| 3.1 型材料とその選択 209 |
| 3.2 表面処理とその選択 211 |
| 3.2.1 拡散処理(ガス軟窒化、炭化物被膜) 212 |
| 3.2.2 蒸着(化学的蒸着.CVD、物理的蒸着.PVD) 212 |
| 3.2.3 めっき 212 |
| 4. プレス金型の加工 213 |
| 4.1 主要金型部品とその加工工程 213 |
| 4.2 主要工程 213 |
| 4.2.1 研削加工 213 |
| 4.2.2 放電加工 214 |
| 4.2.3 組立調整 214 |
| 5. プレス金型のCAD・CAM 214 |
| 6. 精密プレス金型の例 215 |
| 7. おわりに 216 |
| まえがき |
| 第1章 金属薄板材料の塑性変形特性と成形性試験法 |
| 1. はじめに 1 |
|
| 90.
|
 図書
図書
|
日本化学会編
|
| 91.
|
 図書
図書
|
パイン [ほか著] ; 湯川泰秀 [ほか] 共訳
| 出版情報: |
東京 : 広川書店, 1982.4-1982.8 2冊 ; 27cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 92.
|
 図書
図書
|
コルトフ [編著] ; 藤原鎮男監訳
| 出版情報: |
東京 : 広川書店, 1975.12 5冊 ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 93.
|
 図書
図書
|
渡辺格, 島内武彦, 京極好正共編
| 出版情報: |
東京 : 培風館, 1979.1-1979.4 2冊 ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 94.
|
 図書
図書
|
Maxine Singer, Paul Berg [著] ; 新井賢一, 正井久雄監訳
| 出版情報: |
東京 : 東京化学同人, 1993.9-1994.2 2冊 ; 27cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 95.
|
 図書
図書
|
貴島静正著
| 出版情報: |
東京 : 裳華房, 1991-1996 4冊 ; 19cm |
| シリーズ名: |
ポピュラーサイエンス |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 96.
|
 図書
図書
|
田河生長 [ほか] 執筆
| 出版情報: |
東京 : 大日本図書, 1994.2-1995.2 2冊 ; 22cm |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 97.
|
 図書
図書
|
千葉滋著
|
| 98.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
内島俊雄, 水田進編著
目次情報:
続きを見る
| 1. 機械的物性を利用する材料 1 |
| 1.1 弾・塑性材料 大塚和弘 1 |
| 1.1.1 構造材料 1 |
| 1.1.2 機能性金属材料 7 |
| 1.2 高強度・高靭性材料 佐久間健人 15 |
| 1.2.1 機械的物性 15 |
| 1.2.2 破壊強度を支配する因子 18 |
| 1.2.3 靭性向上の方策 21 |
| 1.2.4 代表的な物質の構造と特性 23 |
| 2. 熱的物性を利用する材料 31 |
| 2.1 高熱伝導材料 水谷惟恭 31 |
| 2.1.1 固体の熱伝導 31 |
| 2.1.2 高熱伝導度をもつ非金属化合物の条件 35 |
| 2.1.3 ダイヤモンド,窒化アルミニウム,炭化ケイ素の熱伝導度 39 |
| 2.1.4 高熱伝導材料の応用 45 |
| 2.2 耐熱高強度材料 木島弌倫 47 |
| 2.2.1 耐熱材料概論 47 |
| 2.2.2 融点 48 |
| 2.2.3 解離圧と反応性 49 |
| 2.2.4 クリープ 50 |
| 2.2.5 熱応力による破壊 52 |
| 3. 電気,磁気,光物性を利用する材料 64 |
| 3.1 半導体材料 64 |
| 3.1.1 シリコンとヒ化ガリウム 鯉沼秀臣 64 |
| 3.1.2 太陽電池 鯉沼秀臣 71 |
| 3.1.3 半導体レーザ 和田恭雄 81 |
| 3.1.4 超LSI 和田恭雄 90 |
| 3.2 超伝導材料 高田雅介 108 |
| 3.2.1 高温超伝導体の発見 108 |
| 3.2.2 金属伝導性と超伝導性 110 |
| 3.2.3 高温超伝導体 113 |
| 3.2.4 酸化物高温超伝導体の薄膜化と線材化 120 |
| 3.2.5 酸化物高温超伝導体の課題 127 |
| 3.2.6 超伝導のメカニズム 129 |
| 3.3 焦電材料と圧電材料 内野研二 130 |
| 3.3.1 強誘電体概説 130 |
| 3.3.2 焦電材料とその応用 139 |
| 3.3.3 圧電材料とその応用 143 |
| 3.4 硬磁性材料と軟磁性材料 山崎陽太郎 157 |
| 3.4.1 磁性材料と磁化 157 |
| 3.4.2 永久磁石材料 161 |
| 3.4.3 軟磁性材料 166 |
| 3.4.4 金属磁性材料と酸化物磁性材料 171 |
| 3.4.5 磁気記録材料 172 |
| 3.4.6 磁性材料と磁気の単位 174 |
| 4. 化学的物性を利用する材料 176 |
| 4.1 吸着・吸収材料 秋葉悦男 177 |
| 4.1.1 吸着・触媒材料-ゼオライト 177 |
| 4.1.2 吸収・吸蔵材料-金属水素化物 183 |
| 4.2 固体電解質材料 水田進・川田達也 190 |
| 4.2.1 イオン伝導体と固体電解質 190 |
| 4.2.2 イオン伝導体内の物質輸送 191 |
| 4.2.3 種々のイオン伝導体とその伝導径路 193 |
| 4.2.4 ジルコニアの構造とその安定化 194 |
| 4.2.5 安定化ジルコニアのイオン伝導 197 |
| 4.2.6 安定化ジルコニアの雰囲気安定住 198 |
| 4.2.7 混合伝導体としての物質輸送 200 |
| 4.2.8 安定化ジルコニアの製造 201 |
| 4.2.9 安定化ジルコニアの応用 203 |
| 5. 材料物性とその応用への概観 水田進・内島俊雄 206 |
| 5.1 機械的物性を利用する材料 206 |
| 5.2 熱的物性を利用する材料 211 |
| 5.3 電気,磁気,光物性を利用する材料 213 |
| 5.4 化学的物性を利用する材料 224 |
| 参者書 226 |
| 索引 233 |
| 1. 機械的物性を利用する材料 1 |
| 1.1 弾・塑性材料 大塚和弘 1 |
| 1.1.1 構造材料 1 |
|
| 99.
|
 図書
図書
|
十河清, 和達三樹, 出口哲生著
| 出版情報: |
東京 : 岩波書店, 2005 2冊 ; 21cm |
| シリーズ名: |
ゼロからの大学物理 ; 1-2 |
| 子書誌情報: |
loading… |
| 所蔵情報: |
loading… |
|
| 100.
|
 図書
図書
東工大
目次DB
|
角南英夫, 川人祥二編著 ; 有本和民 [ほか] 著
目次情報:
続きを見る
| 第Ⅰ編メモリデバイス 1 |
| 1 メモリデバイスの基礎 3 |
| 1.1 半導体メモリとは 3 |
| 1.1.1 各種半導体メモリ概要 4 |
| 1.1.2 現用大規模メモリ 6 |
| 1.1.3 新規材料を用いたメモリ 12 |
| 1.2 半導体メモリの市場 14 |
| 1.2.1 RAM(DRAM)の市場 16 |
| 1.2.2 RoM(NANDフラッシュメモリ)の市場 17 |
| 文献 18 |
| 2 量産中のメモリ 19 |
| 2.1 DRAM 19 |
| 2.1.1 DRAMのメモリセル構造 20 |
| 2.1.2 DRAMの基本構成と動作原理 22 |
| 2.1.3 メモリセルのアレイ配置 26 |
| 2.1.4 メモリセルの情報保持特性 29 |
| 2.1.5 メモリセル製造技術 33 |
| 2.1.6 DRAM微細化の推移 36 |
| 2.1.7 DRAMの微細化を支える自己整合技術 38 |
| 2.1.8 キャパシタ絶縁膜(high-κ絶縁膜) 40 |
| 2.1.9 DRAMの将来方向 42 |
| 2.2 SRAM |
| 2.2.1 SRAMの基本構成と動作原理 45 |
| 2.2.2 メモリセルのレイアウト 46 |
| 2.2.3 高速化・低消費電力技術 50 |
| 2.2.4 SRAMの課題と対策(ばらつき対策) 62 |
| 2.3 EEPROM 70 |
| 2.3.1 EEPROMの基本構成と動作原理 71 |
| 2.3.2 フラッシュEEPROMへの発展 77 |
| 2.3.3 高信頼化技術 86 |
| 2.3.4 多値記憶技術 90 |
| 文献 93 |
| 3 小規模生産中のメモリ 101 |
| 3.1 FeRAM(強誘電体メモリ) 101 |
| 3.1.1 FeRAMのセル基本構成と動作原理 102 |
| 3.1.2 メモリセル形成技術 104 |
| 3.1.3 強誘電体物性の基礎(薄膜PZTについて) 106 |
| 3.1.4 高速化・長寿命化技術 112 |
| 3.1.5 FeRAMの課題と対策 115 |
| 3.2 MRAM 116 |
| 3.2.1 MRAMの基本構成と動作原理 116 |
| 3.2.2 磁界書込みMRAM 121 |
| 3.2.3 スピン注入MRAM 125 |
| 3.2.4 MRAMのスケーラビリティ 129 |
| 3.2.5 まとめ 130 |
| 3.3 PCM 130 |
| 3.3.1 PCMの基本構成と動作原理 130 |
| 3.3.2 相変化メモリの原理と特徴 131 |
| 3.3.3 相変化材料 133 |
| 3.3.4 メモリセル構造 135 |
| 3.3.5 動作特性 138 |
| 3.3.6 アプリケーションと課題・対策 143 |
| 文献 144 |
| 4 今後に期待されるメモリ 151 |
| 4.1 抵抗メモリ(ReRAM) 151 |
| 4.1.1 強相関電子系酸化膜 152 |
| 4.1.2 メモリセルと動作原理 153 |
| 4.1.3 信頼性 154 |
| 4.1.4 応用 154 |
| 4.2 そのほかに提案されているメモリ 154 |
| 4.2.1 単電子メモリ 155 |
| 4.2.2 スピントランジスタ 155 |
| 4.3 実用化の要件 156 |
| 文献 157 |
| 第Ⅱ編 イメージセンサ 159 |
| 5 イメージセンサの基本構成 161 |
| 5.1 イメージセンサの基本構成 161 |
| 5.1.1 リニアセンサとエリアセンサ 161 |
| 5.1.2 受光から出力までの信号の流れ 162 |
| 5.1.3 画素の選択と走査 163 |
| 5.2 光電変換と信号検出 165 |
| 5.2.1 光の吸収 165 |
| 5.2.2 光電変換デバイスと光起電力の発生 169 |
| 5.2.3 電荷蓄積 174 |
| 5.2.4 電荷転送 175 |
| 5.2.5 電荷検出 179 |
| 5.3 イメージセンサの基本特性 181 |
| 5.3.1 感度 181 |
| 5.3.2 ノイズ 184 |
| 5.3.3 暗電流 190 |
| 5.3.4 ダイナミックレンジとSN比 193 |
| 5.3.5 解像度 195 |
| 文献 198 |
| 6 CCDイメージセンサ 201 |
| 6.1 CCD(電荷結合素子)の |
| 6.1.1 CCDの概念 201 |
| 6.1.2 電荷転 202 |
| 6.1.3 電荷検出 214 |
| 6.2 CCDの駆動力式 217 |
| 6.2.1 4相駆動 217 |
| 6.2.2 2相駆動 218 |
| 6.3 CCDイメージセンサの構造機能 220 |
| 6.3.1 構造(フレーム転送,インターライン転送) 220 |
| 6.3.2 基板構造・電子シャッタ動作 222 |
| 6.3.3 光電変換素子構造 225 |
| 6.3.4 カラーフィルタ,マイクロレンズ 225 |
| 6.4 CCDイメージセンサの諸特性 227 |
| 6.4.1 転送効率 227 |
| 6.4.2 残像 229 |
| 6.4.3 ブルーミングとスミア 231 |
| 6.4.4 クロストーク 231 |
| 6.4.5 ノイズ 232 |
| 6.4.6 暗電流・白点欠陥 233 |
| 6.4.7 完全空乏型CCD 234 |
| 文 献 235 |
| 7 CMOSイメージセンサ 237 |
| 7.1 CMOSイメージセンサの基本構成 271 |
| 7.1.1 CMOSイメージセンサの歴史 237 |
| 7.1.2 アーキテクチャ 238 |
| 7.1.3 アドレッシング方式 240 |
| 7.2 画素構成 240 |
| 7.2.1 パッシブピクセル(PPS)型 241 |
| 7.2.2 アクティブピクセル(APS)型 242 |
| 7.2.3 電荷転送型と非転送型 246 |
| 7.2.4 フォトゲート型 248 |
| 7.2.5 埋込みフォトダイオード(PPD)による電荷転送型 249 |
| 7.2.6 トランジスタ共有/選択トタンジスタレス 254 |
| 7.2.7 基板構造 256 |
| 7.2.8 カラーフィルタ,マイクロレンズ 258 |
| 7.3 CMOSイメージセンサの基本性能とその改善 261 |
| 7.3.1 感度 261 |
| 7.3.2 飽和信号 262 |
| 7.3.3 残像 262 |
| 7.3.4 ブルーミング 263 |
| 7.3.5 暗電流・欠陥 264 |
| 7.3.6 固定パターンノイズ(FPN) 265 |
| 7.3.7 クロストーク 266 |
| 7.3.8 電圧・消費電力 266 |
| 7.4 ノイズキャンセル(相関2重サンプリング)と信号読出し 267 |
| 7.4.1 ノイズの発生源 267 |
| 7.4.2 ノイズキャンセル回路 271 |
| 7.4.3 CDS回路のノイズ低減効果 274 |
| 7.4.4 高利得カラム増幅とノイズ低減効果 278 |
| 7.4.5 A/D変換を用いた信号読出し 281 |
| 7.4.6 画素の微細化に伴うノイズ増加 284 |
| 文献 286 |
| 索引 289 |
| 第Ⅰ編メモリデバイス 1 |
| 1 メモリデバイスの基礎 3 |
| 1.1 半導体メモリとは 3 |
|