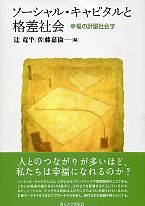| 1.
図書 |
遠藤薫, 佐藤嘉倫, 今田高俊編著
目次情報:
続きを見る
概要:
本書は、社会システム論と自己組織性論とを軸にした、社会学の本質に迫る論考の集成である。21世紀の社会理論のありかたを鋭く問い、社会学における理論の復権を告げる。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.
図書 |
山脇直司編
目次情報:
続きを見る
概要:
科学と科学者のあり方は?/科学では答えることのできないトランス・サイエンスとしての倫理・公共哲学的課題にどのように取り組むか?/今後の教養教育をいかにすべきか?3・11後の原発事故によって科学・技術と社会倫理に突き付けられた課題を統合的に考
…
察する。
続きを見る
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.
図書 |
今田高俊, 舘岡康雄編
目次情報:
続きを見る
概要:
“その先の近代”を生きるための社会学。シナジーとは、人びとやことがらが相互に作用しあい、新たな効果や機能を生みだしたり、高めたりする相乗作用のことである。消費の場で、職場や家庭で、医療の場で、経営の場で、さまざまな場面におけるシナジー社会の
…
きざしをとりあげ、その可能性をさぐる。
続きを見る
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.
図書 |
辻竜平, 佐藤嘉倫編
目次情報:
続きを見る
概要:
人とのつながりが多いほど、私たちは幸福になれるのか?ソーシャル・キャピタルとは、人びとがもつネットワークや信頼関係のことである。これらは格差の縮小あるいは拡大に、どのような影響をもたらしているのか。また、ソーシャル・キャピタル自体は人びとに
…
どのように分配されているのか。計量データをさまざまなアプローチから分析し、現代日本の課題を明らかにする。
続きを見る
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.
図書 |
日本学術協力財団編集 ; 今田高俊 [ほか執筆]
目次情報:
続きを見る
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.
図書 |
金子勇 [ほか] 著
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.
図書 |
山脇直司編
目次情報:
続きを見る
概要:
従来の教養教育論のレベルを超えて、「専門教育との相互連関」や、タコツボ的な学問状況を突破する「統合知」という観点から、18名の著名な論者が4部構成で教養教育を包括的・多面的に論じ合い、人間論・存在論や現代社会の重要なテーマを、「統合的教養」
…
という観点から考察。
続きを見る
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.
図書 東工大 |
東工大
目次DB |
猪原健弘編著
目次情報:
続きを見る
|